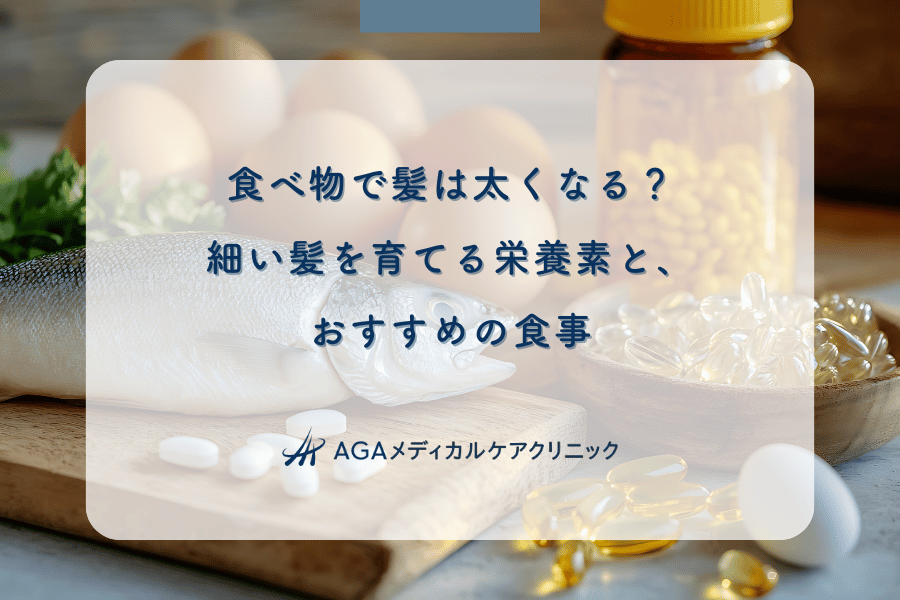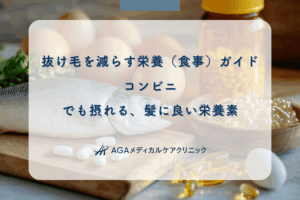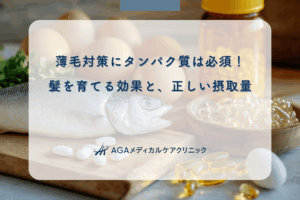鏡を見るたび、あるいは手で髪を触ったときに「以前より髪が細くなった気がする」「髪にハリやコシがなくなってきた」と感じる男性は少なくありません。
髪のボリュームが減ると、全体的な印象も変わってしまいます。育毛剤やシャンプーに関心がいきがちですが、実は日々の「食べ物」が髪の太さや健康に深く関わっています。
私たちの体と同様に、髪の毛も食べたものから作られる栄養素をエネルギー源にしています。
この記事では、なぜ食べ物が髪の太さに関係するのか、細い髪を太く育てるためにどのような栄養素が必要で、具体的にどんな食事を心がければ良いのかを詳しく解説します。
食生活を見直して、内側から健康な髪を育てる第一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪が細くなる原因と食べ物の関係
髪の毛が細くなる背景には、さまざまな要因が考えられます。遺伝的な要素もありますが、それ以上に日々の生活習慣、特に食事が髪の状態に与える影響は大きいものです。
なぜ食べ物が髪の太さに関係するのか、まずは髪の毛の基本的な仕組みから理解を深めていきましょう。
髪の毛の仕組みと成長周期
私たちが「髪の毛」として認識している部分は、主に「ケラチン」というタンパク質から構成されています。毛根の奥にある「毛球部」で作られた髪の毛が、頭皮の外へと押し出されて成長していきます。
この髪の成長には「ヘアサイクル(毛周期)」と呼ばれる周期が存在します。
ヘアサイクルは、髪が活発に成長する「成長期」、成長が止まる「退行期」、そして髪が抜け落ちる準備をする「休止期」の3つに分かれます。
健康な状態であれば、髪の多く(約85%〜90%)が成長期にあり、この期間が2年から6年ほど続きます。しかし、何らかの原因でこのヘアサイクルが乱れ、成長期が短くなると、髪はじゅうぶんに太く成長する前に退行期・休止期へと移行してしまいます。
これが「髪が細くなる」一つの大きな理由です。
なぜ髪は細くなるのか?遺伝以外の要因
遺伝以外で髪が細くなる、あるいはヘアサイクルが乱れる主な要因としては、ストレス、睡眠不足、血行不良、そして栄養不足が挙げられます。
特に現代社会では、多忙な生活によるストレスや不規則な生活が血行不良を招きがちです。
頭皮の血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなります。また、睡眠不足は髪の成長を促す成長ホルモンの分泌を妨げます。
これらの要因が複合的に絡み合い、毛根にある髪の製造工場ともいえる「毛母細胞」の働きを低下させ、結果として細く弱い髪しか作れなくなってしまうのです。
栄養不足が髪の太さに与える影響
体にとって栄養が重要なように、髪にとっても栄養は生命線です。髪の主成分であるタンパク質が不足すれば、当然ながら健康な髪は作れません。
また、タンパク質を髪の毛(ケラチン)に変えるためには、ビタミンやミネラルといった栄養素の助けが必要です。
極端なダイエットや偏った食事によってこれらの栄養素が不足すると、体は生命維持に重要な臓器(脳や心臓など)へ優先的に栄養を送ります。
その結果、生命維持の優先度が低い髪の毛への栄養供給は後回しにされてしまいます。
栄養が届かなければ毛母細胞は活発に働けず、新しく生えてくる髪は細くなり、すでに生えている髪も弱々しくなってしまいます。
食生活の乱れが頭皮環境を悪化させる
髪の土壌ともいえる頭皮環境も、髪の太さに直結します。例えば、脂っこい食べ物や糖分の多い食事に偏ると、皮脂が過剰に分泌されやすくなります。
過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こす原因となり、健康な髪の成長を妨げます。
逆に、栄養バランスの取れた食事は、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を正常に保ち、柔軟で健康な頭皮環境を維持する助けとなります。
髪を太く育てるためには、髪の「材料」を補給するだけでなく、その「土壌」である頭皮環境を食事によって整える意識も重要です。
髪を太く育てるために重要な栄養素
健康で太い髪を育てるためには、特定の食材だけを食べるのではなく、バランスの取れた食事が基本です。その中でも、特に髪の成長に深く関わる栄養素が存在します。
ここでは、髪の「材料」となり、その成長を「サポート」する重要な栄養素について解説します。
タンパク質 (ケラチン) 髪の主成分
髪の毛の約90%以上は「ケラチン」というタンパク質でできています。タンパク質は、肉、魚、卵、大豆製品などに豊富に含まれる栄養素であり、これが不足すると髪の材料そのものが足りなくなってしまいます。
材料が不足すれば、当然ながら太く丈夫な髪を作ることはできません。タンパク質は髪の毛の土台を作る、最も重要な栄養素といえます。
タンパク質は体内で一度アミノ酸に分解されてから再合成されますが、ケラチンを構成するためにはさまざまな種類のアミノ酸が必要となります。
亜鉛 ミネラルの王様
亜鉛は、髪の成長において非常に重要な役割を担うミネラルです。摂取したタンパク質(アミノ酸)を髪の毛(ケラチン)へと再合成する際に、亜鉛は酵素の働きを助ける「補酵素」として機能します。
どれだけタンパク質を摂取しても、亜鉛が不足していると効率よく髪の毛に変換できません。
また、亜鉛は毛母細胞の細胞分裂を活性化させる働きも持っています。髪の毛が成長するということは、毛母細胞が活発に分裂を繰り返すことです。
亜鉛はこの細胞分裂をサポートし、ヘアサイクルを正常に保つ上で大切な役割を果たします。亜鉛は体内で作ることができず、汗や尿と共に排出されやすいため、食事から意識して摂取する必要があります。
ビタミンB群 頭皮環境と代謝をサポート
ビタミンB群は、エネルギー代謝を助ける栄養素として知られていますが、髪の健康にも深く関わっています。特に重要なのがビタミンB2とビタミンB6です。
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミンであり、頭皮の皮脂分泌をコントロールする働きがあります。不足すると皮脂が過剰になり、頭皮環境の悪化を招くことがあります。
一方、ビタミンB6はタンパク質の代謝を助ける働きがあります。摂取したタンパク質がアミノ酸に分解され、ケラチンとして再合成される流れをスムーズにします。
亜鉛と同様に、タンパク質を髪に変えるためのサポート役として重要です。
ビタミンA・C・E 血行促進と抗酸化
ビタミンA、C、Eは、その高い抗酸化作用から「ビタミンACE(エース)」とも呼ばれます。これらのビタミンは、頭皮環境を健やかに保つために役立ちます。
ビタミンAは、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を正常に保ち、乾燥やフケを防ぎます。ビタミンCは、頭皮の血管や毛根を支えるコラーゲンの生成に必要です。
また、鉄分の吸収を助ける働きもあります。ビタミンEは、末梢血管を広げて血流を良くする働きがあり、毛根まで栄養素を運ぶサポートをします。
これら3つのビタミンは、お互いに協力し合って働くため、合わせて摂取することが望ましいです。
髪の成長に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 不足した場合の影響 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる | 髪が細くなる、抜け毛、髪のツヤが失われる |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける、細胞分裂を促す | 髪の成長が遅れる、抜け毛が増える |
| ビタミンB群 | タンパク質の代謝を助ける、皮脂分泌を調整する | 頭皮環境の悪化(フケ、かゆみ)、脂漏性皮膚炎 |
| ビタミンA・C・E | 血行促進、抗酸化作用、頭皮の健康維持 | 頭皮の乾燥、血行不良による栄養不足 |
【タンパク質】を効率良く摂取する食材
髪の主成分であるタンパク質は、健康な髪を育てる上で最も基本となる栄養素です。
タンパク質はアミノ酸から構成されており、食品によって含まれるアミノ酸の種類やバランスが異なります。効率よく摂取するための食材選びが重要です。
動物性タンパク質のおすすめ (肉・魚・卵)
動物性タンパク質は、体内で合成できない必須アミノ酸をバランスよく含んでいる「良質なタンパク質」です。
特に、鶏のささみや胸肉、豚ヒレ肉、牛の赤身肉などは、脂質を抑えながら効率よくタンパク質を摂取できるためおすすめです。
魚類、特にアジやサバ、イワシなどの青魚は、タンパク質と同時にDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)といった良質な脂質も摂取できます。
これらは血液をサラサラにし、頭皮への血流改善にも役立ちます。卵は「完全栄養食品」と呼ばれるほど栄養価が高く、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく含んでいます。
手軽に食事に取り入れられる点も大きな魅力です。
植物性タンパク質の上手な取り入れ方 (大豆製品)
植物性タンパク質の代表格は、豆腐、納豆、豆乳などの大豆製品です。大豆製品は低脂質でありながらタンパク質が豊富です。
また、大豆に含まれる「大豆イソフラボン」は、男性ホルモンの過剰な働きを抑制する可能性が指摘されており、髪の健康維持の観点からも注目されています。
ただし、植物性タンパク質だけでは一部のアミノ酸が不足しがちです。動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく組み合わせることが、髪の材料となるアミノ酸を効率よく体に取り込むコツです。
例えば、肉料理に豆腐を加える、納豆と卵をご飯に混ぜる、といった工夫が有効です。
高タンパク質食材の例
| 分類 | 主な食材 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| 動物性 (肉類) | 鶏ささみ・胸肉、豚ヒレ肉、牛赤身肉、レバー | 脂身の少ない部位を選ぶ。レバーは亜鉛やビタミンも豊富。 |
| 動物性 (魚介類) | アジ、サバ、イワシ、鮭、マグロ(赤身)、卵 | 青魚は良質な脂質(DHA・EPA)も摂取できる。 |
| 植物性 | 豆腐、納豆、豆乳、厚揚げ、きな粉 | 動物性タンパク質と組み合わせてバランスを整える。 |
タンパク質摂取の注意点とバランス
タンパク質が重要だからといって、そればかりを過剰に摂取するのはよくありません。
特に動物性タンパク質に偏り、脂質の多い部位ばかりを食べていると、カロリーオーバーや脂質の過剰摂取につながり、かえって頭皮環境を悪化させる可能性があります。
また、タンパク質を一度に大量に摂取しても、体内で処理しきれない分は排出されてしまいます。
毎食、手のひら一枚分程度のタンパク質源(肉、魚、卵、大豆製品のいずれか)をコンスタントに摂取することを心がけましょう。
野菜や海藻類なども一緒に摂り、全体的な栄養バランスを整えることが大切です。
【亜鉛】を補給するためのおすすめ食材
亜鉛は、タンパク質を髪の毛(ケラチン)に合成する働きを助ける、髪の成長に欠かせないミネラルです。
しかし、亜鉛は体内に蓄積しにくく、吸収率もあまり高くないため、日々の食事から意識的に摂取する必要があります。
亜鉛が豊富な食材 (牡蠣・レバー・赤身肉)
亜鉛を特に多く含む食材として知られているのが「牡蠣(カキ)」です。牡蠣は「海のミルク」とも呼ばれ、亜鉛の含有量は全食品の中でもトップクラスです。
季節が限られるため、摂取しにくい場合は水煮缶などを利用するのも一つの方法です。
その他、豚や牛のレバー、牛肉の赤身肉も亜鉛の優れた供給源です。レバーはタンパク質やビタミンA、ビタミンB群も豊富で、髪の健康にとって総合的に優れた食材といえます。
また、チーズなどの乳製品、アーモンドやカシューナッツなどのナッツ類、玄米やそばなどにも亜鉛は含まれています。
亜鉛の吸収を高める工夫
亜鉛は、そのままだと体に吸収されにくい性質を持っています。しかし、特定の栄養素と一緒に摂取することで、吸収率を高めることができます。その代表格が「ビタミンC」と「クエン酸」です。
ビタミンCは野菜や果物に、クエン酸はレモンや梅干し、お酢などに多く含まれています。
例えば、牡蠣にレモンを絞る、赤身肉のステーキに酸味のあるソースをかける、といった食べ合わせは、味の面だけでなく栄養学的にも理にかなっています。
逆に、インスタント食品やスナック菓子に多く含まれる「リン酸塩」や、ほうれん草などに含まれる「シュウ酸」、玄米や豆類に含まれる「フィチン酸」は、亜鉛の吸収を妨げることがあるため、過剰な摂取には注意が必要です。
(ただし、シュウ酸やフィチン酸は通常の食生活では問題になることは少ないです)。
亜鉛を含む食材と摂取のポイント
| 分類 | 主な食材 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| 魚介類 | 牡蠣(生・水煮缶)、うなぎ、たらこ | 牡蠣は含有量が非常に多い。 |
| 肉類 | 豚レバー、牛レバー、牛赤身肉 | レバーは他のビタミンも豊富。 |
| その他 | チーズ、卵黄、アーモンド、納豆、高野豆腐 | ビタミンCやクエン酸と合わせると吸収率が向上。 |
亜鉛不足のサインと摂取目安
亜鉛が不足すると、髪の毛の成長が妨げられるだけでなく、「味覚がおかしい(味がしない)」、「爪に白い斑点ができる」、「傷の治りが遅い」といったサインが現れることがあります。
これらの症状が見られる場合は、亜鉛不足を疑う必要があるかもしれません。
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によると、成人男性の亜鉛の推奨量は1日あたり約11mgです。
しかし、亜鉛は吸収率が低く、アルコールの摂取や激しい運動によっても失われやすいため、推奨量を満たしていても不足気味になることがあります。
サプリメントで補う方法もありますが、まずは牡蠣やレバー、赤身肉などを食事に取り入れることから始めましょう。
【ビタミン群】を意識した食事メニュー
ビタミンは、タンパク質や脂質、糖質の代謝を助け、体の機能を正常に保つために必要な栄養素です。
髪の健康においては、特にビタミンB群と、抗酸化作用を持つビタミンA・C・Eが重要な役割を果たします。
皮脂コントロールと代謝を助けるビタミンB群
ビタミンB群は、頭皮環境と髪の毛の「製造」の両方に関わります。特にビタミンB2は、脂質の代謝に関与し、皮脂の分泌量をコントロールします。
不足すると頭皮がベタついたり、逆に乾燥したりと不安定になりがちです。ビタミンB6は、タンパク質の代謝をサポートし、ケラチンの合成を円滑にします。
これらは単体ではなく、ビタミンB群としてチームで働くため、B群全体をバランスよく摂取することが望ましいです。
ビタミンB群は、豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、カツオ、玄米、納豆などに多く含まれています。
ビタミンB群が豊富な食材
| ビタミンの種類 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂の分泌調整、皮膚や粘膜の健康維持 | レバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品 |
| ビタミンB6 | タンパク質(ケラチン)の合成サポート | マグロ、カツオ、鮭、レバー、鶏肉、バナナ |
| ビオチン | 皮膚や髪の健康維持に関わる | レバー、卵黄、ナッツ類、きのこ類 |
頭皮の健康を守る抗酸化ビタミン (A・C・E)
ビタミンA、C、Eは、体内の活性酸素を除去する「抗酸化作用」を持っています。活性酸素は、ストレスや紫外線、喫煙などによって発生し、細胞を傷つけ(酸化させ)、老化を促進します。
頭皮の細胞が酸化ダメージを受けると、毛母細胞の働きが低下し、健康な髪が育ちにくくなります。
ビタミンAは頭皮のうるおいを保ち、ビタミンCは毛細血管を丈夫にするコラーゲンの生成を助け、ビタミンEは血行を促進して栄養素を毛根に届けます。
これらを積極的に摂取することは、頭皮を健康な状態に保ち、髪が育ちやすい環境を作ることにつながります。
抗酸化ビタミンが豊富な食材
| ビタミンの種類 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 頭皮のターンオーバー正常化、乾燥防止 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜(人参、かぼちゃ) |
| ビタミンC | コラーゲン生成、鉄分吸収促進、抗酸化 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化 | アーモンド(ナッツ類)、アボカド、植物油 |
忙しい朝でも簡単なビタミン補給術
栄養バランスが重要とわかっていても、忙しい朝はなかなか手が回らないものです。しかし、朝食は日中のエネルギー源であり、頭皮に栄養を送るためにも重要です。
例えば、いつもの朝食にプラス一品するだけでも違います。
ビタミンC補給のためにキウイやイチゴを数個食べる、ビタミンE補給のためにヨーグルトにアーモンドを数粒加える、ビタミンB群補給のためにご飯を玄米に変える、あるいは納豆や卵を追加するなど、簡単な工夫でビタミンを補給できます。
朝食プラス一品の例
- ヨーグルト+ナッツ(ビタミンE)
- トースト+アボカド(ビタミンE)
- ご飯+納豆(ビタミンB群)
- いつもの食事+キウイ(ビタミンC)
髪の成長を妨げる可能性のある食習慣
髪に良い栄養素を摂取することも大切ですが、同時に、髪の成長を妨げる可能性のある食習慣を避けることも重要です。
知らず知らずのうちに、頭皮環境や血流を悪化させる食事をしていないか、日々の食生活を見直してみましょう。
過度な脂質の摂取と頭皮への影響
揚げ物、ファストフード、スナック菓子、脂身の多い肉などに含まれる動物性脂肪やトランス脂肪酸を過剰に摂取すると、血液中の中性脂肪やコレステロールが増加し、血液がドロドロになりがちです。
頭皮の毛細血管は非常に細いため、血流が悪化すると毛根への栄養供給が真っ先に滞ってしまいます。
また、過剰な脂質は皮脂の分泌を促します。皮脂は頭皮を守るために必要ですが、多すぎると毛穴を塞ぎ、雑菌が繁殖しやすい環境を作ってしまいます。
これが頭皮の炎症(脂漏性皮膚炎など)につながり、抜け毛や細い髪の原因となることがあります。
糖質の摂りすぎが引き起こす問題
甘いお菓子やジュース、白米やパンなどの精製された炭水化物を一度に多く摂取すると、血糖値が急上昇します。すると、血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されます。
このインスリンの分泌が過剰になると、皮脂腺が刺激され、皮脂の分泌が活発になるといわれています。
さらに、糖質をエネルギーに変える際には、ビタミンB群が大量に消費されます。
つまり、糖質を摂りすぎると、本来髪の毛の成長や頭皮環境の維持に使われるべきビタミンB群が、糖の代謝のために奪われてしまうのです。結果として、髪に必要な栄養が不足する事態を招きます。
アルコールと喫煙の髪へのダメージ
適度なアルコールは血行を促進する面もありますが、過度な飲酒は髪にとってマイナスに働きます。
アルコールを肝臓で分解する際には、アミノ酸やビタミン、そして特に亜鉛が大量に消費されます。髪の合成に必要な亜鉛がアルコールの分解に使われてしまうのです。
喫煙は、髪の健康にとって最も避けるべき習慣の一つです。タバコに含まれるニコチンには、血管を強力に収縮させる作用があります。
これにより頭皮の血行が著しく悪化し、毛根への酸素や栄養素の供給が妨げられます。また、喫煙は体内のビタミンCを大量に破壊し、活性酸素を発生させるため、頭皮の老化を早める原因にもなります。
見直したい食習慣
| 食習慣 | 髪への主な影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 脂っこい食事(揚げ物・ファストフード) | 皮脂の過剰分泌、血行不良 | 脂身の少ない肉や魚を選ぶ、蒸し料理や焼き料理にする。 |
| 糖質の過剰摂取(甘い物・ジュース) | ビタミンB群の消費、皮脂の分泌促進 | 白米を玄米に、ジュースをお茶や水にする。 |
| 過度なアルコール摂取 | 亜鉛やビタミンの大量消費 | 休肝日を設け、適量を守る。亜鉛を含むおつまみを選ぶ。 |
無理なダイエットと栄養失調
体重を減らすために、食事を極端に抜いたり、「〇〇だけ食べる」といった偏ったダイエットを行ったりすると、体は深刻な栄養不足状態に陥ります。
特にタンパク質やミネラルが不足すると、体は生命維持を優先し、髪の毛への栄養供給を停止してしまいます。
ダイエット中であっても、髪の材料であるタンパク質、そしてそれをサポートするビタミンやミネラルは、最低限摂取する必要があります。
健康的なダイエットは、バランスの取れた食事を基本としながら、摂取カロリーを適度に調整することが前提です。
髪を育てるための食事の取り方と生活習慣
髪に良い栄養素を理解し、悪い食習慣を避けることができたら、次はその「食べ方」と、食事以外の生活習慣にも目を向けてみましょう。
栄養素を効率よく体に届け、髪の成長を最大限にサポートするためのポイントを紹介します。
バランスの良い食事 (PFCバランス) の基本
特定の栄養素だけを摂取しても、髪は健康に育ちません。タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の「PFCバランス」を意識することが重要です。
タンパク質は髪の材料、炭水化物は体の主要なエネルギー源、脂質はホルモンの材料や細胞膜の構成要素となります。
炭水化物を極端に抜くと、体はエネルギー不足を補うためにタンパク質を分解してエネルギー源として使おうとします。これでは、せっかく摂取したタンパク質が髪の材料として使われません。
主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル)が揃った「定食スタイル」を意識することが、バランスの良い食事への近道です。
「まごわやさしい」(豆・ごま・わかめ・野菜・魚・しいたけ・いも)といった、多様な食材を取り入れることも有効です。
食べる時間と髪の成長
食事は、内容だけでなく時間も大切です。特に夜遅い時間の食事、いわゆる「夜食」は避けるべきです。
夜遅くに食べると、消化活動のために胃腸に血液が集中し、睡眠中に行われるべき髪の成長や修復に使われるエネルギーや栄養が不足しがちになります。
また、夜遅い食事は中性脂肪として蓄積されやすく、肥満や血行不良の原因にもなります。
夕食はなるべく就寝の3時間前までに済ませ、朝・昼・晩とできるだけ決まった時間に食事を摂ることで、体内リズムを整え、栄養の吸収効率を高めることができます。
食事以外で気をつけたい生活習慣 (睡眠・運動)
健康な髪を育てるためには、食事の改善と合わせて生活習慣全体を見直すことが重要です。特に「睡眠」は、髪の成長と深く関わっています。
髪の毛は、私たちが寝ている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長が促されます。特に、入眠後の深い眠り(ノンレム睡眠)の時間帯に成長ホルモンは最も多く分泌されます。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。質の良い睡眠を最低でも6〜7時間は確保するよう努めましょう。
髪の健康を支える生活のポイント
- 質の良い睡眠(6時間以上)
- 適度な運動(ウォーキングなど)
- ストレスの管理(趣味の時間など)
また、「適度な運動」も血行促進に役立ちます。デスクワークが多い人は、全身の血流が滞りがちです。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を習慣にすることで、全身の血行が良くなり、頭皮にも栄養が届きやすくなります。
運動はストレス発散にもつながり、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
食事に戻る
よくある質問
ここでは、食べ物と髪の毛に関する、よく寄せられる質問についてお答えします。
- 特定の食べ物だけを食べ続ければ髪は太くなりますか?
-
いいえ、特定の食べ物だけを食べ続けても髪が太くなることはありません。
例えば、髪に良いとされる亜鉛を多く含む牡蠣や、タンパク質が豊富な肉ばかりを食べていても、他の栄養素が不足していては健康な髪は育ちません。
髪の成長には、タンパク質、亜鉛、ビタミンB群、ビタミンA・C・Eなど、多くの栄養素がチームとして働く必要があります。
一つの食材に偏るのではなく、多様な食材をバランスよく食べることが最も重要です。
- サプリメントで栄養を補うのはどうですか?
-
食事が不規則になりがちな場合や、特定の栄養素がどうしても不足する場合は、サプリメントで補うことも一つの方法です。
特に亜鉛やビタミンB群は、現代の食生活では不足しやすい栄養素でもあります。ただし、サプリメントはあくまで「補助」です。
食事から栄養を摂ることに比べ、サプリメントでは栄養素の吸収率が異なる場合もあります。
まずは食事内容の改善を最優先し、それでも足りない部分をサプリメントで補うという考え方が望ましいです。
また、特定の栄養素の過剰摂取は、かえって体のバランスを崩す可能性もあるため、摂取量を守ることが大切です。
- 食事改善の効果はどれくらいで現れますか?
-
食事を改善してすぐに髪が太くなるわけではありません。
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、今生えている髪は、数ヶ月前に毛根で作られたものです。
食事改善によって頭皮環境や体内の栄養状態が良くなっても、その影響が新しく生えてくる髪に現れるまでには時間がかかります。
髪の毛は1ヶ月に約1cm程度しか伸びません。
効果を実感するためには、最低でも3ヶ月から6ヶ月、あるいはそれ以上、継続してバランスの良い食生活を送る必要があります。焦らず、気長に取り組む姿勢が重要です。
- 外食が多い場合の食事の選び方を教えてください。
外食が多いと、どうしても脂質や糖質、塩分が過剰になりがちです。外食の際は、丼物やラーメン、パスタといった「単品メニュー」をできるだけ避けましょう。
これらは炭水化物に偏り、ビタミンやミネラルが不足しがちです。
おすすめは、主食・主菜・副菜が揃った「定食」です。焼き魚定食や生姜焼き定食、刺身定食などを選び、可能であれば野菜の小鉢やサラダを追加するとバランスが良くなります。
コンビニエンスストアを利用する場合も、おにぎりやパンだけでなく、サラダチキンやゆで卵、野菜サラダ、海藻の入ったスープなどを組み合わせる工夫をしましょう。
Reference
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
LE FLOC’H, Caroline, et al. Effect of a nutritional supplement on hair loss in women. Journal of cosmetic dermatology, 2015, 14.1: 76-82.
ABDO, Farida Samy. Hair Integrity and Health with Dieting. NILES journal for Geriatric and Gerontology, 2025, 8.3: 273-288.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.