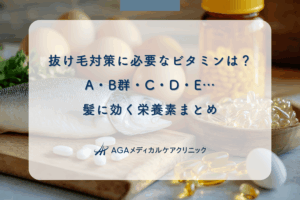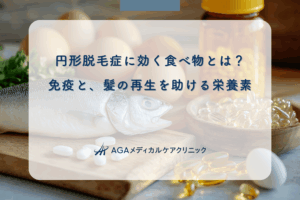鏡を見るたび、枕に残る髪の毛を見るたび、将来への不安がよぎることはありませんか。薄毛の悩みは非常にデリケートですが、決してあなた一人だけのものではありません。
多くの方が同じように悩んでいます。実は、その対策の第一歩は、日々の「食事」にあるかもしれません。
この記事では、なぜ食事が髪の健康に直結するのかを解き明かし、薄毛予防のために積極的に摂りたい「タンパク質」や「亜鉛」などの栄養素、そして逆に避けるべきNGな食品について詳しく解説します。
毎日の食卓から始められる「ハゲないための食事術」を知り、健やかな髪を育むための具体的なヒントを手に入れましょう。食生活の見直しは、未来の自分への大切な投資です。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ食事は髪の健康に関係するのか
毎日の食事が髪の毛の健康状態に深く関わっています。髪は体が摂取した栄養素から作られており、栄養バランスが崩れれば、髪の成長や頭皮環境に直接的な影響が及びます。
髪の毛は何からできている?
髪の毛の主成分は、「ケラチン」というタンパク質の一種です。全体の約80%から90%を占めています。つまり、良質なタンパク質が不足すれば、健康な髪の毛を作る材料が足りなくなることを意味します。
髪は皮膚の一部が変化したものであり、食事から摂る栄養素が、毛根にある毛母細胞に血液を通じて運ばれ、細胞分裂を繰り返すことで成長します。
栄養不足が引き起こすヘアサイクルの乱れ
髪には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)があります。健康な髪は、数年続く成長期に太く長く育ちます。
しかし、食事から得る栄養が不足すると、毛母細胞の活動が鈍くなり、この成長期が短くなることがあります。
結果として、髪が十分に育つ前に抜け落ちる「退行期」や「休止期」に移行しやすくなり、薄毛や抜け毛が目立つ原因となります。
頭皮環境と食事のつながり
髪が育つ土壌である頭皮も、もちろん食事の影響を受けます。例えば、脂っこい食事や糖分の多い食事を続けると、皮脂の分泌が過剰になることがあります。
過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こすなど頭皮環境を悪化させ、健康な髪の成長を妨げる一因となります。
逆に、ビタミン類などが不足すると頭皮が乾燥しやすくなり、フケやかゆみの原因にもなります。
薄毛予防に重要な栄養素「タンパク質」の働き
髪の毛の主成分であるケラチンを生成するために、タンパク質は最も重要な栄養素です。タンパク質が不足すると、髪の毛の質が低下し、細く弱い髪になる可能性があります。
髪の主成分「ケラチン」とタンパク質
髪の大部分を構成するケラチンは、18種類のアミノ酸が結合してできています。このアミノ酸の元となるのが、食事から摂取するタンパク質です。
肉、魚、卵、大豆製品などに含まれるタンパク質は、体内でアミノ酸に分解され、再びケラチンとして合成されて髪の毛となります。特に、ケラチンを構成するアミノ酸の中では「シスチン」が重要です。
タンパク質が不足するとどうなる?
体は生命維持に必要な臓器や筋肉へ優先的にタンパク質(アミノ酸)を送ります。髪の毛は生命維持の優先度が低いため、タンパク質の摂取量が不足すると、髪にまで栄養が回りにくくなります。
その結果、新しい髪が作られにくくなったり、髪が細くなったり、ツヤが失われたり、切れ毛や枝毛が増えたりするなど、髪のトラブルにつながりやすくなります。
タンパク質を効率よく摂る食材
タンパク質は毎日の食事で意識して摂取することが大切です。特に良質なタンパク質を含む食材を積極的に取り入れましょう。
タンパク質が豊富な食材の例
| 食材カテゴリ | 主な食材 | 特徴 |
|---|---|---|
| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、赤身肉 | 高タンパク・低脂質。 |
| 魚介類 | アジ、サバ、イワシ、鮭、エビ | 良質な脂質(EPA・DHA)も摂れる。 |
| 卵・乳製品 | 鶏卵、牛乳、ヨーグルト、チーズ | ビタミンやミネラルも豊富。 |
| 大豆製品 | 納豆、豆腐、豆乳、きな粉 | 植物性タンパク質とイソフラボン。 |
動物性と植物性タンパク質のバランス
タンパク質には、肉や魚などの「動物性タンパク質」と、大豆製品などの「植物性タンパク質」があります。動物性タンパク質はアミノ酸バランスに優れていますが、脂質も多く含みがちです。
植物性タンパク質は脂質が少ない傾向にありますが、特定のアミノ酸が不足することもあります。大切なのは、どちらかに偏るのではなく、両方をバランスよく摂取することです。
多様な食材からタンパク質を摂るよう心がけましょう。
髪の成長を支える「亜鉛」の力
亜鉛は、タンパク質の合成をサポートし、正常な細胞分裂を促すために重要なミネラルです。髪の毛の主成分であるケラチンの合成にも深く関わっており、不足すると抜け毛のリスクが高まります。
亜鉛が持つ重要な役割とは
亜鉛は体内で多くの酵素の働きを助ける補酵素として機能します。特に重要なのが、タンパク質の合成と細胞分裂への関与です。
毛母細胞は体の中でも特に細胞分裂が活発な場所の一つであり、亜鉛はその活動を支えるために必要です。また、亜鉛は男性ホルモンのバランスにも影響を与えると考えられています。
亜鉛不足が薄毛につながる理由
亜鉛が不足すると、タンパク質からケラチンを合成する働きが低下します。その結果、新しい髪が作られにくくなったり、髪の成長が妨げられたりします。
また、毛母細胞の分裂が滞ることでヘアサイクルが乱れ、成長期が短縮して抜け毛が増える可能性があります。
亜鉛は体内で生成できず、汗などでも失われやすいため、食事から意識的に摂取する必要があります。
亜鉛を多く含む食べ物
亜鉛は様々な食品に含まれていますが、特に含有量が多いものを知っておくと便利です。
吸収率を高めるために、ビタミンCやクエン酸(レモンや梅干しなど)と一緒に摂るのも良い方法です。
亜鉛を豊富に含む食材の例
| 食材カテゴリ | 主な食材 | 摂取時のポイント |
|---|---|---|
| 魚介類 | 牡蠣(かき)、うなぎ、いわし | 牡蠣は特に含有量が多い。 |
| 肉類 | レバー(特に豚)、赤身肉(牛) | タンパク質も同時に摂れる。 |
| その他 | チーズ、卵黄、納豆、アーモンド | 間食や朝食に取り入れやすい。 |
タンパク質・亜鉛以外で意識したい栄養素
髪の健康を維持するためには、タンパク質や亜鉛だけでなく、他のビタミンやミネラルもバランスよく摂取することが重要です。
これらの栄養素が互いに助け合い、頭皮環境を整え、髪の成長をサポートします。
ビタミンB群の働きと含まれる食品
ビタミンB群は、エネルギー代謝を助け、頭皮の健康を保つのに役立ちます。特にビタミンB2は皮脂の分泌をコントロールし、頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を促進します。
ビタミンB6はタンパク質の代謝を助け、ケラチンの合成をサポートします。
ビタミンB群が豊富な食材
| ビタミン | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂コントロール、細胞再生 | レバー、うなぎ、卵、納豆 |
| ビタミンB6 | タンパク質代謝、ケラチン合成 | マグロ、カツオ、バナナ、鶏肉 |
ビタミンA・C・Eの頭皮への効果
ビタミンA、C、Eは、その抗酸化作用から「ビタミンACE(エース)」とも呼ばれ、頭皮の健康維持に貢献します。ビタミンAは頭皮の潤いを保ち、ターンオーバーを正常化します。
ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、頭皮を丈夫にし、また鉄分の吸収を高めます。ビタミンEは血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくします。
ビタミンA・C・Eが豊富な食材
| ビタミン | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンA | 頭皮の潤い、新陳代謝 | レバー、緑黄色野菜(人参、ほうれん草) |
| ビタミンC | コラーゲン生成、鉄分吸収UP | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | アーモンド、アボカド、かぼちゃ、植物油 |
鉄分と髪の健康
鉄分は、血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担います。頭皮や毛母細胞も活動するために多くの酸素を必要とします。
鉄分が不足すると、毛母細胞に十分な酸素が届かず、細胞分裂が鈍くなり、髪の成長に影響が出る可能性があります。特にレバーや赤身肉、ほうれん草、ひじきなどに多く含まれます。
イソフラボンと男性ホルモン
大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きを持つことで知られています。
男性型脱毛症(AGA)の原因の一つとされる男性ホルモンの働きを抑制する可能性が指摘されており、薄毛予防の観点から注目されることがあります。
納豆や豆腐などを食事に取り入れることで、タンパク質と同時にイソフラボンも摂取できます。
薄毛予防のために避けたいNGな食事
健康な髪を育むためには、必要な栄養素を摂るだけでなく、髪の成長を妨げる可能性のある食事を避けることも同じくらい重要です。
特に脂質や糖質の過剰摂取は頭皮環境の悪化につながります。
高脂質な食事のリスク
揚げ物、スナック菓子、脂身の多い肉など、脂質(特に飽和脂肪酸やトランス脂肪酸)を多く含む食事は、血液中のコレステロールを増やし、血液をドロドロにしがちです。
その影響で頭皮への血流が悪化し、毛根に栄養が届きにくくなります。また、過剰な脂質は皮脂の分泌を増やし、毛穴の詰まりや脂漏性皮膚炎などを引き起こし、頭皮環境を悪化させる原因となります。
過剰な糖分の摂取
甘いお菓子やジュース、白米やパンなどの精製された炭水化物の摂りすぎも注意が要ります。
糖質を過剰に摂取すると、体内でタンパク質と結びついて「糖化」という現象を引き起こし、細胞の老化を早めるAGEs(終末糖化産物)を生成します。
これは頭皮の弾力性を失わせ、硬くすることにつながります。また、糖質の代謝にはビタミンB群が大量に消費されるため、髪に必要なビタミンB群が不足しがちになります。
注意したい高脂質・高糖質な食べ物
| 分類 | 具体例 | 主な問題点 |
|---|---|---|
| 高脂質な食事 | フライドポテト、唐揚げ、ラーメン | 皮脂の過剰分泌、血行不良 |
| 高糖質な食事 | ケーキ、菓子パン、清涼飲料水 | 糖化による老化促進、ビタミンB群消費 |
アルコールの飲み過ぎに注意
適度なアルコールは血行を良くすることもありますが、飲み過ぎは禁物です。アルコールを分解する過程で、髪に必要なアミノ酸(特にシスチン)やビタミンB群、亜鉛が大量に消費されてしまいます。
また、過度な飲酒は睡眠の質を低下させ、髪の成長に必要な成長ホルモンの分泌を妨げることにもなります。
塩分の摂りすぎと血流
インスタント食品や加工食品に多く含まれる塩分の摂りすぎは、高血圧の原因となり、血管に負担をかけます。
頭皮には毛細血管が張り巡らされていますが、高血圧によって血流が悪化すると、毛根への栄養補給がスムーズに行われなくなります。
日頃から薄味を心がけ、外食や加工食品の利用が多い人は特に注意しましょう。
ハゲないための食生活改善のコツ
特定の栄養素だけを摂取するのではなく、毎日の食生活全体を見直し、バランスの取れた食事を継続することが、薄毛予防への近道です。無理なく続けられる小さなコツから始めましょう。
1日3食バランスよく食べる
最も基本でありながら重要なのが、1日3食を決まった時間に、バランスよく食べることです。
朝食を抜いたり、食事の間隔が空きすぎたりすると、体はエネルギー不足を感じ、髪への栄養供給が後回しになりがちです。
主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル)を揃えることを意識し、様々な食材から栄養を摂るようにしましょう。
食べる順番を意識する
食事の際に食べる順番を工夫することも有効です。まず野菜や海藻類(食物繊維)から食べ始め、次におかず(タンパク質・脂質)、最後にご飯やパン(炭水化物)を食べるようにします。
こうすることで、血糖値の急激な上昇を抑えることができ、糖化の予防やビタミンB群の無駄遣いを防ぐことにつながります。
食事改善の小さな工夫
- 野菜から先に食べる
- よく噛んでゆっくり食べる
- 間食はナッツやヨーグルトにする
よく噛んで食べる習慣
忙しいと早食いになりがちですが、一口一口をよく噛んで食べることも大切です。よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐことができます。
また、消化・吸収が助けられ、栄養素を効率よく体内に取り込むことにもつながります。唾液の分泌も促進され、口腔内の健康維持にも役立ちます。
無理な食事制限は逆効果
ダイエットなどのために極端な食事制限を行うと、髪に必要な栄養素が真っ先に不足します。特にタンパク質やミネラルが不足すると、髪は細く弱くなり、抜け毛が増える原因となります。
健康な髪を保つためには、必要なカロリーと栄養素をしっかり摂取することが前提です。もし減量が必要な場合でも、バランスの取れた食事を心がけながら、適度な運動と組み合わせて行いましょう。
食事以外の生活習慣も見直そう
薄毛予防は食事だけで完結するものではありません。食事で摂った栄養素を効率よく髪に届けるためには、健康的な生活習慣が土台となります。
睡眠、ストレス、運動の3つの側面から見直してみましょう。
質の良い睡眠の重要性
髪の毛の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。特に、入眠後の深いノンレム睡眠の間に最も多く分泌されると言われています。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、毛母細胞の分裂や修復が十分に行われません。
毎日6〜8時間のまとまった睡眠時間を確保し、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、リラックスして眠れる環境を整えましょう。
ストレス管理とリラックス法
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。そのため頭皮の血流が悪化し、毛根に栄養が届きにくくなります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こすこともあります。自分なりのリラックス法を見つけ、ストレスを溜め込まないことが大切です。
生活習慣の見直しポイント
- 十分な睡眠時間の確保
- 趣味や入浴でのリラックス
- 適度な有酸素運動
適度な運動で血流促進
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、全身の血流、特に頭部への血流が滞りがちです。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な運動を習慣にすることで、全身の血行が良くなり、頭皮の毛細血管にもしっかりと血液(栄養)が届くようになります。
運動はストレス解消にも役立つため、一石二鳥の効果が期待できます。
食事に戻る
Q&A
ハゲないための食事術に関してよく寄せられる疑問にお答えします。
- サプリメントで栄養を補うのは効果がありますか?
-
食事から全ての栄養素をバランスよく摂ることが基本ですが、食生活が不規則になりがちな場合、サプリメントで不足しがちな栄養素(特に亜鉛やビタミンB群など)を補うことは一つの方法です。
ただし、サプリメントはあくまで補助的なものです。過剰摂取はかえって体に負担をかけることもあるため、適切な量を守り、食事改善と並行して利用することを考えましょう。
- 特定の食べ物だけを食べ続ければ髪は生えますか?
-
特定の食品(例えば、わかめや昆布など)だけを食べても、それだけで髪が生えたり増えたりすることはありません。
髪の健康は、タンパク質、亜鉛、ビタミンなど多くの栄養素が複合的に関わり合って維持されています。
海藻類はミネラルが豊富で髪に良い食材の一つですが、そればかりに偏らず、多様な食材をバランスよく食べることが最も重要です。
- 食生活を改善してからどれくらいで効果が出ますか?
-
髪の毛にはヘアサイクルがあるため、食生活を改善してもすぐに目に見える効果が現れるわけではありません。
今生えている髪の質が変わるのではなく、これから新しく生えてくる髪の毛が健康になる、あるいはヘアサイクルが正常化する、という形で影響が出ます。
最低でも3ヶ月から6ヶ月は、根気よく健康的な食生活を続けることが必要です。
- 外食が多い場合の注意点はありますか?
-
外食は一般的に脂質、糖質、塩分が多くなりがちで、ビタミンやミネラルが不足しやすい傾向があります。
外食する際は、できるだけ野菜(サラダや小鉢など)を追加で注文する、ラーメンのスープは飲み干さない、揚げ物よりも焼き魚や刺身、蒸し料理などを選ぶ、といった工夫を心がけましょう。
定食形式で主菜・副菜が揃っているものを選ぶのが比較的バランスを取りやすいです。
Reference
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
RAJENDRASINGH, Rajesh Rajput. Nutritional correction for hair loss, thinning of hair, and achieving new hair regrowth. In: Practical Aspects of Hair Transplantation in Asians. Tokyo: Springer Japan, 2017. p. 667-685.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
ABDO, Farida Samy. Hair Integrity and Health with Dieting. NILES journal for Geriatric and Gerontology, 2025, 8.3: 273-288.
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.