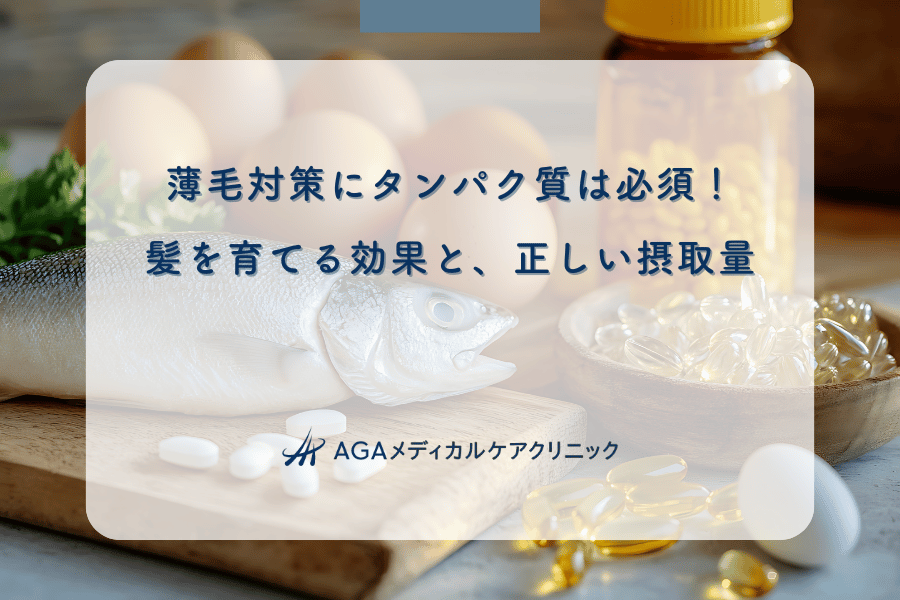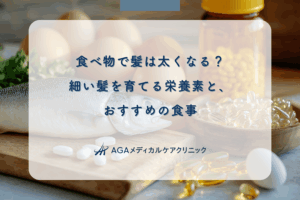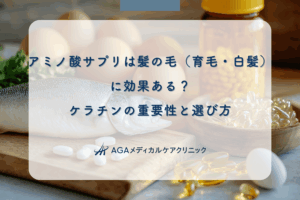鏡を見るたびに気になる、髪のボリュームダウンや抜け毛。「薄毛対策」として育毛剤や頭皮マッサージを試している方も多いでしょう。
しかし、髪の毛そのものを作る「栄養素」が足りていなければ、十分な効果は期待できません。その最も重要な栄養素が「タンパク質」です。髪の約90%はタンパク質でできています。
この記事では、なぜ薄毛対策にタンパク質が必要なのか、髪を育てる具体的な効果、そして1日にどれくらい摂取すべきか、正しい知識を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
タンパク質と髪の毛の深い関係
薄毛対策を考える上で、タンパク質の摂取は基本中の基本です。私たちの体を作る上で中心的な役割を担うタンパク質は、もちろん髪の毛にとっても命綱とも言える存在です。
なぜそれほどまでにタンパク質が重要なのか、その根本的な理由から見ていきましょう。
髪の主成分は「ケラチン」というタンパク質
私たちが毎日目にしている髪の毛。その成分の約90%以上は、「ケラチン」という種類のタンパク質から構成されています。
ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできており、髪の強さやしなやかさを生み出しています。つまり、髪の毛の「材料」そのものがタンパク質だということです。
どれだけ高価な育毛剤で頭皮環境を整えても、主原料であるタンパク質が体内に不足していては、健康な髪の毛は作られません。
タンパク質不足が招く髪への深刻な影響
もし体内のタンパク質が不足すると、私たちの体は生命維持に重要な臓器や筋肉へ優先的にタンパク質を供給しようと働きます。
髪の毛や爪は、生命維持の観点からは優先度が低く設定されます。その結果、髪の毛を作るためのタンパク質(ケラチン)の合成が後回しになり、以下のような深刻な影響が現れ始めます。
- 髪の毛が細くなる(軟毛化)
- 髪の成長が遅くなる
これらが進行すると、抜け毛が増えたり、髪全体のボリュームが失われたりする、いわゆる「薄毛」の状態につながってしまいます。
薄毛対策の土台としてのタンパク質の役割
薄毛対策には、頭皮の血行促進、男性ホルモンの影響の抑制、頭皮環境の改善など、様々なアプローチがあります。しかし、それらはすべて「健康な髪を育てるための環境整備」です。
タンパク質を十分に摂取することは、その環境で育つ「髪の毛の材料を確保する」という、最も根本的な土台作りにあたります。
家を建てる際に、土地を整地する(頭皮ケア)のと同じくらい、良質な建材(タンパク質)を用意することが大切なのです。
髪を育てる!タンパク質の具体的な効果
タンパク質が髪の材料であることは分かりました。では、タンパク質をしっかり摂取することで、具体的にどのような「髪を育てる効果」が期待できるのでしょうか。
毛根部分で起こっている活動に着目して解説します。
毛母細胞の働きを活発にする
髪の毛は、毛穴の奥にある「毛乳頭」が毛細血管から栄養を受け取り、その栄養をもとに「毛母細胞」が細胞分裂を繰り返すことで作られます。
この毛母細胞が分裂する際のエネルギー源、そして細胞そのものの構成要素として、タンパク質(アミノ酸)が必要です。
タンパク質が十分にあれば、毛母細胞は活発に分裂を繰り返すことができ、髪の毛を力強く押し上げていきます。
強く太い髪の毛の生成をサポート
タンパク質が不足すると、毛母細胞は十分な材料がないまま髪を作らなければなりません。その結果、十分に太くなれず、細く弱々しい髪の毛(軟毛)になってしまいます。
細い髪は外部からのダメージに弱く、切れ毛や抜け毛の原因にもなります。
タンパク質を適切に摂取することは、髪の内部構造を密にし、ハリやコシのある、強く太い髪の毛を育てるために直接的に貢献します。
ヘアサイクル(毛周期)を整えるサポート
髪の毛には「成長期(髪が伸びる時期)」「退行期(成長が止まる時期)」「休止期(髪が抜け落ちる時期)」というヘアサイクルがあります。
薄毛が進行している状態では、この「成長期」が短くなり、髪が十分に育つ前に抜け落ちてしまうケースが多く見られます。
タンパク質をはじめとする栄養素が安定して供給されると、毛母細胞が活発に働き続けられるため、本来の「成長期」の期間を維持しやすくなります。
ヘアサイクルが整うことは、抜け毛を減らし、髪全体の密度を保つ上で非常に重要です。
あなたに必要なタンパク質の摂取量を知ろう
タンパク質の重要性がわかったところで、次に「では、1日にどれくらい摂取すればよいのか?」という疑問にお答えします。
やみくもに多く摂ればよいというものではなく、ご自身の体重や活動量に合わせた適切な量を知ることが大切です。
1日に必要なタンパク質の目安
厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準」では、成人男性のタンパク質「推奨量」は1日65gとされています。これは、健康を維持するための一般的な目安です。
ただし、これはあくまで標準的な数値であり、体重や日常の活動レベルによって必要な量は変わってきます。
体重別に見る推奨摂取量
より個人に合わせた必要量を計算する場合、「体重1kgあたり何gか」という考え方を用います。一般的な成人であれば「体重1kgあたり1.0g」が一つの目安です。
例えば、体重70kgの人であれば、1日70gのタンパク質が必要となります。
日常的に筋力トレーニングなど運動習慣がある人は、筋肉の修復と成長のためにより多くのタンパク質が必要となり、体重1kgあたり1.5g〜2.0g程度を目安にすることもあります。
体重別のタンパク質摂取目安(1日あたり)
| 体重 | 一般的な活動量 (体重×1.0g) | 運動習慣がある場合 (体重×1.5g) |
|---|---|---|
| 60kg | 60g | 90g |
| 70kg | 70g | 105g |
| 80kg | 80g | 120g |
薄毛が気になる場合の摂取量の考え方
薄毛や髪質の低下が気になる場合、まずは現在の食生活で「体重1kgあたり1.0g」の基準を満たせているかを確認しましょう。
もし明らかに不足しているようであれば、まずはこの基準量を安定して摂取することを目指します。
タンパク質は髪だけでなく、筋肉、内臓、皮膚など、体のあらゆる部分で使われるため、まずは体全体の必要量を満たすことが、髪へ栄養を届けるための第一歩です。
摂取量が多すぎてもダメ? 過剰摂取のリスク
「髪のために」と、タンパク質を極端に多く摂取することは推奨できません。タンパク質を摂取すると、体内で分解される過程で「窒素」が発生します。
この窒素は、肝臓で尿素に変換され、最終的に腎臓でろ過されて尿として排出されます。タンパク質を過剰に摂取し続けると、この肝臓や腎臓に大きな負担をかけてしまう可能性があります。
特に腎機能が低下している方は注意が必要です。何事もバランスが大切であり、目安量を大きく超えるような摂取は避けましょう。
効果的なタンパク質の摂取方法(食品編)
タンパク質を摂取するといっても、具体的にどのような食品から摂るのが効果的なのでしょうか。タンパク質には大きく分けて「動物性」と「植物性」の2種類があり、それぞれに特徴があります。
バランス良く摂取することが、健康な髪を育てる鍵となります。
動物性タンパク質の特徴と食材
肉、魚、卵、乳製品などに含まれるタンパク質です。動物性タンパク質の最大のメリットは「アミノ酸スコア」が高いことです。
アミノ酸スコアとは、体内で合成できない9種類の「必須アミノ酸」がどれだけバランス良く含まれているかを示す指標です。動物性タンパク質は、このバランスに優れており、体内で効率よく利用されます。
髪の主成分であるケラチンを構成するアミノ酸(特にメチオニン)も効率的に摂取できます。ただし、食材によっては脂質(飽和脂肪酸)も多く含むため、部位や調理法に注意が必要です。
植物性タンパク質の特徴と食材
大豆製品、穀物、野菜などに含まれるタンパク質です。植物性タンパク質のメリットは、動物性に比べて低脂質・低カロリーである点です。
また、食物繊維やビタミン、ミネラル、抗酸化物質(イソフラボンなど)も同時に摂取できることが多いのも魅力です。
特に大豆製品に含まれるイソフラボンは、男性ホルモンのバランスを整える働きが期待されており、薄毛対策の観点からも注目されます。
動物性と植物性をバランス良く摂るコツ
理想は「動物性:植物性 = 1:1」の割合で摂取することです。
例えば、朝食は卵(動物性)と納豆(植物性)、昼食は鶏むね肉(動物性)、夕食は魚(動物性)と豆腐の味噌汁(植物性)といった具合です。
片方に偏るのではなく、多様な食材からタンパク質を摂ることで、必須アミノ酸だけでなく、髪の成長に必要な他の栄養素も同時に補うことができます。
タンパク質を多く含む主な食品
| 分類 | 食品名 (可食部100gあたり) | タンパク質量 (目安) |
|---|---|---|
| 動物性 | 鶏むね肉(皮なし) | 約23.3g |
| 鮭(しろさけ) | 約22.3g | |
| 卵(全卵) | 約12.3g (Mサイズ1個で約6.2g) | |
| プロセスチーズ | 約22.7g | |
| 植物性 | 納豆 | 約16.5g (1パック50gで約8.3g) |
| 木綿豆腐 | 約7.0g | |
| アーモンド(乾) | 約19.6g |
忙しい人へ プロテインやサプリの活用術
毎日の食事で十分なタンパク質を摂るのが理想ですが、忙しい現代人にとって、3食すべてでバランスを考えるのは難しい場合もあります。
そのような時は、プロテインドリンクやサプリメントを上手に活用するのも一つの方法です。
食事で補いきれない場合の選択肢
特に朝食を抜きがちな人や、昼食が麺類や丼物で偏りがちな人は、タンパク質が不足しやすい傾向にあります。
1日の目標量に届かないと感じる日や、運動後で特にタンパク質を補給したいタイミングで、補助的にプロテインを活用するのは非常に効率的です。
あくまで食事の補助として捉え、基本は食事から摂る意識を持ちましょう。
プロテインの種類と選び方
プロテインにはいくつか種類があり、それぞれ吸収速度や特徴が異なります。目的に合わせて選ぶことが大切です。
主なプロテインの種類と特徴
| 種類 | 原料 | 特徴 |
|---|---|---|
| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収が速い。運動後や朝の摂取に向く。アミノ酸スコアが高い。 |
| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収がゆっくり。腹持ちが良く、就寝前や間食に向く。 |
| ソイプロテイン | 大豆 | 吸収がゆっくり。植物性。イソフラボンも摂取できる。 |
薄毛対策を意識する場合、アミノ酸バランスの良い「ホエイ」を基本にしつつ、植物性タンパク質も補える「ソイ」を併用する、あるいはソイを選ぶのも良い考え方です。
タンパク質関連のサプリメント(アミノ酸)
タンパク質は体内でアミノ酸に分解されてから吸収されます。
そのため、すでに分解された状態のアミノ酸(BCAAやEAAなど)や、髪の主成分ケラチンの構成に重要な「L-シスチン」や「メチオニン」といった特定のアミノ酸をサプリメントで直接補給する方法もあります。
これらはプロテインよりもさらに吸収が速いですが、あくまで特定の目的を補強するものとして考え、まずはタンパク質全体の摂取量を確保することを優先しましょう。
タンパク質だけでは不十分? 髪育を加速させる相乗効果
ここまでタンパク質の重要性を強調してきましたが、実はタンパク質だけを大量に摂取しても、それだけでは効率よく髪の毛にはなってくれません。
摂取したタンパク質が体内で適切に利用され、髪の毛として合成されるためには、他の栄養素によるサポートが必要です。
タンパク質の働きを助ける「亜鉛」
亜鉛は、薄毛対策においてタンパク質と並んで非常に重要なミネラルです。亜鉛には、摂取したタンパク質を髪の毛(ケラチン)に再合成するのを助ける重要な働きがあります。
どれだけタンパク質を摂っても、亜鉛が不足していると、髪の毛への変換がスムーズに進みません。
また、亜鉛はAGA(男性型脱毛症)の原因とされる5αリダクターゼという酵素の働きを抑制する可能性も指摘されています。牡蠣、レバー、赤身肉、ナッツ類などに多く含まれます。
代謝をサポートする「ビタミンB群」
ビタミンB群、特に「ビタミンB2」と「ビタミンB6」はタンパク質の代謝に深く関わっています。ビタミンB6は、タンパク質をアミノ酸に分解し、再合成するのを助けます。
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助け、頭皮環境を健やかに保つ役割があります。これらが不足すると、タンパク質を効率よくエネルギーや体の材料に変えることができません。
レバー、青魚、バナナ、玄米などに多く含まれます。
頭皮環境を整える「ビタミンC・E」
ビタミンCは、コラーゲンの生成を助け、頭皮の健康や毛細血管を丈夫に保つ働きがあります。また、鉄分の吸収を助ける役割もあります。
ビタミンEは、その強い抗酸化作用で知られ、頭皮の血行を促進し、毛母細胞へ栄養を届けるサポートをします。これらのビタミンは、タンパク質が働くための「土壌(頭皮)」を整える役割を担います。
髪育をサポートする他の栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | タンパク質の合成(ケラチン生成)を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉、アーモンド |
| ビタミンB群 (B2, B6) | タンパク質の代謝をサポートする | レバー、マグロ、カツオ、バナナ、卵 |
| ビタミンC・E | 頭皮環境を整え、血行を促進する | ピーマン、ブロッコリー、ナッツ類、植物油 |
薄毛対策でタンパク質を摂る際の注意点
健康な髪を育てるためにタンパク質は重要ですが、摂取の仕方にはいくつかの注意点があります。
間違った摂り方をすると、かえって体に負担をかけたり、期待した効果が得られなかったりすることもあります。
一度に大量摂取せず、こまめに分ける
私たちの体は、一度に吸収・処理できるタンパク質の量に限界があります。
例えば、1日の目標が90gだからといって、夕食だけで90gを摂取しようとしても、その多くは吸収しきれずに体外へ排出されたり、脂肪として蓄積されたりしてしまいます。
1回の食事で吸収できるのは30g〜40g程度とも言われます。朝・昼・晩の3食、あるいは間食も利用して、こまめに分けて摂取するのが最も効率的です。
脂質の摂り過ぎに注意(特に動物性)
タンパク質を摂ろうとして、脂身の多い肉(バラ肉やサーロイン)や揚げ物ばかりを選んでいると、同時に大量の脂質(特に飽和脂肪酸)を摂取することになります。
脂質の過剰摂取は、皮脂の分泌を過剰にし、頭皮環境を悪化させる(脂漏性脱毛症など)可能性があります。また、血液がドロドロになり、頭皮への血流が悪化する原因にもなります。
タンパク質源としては、鶏むね肉、ささみ、白身魚、赤身肉、大豆製品など、高タンパク・低脂質な食材を意識して選びましょう。
腎臓への負担を考慮する
前述の通り、タンパク質を代謝する過程で腎臓には負担がかかります。
健康な人であれば目安量の摂取は問題ありませんが、すでに腎機能に不安がある方や、健康診断で数値の異常を指摘されたことがある方は、タンパク質の摂取量を増やす前に必ず医師に相談してください。
また、水分補給をしっかり行うことも、老廃物の排出を助け、腎臓の負担を軽減することにつながります。
朝食でのタンパク質摂取の重要性
朝食を抜いたり、パンやおにぎりだけで済ませたりしていませんか? 就寝中にタンパク質が消費された後、朝は体が栄養(特にタンパク質)を最も欲している状態です。
朝食でタンパク質をしっかり補給することで、日中の活動エネルギーが確保できるだけでなく、体内のアミノ酸濃度を一日中安定させることができます。
卵、納豆、ヨーグルト、プロテインドリンクなど、手軽なものでも良いので、朝食に一品タンパク質を加える習慣をつけましょう。
タンパク質の摂取タイミング例(1日80g目標)
| タイミング | 摂取例 | タンパク質量 (目安) |
|---|---|---|
| 朝食 | 卵1個、納豆1パック、ごはん | 約15g |
| 昼食 | 鶏むね肉のサラダチキン(100g) | 約23g |
| 間食 | プロテイン(1杯) | 約20g |
| 夕食 | 鮭1切れ(100g)、豆腐半丁(150g) | 約32g |
栄養素に戻る
薄毛とタンパク質に関するよくある質問
最後に、薄毛とタンパク質の関係について、多くの方が抱く疑問にお答えします。
- プロテインを飲むと薄毛になりますか?
-
いいえ、プロテインを飲むこと自体が薄毛の直接的な原因になることはありません。むしろ、食事でタンパク質が不足している人にとっては、薄毛対策のサポートになります。
ただし、「プロテイン=筋肉増強剤」という誤ったイメージから、男性ホルモン(テストステロン)を増加させ、結果としてAGA(男性型脱毛症)を進行させるのではないかと心配する声があります。
しかし、プロテインは単なるタンパク質(食品)であり、ホルモンバランスを直接的に大きく変動させるものではありません。適切な量を守って摂取する限り、心配する必要は低いと考えられます。
- タンパク質を摂り始めたら、どれくらいで効果が出ますか?
-
髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びません。また、栄養状態が改善されてから、新しく健康な髪が作られ、それが目に見える長さまで伸びてくるには時間がかかります。
そのため、タンパク質の摂取を意識し始めてから髪質の変化を実感するまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月は必要と考えるのが妥当です。
ヘアサイクルは数年にわたる長いものですので、短期的な結果を求めず、継続的な食生活の改善として捉えることが大切です。
- 髪に良いタンパク質の種類はありますか?
-
特定の「髪に良いタンパク質」というものはありません。重要なのは、髪の主成分であるケラチンを構成するアミノ酸を含む、バランスの取れたタンパク質を摂取することです。
動物性タンパク質(肉、魚、卵など)と植物性タンパク質(大豆製品など)を偏りなく、多様な食品から摂ることを心がけてください。
特に大豆に含まれるイソフラボンは、薄毛対策の観点からもメリットが期待できるため、意識して取り入れると良いでしょう。
- タンパク質が足りているか確認する方法はありますか?
-
厳密に知るには血液検査などが必要ですが、セルフチェックとしては、まず毎日の食事内容を記録し、摂取量を計算してみるのが一番です。
「体重1kgあたり1.0g」の目安に達しているかを確認しましょう。
また、体からのサインとして、「爪が割れやすくなった」「肌のハリが失われた」「筋肉が落ちやすくなった」といった変化も、タンパク質不足のサインである可能性があります。
髪の毛は栄養が最後に回される場所ですので、これらのサインが出ている場合は、髪にも十分な栄養が届いていない可能性があります。
Reference
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
NATARELLI, Nicole; GAHOONIA, Nimrit; SIVAMANI, Raja K. Integrative and mechanistic approach to the hair growth cycle and hair loss. Journal of clinical medicine, 2023, 12.3: 893.
MILLER, William Jack, et al. Effects of high protein diets with normal and low energy intake on wound healing, hair growth, hair and serum zinc, and serum alkaline phosphatase in dairy heifers. The Journal of Nutrition, 1969, 98.4: 411-419.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.
HORNFELDT, Carl S. Growing evidence of the beneficial effects of a marine protein‐based dietary supplement for treating hair loss. Journal of Cosmetic Dermatology, 2018, 17.2: 209-213.