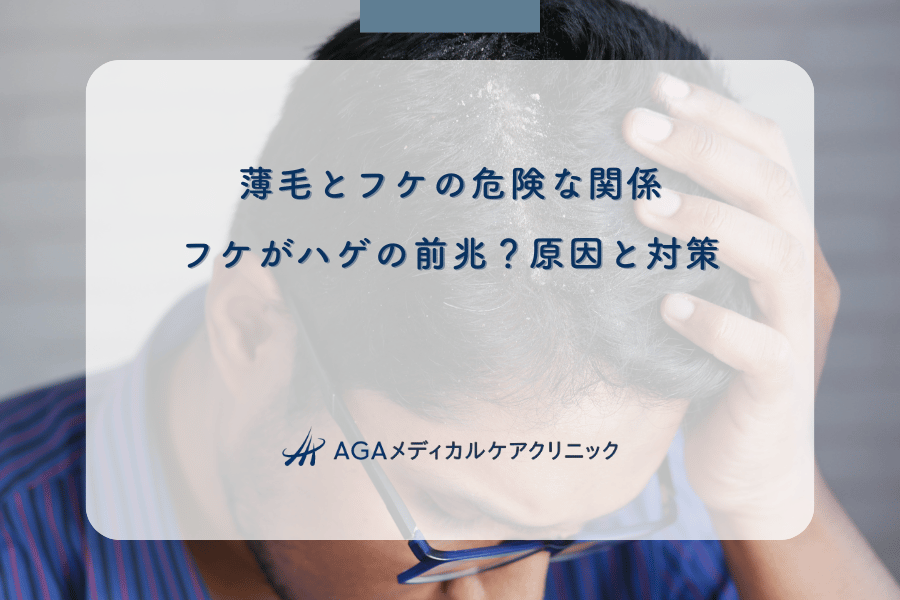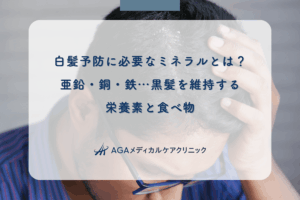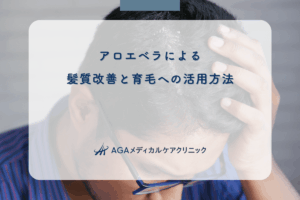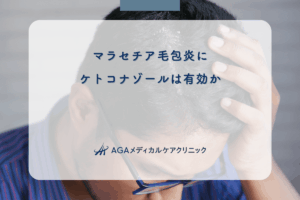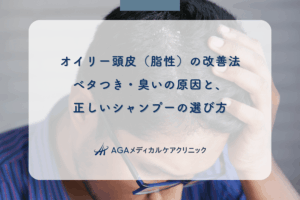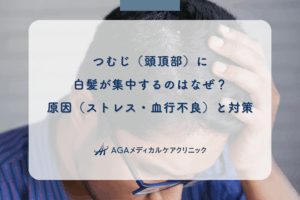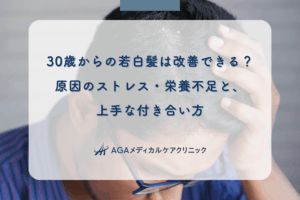ふと肩を見ると、黒いスーツに白い粉が…。そんなフケの悩み、ありませんか。フケが出るだけでも気になりますが、「もしかして、これは薄毛の前兆なのでは?」と不安に感じている方も多いかもしれません。
その不安は、残念ながら的を射ている可能性があります。フケと薄毛は、どちらも頭皮環境の悪化という共通の根から生じている場合が多いのです。
この記事では、なぜフケが薄毛のサインとなり得るのか、その原因と具体的な対策を詳しく解説します。
フケの種類を知り、正しいケアを実践することで、頭皮環境を整え、健やかな髪を守る第一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
フケがハゲの前兆と言われる理由
フケがハゲ(薄毛・AGA)の前兆と言われるのは、フケの発生自体が「頭皮環境が正常ではない」という危険信号だからです。
髪の毛は頭皮という土壌から生えており、その土壌が荒れていれば、健康な髪が育ちにくくなるのは当然のこと。
フケが大量に発生している状態は、薄毛につながる頭皮トラブルがすでに進行している可能性を示唆しています。
頭皮環境の悪化シグナル
健康な頭皮は、適度な皮脂と水分によってバリア機能が保たれ、ターンオーバー(新陳代謝)が正常に行われます。
このターンオーバーによって古い角質が剥がれ落ちるのが、本来の「フケ」です。通常は非常に小さく目に見えません。
しかし、何らかの原因で頭皮環境が悪化すると、このターンオーバーの周期が乱れます。早まった周期で未熟な角質が大量に剥がれ落ちたり、皮脂が過剰に分泌されて角質が大きな塊になったりします。
これが、私たちが「フケが出た」と認識する状態です。つまり、目に見えるフケは、頭皮のバリア機能が低下し、炎症やかゆみ、乾燥、過剰な皮脂分泌といったトラブルを抱えている証拠なのです。
フケと薄毛の共通原因
フケを引き起こす原因の多くは、薄毛を引き起こす原因とも重なります。
例えば、過剰な皮脂分泌はフケ(脂性フケ)の原因であると同時に、毛穴を詰まらせて炎症を引き起こし、髪の成長を妨げる要因にもなります。
また、頭皮の乾燥はフケ(乾燥フケ)の原因であり、バリア機能の低下を招き、外部からの刺激に弱いデリケートな頭皮状態にします。これが炎症につながり、抜け毛を誘発することもあります。
生活習慣の乱れ、特に食生活の偏りや睡眠不足、ストレスなども、頭皮の血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こし、フケと薄毛の両方を悪化させる共通の要因です。
放置が招くリスク
フケを「ただの汚れ」と軽視して放置すると、頭皮環境はさらに悪化します。フケや過剰な皮脂をエサにして雑菌(特にマラセチア菌)が繁殖し、かゆみや炎症を引き起こします。
かゆいからと頭皮を掻きむしれば、頭皮が傷つき、さらに炎症が悪化し、毛根にダメージを与えてしまいます。
この炎症が慢性化すると、「脂漏性皮膚炎」や「粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう)」といった、抜け毛を伴う頭皮の疾患に発展する危険性もあります。
フケは、頭皮が発する初期の警告であり、それを無視すれば薄毛という深刻な結果につながる可能性が高まるのです。
フケの種類とそれぞれの特徴
フケには、大きく分けて「乾燥フケ(乾性フケ)」と「脂性フケ(脂漏性フケ)」の2種類があり、それぞれ原因や対策が異なります。
自分のフケがどちらのタイプかを知ることが、適切なケアの第一歩です。頭皮の状態やフケの見た目から、自分のタイプを判断してみましょう。
乾燥フケ(乾性フケ)とは
乾燥フケは、頭皮が乾燥することによって発生するフケです。頭皮の皮脂分泌が少なすぎたり、洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったりすることが主な原因です。
頭皮の水分が失われ、バリア機能が低下すると、角質が細かく剥がれやすくなります。このタイプは、特に空気が乾燥する冬場に悪化しやすい傾向があります。
特徴としては、パラパラとした細かい粉状で、白くカサカサしています。肩や首筋に落ちやすいため、黒っぽい服を着ていると目立ちやすいです。頭皮自体も乾燥しており、かゆみを伴うことも少なくありません。
脂性フケ(脂漏性フケ)とは
脂性フケは、頭皮の皮脂が過剰に分泌されることによって発生するフケです。
男性ホルモンの影響や、脂っこい食事、ストレスなどで皮脂分泌が活発になると、この皮脂をエサにする常在菌「マラセチア菌」が異常増殖しやすくなります。
マラセチア菌が皮脂を分解する際に発生する物質が頭皮を刺激し、炎症とターンオーバーの異常を引き起こします。
特徴としては、ベタベタと湿り気があり、乾燥フケよりも大きく黄色っぽい色をしています。頭皮にこびりついたり、髪の根元にくっついたりすることが多く、独特の臭いを伴うこともあります。
頭皮もベタつきやすく、強いかゆみや赤みを伴う「脂漏性皮膚炎」に進行しやすいのもこのタイプです。
フケの種類の見分け方
自分のフケがどちらのタイプかを見分けるには、フケの形状と頭皮の状態をチェックするのが最も分かりやすい方法です。以下の表で、ご自身の状態と照らし合わせてみてください。
フケの種類別チェックポイント
| チェック項目 | 乾燥フケ(乾性フケ) | 脂性フケ(脂漏性フケ) |
|---|---|---|
| フケの見た目 | 小さく、カサカサ、粉っぽい | 大きく、ベタベタ、湿っぽい |
| フケの色 | 白 | 白~黄色っぽい |
| 頭皮の状態 | 乾燥している、つっぱる感じがする | ベタついている、脂っぽい |
| かゆみ | 乾燥によるかゆみ(チクチク) | 炎症によるかゆみ(強い) |
| 発生しやすい時期 | 秋~冬(空気が乾燥する時期) | 夏(汗や皮脂が増える時期)※個人差あり |
ただし、これらは一般的な傾向であり、両方の特徴を併せ持つ混合タイプの場合もあります。
判断に迷う場合や、かゆみや炎症がひどい場合は、自己判断せずに皮膚科を受診することをおすすめします。
フケを発生させる主な原因
フケが発生する背景には、頭皮環境を乱すさまざまな要因が隠されています。フケは単に不潔だからという理由だけで発生するわけではなく、日々の生活習慣やヘアケアの方法が大きく関わっています。
主な原因を理解し、当てはまるものがないか見直してみましょう。
間違ったヘアケア
毎日のシャンプーが、逆にフケの原因になっているケースは少なくありません。
例えば、洗浄力の強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、頭皮を守るのに必要な皮脂まで奪い去り、乾燥フケを引き起こしやすくします。
逆に、頭皮がベタつくからと1日に何度もシャンプーをすると、頭皮は失われた皮脂を補おうとさらに過剰に皮脂を分泌し、脂性フケが悪化するという悪循環に陥ることもあります。
また、熱すぎるお湯での洗髪、爪を立ててゴシゴシ洗う、すすぎ残しなども頭皮を傷つけたり刺激したりする原因となります。
生活習慣の乱れ
頭皮の健康は、体全体の健康状態と密接に関連しています。特に食生活、睡眠、ストレスの影響は顕著です。
食生活と頭皮の健康
脂質の多い揚げ物やスナック菓子、糖質の多い甘いもの、刺激の強い香辛料などの過剰摂取は、皮脂の分泌を促し、脂性フケの原因となります。
一方で、過度なダイエットは栄養不足を招き、頭皮の乾燥やターンオーバーの乱れにつながります。頭皮の健康を保つためには、ビタミンB群やタンパク質など、バランスの取れた食事が重要です。
睡眠不足の影響
睡眠中は成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や新陳代謝(ターンオーバー)が行われます。睡眠不足が続くと、この働きが滞り、頭皮のターンオーバーが乱れてフケが発生しやすくなります。
また、血行不良にもつながり、髪の成長に必要な栄養が頭皮に届きにくくなります。
ストレスの影響
精神的なストレスは、自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こします。この影響で、血管が収縮して頭皮の血行が悪くなったり、皮脂の分泌が過剰になったり、免疫力が低下したりします。
ストレスがフケやかゆみを悪化させ、さらにそのことがストレスになるという悪循環も起こり得ます。適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。
マラセチア菌の異常増殖
マラセチア菌は、誰の頭皮にも存在する常在菌(カビの一種)です。通常は害はありませんが、皮脂や汗、湿気などをエサにして増殖します。
何らかの原因で皮脂が過剰に分泌されたり、頭皮の免疫力が低下したりすると、マラセチア菌が異常に増殖します。
この菌が皮脂を分解する際に生み出す脂肪酸が頭皮を刺激し、炎症(脂漏性皮膚炎)を引き起こし、ターンオーバーを異常に早めることで、脂性フケが大量に発生する原因となります。
薄毛につながる危険なフケのサイン
フケが出ている状態はすべて頭皮環境の悪化を示していますが、中でも特に注意が必要な「危険なフケ」のサインがあります。
これらのサインが見られた場合、すでに薄毛が進行しやすい状態になっているか、頭皮の疾患が隠れている可能性があります。早急な対策が必要です。
フケが急に増えた
以前は気にならなかったのに、ここ最近、急にフケの量が目に見えて増えたという場合は注意が必要です。これは、頭皮のターンオーバーが急激に乱れたことを示しています。
生活習慣の大きな変化や強いストレス、あるいは使用しているヘアケア製品が合わなくなったなど、何らかの強い要因によって頭皮環境が急速に悪化している可能性があります。
かゆみや赤みを伴うフケ
フケと同時に、頭皮に強いかゆみや赤み、湿疹などが出ている場合、それは単なるフケではなく「脂漏性皮膚炎」や「接触性皮膚炎(かぶれ)」などの皮膚疾患の可能性があります。
特に脂漏性皮膚炎は、マラセチア菌の異常増殖による炎症であり、放置すると炎症が毛穴の奥深くまで及び、毛根にダメージを与えて抜け毛(脂漏性脱毛症)を引き起こすことがあります。
かゆいからと掻いてしまうと、さらに炎症が悪化し、薄毛のリスクを高めます。
ベタついた大きなフケ
乾燥したパラパラしたフケよりも、ベタベタと湿り気があり、サイズが大きく、頭皮にこびりついているようなフケは、脂性フケの中でも特に状態が悪いサインです。
過剰な皮脂分泌とターンオーバーの極端な乱れを示しています。このようなフケは毛穴を塞ぎやすく、毛穴内部での炎症(毛嚢炎)を引き起こす原因となります。
毛穴が塞がれ、炎症が起これば、髪の正常な成長は妨げられ、抜け毛や細毛につながります。
フケ対策が効かない
市販のフケ用シャンプーを使ってみたり、生活習慣を改めたりしても、フケが一向に改善しない、あるいは悪化する一方だという場合も危険なサインです。
セルフケアでは対応できないレベルまで頭皮環境が悪化しているか、あるいはフケの原因が「乾癬(かんせん)」など、別の皮膚疾患である可能性も考えられます。
自己流のケアを続けることでかえって症状を悪化させることもあるため、専門家である皮膚科医の診断を仰ぐことが賢明です。
危険なフケのサインまとめ
| 危険なサイン | 考えられる状態 | 放置するリスク |
|---|---|---|
| 急激なフケの増加 | 頭皮環境の急激な悪化、ターンオーバーの重度の乱れ | 急速な頭皮トラブルの進行 |
| 強いかゆみ・赤み | 脂漏性皮膚炎、接触性皮膚炎などの炎症 | 炎症による毛根へのダメージ、脂漏性脱毛症 |
| ベタついた大きなフケ | 重度の皮脂過剰、毛穴の詰まり | 毛嚢炎、髪の成長阻害、抜け毛 |
フケと薄毛を防ぐための正しいシャンプー方法
フケと薄毛の対策において、毎日のシャンプーは最も基本的かつ重要なケアです。
頭皮を清潔に保ちつつ、必要な潤いを奪わない「正しいシャンプー方法」を身につけることが、頭皮環境改善の鍵となります。洗い方一つで、頭皮の状態は大きく変わります。
シャンプー選びの基本
フケ対策の第一歩は、自分の頭皮タイプやフケの種類に合ったシャンプーを選ぶことです。単に「フケ用」と書かれているものではなく、乾燥フケなのか脂性フケなのかによって選ぶべき成分が異なります。
乾燥フケの場合は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系やベタイン系の洗浄成分をベースにし、セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分が配合されたものが適しています。
脂性フケの場合は、過剰な皮脂を適度に洗い流しつつ、マラセチア菌の増殖を抑える抗真菌成分(ミコナゾール硝酸塩、ピロクトンオラミンなど)や、炎症を抑える成分(グリチルリチン酸ジカリウムなど)が配合された薬用シャンプー(医薬部外品)が有効です。
フケの種類別おすすめシャンプー成分
| フケの種類 | シャンプーの選び方 | 主な有効成分・保湿成分例 |
|---|---|---|
| 乾燥フケ | 洗浄力が穏やか(アミノ酸系など)、保湿成分配合 | セラミド、ヒアルロン酸、グリセリン、コラーゲン |
| 脂性フケ | 抗真菌成分配合、抗炎症成分配合(薬用) | ミコナゾール硝酸塩、ピロクトンオラミン、グリチルリチン酸2K |
正しい洗い方の手順
シャンプーは「髪」ではなく「頭皮」を洗うことを意識します。以下の手順で、頭皮に負担をかけずに汚れを落としましょう。
- ブラッシング:乾いた髪の状態で、まず毛先のもつれを解き、次に頭皮から毛先に向かって優しくブラッシングします。ほこりや汚れを浮かせ、シャンプーの泡立ちを良くします。
- 予洗い:シャンプーをつける前に、38度程度のぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと濡らします。1分〜2分ほど時間をかけ、お湯だけで汚れの多くを洗い流すイメージです。
- 泡立て:シャンプーを適量手に取り、手のひらで軽く泡立ててから、頭皮の数か所につけます。直接頭皮につけてから泡立てると、その部分に洗浄成分が集中しすぎるため避けます。
- 洗う:指の腹(指紋のある部分)を使って、頭皮全体をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。頭皮が傷つき、炎症の原因となります。
洗う際は、皮脂の分泌が多い生え際、頭頂部、後頭部を特に丁寧に洗うと良いでしょう。
すすぎと乾燥の重要性
シャンプーの成分が頭皮に残ると、それが刺激となってフケやかゆみの原因になります。「洗う時間の倍はすすぐ」くらいの意識で、ぬるま湯で徹底的に洗い流します。
特に、耳の後ろや襟足はすすぎ残しが多い部分なので注意しましょう。シャワーヘッドを頭皮に近づけ、指の腹で頭皮を軽くこするようにしながら流すと効果的です。
洗髪後は、タオルでゴシゴシ擦らず、優しく押さえるようにして水分を吸い取ります(タオルドライ)。その後、必ずドライヤーで頭皮から乾かします。
髪が濡れたまま寝てしまうと、雑菌が繁殖しやすい環境(高温多湿)を作り出し、フケや臭いの原因になるため、面倒でも必ず乾かしきる習慣をつけましょう。
日常生活でできる頭皮環境の改善策
頭皮環境は、シャンプーなどの外側からのケア(エクスターナルケア)だけでなく、体の中から整える内側からのケア(インターナルケア)も非常に重要です。
フケや薄毛の根本的な改善を目指すには、日々の生活習慣を見直すことが欠かせません。バランスの取れた食事、質の良い睡眠、そしてストレス管理が三本柱となります。
食生活の見直し
食べたものが頭皮や髪の健康に直結します。特に皮脂の分泌をコントロールし、頭皮の新陳代謝をサポートする栄養素を意識的に摂取することが大切です。
脂質の多い食事(ファストフード、揚げ物、肉の脂身など)や糖質の多いもの(菓子パン、ジュース、お菓子など)ばかり食べていると、皮脂の分泌が過剰になりがちです。
これらを控えめにし、代わりにビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE、タンパク質、亜鉛などをバランス良く摂るよう心がけましょう。
頭皮ケアに役立つ主な栄養素と食品例
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂の分泌を調整し、皮膚の健康維持を助ける | レバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品 |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助け、新陳代謝を促す | マグロ、カツオ、鶏ささみ、バナナ、にんにく |
| 亜鉛 | 髪の主成分(ケラチン)の合成を助ける | 牡蠣、牛肉(赤身)、レバー、チーズ |
| タンパク質 | 髪の毛そのものを作る材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
質の高い睡眠の確保
頭皮の細胞は、私たちが寝ている間に修復・再生されます。
特に、入眠から最初の3時間に多く分泌される「成長ホルモン」が、頭皮のターンオーバーを正常化し、毛髪の成長を促す上で重要な役割を果たします。
睡眠時間が不足したり、夜更かしなどで睡眠のリズムが乱れたりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、頭皮環境の悪化や髪の成長不良につながります。
毎日6〜7時間の睡眠時間を確保することを目標にし、特に「睡眠の質」を高めることが大切です。
寝る前のスマートフォン操作を控える、リラックスできる環境を整えるなど、深く眠るための工夫を取り入れましょう。
ストレス管理の方法
現代社会でストレスをゼロにすることは困難ですが、溜め込まないように管理することは可能です。
過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、頭皮の血流を悪化させたり、皮脂の分泌を過剰にしたりします。これがフケや抜け毛の間接的な引き金となります。
自分なりのリフレッシュ方法を見つけることが重要です。例えば、適度な運動(ウォーキング、ジョギング、ストレッチなど)は、血行を促進するだけでなく、気分転換にも効果的です。
また、趣味に没頭する時間を作る、ゆっくり入浴する、信頼できる人と話すなども良いストレス解消法になります。日常生活の中に、意識的に「リラックスする時間」を取り入れるようにしましょう。
フケ・薄毛対策と育毛剤の活用
フケや頭皮のかゆみ、乾燥といったトラブルをケアし、頭皮環境を整えることは、薄毛対策の土台作りそのものです。
セルフケアを徹底してもフケが改善しない場合や、フケと同時に薄毛の兆候(抜け毛の増加、髪のハリ・コシ低下など)が気になる場合には、育毛剤の活用も有効な選択肢となります。
育毛剤がフケ対策にもなる?
育毛剤の主な目的は「今ある髪を健康に育てる」ことや「抜け毛を予防する」ことです。
そのために、多くの育毛剤には、髪が育ちやすい頭皮環境(=フケや炎症が起こりにくい頭皮環境)に整えるための成分が含まれています。
したがって、フケの原因が頭皮の炎症や乾燥にある場合、育毛剤に配合されている抗炎症成分や保湿成分が、結果としてフケの改善に役立つことがあります。
ただし、脂性フケの原因であるマラセチア菌を殺菌するような「治療」目的の成分は、育毛剤ではなく「発毛剤」や「フケ用シャンプー」に含まれることが一般的です。
頭皮環境を整える成分
育毛剤を選ぶ際は、薄毛対策の有効成分(例:センブリエキスなど)だけでなく、どのような頭皮ケア成分が含まれているかにも注目すると良いでしょう。
特にフケや頭皮トラブルが気になる方には、以下のような成分が配合されたものが適しています。
育毛剤に含まれる主な頭皮ケア成分例
| 成分カテゴリ | 期待される役割 | 代表的な成分例 |
|---|---|---|
| 抗炎症成分 | 頭皮の炎症、かゆみ、赤みを抑える | グリチルリチン酸ジカリウム、アラントイン |
| 保湿成分 | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能をサポートする | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、各種植物エキス |
| 血行促進成分 | 頭皮の血流を良くし、栄養を行き渡らせる | センブリエキス、ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール) |
乾燥フケに悩む方は保湿成分重視、かゆみや赤みが気になる方は抗炎症成分重視、といった選び方が可能です。
育毛剤の正しい使い方
育毛剤は、頭皮が清潔な状態で使用するのが最も効果的です。したがって、シャンプー・乾燥後の夜のケアとして取り入れるのが一般的です。育毛剤を使用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 頭皮を清潔にする:シャンプーで汚れや皮脂をしっかり落とし、ドライヤーで頭皮を(完全にではなく)8〜9割ほど乾かします。
- 適量を塗布する:製品に記載されている使用量を守り、髪ではなく「頭皮」に直接塗布します。
- マッサージ:塗布後、指の腹を使って頭皮全体を優しくマッサージし、育毛剤を馴染ませるとともに血行を促進します。
育毛剤は医薬品ではなく、あくまで頭皮環境を整えたり、抜け毛を予防したりするものです。使用してすぐにフケや薄毛が劇的に改善するわけではありません。
最低でも3ヶ月から6ヶ月は、日々のケアとして継続することが大切です。
よくある質問
薄毛とフケに関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で解説します。頭皮の悩みはデリケートですが、正しい知識を持つことが解決への第一歩です。
- フケが出たらシャンプーは毎日しない方がいい?
-
一概には言えません。フケの種類によります。脂性フケで頭皮がベタつく場合は、皮脂や汚れを溜めないために毎日シャンプー(場合によっては朝晩2回)が必要なこともあります。
一方、乾燥フケの場合は、洗いすぎると必要な皮脂まで奪ってしまい乾燥が悪化するため、洗浄力のマイルドなシャンプーで優しく洗うか、場合によっては2日に1回にするなど頻度を調整する方が良いこともあります。
ただし、洗わない期間が長すぎると雑菌が繁殖しやすくなるため、基本的には1日1回、自分の頭皮状態に合ったシャンプーで正しく洗うことを推奨します。
- フケ用シャンプーはずっと使い続けても大丈夫?
-
フケ用シャンプーにも種類があります。
抗真菌成分などが含まれる薬用シャンプーの場合、フケや炎症が改善した後も使い続けると、頭皮に必要な常在菌まで減らしすぎてしまい、かえって頭皮環境のバランスを崩す可能性があります。
症状が改善したら、通常のシャンプーや、保湿・頭皮ケアを目的としたマイルドなシャンプーに切り替えるか、使用頻度を週に数回に減らすなどの調整が必要です。
製品の説明書をよく読んで使用してください。
- 頭皮が乾燥するのに脂性フケが出ることはある?
-
はい、あり得ます。これは「インナードライ(乾燥性脂性肌)」と呼ばれる状態です。
頭皮の内部(角質層)は乾燥しているのに、それを補おうとして皮脂が過剰に分泌されてしまい、表面はベタつくという状態です。
この場合、洗浄力の強いシャンプーで皮脂を取り除こうとすると、内部の乾燥がさらに進み、悪循環に陥ります。
対策としては、洗浄力はマイルドでありながらも、保湿成分(セラミドなど)をしっかり補給できるヘアケアが求められます。
- フケが改善すれば薄毛も治る?
-
フケが原因で頭皮環境が悪化し、一時的に抜け毛が増えていた場合(粃糠性脱毛症など)は、フケが改善し頭皮環境が正常化することで、抜け毛が減り、髪が元に戻る可能性はあります。
しかし、薄毛の原因がAGA(男性型脱毛症)である場合、フケ対策はあくまで頭皮環境を整える「土台作り」であり、フケが治ってもAGAの進行自体が止まるわけではありません。
AGAによる薄毛には、別途専門の対策が必要となります。
- かゆみがひどい場合すぐに病院へ行くべきか?
-
はい、かゆみが我慢できないほど強い場合や、市販のフケ用シャンプーを1〜2週間試しても全く改善しない、あるいは悪化するようであれば、早めに皮膚科を受診してください。
自己判断でケアを続けると、症状を悪化させる恐れがあります。脂漏性皮膚炎や乾癬など、専門的な治療が必要な皮膚疾患が隠れている可能性もあります。
医師の診断を受け、適切な治療薬(塗り薬など)を処方してもらうことが、早期改善への近道です。
Reference
FAGHIHKHORASANI, Amirhosein, et al. The Relationship between Seborrheic Dermatitis and Androgenetic Alopecia in Patients Referred to a Skin Clinic in Tehran, Iran: A Retrospective Study. Journal of Health Reports and Technology, 2024, 10.1.
BORDA, Luis J.; WIKRAMANAYAKE, Tongyu C. Seborrheic dermatitis and dandruff: a comprehensive review. Journal of clinical and investigative dermatology, 2015, 3.2: 10.13188/2373-1044.1000019.
SCHWARTZ, James R., et al. A comprehensive pathophysiology of dandruff and seborrheic dermatitis–towards a more precise definition of scalp health. Acta dermato-venereologica, 2013, 93.2: 131-137.
TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
TRÜEB, Ralph M. Is androgenetic alopecia a photoaggravated dermatosis?. Dermatology, 2003, 207.4: 343-348.
ASFOUR, Leila; CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. Endotext [Internet], 2023.
SUZUKI, Kazuhiro, et al. Scalp microbiome and sebum composition in Japanese male individuals with and without androgenetic alopecia. Microorganisms, 2021, 9.10: 2132.
TRÜEB, Ralph M.; GAVAZZONI DIAS, Maria Fernanda Reis. Fungal diseases of the hair and scalp. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 151-195.
HO, Bryan Siu-Yin, et al. Microbiome in the hair follicle of androgenetic alopecia patients. PLoS One, 2019, 14.5: e0216330.