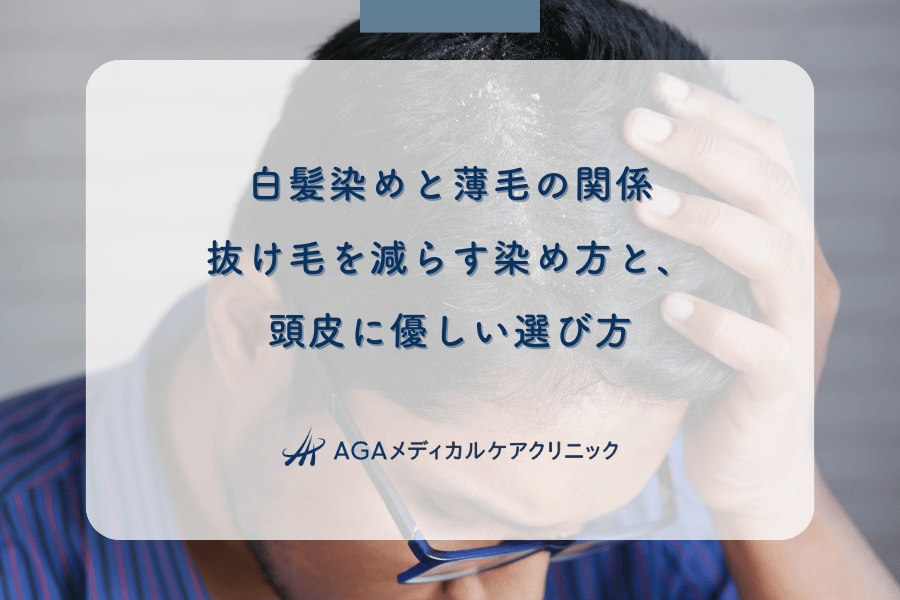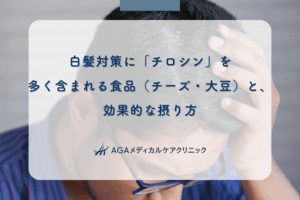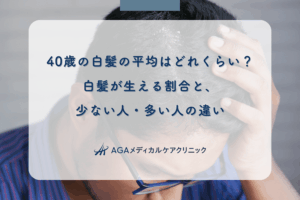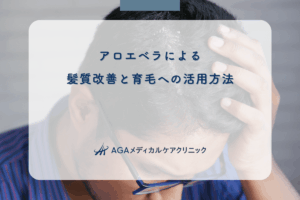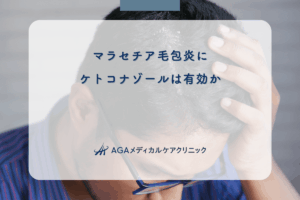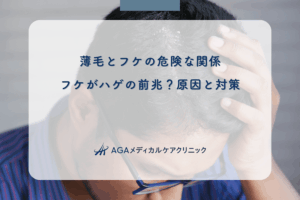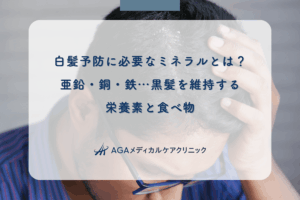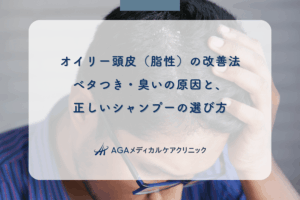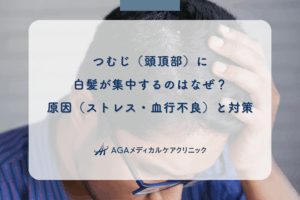白髪が目立ち始めると、多くの方が白髪染めを検討します。しかし同時に、「白髪染めを続けると薄毛になるのではないか」「抜け毛が増えた気がする」といった不安を感じる男性も少なくありません。
白髪を隠したいという思いと、髪や頭皮への負担を心配する思いの間で悩むのは自然なことです。
この記事では、白髪染めと薄毛や抜け毛の気になる関係性について解説します。
白髪染めが頭皮や髪に与える影響を理解し、抜け毛を減らすための頭皮に優しい染め方や、適切な白髪染めの選び方について、詳しく見ていきましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
白髪染めが薄毛や抜け毛を直接引き起こす?気になる関係性
多くの方が抱く「白髪染めは薄毛の原因になる」という不安。この点は、白髪染めをためらう大きな理由の一つかもしれません。
実際のところ、白髪染めと薄毛・抜け毛にはどのような関係があるのでしょうか。誤解されている部分も含めて、その関係性を明らかにします。
「白髪染め=薄毛」は誤解?
結論から言うと、市販されている白髪染めや美容室で使われる一般的な染毛剤が、直接的にAGA(男性型脱毛症)のような薄毛を引き起こす医学的根拠は現在のところ明確ではありません。
AGAは主に遺伝や男性ホルモンの影響によって引き起こされるものであり、白髪染めの化学成分がその直接の原因となるわけではないのです。
しかし、これは「白髪染めが髪や頭皮に全く無害である」という意味ではありません。使い方や体質によっては、頭皮環境を悪化させ、抜け毛につながる可能性は否定できません。
頭皮への刺激が抜け毛につながる可能性
白髪染めに含まれる化学成分、特にアルカリ剤や酸化染料(ジアミン系など)、過酸化水素水などは、頭皮に対して一定の刺激を与えます。
敏感肌の方や頭皮が乾燥している方の場合、これらの成分が頭皮の炎症(かゆみ、赤み、湿疹など)を引き起こすことがあります。頭皮が炎症を起こすと、毛根が正常に髪を育てる環境が損なわれます。
健康な髪が育ちにくくなったり、今ある髪の毛周期が乱れて通常より早く抜け落ちてしまったりする可能性があり、これが「抜け毛が増えた」と感じる一因になり得ます。
頭皮への主な刺激要因
- 化学成分(アルカリ剤・染料)による刺激
- アレルギー反応(ジアミンなど)
- 染毛剤の洗い残しによる刺激
髪のダメージによる切れ毛と抜け毛の違い
白髪染めは、髪のキューティクルを開いて内部に色素を入れるため、繰り返すことで髪のタンパク質が流出し、髪自体がダメージを受けます。
髪がもろくなると、少しの摩擦やブラッシングで途中で切れてしまう「切れ毛」が起こりやすくなります。
シャンプーや朝起きた時に枕についた毛を見たとき、それが毛根から抜けた「抜け毛」なのか、途中で切れた「切れ毛」なのかを混同している場合があります。
白髪染めによるダメージは、主に「切れ毛」を増やします。これが薄毛に見える一因となることはありますが、毛根から抜ける「抜け毛」とは区別して考える必要があります。
アレルギー反応(かぶれ)と頭皮環境の悪化
白髪染めで特に注意が必要なのが、アレルギー性接触皮膚炎、いわゆる「かぶれ」です。主に酸化染料であるジアミン系の成分が原因(アレルゲン)となることが多いです。
一度アレルギーを発症すると、その後は同じ成分に触れるたびに重い症状が出ることがあります。かぶれによって頭皮が激しい炎症を起こすと、頭皮環境は極端に悪化します。
場合によっては、炎症部分の毛が抜け落ちてしまうこともあり、これが抜け毛の深刻な原因となることがあります。
アレルギーは体質の変化によって突然発症することもあるため、毎回必ずパッチテストを行うことが重要です。
なぜ白髪染めで髪や頭皮が傷むのか
白髪染めがなぜ髪や頭皮に負担をかけるのか、その理由を知ることは、適切なケアや製品選びにつながります。
ここでは、白髪染めに含まれる主な化学成分の役割と、それが髪や頭皮にどのような影響を与えるのかを解説します。
白髪染めに含まれる主な化学成分
一般的なアルカリ性カラー(永久染毛剤)の白髪染めは、主に「1剤」と「2剤」を混ぜて使用します。1剤にはアルカリ剤と酸化染料(色の素)が、2剤には過酸化水素水(酸化剤)が含まれています。
これらの成分が化学反応を起こすことで、髪の内部までしっかりと染め上げることができます。しかし、これらの成分は同時に、髪や頭皮への刺激となる可能性も持っています。
アルカリ剤がキューティクルに与える影響
アルカリ剤(アンモニアなど)の主な役割は、髪の表面を覆っているウロコ状の「キューティクル」を開かせることです。
キューティクルが開くことで、染料が髪の内部(コルテックス)まで浸透できます。しかし、キューティクルを無理に開かせることは、髪のバリア機能を低下させます。
染毛後、キューティクルが完全に閉じきらないと、髪内部の水分やタンパク質が流出しやすくなり、パサつきや乾燥、枝毛の原因となります。
また、アルカリ剤は頭皮にとっても刺激物であり、ピリピリとした刺激を感じる原因の一つです。
酸化染料(ジアミン系)の刺激性
酸化染料は、白髪をしっかりと染めるために中心的な役割を果たす成分です。
特に「パラフェニレンジアミン(PPD)」に代表されるジアミン系の染料は、少量で濃く染まり、色持ちが良いという優れた特徴を持っています。
しかしその一方で、アレルギー反応を引き起こしやすい成分としても知られています。
前述の通り、ジアミンアレルギーを発症すると、かゆみや発疹、腫れといった重い症状が出ることがあり、頭皮環境に深刻なダメージを与える可能性があります。
過酸化水素水(ブリーチ剤)の役割と負担
2剤の主成分である過酸化水素水は、主に二つの役割を持ちます。一つは、髪のメラニン色素をわずかに脱色(ブリーチ)し、染料が入りやすく、また発色しやすくする役割。
もう一つは、1剤の酸化染料と反応して発色させる役割です。この脱色作用と酸化反応は、髪と頭皮にとって負担となります。
特に頭皮に付着すると、刺激を感じたり、頭皮の皮脂を過剰に奪ったりして、乾燥やかゆみを引き起こすことがあります。
染毛剤の主な化学成分と影響
| 成分名(例) | 主な役割 | 頭皮・髪への影響(可能性) |
|---|---|---|
| アルカリ剤(アンモニア等) | キューティクルを開く | 頭皮への刺激、髪の乾燥・ダメージ |
| 酸化染料(ジアミン等) | 発色・染色 | アレルギー反応、頭皮刺激 |
| 過酸化水素水 | 脱色、染料の酸化 | 頭皮刺激、髪のダメージ、乾燥 |
抜け毛を減らすために注意したい白髪染めの頻度とタイミング
白髪染めによる頭皮や髪への負担をゼロにすることは難しいかもしれませんが、頻度やタイミングを工夫することで、そのダメージを最小限に抑え、抜け毛のリスクを減らすことは可能です。
どのくらいの期間をあけるべきか、どのような状態の時は避けるべきかを知っておきましょう。
適切な白髪染めの間隔とは
白髪染めの適切な間隔は、使用する染毛剤の種類や白髪の目立ち具合によって異なります。一般的なアルカリ性カラーの場合、髪全体を染めるのは2か月から3か月に1回程度が目安とされます。
しかし、根元の白髪は2週間から1か月もすれば目立ってきます。そのため、美容室では1か月から1か月半に1回程度の「リタッチ(根元染め)」を推奨することが多いです。
セルフカラーの場合も、全体染めは避け、伸びてきた部分だけを染めるリタッチを中心に行うことで、既に染まっている毛先へのダメージの蓄積を防げます。
頭皮のコンディションが悪い時の染髪は避ける
頭皮に傷、湿疹、かゆみ、赤みなどの異常がある時は、白髪染めを行うべきではありません。
頭皮のバリア機能が低下している状態であり、そこに染毛剤の化学成分が触れると、症状を悪化させたり、強い刺激を感じたり、アレルギー反応が起こりやすくなったりします。
頭皮の状態が健康に戻るまで待ちましょう。
また、体調が優れない時や、病中・病後、妊娠中なども皮膚が敏感になっている可能性があるため、染髪は避ける方が賢明です。自分の頭皮と体をよく観察することが大切です。
リタッチ(根元染め)を活用するメリット
白髪が気になるのは主に新しく生えてきた根元の部分です。毎回毛先まで全体を染めると、既に染まっている部分にさらに薬剤を重ねることになり、髪のダメージは深刻化します。
リタッチは、この新しく生えてきた部分(新生部)だけに薬剤を塗布する方法です。これにより、毛先への不要なダメージを避けつつ、見た目の白髪をカバーできます。
頭皮に薬剤が付着する範囲も最小限に抑えられるため、頭皮への負担軽減にもつながります。セルフカラーでも、リタッチ専用のコームなどを使うと行いやすくなります。
美容室とセルフカラーの頻度の違い
美容室では、プロの美容師が頭皮や髪の状態を見極め、できるだけ頭皮に薬剤をつけない技術(ゼロテクニックなど)を用いて施術します。
また、使用する薬剤も髪質に合わせて調整することが可能です。一方、セルフカラーは手軽ですが、自分で薬剤を塗るため、どうしても頭皮に薬剤がベッタリと付着しやすくなります。
この違いから、頭皮への負担はセルフカラーの方が大きくなる傾向があります。
美容室とセルフカラーの比較
| 比較項目 | 美容室での施術 | セルフカラー |
|---|---|---|
| 頭皮への配慮 | プロによる塗布技術(ゼロテク等) | 自己責任(薬剤が付着しやすい) |
| 薬剤選定 | 髪質・頭皮状態を考慮可能 | 自分で選ぶ必要あり |
| ダメージの均一性 | 新生部と既染部を塗り分け可能 | 全体に塗りやすくムラや過剰塗布のリスク |
頭皮ダメージを抑える白髪染めの種類と特徴
白髪染めと一口に言っても、その種類は様々です。染まり方や色持ち、そして頭皮や髪への負担の度合いも異なります。
薄毛や抜け毛が気になる方は、それぞれの特徴を理解し、自分に合ったタイプを選ぶことが重要です。ここでは代表的な白髪染めの種類を比較します。
永久染毛剤(アルカリカラー)の特徴
一般的に「白髪染め」として最も多く使われているのがこのタイプです。1剤と2剤を混ぜて使用し、髪の内部までしっかり染めるため、色持ちが非常に良い(約2~3か月)のが最大の特徴です。
しかし、前述の通りアルカリ剤や酸化染料、過酸化水素水を含むため、頭皮や髪への負担は最も大きくなります。特にジアミン系染料によるアレルギーのリスクがあるため、使用前のパッチテストは必須です。
酸性カラー(ヘアマニキュア)のメリット・デメリット
ヘアマニキュアは、髪の表面を酸性の染料でコーティングするように染めるタイプです。アルカリ剤や過酸化水素水を使用せず、キューティクルを開かないため、髪へのダメージはほとんどありません。
頭皮への刺激も少ないです。
メリットは髪や頭皮に優しいことですが、デメリットとして、髪の内部までは染まらないため色持ちが短い(約2~4週間)こと、地肌につくと落ちにくいこと、汗や雨で色落ちしやすいことが挙げられます。
カラートリートメント・カラーシャンプーの手軽さ
カラートリートメントやカラーシャンプーは、日々のシャンプーやトリートメントの代わりに使うことで、徐々に髪の表面に色を付けていくタイプです。
染料が穏やかで、アルカリ剤なども含まないため、髪や頭皮への負担はほぼ無いと言えます。毎日使える手軽さも魅力です。
ただし、1回ではほとんど染まらず、連続使用してようやく白髪がぼかせる程度です。
しっかり染めたい方には物足りませんが、頭皮への優しさを最優先する方や、次の美容室までのつなぎとして使うのに適しています。
ヘナなど植物性染料の選択肢
ヘナは、植物(ヘンナ)の葉を乾燥させて粉末にした天然の染料です。化学染料(ジアミン)を含まない100%のヘナは、アレルギーのリスクが低く、頭皮や髪に優しいとされています。
髪のタンパク質に絡みつくように染まり、トリートメント効果で髪にハリやコシを与えるとも言われます。
ただし、染まる色がオレンジ系に限られること、染めるのに時間がかかること、植物アレルギーの可能性がゼロではないこと、ヘナの後にアルカリカラーで色を変えにくいことなどの注意点もあります。
ヘナに化学染料を混ぜた「ケミカルヘナ」もあるため、成分の確認が必要です。
染毛剤の種類別比較
| 種類 | 染毛の仕組み | 頭皮への優しさ(目安) |
|---|---|---|
| 永久染毛剤(アルカリ) | 髪内部まで染める | △(刺激・アレルギーリスクあり) |
| 酸性カラー(ヘアマニキュア) | 髪表面をコーティング | 〇(刺激少ないが地肌付着注意) |
| カラートリートメント等 | 髪表面に徐々に付着 | ◎(負担ほぼなし・染まり穏やか) |
| ヘナ(天然100%) | 髪表面のタンパク質に絡む | ◎(植物アレルギー注意) |
自宅で実践できる頭皮に優しい染め方の工夫
美容室での施術が頭皮には優しいと分かっていても、時間や費用の面でセルフカラーを選ぶ方も多いでしょう。
自宅で白髪染めを行う場合でも、いくつかの点に注意するだけで、頭皮への負担を大きく減らすことができます。抜け毛予防のために、ぜひ実践してください。
事前のパッチテストを毎回行う重要性
最も重要なのがパッチテスト(皮膚アレルギー試験)です。これは、アレルギー反応が起きないかを事前に確認するためのテストです。
染毛剤の説明書に従い、染毛の48時間前に、薬剤を腕の内側などの目立たない皮膚に少量塗布し、様子を見ます。
これまで問題がなかった人でも、体質の変化で突然アレルギーを発症することがあります。「面倒だから」「前回大丈夫だったから」と省略せず、必ず毎回行ってください。
かぶれによる頭皮のダメージは、抜け毛の大きな原因となります。
頭皮に薬剤を直接つけない「ゼロテク」
美容室で行われる「ゼロテクニック(ゼロテク)」は、コーム(櫛)を使って、薬剤を頭皮に直接つけず、髪の根元ギリギリから塗布する技術です。
セルフカラーで完璧に実践するのは難しいですが、意識するだけでも違います。薬剤を頭皮に擦り込むように塗るのではなく、髪の毛だけに塗るように心がけましょう。
特に染毛剤を塗布した後に頭皮マッサージをするのは、薬剤を頭皮に刷り込む行為であり、絶対に避けるべきです。
保護オイルやクリームで頭皮を守る
染毛剤を塗る前に、頭皮(特に生え際や分け目など)に専用の保護オイルや、油性のクリーム(ワセリンなど)を薄く塗っておくことで、薬剤が頭皮に直接付着するのを防ぐバリアになります。
これにより、薬剤による刺激やアレルギー反応のリスクを低減できます。ただし、髪の毛にオイルやクリームが付きすぎると染まりが悪くなるため、頭皮にだけ塗るように注意が必要です。
放置時間を守り、しっかり洗い流す
「しっかり染めたい」という思いから、説明書に記載されている放置時間よりも長く置いてしまう方がいますが、これは逆効果です。
染まり具合が劇的に良くなるわけではなく、むしろ頭皮と髪が薬剤にさらされる時間が長くなることで、ダメージが大きくなるだけです。規定の放置時間を厳守してください。
染毛後は、洗い流しが非常に重要です。色が出なくなるまで、ぬるま湯で徹底的にすすぎます。シャンプーは2回行うなどして、染毛剤が頭皮や髪に残らないよう、丁寧に洗い流しましょう。
セルフカラー時の注意点
| 工夫 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| パッチテスト | アレルギー反応の事前確認 | 染毛の48時間前に毎回実施 |
| 頭皮保護 | 薬剤の直接付着を防止 | 専用オイルやワセリンを生え際に塗布 |
| 塗布方法 | 頭皮への刺激軽減 | 頭皮に擦り込まず、髪を中心に塗る |
薄毛が気になる場合の白髪染め選びのポイント
薄毛や抜け毛が気になり始めたら、白髪染めの選び方もより慎重になる必要があります。頭皮への優しさを考慮しつつ、髪を健やかに見せるための成分にも注目してみましょう。
ここでは、薄毛が気になる方が白髪染めを選ぶ際の具体的なポイントを挙げます。
ジアミンフリー・低アルカリ処方を選ぶ
頭皮への刺激やアレルギーのリスクを減らすため、まずは成分表示を確認しましょう。
アレルギーの原因となりやすい「パラフェニレンジアミン」などのジアミン系染料を使用していない「ジアミンフリー」の製品が選択肢になります。
ただし、ジアミンフリーでも他の染料でアレルギーが起きる可能性はあるため、パッチテストは必要です。
また、キューティクルを開くアルカリ剤の配合量を抑えた「低アルカリ処方」の製品も、髪や頭皮へのダメージを軽減するのに役立ちます。
頭皮ケア成分(保湿成分など)配合製品
最近の白髪染めの中には、染めるだけでなく、頭皮や髪をケアする成分を配合している製品も増えています。
薄毛が気になる方は、特に頭皮の乾燥がフケやかゆみを引き起こし、頭皮環境を悪化させる一因となるため、「保湿成分」に注目しましょう。
セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、各種植物エキスなどが代表的です。これらの成分が頭皮の潤いを保ち、健やかな状態を維持するのを助けます。
髪にハリ・コシを与えるタイプ
薄毛が気になる場合、髪のボリュームダウンも悩みの一つです。
白髪染め製品の中には、髪の内部を補修し、ハリやコシを与える成分(ケラチン、コラーゲン、シルクプロテインなど)を配合しているものがあります。
髪1本1本がしっかりすることで、全体のボリューム感が増し、薄毛が目立ちにくくなる効果が期待できます。染めながらヘアケアもできる製品を選ぶと良いでしょう。
刺激臭の少ないものを選ぶ
白髪染め特有のツンとした刺激臭は、主にアルカリ剤(アンモニア)によるものです。
この臭いが苦手という方も多いですが、臭いが強いということは、それだけ揮発性のアルカリ剤が多く含まれている可能性を示唆します。
最近は、刺激臭を抑えた処方(モノエタノールアミンなど他のアルカリ剤を使用)の製品や、香料でマスキングしている製品も多くあります。
ストレスなく使用できるものを選ぶことも、継続的なケアには重要です。ただし、臭いが少ないからといって刺激がゼロというわけではない点には注意が必要です。
注目したい成分
| 成分カテゴリ | 期待される役割 | 具体的な成分例 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | 頭皮の乾燥を防ぎ、潤いを保つ | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン |
| 抗炎症成分 | 頭皮の炎症(かゆみ等)を抑える | グリチルリチン酸ジカリウム(2K) |
| ハリ・コシ成分 | 髪の内部を補修し、ボリューム感を出す | 加水分解ケラチン、加水分解シルク |
白髪染め後の頭皮ケアで抜け毛を予防
白髪染めによるダメージを最小限に抑えるには、染めた後のアフターケアが非常に重要です。染毛直後の頭皮は、化学成分の影響で敏感になり、バリア機能が低下している状態です。
ここで適切なケアを行うかどうかで、将来の頭皮環境、ひいては抜け毛の予防に大きな差が出ます。
染めた当日のシャンプー方法
染毛剤を洗い流す際は、まずぬるま湯で薬剤をしっかりと乳化させながら、色が出なくなるまで丁寧にすすぎます。その後、シャンプーを使って残った薬剤や汚れを洗い流します。
この時、爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。
シャンプー剤は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系など、低刺激性のものを選ぶのが望ましいです。
可能であれば、染めた当日の夜は湯洗い(シャンプー剤を使わない)にとどめ、翌日の夜からシャンプーを使うと、色素の定着を助けつつ頭皮を休ませることができます。
当日の洗髪ポイント
- 染めた直後はぬるま湯でのすすぎを徹底的に
- シャンプーは当日の夜か翌日以降に
- 低刺激性(アミノ酸系など)のシャンプーを選ぶ
頭皮の保湿ケアの重要性
染毛後の頭皮は、アルカリ剤や過酸化水素水の影響で乾燥しやすくなっています。頭皮が乾燥すると、かゆみやフケが発生しやすくなり、頭皮環境が悪化して抜け毛につながります。
シャンプー後は、タオルドライで優しく水分を拭き取った後、頭皮専用のローションや保湿美容液を使って、頭皮に潤いを与えましょう。
特に乾燥しやすい生え際や分け目は丁寧に保湿することが大切です。アルコール(エタノール)の配合が少ない、低刺激性の保湿剤を選びましょう。
血行を促進する頭皮マッサージ
頭皮の血行が悪いと、髪の毛根に十分な栄養が届かず、健康な髪が育ちにくくなります。ただし、染毛当日は頭皮が敏感になっているため、強いマッサージは避けるべきです。
染毛から数日経って頭皮の状態が落ち着いたら、頭皮マッサージを取り入れましょう。シャンプー中や、育毛剤を塗布した後などに、指の腹を使って頭皮全体を動かすように優しくマッサージします。
これにより頭皮の血流が促進され、リラックス効果も期待できます。継続することが重要です。
育毛剤使用のタイミング
薄毛対策として育毛剤を使用している場合、白髪染め当日の使用は控えるのが賢明です。染毛直後の敏感な頭皮に育毛剤(特にアルコールを含むもの)を使用すると、刺激が強すぎることがあります。
また、毛穴に染毛剤が残っている可能性も否定できません。白髪染めをした日は、前述の保湿ケアにとどめ、育毛剤の使用は翌日以降、頭皮の状態が落ち着いてから再開するのが良いでしょう。
頭皮環境を整えることが、育毛剤の効果を最大限に引き出すためにも必要です。
染毛後のケア概要
| ケア | ポイント | 期待されること |
|---|---|---|
| 洗い流し・洗髪 | ぬるま湯で優しく、低刺激シャンプー | 残留薬剤の除去、頭皮負担軽減 |
| 頭皮保湿 | 専用ローション等で潤い補給 | 乾燥、かゆみ、フケの防止 |
| 頭皮マッサージ | 染毛数日後から優しく行う | 血行促進、頭皮環境の改善 |
白髪対策に戻る
白髪染めと薄毛に関するよくある質問
ここでは、白髪染めと薄毛に関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。
- 白髪染めを続けると、本当に薄毛になりますか?
-
白髪染めの薬剤が直接的にAGA(男性型脱毛症)を引き起こすことはありません。
しかし、染毛剤に含まれる化学成分による頭皮への刺激、アレルギー反応による炎症、洗い残しなどが原因で頭皮環境が悪化することはあります。
頭皮環境の悪化は、健康な髪の育成を妨げ、抜け毛や髪の細毛化につながる間接的な要因となる可能性はあります。
適切な製品選びと、頭皮に優しい染め方、染めた後のケアを徹底することが重要です。
- 頭皮に優しい白髪染め(カラートリートメントなど)でも、しっかり染まりますか?
-
頭皮への優しさと染毛力は、トレードオフの関係にあることが多いです。
カラートリートメントやヘアマニキュアは、髪や頭皮への負担が少ない分、アルカリカラー(永久染毛剤)のように1回で髪の内部までしっかり染める力は弱いです。
カラートリートメントは数回の連続使用で徐々に色が入るタイプですし、ヘアマニキュアは髪の表面をコーティングするため、色持ちが比較的短いです。
ご自身の求める染まり具合と、頭皮への優しさのバランスを考えて選ぶ必要があります。
- 薄毛治療中に白髪染めをしても大丈夫ですか?
-
薄毛治療(内服薬や外用薬の使用など)を行っている場合、頭皮が通常よりも敏感になっている可能性があります。
白髪染めを行う場合は、まず治療を受けているクリニックの医師に相談することを強く推奨します。
医師の許可が出た場合でも、染める際はアルカリカラーを避け、ヘアマニキュアやカラートリートメントなど、できるだけ頭皮に負担のかからない方法を選ぶべきです。
また、美容室で事情を説明し、プロに施術してもらう方が安全です。
- 白髪を抜くと増える、または薄毛になりますか?
-
「白髪を抜くと増える」というのは俗説で、医学的根拠はありません。白髪になるかどうかは、その毛根の色素細胞の働きによります。
しかし、白髪を無理に抜く行為は、毛根やその周辺の頭皮を傷つけることになります。
毛穴が炎症を起こしたり、毛周期が乱れたり、最悪の場合、その毛穴から新しい髪が生えてこなくなる(永久脱毛に近い状態)リスクもあります。
これは薄毛に直結する行為ですので、白髪は抜かずに、根元で切るか、染めるようにしてください。
Reference
PALANIAPPAN, Vijayasankar; KARTHIKEYAN, Kaliaperumal; ANUSUYA, Sadhasivamohan. Dermatological adverse effects of hair dye use: A narrative review. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2024, 90.4: 458-470.
KIM, Ki-Hyun; KABIR, Ehsanul; JAHAN, Shamin Ara. The use of personal hair dye and its implications for human health. Environment international, 2016, 89: 222-227.
HE, Yongyu, et al. Mechanisms of impairment in hair and scalp induced by hair dyeing and perming and potential interventions. Frontiers in Medicine, 2023, 10: 1139607.
HE, Lin, et al. Hair dye ingredients and potential health risks from exposure to hair dyeing. Chemical Research in Toxicology, 2022, 35.6: 901-915.
ZHANG, Guojin; MCMULLEN, Roger L.; KULCSAR, Lidia. Investigation of hair dye deposition, hair color loss, and hair damage during multiple oxidative dyeing and shampooing cycles. J. Cosmet. Sci, 2016, 67: 1-11.
ROH, Hee-Young; KIM, Yoon-Shin. A study on harmful effects of hair dying products and safety measures. Kor J Aesthet Cosmetol, 2008, 6.3.
ALGHAMDI, Khalid M.; MOUSSA, Noura A. Local side effects caused by hair dye use in females: Cross-sectional survey. Journal of cutaneous medicine and surgery, 2012, 16.1: 39-44.
MOREL, Olivier JX; CHRISTIE, Robert M. Current trends in the chemistry of permanent hair dyeing. Chemical reviews, 2011, 111.4: 2537-2561.
LEE, Jooyoung; KWON, Ki Han. Considering the risk of a coloring shampoo with the function of gray hair cover cosmetology and skin barrier: A systematic review. Health Science Reports, 2023, 6.5: e1271.
SCHLATTER, Harald; LONG, Timothy; GRAY, John. An overview of hair dye safety. Journal of Cosmetic Dermatology, 2007, 6: 32-36.