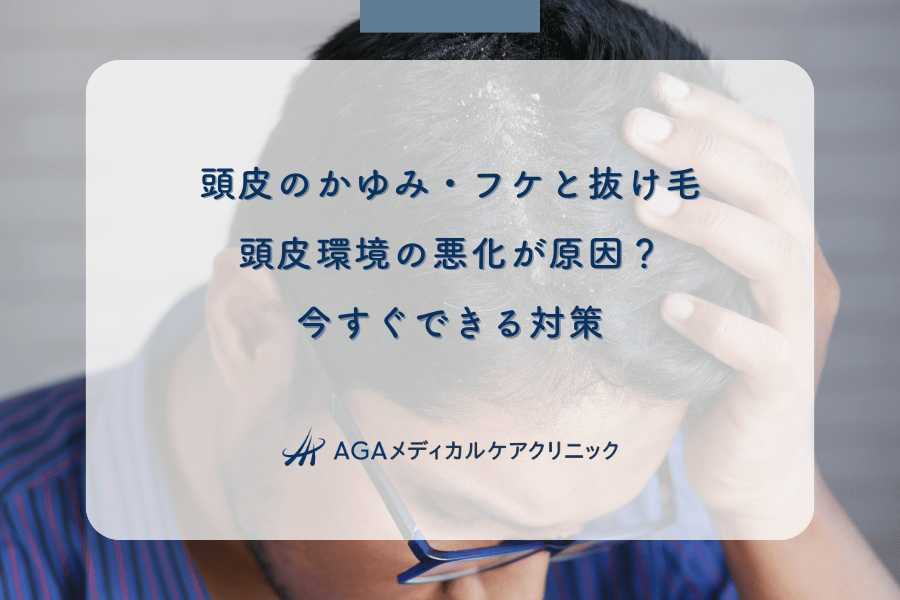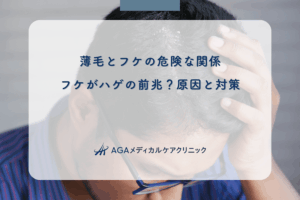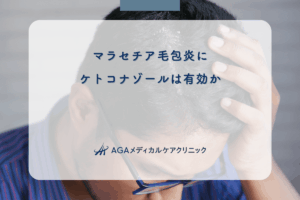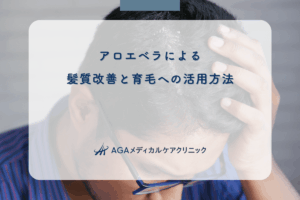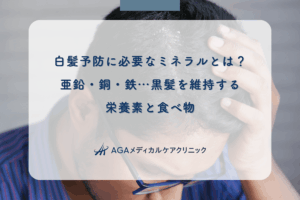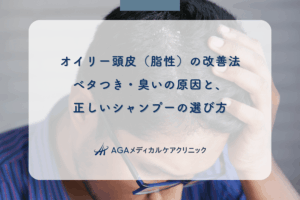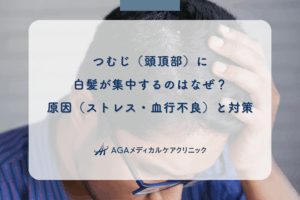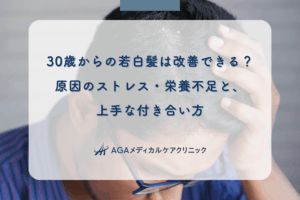ふとした瞬間に感じる頭皮のかゆみ。スーツの肩に落ちたフケ。そして、枕や排水溝に目立つ抜け毛。
これらが同時に気になり始めると、「もしかして、頭皮に何か重大な問題が起きているのでは?」と不安になりますよね。そのかゆみやフケ、実は抜け毛と深く関係しているかもしれません。
多くの場合、その根底には「頭皮環境の悪化」が潜んでいます。
この記事では、なぜ頭皮のかゆみやフケが抜け毛につながるのか、その原因と、今日からすぐに始められる具体的な対策を詳しく解説します。
あなたの頭皮の悩みを解消し、健やかな髪を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
抜け毛とかゆみの気になる関係性
抜け毛とかゆみは、多くの場合、頭皮環境の悪化という共通の原因から発生します。
かゆみを感じる状態は、すでに頭皮が何らかの刺激やトラブルを抱えているサインであり、それが抜け毛を助長する環境を作り出していることを示唆しています。
頭皮のかゆみが抜け毛につながる流れ
頭皮にかゆみが生じると、私たちは無意識のうちに、あるいは我慢できずに頭皮を掻いてしまいます。この「掻く」という行為が、物理的なダメージを頭皮と毛根に与えます。
指や爪で頭皮を掻きむしることで、頭皮の表面にあるバリア機能(角質層)が傷つきます。
バリア機能が低下すると、外部からの刺激(紫外線、ホコリ、化学物質など)が侵入しやすくなり、さらに炎症やかゆみが悪化するという悪循環に陥ります。
炎症が毛根の深くまで及ぶと、髪の毛を正常に成長させる「毛母細胞」の働きが阻害されます。結果として、まだ成長途中であったり、健康であったりする髪の毛までもが抜けやすくなってしまうのです。
また、掻き傷から雑菌が侵入し、毛穴の炎症(毛嚢炎)を引き起こすこともあり、これも抜け毛の直接的な原因となり得ます。
かゆみとフケが同時に起こる理由
かゆみとフケが同時に発生するのは、頭皮のターンオーバー(新陳代謝)が正常に行われていない証拠です。健康な頭皮では、古い角質が目に見えないほど小さな垢となって自然に剥がれ落ちます。
しかし、何らかの原因で頭皮環境が悪化すると、このターンオーバーが極端に早まったり、乱れたりします。
ターンオーバーが早すぎると、角質細胞が未熟なまま、まとまって剥がれ落ちてしまいます。これが、目に見える「フケ」となります。
フケには、頭皮の乾燥が原因で起こる「乾性フケ」(カサカサして小さい)と、皮脂の過剰分泌が原因で起こる「脂性フケ」(ベタベタして大きい)があります。
どちらのタイプも、頭皮のバリア機能が低下している状態を示しており、外部からの刺激を受けやすくなるため、かゆみを伴うことが非常に多いのです。
放置するリスクとは
「少しくらいのかゆみだから」「フケは体質だから」と、これらのサインを軽視して放置することは危険です。初期のかゆみやフケは、頭皮環境が悪化し始めているという重要な警告です。
この段階で対処しなければ、頭皮の状態はさらに悪化します。
炎症が慢性化すると、頭皮自体が硬くなり、血行も悪くなります。髪の毛の成長には、血液を通じて運ばれる酸素や栄養素が不可欠ですが、血行不良はその供給を滞らせます。
栄養不足に陥った毛根は、髪の毛を太く長く育てることができなくなり、髪は細く弱々しくなっていきます(軟毛化)。
そして最終的には、抜け毛の増加、さらには薄毛の進行へとつながる可能性が高まります。かゆみやフケは、将来の深刻な抜け毛問題の序章かもしれないのです。
頭皮のかゆみとフケを引き起こす主な原因
頭皮のかゆみやフケは、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って発生することが一般的です。
主な原因は、頭皮の「乾燥」または「皮脂の過剰分泌」であり、これらは間違ったヘアケアや生活習慣によって引き起こされます。
乾燥による頭皮環境の乱れ
頭皮も肌の一部であり、乾燥すればバリア機能が低下します。特に空気が乾燥する冬場や、エアコンの効いた室内に長時間いると、頭皮の水分は奪われやすくなります。
また、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、熱いお湯での洗いすぎも、頭皮の保湿に必要な皮脂まで取り除いてしまい、乾燥を招きます。
頭皮が乾燥すると、角質層がめくれ上がりやすくなり、外部からのわずかな刺激にも敏感に反応してかゆみが生じます。
そして、乾燥によって剥がれやすくなった角質が、パラパラとした細かい「乾性フケ」となります。乾燥した頭皮は、いわば守る力を失った状態であり、非常にデリケートになっています。
皮脂の過剰分泌とその影響
頭皮の乾燥とは逆に、皮脂が過剰に分泌されることも、かゆみやフケの大きな原因となります。
頭皮はもともと皮脂腺が多い部位ですが、ホルモンバランスの乱れ、脂っこい食事の多い食生活、ストレス、不規則な生活などが原因で、皮脂の分泌がコントロールを失うことがあります。
過剰に分泌された皮脂は、毛穴を詰まらせたり、酸化して刺激物質に変わったりします。
さらに重要なのは、この豊富な皮脂をエサにして「マラセチア菌」という常在菌(普段は誰の頭皮にもいるカビの一種)が異常繁殖することです。
マラセチア菌は、皮脂を分解する際に遊離脂肪酸という刺激物質を生成し、これが頭皮を刺激して炎症やかゆみを引き起こします。
この状態が「脂漏性皮膚炎」の入り口であり、ベタベタとした「脂性フケ」の原因ともなります。
皮脂分泌に影響を与える主な要因
| 要因カテゴリ | 具体的な内容 | 頭皮への影響 |
|---|---|---|
| 食生活 | 脂質の多い食事、糖分の過剰摂取 | 皮脂腺の活動を活発化させ、皮脂分泌を促す。 |
| 生活習慣 | 睡眠不足、過度なストレス | 自律神経やホルモンバランスが乱れ、皮脂コントロールが不安定になる。 |
| ホルモン | 男性ホルモンの影響 | 男性ホルモン(特にDHT)は皮脂腺を刺激する作用がある。 |
シャンプーやヘアケア製品の不一致
毎日使っているシャンプーが、実は頭皮トラブルの原因になっているケースは少なくありません。
例えば、皮脂が多いと感じている人が、洗浄力の非常に強い「高級アルコール系」のシャンプーを使い続けると、必要な皮脂まで奪いすぎてしまい、かえって乾燥を招いたり、不足した皮脂を補おうと過剰分泌を引き起こしたりすることがあります。
逆に、乾燥肌の人がマイルドな洗浄力のシャンプーを使っても、皮脂や汚れが十分に落ちきらず、雑菌の繁殖を招くこともあります。
また、シャンプーやトリートメントのすすぎ残しは、化学成分が頭皮に残留し、強い刺激となってかゆみや炎症を引き起こす代表的な原因です。
自分の頭皮タイプに合っていない製品を選んだり、使い方を間違えたりすることが、環境悪化に直結します。
皮膚炎の可能性(脂漏性皮膚炎など)
セルフケアをしても一向にかゆみやフケが改善しない場合、あるいは赤みや湿疹、ただれなどを伴う場合は、単なる頭皮トラブルではなく、治療が必要な「皮膚炎」を発症している可能性があります。
代表的なものに、前述した「脂漏性皮膚炎」があります。これはマラセチア菌の異常繁殖が関与しており、強いかゆみとベタついたフケ、頭皮の赤みが特徴です。
他にも、特定の物質に対するアレルギー反応である「接触皮膚炎」(ヘアカラー剤や特定のシャンプー成分が原因)、アトピー性皮膚炎の一環として頭皮に症状が出る場合、乾癬(かんせん)という慢性の皮膚疾患が頭皮に現れる場合などがあります。
これらは自己判断での対処が難しく、専門家による診断が重要です。
頭皮環境を悪化させる日常生活の落とし穴
頭皮のかゆみや抜け毛は、特別な原因だけでなく、日々の何気ない生活習慣の積み重ねによって引き起こされていることが多くあります。
食生活の乱れ、睡眠不足、ストレス、そして間違ったヘアケアが、知らず知らずのうちに頭皮環境を悪化させています。
食生活の偏りが頭皮に与える影響
私たちの体は、食べたもので作られています。当然、頭皮や髪の毛も例外ではありません。ジャンクフードやコンビニ弁当、外食など、脂質や糖質に偏った食事が続くと、皮脂の分泌が過剰になりがちです。
過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、雑菌の温床となり、かゆみや脂性フケ、炎症を引き起こします。
一方で、過度なダイエットなどで栄養が不足すると、髪の毛を作るために必要な栄養素が頭皮まで届かなくなります。
特に、髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)や、その合成を助ける亜鉛、頭皮の健康を保つビタミンB群などが不足すると、髪は細くなり、抜け毛が増える原因となります。
バランスの取れた食事が、健やかな頭皮環境の土台となります。
頭皮と髪の健康を支える栄養素の例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の毛の主成分(ケラチン)を作る。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンB群 | 皮脂の分泌を調整し、頭皮の新陳代謝を促す。 | レバー、豚肉、マグロ、納豆 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、新しい髪の毛を作る。 | 牡蠣、牛肉、レバー、チーズ |
睡眠不足とストレスの関係
睡眠とストレスは、頭皮環境に密接に関わっています。睡眠中には「成長ホルモン」が分泌されます。
このホルモンは、日中に受けたダメージを修復し、細胞の新陳代謝(ターンオーバー)を促す重要な役割を担っています。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、頭皮の修復が追いつかなくなります。その結果、バリア機能が低下し、かゆみやフケ、抜け毛が起こりやすくなります。
また、精神的なストレスを感じると、体は緊張状態になります。自律神経のうち交感神経が優位になり、血管が収縮します。
頭皮には毛細血管が張り巡らされていますが、血管が収縮すると血流が悪化し、毛根への栄養補給が滞ります。さらに、ストレスはホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌を引き起こすことも知られています。
ストレス社会で生きる私たちにとって、いかにリラックスする時間を作るかが、頭皮の健康維持にもつながります。
間違ったヘアケア習慣
良かれと思って行っているヘアケアが、逆に頭皮を傷めている可能性もあります。
例えば、頭皮のかゆみやベタつきが気になるからといって、1日に何度もシャンプーをしたり、爪を立ててゴシゴシと強く洗いすぎたりする行為です。
これは必要な皮脂まで奪い去り、頭皮を乾燥させ、バリア機能を破壊します。かゆいからこそ、優しく洗う必要があるのです。
シャンプー後のすすぎが不十分で、シャンプー剤やコンディショナーが頭皮に残っていると、それが刺激となってかゆみや炎症を引き起こします。
また、髪を洗った後、濡れたまま放置するのも禁物です。湿った頭皮は雑菌が繁殖しやすい絶好の環境であり、かゆみや嫌なニオイの原因となります。
ドライヤーでしっかりと、しかし熱すぎない温度で乾かすことが大切です。
今日から実践できる頭皮のかゆみ・フケ対策
頭皮のかゆみやフケは、頭皮環境が悪化しているサインです。この問題を解決するためには、まず日々の「洗い方」と「選び方」、そして「生活習慣」を見直すことが基本となります。
すぐに取り組める具体的な対策を紹介します。
正しいシャンプー方法の見直し
頭皮トラブルの多くは、間違ったシャンプー方法に起因しています。正しい洗い方をマスターするだけで、頭皮環境は大きく改善することがあります。
まず、シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度程度が目安)で頭皮と髪をしっかりと予洗いします。これだけで、ホコリや皮脂汚れの多くを落とすことができます。
次に、シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。洗う際は、爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく揉み洗いします。
特に、皮脂の多い生え際や頭頂部は丁寧に洗いましょう。
最も重要なのが「すすぎ」です。シャンプー剤が頭皮に残らないよう、洗う時にかけた時間の倍以上の時間をかけて、ぬるま湯で徹底的にすすぎます。
耳の後ろや襟足は残りやすいので注意が必要です。最後に、清潔なタオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで頭皮から中心に乾かします。
自分に合ったシャンプーの選び方
シャンプーは、自分の頭皮の状態に合わせて選ぶことが重要です。洗浄成分によって特徴が異なるため、以下の表を参考に選んでみてください。
頭皮タイプ別シャンプー選びのポイント
| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨されるシャンプー(洗浄成分) |
|---|---|---|
| 乾燥肌・敏感肌 | カサカサしたフケ、かゆみが出やすい | アミノ酸系(例:ココイルグルタミン酸Na) ベタイン系(例:コカミドプロピルベタイン) |
| 脂性肌(オイリー肌) | ベタつくフケ、頭皮がテカりやすい | 高級アルコール系(例:ラウレス硫酸Na)※ 石けん系(例:石ケン素地) |
| フケ・かゆみが特に酷い | 炎症や赤みを伴う場合がある | 薬用シャンプー(抗真菌・抗炎症成分配合) |
※高級アルコール系は洗浄力が強いため、脂性肌の人でも洗いすぎによる乾燥を招く場合があります。頭皮の状態を見ながら使用を判断する必要があります。
頭皮の保湿ケアの重要性
顔のスキンケアで化粧水や乳液を使うように、頭皮も保湿が必要です。特に乾燥が気になる場合や、シャンプー後に頭皮がつっぱる感じがする場合は、保湿ケアを取り入れましょう。
頭皮専用のローションや保湿剤(セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなどが配合されたもの)が市販されています。これらを、お風呂上がりの清潔な頭皮に直接塗布し、指の腹で優しくなじませます。
頭皮が潤うことでバリア機能が整い、外部刺激によるかゆみを防ぐ効果が期待できます。
生活習慣の具体的な改善点
頭皮環境は、体の内側からの影響を強く受けます。シャンプーなどの外側からのケアと同時に、生活習慣の改善も進めましょう。
食事では、脂っこいものや甘いもの、刺激物を控えめにし、ビタミンやミネラル、タンパク質をバランスよく摂取することを心がけます。特にビタミンB群(皮脂コントロール)や亜鉛(新陳代謝)は重要です。
睡眠は、質と量の両方を確保します。最低でも6時間以上、できれば日付が変わる前には就寝し、成長ホルモンの分泌を促しましょう。
適度な運動は血行を促進し、ストレス解消にも役立ちます。ウォーキングやジョギングなど、続けやすいものから始めてみてください。
抜け毛対策としての頭皮環境ケア
抜け毛を減らすためには、髪の毛そのものではなく、その土台である「頭皮環境」を健やかに保つことが何よりも大切です。
かゆみやフケのない清潔で柔軟な頭皮は、健康な髪を育むための第一歩です。
頭皮マッサージの基本的な方法
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに有効です。血流が良くなれば、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きやすくなります。
シャンプー中、またはお風呂上がりで頭皮が清潔な時に行うのがおすすめです。両手の指の腹を使い、頭皮全体を優しく掴むように動かします。爪を立てたり、強くこすったりするのは逆効果です。
生え際から頭頂部へ、側頭部から頭頂部へ、襟足から頭頂部へと、下から上へ向かって引き上げるように行うと効果的です。心地よいと感じる強さで、毎日数分間続けることが大切です。
頭皮マッサージの注意点
| 項目 | 注意点 | 理由 |
|---|---|---|
| 爪 | 爪を立てず、指の腹を使う | 頭皮を傷つけ、炎症の原因となるため。 |
| 強さ | 「気持ちいい」と感じる程度 | 強すぎると頭皮や毛細血管に負担がかかる。 |
| タイミング | 頭皮が清潔な時(例:シャンプー中) | 毛穴に汚れが詰まった状態で行うと、トラブルを悪化させる可能性。 |
育毛剤や発毛剤の役割と選び方
頭皮環境を整えるケアと並行して、育毛剤や発毛剤の使用を検討するのも一つの方法です。ただし、両者には明確な違いがあります。
「育毛剤」は、主に医薬部外品に分類されます。その目的は、今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防することです。
血行促進成分や抗炎症成分、保湿成分などが配合されており、頭皮環境を整える働きが中心です。「発毛剤」は、医薬品に分類されます。
ミノキシジルなどの発毛効果が認められた有効成分が配合されており、新しい髪の毛を生やし、髪を太くする(壮年性脱毛症における)効果が期待できます。
かゆみやフケが出ている段階では、まずは頭皮環境を整える「育毛剤」から試してみるのがよいでしょう。特に、かゆみを抑える抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)が配合されたものが適しています。
発毛剤は効果が高い反面、副作用のリスクや、アルコール成分による刺激を感じる場合もあるため、頭皮の状態が安定してから検討するか、専門家に相談することが賢明です。
紫外線対策の必要性
顔や腕の日焼けは気にしても、頭皮の紫外線対策は見落としがちです。しかし、頭皮は体の中で最も太陽に近い位置にあり、紫外線のダメージを直接受けています。
紫外線は、頭皮の乾燥や炎症を引き起こすだけでなく、活性酸素を発生させて毛母細胞の働きを低下させます。これが、抜け毛や白髪の原因にもなります。
外出時には、帽子をかぶる、日傘をさす、または頭皮・髪用の日焼け止めスプレーを利用するなどして、頭皮を紫外線から守る意識を持つことが、長期的な抜け毛対策につながります。
セルフケアで改善しない場合の対処法
日々のシャンプー方法や生活習慣を見直しても、頭皮のかゆみやフケ、抜け毛が一向に改善しない場合、あるいは症状が悪化する場合は、自己判断でのケアを続けず、専門家の助けを借りるべきです。
皮膚の病気や、AGA(男性型脱毛症)が隠れている可能性があります。
専門家(皮膚科医)に相談する目安
セルフケアで対応できる範囲を超えているかどうかを見極めることが重要です。以下のような症状が続く場合は、早めに皮膚科を受診することを強く推奨します。
受診を推奨する症状の例
| 症状 | 具体的な状態 | 考えられる可能性 |
|---|---|---|
| 強いかゆみ | 我慢できないほどのかゆみ、夜眠れない | 重度の炎症、アレルギー |
| フケの異常 | フケの量が急に増えた、ベタベタした大きなフケ | 脂漏性皮膚炎 |
| 頭皮の赤み・湿疹 | 頭皮が広範囲に赤い、ブツブツができている | 接触皮膚炎、乾癬など |
| 抜け毛の急増 | 明らかに抜け毛の量が増え、地肌が目立ってきた | AGA、円形脱毛症など |
皮膚科で行われる主な検査と対応
皮膚科では、まず医師による視診(頭皮の状態を目で見る)と問診(いつから、どのような症状か、生活習慣など)が行われます。
これらの診察によって、多くの頭皮トラブル(乾燥、脂漏性皮膚炎など)の診断が可能です。
必要に応じて、フケの一部を採取して顕微鏡で調べる「真菌検査」(マラセチア菌の増殖を確認)や、アレルギーが疑われる場合の「パッチテスト」、抜け毛の状態を詳しく調べる「ダーモスコピー検査」(毛穴や毛髪の状態を拡大して観察)などを行います。
診断に基づき、脂漏性皮膚炎であれば抗真菌薬(菌の増殖を抑える)やステロイド外用薬(炎症を抑える)が処方されます。
乾燥や炎症が原因であれば、保湿剤や非ステロイド系の抗炎症薬が処方されることが一般的です。医師の指示に従って正しく薬を使用することが、早期改善への近道です。
AGA(男性型脱毛症)の可能性
抜け毛が特定のパターン(生え際の後退や頭頂部の薄毛)で進行しており、かゆみやフケの治療をしても抜け毛が減らない場合、AGA(男性型脱毛症)の可能性があります。
AGAは、男性ホルモンと遺伝的要因が関与する進行性の脱毛症であり、頭皮環境の悪化とは別の原因で発症します。
ただし、脂漏性皮膚炎などの頭皮トラブルがAGAの進行を早めることはあるため、まずは皮膚科で頭皮の炎症を治療することが先決です。
その上で、AGAが疑われる場合は、皮膚科またはAGA専門のクリニックで相談する必要があります。
AGAには内服薬(フィナステリド、デュタステリド)や外用薬(ミノキシジル)による治療法が確立されています。
頭皮ケアと育毛剤の併用について
頭皮のかゆみやフケを抑えるためのケアと、抜け毛対策としての育毛剤は、適切な順序と方法で併用することで、より良い頭皮環境を目指すことができます。
ただし、頭皮が荒れている時の使用には注意が必要です。
育毛剤を使用するタイミング
育毛剤の最も効果的な使用タイミングは、お風呂上がりです。シャンプーによって頭皮の汚れや余分な皮脂が取り除かれ、毛穴が清潔になっている状態だからです。
また、体が温まって血行が良くなっているため、育毛剤の成分が浸透しやすくなっています。
髪の毛をタオルドライした後、ドライヤーで頭皮と髪を8割程度乾かします。完全に乾かしきる前(少し湿り気が残る程度)に育毛剤を塗布し、指の腹で優しく頭皮全体になじませるようにマッサージします。
その後、再度ドライヤー(冷風または温風を遠くから当てる)で頭皮をしっかり乾かしましょう。頭皮が濡れたままでは、雑菌が繁殖しやすくなり、逆効果です。
かゆみがある時の育毛剤使用の注意点
頭皮にかゆみや赤み、炎症がある場合、育毛剤の使用は慎重になる必要があります。
育毛剤には、血行促進のためのアルコール(エタノール)や、清涼感を与えるためのメントールなどが含まれていることが多く、これらが炎症を起こしているデリケートな頭皮には強い刺激となり、かゆみや炎症を悪化させる恐れがあります。
まずはシャンプーの見直しや皮膚科の受診によって、かゆみや炎症を鎮めることを最優先にしてください。
どうしても育毛剤を使いたい場合は、アルコールフリーや敏感肌用と記載された低刺激性の製品を選ぶか、抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)が配合された、かゆみ・フケ防止を謳う育毛剤を選びましょう。
使用前に確認すべき点
- 頭皮に赤みや湿疹、傷がないか
- アルコールやメントールなど刺激成分の有無
使用を開始する際は、まず少量を目立たない部分(腕の内側など)で試すパッチテストを行うと、より安全です。
育毛剤の成分と頭皮への影響
育毛剤には、抜け毛予防や健やかな髪の育成のために、様々な有効成分が配合されています。かゆみやフケが気になる場合は、以下の表のような成分に着目して選ぶと良いでしょう。
かゆみ・フケ対策として注目したい育毛剤の成分例
| 成分カテゴリ | 代表的な成分名 | 期待される主な働き |
|---|---|---|
| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸2K、アラントイン | かゆみや炎症を鎮め、頭皮の荒れを防ぐ。 |
| 保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン | 頭皮に潤いを与え、乾燥によるかゆみやフケを防ぐ。 |
| 血行促進成分 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 | 頭皮の血流を改善し、毛根への栄養補給を助ける。 |
これらの成分が、悪化した頭皮環境を整え、かゆみやフケを抑えながら、抜け毛を予防する手助けとなります。
自分の頭皮の状態に合った育毛剤を選び、日々のケアに取り入れることが大切です。
よくある質問
- 頭皮のかゆみは市販薬で対応できますか?
-
軽度のかゆみや乾燥によるものであれば、市販の頭皮用ローション(保湿成分配合)や、非ステロイド系の鎮痒(ちんよう)剤で一時的に和らげることが可能な場合があります。
しかし、赤みやフケを伴う場合、脂漏性皮膚炎などの可能性もあるため、症状が続くようであれば自己判断せず皮膚科医に相談することをおすすめします。
- シャンプーは毎日するべきですか?
-
基本的には、頭皮の汚れや余分な皮脂はその日のうちにリセットするため、毎日シャンプーすることが推奨されます。
特に皮脂分泌の多い男性や、日中汗をかいた場合は、清潔を保つために洗いましょう。
ただし、乾燥が非常に強い場合は、洗浄力のマイルドなシャンプーを選んだり、2日に1回にするなど、ご自身の頭皮の状態に合わせて調整することも必要です。
- フケとかゆみが治まれば抜け毛も止まりますか?
-
フケやかゆみが原因で引き起こされていた抜け毛(頭皮環境の悪化によるもの)であれば、頭皮環境が改善することで、抜け毛が減少する可能性は高いです。
しかし、抜け毛の原因がAGA(男性型脱毛症)など別の要因である場合、フケやかゆみが治まっても、AGA自体の進行は止まらないため、抜け毛が続くことがあります。
- 食生活で特に気をつけることは何ですか?
-
まずは、皮脂の過剰分泌につながる脂っこい食事(揚げ物、ファストフードなど)や、糖質の多いお菓子、ジュース類を摂りすぎないことです。
その上で、髪の毛の材料となるタンパク質(肉・魚・大豆)、頭皮の新陳代謝を助けるビタミンB群(レバー・豚肉・マグロ)、血行を良くするビタミンE(ナッツ類・アボカド)などをバランス良く摂ることを意識してください。
フケと薄毛の関係に戻る
Reference
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
KERR, Kathy, et al. Epidermal changes associated with symptomatic resolution of dandruff: biomarkers of scalp health. International journal of dermatology, 2011, 50.1: 102-113.
ASFOUR, Leila; CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. Endotext [Internet], 2023.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.
TRÜEB, Ralph M. Is androgenetic alopecia a photoaggravated dermatosis?. Dermatology, 2003, 207.4: 343-348.
PIÉRARD, G. E., et al. Improvement in the inflammatory aspect of androgenetic alopecia. A pilot study with an antimicrobial lotion. Journal of dermatological treatment, 1996, 7.3: 153-157.
LOCKER, Kathryn CS, et al. Understanding the dandruff flare‐up: A cascade of measurable and perceptible changes to scalp health. International Journal of Cosmetic Science, 2025.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
PEKMEZCI, Erkin; DÜNDAR, Cihat; TÜRKOĞLU, Murat. A proprietary herbal extract against hair loss in androgenetic alopecia and telogen effluvium: A placebo-controlled, single-blind, clinical-instrumental study. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat, 2018, 27.2: 51-57.