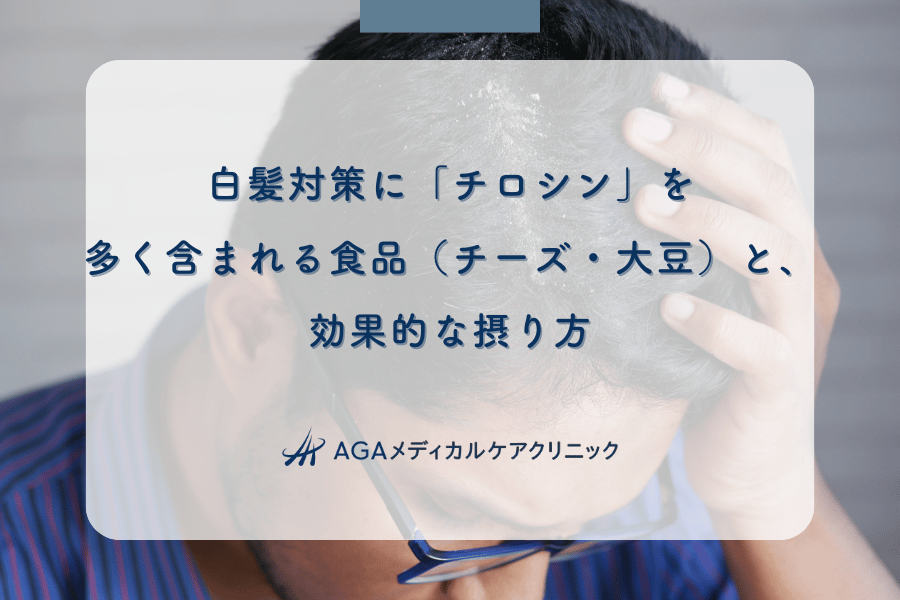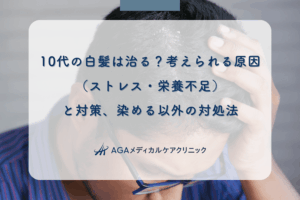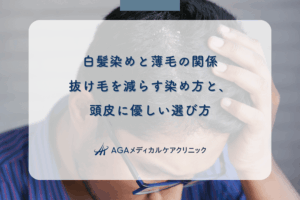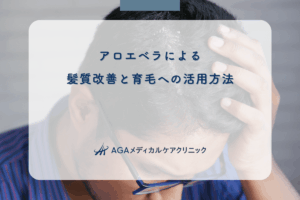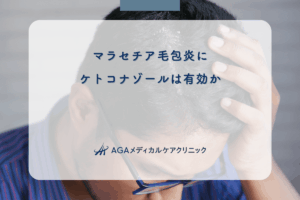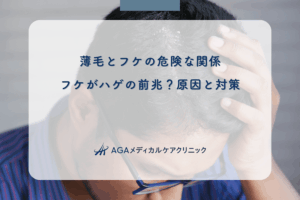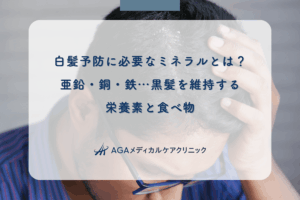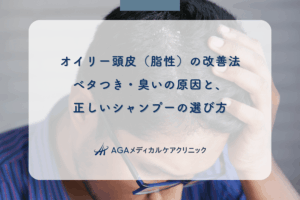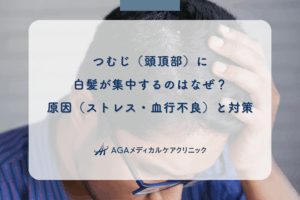鏡を見るたびに増えているように感じる白髪。「もう年齢だから仕方ない」と諦めていませんか。白髪は加齢だけでなく、栄養不足も関係している可能性があります。
特に注目したいのが、アミノ酸の一種である「チロシン」です。チロシンは、髪を黒くするメラニン色素の原料となります。
この記事では、白髪とチロシンの関係性を詳しく解説し、チロシンを多く含む代表的な食品であるチーズや大豆製品、さらに効果的な摂取方法まで、白髪対策のヒントを分かりやすく紹介します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
白髪とチロシンの関係性とは
白髪対策を考える上で、「チロシン」という栄養素が注目を集めています。しかし、なぜチロシンが白髪と関係するのでしょうか。
まずは、白髪が生える背景と、そこでチロシンが果たす役割について基本的な知識を確認しましょう。
そもそも白髪はなぜ生えるのか
髪の毛は、毛根にある毛包という場所で作られます。生まれたばかりの髪の毛は、実はすべて白い色をしています。この時点ではまだ色が付いていません。
髪の毛が黒や褐色になるのは、毛根にある「メラノサイト(色素形成細胞)」という細胞の働きによるものです。
メラノサイトが「メラニン色素」を生成し、それが髪の毛の内部に取り込まれることで、私たちが見慣れた髪色になります。
白髪は、このメラノサイトの働きが何らかの理由で低下したり、メラノサイト自体が消失したりして、メラニン色素が作られなくなるか、髪に取り込まれなくなることで発生します。
その原因は多岐にわたります。最も大きな要因は加齢ですが、それ以外にも遺伝的要因、精神的なストレス、生活習慣の乱れ、そして栄養状態も深く関わっていると考えられています。
メラニン色素と髪色のつながり
メラニン色素には、大きく分けて「ユーメラニン(黒褐色系)」と「フェオメラニン(黄赤色系)」の2種類があります。髪の色は、これら2種類のメラニンの量とバランスによって決まります。
日本人のような黒髪は、ユーメラニンが非常に多い状態です。白髪は、これらのメラニン色素が全く、あるいはほとんど含まれていない状態の髪を指します。
つまり、髪を黒く保つためには、メラノサイトが活発に働き、メラニン色素を安定して供給し続けることが重要なのです。
チロシンが黒髪の材料になる仕組み
ここで「チロシン」が登場します。チロシンは、体内で合成可能な「非必須アミノ酸」の一種ですが、食事から摂取することも重要なたんぱく質の構成要素です。
このチロシンこそが、メラニン色素の「原料」となります。メラノサイトの中では、「チロシナーゼ」という酵素の働きによって、チロシンが段階的に化学変化を起こし、最終的にメラニン色素が生成されます。
具体的には、チロシンがチロシナーゼによってドーパ、ドーパキノンへと変化し、そこからさらに複雑な反応を経てユーメラニンやフェオメラニンが作られます。
つまり、チロシンは黒髪の色の元となる、非常に大切な出発点なのです。
チロシン不足が白髪の一因になる可能性
もし体内のチロシンが不足すると、どうなるでしょうか。メラノサイトが元気で、チロシナーゼ酵素も十分に存在していても、肝心の原料であるチロシンが足りなければ、メラニン色素を十分に生成できません。
その結果、新しく生えてくる髪に色を付けることができず、白髪として生えてくる可能性が高まります。
もちろん、白髪の原因はチロシン不足だけではありませんが、バランスの取れた栄養摂取、特にメラニンの原料となるチロシンを食事からしっかり摂ることは、健やかな黒髪を維持するための一つの対策と言えるでしょう。
チロシンを多く含む主な食品群
チロシンが白髪対策に重要と分かっても、具体的にどのような食品に多く含まれているのでしょうか。チロシンはアミノ酸の一種であり、たんぱく質が豊富な食品に含まれています。
ここでは、チロシンを摂取しやすい主な食品群を紹介します。
毎日の食卓に取り入れたい乳製品
乳製品は、チロシンの優れた供給源です。特にチーズは含有量が多いことで知られています。「チロシン」という名前自体が、ギリシャ語の「Tyri(チーズ)」に由来しているほどです。
チーズの中でも、製造の過程でたんぱく質が凝縮・熟成されるハードタイプやセミハードタイプのチーズは、特にチロシンが豊富です。
例えば、パルメザンチーズ(粉チーズ)は少量でも多くのチロシンを摂取できます。
チーズの種類別チロシン含有量目安(100gあたり)
| 食品名 | 種類 | チロシン含有量 (mg) |
|---|---|---|
| パルメザンチーズ | ハード | 約 2,500 – 3,000 mg |
| チェダーチーズ | セミハード | 約 1,500 – 1,800 mg |
| プロセスチーズ | プロセス | 約 1,300 – 1,600 mg |
※含有量は製品や製法により異なります。あくまで目安としてください。 この表からも分かる通り、チーズはチロシン補給に非常に効率的な食品です。
日本の食文化に根付く大豆製品
日本人にとって非常に馴染み深い大豆製品も、チロシンを豊富に含む食品群です。「畑の肉」と呼ばれる大豆は、良質なたんぱく質の供給源であり、それに伴いチロシンも多く含んでいます。
納豆、豆腐、油揚げ、きな粉、豆乳など、日常的に取り入れやすい食品が多いのが特徴です。
特に、水分が少なく大豆の成分が凝縮されている食品、例えば高野豆腐(凍り豆腐)やきな粉は、重量あたりのチロシン含有量が高くなります。
主な大豆製品のチロシン含有量目安(100gあたり)
| 食品名 | 種類 | チロシン含有量 (mg) |
|---|---|---|
| きな粉(全粒大豆) | 大豆加工品 | 約 1,400 mg |
| 高野豆腐(乾) | 大豆加工品 | 約 2,000 mg (※乾燥状態) |
| 納豆(糸引き) | 大豆発酵食品 | 約 400 – 500 mg |
※高野豆腐は乾燥状態での数値であり、水戻しすると重量あたりの数値は変わりますが、原料として豊富に含むことが分かります。
その他の注目すべきチロシン源
チーズや大豆製品以外にも、チロシンを含む食品は多数あります。
例えば、魚介類、特にカツオやマグロなどの赤身魚、たらこやしらす干しにも含まれます。肉類(鶏肉、豚肉、牛肉)や卵も良質なたんぱく質源であり、チロシンを補給できます。
また、種実類では、かぼちゃの種やアーモンド、ピーナッツ、ごまなどにも比較的多く含まれています。これらは間食として取り入れるのも良いでしょう。
動物性たんぱく質と植物性たんぱく質
チロシンは動物性たんぱく質(肉、魚、卵、乳製品)と植物性たんぱく質(大豆製品、穀物)の両方に含まれています。
白髪対策や健康維持のためには、どちらかに偏るのではなく、多様な食品からバランスよくたんぱく質を摂取することが重要です。
動物性食品はチロシンと同時に、後述するビタミンB群やミネラル(特に亜鉛や銅)も含むことが多く、植物性食品は食物繊維や抗酸化物質を一緒に摂取できる利点があります。
日々の食事で、これらの食品群を組み合わせて取り入れることを意識しましょう。
チロシンが豊富な食品(乳製品)
チロシンを多く含む食品群の中でも、特におすすめしたいのが乳製品、とりわけチーズです。ここでは、乳製品がなぜ白髪対策に適しているのか、その理由と具体的な取り入れ方について詳しく見ていきます。
チーズが白髪対策におすすめの理由
チーズが推奨される最大の理由は、そのチロシン含有量の高さにあります。前述の通り、パルメザンチーズやチェダーチーズなど、熟成タイプのチーズは非常に多くのチロシンを含んでいます。
また、チーズはたんぱく質が分解・熟成される過程で、アミノ酸が吸収されやすい形になっているとも言われています。手軽に食べられる点も魅力です。
料理に加えたり、そのままおやつとして食べたりと、食生活に取り入れやすいのが大きな利点です。
さらに、チーズにはチロシンだけでなく、髪の主成分であるたんぱく質や、骨の健康に必要なカルシウム、皮膚や粘膜の健康を助けるビタミンAやビタミンB2なども含まれており、総合的な栄養補給にも役立ちます。
特におすすめのチーズの種類
チロシンを効率的に摂取したい場合、水分が少なく硬い「ハードタイプ」や「セミハードタイプ」のチーズを選ぶと良いでしょう。
- パルメザンチーズ(パルミジャーノ・レッジャーノ)
- チェダーチーズ
- ゴーダチーズ
- エメンタールチーズ
パルメザンチーズは粉末状のものが市販されており、パスタやサラダ、スープに振りかけるだけで手軽にチロシンをプラスできます。
チェダーチーズやゴーダチーズは、スライスしてパンに乗せたり、カットしてそのまま食べたりするのに適しています。
チーズを食べる際の注意点
チーズは栄養価が高い一方で、脂質や塩分も多く含む傾向があります。特に白髪対策として毎日摂取したい場合、食べ過ぎには注意が必要です。
脂質の摂りすぎは、カロリーオーバーによる体重増加や、頭皮環境の悪化(皮脂の過剰分泌など)につながる可能性も否定できません。また、塩分の過剰摂取は健康全般に影響を与えます。
カッテージチーズやリコッタチーズ、モッツァレラチーズなどのフレッシュタイプのチーズは、ハードタイプに比べるとチロシン含有量は少なめですが、脂質や塩分が控えめな製品が多いです。
これらとハードタイプを日によって使い分けるなど、バランスを考えることが大切です。
ヨーグルトや牛乳のチロシン含有量
チーズ以外の乳製品、例えばヨーグルトや牛乳にもチロシンは含まれています。ただし、これらは水分が多いため、100gあたりの含有量で比較するとチーズよりも少なくなります。
しかし、ヨーグルトや牛乳は毎日継続して摂取しやすい食品です。特にヨーグルトは腸内環境を整える乳酸菌も一緒に摂れるという利点があります。
朝食にヨーグルトや牛乳を取り入れる習慣は、チロシンを安定的に補給する上で有効な方法と言えるでしょう。
チロシンが豊富な食品(大豆製品)
乳製品と並んで、チロシンの優れた供給源となるのが大豆製品です。
日本の伝統的な食生活に欠かせない大豆製品は、白髪対策だけでなく、男性の健康維持全般においても多くの利点を持っています。
大豆製品が持つ多面的な健康効果
大豆製品の魅力は、チロシンが豊富であることだけではありません。大豆たんぱく質は、コレステロール値の改善に役立つことが知られています。
また、大豆イソフラボンという成分は、抗酸化作用を持つほか、男性ホルモンのバランスにも良い影響を与える可能性が研究されています。
さらに、食物繊維やビタミン、ミネラルもバランスよく含んでおり、健康的な食生活の基盤となる食品です。
白髪対策と同時に、生活習慣病の予防や健康維持を目指す上で、積極的に取り入れたい食品群です。
納豆や豆腐の日常的な取り入れ方
大豆製品の中でも、納豆や豆腐は特におすすめです。これらは調理の手間が少なく、ほぼ毎日でも食べやすいという大きな利点があります。
納豆は朝食の定番として、ご飯にかけるだけでなく、オムレツの具材にしたり、サラダのトッピングにしたりと活用できます。納豆菌による発酵の力も期待できます。
豆腐は、冷奴や湯豆腐のようにシンプルに食べるほか、味噌汁の具、炒め物、煮物など、和洋中どんな料理にも使えます。
木綿豆腐は充填豆腐(絹ごし)よりもたんぱく質やチロシンの含有量が多い傾向にあります。
味噌や醤油に含まれるチロシン
味噌や醤油も大豆から作られる発酵食品であり、チロシンを含んでいます。これらは調味料として使用するため、一度に摂取する量は少ないですが、「ほぼ毎日使う」という点で重要です。
日々の食事で味噌汁を飲む、和え物や煮物に醤油を使うことは、知らず知らずのうちにチロシンを補給する助けになっています。
出汁をしっかり取り、塩分控えめでも美味しく食べられるよう工夫すると、健康的に継続できます。
豆乳の活用方法
牛乳と同様に、豆乳も手軽にチロシンを摂取できる飲料です。牛乳が苦手な方でも、豆乳であれば飲めるという場合もあるでしょう。
そのまま飲むだけでなく、コーヒーや紅茶に入れたり、スムージーのベースにしたり、シチューやスープなどの料理に使ったりすることもできます。無調整豆乳の方が、大豆の成分がより多く含まれています。
このように、大豆製品は非常にバリエーションが豊かです。一つの食品に偏らず、様々な大豆製品をローテーションで取り入れることで、飽きずにチロシン摂取を続けることができます。
チロシンを効率良く摂取するための食べ合わせ
白髪対策のためには、チロシンという「原料」をただ摂取するだけでは十分ではありません。
そのチロシンが体内で効率よくメラニン色素に変わるよう、「サポート役」となる栄養素を一緒に摂ることが非常に重要です。ここでは、効果的な食べ合わせについて解説します。
チロシンの吸収を助ける栄養素
チロシンはアミノ酸の一種です。食事から摂ったたんぱく質が消化されてアミノ酸になり、腸から吸収されます。この吸収や、その後の代謝を助ける栄養素があります。
特に、チロシンからメラニン色素が生成される際には「チロシナーゼ」という酵素が働きますが、この酵素の働きを助ける栄養素を意識して摂ることが鍵となります。
ビタミンB6を多く含む食品
ビタミンB6は、たんぱく質やアミノ酸の代謝に深く関わるビタミンです。チロシンを含むたんぱく質の分解や、チロシンの体内での利用を助ける働きをします。
また、ビタミンB6は健康な皮膚や髪を維持するためにも必要な栄養素です。チロシンを多く含む食品とビタミンB6を多く含む食品を組み合わせることで、より効率的な栄養補給が期待できます。
ビタミンB6が豊富な食材例
| 食品カテゴリー | 主な食材 |
|---|---|
| 魚類 | カツオ、マグロ(赤身)、サケ、サバ |
| 肉類 | 鶏むね肉、鶏ささみ、レバー |
| その他 | バナナ、にんにく、玄米 |
例えば、「マグロの刺身(チロシン+B6)」や「鶏むね肉とバナナのスムージー(チロシン+B6)」、「納豆(チロシン)にごま(B6含む)をかける」といった組み合わせが考えられます。
銅(ミネラル)の役割と含まれる食品
白髪対策において、ミネラルの「銅」は非常に重要な役割を果たします。なぜなら、メラニン色素を作る酵素「チロシナーゼ」は、その活性中心に銅を持つ「銅酵素」だからです。
つまり、チロシンという原料がいくらあっても、銅が不足してチロシナーゼが正常に働かなければ、メラニン色素は作られません。
銅は体内で合成できないため、食事から摂取する必要があります。
銅を補給できる食材例
| 食品カテゴリー | 主な食材 |
|---|---|
| 魚介類 | カキ(牡蠣)、エビ、イカ、ホタルイカ |
| 種実類 | アーモンド、カシューナッツ、ごま |
| その他 | 牛レバー、大豆製品、ココア |
大豆製品はチロシンと銅の両方を含む優れた食品であることがわかります。また、チーズ(チロシン)と一緒にアーモンド(銅)を間食にするのも良い組み合わせです。
バランスの良い食事が基本
チロシン、ビタミンB6、銅。これらが白髪対策の栄養面でのキープレイヤーです。しかし、これらの栄養素だけを偏って摂れば良いというわけではありません。
例えば、ビタミンCはメラニン生成の特定の段階を助けるとも言われていますし、亜鉛は髪の主成分であるケラチンの合成に必要です。
結局のところ、特定の食品に頼るのではなく、主食・主菜・副菜をそろえ、多様な食材から栄養を摂取する「バランスの良い食事」こそが、健やかな髪を育む一番の近道です。
チロシンが豊富な食品は、そのバランスの良い食事の中に上手に組み込んでいきましょう。
チロシン摂取における注意点とポイント
チロシンが白髪対策に役立つ可能性があるからといって、やみくもに摂取するのは賢明ではありません。適切な摂取方法や、知っておくべき注意点があります。
サプリメントの利用法や、食事以外の対策とのバランスについても考えてみましょう。
1日のチロシン摂取目安量
チロシンは非必須アミノ酸であり、健康な人であれば体内でフェニルアラニンという別のアミノ酸からも合成されます。そのため、必須アミノ酸のような明確な「推奨摂取量」は定められていません。
一般的な成人のたんぱく質推奨量を満たしていれば、通常の食事でチロシンが極端に不足することは考えにくいとされています。
体重1kgあたり1gのたんぱく質(例:体重60kgなら60g)を目安に、多様な食品からたんぱく質をしっかり摂取することを心がければ、チロシンもそれに伴って摂取できます。
例えば、チーズ30gと納豆1パック、鶏むね肉100gを1日で食べれば、それだけで多くのチロシンを補給できます。
サプリメントを利用する場合の考え方
チロシンはサプリメントとしても市販されています。食事だけでは不安な方や、多忙で食事が偏りがちな方が利用を検討することもあるでしょう。
サプリメントを利用する際は、必ず製品に記載されている目安量を守ってください。食品から摂取する場合と異なり、特定の成分だけを高濃度で摂取することになるため、過剰摂取のリスクがあります。
また、チロシンは特定の薬(甲状腺関連やうつ病治療薬の一部など)と相互作用を起こす可能性が指摘されています。
持病がある方や薬を服用中の方は、サプリメントを利用する前に必ず医師や薬剤師に相談してください。基本は食事から、サプリメントはあくまで補助的なものと考えるのが安全です。
チロシンだけ摂れば白髪は防げるのか
これが最も重要なポイントですが、答えは「ノー」です。白髪の原因は非常に複雑で、チロシン不足はその一因に過ぎない可能性があります。
加齢によるメラノサイトの機能低下、遺伝的要因、強いストレスによる血行不良や活性酸素の増加、睡眠不足や喫煙といった生活習慣の乱れなど、多くの要因が絡み合っています。
いくらチロシンを大量に摂取しても、酵素(チロシナーゼ)の働きが弱っていればメラニンは作られませんし、強いストレスで頭皮の血流が悪ければ、メラノサイトに栄養が届きません。
チロシンの摂取は、あくまで白髪対策の「守り」の一つと捉えるべきです。
食事以外の白髪対策との併用
チロシンを食事からしっかり摂ることに加えて、総合的な生活改善を行うことが、白髪対策の効果を高める鍵となります。
特に、頭皮の血行を良くすることは、毛根に栄養を届けるために重要です。
- 十分な睡眠
- 適度な運動
- ストレスの効果的な発散
- 禁煙
- 頭皮マッサージ
これらの生活習慣の見直しは、白髪対策だけでなく、育毛や健康維持全般に良い影響を与えます。チロシン摂取と併せて、ぜひ実践してみてください。
チロシン以外に注目したい白髪対策の栄養素
白髪対策は、チロシンだけでは完結しません。髪の健康を維持し、メラノサイトが正常に働く環境を整えるためには、他の栄養素も同様に重要です。
ここでは、チロシンと併せて摂取したい、健やかな髪のための栄養素を紹介します。
髪の健康を支えるたんぱく質
言うまでもなく、髪の毛そのものの主成分は「ケラチン」というたんぱく質です。
チロシンもたんぱく質を構成するアミノ酸の一つですが、それ以外のアミノ酸もバランスよく摂取しなければ、丈夫で健康な髪は作られません。
肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など、良質なたんぱく質源を毎食取り入れることが基本です。これらの食品はチロシンも同時に補給できるため、一石二鳥と言えます。
たんぱく質が不足すると、髪が細くなったり、ハリやコシが失われたりする原因にもなります。
血行促進に関わるビタミンE
ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、強い抗酸化作用を持つことで知られています。体内の脂質の酸化を防ぎ、細胞の健康維持を助けます。
さらに、ビタミンEには末梢血管を広げ、血流を良くする働きがあります。頭皮の毛細血管の血流が改善すれば、毛根にあるメラノサイトや毛母細胞に必要な栄養素や酸素が届きやすくなります。
ビタミンEは、アーモンドなどのナッツ類、かぼちゃ、アボカド、植物油(ひまわり油、オリーブオイルなど)に多く含まれています。
メラノサイトの働きを助けるミネラル
チロシンの項目で触れた「銅」以外にも、髪の健康に重要なミネラルがあります。代表的なものが「亜鉛」と「ヨウ素(ヨード)」です。
亜鉛は、たんぱく質の再合成、つまり髪(ケラチン)を作る際に必要なミネラルです。細胞分裂にも関わるため、新しい髪が作られる毛母細胞の働きに重要です。亜鉛はカキ(牡蠣)やレバー、赤身肉、チーズに多く含まれます。
ヨウ素は、甲状腺ホルモンの構成成分であり、全身の新陳代謝を活発にします。
メラノサイトの働きを活性化させるとも言われており、髪の健康維持に間接的に関わっています。ヨウ素は昆布やわかめ、ひじきなどの海藻類に豊富です。
髪の健康維持に役立つ主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 髪(ケラチン)の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンE | 抗酸化作用、血行促進 | ナッツ類、アボカド、植物油 |
| 亜鉛 | たんぱく質の合成、細胞分裂 | カキ、レバー、赤身肉 |
| ヨウ素 | 新陳代謝の促進 | 海藻類(昆布、わかめ) |
このように、多くの栄養素が互いに関わり合って髪の健康は保たれています。チロシンを意識しつつも、これらの栄養素も不足しないよう、幅広い食品を食べるようにしましょう。
白髪対策に戻る
Q&A
最後に、白髪対策としてのチロシン摂取に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめます。
- チロシンはいつ摂取するのが効果的ですか?
-
チロシンの摂取タイミングについて、白髪対策の観点で医学的に「この時間が最適」と明確に定められているわけではありません。
チロシンは食品中のたんぱく質に含まれるため、通常の食事と共に摂取することになります。
大切なのは、一度に大量に摂ることよりも、毎日継続して必要な量を補給し続けることです。
3度の食事でたんぱく質が不足しないよう、朝食に納豆やヨーグルト、昼食・夕食で肉や魚、豆腐などをバランスよく取り入れることをおすすめします。
- チロシンを摂りすぎるとどうなりますか?
-
通常の食事からチロシンを摂取する場合、摂りすぎによる健康被害を心配する必要はほとんどありません。食品から摂取する限り、過剰になることは考えにくいです。
ただし、前述の通り、サプリメントで高用量を長期間摂取する場合は注意が必要です。
チロシンは体内でドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の前駆体にもなるため、過剰摂取が心拍数の上昇や血圧の変動などを引き起こす可能性が理論上考えられます。
特に持病のある方は、サプリメントの使用は慎重に行い、医師に相談してください。
- 食品から摂るのとサプリメントではどちらが良いですか?
-
白髪対策や健康維持の観点からは、まず「食品」からの摂取を最優先すべきです。
食品からはチロシンだけでなく、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど、髪の健康に必要な他の栄養素も同時に摂取できるからです。
例えば、チーズからはチロシンと亜鉛、大豆製品からはチロシンと銅、マグロからはチロシンとビタミンB6が摂れます。
こうした栄養素の相乗効果が期待できるのが、食事の最大の利点です。サプリメントは、どうしても食事が偏ってしまう時の補助的な手段として位置づけるのが良いでしょう。
- チロシンを摂り始めたら、どれくらいで白髪への効果を感じますか?
-
栄養摂取による体質改善、特に髪質の改善には時間がかかります。髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びません。
食生活を見直してチロシンや関連栄養素の摂取を増やしたとしても、その影響が新しく生えてくる髪に現れるまでには、数ヶ月単位の時間が必要です。
また、チロシンを摂取したからといって、すでに生えている白髪が黒髪に戻ることはありません。あくまで「これから生えてくる髪」に対する予防的アプローチです。
さらに、白髪の原因がチロシン不足以外(加齢や遺伝など)にある場合は、食事改善だけでは効果を実感しにくいこともあります。
即効性を期待せず、健康的な食生活を続けるという長期的な視点が重要です。
Reference
YADAV, Mahipat S.; KUSHWAHA, Neeti; MAURYA, Neelesh K. The Influence of Diet, Lifestyle, and Environmental Factors on Premature Hair Greying: An Evidence-Based Approach. Archives of Clinical and Experimental Pathology, 2025, 4.1.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
TRÜEB, Ralph M. Value of nutrition-based therapies for hair growth, color, and quality. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 225-255.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
WATSON, Adrian, et al. Tyrosine supplementation and hair coat pigmentation in puppies with black coats–A pilot study. Journal of Applied Animal Nutrition, 2015, 3: e10.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
ABDO, Farida Samy. Hair Integrity and Health with Dieting. NILES journal for Geriatric and Gerontology, 2025, 8.3: 273-288.
TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 111-223.
WATSON, Adrian, et al. Increased dietary intake of tyrosine upregulates melanin deposition in the hair of adult black-coated dogs. Animal Nutrition, 2018, 4.4: 422-428.
YU, S.; ROGERS, Q. R.; MORRIS, J. G. Effect of low levels of dietary tyrosine on the hair colour of cats. Journal of Small Animal Practice, 2001, 42.4: 176-180.