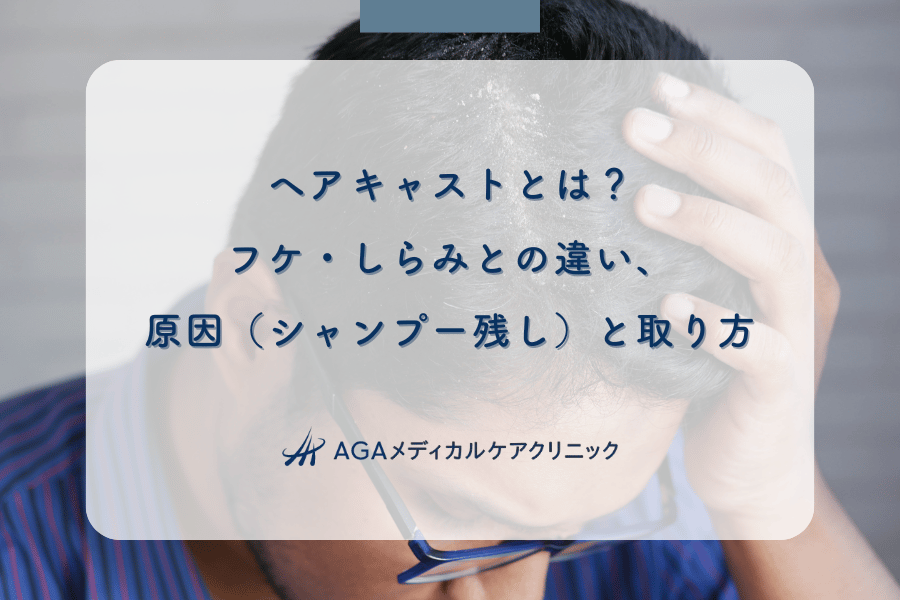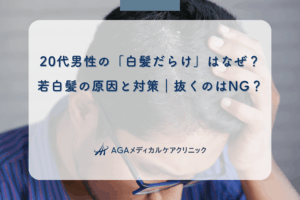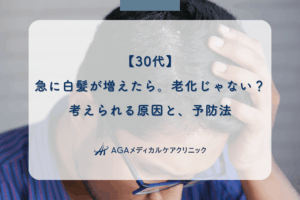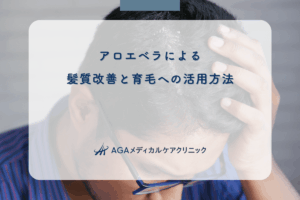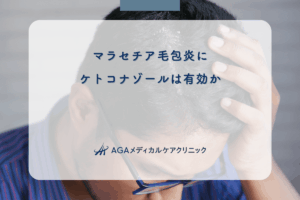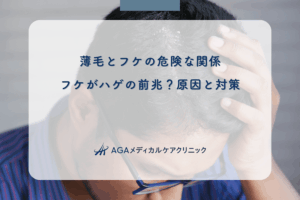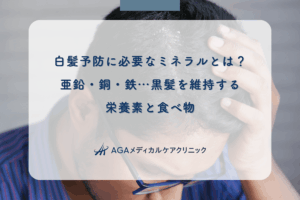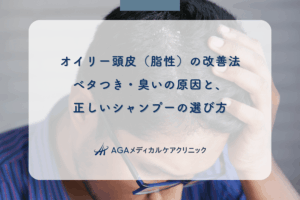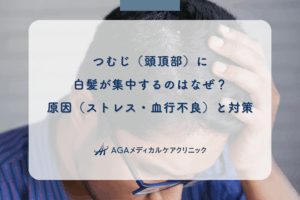ふと髪の毛を見たとき、根元近くに白い付着物を見つけて「これは何だろう?」「もしかしてフケやしらみ?」と不安になった経験はありませんか。
その白い物体の正体は、「ヘアキャスト」かもしれません。ヘアキャスト自体は病気ではなく、頭皮環境のサインともいえます。
この記事では、ヘアキャストとは何か、多くの人が悩むフケやしらみとの明確な違い、そしてヘアキャストができる主な原因、特にシャンプーのすすぎ残しとの関係について詳しく解説します。
さらに、気になるヘアキャストの安全な取り方と、再発を防ぐための頭皮ケアについてもご紹介します。正しい知識を身につけ、健やかな頭皮環境を取り戻しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ヘアキャストとは?その正体と特徴
「ヘアキャスト」という言葉を初めて聞く人も多いかもしれません。まずは、このヘアキャストが一体何なのか、その正体と具体的な特徴について理解を深めましょう。
髪の毛を取り巻く白い鞘(さや)
ヘアキャストは、髪の毛の根元から数センチほどの部分に、まるで鞘(さや)のように巻き付いている、白く半透明な付着物です。髪の毛をぐるりと囲むように筒状に付着しているのが大きな特徴です。
髪をかき分けたり、ブラッシングしたりした際に見つかることが多く、数本から数十本の髪に見られることもあります。
ヘアキャストの主な成分
ヘアキャストを形成している主な成分は、古くなった頭皮の角質(ケラチン)や、皮脂腺から分泌された皮脂が混ざり合ったものです。
これらが髪の毛の成長とともに毛穴から押し出され、毛幹(髪の毛本体)にこびりついて固まることで形成されます。毛根鞘(もうこんしょう)の一部が剥がれて残ったものともいわれています。
痛みやかゆみは伴う?
ヘアキャストそのものが、直接的に痛みやかゆみを引き起こすことはほとんどありません。無症状であることが多いため、自分では気づきにくい場合もあります。
ただし、ヘアキャストが発生する背景には、頭皮環境の乱れ(例えば皮脂の過剰分泌や乾燥)が隠れていることがあります。
そうした頭皮環境の乱れが、結果としてかゆみや赤みを伴う原因になる可能性はあります。
ヘアキャストの基本的な性質
| 特徴 | 詳細 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 形状 | 髪の毛を筒状に取り巻く鞘(さや)状 | なし (まれに関連する頭皮環境によりかゆみ) |
| 色 | 白色または半透明 | なし |
| 付着部位 | 毛幹 (主に根元付近) | なし |
ヘアキャストと見間違いやすい症状
髪の毛に白いものが付着していると、多くの人がまずフケやしらみ(特にその卵)を疑います。しかし、ヘアキャストはこれらとは全く異なるものです。
ここでは、ヘアキャストと混同しやすい症状との違いを明確にし、見分け方を解説します。
フケとの違い
フケは、頭皮のターンオーバー(新陳代謝)によって剥がれ落ちた古い角質です。
通常は非常に小さく目に見えにくいものですが、頭皮環境が乱れると角質が大きくまとまって剥がれ、目に見えるフケとなります。
ヘアキャストが髪の毛に鞘状に「巻き付いている」のに対し、フケは頭皮や髪の毛に「乗っている」だけ、あるいは「付着している」だけです。
そのため、フケは軽く手で払ったり、ブラッシングしたりすると簡単に髪から離れます。
一方、ヘアキャストは髪にしっかり巻き付いているため、指でしごいても簡単には取れず、毛先に向かってスライドさせることができます。
しらみ(アタマジラミ)の卵との違い
アタマジラミの卵は「シラミの卵」とも呼ばれ、白や黄白色をしています。これもヘアキャストと同様に毛幹に付着しますが、決定的な違いはその付着方法と形状です。
シラミの卵は、セメントのような強固な物質で髪の毛の「片側」にしっかりと固定されています。そのため、指でつまんでも全く動きません。
また、形状は涙滴状や楕円形をしています。対照的に、ヘアキャストは髪の毛全体を「筒状」に囲んでおり、指でしごくと毛先に向かって動かすことが可能です。
アタマジラミの成虫が見つかったり、強いかゆみを伴ったりする点も、しらみを見分ける重要なポイントです。
皮脂の塊やその他の付着物
頭皮の皮脂分泌が非常に多い場合、皮脂が毛穴周りや髪の根元で固まり、白い塊のように見えることがあります。
これはヘアキャストのように鞘状にはならず、より脂っぽくベタついた感触が特徴です。また、ヘアスプレーやワックスなどのスタイリング剤が洗い落とせず、白い粉や塊として髪に残ることもあります。
これらも通常、ブラッシングや洗浄で比較的容易に取り除けます。
見分け方のポイント
| 項目 | ヘアキャスト | フケ (乾燥性・脂性) | しらみの卵 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 髪を囲む筒状(鞘状) | 鱗片状、粉状、または塊状 | 楕円形、涙滴状 |
| 付着状態 | 髪に巻き付いている (毛先へ動かせる) | 髪や頭皮に乗っている (簡単に取れる) | 髪の片側に固く付着 (動かない) |
| かゆみ等 | 基本的にはない | かゆみや炎症を伴うことがある | 強いかゆみ (成虫による) |
ヘアキャストが発生する主な原因
ヘアキャスト自体は病気ではありませんが、その発生は頭皮環境やヘアケアの方法に何らかの偏りがあることを示唆しています。
なぜヘアキャストができてしまうのか、その主な原因を探っていきましょう。
最大の原因?シャンプーやコンディショナーのすすぎ残し
ヘアキャストの発生原因として最も多く指摘されるのが、シャンプーやコンディショナー、トリートメントなどの「すすぎ残し」です。
特に、髪の根元や生え際、耳の後ろなどはすすぎにくい部分であり、洗浄成分や保湿成分が残りやすい場所です。
これらの残留物が、頭皮から分泌される皮脂や剥がれ落ちた角質と混ざり合い、毛幹に蓄積していきます。これが乾燥して固まることで、ヘアキャストが形成されると考えられています。
タイトルにもある通り、シャンプー残しはヘアキャストの主要な原因の一つといえます。
皮脂の過剰分泌と頭皮環境
頭皮の皮脂分泌が過剰な状態(脂性肌)も、ヘアキャストの原因となります。
皮脂は頭皮を守るために必要なものですが、ホルモンバランスの乱れ、食生活、ストレス、体質などによって分泌量が増えすぎることがあります。
過剰な皮脂が毛穴周りに溜まり、古い角質と混ざり合うことで、ヘアキャストが形成されやすくなります。特に男性は皮脂分泌が活発な傾向にあるため、注意が必要です。
ヘアスタイリング剤の残留
ワックス、ジェル、スプレーなどのヘアスタイリング剤を多用し、その日のうちにしっかりと洗い流せていない場合も、ヘアキャストの原因になり得ます。
スタイリング剤の成分が髪や頭皮に残り、皮脂や角質と結びついて蓄積し、ヘアキャストを形成する材料となってしまいます。
ヘアキャストの原因となりやすいヘアケア製品
| 製品タイプ | 残りやすい成分 | 注意点 |
|---|---|---|
| シャンプー | 洗浄成分 (界面活性剤) | 特に髪の根元、生え際のすすぎを徹底する。 |
| コンディショナー | 油分、保湿成分 (シリコーン等) | 頭皮に直接つけず、髪の中間から毛先に使う。 |
| スタイリング剤 | 樹脂成分、油分 | 毎日しっかり洗い流す。洗浄力の適切なシャンプーを選ぶ。 |
頭皮のターンオーバーの乱れ
頭皮も肌の一部であり、一定の周期で新しい細胞に生まれ変わっています(ターンオーバー)。
しかし、睡眠不足、ストレス、栄養バランスの偏り、あるいは不適切なヘアケアによってこの周期が乱れると、古い角質が正常に剥がれ落ちず、頭皮に蓄積しやすくなります。
蓄積した角質が皮脂と混ざり合うことで、ヘアキャストだけでなく、フケなどの頭皮トラブルの原因にもなります。
ヘアキャストができやすい人の特徴
ヘアキャストは誰にでもできる可能性がありますが、特定の生活習慣や頭皮の状態を持つ人は、より発生しやすい傾向があります。ご自身の状況と照らし合わせてチェックしてみましょう。
洗髪が不十分な人
最も分かりやすい特徴は、洗髪やすすぎが不十分な人です。
シャンプーを泡立てずに頭皮に直接つけたり、指の腹で頭皮をしっかり洗えていなかったり、シャワーの時間が短くすすぎが甘かったりすると、洗浄成分や汚れが残りやすくなります。
これがヘアキャストの直接的な原因(シャンプー残し)となります。
皮脂分泌が多い人(特に男性)
体質的に皮脂分泌が多い人、いわゆる脂性肌の人は、ヘアキャストの材料となる皮脂が常に多い状態です。
特に男性ホルモンの影響で皮脂分泌が活発になりやすい男性は、女性に比べてヘアキャストができやすい傾向があるといえます。
また、思春期などホルモンバランスが変化しやすい時期にも見られやすいです。
ヘアケア製品を多用する人
髪のダメージケアのためにトリートメントやヘアオイルを頭皮近くまでしっかりつけたり、セットのためにスタイリング剤を毎日多量に使用したりする人も注意が必要です。
使用量が多いほど、洗い残しが発生するリスクも高まります。ヘアケア製品が頭皮に残らないよう、適切な使用と丁寧な洗浄が重要です。
ヘアキャストリスクのセルフチェック
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| シャンプーのすすぎは1分未満だ | ||
| コンディショナーを頭皮からつけている | ||
| スタイリング剤を毎日使うが、夜は面倒で洗髪しないことがある | ||
| 頭皮がベタつきやすいと感じる | ||
| 髪を乾かさずに寝ることが多い |
「はい」が多いほど、ヘアキャストが発生しやすい生活習慣である可能性が高まります。
頭皮トラブルを抱えている人
すでに脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)や乾癬(かんせん)など、頭皮の炎症やターンオーバーの異常を伴う皮膚疾患がある場合、角質や皮脂の状態が通常と異なるため、ヘアキャストが発生しやすくなることがあります。
これらの場合は、ヘアキャストの対処と同時に、根本的な皮膚疾患の管理が重要です。
ヘアキャストの正しい取り方と対処法
ヘアキャストを見つけたとき、無理やり取ろうとすると髪や頭皮を傷める原因になります。
ここでは、頭皮に優しく、安全にヘアキャストを取り除く方法と、その後の対処法について解説します。
無理に引き抜くのはNG
ヘアキャストは髪に巻き付いているため、気になって爪でカリカリと剥がしたり、無理に引き抜こうとしたりしがちです。
しかし、このような行為は髪のキューティクルを傷つけ、枝毛や切れ毛の原因となります。また、頭皮を傷つけて炎症を引き起こす可能性もあるため、絶対にやめましょう。
正しいシャンプー方法での洗浄
ヘアキャストは、基本的には日々の正しいシャンプーで徐々に取り除くことができます。重要なのは「予洗い」と「すすぎ」です。
まず、シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度程度が目安)で1〜2分かけて頭皮と髪をしっかり予洗いします。これだけで汚れの多くは落ちます。
次に、シャンプーを手のひらでよく泡立て、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててはいけません。
最後に、洗うとき以上に時間をかけて、シャンプー剤が頭皮や髪の根元に残らないよう、徹底的にすすぎます。
正しいシャンプーの手順(ヘアキャスト対策)
| 手順 | ポイント | 目的 |
|---|---|---|
| ブラッシング | 乾いた状態で、毛先から優しくとかす | ほこり除去、お湯の浸透促進 |
| 予洗い | ぬるま湯で1〜2分、頭皮までしっかり濡らす | 汚れの約7割を除去、泡立ち促進 |
| シャンプー | 手のひらで泡立て、指の腹で頭皮を洗う | 頭皮の皮脂や汚れを落とす |
| すすぎ | シャンプーの倍の時間をかけ、根元から徹底的に | ヘアキャスト原因の除去(最重要) |
オイルを使った除去方法
シャンプーだけではなかなか取れない頑固なヘアキャストには、オイルを使った方法を試してみるのもよいでしょう。
ヘアキャストは皮脂や角質が固まったものであるため、油分で柔らかくすることで取れやすくなります。
シャンプー前の乾いた頭皮と髪に、オリーブオイル、ホホバオイル、または市販の頭皮クレンジングオイルなどをヘアキャストが付着している部分になじませます。
指の腹で優しくマッサージし、オイルを浸透させます。その後、蒸しタオルなどで頭を包み、10〜15分ほど置いてから、通常のシャンプー(できれば2度洗い)を丁寧に行います。
オイルが残らないよう、すすぎは念入りにしてください。
オイルクレンジングに必要なもの
- 頭皮用クレンジングオイル(またはオリーブオイル等)
- 蒸しタオル(またはシャワーキャップ)
ブラッシングでの物理的な除去
シャンプーやオイルケアでヘアキャストが柔らかくなった後、目の細かいコーム(櫛)やブラシを使って、根元から毛先に向かって優しく梳かすことで、物理的に取り除く方法もあります。
ただし、この際も無理に引っ張らず、髪が絡まないように注意深く行う必要があります。
濡れた髪は傷みやすいため、タオルドライの後、ドライヤーで乾かしながら行うか、完全に乾かしてから行うのがよいでしょう。
ヘアキャストを防ぐための頭皮ケア
ヘアキャストは一度取り除いても、原因となる頭皮環境やヘアケア習慣が変わらなければ再発しやすいものです。健やかな頭皮を保ち、ヘアキャストを防ぐための予防策を日常生活に取り入れましょう。
毎日の正しい洗髪とすすぎの徹底
予防において最も重要なのは、やはり「すすぎ残し」を防ぐことです。これがヘアキャストの最大の原因(シャンプー残し)であることが多いためです。
毎日洗髪する場合でも、雑になってはいけません。特にコンディショナーやトリートメントは頭皮を避け、髪にのみ塗布し、ヌルつきが完全になくなるまでしっかりとすすぐ習慣をつけましょう。
シャワーヘッドを頭皮に近づけ、髪の根元や耳の後ろ、襟足なども意識して洗い流すことが大切です。
頭皮に合ったシャンプー選び
自分の頭皮タイプに合わないシャンプーを使い続けることも、頭皮環境を乱す原因となります。
皮脂が多いと感じる人は、余分な皮脂を適度に洗浄できるスカルプケア用や脂性肌用のシャンプーを検討するのもよいでしょう。
逆に、洗浄力が強すぎて頭皮が乾燥すると、バリア機能が低下し、かえって皮脂が過剰に分泌されたり、角質が剥がれやすくなったりすることもあります。
自分の頭皮の状態を見極め、適切な洗浄力のものを選ぶことが重要です。
頭皮タイプ別シャンプー選びの視点
| 頭皮タイプ | 特徴 | シャンプー選びのポイント |
|---|---|---|
| 脂性肌 | ベタつきやすい、日中も皮脂が気になる | 皮脂をしっかり洗浄できるタイプ (スカルプケア用など) |
| 乾燥肌 | カサつきやすい、かゆみが出やすい | 洗浄力がマイルドなアミノ酸系、保湿成分配合タイプ |
| 敏感肌 | 刺激を感じやすい、赤みが出やすい | 低刺激性、無添加、アレルギーテスト済みなど |
頭皮の保湿と生活習慣の見直し
洗髪後は、頭皮も肌と同じように保湿ケアをすることが、乾燥や過剰な皮脂分泌を防ぐ上で役立ちます。頭皮用のローションやエッセンスを使い、潤いを保ちましょう。
また、頭皮環境は体内の状態を反映します。脂っこい食事や糖分の多い食事を控え、ビタミンやミネラルを豊富に含む野菜や魚などをバランス良く摂る食生活を心がけましょう。十分な睡眠時間を確保し、ストレスを溜めないようにすることも、健やかな頭皮のターンオーバーを支えるために必要です。
ヘアケア製品の使用量と洗い残しへの注意
スタイリング剤やトリートメントは、適切な量を守り、頭皮に極力付着させないように注意して使用します。
特にスタイリング剤を使用した日は、その日のうちに必ずシャンプーでリセットし、残留物が蓄積しないようにしましょう。
ヘアキャストが改善しない場合の相談先
セルフケアを続けてもヘアキャストが減らない、またはかゆみや赤みなど他の症状が出てきた場合は、自己判断を続けずに専門家に相談することが賢明です。
症状が続く場合は皮膚科へ
ヘアキャストが頻繁に再発する、量が多い、あるいは頭皮に強いかゆみ、フケ、赤み、湿疹などを伴う場合は、皮膚科専門医を受診しましょう。
ヘアキャストだと思っていたものが、実は脂漏性皮膚炎や頭部乾癬(かんせん)、白癬(はくせん:水虫菌の一種)など、治療が必要な皮膚疾患の症状の一部である可能性も否定できません。
皮膚科受診を推奨する症状
- セルフケア(特にすすぎの徹底)を2週間続けても改善しない
- 強いかゆみや痛みを伴う
- 頭皮が赤く炎症を起こしている、またはジクジクしている
皮膚科で受ける検査や診断
皮膚科では、医師が視診や触診で頭皮や髪の状態を詳しく確認します。ヘアキャストと他の疾患(フケ、しらみの卵、皮膚炎など)とを鑑別診断します。
場合によっては、ヘアキャストの一部や頭皮の角質を採取し、顕微鏡で検査(真菌がいないかなど)を行うこともあります。
これにより、ヘアキャストの原因となっている根本的な頭皮の状態や、隠れた皮膚疾患の有無を明らかにします。
自己判断のリスクと専門家によるケアの重要性
ヘアキャストと自己判断し、実際はしらみであった場合、放置すると家族や周囲の人にうつしてしまうリスクがあります。
また、脂漏性皮膚炎などを放置すれば、症状が悪化し、抜け毛の原因につながる可能性もあります。
ヘアキャスト自体は深刻な病気ではありませんが、「頭皮環境が乱れているサイン」として受け止めることが重要です。
原因(シャンプー残しなど)を正しく特定し、適切なケアを行うために、改善が見られない場合は早めに専門家の診断を仰ぎましょう。
ヘアキャストに関するよくある質問
- ヘアキャストは自然に治りますか?
-
ヘアキャストは、その原因となっているヘアケア習慣や頭皮環境が改善されれば、自然と発生しなくなります。
特に「シャンプー残し」が原因(ヘア キャスト 原因)である場合、日々のすすぎを徹底するだけで、数週間程度で目立たなくなることが多いです。
ただし、原因が解消されない限り、再発を繰り返す可能性があります。
- ヘアキャストは抜け毛の原因になりますか?
-
ヘアキャストそのものが、直接的に髪を抜けさせる原因とはなりません。
しかし、ヘアキャストが発生するような頭皮環境(皮脂の過剰分泌、シャンプー残しによる毛穴周りの不衛生な状態)が続くと、毛穴が詰まったり、頭皮が炎症を起こしたりする可能性があります。
そうした劣悪な頭皮環境が、間接的に髪の健やかな成長を妨げ、抜け毛や薄毛のリスクを高めることは考えられます。
- 子供にもヘアキャストはできますか?
-
はい、子供にもヘアキャストはできます。特に、自分でシャンプーをするようになり、すすぎがまだ上手にできていない学童期のお子さんに見られることがあります。
また、皮脂分泌が活発になる思春期にも発生しやすくなります。
子供の髪にヘアキャストを見つけた場合も、まずはフケやしらみの卵でないかを確認し、シャンプーのすすぎがしっかりできているかを見直してあげることが大切です。
- ヘアキャストに市販薬は効きますか?
-
ヘアキャスト自体は病気ではないため、「ヘアキャストを溶かす薬」というものはありません。
ただし、ヘアキャストの原因として脂漏性皮膚炎などが関与している場合、炎症やかゆみを抑える市販の頭皮用ローション(非ステロイド性など)が症状緩和に役立つことはあります。
しかし、まずは原因の除去(すすぎの徹底や正しい洗髪)が最優先です。
フケ・かゆみ用の薬用シャンプー(抗真菌成分配合など)が、皮脂環境を整える上で間接的に有効な場合もありますが、自己判断が難しい場合は皮膚科に相談することをお勧めします。
フケの原因と対策に戻る
Reference
TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
TRÜEB, Ralph M.; GAVAZZONI DIAS, Maria Fernanda Reis. Fungal diseases of the hair and scalp. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 151-195.
KINGSLEY, Philip. The Hair Bible: A Complete Guide to Health and Care. Aurum, 2014.
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.
GEISLER, Amaris N., et al. Updates on disorders in curly hair. International Journal of Dermatology, 2024, 63.9: 1145-1154.