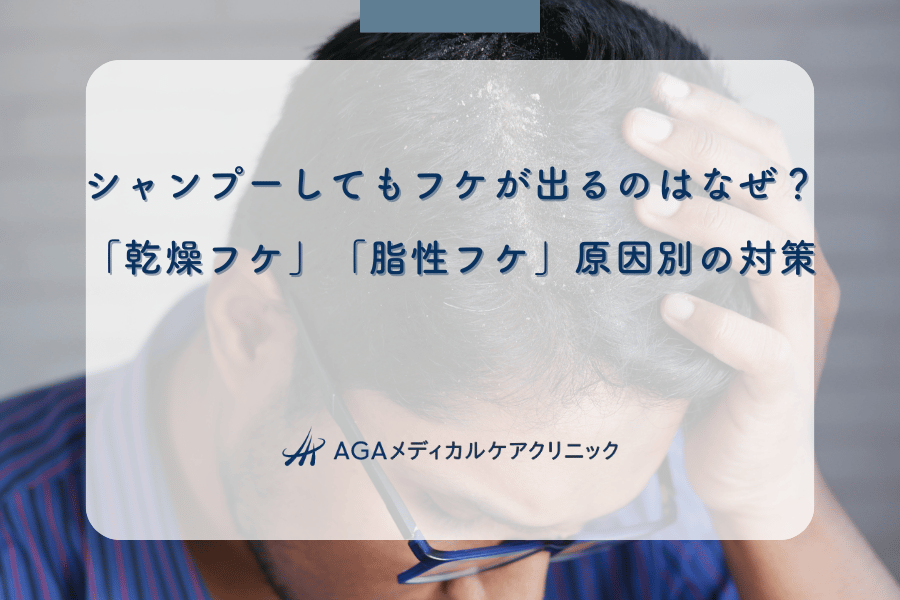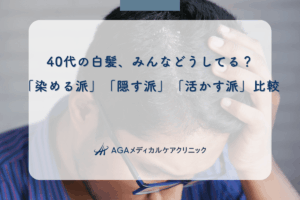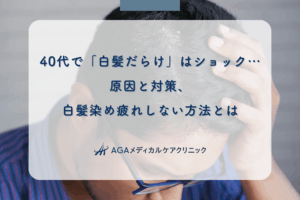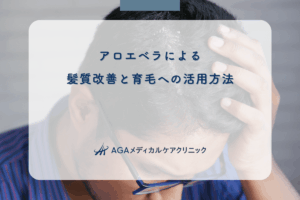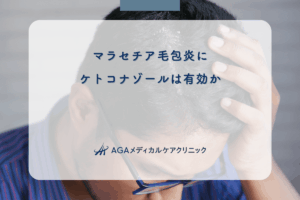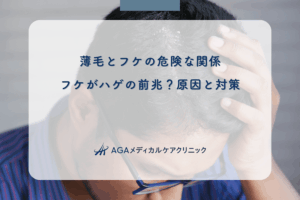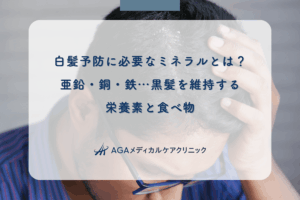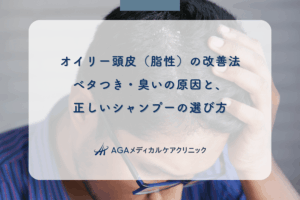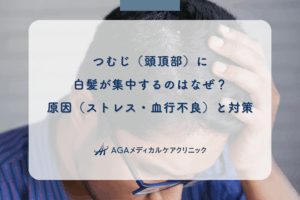毎日しっかりシャンプーをしているのに、肩に落ちるフケや頭皮のベタつきが気になる。そんな悩みを抱えていませんか?フケは不潔にしているから出る、というわけではありません。
実は、フケには「乾燥フケ」と「脂性フケ」の2種類があり、それぞれ原因が異なります。
自分のフケがどちらのタイプなのかを理解し、その原因に合った正しい対策を行うことが、フケ改善への近道です。
この記事では、シャンプーしてもフケが出る理由と、タイプ別の具体的な対策を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
フケの正体とは?まずは基本を知ろう
フケと聞くと、すぐに「不潔」というイメージを持つかもしれませんが、それは誤解です。フケの正体を知ることは、適切なケアへの第一歩となります。
フケは頭皮のターンオーバーの証拠
私たちの皮膚が新陳代謝によって生まれ変わるように、頭皮も「ターンオーバー」を繰り返しています。頭皮の一番外側にある「角質細胞」が役目を終えると、アカとなって剥がれ落ちます。
これがフケの正体です。つまり、フケが出ること自体は、誰にでも起こる正常な生理現象なのです。
目に見えるフケが問題
通常、健康な頭皮から出るフケは非常に小さく、肉眼ではほとんど見えません。シャンプーや日常生活の中で自然に洗い流されたり、剥がれ落ちたりしています。
しかし、何らかの原因で頭皮のターンオーバーが異常に早まったり、頭皮環境が悪化したりすると、角質細胞が未熟なまま、あるいは大きな塊となって剥がれ落ちるようになります。
これが、私たちが「フケが出ている」と認識する、目に見えるフケです。
フケの種類を見極めることが第一歩
目立つフケには、大きく分けて「乾燥フケ」と「脂性フケ」の2種類が存在します。これらは見た目や性質だけでなく、発生する原因が全く異なります。
そのため、フケ対策を行う上で、自分のフケがどちらのタイプなのかを正確に見極めることが非常に重要です。間違ったケアは、かえって症状を悪化させる可能性もあります。
頭皮環境のバロメーターとしてのフケ
目に見えるフケが多い状態は、頭皮が「助けて」とサインを出している状態とも言えます。乾燥しすぎているのか、それとも皮脂が多すぎるのか。
フケの状態は、現在の頭皮環境がどうなっているかを示すバロメーターの役割を果たします。
フケを単なる厄介者として扱うのではなく、頭皮からのメッセージとして受け止め、根本的な原因を探ることが大切です。
あなたのフケはどっち?「乾燥フケ」と「脂性フケ」の見分け方
フケ対策の基本は、自分のフケタイプを知ることから始まります。あなたのフケはカサカサしていますか?それともベタベタしていますか?特徴を比べてみましょう。
「乾燥フケ」の特徴
乾燥フケは、その名の通り頭皮の乾燥が主な原因で発生します。特徴は、カサカサとしていて、白く細かい粉状であることが多いです。
非常に軽いため、髪をかき上げたり、少し頭を動かしたりするだけでパラパラと肩や服に落ちやすいです。頭皮自体も乾燥してつっぱる感じがしたり、かゆみを伴ったりすることがあります。
「脂性フケ」の特徴
脂性フケは、頭皮の皮脂が過剰に分泌されることが主な原因です。特徴は、ベタベタとして湿り気があり、黄色っぽい色をしていることが多いです。
乾燥フケと比べてフケのサイズが大きく、塊になりやすい傾向があります。皮脂と混じり合っているため頭皮や髪の根元に張り付きやすく、簡単には落ちません。
頭皮のベタつきや、皮脂が酸化したようなニオイを伴うこともあります。
自分のフケタイプをチェック
自分のフケがどちらのタイプか判断がつかない場合は、ティッシュペーパーや黒い紙を使ってチェックしてみましょう。シャンプー前に、指の腹で頭皮を優しくこすり、落ちてきたフケを観察します。
パラパラと細かく白いものが多ければ乾燥フケ、ベタッとした塊や黄色っぽいものが多ければ脂性フケの可能性が高いです。
また、フケだけでなく、普段の頭皮の状態(乾燥しやすいか、ベタつきやすいか)も合わせて判断材料にしましょう。
フケタイプ簡易チェック
| チェック項目 | 乾燥フケ | 脂性フケ |
|---|---|---|
| フケの形状 | カサカサ、パラパラ、細かい粉状 | ベタベタ、湿っぽい、大きな塊 |
| フケの色 | 白い | 白〜黄色っぽい |
| 頭皮の状態 | 乾燥している、つっぱる感じがする | ベタついている、脂っぽい |
| 発生場所 | 頭全体、特に乾燥しやすい部分 | 頭皮に張り付く、髪の根元 |
混合タイプの可能性
中には、乾燥フケと脂性フケの両方の特徴を持つ「混合タイプ」の人もいます。例えば、頭皮全体は乾燥しているのに、Tゾーンや生え際だけベタつくといったケースです。
また、季節によってフケのタイプが変わることもあります。自分の状態をよく観察し、どちらの傾向が強いかを見極めることが必要です。
「乾燥フケ」が発生する主な原因
パラパラと落ちる乾燥フケ。その背景には、頭皮の水分と油分のバランスが崩れ、バリア機能が低下している状態があります。主な原因を見ていきましょう。
シャンプーのしすぎ・洗浄力が強すぎる
フケを気にするあまり、1日に何度もシャンプーをしたり、洗浄力の非常に強いシャンプー(例:高級アルコール系など)を必要以上に使ったりすると、頭皮を守るために必要な皮脂まで根こそぎ洗い流してしまいます。
皮脂が不足すると、頭皮の水分が蒸発しやすくなり、乾燥を招きます。これが乾燥フケの大きな原因の一つです。
間違ったヘアケア
日々のケア方法も頭皮の乾燥に影響します。例えば、42℃を超えるような熱すぎるお湯でのシャンプーは、必要な皮脂を奪いやすくなります。
また、シャンプー後のドライヤーを長時間、頭皮に近づけすぎると、熱によって頭皮の水分が奪われて乾燥します。逆に、自然乾燥は頭皮に雑菌が繁殖しやすい環境を作るため、フケの原因となり得ます。
空気の乾燥(季節や室内環境)
外的な環境要因も無視できません。特に空気が乾燥する冬場は、肌がカサカサするのと同じように、頭皮も乾燥しやすくなります。
また、季節に関わらず、エアコンの効いた部屋に長時間いると、室内の湿度が下がり、頭皮の水分が奪われて乾燥フケが発生しやすくなります。
生活習慣の乱れ
不規則な生活や栄養バランスの偏りも、頭皮の健康に影響します。特に睡眠不足は、肌のターンオーバーを促進する成長ホルモンの分泌を妨げます。
また、ビタミンAやビタミンB群など、皮膚の健康維持に必要な栄養素が不足すると、頭皮のバリア機能が低下し、乾燥しやすくなります。
「脂性フケ」が発生する主な原因
ベタベタとした脂性フケは、皮脂の過剰分泌が引き金となっています。なぜ皮脂が多くなりすぎるのか、その原因を探ります。
皮脂の過剰分泌
脂性フケの根本には、皮脂腺からの皮脂分泌が過剰になる状態があります。これは、体質(脂性肌)や、ホルモンバランスの影響が大きいです。
特に男性ホルモン(テストステロン)は皮脂腺の働きを活発にする作用があり、女性よりも男性の方が皮脂分泌が多くなりがちです。
思春期やストレスなどでホルモンバランスが乱れると、皮脂分泌がコントロールできなくなることがあります。
マラセチア菌の増殖
私たちの頭皮には、「マラセチア菌」という常在菌(カビの一種)が存在します。この菌は皮脂をエサにして生きており、通常は特に問題を起こしません。
しかし、何らかの原因で皮脂が過剰に分泌されると、マラセチア菌がそれをエサにして異常増殖します。
増殖したマラセチア菌は、皮脂を分解する際に頭皮を刺激する物質を作り出し、その結果、頭皮のターンオーバーが異常に早まり、ベタベタとした脂性フケが大量に発生します。
マラセチア菌と脂性フケ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| マラセチア菌とは | 頭皮に誰もが持っている常在菌(カビの一種) |
| 菌のエサ | 頭皮の皮脂 |
| 増殖のきっかけ | 過剰な皮脂分泌、高温多湿な環境、不十分な洗浄 |
| フケへの影響 | 菌が皮脂を分解する際の刺激でターンオーバーが異常に早まり、脂性フケが増加 |
食生活の乱れ
毎日の食事が皮脂分泌に直結していることもあります。脂っこい揚げ物やジャンクフード、動物性脂肪の多い肉類などを過剰に摂取すると、皮脂の原料となる中性脂肪が増加し、皮脂分泌が促進されます。
また、糖分の多いお菓子や清涼飲料水、アルコールの過剰摂取も、皮脂の分泌を増やす原因となります。
ストレスや生活習慣の乱れ
過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こします。これにより、皮脂分泌をコントロールする働きが低下し、皮脂が過剰に出やすくなります。
また、睡眠不足や不規則な生活も同様にホルモンバランスに影響を与え、脂性フケを悪化させる要因となります。
フケタイプ別の主な原因まとめ
| フケタイプ | 主な原因 | キーワード |
|---|---|---|
| 乾燥フケ | 頭皮の皮脂不足、バリア機能の低下 | 洗浄のしすぎ、空気の乾燥、血行不良 |
| 脂性フケ | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖 | ホルモンバランス、脂っこい食事、ストレス |
今すぐ見直そう!フケ対策の基本となるシャンプー方法
シャンプーしてもフケが出るからといって、シャンプーをやめるわけにはいきません。フケ対策の鍵は、シャンプーの「選び方」と「やり方」にあります。
自分のタイプに合った正しいシャンプー方法を身につけましょう。
正しいシャンプー選び
フケ対策は、自分のフケタイプに合ったシャンプーを選ぶことから始まります。洗浄力が強すぎても弱すぎても、フケの原因となります。
フケタイプ別シャンプー選びのポイント
| フケタイプ | シャンプー選びのポイント | 注目成分の例 |
|---|---|---|
| 乾燥フケ | 洗浄力がマイルドで、保湿成分が配合されているもの。 | アミノ酸系洗浄成分、ベタイン系洗浄成分、セラミド、ヒアルロン酸 |
| 脂性フケ | 適度な洗浄力があり、余分な皮脂や汚れをしっかり落とせるもの。抗真菌(抗カビ)成分配合のものも有効。 | 高級アルコール系洗浄成分(適度に使用)、ミコナゾール硝酸塩、ピロクトンオラミン |
シャンプー前の準備
シャンプーの効果を最大限に高めるため、洗う前の準備も重要です。まず、乾いた髪の状態でブラッシングをします。これにより、髪の絡まりをほどき、ホコリや頭皮の汚れを浮かび上がらせることができます。
その後、38℃程度のぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと予洗いします。この予洗いだけで、髪の汚れの多くは落ちると言われています。
シャンプーの正しい手順
シャンプー剤は、直接頭皮につけるのではなく、まず手のひらでよく泡立てます。泡立てるのが苦手な場合は、泡で出るタイプのシャンプーや、洗顔用の泡立てネットを使うのも良い方法です。
泡立てたシャンプーを髪全体になじませたら、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。この時、絶対に爪を立ててはいけません。
爪を立てると頭皮が傷つき、そこから炎症を起こしたり、乾燥フケの原因になったりします。
シャンプー時の注意点
| NG行動 | 理由 | 正しい方法 |
|---|---|---|
| 爪を立てて洗う | 頭皮を傷つけ、バリア機能を低下させる | 指の腹でマッサージするように洗う |
| ゴシゴシと強くこする | 摩擦が刺激となり、必要な皮脂まで奪う | 泡の力で汚れを浮かせるイメージで優しく洗う |
| 熱すぎるお湯ですすぐ | 皮脂を取りすぎ、頭皮の乾燥を招く | 38℃前後のぬるま湯でしっかりすすぐ |
すすぎは「これでもか」というほど念入りに
シャンプーで最も重要なのは「すすぎ」と言っても過言ではありません。
シャンプー剤やコンディショナーの成分が頭皮に残っていると、それが毛穴を詰まらせたり、頭皮を刺激したりして、フケやかゆみの原因となります。
特に、生え際、耳の後ろ、襟足などはすすぎ残しが多い部分です。洗う時にかけた時間の2倍以上の時間をかけるつもりで、ぬるま湯で念入りに洗い流しましょう。
シャンプー以外の日常生活でできるフケ対策
フケの改善には、シャンプー方法の見直しと並行して、日々の生活習慣を整えることが非常に重要です。頭皮も体の一部であり、体の内側からのケアが頭皮環境に反映されます。
頭皮の保湿ケア
特に乾燥フケに悩む人は、顔のスキンケアと同様に、頭皮の保湿を意識しましょう。
シャンプー後、髪を乾かした後に、頭皮専用のローションや保湿剤を使用することで、乾燥を防ぎ、バリア機能をサポートします。
アルコール(エタノール)の配合が多いものは、かえって乾燥を招くことがあるため、敏感な場合は成分表示を確認しましょう。
食生活の改善
健康な頭皮環境は、バランスの取れた食事から作られます。特に意識して摂取したいのは、皮膚や粘膜の健康を保ち、皮脂の分泌をコントロールする働きがあるビタミンB群(B2、B6など)です。
また、抗酸化作用があり、頭皮の血行を促進するビタミンE、髪の毛の主成分であるタンパク質も重要です。 一方で、脂性フケに悩む人は、以下のような皮脂分泌を促進する食品を控えることも大切です。
- 脂質の多い揚げ物やスナック菓子
- 糖分の多いお菓子やジュース
- 刺激の強い香辛料やアルコール類
頭皮環境をサポートする栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 (B2, B6) | 皮脂分泌のコントロール、皮膚の新陳代謝をサポート | レバー、うなぎ、納豆、マグロ、カツオ、バナナ |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康維持、頭皮の乾燥を防ぐ | 緑黄色野菜(ニンジン、カボチャ)、レバー、うなぎ |
| タンパク質 | 髪の毛や皮膚の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
質の良い睡眠
睡眠中は、細胞の修復や再生を促す「成長ホルモン」が最も多く分泌される時間帯です。
特に、入眠から最初の3時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、この時間に質の良い深い眠りを得ることが、頭皮のターンオーバーを正常化するために必要です。
睡眠不足はターンオーバーのサイクルを乱し、フケの発生につながります。
ストレス管理
現代社会においてストレスをゼロにすることは難しいですが、溜め込まない工夫が大切です。ストレスは自律神経のバランスを崩し、血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こします。
これらは皮脂の過剰分泌(脂性フケ)や、頭皮への栄養不足(乾燥フケ)の両方の原因となります。
趣味の時間を楽しむ、適度な運動で汗を流す、ゆっくりと入浴するなど、自分なりのリラックス方法を見つけて実践しましょう。
それでもフケが改善しない場合は?
セルフケアを丁寧に行っても、フケが一向に良くならない、あるいは悪化する。そんな時は、別の原因が隠れているかもしれません。
シャンプーやケア方法の再点検
まずは、もう一度、自分のケア方法がフケのタイプに合っているかを確認しましょう。
「乾燥フケ」だと思って保湿ケアを頑張っていたら、実は「脂性フケ」で、保湿成分がマラセチア菌のエサになっていた、という逆のケースもあります。
シャンプーの選び方、洗い方、すすぎ方、生活習慣など、基本に立ち返って見直してみましょう。
生活習慣の見直しを継続する
食生活や睡眠の改善といった体質改善は、すぐに結果が出るものではありません。
頭皮のターンオーバーの周期(約28日〜40日)を考慮すると、効果を実感するまでには最低でも1ヶ月以上、継続することが重要です。数日で諦めず、根気強くケアを続けましょう。
脂漏性皮膚炎などの可能性
フケ対策をしても改善しない場合、それは単なるフケではなく、「脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)」という皮膚の病気かもしれません。
脂漏性皮膚炎は、脂性フケの原因であるマラセチア菌が関与し、頭皮に炎症が起きた状態です。フケに加えて、以下のような症状がある場合は注意が必要です。
- 我慢できないほどの強いかゆみ
- 頭皮の赤み、ただれ
- フケが黄色く、ジュクジュクしている
この他にも、頭皮が銀白色のフケで厚く覆われる「乾癬(かんせん)」や、「アトピー性皮膚炎」など、フケと似た症状を示す他の皮膚疾患の可能性もあります。
セルフケアで改善しない場合のサイン
| 項目 | 単なるフケ | 脂漏性皮膚炎などの疑い |
|---|---|---|
| かゆみ | 軽度、または時々かゆい程度 | 我慢できないほど強い、持続的 |
| 頭皮の色 | ほぼ正常、または乾燥・ベタつき | 赤みを帯びている、炎症を起こしている |
| フケの状態 | パラパラ(乾燥)またはベタベタ(脂性) | 黄色くジュクジュクしている、厚いかさぶた状 |
| セルフケア | 適切なケアで改善傾向が見られる | ケアをしても改善しない、または悪化する |
専門医(皮膚科)への相談
上記のような症状が見られる場合や、セルフケアを1ヶ月以上続けてもフケが全く改善しない場合は、自己判断を続けずに専門医である皮膚科を受診しましょう。
脂漏性皮膚炎などの場合は、炎症を抑える薬や、マラセチア菌を抑える抗真菌薬の処方が必要となります。専門家による正確な診断と治療を受けることが、早期改善への一番の近道です。
Q&A
フケに関するよくある質問にお答えします。
- フケは他人にうつりますか?
-
フケそのものが、人から人へとうつることはありません。肩にフケが落ちたからといって、それが他人の頭皮でフケの原因になることはありませんので安心してください。
ただし、脂性フケの原因の一つであるマラセチア菌は誰もが持っている常在菌であり、感染症ではありません。
- 育毛剤や発毛剤はフケに影響しますか?
-
使用する製品によります。育毛剤や発毛剤には、血行促進成分や清涼感を与えるためにアルコール(エタノール)が高濃度で配合されていることがあります。
このアルコールが頭皮の水分を奪い、乾燥フケの原因となることがあります。また、頭皮に炎症やフケがある状態で使用すると、育毛剤の成分が刺激となり、症状を悪化させる可能性もあります。
まずはフケを改善し、頭皮環境を整えてから使用することが望ましいです。
- シャンプーは朝と夜、どちらが良いですか?
-
基本的には、1日の終わりに「夜」シャンプーすることをおすすめします。
日中に付着したホコリ、汗、皮脂などの汚れをその日のうちに洗い流し、頭皮を清潔な状態にしてから就寝することが、頭皮環境を健やかに保つために重要です。
朝シャンは、必要な皮脂まで洗い流してしまい、日中の紫外線のダメージを受けやすくなる可能性もあります。
- フケが出やすい季節はありますか?
-
フケのタイプによって、悪化しやすい季節が異なる傾向があります。「乾燥フケ」は、外気が乾燥し、暖房の使用で室内湿度も下がる秋から冬にかけて悪化しやすいです。
一方、「脂性フケ」は、気温と湿度が上昇し、汗や皮脂の分泌が活発になる春から夏にかけて悪化しやすいと言われています。
- フケを防ぐために市販薬を使っても良いですか?
-
フケやかゆみを抑えることを目的とした市販のシャンプーやローション(医薬部外品や第2類医薬品)を使用することも一つの方法です。
特に脂性フケの場合は、マラセチア菌の増殖を抑える抗真菌成分(ミコナゾール硝酸塩など)や、かゆみや炎症を抑える成分(グリチルリチン酸ジカリウムなど)が配合されたものが有効な場合があります。
ただし、自分のフケタイプに合っているかを確認し、使用上の注意をよく読んでから使いましょう。数週間使用しても改善が見られない場合は、使用を中止し皮膚科に相談してください。
フケの原因と対策に戻る
Reference
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.
SCHWARTZ, James R.; JOHNSON, Eric S.; DAWSON, Thomas L. Shampoos for normal scalp hygiene and dandruff. Cosmetic Dermatology: Products and Procedures, 2022, 165-174.
KERR, Kathy, et al. Epidermal changes associated with symptomatic resolution of dandruff: biomarkers of scalp health. International journal of dermatology, 2011, 50.1: 102-113.
NEWTON‐FENNER, A., et al. Clear scalp, clear mind: Examining the beneficial impact of dandruff reduction on physical, emotional and social wellbeing. International journal of cosmetic science, 2025, 47.3: 466-475.
TRÜEB, Ralph M., et al. Scal
p condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
SCHWARTZ, J. R., et al. The role of oxidative damage in poor scalp health: ramifications to causality and associated hair growth. International Journal of Cosmetic Science, 2015, 37: 9-15.
NARSHANA, M., et al. An overview of dandruff and novel formulations as a treatment strategy. Int J Pharm Sci Res, 2018, 9.2: 417-431.
TRÜEB, Ralph M. Shampoos: ingredients, efficacy and adverse effects. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2007, 5.5: 356-365.
KUMARI, KM U.; YADAV, Narayan Prasad; LUQMAN, Suaib. Promising essential oils/plant extracts in the prevention and treatment of dandruff pathogenesis. Current topics in medicinal chemistry, 2022, 22.13: 1104-1133.