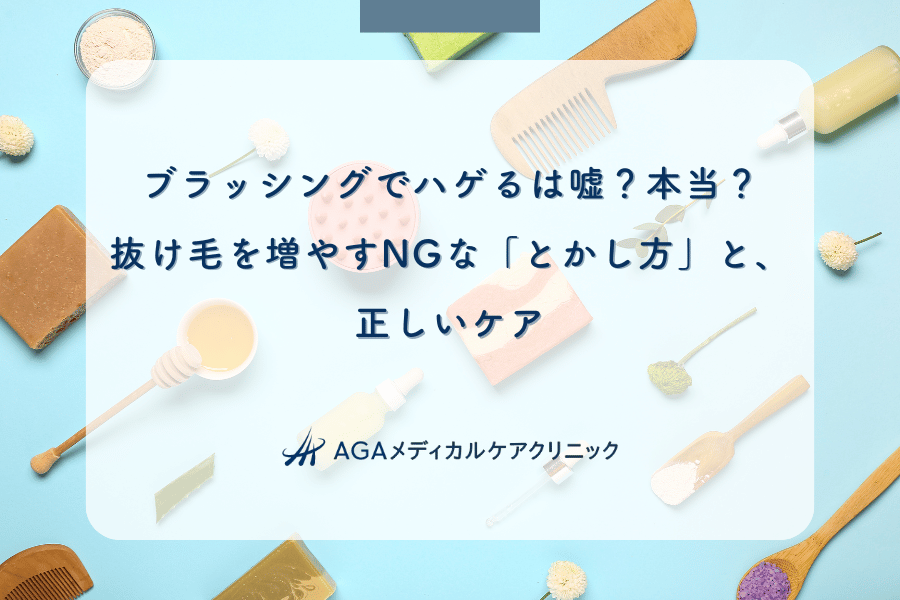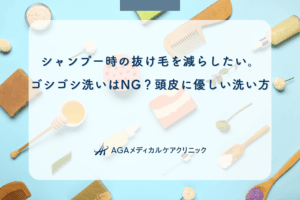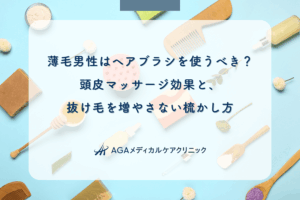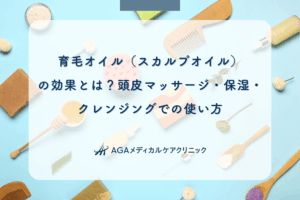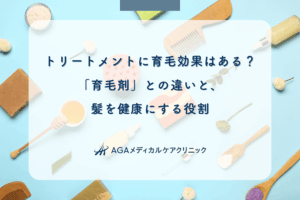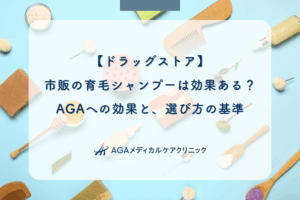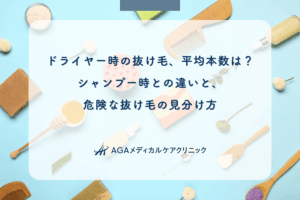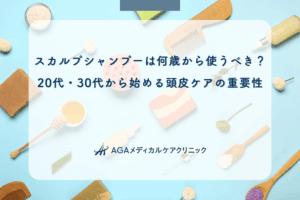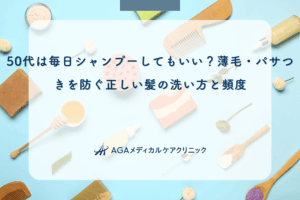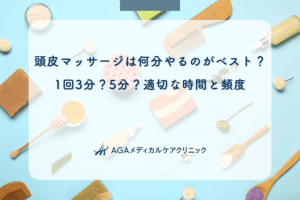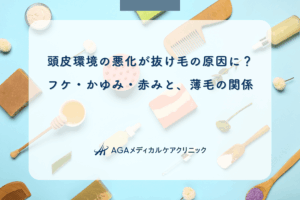ブラッシングするたびにブラシに絡まる抜け毛を見て、「このままブラッシングを続けたらハゲるのではないか」と不安に感じている男性は少なくないでしょう。その不安、本当に正しいのでしょうか。
実は、ブラッシングが直接的なハゲる原因になるというのは、多くの場合誤解かもしれません。
この記事では、ブラッシングと抜け毛の本当の関係性、そして知らず知らずのうちに頭皮や髪にダメージを与えているかもしれないNGな「とかし方」を詳しく解説します。
さらに、健やかな頭皮環境を守るための正しいブラッシング方法と、日常で取り入れたいケアについても紹介します。
この記事を読めば、ブラッシングに対する不安が解消され、毎日の習慣を効果的な頭皮ケアの時間へと変える知識が身につくはずです。正しいケアで、自信の持てる髪を目指しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「ブラッシングでハゲる」は本当?噂の真相
多くの男性が抱く「ブラッシングするとハゲる」という不安。しかし、この噂は本当なのでしょうか。結論から言えば、正しい方法で行うブラッシングが、薄毛やハゲる直接的な原因になることはありません。
むしろ、適切なブラッシングは頭皮環境にとって多くの良い影響をもたらします。このセクションでは、ブラッシングと抜け毛に関する誤解と真実を解き明かしていきます。
ブラッシングで抜け毛が増える感覚の正体
ブラッシングをした後に、ブラシに多くの髪の毛がついていて驚いた経験はありませんか。これを見て「ブラッシングが抜け毛を増やしている」と感じてしまうのも無理はありません。
しかし、その抜け毛の多くは、すでにヘアサイクル(毛周期)を終え、自然に抜け落ちる段階にあった髪の毛です。
髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、休止期に入った髪は数ヶ月で自然に抜け落ちます。
ブラッシングは、そのタイミングでたまたま頭皮に残っていた「抜けるべき髪」を集め、可視化しているにすぎません。
健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けており、ブラッシングによってそれらがまとめて取り除かれるため、多く抜けたように感じてしまうのです。
結論:正しいブラッシングはハゲる原因にならない
前述の通り、ヘアサイクルを終えた髪が抜けるのは自然な現象です。適切な力加減と方法で行うブラッシングが、健康な「成長期」の髪を無理やり引き抜き、薄毛を進行させることは考えにくいです。
もしブラッシングで健康な髪まで抜けてしまうとすれば、それはブラッシングの方法が間違っているか、あるいは頭皮や髪自体に何らかの問題がある可能性が高いです。
正しいブラッシングは、髪の絡まりをほぐし、頭皮環境を整えるための重要なケアの一つです。ハゲることを恐れてブラッシングを避けることは、むしろ逆効果になる可能性すらあります。
むしろブラッシングは頭皮に良い影響も
正しいブラッシングは、薄毛の原因になるどころか、健やかな頭皮環境を維持するために多くのメリットをもたらします。
まず、ブラシが頭皮に適度な刺激を与えることで、頭皮の血行が良くなることが期待できます。血行が良くなれば、髪の成長に必要な栄養素が毛根に行き渡りやすくなります。
また、ブラッシングによって髪についたホコリや汚れ、古い角質などを浮き上がらせることができます。これにより、シャンプー時の泡立ちや洗浄効果が高まります。
さらに、頭皮の皮脂腺から分泌された皮脂を、ブラシを使って髪全体に行き渡らせることで、髪に自然なツヤを与え、乾燥から守る役割も果たします。
抜け毛が目立つ場合に考えられる他の原因
ブラッシングのせいだと思っていた抜け毛が、実は別の要因によって引き起こされている可能性もあります。
もし、自然な抜け毛の範囲(1日100本程度)を明らかに超えている、あるいは特定の部位だけが薄くなってきたと感じる場合は、他の原因を疑う必要があります。
特に男性の場合、AGA(男性型脱毛症)が進行している可能性が考えられます。
その他にも、過度なストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、喫煙などの生活習慣の乱れも、頭皮環境を悪化させ、抜け毛を増やす要因となります。
抜け毛が目立つ主な原因
| 主な原因 | 概要 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| AGA(男性型脱毛症) | 男性ホルモンの影響でヘアサイクルが乱れ、髪が十分に育つ前に抜けてしまう症状。 | 専門クリニックでの相談、治療薬の使用検討。 |
| 生活習慣の乱れ | 睡眠不足、栄養偏重、運動不足、喫煙など。頭皮の血行不良や栄養不足を招く。 | 生活習慣の見直し、バランスの良い食事、十分な睡眠。 |
| ストレス | 過度な精神的・身体的ストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行を悪化させる。 | リラックスできる時間の確保、趣味、適度な運動。 |
抜け毛を増やすNGなブラッシング方法
正しいブラッシングは頭皮に良い影響を与えますが、一方で間違ったブラッシング方法は、かえって髪や頭皮を傷つけ、抜け毛を助長してしまう危険性があります。
知らず知らずのうちに、大切な髪にダメージを与える「NGなとかし方」をしていないか、日々の習慣を見直してみましょう。ここでは、特に避けるべき代表的なNGブラッシング方法を紹介します。
濡れた髪を無理にとかす
お風呂上がりやシャワーの後、髪が濡れたままの状態でブラッシングするのは非常に危険です。髪の毛は、濡れると表面のキューティクルが開いた状態になります。
キューティクルは髪の内部を守る鎧のようなものですが、開いているときは非常にデリケートで剥がれやすくなっています。
この無防備な状態でブラシを通すと、摩擦によってキューティクルが傷ついたり、剥がれたりしてしまいます。
また、濡れた髪は乾いているときよりも強度が低く、引っ張る力にも弱いため、少しの力でも切れ毛や抜け毛につながりやすいのです。
必ず、タオルドライである程度水分を取り、ドライヤーでしっかり乾かしてからブラッシングするようにしましょう。
力を入れすぎるゴシゴシ洗いならぬ「ゴシゴシとかし」
髪の絡まりを無理やりほどこうとして、力を込めてブラシを動かす「ゴシゴシとかし」は、髪と頭皮の両方に深刻なダメージを与えます。
強い力でブラッシングすると、健康な髪の毛まで無理やり引き抜いてしまう「牽引(けんいん)性脱毛症」の原因になることがあります。
また、ブラシの毛先が頭皮を強くこすることで、頭皮に目に見えない細かな傷がつき、炎症やかゆみを引き起こすこともあります。
髪が絡まっている場合は、まず毛先から優しくほぐし、徐々に根元に向かってとかしていくのが基本です。急いでいるときほど、力任せになりがちなので注意が必要です。
頭皮にブラシを強く押し当てる
頭皮の血行促進を意識するあまり、ブラシを頭皮に強く押し当ててしまうのもNGです。適度な刺激は血行を良くしますが、力が強すぎると頭皮を傷つける原因になります。
「ゴシゴシとかし」と同様に、頭皮に炎症やフケ、かゆみを引き起こす可能性があります。特に、ブラシの先端が尖っているものや、素材が硬すぎるものを使っている場合は注意が必要です。
ブラッシングは「髪をとかす」のが主目的であり、頭皮マッサージは指の腹で行うなど、分けて考えるのが賢明です。ブラシが頭皮に「触れる」程度の優しい力加減を心がけましょう。
汚れたブラシを使い続ける
毎日使うブラシですが、定期的にお手入れをしていますか?ブラシには、抜けた髪の毛だけでなく、ホコリ、皮脂、フケ、整髪料の残りなどが蓄積していきます。
この汚れたブラシを使い続けると、雑菌が繁殖しやすくなります。汚れたブラシでブラッシングすることは、頭皮に雑菌や汚れを再び塗り広げているようなものです。
これにより、頭皮環境が悪化し、毛穴の詰まり、ニオイ、かゆみ、炎症などを引き起こし、結果として抜け毛につながる可能性があります。
ブラシは最低でも月に一度は洗浄するなど、清潔な状態を保つことが重要です。ブラシの素材に合ったお手入れ方法を確認しましょう。
避けるべきNGブラッシング行為
| NG行為 | 髪への影響 | 頭皮への影響 |
|---|---|---|
| 濡れた髪をとかす | キューティクルの損傷、切れ毛 | 特になし(ただし髪が抜けやすい) |
| 力を入れすぎる | 切れ毛、髪の引き抜き | 頭皮の擦り傷、炎症、牽引性脱毛症 |
| 頭皮への強い押し当て | 特になし | 頭皮の傷、炎症、フケ、かゆみ |
| 汚れたブラシの使用 | 汚れの再付着 | 雑菌の繁殖、毛穴詰まり、炎症 |
なぜNGなブラッシングが頭皮に悪いのか
前章で挙げたNGなブラッシング方法は、具体的にどのような害を髪と頭皮にもたらすのでしょうか。単に「痛いからダメ」というだけではありません。
間違った習慣が引き起こすダメージの背景を理解することで、より意識的に正しいケアを実践できるようになります。
ここでは、NGブラッシングがもたらす三つの主な悪影響について解説します。
キューティクルへのダメージ
髪の毛の表面は、うろこ状のキューティクルという組織で覆われています。キューティクルは、髪の内部にある水分やタンパク質を守り、外部の刺激から髪を保護する重要な役割を担っています。
しかし、濡れた状態でのブラッシングや、過度な摩擦を与える「ゴシゴシとかし」によって、このキューティクルは簡単に傷つき、剥がれてしまいます。
キューティクルが損傷すると、髪内部の水分が蒸発しやすくなり、髪は乾燥してパサパサになります。また、外部からのダメージも受けやすくなり、切れ毛や枝毛が非常に増えやすくなります。
一度剥がれたキューティクルは再生しないため、ダメージが蓄積していく一方です。
頭皮の炎症や傷
力を入れすぎたブラッシングや、頭皮への強い押し当ては、デリケートな頭皮の表面を傷つけます。ブラシの硬い毛先が頭皮をひっかき、目には見えない小さな傷を無数につけてしまうのです。
頭皮に傷がつくと、そこから雑菌が侵入しやすくなり、炎症や化膿を引き起こす可能性があります。また、頭皮が傷つくことでバリア機能が低下し、乾燥やかゆみ、フケの過剰な発生につながることもあります。
汚れたブラシを使っている場合は、雑菌を直接傷口に擦り込んでいることになり、さらに状況を悪化させます。頭皮環境の悪化は、健康な髪が育つ土壌を失うことと同義であり、抜け毛や薄毛に直結します。
牽引(けんいん)性脱毛症のリスク
牽引性脱毛症とは、髪の毛が長時間にわたって強く引っ張られ続けることによって、毛根がダメージを受け、髪が抜けてしまう脱毛症のことです。
ポニーテールやきついお団子ヘアなどを長期間続ける女性に多いとされていますが、男性でも間違ったブラッシングによって引き起こされる可能性があります。
特に、髪の絡まりを力ずくでほどこうとすると、毛根に強い負荷がかかります。この負荷が日常的に繰り返されると、毛根が弱り、まだ成長期にあるはずの健康な髪までもが抜け落ちてしまうのです。
さらに、毛根自体がダメージを受けると、新しい髪が生えてこなくなる可能性もあります。優しい力加減でのブラッシングは、牽引性脱毛症を予防するためにも非常に重要です。
ブラッシングの前に確認したいブラシの選び方
正しいブラッシングを行うためには、自分に合ったブラシを選ぶことが不可欠です。ブラシと一口に言っても、その種類、素材、形状は多岐にわたります。
自分の髪質や頭皮の状態、使用する目的に合っていないブラシを使うと、かえって髪や頭皮を傷める原因にもなりかねません。ここでは、健やかな頭皮ケアのためのブラシ選びのポイントを解説します。
目的別ブラシの種類と特徴
ブラシは主に、髪のもつれをほぐしたり、ブローに使ったり、頭皮マッサージを目的としたりするものなどがあります。
それぞれの特徴を理解し、目的に合わせて使い分けるのが理想です。
主なブラシの種類と用途
| ブラシの種類 | 主な特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| クッションブラシ | ブラシの根本がゴムなどの柔らかいクッションになっており、頭皮への当たりが優しい。 | 日常のブラッシング、頭皮マッサージ、ブロー。 |
| デンマンブラシ | ゴム製の台座にナイロンピンなどが並び、髪をしっかり捉える。 | ブロー時のスタイリング、髪のボリューム調整。 |
| スケルトンブラシ | ブラシの目が粗く、すき間が多いため、濡れた髪にも使いやすい(※優しくが前提)。 | シャンプー前のホコリ取り、大まかなもつれ解消。 |
| ロールブラシ | 円筒形で、動物毛やナイロンピンが植えられている。 | ブロー時のカール付け、ストレートヘアのスタイリング。 |
男性が日常的に頭皮ケアも兼ねて使用するなら、頭皮への刺激がマイルドな「クッションブラシ」がおすすめです。
頭皮に優しい素材とは?
ブラシのピン(毛)の素材も重要です。素材によって、頭皮への刺激や静電気の発生しやすさが異なります。
ブラシのピン素材比較
| 素材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 動物毛(豚毛・猪毛) | 髪の油分をなじませツヤを出す。静電気が起きにくい。適度な硬さ。 | 水洗いに弱い。価格が比較的高め。 |
| ナイロン・ポリエチレン | 耐久性が高く、水洗い可能でお手入れが楽。価格が手頃。 | 静電気が起きやすい。先端が硬いと頭皮を傷める可能性。 |
| 木製(竹製など) | 静電気が非常に起きにくい。頭皮への当たりが柔らかい。 | 水に弱く、カビやすい。耐久性がやや低い。 |
頭皮への優しさを最優先するなら、先端が丸く加工されたナイロン製(クッションブラシによく使われる)や、木製・竹製のものが良いでしょう。動物毛も適度な刺激とツヤ出し効果が期待できます。
ブラシの形状と髪質・毛量の相性
ブラシの形状やピンの密度も、使い心地や髪への影響を左右します。
一般的に、髪の毛が多い人や太い人は、ブラシのピンがしっかりしていて、ある程度目が粗いものの方が、髪を無理に引っ張らずにとかすことができます。
逆に、髪が少ない人や細い人は、ピンが柔らかく、密度がそれほど高くないものの方が、頭皮に余計な負担をかけずに済みます。自分の髪質や毛量を考慮して、スムーズにとかせるブラシを選びましょう。
買い替えのサインと適切なお手入れ頻度
どんなに良いブラシも、劣化したり汚れたりすれば、その効果は半減し、むしろ頭皮に悪影響を与えます。ブラシは消耗品と考え、定期的なお手入れと交換を心がけましょう。
ブラシ交換の目安
- ピン(毛先)が広がったり、折れたり、抜けたりしている。
- クッション部分が劣化して弾力がなくなった。
- 洗浄しても汚れやニオイが取れなくなった。
- 木製・竹製ブラシにカビやひび割れが生じた。
これらのサインが見られたら、新しいブラシへの交換時期です。
また、お手入れの頻度としては、ナイロン製などで水洗いできるものは月に1〜2回程度、動物毛や木製の水に弱いものは、専用のクリーナーでこまめにホコリや髪の毛を取り除くようにしましょう。
頭皮と髪を守る正しいブラッシングの手順
自分に合ったブラシを選んだら、次はいよいよ実践です。頭皮と髪に負担をかけず、ブラッシングの効果を最大限に引き出すためには、正しい手順とタイミングが重要です。
力任せにとかすのではなく、一つ一つの動作を丁寧に行うことを意識しましょう。ここでは、基本となる正しいブラッシングの手順を紹介します。
タイミングはいつがベスト?
ブラッシングは、1日に何度も行う必要はありません。むしろ、やりすぎは摩擦によるダメージを増やすだけです。
最も効果的なタイミングは、1日の汚れを落とす「シャンプー前」と、髪型を整える「スタイリング前(朝)」です。
ブラッシングの推奨タイミング
| タイミング | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| シャンプー前 | 髪の絡まりをほぐす。頭皮の汚れやホコリを浮かす。 | 乾いた状態で行う。シャンプーの泡立ちが良くなる。 |
| スタイリング前(朝) | 寝癖を直し、髪の流れを整える。頭皮の血行促進。 | 乾いた髪に行う。無理に引っ張らない。 |
| 就寝前 | (任意)日中のホコリを落とし、髪をリセットする。 | やりすぎない程度に。リラックス効果も。 |
前述の通り、髪が濡れているシャンプー後(ドライヤー前)のブラッシングは、ダメージの原因になるため避けるのが賢明です。
もし濡れた髪をとかす必要がある場合は、目の粗いコーム(櫛)やスケルトンブラシで、細心の注意を払って行いましょう。
ステップ1:毛先の絡まりを優しくほぐす
ブラッシングの基本は「毛先から」です。いきなり根元からブラシを通すと、途中にある絡まりに引っかかり、無理な力で髪を引きちぎったり、毛根に負担をかけたりしてしまいます。
まずは、手ぐしやブラシの先端を使って、髪の毛先部分の小さな絡まりを優しく丁寧にほぐしていきます。特に髪が長い人や、パーマなどで絡まりやすい人は、この工程を怠らないことが重要です。
ステップ2:髪の中間から毛先へ
毛先の絡まりが取れたら、次は髪の中間あたりから毛先に向かってブラシを通します。この段階でも、まだ根元からはとかしません。中間から毛先までの流れをスムーズに整えるイメージです。
もし途中で引っかかりを感じたら、無理に力を加えず、一度ブラシを離し、再度毛先からほぐし直すくらいの慎重さが必要です。数回に分けて優しくとかし、髪の通りを良くしていきます。
ステップ3:最後に根元から全体をとかす
毛先から中間までの流れがスムーズになったら、いよいよ最後に髪の根元から毛先に向かって、髪全体をとかします。この時、ブラシを頭皮に強く押し付ける必要はありません。
頭皮の表面を「なでる」程度の軽いタッチでブラシを動かします。
頭皮全体に行き渡るように、生え際から襟足へ、前から後ろへ、またサイドから頭頂部へなど、いくつかの方向に分けてブラシを通すと、頭皮全体の血行促進にもつながり効果的です。
この一連の流れを、力を入れずにリラックスして行うことが、頭皮と髪を守る正しいブラッシングです。
ブラッシング以外の重要な頭皮ケア
正しいブラッシングは健やかな頭皮環境の維持に役立ちますが、それだけで薄毛や抜け毛の悩みがすべて解決するわけではありません。
ブラッシングは、あくまでトータルな頭皮ケアの一部です。
日々のシャンプー方法、頭皮マッサージ、そして体の中から整える生活習慣など、他のケアと組み合わせることで、ブラッシングの効果も一層高まります。
ここでは、ブラッシングと併せて行いたい重要な頭皮ケアを紹介します。
正しいシャンプーの方法
毎日のシャンプーは、頭皮環境を左右する最も重要なケアの一つです。シャンプー前にはブラッシングで汚れを浮かせておきましょう。
シャンプー時は、まずお湯で髪と頭皮をしっかり「予洗い」することが大切です。
これだけで汚れの多くは落ちます。シャンプー剤は手のひらでよく泡立ててから髪につけ、爪を立てずに指の腹を使って頭皮を優しくマッサージするように洗います。
すすぎ残しは頭皮のトラブルの原因になるため、シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて念入りにすすぎましょう。
頭皮マッサージのすすめ
ブラッシングによる血行促進効果に加え、指の腹を使った頭皮マッサージもおすすめです。頭皮が硬くなっていると血行が悪くなり、髪に栄養が届きにくくなります。
シャンプー中や、お風呂上がりの血行が良いときなどに、指の腹で頭皮全体を優しく揉みほぐしましょう。両手の指で頭皮を掴み、頭蓋骨から動かすようなイメージで行うと効果的です。
リラックス効果もあり、ストレス緩和にもつながります。
バランスの取れた食事と生活習慣
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。
健やかな髪を育てるためには、タンパク質(肉、魚、大豆製品など)、ビタミン(野菜、果物など)、ミネラル(特に亜鉛。海藻類、ナッツ類など)をバランス良く摂取することが重要です。
外食が多い、あるいは特定の食品ばかり食べているという人は、栄養バランスを見直してみましょう。また、髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に多く分泌されます。
質の良い睡眠を十分にとることも、抜け毛対策には必要です。
健やかな髪のための生活習慣
- 十分な睡眠時間(6〜8時間目安)
- 適度な運動(ウォーキングなど有酸素運動)
- 禁煙(喫煙は血行を悪化させます)
- ストレスの適度な発散
育毛剤の活用も選択肢に
セルフケアを続けていても抜け毛が気になる、あるいはAGAの兆候が見られるなど、より積極的なケアを望む場合は、育毛剤の活用も有効な選択肢の一つです。
育毛剤には、頭皮の血行を促進したり、毛根に栄養を与えたり、フケやかゆみを抑えたりすることで、頭皮環境を整え、健康な髪の成長をサポートする働きが期待できます。
自分の頭皮の状態や悩みに合った成分が配合された育毛剤を選び、正しいブラッシングやシャンプーと併用することで、相乗効果が期待できるでしょう。
ただし、育毛剤は医薬品の「発毛剤」とは異なり、あくまで「今ある髪を健やかに育てる」「抜け毛を防ぐ」ことを目的としています。
主な頭皮ケアの比較
| ケア方法 | 主な目的 | 期待できること |
|---|---|---|
| 正しいブラッシング | 汚れ除去、血行促進、皮脂の均一化 | 頭皮環境の整備、髪のツヤ出し |
| 正しいシャンプー | 頭皮の洗浄、皮脂コントロール | 毛穴の詰まり解消、フケ・かゆみ予防 |
| 頭皮マッサージ | 血行促進、頭皮を柔らかくする | 栄養運搬のサポート、リラックス |
| 育毛剤の使用 | 頭皮環境の改善、栄養補給、血行促進 | 抜け毛予防、育毛促進、フケ・かゆみ予防 |
頭皮ケアグッズに戻る
Q&A
ここでは、ブラッシングと抜け毛に関して、多くの人が疑問に思う点やよくある質問についてお答えします。
- 朝と夜、どちらのブラッシングが重要ですか?
-
どちらも重要ですが、目的が異なります。夜(シャンプー前)のブラッシングは、1日の汚れやホコリを落とし、シャンプーの効果を高めるために重要です。
朝(スタイリング前)のブラッシングは、寝癖を直し、髪型を整えるとともに、頭皮の血行を促して1日のスタートを切るために役立ちます。
どちらか一方ではなく、両方のタイミングで優しく行うことをおすすめします。
- 静電気を防ぐブラッシング方法はありますか?
-
冬場など乾燥する季節は、ブラッシングで静電気が起きやすくなります。静電気はキューティクルを傷める原因にもなります。
対策として、静電気が起きにくい動物毛や木製のブラシを選ぶことが有効です。
また、ブラッシングの前に、髪にヘアオイルや洗い流さないトリートメントを少量なじませて保湿するのも良い方法です。
ブラシ自体を少し湿らせる方法もありますが、素材によっては(動物毛や木製)傷む原因になるため注意が必要です。
- ブラシはどれくらいの頻度で洗えばよいですか?
-
ブラシの汚れは頭皮トラブルの原因になるため、こまめなお手入れが必要です。ブラシに絡まった髪の毛は、使うたびに取り除くのが理想です。
洗浄の頻度は、ブラシの素材や使用頻度、整髪料の使用の有無にもよりますが、水洗いできるナイロン製などのブラシは、最低でも月に1〜2回はシャンプーを薄めたお湯などで洗い、しっかり乾燥させましょう。
水洗いに適さない動物毛や木製のブラシは、専用のクリーナーを使ったり、乾いた布で拭いたりして、清潔に保ってください。
- ブラッシング以外で気をつけるべき抜け毛対策は?
-
本記事でも触れた通り、正しいシャンプー、バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理が基本となります。これらに加えて、紫外線対策も重要です。
頭皮も肌の一部であり、紫外線を浴びると日焼けして乾燥し、炎症を起こすことがあります。これは毛根にダメージを与え、抜け毛の原因となります。
外出時は帽子をかぶる、日傘を使う、または頭皮用の日焼け止めスプレーを利用するなどして、頭皮を紫外線から守る意識も持ちましょう。
Reference
LEWALLEN, Robin, et al. Hair care practices and structural evaluation of scalp and hair shaft parameters in African American and Caucasian women. Journal of cosmetic dermatology, 2015, 14.3: 216-223.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
GAN, Desmond CC; SINCLAIR, Rodney D. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2005. p. 184-189.
ROBBINS, Clarence R. Chemical and physical behavior of human hair. New York, NY: Springer New York, 2002.
OLSEN, Elise A., et al. Central hair loss in African American women: incidence and potential risk factors. Journal of the American Academy of Dermatology, 2011, 64.2: 245-252.
MCMICHAEL, Amy J. Hair and scalp disorders in ethnic populations. Dermatologic clinics, 2003, 21.4: 629-644.
MARSH, Jennifer Mary, et al. Healthy hair. New York: Springer International Publishing, 2015.
MONSELISE, Assaf, et al. What ages hair?. International journal of women’s dermatology, 2017, 3.1: S52-S57.
ROBBINS, Clarence R. The physical properties of hair fibers. In: Chemical and physical behavior of human hair. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. p. 537-640.