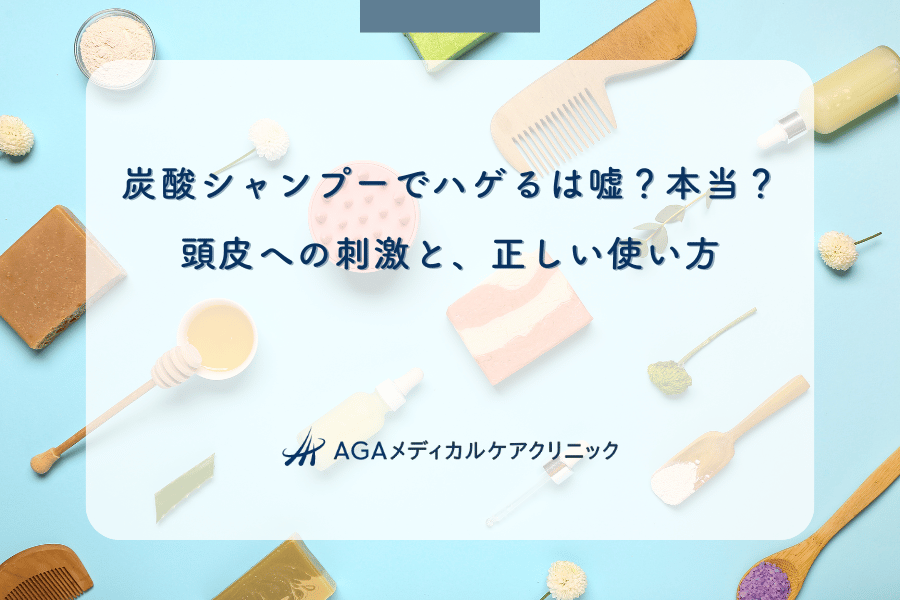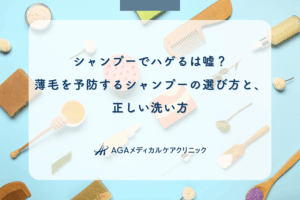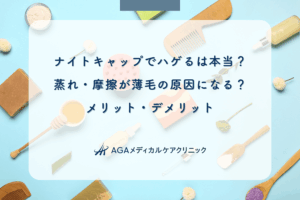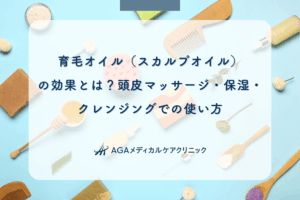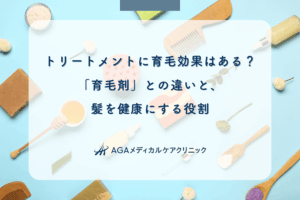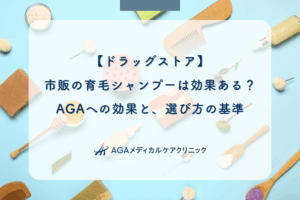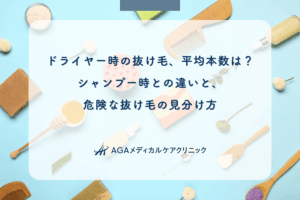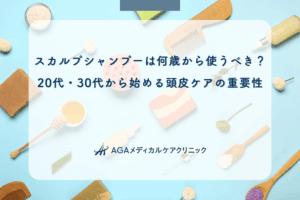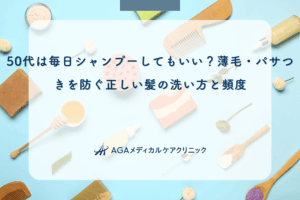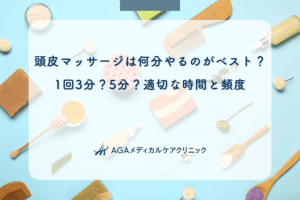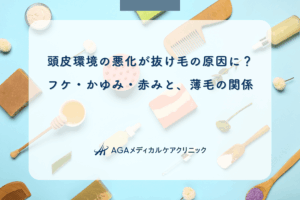炭酸シャンプーのシュワシュワとした独特な使用感が注目を集め、多くの男性用ヘアケア製品にも取り入れられています。
その一方で、「炭酸の刺激でハゲるのではないか」「頭皮に悪影響があるのでは」といった不安な声も聞かれます。果たしてその噂は本当なのでしょうか。
この記事では、なぜ「炭酸シャンプーでハゲる」という誤解が生まれたのか、炭酸シャンプーが頭皮に与える本当の影響(刺激やメリット)、そして薄毛を心配する男性が知っておくべき正しい使い方や選び方まで、詳しく解説します。
あなたの頭皮ケアの疑問を解消し、健やかな頭皮環境を目指すお手伝いをします。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「炭酸シャンプーでハゲる」という噂の真相
結論から言うと「ハゲる」は誤解
まず結論からお伝えします。「炭酸シャンプーを使用したからといって、それが直接的な原因でハゲる(薄毛が進行する)」という医学的・科学的根拠はありません。
むしろ、この記事で後述する「正しい使い方」を守れば、頭皮環境を健やかに保つ助けとなり、薄毛予防の一環として役立つ可能性を持っています。
炭酸シャンプーは、毛穴に詰まった皮脂汚れや古い角質を効果的に洗浄することを目的としています。
頭皮環境の悪化(汚れの詰まりや血行不良)は抜け毛の一因となるため、頭皮を清潔に保つことは非常に重要です。したがって、「炭酸シャンプー=ハゲる」という認識は誤解であると言えます。
なぜ「ハゲる」と言われるようになったのか
では、なぜこのようなネガティブな噂が広まったのでしょうか。いくつかの理由が考えられます。
第一に、「炭酸=刺激が強い」というイメージです。炭酸飲料を飲んだ時の刺激や、炭酸泉に入った時の感覚から、「強い刺激が頭皮にダメージを与え、毛根を弱らせるのではないか」と連想する人がいるかもしれません。
第二に、洗浄力の高さによる誤解です。炭酸シャンプーは一般的なシャンプーよりも皮脂や汚れをしっかり落とす製品が多い傾向にあります。
そのため、必要な皮脂まで取り過ぎてしまい、頭皮が乾燥し、バリア機能が低下することがあります。頭皮が乾燥すると、フケやかゆみが発生しやすくなり、頭皮環境が悪化します。
この状態が続けば、間接的に抜け毛につながる可能性もゼロではありません。しかし、これは「炭酸」そのものではなく、「洗浄力の強すぎる製品を不適切な頻度で使った」結果です。
第三に、使用初期の一時的な抜け毛です。まれに、頭皮環境が変化する過程で、一時的に抜け毛が増えたと感じる人がいます。
しかし、これは多くの場合、すでに休止期に入っていた髪の毛が新しいシャンプーの洗浄作用で抜け落ちただけで、ヘアサイクルが乱れたわけではありません。
炭酸シャンプーと抜け毛の直接的な因果関係
前述の通り、炭酸シャンプーの成分自体に脱毛を促進するような作用はありません。炭酸(二酸化炭素)が毛根を破壊したり、ヘアサイクルを強制的に短縮させたりすることはありません。
抜け毛の主な原因は、男性ホルモンの影響(AGA)、遺伝、生活習慣の乱れ、ストレス、頭皮環境の悪化など多岐にわたります。
炭酸シャンプーは、これらのうち「頭皮環境の悪化」に対して、汚れを落とすことでアプローチするアイテムです。直接の原因ではなく、むしろ頭皮環境を整えるためのケア用品と理解するのが正しいでしょう。
頭皮タイプ別に見る使用上の懸念点
「ハゲる」ことはありませんが、誰にでも無条件で合うわけではありません。ご自身の頭皮タイプを理解し、適切に使うことが重要です。
特に乾燥肌や敏感肌の人は、洗浄力の高さが裏目に出る可能性があります。
頭皮タイプ別 使用時のポイント
| 頭皮タイプ | 懸念点と対策 | 推奨頻度(目安) |
|---|---|---|
| 脂性肌(オイリー肌) | 皮脂詰まりの解消に期待できます。ベタつきが気になる人に向いています。 | 週2~3回 |
| 乾燥肌 | 皮脂の取りすぎに注意が必要です。洗浄力がマイルドな製品を選び、頻度を抑えます。 | 週1回程度 |
| 敏感肌 | 炭酸の刺激を強く感じやすいです。使用前にパッチテストを行うことを推奨します。 | 週1回、またはそれ以下 |
炭酸シャンプーとは?基本的な仕組みを理解する
炭酸ガス(二酸化炭素)の役割
炭酸シャンプーの主役は、水に溶け込んだ炭酸ガス(二酸化炭素)です。この炭酸ガスが、シュワシュワとした泡を生み出します。
炭酸ガスの主な役割は二つあります。一つは物理的な洗浄力の補助です。
非常に細かい炭酸の泡が、毛穴の奥や髪の毛に付着した皮脂汚れ、古い角質、整髪料の洗い残しなどの隙間に入り込み、汚れを浮き上がらせる働きをします。
ゴシゴシと強く擦らなくても、汚れを効率よく除去する助けとなります。
一般的なシャンプーとの違い
一般的なシャンプーの主な洗浄成分は「界面活性剤」です。これは水と油をなじませることで、頭皮や髪の汚れ(主に皮脂)を洗い流します。
一方、炭酸シャンプーも界面活性剤を含んでいますが、それに加えて「炭酸ガスの物理的な洗浄力」を利用している点が大きな違いです。
一般的なシャンプーとの比較
| 項目 | 炭酸シャンプー | 一般的なシャンプー |
|---|---|---|
| 洗浄の仕組み | 界面活性剤(化学的)+ 炭酸ガス(物理的) | 界面活性剤(化学的)が中心 |
| 期待される主な効果 | 毛穴のディープクレンジング、血行促進サポート | 髪や頭皮の日常的な洗浄 |
| 位置づけ | 週数回のスペシャルケア | 毎日のデイリーケア |
炭酸シャンプーは、日常的な洗浄というよりは、「週に数回のスペシャルケア」や「ディープクレンジング」として位置づけるのが一般的です。
「高濃度炭酸」とは何を指すのか
製品のパッケージで「高濃度炭酸」という言葉を目にすることがあります。
これは、シャンプーに含まれる炭酸ガスの濃度が高いことを示しており、一般的に「ppm(ピーピーエム)」という単位で表します。
ppmは「100万分の1」を示す単位で、例えば1,000ppmであれば、製品1kgあたり1,000mg(=1g)の炭酸ガスが溶け込んでいることを意味します。
「高濃度」とされる具体的な数値に明確な定義はありませんが、一般的には1,000ppm以上のものを指すことが多いようです。中には5,000ppmや10,000ppmを超える製品も存在します。
濃度が高ければ高いほど洗浄力や刺激が強まる傾向にあるため、自分の頭皮の状態に合わせて選ぶ必要があります。
頭皮ケアにおける炭酸の働き
頭皮ケアにおいて炭酸に期待するのは、洗浄力だけではありません。もう一つの重要な働きが「血行促進のサポート」です。炭酸ガスは皮膚(角質層まで)に浸透しやすい性質を持っています。
頭皮から炭酸ガスが浸透すると、一時的にその部分が軽い酸欠状態のように認識されます。すると、体はより多くの酸素を運ぼうとして、血管を拡張させ、血流を促そうとします。
これが血行促進のサポートにつながると考えられています。頭皮の血行が良くなることは、髪の毛の成長に必要な栄養素を毛根に届けやすくするために非常に重要です。
炭酸シャンプーが頭皮に与える良い影響(メリット)
毛穴の汚れと皮脂のディープクレンジング効果
炭酸シャンプーが持つ微細な泡は、通常のシャンプーの泡では届きにくい毛穴の奥深くまで浸透しやすい特徴があります。
男性は特に皮脂分泌が活発なため、毛穴に皮脂や古い角質が固まって「角栓(かくせん)」のようになっていることがあります。これが酸化するとニオイの原因になったり、頭皮環境を悪化させたりします。
炭酸シャンプーは、これらの頑固な汚れを浮かび上がらせ、効率的に除去する「ディープクレンジング効果」が期待できます。頭皮をリセットし、清潔な状態を保つことは、健やかな髪を育むための第一歩です。
頭皮の血行促進サポート
前述の通り、炭酸ガスには頭皮の血行をサポートする働きが期待されています。髪の毛は、毛根にある「毛母細胞」が細胞分裂を繰り返すことで成長します。
そのエネルギー源となる栄養素や酸素は、すべて血液によって運ばれます。つまり、頭皮の血行が悪いと、毛母細胞に十分な栄養が届かず、髪の毛が細くなったり、成長が妨げられたりする可能性があります。
炭酸シャンプーによるマッサージを伴う洗髪は、この血行を一時的に促進し、栄養が届きやすい頭皮環境をサポートします。
頭皮環境を健やかに保つ(弱酸性)
健康な頭皮の表面は、pH(ペーハー)値が「弱酸性」(pH4.5~6.0程度)に保たれています。この弱酸性の環境が、皮膚のバリア機能や常在菌のバランスを維持しています。
しかし、汗や皮脂汚れ、あるいは洗浄力の強すぎるアルカリ性のシャンプーによって、このバランスが崩れることがあります。
炭酸ガスが溶け込んだ水(炭酸水)は弱酸性です。炭酸シャンプーを使用することは、頭皮を本来の弱酸性の状態に引き戻し、バリア機能をサポートする上で役立ちます。
フケやかゆみ、ニオイへのアプローチ
フケやかゆみ、頭皮のニオイの原因は様々ですが、主な原因の一つに「皮脂の過剰分泌」と「汚れの残留」があります。
特に脂性フケ(湿ったフケ)やニオイは、過剰な皮脂をエサにマラセチア菌などの常在菌が異常増殖し、その代謝物や酸化した皮脂が原因となります。
炭酸シャンプーで余分な皮脂や汚れをしっかり取り除くことは、これらの菌の増殖を抑え、不快な症状を軽減する助けとなります。
頭皮の悩みと炭酸シャンプーに期待できること
| 頭皮の悩み | 炭酸シャンプーに期待できる主な役割 |
|---|---|
| 頭皮のベタつき | 余分な皮脂の効果的な洗浄 |
| 毛穴の詰まり感 | 固まった皮脂や古い角質の除去サポート |
| 頭皮のニオイ | ニオイの原因となる酸化した皮脂汚れの洗浄 |
炭酸シャンプーの刺激とデメリット
炭酸の刺激は強すぎる?
炭酸シャンプーの「シュワシュワ」「ピリピリ」とした感覚は、炭酸ガスが皮膚に触れることによる刺激です。
この感覚は血行が促進されているサインとも言われますが、感じ方には大きな個人差があります。
健康な頭皮であれば心地よい刺激と感じることが多いですが、頭皮が乾燥していたり、敏感になっていたりすると、「痛み」や「不快感」として感じることがあります。
特に、頭皮に小さな傷や湿疹、炎症などがある場合は、その部分に炭酸がしみて強い痛みを感じる可能性があります。もし使用中に強い痛みや赤みが出た場合は、すぐに洗い流し、使用を中止してください。
使用に注意が必要な頭皮状態
- 頭皮に傷や湿疹、炎症がある
- アトピー性皮膚炎など、皮膚疾患がある
- 極度の敏感肌で、過去に化粧品でトラブルがあった
- 日焼けなどで頭皮がダメージを受けている
必要な皮脂まで落としすぎる可能性
炭酸シャンプーのメリットである「高い洗浄力」は、同時にデメリットにもなり得ます。頭皮の皮脂は、すべてが悪者ではありません。
皮脂が薄く膜(皮脂膜)を作ることで、頭皮の水分蒸発を防ぎ、外部の刺激から守る「バリア機能」の役割を担っています。
しかし、洗浄力が強すぎる炭酸シャンプーを毎日使ったりすると、この必要な皮脂膜まで根こそぎ洗い流してしまう恐れがあります。
乾燥肌・敏感肌の人が注意すべきこと
皮脂膜が失われると、頭皮は無防備な状態になり、乾燥しやすくなります。
そして、頭皮が「乾燥しすぎている」と判断すると、かえって皮脂を過剰に分泌しようとする「インナードライ」状態に陥ることもあります。
もともと皮脂分泌が少ない乾燥肌の人や、外部からの刺激に反応しやすい敏感肌の人は、炭酸シャンプー選びに特に注意が必要です。
炭酸濃度が高すぎるものや、洗浄成分として「ラウリル硫酸Na」「ラウレス硫酸Na」などの高級アルコール系(硫酸系)を主成分とするシャンプーは、刺激が強く、乾燥を助長する可能性があります。
使用頻度が高すぎる場合の問題点
脂性肌の人であっても、炭酸シャンプーの使いすぎは推奨しません。皮脂を落としすぎることが頭皮の乾燥を招き、バリア機能を低下させるリスクは誰もが持っています。
頭皮のバリア機能が低下すると、紫外線や空気中のホコリ、雑菌などの影響を受けやすくなり、かゆみや炎症、抜け毛といったトラブルにつながりかねません。
「ハゲる」という誤解は、この「使いすぎ」による頭皮環境の悪化が原因である可能性が非常に高いです。
炭酸シャンプーは「毎日の汚れを落とすもの」というより、「定期的な大掃除(ディープクレンジング)」と捉え、適切な使用頻度を守ることが重要です。
「ハゲる」と誤解しないための正しい使い方
適切な使用頻度の目安
炭酸シャンプーの恩恵を最大限に受け、デメリットを避けるためには、使用頻度が鍵となります。多くの製品は、毎日の使用ではなく、週に1~3回程度のスペシャルケアとしての使用を推奨しています。
脂性肌でベタつきがひどい人でも、まずは週2~3回から始め、頭皮の様子を見ながら調整するのが良いでしょう。乾燥肌や敏感肌の人は週に1回、あるいは2週間に1回程度でも十分な場合があります。
推奨される使用頻度の目安
| 頭皮の状態 | 推奨頻度 | 目的 |
|---|---|---|
| ベタつきが非常に強い(脂性肌) | 週2~3回 | 溜まった皮脂のディープクレンジング |
| 標準的・やや脂性 | 週1~2回 | 定期的な頭皮環境リセット |
| 乾燥・敏感 | 週1回またはそれ以下 | 刺激を避けつつ毛穴の汚れ除去 |
炭酸シャンプーを使わない日は、普段使っているアミノ酸系シャンプーなどで優しく洗いましょう。
シャンプー前の予洗いの重要性
これは炭酸シャンプーに限らず全てのシャンプーに言えることですが、洗髪前の「予洗い(よあらい)」は非常に重要です。
シャンプーを付ける前に、38度程度のぬるま湯で頭皮と髪を1分~2分ほどしっかりと洗い流します。実は、これだけで髪についたホコリや汗、軽い汚れの7割程度は落ちると言われています。
予洗いをしっかり行うことで、シャンプーの使用量を減らせるだけでなく、泡立ちが格段に良くなります。特に炭酸シャンプーの効果を高めるためには、まずお湯で落とせる汚れを落としておくことが大切です。
効果的な泡立て方と洗い方
炭酸シャンプーには、泡で出てくるエアゾールタイプと、自分で泡立てる液体タイプがあります。
エアゾールタイプの場合、手で泡立てる必要はありません。適量を手に取り、そのまま頭皮の数カ所(額の生え際、頭頂部、後頭部、耳の上など)に直接泡を乗せていきます。
その後、指の腹を使って、頭皮全体に泡を行き渡らせるように優しくマッサージします。
液体タイプの場合、まずは手のひらで軽く泡立ててから髪につけます。炭酸シャンプーは一般的なシャンプーより泡立ちが控えめな製品もありますが、泡の量が少なくても洗浄力はあります。
共通して重要なのは、「爪を立てず、指の腹で洗う」ことです。頭皮はデリケートなため、爪を立ててゴシゴシ擦ると細かい傷がつき、そこから炎症を起こす可能性があります。
毛穴の汚れを「揉み出す」ようなイメージで、下から上へ、頭皮を動かすように優しくマッサージするのがコツです。
すすぎ残しを防ぐ徹底した洗い流し
炭酸シャンプーの成分や、浮き上がらせた汚れが頭皮に残ってしまうと、それがかゆみやフケ、ニオイの原因となり、頭皮環境を悪化させます。
特に炭酸シャンプーの濃密な泡は、一般的なシャンプーよりも残りやすい傾向があります。洗う時間の2倍以上の時間をかけるつもりで、徹底的にすすぎましょう。
シャワーヘッドを頭皮に近づけ、髪の毛の中にも指を入れながら、ぬるま湯でしっかりと洗い流します。耳の後ろ、首筋(襟足)、額の生え際は、特に泡が残りやすい場所なので、意識してすすいでください。
薄毛を気にする男性のための炭酸シャンプー選び
炭酸濃度(ppm)のチェック
炭酸シャンプーのパワーの指標の一つが「炭酸濃度(ppm)」です。前述の通り、1,000ppm以上を高濃度と呼ぶことが多いですが、製品によっては8,000ppmや10,000ppmを超えるものもあります。
一般的に、濃度が高いほど皮脂の洗浄力や血行促進サポートが期待できますが、同時に頭皮への刺激も強くなる傾向があります。
初めて使う人や敏感肌の人は、まずは1,000ppm~3,000ppm程度のものから試し、頭皮が慣れてきたら高濃度のものに挑戦するなど、自分の肌質と相談しながら選ぶことが重要です。
配合されている洗浄成分
炭酸ガスだけでなく、ベースとなる洗浄成分(界面活性剤)の種類も必ず確認しましょう。「ハゲる」という不安を持つ人は、頭皮への優しさを最優先に考えるべきです。
主な洗浄成分の種類と特徴
| 成分系統 | 特徴 | 肌への優しさ |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | (例:ココイルグルタミン酸~) マイルドな洗浄力、保湿性が高い。 | ◎ 優しい |
| ベタイン系 | (例:コカミドプロピルベタイン~) ベビーシャンプーにも使用される低刺激成分。 | ◎ 優しい |
| 高級アルコール系 | (例:ラウレス硫酸~) 泡立ちが良く洗浄力が強いが、刺激も強め。 | △ 脂性肌向き・乾燥肌注意 |
薄毛や頭皮環境を気にする男性には、必要な皮脂を残しつつ優しく洗い上げる「アミノ酸系」や「ベタイン系」を主成分とした炭酸シャンプーを推奨します。
保湿成分や頭皮ケア成分の有無
炭酸シャンプーによる洗浄後の乾燥を防ぐため、保湿成分が配合されているかどうかも重要なチェックポイントです。ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン、リピジュア®などが代表的な保湿成分です。
また、頭皮環境を整えるためのサポート成分(抗炎症成分のグリチルリチン酸2Kや、血行促進をサポートするセンブリエキス、オタネニンジンエキスなど)が配合されている製品もあります。
育毛剤メディアとして推奨するのは、こうした洗浄以外のプラスアルファのケアができる製品です。
注目したい保湿・サポート成分(例)
- ヒアルロン酸(高い保水力)
- セラミド(バリア機能サポート)
- グリチルリチン酸2K(抗炎症)
- 植物エキス(センブリ、オタネニンジンなど)
添加物(シリコンなど)の確認
シリコン(ジメチコン、シクロメチコンなど)は、髪の毛のキューティクルをコーティングし、指通りを滑らかにする成分です。髪のきしみを防ぐメリットがありますが、
一方で、頭皮に残りやすく毛穴を詰まらせる可能性があるとも言われています。
頭皮の健康を第一に考える「スカルプケア」を目的とするならば、シリコンが配合されていない「ノンシリコン」タイプの炭酸シャンプーを選ぶのが良いでしょう。
ただし、ノンシリコンシャンプーは洗い上がりに髪がきしみやすいため、その後のトリートメントで髪の毛のケアを別途行う必要があります。
育毛剤と炭酸シャンプーの併用
炭酸シャンプー使用後の育毛剤は効果的か
炭酸シャンプーと育毛剤の併用は、非常に良い組み合わせです。育毛剤は、頭皮に有効成分を浸透(※角質層まで)させることでその効果を発揮します。
しかし、頭皮が皮脂や汚れで詰まっていると、育毛剤が毛穴の奥まで届かず、十分な効果が期待できません。
炭酸シャンプーは、この育毛剤の通り道を妨げる「毛穴の詰まり」を解消するのに役立ちます。
頭皮をディープクレンジングし、清潔でリセットされた状態にすることで、育毛剤の成分が浸透しやすい土台を作ることができます。
頭皮を清潔にする重要性
薄毛対策の基本は、育毛剤を塗ること以前に、まず頭皮環境を正常に保つことです。どれだけ高価な育毛剤を使っても、土壌となる頭皮が荒れていては、健康な髪は育ちません。
炭酸シャンプーで定期的に頭皮の大掃除を行い、血行をサポートし、清潔な状態を維持することは、育毛剤の効果を最大限に引き出すためにも重要です。
併用時の正しい使用順序
併用する場合の正しい順序を理解し、育毛剤の浸透を妨げないようにしましょう。
シャンプーから育毛剤までの流れ
| 順序 | 行うこと | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 炭酸シャンプー(または通常シャンプー) | 頭皮の汚れをしっかり落とし、徹底的にすすぐ。 |
| 2 | タオルドライ | 擦らず、優しく押さえるように水分を拭き取る。 |
| 3 | ドライヤー | 頭皮を中心にしっかり乾かす。生乾きは厳禁。 |
| 4 | 育毛剤塗布 | 頭皮が乾いた状態で塗布し、優しくマッサージする。 |
シャンプーで清潔にし、しっかり乾かしてから育毛剤を使うことが効果を高める鍵です。頭皮が濡れたままだと育毛剤の成分が薄まったり、雑菌が繁殖したりする原因になります。
シャンプー・洗い方に戻る
Q&A
- 炭酸シャンプーは毎日使っても良いですか?
-
製品によっては毎日の使用が可能と謳っているものもありますが、基本的には推奨しません。
特に洗浄力が高い製品や高濃度の製品を毎日使うと、頭皮に必要な皮脂まで奪いすぎ、乾燥やバリア機能の低下を招く恐れがあります。
脂性肌の人でも週2~3回、乾燥肌や敏感肌の人は週1回程度を目安にし、頭皮のコンディションを見ながら使用頻度を調整してください。
スペシャルケアとして位置づけるのが最も安全で効果的です。
- 炭酸がしみる感じがしますが、大丈夫ですか?
-
軽いピリピリ感やシュワシュワ感は、炭酸ガスによる刺激や血行が促進されている感覚であることが多いです。
一時的で、洗い流した後に赤みやヒリヒリ感が残らなければ、大きな問題はありません。
ただし、もし「痛み」として感じる場合や、洗い流した後も赤みやかゆみが続く場合は、その製品があなたの頭皮に合っていない可能性があります。
直ちに使用を中止し、場合によっては皮膚科専門医に相談してください。頭皮に傷や湿疹がある時も使用を避けましょう。
- 炭酸シャンプーだけで髪はきしみませんか?
-
きしむ可能性はあります。炭酸シャンプーは、髪の指通りを良くするシリコンなどのコーティング剤を含まない(ノンシリコン)製品が多いです。
また、洗浄力が高いため、髪の表面の油分や汚れがしっかり落ちることで、髪本来の状態(キューティクルがやや開いた状態)に戻り、きしみを感じやすくなります。
これは汚れが落ちた証拠でもありますが、きしみや絡まりが気になる場合は、シャンプー後に別途トリートメントやコンディショナーを毛先中心に使用し、髪の毛のケアを行ってください。
その際、トリートメント類が頭皮に残らないよう注意しましょう。
- 効果を実感できるまでどのくらいかかりますか?
-
「毛穴の汚れが落ちたサッパリ感」や「頭皮のベタつきの軽減」といった洗浄効果は、1回の使用でも実感しやすいです。
しかし、「頭皮環境の改善」や「フケ・かゆみの減少」といった効果は、すぐには表れません。
頭皮のターンオーバー(生まれ変わり)の周期や、これまでの頭皮状態によって個人差がありますが、まずは1ヶ月~3ヶ月程度、正しい頻度で継続して使用し、頭皮の変化を観察してみてください。
Reference
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
TRÜEB, Ralph M. Shampoos: ingredients, efficacy and adverse effects. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2007, 5.5: 356-365.
FENG, Chengcheng, et al. Analysis of common treatment drugs and allergen sensitization in hair loss patients. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.2: e16798.
DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni; LOURES, Aline Falci; EKELEM, Chloe. Hair cosmetics for the hair loss patient. Indian Journal of Plastic Surgery, 2021, 54.04: 507-513.
SANG, Sze-Huey, et al. A Review on Synthetic Shampoo Ingredients and Their Adverse Health Effects. Current Trends in Biotechnology and Pharmacy, 2023, 17.4A (Supplement): 50-60.
CHEN, Dongxiao, et al. Anti‐hair loss effect of a shampoo containing caffeine and adenosine. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.9: 2927-2933.
CLINE, Abigail; UWAKWE, Laura N.; MCMICHAEL, Amy J. No sulfates, no parabens, and the “no-poo” method: a new patient perspective on common shampoo ingredients. Cutis, 2018, 101.1: 22-26.
BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.
PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.
GRAY, John. Hair care and hair care products. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 227-236.