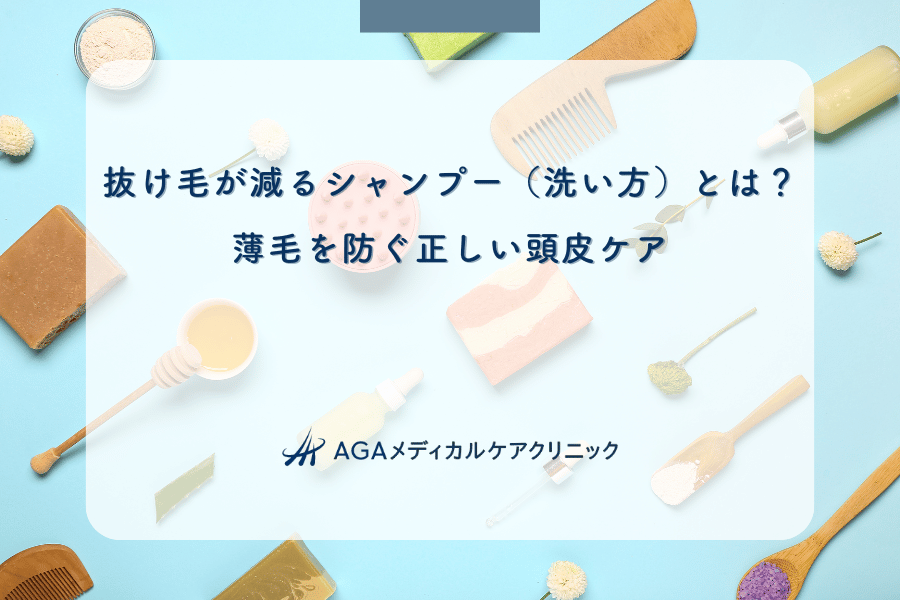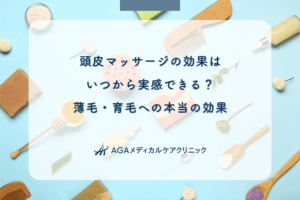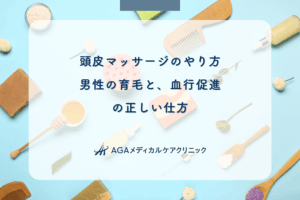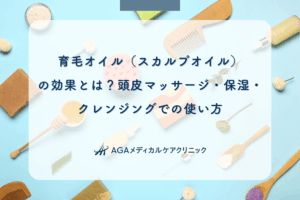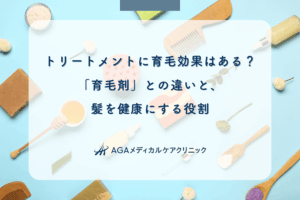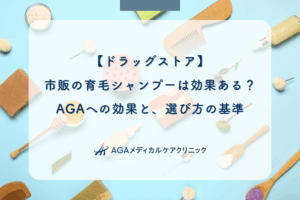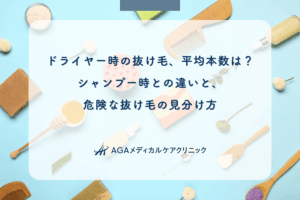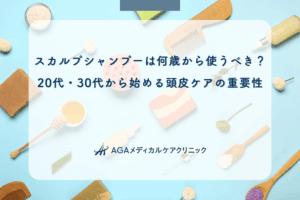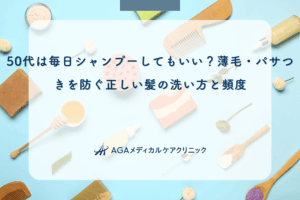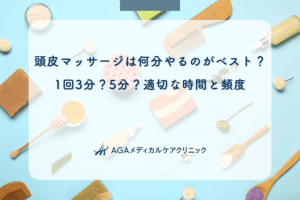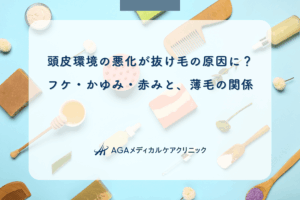お風呂場の排水溝にたまる髪の毛、朝起きた時に枕についている抜け毛を見て、「もしかして薄毛が進行しているのでは?」と不安に感じていませんか。
抜け毛の原因は様々ですが、毎日のシャンプー(洗い方)が頭皮環境を悪化させ、抜け毛を助長している可能性も否定できません。
この記事では、抜け毛を減らすために知っておきたい正しいシャンプーの選び方と、薄毛を防ぐための具体的な頭皮ケア(洗い方)を詳しく解説します。
自分に合ったシャンプーを見つけ、日々の洗い方を丁寧に見直すことで、頭皮環境を健やかに保ち、抜け毛の悩みに真剣に向き合いましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ抜け毛は起こるのか?シャンプーとの関係性
抜け毛は、多くの場合「ヘアサイクル(毛周期)」の乱れによって発生します。
髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、通常であれば休止期に入った髪が自然に抜け落ち、新しい髪が成長を始めます。
しかし、何らかの要因でこのサイクルが乱れ、成長期が短くなったり、休止期が長くなったりすると、髪が十分に育つ前に抜けてしまい、抜け毛や薄毛が目立つようになります。
抜け毛が増える主な原因
抜け毛が増加する原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いです。
AGA(男性型脱毛症)のように遺伝的・ホルモン的な要因が強く関わるものもあれば、日々の生活習慣が大きく影響するものもあります。
特に頭皮環境の悪化は、健康な髪の成長を妨げる大きな原因となります。
抜け毛の主な要因分類
| 要因の分類 | 具体的な内容 | シャンプーとの関連 |
|---|---|---|
| 内的要因 | AGA(男性型脱毛症)、遺伝、ストレス、ホルモンバランスの乱れ、栄養不足 | 直接的な治療はできないが、頭皮環境を整える補助的な役割を持つ。 |
| 外的要因 | 不適切なヘアケア(間違ったシャンプー)、頭皮の乾燥・皮脂過剰、紫外線ダメージ | シャンプーの選び方や洗い方で、これらの外的要因を軽減・改善できる可能性が高い。 |
頭皮環境と抜け毛の深い結びつき
健康な髪は、健康な頭皮という「土壌」から育ちます。頭皮環境が悪化すると、髪の成長が妨げられ、抜け毛が増加します。
例えば、頭皮が乾燥しすぎると、フケやかゆみが発生し、角質層がダメージを受けやすくなります。逆に、皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が詰まり、皮脂を栄養源とする雑菌が繁殖しやすくなります。
これが炎症(脂漏性皮膚炎など)を引き起こし、抜け毛につながるケースもあります。
間違ったシャンプー選びが抜け毛を招く
毎日使うシャンプーが、実は自分の頭皮に合っていない場合、それが抜け毛の原因となっているかもしれません。
洗浄力が強すぎるシャンプーは、頭皮を守るために必要な皮脂まで洗い流してしまい、頭皮の乾燥やバリア機能の低下を招きます。
その結果、外部からの刺激に弱くなり、かゆみや炎症が起こりやすくなります。
逆に、洗浄力が弱すぎると、余分な皮脂や汚れが落としきれず、毛穴の詰まりや雑菌の繁殖を引き起こす可能性があります。
洗いすぎ・洗わなすぎが引き起こす問題
「頭皮を清潔に保つため」と1日に何度もシャンプーをすると、必要な皮脂まで奪い去り、頭皮が乾燥しやすくなります。
頭皮は乾燥すると、それを補おうとして逆に皮脂を過剰に分泌することがあり、悪循環に陥ります。
一方で、数日間髪を洗わないと、汗や皮脂、ホコリ、スタイリング剤などが頭皮に蓄積します。これらの汚れは酸化し、毛穴を詰まらせ、雑菌の温床となります。
雑菌が繁殖すると、かゆみやニオイ、炎症の原因となり、頭皮環境は著しく悪化します。シャンプーは、適切な頻度(通常は1日1回)で、正しく行うことが重要です。
抜け毛予防のためのシャンプー選びの基本
抜け毛対策の第一歩は、自分の頭皮状態を正しく理解し、それに合ったシャンプーを選ぶことです。
洗浄成分や配合されている成分に注目し、頭皮環境を整えるサポートができる製品を選びましょう。
自分の頭皮タイプを知る
まずは自分の頭皮がどのタイプなのかを把握することが大切です。頭皮タイプによって、選ぶべきシャンプーの洗浄力や特徴が異なります。
頭皮タイプ簡易チェック
| 頭皮タイプ | 主な特徴 |
|---|---|
| 乾燥肌・敏感肌 | 洗髪後につっぱり感がある。細かいフケが出やすい。かゆみを感じやすい。 |
| 脂性肌(オイリー肌) | 洗髪して半日ほどで髪がベタつく。頭皮が脂っぽく、ニオイが気になることがある。 |
| 混合肌 | Tゾーンはベタつくが、頭頂部や生え際は乾燥するなど、部分的に状態が異なる。 |
乾燥肌・敏感肌タイプ
このタイプの人は、洗浄力がマイルドなシャンプーを選ぶ必要があります。アミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を主成分とするシャンプーが適しています。
保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸、グリセリンなど)が配合されていると、さらに良いでしょう。
脂性肌(オイリー肌)タイプ
余分な皮脂をしっかりと洗い流し、頭皮を清潔に保つ必要があります。
ただし、洗浄力が強すぎると逆効果になることもあるため、適度な洗浄力を持つ石けん系や、アミノ酸系の中でも洗浄力がやや高めのもの(ラウロイルメチルアラニンNaなど)を選ぶと良いでしょう。
皮脂の分泌を抑える成分や、抗菌・抗炎症成分(ピロクトンオラミン、グリチルリチン酸2Kなど)が配合されたスカルプシャンプーも選択肢になります。
混合肌タイプ
基本的な洗浄力は持ちつつ、頭皮の潤いを奪いすぎないアミノ酸系シャンプーをベースに選ぶことを推奨します。
洗い方を工夫し、皮脂が多い部分を重点的に、乾燥しやすい部分は優しく洗うといった調整も大切です。
注目すべきシャンプーの洗浄成分
シャンプーの性質を決定づけるのが「洗浄成分(界面活性剤)」です。
成分表示は配合量が多い順に記載されているため、水の次に記載されている成分(多くの場合は主となる洗浄成分)に注目してください。
主な洗浄成分の種類と特徴
| 洗浄成分の系統 | 代表的な成分名 | 特徴(洗浄力・刺激) |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルメチルアラニンNa など | 洗浄力:マイルド、刺激:低い。頭皮の潤いを保ちやすい。 |
| ベタイン系 | コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタイン など | 洗浄力:非常にマイルド、刺激:非常に低い。アミノ酸系と併用されることが多い。 |
| 高級アルコール系 | ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na など | 洗浄力:強い、刺激:やや強い。泡立ちが良く安価だが、乾燥肌には不向きな場合がある。 |
| 石けん系 | 石ケン素地、脂肪酸Na、脂肪酸K など | 洗浄力:強い、刺激:アルカリ性でやや強い。さっぱりとした洗い上がりだが、髪がきしみやすい。 |
抜け毛や頭皮の乾燥が気になる方は、まず「アミノ酸系」や「ベタイン系」を主成分としたシャンプーを試してみることをお勧めします。
避けた方が良い可能性のある成分
すべての人に当てはまるわけではありませんが、敏感肌の人や頭皮トラブルを抱えている人は、特定の成分によって刺激を感じることがあります。
例えば、高級アルコール系(特にラウリル硫酸Naなど)の強い洗浄成分は、必要な皮脂まで奪いすぎる可能性があります。
また、合成香料、合成着色料、防腐剤(パラベンなど)、シリコン(ジメチコンなど)が刺激になる人もいます。
ただし、シリコン自体は髪のきしみを防ぐコーティング剤であり、頭皮に悪影響を与えるという明確な根拠は限定的です。
洗い残しがなければ問題ないことが多いですが、毛穴詰まりを懸念する場合はノンシリコンタイプを選ぶのも一つの方法です。
育毛剤ユーザー向けのシャンプー選び
育毛剤や発毛剤を使用している方は、その浸透を妨げないシャンプー選びが大切です。頭皮の汚れや余分な皮脂をきちんと落とし、毛穴を清潔な状態にする必要があります。
そのため、適度な洗浄力を持つスカルプシャンプーやアミノ酸系シャンプーが適しています。また、育毛剤の成分とシャンプーの成分が干渉しないよう、シンプルな処方のものを選ぶと良いでしょう。
薄毛を防ぐ!正しいシャンプー(洗い方)の完全ガイド
抜け毛を防ぐためには、シャンプー剤選びと同じくらい「洗い方」が重要です。頭皮を傷つけず、汚れだけを的確に落とす技術を身につけましょう。
ここでは、薄毛を防ぐための正しいシャンプーの手順を詳しく解説します。
シャンプー前の準備「ブラッシングと予洗い」
シャンプーの効果を最大限に高めるため、洗う前の準備が大切です。
ブラッシング
まず、乾いた髪の状態でブラッシングを行います。毛先の絡まりをほぐしてから、徐々に根元に向かってとかしていきます。
これにより、髪についたホコリや汚れを浮かせ、シャンプーの泡立ちを良くします。また、頭皮の血行促進にもつながります。
予洗い(湯シャン)
シャンプーをつける前に、38度前後のぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと濡らします。
これを「予洗い」と呼びます。1分から2分程度かけて、指の腹で頭皮を軽くマッサージするようにしながら、お湯だけで汚れを洗い流します。
実は、この予洗いだけで髪の汚れの7割程度は落ちると言われています。予洗いを丁寧に行うことで、シャンプーの使用量を減らし、泡立ちを格段に良くすることができます。
シャンプーの泡立て方と適切な量
シャンプーの原液を直接頭皮につけるのは避けてください。
刺激が強すぎたり、すすぎ残しの原因になったりします。シャンプーは手のひらに適量(ミディアムヘアで1プッシュ程度)を取り、少量のお湯を加えて両手でしっかりと泡立てます。
泡立てネットを使うと、より簡単にもっちりとした泡を作ることができます。泡立てたシャンプーを髪全体、特に頭皮に行き渡らせます。
頭皮を傷つけない「指の腹」での洗い方
髪を洗うというよりも、「頭皮を洗う」意識が重要です。絶対に爪を立ててはいけません。爪を立てると頭皮が傷つき、そこから炎症が起きる可能性があります。
使うのは「指の腹」です。指の腹を頭皮に密着させ、小刻みにジグザグと動かしながら頭皮全体をマッサージするように洗います。特に皮脂の分泌が多い頭頂部、生え際、後頭部は丁寧に洗いましょう。
ゴシゴシと力を入れる必要はありません。泡が汚れを浮かせてくれるので、優しく動かすだけで十分です。
正しい洗髪のポイント
- 予洗いをしっかり行う
- シャンプーは手で泡立てる
- 爪を立てず、指の腹で洗う
すすぎ残しを防ぐ徹底的なすすぎ
シャンプー(洗い方)の中で、最も重要とも言えるのが「すすぎ」です。シャンプー剤が頭皮に残っていると、それが毛穴を塞ぎ、かゆみや炎症、抜け毛の原因となります。
洗う時にかけた時間の2倍以上の時間をかけるつもりで、徹底的にすすぎましょう。
ぬるま湯のシャワーを頭皮に当てながら、指の腹を使って頭皮を軽くこするようにして、泡やぬめり感が完全になくなるまで洗い流します。
特に、耳の後ろ、生え際、襟足(えりあし)はシャンプー剤が残りやすい部分なので、意識して丁寧にすすいでください。
シャンプー後の頭皮ケアと乾燥方法
シャンプーで頭皮を清潔にした後は、適切なアフターケアが抜け毛予防につながります。濡れたまま放置することは、頭皮環境にとって良くありません。
タオルドライの正しい手順
濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。ゴシゴシと強くこするように拭くと、髪がダメージを受け、切れ毛の原因になります。
まずは、清潔なタオルで頭皮の水分を優しく押さえるように拭き取ります。次に、髪の毛をタオルで挟み込み、ポンポンと優しく叩くようにして水分を吸収させます。
吸収性の高いマイクロファイバータオルを使うのも効率的です。
ドライヤーで頭皮をしっかり乾かす重要性
「ドライヤーは髪を傷める」と自然乾燥を選ぶ人もいますが、抜け毛予防の観点からはお勧めできません。
髪が濡れた状態が続くと、頭皮の温度が下がり血行が悪くなるほか、雑菌が繁殖しやすい環境(高温多湿)を作り出してしまいます。これがニオイやかゆみ、抜け毛の原因となります。
タオルドライの後は、速やかにドライヤーで乾かしましょう。
まずは頭皮(根元)から乾かします。ドライヤーを頭皮から15〜20cmほど離し、温風を同じ場所に当て続けないよう、小刻みに振りながら全体を乾かしていきます。
頭皮が8割方乾いたら、冷風に切り替えて頭皮の熱を冷まし、開いたキューティクルを引き締めると、髪にツヤが出ます。
頭皮用保湿剤や育毛剤のタイミング
頭皮の乾燥が気になる場合は、ドライヤーで乾かした後に頭皮用のローションや保湿剤を使って潤いを補給します。
育毛剤や発毛剤を使用するタイミングも、ドライヤーで頭皮をしっかり乾かした後です。頭皮が清潔で乾いている状態が、成分が最も浸透しやすい状態です。
育毛剤を塗布した後は、指の腹で優しく頭皮マッサージを行い、血行を促進させるとより効果的です。
頭皮環境を悪化させるNGな洗い方
良かれと思ってやっている習慣が、実は頭皮にダメージを与え、抜け毛を促進しているかもしれません。以下のようなNGな洗い方をしていないかチェックしてみましょう。
熱すぎるお湯での洗髪
40度を超えるような熱いお湯は、頭皮にとって刺激が強く、必要な皮脂まで奪い去ってしまいます。これにより頭皮が乾燥し、かゆみやフケの原因となります。
シャンプーやすすぎに適した温度は、38度前後の「ぬるま湯」です。少し物足りなく感じるかもしれませんが、頭皮への負担を考えるとこの温度が適切です。
爪を立ててゴシゴシ洗う
頭皮のかゆみを感じると、つい爪を立てて強く洗いたくなりますが、これは絶対にやめてください。
頭皮は非常にデリケートです。爪で引っ掻くと、目に見えない小さな傷が無数につき、そこから雑菌が侵入したり、炎症を起こしたりします。
この頭皮の傷が、抜け毛や薄毛の引き金になることもあります。必ず「指の腹」で優しく洗うことを徹底してください。
シャンプーを直接頭皮につける
シャンプーの原液は濃度が高く、そのまま頭皮につけると刺激が強すぎる場合があります。
また、特定の場所に原液が集中することで、その部分だけが過剰に洗浄されたり、すすぎ残しが発生しやすくなったりします。
シャンプーは必ず手のひらでしっかり泡立ててから、髪全体、そして頭皮へと広げるようにしてください。
髪が濡れたまま寝てしまう
シャンプー後、髪を乾かさずに寝てしまうのは最悪の習慣の一つです。濡れた髪と頭皮は、枕との摩擦でキューティクルが剥がれやすく、髪が傷む原因になります。
さらに、濡れた頭皮は雑菌の絶好の繁殖場所です。雑菌が繁殖すると、ニオイやかゆみ、フケ、さらには脂漏性皮膚炎などを引き起こし、頭皮環境を著しく悪化させます。
必ずドライヤーで頭皮と髪をしっかり乾かしてから寝るようにしましょう。
頭皮に良くないNG習慣とその影響
| NG習慣 | 頭皮への主な影響 | 推奨される対策 |
|---|---|---|
| 熱すぎるお湯(40度以上) | 必要な皮脂を除去し、頭皮が乾燥する。 | 38度前後のぬるま湯で洗う。 |
| 爪を立てて洗う | 頭皮に傷がつき、炎症や雑菌繁殖の原因になる。 | 指の腹で優しくマッサージするように洗う。 |
| 濡れたまま寝る | 雑菌が繁殖しやすく、ニオイやかゆみの原因になる。 | ドライヤーで頭皮からしっかり乾かす。 |
シャンプー(洗い方)以外で見直すべき生活習慣
抜け毛対策は、シャンプーや洗い方の見直しだけでは十分ではありません。髪の健康は、体全体の健康状態と密接に関連しています。
日々の生活習慣を見直すことも、薄毛を防ぐためには非常に重要です。
栄養バランスの取れた食事
髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質の摂取は必須です。
また、タンパク質を髪の毛に合成するのを助ける「亜鉛」や、頭皮の血行を良くする「ビタミンE」、頭皮の新陳代謝を促す「ビタミンB群」などもバランス良く摂取することが求められます。
頭皮と髪の健康に必要な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質を髪に合成するのを助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂のバランスを整える。 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、納豆 |
外食やインスタント食品が多いと、脂質や糖質に偏りがちです。上記の栄養素を意識して、バランスの取れた食事を心がけましょう。
質の良い睡眠の確保
髪の成長には「成長ホルモン」が深く関わっています。成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。
特に、入眠後の深いノンレム睡眠時に多く分泌されるため、睡眠時間が不足したり、睡眠の質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が滞り、髪の成長に悪影響を及ぼします。
毎日6〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保し、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、質の良い睡眠を心がけることが大切です。
ストレス管理とリフレッシュ法
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させます。血管が収縮すると、頭皮への血流が悪くなり、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなります。
これが抜け毛や薄毛の原因となることがあります。現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりの解消法を見つけることが重要です。
ストレス対策の例
- 適度な運動(ウォーキング、ジョギング)
- 趣味の時間を持つ(読書、音楽鑑賞、映画)
- リラックスできる時間(入浴、瞑想)
これらを日常生活に取り入れ、上手にストレスと付き合っていくことが、頭皮の健康にもつながります。
喫煙や過度な飲酒の影響
喫煙は、ニコチンの作用で血管を強力に収縮させ、頭皮の血流を著しく悪化させます。また、ビタミンCなど髪の健康に必要な栄養素も大量に消費してしまいます。
抜け毛対策を本気で考えるなら、禁煙することが強く推奨されます。
適度な飲酒は血行を良くすることもありますが、過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、髪の毛の材料となるタンパク質の合成を妨げる可能性があります。
また、アルコールの分解には亜鉛やビタミンが消費されるため、栄養不足にもつながります。お酒はほどほどに楽しむ程度に留めましょう。
抜け毛・薄毛対策シャンプーの種類
市場には「抜け毛予防」「スカルプケア」を謳うシャンプーが数多く存在します。ここでは、代表的なシャンプーの種類とその特徴を解説し、どのような人に向いているかを紹介します。
アミノ酸系シャンプーの特徴
アミノ酸系シャンプーは、洗浄成分としてアミノ酸由来の成分(ココイルグルタミン酸~、ラウロイルメチルアラニン~など)を使用しています。
人間の皮膚や髪と同じ弱酸性で、洗浄力がマイルドなのが最大の特徴です。
必要な皮脂を落としすぎず、頭皮の潤いを保ちながら洗えるため、乾燥肌や敏感肌の人、そして抜け毛が気になり始めた初期段階の人に最も適しています。
泡立ちは控えめな製品もありますが、予洗いをしっかり行えば問題なく洗えます。
スカルプシャンプー(薬用・医薬部外品)とは
スカルプシャンプーは、髪そのものよりも「頭皮環境を整える」ことを目的としたシャンプーです。
「薬用」や「医薬部外品」と表示されているものは、厚生労働省が認可した有効成分が一定濃度配合されています。
例えば、フケやかゆみを防ぐ抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)や、雑菌の繁殖を抑える殺菌成分(ピロクトンオラミンなど)が配合されているものが多いです。
脂性肌でベタつきやニオイが気になる人、フケやかゆみに悩んでいる人に適しています。ただし、洗浄力が強い製品もあるため、乾燥肌の人は成分をよく確認する必要があります。
ノンシリコンシャンプーの役割
ノンシリコンシャンプーは、髪をコーティングするシリコン(ジメチコン、シクロメチコンなど)が配合されていないシャンプーを指します。
シリコンが毛穴に詰まることを懸念する人から選ばれることが多いです。洗い上がりがさっぱりとし、髪が軽くなる(ボリュームが出やすくなる)傾向があります。
ただし、シリコン自体が直接的な抜け毛の原因であるという科学的根拠は強くありません。シリコンの有無よりも、洗浄成分が自分の頭皮に合っているかどうかが重要です。
シリコンが入っていない分、髪がきしみやすい場合があるため、その場合はトリートメントで補う必要があります。
シャンプーの種類別特徴と適した頭皮タイプ
| シャンプーの種類 | 主な特徴 | 適した頭皮タイプ |
|---|---|---|
| アミノ酸系シャンプー | 洗浄力がマイルド。弱酸性で低刺激。頭皮の潤いを保ちやすい。 | 乾燥肌、敏感肌、抜け毛が気になり始めた人 |
| スカルプシャンプー(薬用) | 頭皮環境を整える目的。抗炎症・殺菌成分などが配合されている。 | 脂性肌、フケ・かゆみが気になる人 |
| ノンシリコンシャンプー | シリコン(コーティング剤)不使用。洗い上がりが軽い。 | さっぱりした洗い上がりが好みの人、髪のボリュームが欲しい人 |
自身の悩みに合わせた選択
最終的には、自分の頭皮の状態と悩みに合わせて選ぶことが大切です。「抜け毛が減る」と評判のシャンプーが、必ずしも自分に合うとは限りません。
まずは自分の頭皮タイプ(乾燥しているか、ベタついているか)を把握し、洗浄成分に注目して選びましょう。
使ってみて「かゆみが出ないか」「フケが増えないか」「洗い上がりが快適か」をチェックし、合わないと感じたら別のものを試す柔軟さも必要です。
シャンプー・洗い方に戻る
よくある質問
ここでは、抜け毛対策やシャンプー(洗い方)に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- シャンプーは朝と夜、どちらが良いですか?
-
基本的には「夜」のシャンプーを推奨します。
1日の活動で頭皮に蓄積した汗、皮脂、ホコリ、スタイリング剤などの汚れを、その日のうちにリセットすることが頭皮環境を健やかに保つために重要です。
また、夜にシャンプーすることで、睡眠中の清潔な頭皮環境を確保し、髪の成長を促す時間帯(成長ホルモンが分泌される時間帯)をサポートできます。
朝シャンは、寝ている間にかいた汗を流す目的では良いですが、夜にしっかり洗っている場合、朝はぬるま湯での予洗い(湯シャン)程度で十分な場合もあります。
洗いすぎによる乾燥を防ぐためにも、シャンプー剤を使った洗髪は1日1回(夜)を基本と考えるのが良いでしょう。
- 抜け毛が気になり始めたら育毛シャンプーを使うべきですか?
-
「育毛シャンプー」という名称の製品(多くはスカルプシャンプーや薬用シャンプー)は、頭皮環境を整え、フケやかゆみを防ぎ、健康な髪が育つ土壌を整えることを目的としています。
シャンプー自体に髪を生やす(発毛)効果はありません。
しかし、抜け毛の原因が頭皮環境の悪化(皮脂過剰や乾燥、炎症など)にある場合、これらのシャンプーに切り替えることで頭皮状態が改善し、結果として抜け毛が減る可能性はあります。
まずは自分の頭皮状態に合った洗浄成分のシャンプーを選ぶことが第一歩です。その上で、頭皮トラブルがある場合は薬用成分の入ったスカルプシャンプーを試す価値はあります。
- シャンプーを変えたら一時的に抜け毛が増えた気がします。
-
シャンプーを変更した直後に、一時的に抜け毛が増えたと感じることがあります。これは、新しいシャンプーの洗浄力や成分が頭皮に合わず、刺激になっている可能性があります。
特に、マイルドな洗浄力のシャンプーから洗浄力の強いシャンプーに変えた場合、頭皮が乾燥しやすくなることがあります。
また、逆も考えられます。もし、かゆみ、フケ、赤みなどを伴う場合は、そのシャンプーの使用を中止し、元のシャンプーに戻すか、さらに低刺激なものに変更することを検討してください。
数日様子を見ても改善しない、または悪化する場合は使用をやめましょう。
- 頭皮マッサージは抜け毛予防に効果がありますか?
-
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進する上で有効な手段です。頭皮が硬くなっていると血流が悪くなり、毛根に十分な栄養が届きにくくなります。
シャンプー中や、育毛剤を塗布した後などに、指の腹を使って頭皮全体を優しく動かす(こするのではなく、頭蓋骨から頭皮を動かすイメージ)マッサージを取り入れることは、抜け毛予防や健やかな髪を育てるために良い習慣と言えます。
ただし、力を入れすぎたり、爪を立てたりすると逆効果になるため、あくまで優しく行うことが大切です。
Reference
PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.
KOBAYASHI, Miwa, et al. Physiological and microbiological verification of the benefit of hair washing in patients with skin conditions of the scalp. Journal of Cosmetic Dermatology, 2016, 15.4: e1-e8.
XIAO, Lei, et al. A Timosaponin B‐II containing scalp care solution for improvement of scalp hydration, dandruff reduction, and hair loss prevention: A comparative study on healthy volunteers before and after application. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.3: 819-824.
LANJEWAR, Ameya, et al. Review on Hair Problem and its Solution. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 2020, 10.3: 322-329.
GEORGE, Neethu Mary; POTLAPATI, Amruthavalli. Shampoo, conditioner and hair washing. International Journal of Research, 2022, 8.1: 185.
SCHWARTZ, James R.; JOHNSON, Eric S.; DAWSON, Thomas L. Shampoos for normal scalp hygiene and dandruff. Cosmetic Dermatology: Products and Procedures, 2022, 165-174.
GUBITOSA, Jennifer, et al. Hair care cosmetics: From traditional shampoo to solid clay and herbal shampoo, a review. Cosmetics, 2019, 6.1: 13.
ZHANG, Yuchen, et al. Effect of shampoo, conditioner and permanent waving on the molecular structure of human hair. PeerJ, 2015, 3: e1296.