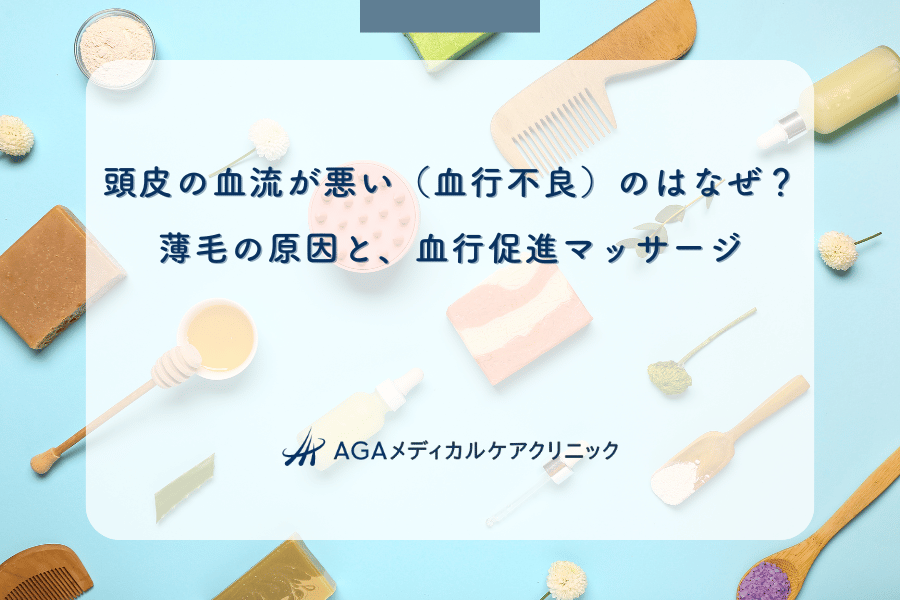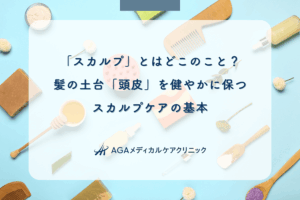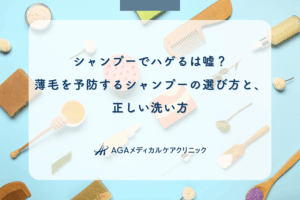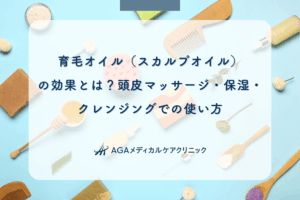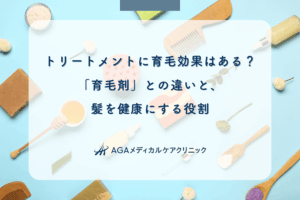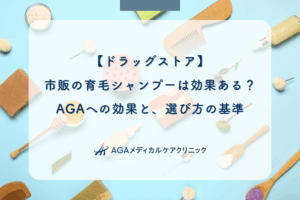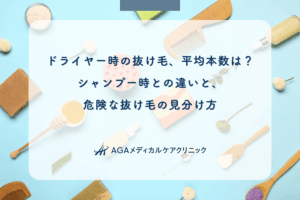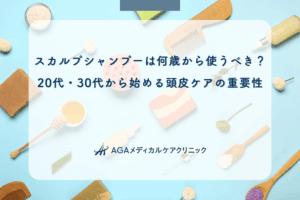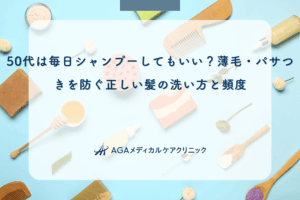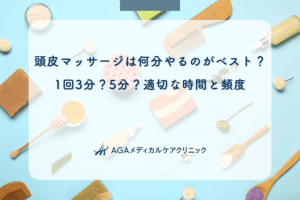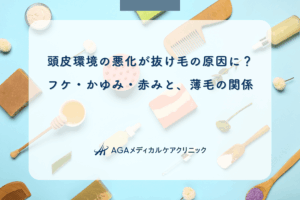「最近、抜け毛が増えた気がする」「髪にハリやコシがなくなってきた」と感じていませんか。もしかすると、その原因は「頭皮の血行不良」にあるかもしれません。
頭皮の血流は、髪の健やかな成長に欠かせない栄養素を運ぶ重要な役割を担っています。しかし、日々の生活習慣やストレスなど、さまざまな要因で血流は簡単に悪化してしまいます。
この記事では、なぜ頭皮の血流が悪くなるのか、それがどのように薄毛につながるのかを詳しく解説します。
さらに、ご自宅で簡単に実践できる頭皮の血行促進マッサージの方法や、生活習慣の改善点についてもご紹介します。
頭皮環境を整え、自信の持てる髪を取り戻すための第一歩として、ぜひご一読ください。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ頭皮の血流が悪い(血行不良)状態になるのか?
頭皮の血流が悪くなる、いわゆる「血行不良」は、一つの原因ではなく、複数の要因が絡み合って発生することがほとんどです。
私たちの日常生活に潜む、血流を妨げる主な原因を見ていきましょう。
生活習慣の乱れが招く血行不良
日々の生活習慣は、頭皮の血流に直接的な影響を与えます。特に食生活の乱れは深刻です。脂っこい食事や高カロリーな食べ物ばかりを摂取していると、血液がドロドロになりがちです。
粘度が高くなった血液は、毛細血管のような細い血管をスムーズに流れにくくなり、結果として頭皮への栄養供給が滞ります。
また、喫煙習慣も大きな要因です。タバコに含まれるニコチンには、血管を強力に収縮させる作用があります。喫煙によって全身の血管が細くなり、特に末端である頭皮の血流は著しく低下します。
過度なアルコール摂取も、分解の過程で血流を悪化させる要因となり得ます。
血流悪化につながる食生活の例
| 習慣 | 主な内容 | 血流への影響 |
|---|---|---|
| 脂質の過剰摂取 | 揚げ物、スナック菓子、脂身の多い肉 | 血液の粘度を高め、流れを悪くする。 |
| 塩分の過剰摂取 | 濃い味付け、加工食品 | 血圧を上昇させ、血管に負担をかける。 |
| 糖質の過剰摂取 | 清涼飲料水、菓子パン、白米の食べ過ぎ | 血糖値の急上昇が血管を傷つける可能性がある。 |
ストレスが血管を収縮させる
現代社会において、ストレスは避けて通れない問題です。仕事上のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、精神的なストレスを感じると、私たちの体は緊張状態に入ります。
このとき、自律神経のうち「交感神経」が優位に働きます。交感神経は、体を活動モードにする神経ですが、同時に血管を収縮させる働きも持っています。
この状態が慢性的に続くと、頭皮の血管も収縮したままになり、血行不良を引き起こします。ストレスを感じたときに、肩や首がこるのと同じように、頭皮も緊張し、硬くなっているのです。
運動不足による全身の血流低下
デスクワーク中心の生活や、日常的に体を動かす習慣がない場合、全身の筋力が低下します。
特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、下半身に溜まった血液を心臓に戻すポンプの役割を果たしています。運動不足でこのポンプ機能が弱まると、全身の血液循環が悪化します。
心臓から送り出される血液の勢いも弱まり、体の末端である頭皮にまで十分な血液が届きにくくなります。定期的な運動は、心肺機能を高め、全身の血流を促進するために重要です。
頭皮の硬さ(コリ)の影響
頭皮が硬い、いわゆる「凝っている」状態も、血行不良のサインであり、原因でもあります。
長時間同じ姿勢でいることによる首や肩のコリ、眼精疲労、ストレスによる緊張などが続くと、頭の筋肉(前頭筋、側頭筋、後頭筋)が強張り、頭皮全体の柔軟性が失われます。
硬くなった頭皮は、その下を通る毛細血管を圧迫し、血流を直接的に妨げます。頭皮を触ってみて、弾力がなく、カチカチに硬い場合は注意が必要です。
頭皮の血流(血行)と薄毛の深い関係
頭皮の血行不良が、なぜ薄毛や抜け毛に直結するのでしょうか。髪の毛が成長する仕組みと、血流の役割を理解することで、その関係性が見えてきます。
髪の成長に必要な栄養素が届かない
髪の毛は、「毛母細胞」という細胞が分裂を繰り返すことによって作られます。この毛母細胞が活発に活動するためには、十分な「栄養」と「酸素」が必要です。
そして、これらを毛母細胞まで運ぶのが、頭皮の毛細血管を流れる血液です。血流が悪くなると、毛母細胞が必要とする栄養素(タンパク質、亜鉛、ビタミンなど)や酸素が不足してしまいます。
栄養不足に陥った毛母細胞は、正常に分裂することができなくなり、結果として細く弱い髪しか作れなくなったり、髪の成長自体が止まってしまったりします。
髪の成長に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の代謝を助け、健康に保つ | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆 |
ヘアサイクル(毛周期)の乱れ
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」と呼ばれる寿命があります。
一本の髪の毛は、「成長期」(髪が太く長く伸びる時期)、「退行期」(成長が止まる時期)、「休止期」(髪が抜け落ちる時期)という流れを繰り返しています。
健康な頭皮では、このヘアサイクルの大部分(約85~90%)を成長期が占めています。
しかし、頭皮の血行不良によって栄養が不足すると、毛母細胞の活動が低下し、この大切な「成長期」が短縮してしまいます。
本来なら数年間続くはずの成長期が数ヶ月で終わってしまい、髪が十分に太く成長する前に退行期・休止期へと移行してしまうのです。
これにより、細く短い髪の毛が増え、全体のボリュームが失われ、薄毛が目立つようになります。
毛母細胞の活動低下
血流が悪化すると、栄養や酸素が届かないだけでなく、もう一つ問題が発生します。
それは、「老廃物の蓄積」です。細胞が活動すれば必ず老廃物が生まれますが、これも血液によって回収され、体外へ排出されます。
血行不良の状態では、この老廃物が毛母細胞の周辺に蓄積しやすくなります。老廃物が溜まった環境は、毛母細胞の活動をさらに妨げることになります。
栄養不足と老廃物の蓄積という二重の打撃により、毛母細胞は本来の働きができなくなり、健康な髪の育成が困難になります。
頭皮の血行不良を示すサイン
頭皮の血行不良は、自覚しにくいものですが、注意深く観察するといくつかのサインが現れます。早めに気づき、対策を講じることが大切です。
頭皮の色でチェック
健康な頭皮は、適度な血流があり、青白い色をしています。しかし、血行不良になると頭皮の色に変化が現れます。
自分で確認するのは難しいかもしれませんが、鏡を使ったり、ご家族に見てもらったりしてチェックしてみましょう。
頭皮の色と状態の目安
| 頭皮の色 | 状態 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| 青白い色 | 健康な状態 | 血流が良く、透明感がある。 |
| 黄色~茶色 | 注意が必要 | 血行不良、皮脂の酸化、代謝の低下。 |
| 赤い色 | 危険な状態 | 炎症、うっ血、強い刺激。 |
頭皮の硬さや弾力
健康な頭皮は柔らかく、指で動かすと皮膚が頭蓋骨の上をスムーズに動きます。一方、血行不良の頭皮は、筋肉が緊張し、老廃物が溜まることで硬くなります。
両手の指の腹で頭全体をつかむようにして、前後左右に動かしてみてください。
もし、頭皮がほとんど動かない、または動かすと痛みを感じるようであれば、頭皮が凝り固まり、血行不良に陥っている可能性が高いです。
抜け毛や髪質の変化
頭皮の血行不良による栄養不足が続くと、髪の毛に直接変化が現れます。
以前と比べて抜け毛の量が明らかに増えた場合、特に細く短い毛(成長しきる前に抜けてしまった毛)が目立つ場合は、ヘアサイクルが乱れているサインです。
また、「髪が細くなった」「ハリやコシがなくなった」「髪がうねるようになった」といった髪質の変化も、毛母細胞の活動が低下していることを示しています。
頭皮のかゆみやフケ
血行不良によって頭皮のターンオーバー(新陳代謝)が乱れると、頭皮のバリア機能が低下します。これにより、外部からのわずかな刺激にも敏感になり、かゆみを感じやすくなります。
また、ターンオーバーが正常に行われないと、古い角質がうまく剥がれ落ちず、フケとして目立つようになります。
特に、乾燥したカサカサしたフケが出る場合は、頭皮の乾燥と血行不良が関係している可能性があります。
自宅でできる!頭皮の血行促進マッサージ
頭皮の血行不良を改善するために、最も手軽で効果的な方法の一つが「頭皮マッサージ」です。硬くなった頭皮をほぐし、毛細血管の血流を直接的に促します。
マッサージの基本的な考え方
頭皮マッサージの目的は、硬くなった頭皮を柔らかくし、滞った血流を改善することです。力を入れすぎたり、爪を立てたりするのは逆効果です。頭皮を傷つけ、炎症を引き起こす可能性があります。
指の腹を使い、「気持ちいい」と感じる程度の優しい圧で、頭皮自体を動かすイメージで行います。リラックスした状態で行うことで、自律神経のバランスも整いやすくなります。
頭部全体の血流を促すマッサージ手順
シャンプー中やお風呂上がりなど、体が温まり血行が良くなっているタイミングで行うのがおすすめです。以下の手順で、頭部全体をまんべんなくほぐしましょう。
まず、両手の指の腹を使い、耳の上(側頭部)に当てます。円を描くように、ゆっくりと頭皮を動かしながら、少しずつ頭頂部に向かって移動させます。
側頭部は疲れが出やすい部分なので、念入りにほぐします。
次に、額の生え際(前頭部)に指を当てます。下から上へ、頭皮を引き上げるようにジグザグに動かしながら、頭頂部までマッサージします。
続いて、後頭部です。両手の指を組み、親指の付け根あたりを首の付け根(後頭部)に当てます。頭を少し後ろに倒し、頭の重みを利用して圧をかけながら、円を描くようにほぐします。
最後に、頭頂部(百会というツボがあるあたり)を、両手の指の腹で優しく、リズミカルに押したり離したりします。頭部全体の血流が集まる場所を刺激することで、マッサージの仕上げとします。
マッサージを行う際の注意点
頭皮マッサージは、正しく行わなければ効果が出ないばかりか、頭皮を傷める原因にもなります。以下の点に十分注意してください。
第一に、爪を絶対に立てないことです。必ず指の腹を使いましょう。爪が長い場合は特に注意が必要です。第二に、強くこすらないこと。マッサージは「押す」「もむ」「動かす」が基本です。
皮膚の表面を強くこすると、摩擦で頭皮が傷つき、炎症や抜け毛の原因になります。第三に、力を入れすぎないこと。「痛気持ちいい」は強すぎるサインかもしれません。「気持ちいい」と感じる圧で行いましょう。
マッサージの適切な頻度
頭皮マッサージは、毎日継続することが大切です。一度に長時間行うよりも、1回あたり3分から5分程度を目安に、毎日続ける方が効果的です。
シャンプーのついでに行う、寝る前のリラックスタイムに取り入れるなど、ご自身の生活の中で習慣化しやすいタイミングを見つけましょう。
継続することで、頭皮の状態は少しずつ改善していきます。
マッサージ以外の頭皮血流改善アプローチ
頭皮マッサージは有効な手段ですが、根本的な血行不良を改善するためには、体質そのものを見直す生活習慣の改善が重要です。マッサージと並行して、以下の点にも取り組みましょう。
バランスの取れた食生活
髪の毛は、私たちが食べたものから作られます。特に、髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮環境を整えるビタミンB群やビタミンEは、健康な髪を育てるために必要です。
特定の食品に偏るのではなく、様々な食材をバランスよく摂ることを心がけましょう。
血流改善と育毛に役立つ栄養素
| 栄養素 | 期待される働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンE | 血管を広げ、血流を良くする。 | アーモンド、かぼちゃ、アボカド |
| EPA・DHA | 血液をサラサラにする。 | 青魚(サバ、イワシ、アジ) |
| カプサイシン | 血行を促進し、体を温める。 | 唐辛子、キムチ |
良質な睡眠の確保
睡眠中は、成長ホルモンが分泌され、体中の細胞が修復・再生される時間です。頭皮や毛母細胞も例外ではありません。
睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、自律神経のバランスも崩れて交感神経が優位になりがちです。これにより血管が収縮し、頭皮の血流が悪化します。
最低でも6〜7時間、できれば質の高い睡眠を確保するよう努めましょう。寝る直前のスマートフォン操作やカフェイン摂取を避けることも有効です。
適度な運動の習慣化
全身の血流を良くするためには、適度な運動が効果的です。特にウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、心肺機能を高め、全身の血液循環を活発にします。
また、ストレッチやヨガは、筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果を高めるため、ストレスによる血行不良の改善にも役立ちます。激しい運動である必要はありません。
日常生活の中で、エスカレーターではなく階段を使う、一駅分歩くなど、小さなことから始めてみましょう。
- ウォーキング(早歩きで20分以上)
- ストレッチ(首・肩周りを中心に)
- 軽い筋力トレーニング(スクワットなど)
正しいシャンプー方法
毎日のシャンプーも、頭皮環境に大きな影響を与えます。洗浄力の強すぎるシャンプーや、熱すぎるお湯での洗髪は、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥やバリア機能の低下を招きます。
また、すすぎ残しは毛穴の詰まりや炎症の原因となります。シャンプーはぬるま湯(38度程度)で行い、指の腹で頭皮を優しく洗い、すすぎは十分すぎるほど丁寧に行うことが大切です。
間違ったシャンプー習慣は、頭皮環境を悪化させ、血行不良を助長することにもなりかねません。
頭皮ケアアイテムの活用
セルフマッサージや生活習慣の改善に加えて、専用のケアアイテムを活用することで、より効果的に頭皮の血行促進をサポートできます。
育毛剤や発毛剤の役割
育毛剤や発毛剤の中には、頭皮の血行を促進することを目的とした成分が含まれているものが多くあります。
例えば、育毛剤に含まれる「センブリエキス」や「ビタミンE誘導体」、発毛剤の有効成分である「ミノキシジル」などは、血管を拡張させたり、血流を促したりする働きが知られています。
頭皮マッサージと併用することで、これらの有効成分が角質層まで浸透しやすくなり、相乗効果が期待できます。ご自身の頭皮の状態や目的に合わせて、適切な製品を選びましょう。
ケアアイテムの主な分類
| 種類 | 主な目的 | 分類(例) |
|---|---|---|
| 育毛剤 | 頭皮環境を整え、抜け毛を防ぎ、育毛を促す。 | 医薬部外品 |
| 発毛剤 | 毛母細胞に働きかけ、新たな髪の毛を生やす。 | 第一類医薬品 |
| スカルプエッセンス | 頭皮の保湿や、フケ・かゆみの防止。 | 化粧品 |
頭皮マッサージ器(スカルプケアブラシ)
「自分でマッサージするのは疲れる」「うまくできているか分からない」という方には、頭皮マッサージ器(スカルプケアブラシ)の活用も一つの方法です。
電動で頭皮を揉みほぐしてくれるものや、シャンプー時に使えるシリコン製のブラシなど、様々な種類があります。
人の手では難しいリズミカルな刺激や、均一な圧をかけることができ、効率的に頭皮をほぐす手助けとなります。
ただし、これも力を入れすぎたり、長時間使用しすぎたりしないよう、説明書をよく読んで正しく使用することが重要です。
炭酸シャンプーの効果
近年注目されている炭酸シャンプーも、血行促進に役立つアイテムです。炭酸ガス(二酸化炭素)には、皮膚から浸透して毛細血管を拡張させる性質があります。
炭酸シャンプーを使用することで、高濃度の炭酸ガスが頭皮に行き渡り、血流が促進される効果が期待できます。
また、炭酸の細かな泡が、通常のシャンプーでは落としきれない毛穴の奥の皮脂汚れや古い角質を吸着して除去する働きもあり、頭皮を清潔に保つ上でも有効です。
頭皮マッサージに戻る
頭皮の血行不良に関するよくある質問
- 頭皮マッサージはいつ行うのが効果的ですか?
-
頭皮マッサージは、体が温まり血行が良くなっているタイミングで行うのが最も効果的です。具体的には、入浴中やシャンプー時、またはお風呂上がりの体がポカポカしている時がおすすめです。
また、夜寝る前に行うと、リラックス効果で睡眠の質を高めることにもつながり、成長ホルモンの分泌を助ける相乗効果も期待できます。
- マッサージ以外に即効性のある方法はありますか?
-
血行不良は日々の積み重ねで起きているため、残念ながら「これだけやればすぐに治る」という魔法のような方法はありません。
しかし、一時的に血流を良くする方法として、首や肩を温めること、軽い運動(ストレッチやウォーキング)をすることは有効です。
首元には太い血管が通っているため、ホットタオルなどで温めるだけでも頭部への血流は改善しやすいです。
ただし、根本的な改善には、マッサージや生活習慣の見直しを継続することが必要です。
- 食事で特に気をつけるべき栄養素は何ですか?
-
髪の成長のためには、まず主成分となる「タンパク質」が重要です。
その上で、血流改善をサポートする栄養素として「ビタミンE」(アーモンド、アボカドなど)、「EPA・DHA」(青魚)、「鉄分」(レバー、ほうれん草)などを意識して摂ると良いでしょう。
逆に、血液をドロドロにする原因となる動物性脂肪(脂身の多い肉やバター)や、トランス脂肪酸(マーガリン、スナック菓子)の摂りすぎには注意が必要です。
- 頭皮が硬いのは遺伝ですか?
-
頭皮の硬さ自体が直接遺伝するわけではありません。
しかし、ストレスを感じやすい体質や、筋肉が緊張しやすい骨格、特定の生活習慣(例えば、デスクワーク中心で肩がこりやすいなど)は、親から子へ似ることがあります。
その結果として、頭皮が硬くなりやすい傾向が似る可能性はあります。
しかし、頭皮の硬さの多くは後天的な要因によるものですので、日々のケアやマッサージによって十分に改善することが可能です。
Reference
BOWERS, R. E. Partial alopecia due to scalp massage. British Journal of Dermatology, 1950, 62.6: 262-264.
SHIMADA, Kunio, et al. Effects of scalp massage on physiological and psychological indices. Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan, 2013, 47.3: 202-208.
KOYAMA, Taro, et al. Standardized scalp massage results in increased hair thickness by inducing stretching forces to dermal papilla cells in the subcutaneous tissue. Eplasty, 2016, 16: e8.
ENGLISH, Robert S.; BARAZESH, James M. Self-assessments of standardized scalp massages for androgenic alopecia: Survey results. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 167-178.
KIM, In-Hong; KIM, Tae-Young; KO, Young-Wan. The effect of a scalp massage on stress hormone, blood pressure, and heart rate of healthy female. Journal of physical therapy science, 2016, 28.10: 2703-2707.
KALAM, Mohd Afsahul, et al. Effect of Oral Unani Formulations and Head Massage Therapy followed by Ḥijāma Bi’l Shart (Wet Cupping) in Diffuse Hair Loss (Intithār al-Sha ‘r): A Case Study. Hippocratic Journal of Unani Medicine, 2023, 18.1: 24-26.
TKACHENKO, Elizabeth, et al. Complementary and alternative medicine for alopecia areata: A systematic review. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 88.1: 131-143.
OH, Gang-Su; KIM, Sung-Nam. Effects of scalp treatment using combinational massage technique on human physiology. Journal of Fashion Business, 2008, 12.3: 87-98.
SEUNG-HWA, Baek. Research Methods on Scalp and Hair Management through the Pass of Time. Journal of Society of Preventive Korean Medicine, 2003, 7.1: 123-132.