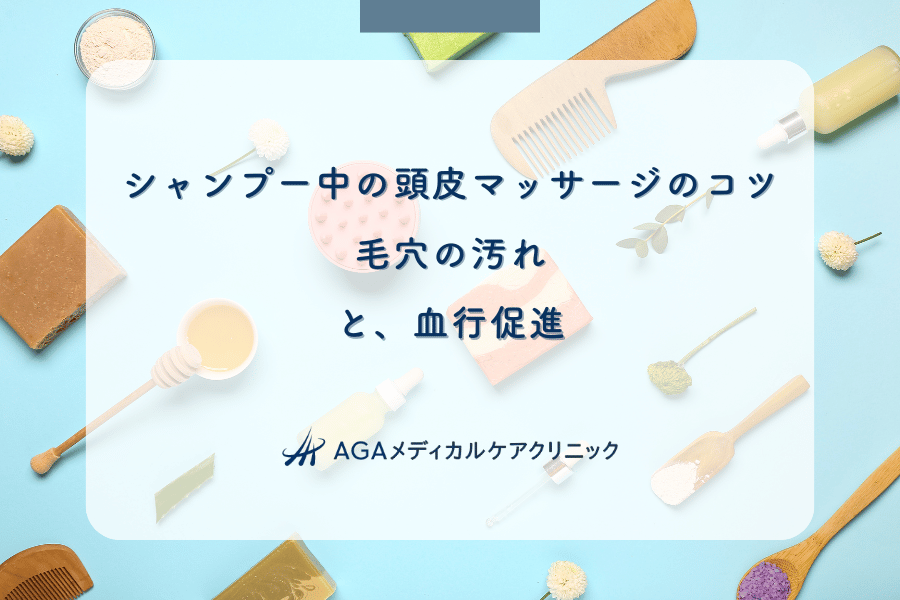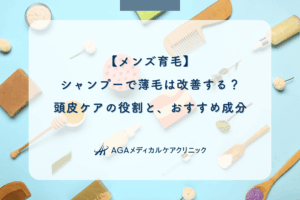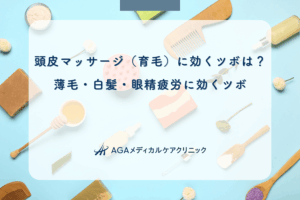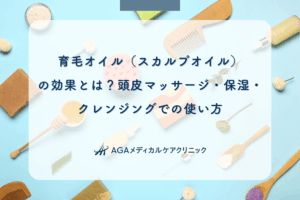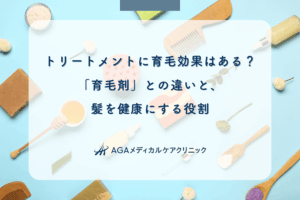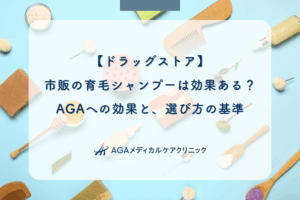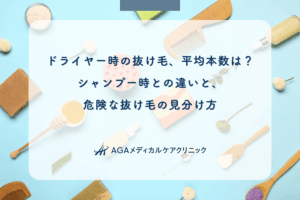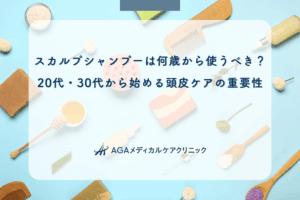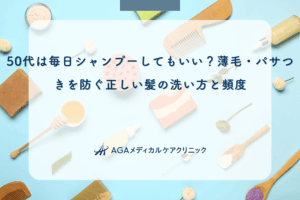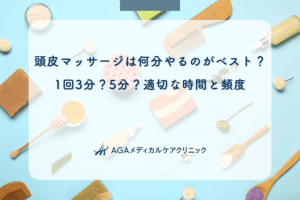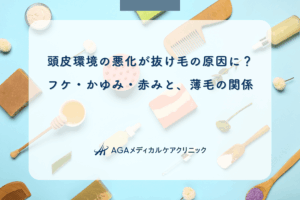毎日のシャンプー時間を、単なる「髪を洗う時間」から「頭皮をケアする時間」に変えてみませんか。男性の頭皮は皮脂の分泌が多く、毛穴が詰まりやすい傾向にあります。
シャンプー中の頭皮マッサージは、この頑固な毛穴の汚れを効果的に浮き上がらせる手助けをします。
さらに、頭皮の血行を促進することで、髪の成長に必要な栄養素が行き渡りやすい環境を整えることが期待できます。
この記事では、育毛に関心を持つ男性に向けて、毛穴の汚れと血行促進という二つの側面に注目し、シャンプー中に行う頭皮マッサージの具体的なコツと注意点を詳しく解説します。
正しい方法を学び、日々の習慣に取り入れて、健やかな頭皮環境を目指しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜシャンプー中の頭皮マッサージが注目されるのか
多くの方が日課として行うシャンプーですが、その時間を活用した頭皮マッサージが、今改めてその重要性を見直されています。
単に髪の汚れを落とすだけでなく、頭皮環境そのものにアプローチする行為として、特に男性のヘアケアにおいて注目を集めているのです。
頭皮環境と髪の健康のつながり
髪の健康は、その土壌である頭皮の状態に大きく左右されます。畑作物が豊かな土壌で育つのと同様に、髪もまた健やかな頭皮環境を必要とします。
頭皮が乾燥しすぎたり、逆に皮脂でベタついたり、あるいは血行が悪くなったりすると、毛根に十分な栄養が届かず、髪の成長に影響が出る可能性があります。
シャンプー中のマッサージは、この頭皮環境を整えるための直接的なアプローチの一つです。
シャンプー時間の有効活用
忙しい現代人にとって、ヘアケアだけに多くの時間を割くのは難しいかもしれません。しかし、シャンプーはほとんどの人が毎日行う習慣です。
このシャンプーの時間を利用して頭皮マッサージを取り入れることは、新たな時間を確保することなく、ケアを習慣化できるという大きな利点があります。
効率的に頭皮ケアを行いたいと考える人にとって、シャンプー中のマッサージは非常に合理的な方法と言えるでしょう。
毛穴の汚れと血行不良のサイン
頭皮のベタつき、フケ、かゆみ、あるいは抜け毛の増加。これらは、頭皮環境が悪化しているサインかもしれません。
特に毛穴に詰まった皮脂汚れや、頭皮が硬くなることによる血行不良は、髪の健やかな成長を妨げる要因となります。
シャンプー中の頭皮マッサージは、これらの問題に早期に対処し、頭皮を良い状態に保つための一助となります。
頭皮マッサージの二大効果 毛穴洗浄と血行促進
シャンプー中に行う頭皮マッサージには、多くのメリットがありますが、特に育毛を考える上で重要なのが「毛穴の洗浄」と「血行の促進」です。
この二つの効果について、もう少し詳しく見ていきましょう。
毛穴の奥の皮脂汚れを浮かす
男性の頭皮は女性に比べて皮脂の分泌量が多い傾向にあります。この皮脂が古い角質やホコリと混ざり合うと、毛穴を塞ぐ「角栓」となり、通常のシャンプーだけではなかなか落としきれないことがあります。
頭皮マッサージは、指の腹を使って頭皮を動かすことで、毛穴の奥に詰まったこれらの汚れを物理的に揉み出し、浮き上がらせる働きを助けます。
これにより、シャンプーの洗浄成分が毛穴の奥まで届きやすくなり、頭皮をより清潔な状態に保つことができます。
血行を促し頭皮に栄養を届ける
髪の毛は、毛根にある毛母細胞が細胞分裂を繰り返すことによって成長します。この毛母細胞の活動エネルギー源となるのが、血液によって運ばれてくる栄養素です。
頭皮が硬くなったり、血行が悪くなったりすると、必要な栄養素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。
頭皮マッサージによって頭皮の筋肉をほぐし、血行を物理的に促すことで、毛根への栄養供給をサポートし、髪が育ちやすい環境を整えることが期待できます。
頭皮マッサージがもたらす主な利点
| 側面 | 期待できる効果 | 補足 |
|---|---|---|
| 毛穴ケア | 皮脂汚れの除去サポート | シャンプーの洗浄力を助け、頭皮を清潔に保つ |
| 血行促進 | 栄養運搬のサポート | 頭皮の筋肉をほぐし、毛根への栄養供給を助ける |
| リラックス | 心身の緊張緩和 | 頭皮のツボを刺激し、日々のストレス軽減にも |
リラクゼーション効果も期待できる
頭皮には多くのツボ(経穴)が集中しています。マッサージによってこれらのツボが適度に刺激されると、自律神経のバランスが整い、心身の緊張がほぐれるリラクゼーション効果も期待できます。
日々のストレスは頭皮の血行を悪化させる一因とも言われます。シャンプー中のマッサージは、心身両面から健やかな頭皮環境づくりをサポートする時間となり得ます。
シャンプー選びがマッサージの質を高める
頭皮マッサージを行う際、どのようなシャンプー剤を使うかも重要なポイントです。
マッサージに適したシャンプーを選ぶことで、頭皮への負担を減らし、マッサージの効果をより高めることにつながります。
頭皮マッサージに適したシャンプーとは
頭皮マッサージには、摩擦を軽減するために「泡立ちの良さ」が求められます。きめ細かく弾力のある泡は、指と頭皮の間のクッションとなり、マッサージ中の物理的な刺激から頭皮を守ります。
また、アミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を主体としたシャンプーは、洗浄力が比較的マイルドで頭皮の潤いを奪いすぎないため、マッサージを伴うシャンプーに適していると言えるでしょう。
避けたいシャンプーの傾向
洗浄力が非常に強いシャンプー剤(例えば、一部の高級アルコール系シャンプー)は、頭皮に必要な皮脂まで取り除いてしまう可能性があります。
マッサージによって毛穴の汚れが浮き上がっている状態では、過度な洗浄力がかえって頭皮を乾燥させ、バリア機能の低下を招くことも考えられます。
また、シリコン(ジメチコンなど)が多く含まれるシャンプーは、すすぎ残しがあると毛穴を塞ぐ原因にもなり得るため、マッサージ後は特に丁寧なすすぎが必要です。
頭皮マッサージを考慮したシャンプー選び
| 観点 | 推奨される傾向 | 注意したい傾向 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | アミノ酸系、ベタイン系(マイルドな洗浄力) | 強すぎる洗浄成分(必要な皮脂まで除去) |
| 泡立ち | きめ細かく弾力のある泡(摩擦軽減) | 泡立ちが悪い(摩擦が強くなる) |
| 頭皮ケア成分 | 保湿成分、抗炎症成分配合 | 刺激の強い添加物(香料、着色料など) |
洗浄力と保湿のバランス
最終的に重要なのは、洗浄力と保湿力のバランスです。毛穴の汚れはしっかり落としつつも、頭皮の潤いは保つ。そんなシャンプーを選ぶことが、頭皮マッサージを安全かつ効果的に行うための鍵となります。
自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、混合肌など)を理解し、それに合ったシャンプーを選ぶように心がけましょう。
実践!シャンプー中に行う頭皮マッサージの基本手順
それでは、具体的にシャンプー中に行う頭皮マッサージの基本的な流れを紹介します。正しい手順を理解し、頭皮を傷つけないように丁寧に行うことが大切です。
マッサージ前の準備(予洗い)
シャンプー剤を髪につける前に、まずはぬるま湯(38度程度が目安)で髪と頭皮をしっかりと予洗いします。この予洗いだけで、髪についたホコリや汚れの多くは落ちると言われています。
また、頭皮を温めて毛穴を開きやすくする効果もあります。時間をかけて、頭皮全体にお湯が行き渡るように丁寧に洗い流しましょう。
効果的な泡立て方
シャンプー剤は、直接頭皮につけるのではなく、手のひらで軽く泡立ててから髪全体になじませるのが基本です。
泡立てが不十分だと、洗浄成分が頭皮に均一に行き渡らず、またマッサージ時の摩擦が大きくなってしまいます。
もし泡立ちが悪い場合は、一度軽く洗い流してから二度洗い(泡立て)を行うか、泡立てネットを使用するのも一つの方法です。
頭皮マッサージシャンプーの基本工程
| 工程 | 内容と目的 |
|---|---|
| 1. 予洗い | ぬるま湯で髪と頭皮の汚れを浮かし、毛穴を開きやすくする。 |
| 2. 泡立て | シャンプー剤を手のひらで泡立て、摩擦を防ぐクッションを作る。 |
| 3. マッサージ洗浄 | 指の腹を使い、頭皮を動かすように洗い、毛穴の汚れと血行にアプローチする。 |
| 4. すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて徹底的に洗い流す。 |
指の腹を使った正しい洗い方
マッサージを行う際は、絶対に爪を立てず、指の腹を使います。指の腹を頭皮にしっかりと密着させ、「頭皮をこする」のではなく、「頭皮そのものを動かす」ようなイメージで行います。
円を描くように、あるいはジグザグに動かしながら、生え際から頭頂部、側頭部から頭頂部、後頭部(襟足)から頭頂部へと、下から上に向かって少しずつ位置をずらしながら頭皮全体をマッサージしていきます。
すすぎ残しを防ぐ徹底的な洗い流し
マッサージが終わったら、すすぎは非常に重要です。シャンプー剤や浮き上がった汚れが頭皮に残っていると、それがかゆみやフケ、毛穴詰まりの新たな原因になってしまいます。
予洗いよりも時間をかけるくらいの意識で、髪の生え際、耳の後ろ、襟足など、すすぎ残しやすい部分も意識して、ぬるま湯で徹底的に洗い流しましょう。
シャワーヘッドを頭皮に近づけて、指の腹で髪をかき分けながら洗い流すと効果的です。頭皮にぬるつきがなくなるまで、しっかりとすすぎます。
頭皮マッサージの効果を高める指の動かし方
基本の手順を覚えたら、次はマッサージの効果をさらに高めるための「指の動かし方」のコツに注目しましょう。力加減や動かす方向が重要です。
圧のかけ方と力加減の目安
力加減は、「気持ち良い」と感じる程度が最適です。強すぎると頭皮を傷めたり、かえって筋肉を緊張させてしまったりする可能性があります。
指の腹を頭皮に固定したら、皮膚の表面だけをこするのではなく、頭蓋骨から頭皮を「剥がす」ようなイメージで、指圧を加えながらゆっくりと動かします。
指に力を入れすぎず、腕の重みを利用するような感覚で行うと良いでしょう。
生え際から頭頂部への流れ
特に前頭部(生え際)から頭頂部にかけては、血行が滞りやすい部分と言われています。両手の指の腹を額の生え際に置き、頭頂部に向かってゆっくりと引き上げるようにマッサージします。
これを数回繰り返します。ジグザグに動かしながら進めるのも効果的です。
部位別マッサージのコツ
| 部位 | 動かし方のイメージ | 特に意識したいこと |
|---|---|---|
| 前頭部(生え際) | 下から上へ引き上げるように | 頭皮全体を動かす意識 |
| 側頭部(耳の上) | 円を描くように揉みほぐす | 耳周りの筋肉をほぐす |
| 後頭部(襟足) | 下から上へ持ち上げるように | 首の付け根の緊張を緩和 |
側頭部と後頭部のほぐし方
側頭部(耳の上あたり)は、両手で頭を包み込むように指の腹を当て、円を描くように優しく揉みほぐします。この部分は、食事の際によく使う筋肉(側頭筋)があり、疲れが溜まりやすい場所でもあります。
後頭部(襟足あたり)は、両手の指を組むようにして頭皮をつかみ、頭頂部に向かって引き上げるように動かします。首や肩のコリとも関連が深いため、リラックスしながら行いましょう。
やってはいけないNGな頭皮マッサージ
良かれと思って行っている頭皮マッサージが、実は頭皮にダメージを与えている可能性もあります。ここで、避けるべきNGな方法を確認しておきましょう。
爪を立てる行為の危険性
これは最も避けるべき行為です。頭皮は非常にデリケートなため、爪を立てて洗うと(たとえ無意識であっても)、頭皮の表面に無数の細かい傷がついてしまいます。
この傷から雑菌が侵入して炎症を起こしたり、頭皮のバリア機能が低下して乾燥やかゆみを引き起こしたりする原因となります。必ず「指の腹」を使うことを徹底してください。
強すぎるマッサージのリスク
「ゴシゴシ」と力任せに強くこするマッサージも危険です。一時的にスッキリした感覚があるかもしれませんが、頭皮への摩擦が大きすぎると、必要な角質まで剥がしてしまい、バリア機能の低下を招きます。
また、強い圧迫は毛細血管を傷つけたり、頭皮の炎症を引き起こしたりする可能性も否定できません。力加減はあくまで「気持ち良い」範囲内に留め、優しく丁寧に行うことが大切です。
頭皮マッサージの注意点まとめ
| NG行為 | 頭皮への影響 | 正しい対処 |
|---|---|---|
| 爪を立てる | 頭皮に傷がつき、炎症や乾燥の原因に | 必ず「指の腹」を使う |
| 強すぎる力でこする | 摩擦によるダメージ、バリア機能の低下 | 「気持ち良い」程度の力加減で頭皮を動かす |
| 長時間のマッサージ | 必要な皮脂まで奪い、乾燥を助長 | トータルで3~5分程度を目安にする |
マッサージの頻度と時間
マッサージのやり過ぎも良くありません。シャンプー中のマッサージは、シャンプーの泡立てからすすぎまで含めて、トータルで3分から5分程度を目安にしましょう。
あまり長時間行うと、頭皮に必要な皮脂まで落としすぎてしまい、かえって乾燥を招くことになります。
頻度としては、毎日のシャンプー時に行うこと自体は問題ありませんが、その日の頭皮の状態(乾燥していないか、ヒリヒリしないか)を確認しながら、力加減や時間を調整することが重要です。
頭皮マッサージ後のアフターケア
シャンプーとマッサージで頭皮を清潔な状態に整えたら、その後のアフターケアも髪の健康を維持するために重要です。洗った後の「乾かし方」と「保湿」がポイントになります。
タオルドライの正しい方法
濡れた髪はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。ゴシゴシと強くこするように拭くと、髪の毛同士が摩擦しあい、キューティクルが剥がれたり傷んだりする原因になります。
タオルで髪を挟み込み、ポンポンと優しく叩くようにして水分を吸い取ります。頭皮に関しても同様に、タオルを頭皮に押し当てるようにして水分を取り除きましょう。
ドライヤーでの乾かし方
自然乾燥は絶対に避けてください。髪が濡れたままの時間が長いと、頭皮で雑菌が繁殖しやすくなり、臭いやかゆみの原因となります。
また、キューティクルが開いたままになり、髪の内部の水分やタンパク質が流出しやすくなります。
ドライヤーは、頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が当たり続けないように、常にドライヤーを振りながら乾かします。
まずは髪の根元(頭皮)から乾かし、全体が8割方乾いたら、冷風に切り替えて仕上げると、キューティクルが引き締まり、髪にツヤが出やすくなります。
保湿(育毛剤やローション)の重要性
シャンプー後の頭皮は、汚れと共に皮脂もある程度洗い流されているため、非常に清潔であると同時に、乾燥しやすい状態でもあります。
このタイミングで、育毛剤や頭皮用ローションを使用して保湿を行うことは非常に効果的です。毛穴がきれいになっているため、有用成分が角質層まで浸透しやすくなっています。
育毛剤などを塗布した後は、再度、指の腹を使って頭皮全体に優しくなじませるようにマッサージ(押さえるように)すると良いでしょう。
- 丁寧なタオルドライ(こすらない)
- ドライヤーによる速やかな乾燥(根元から)
- 清潔な頭皮への保湿(育毛剤・ローション)
頭皮マッサージに戻る
Q&A
シャンプー中の頭皮マッサージに関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 頭皮マッサージは毎日行うべきですか?
-
はい、シャンプー自体を毎日行うのであれば、その際のマッサージも毎日行っても問題ありません。ただし、前述の通り「正しい方法」で行うことが前提です。
爪を立てたり、強くこすりすぎたりする方法を毎日続けると、逆効果になります。指の腹で優しく、3分から5分程度の適切な時間で行うことを心がけてください。
もし頭皮に赤みやヒリヒリ感、痛みなどを感じる場合は、マッサージを一時中断し、力の入れすぎや洗いすぎがなかったかを見直しましょう。
- マッサージを行う一番良いタイミングはいつですか?
-
最も一般的で習慣化しやすいのは、入浴時の「シャンプー中」です。
体が温まることで頭皮の血行も良くなっており、毛穴も開きやすいため、マッサージによる毛穴洗浄や血行促進の効果が期待しやすいタイミングと言えます。
シャンプーの泡が摩擦を軽減してくれるため、頭皮への負担も少なく済みます。
シャンプー中以外に行う場合は、頭皮が乾いた状態でのマッサージとなり、摩擦が大きくなりやすいため、頭皮用のローションやオイルなどを使用して滑りを良くする工夫が必要です。
- 頭皮マッサージで髪の毛は増えますか?
-
頭皮マッサージが直接的に「発毛」を引き起こしたり、「髪の毛を増やす」ことを保証するものではありません。
髪の毛の成長には、遺伝、ホルモンバランス、栄養状態、生活習慣など、非常に多くの要因が複雑に関わっています。
しかし、頭皮マッサージは、毛穴の詰まりを改善し、頭皮の血行を促進することで、「髪の毛が健やかに育つための土壌(頭皮環境)を整える」ための重要なケアの一つです。
育毛剤の浸透を助ける役割も期待できるため、薄毛や抜け毛対策の一環として、日々のケアに取り入れる価値は非常に高いと言えます。
- マッサージをすると抜け毛が増えた気がするのですが。
-
マッサージを始めた初期に、一時的に抜け毛が増えたと感じることがあります。
これは、マッサージの刺激によって、すでに休止期(髪が抜け落ちる準備期間)に入っていた髪の毛が抜け落ちやすくなるためと考えられます。
これらは、いずれ自然に抜け落ちるはずだった髪の毛です。正しい方法(爪を立てず、優しく)で行っている限り、マッサージが原因で健康な髪が抜けることはありません。
ただし、数週間続けても抜け毛が明らかに増え続ける場合や、頭皮に異常(強いかゆみや痛み)を感じる場合は、マッサージの方法が間違っているか、他の原因が考えられるため、専門家に相談することも検討してください。
Reference
BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.
DHANESH, Musale Shreya; SANTOSH, Bhujbal Rutuja; NAIKAWADI, Nishigandha D. Revolutionizing Hair Care with Cosmetic Products. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development, 2024, 12.3: 157-158.
AL-WORAFI, Yaser Mohammed. Evidence-Based Complementary, Alternative and Integrated Medicine and Efficacy and Safety: Hair Care. In: Handbook of Complementary, Alternative, and Integrative Medicine. CRC Press. p. 920-938.
SHIMADA, Kunio, et al. Effects of scalp massage on physiological and psychological indices. Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan, 2013, 47.3: 202-208.
ROBBINS, Clarence R. Chemical and physical behavior of human hair. New York, NY: Springer New York, 2002.
KAUR, Manpreet. Hair hygiene. Dr.(Mrs.) Indrajit Walia, Principal National Institute of Nursing Education Dr. Lakhbir Dhaliwal, Professor & Head, 2010, 16.
PUNYANI, Supriya, et al. The impact of shampoo wash frequency on scalp and hair conditions. Skin appendage disorders, 2021, 7.3: 183-193.
LANJEWAR, Ameya, et al. Review on Hair Problem and its Solution. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 2020, 10.3: 322-329.
HAI, Nguyen Dao Xuan; THINH, Nguyen Truong. Scalp massage therapy according to symptoms based on Vietnamese traditional medicine. In: International Conference on Innovative Technology, Engineering and Science. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 233-244.
OH, Gang-Su; KIM, Sung-Nam. Effects of scalp treatment using combinational massage technique on human physiology. Journal of Fashion Business, 2008, 12.3: 87-98.