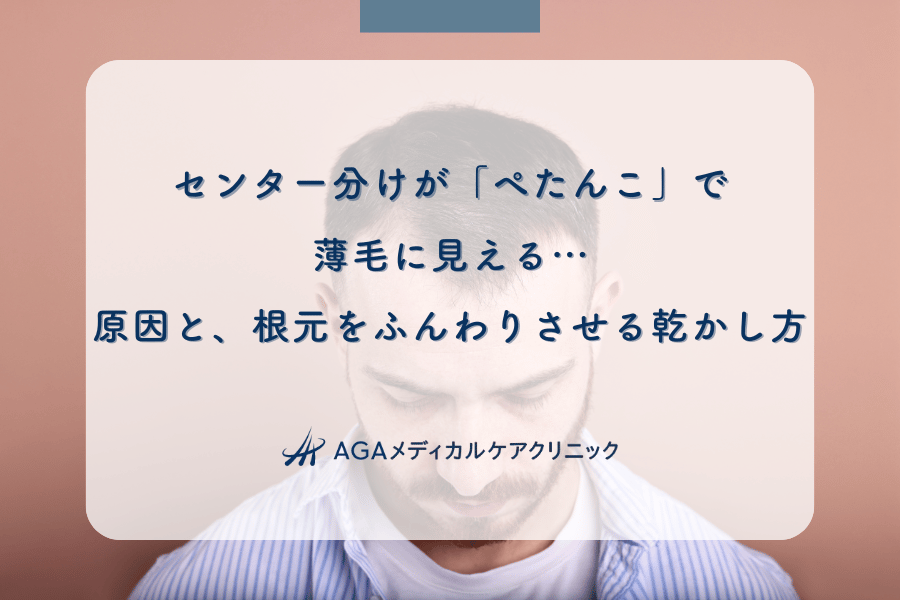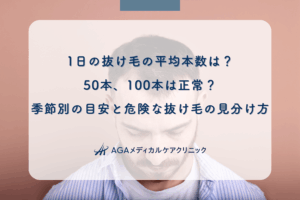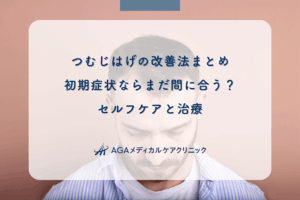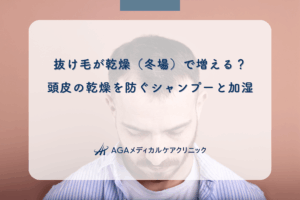鏡の前でセンター分けにスタイリングしたものの、どうも根元が「ぺたんこ」で決まらない。それどころか、地肌が透けて見えて薄毛のように感じてしまう…。
そんな悩みを抱えていませんか。センター分けは知的な印象を与える人気のスタイルですが、一歩間違えると髪のボリューム不足が目立ちやすくなります。
この記事では、なぜセンター分けがぺたんこになってしまうのか、その根本的な原因を深掘りします。
さらに、美容室で仕上げてもらったような、根元からふんわりとしたボリューム感を自宅で再現するための「正しい乾かし方」を徹底的に解説します。
毎日のヘアケアを見直すことで、あなたの印象は大きく変わるはずです。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜあなたのセンター分けは「ぺたんこ」になるのか?
センター分けがぺたんこになってしまう背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
単に髪質の問題だと諦める前に、まずはその原因を正しく理解することが、ふんわりヘアへの第一歩です。
髪のボリュームダウンが薄毛に見える仕組み
センター分けは、髪を左右均等に分けるスタイルです。このため、分け目の部分が直線的に露出し、頭皮が他の髪型よりも見えやすくなります。
ここで髪の根元が立ち上がらず、頭皮に張り付くように「ぺたんこ」になってしまうと、分け目の直線がさらに強調されます。
結果として、地肌の見える面積が広くなったように感じさせ、実際以上に髪が薄く、寂しい印象を与えてしまうのです。
特に、つむじ周辺から額にかけては、もともと髪が薄くなりやすい部分でもあります。
センター分けにすることで、その部分のボリューム不足がダイレクトに視線を集めてしまうため、薄毛の悩みが深刻化しやすいのです。
頭皮環境と髪のハリ・コシの関係
髪の根元がふんわりと立ち上がるためには、髪そのものに「ハリ」と「コシ」が必要です。
ハリやコシは、髪内部のタンパク質や水分バランスによって決まりますが、その土台となるのが頭皮の健康状態です。
例えば、頭皮が乾燥していると、髪も水分を失いやすくなり、細く弱々しい髪になりがちです。
逆に、皮脂が過剰に分泌されていると、その皮脂が毛穴を塞いだり、髪の根元にまとわりついたりします。
皮脂の重みで髪は根元から倒れやすくなり、ぺたんことした仕上がりになってしまいます。不健康な頭皮環境は、太く丈夫な髪の成長を妨げ、結果としてボリュームダウンにつながるのです。
髪質や生え方の影響
もちろん、生まれ持った髪質や生え方も、センター分けの仕上がりに影響を与えます。
髪が細く、柔らかい「軟毛」と呼ばれる髪質の方は、髪自体に重さを支える力が弱いため、どうしても根元が寝てしまいがちです。
また、髪の生え方が頭皮に対して垂直ではなく、寝るように生えている「寝癖(ねぐせ)」が強い方も、根元を立ち上げることが難しくなります。
これらは体質的なものですが、後述するドライヤーテクニックやスタイリング方法によって、ある程度カバーすることが可能です。
間違ったヘアケアが原因かも
毎日の習慣が、知らず知らずのうちに髪のボリュームを奪っている可能性もあります。
例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーで頭皮の必要な皮脂まで奪ってしまうと、頭皮は乾燥を防ごうとして逆に皮脂を過剰分泌させることがあります。これが「ぺたんこ」の原因になることは前述の通りです。
また、トリートメントやコンディショナーを髪の根元、つまり頭皮にまでベッタリと塗布していませんか。
これらの保湿・補修成分は毛先には必要ですが、根元に付着するとその重みで髪が立ち上がりにくくなります。正しいヘアケアを学ぶことが、ボリュームアップの近道です。
「ぺたんこ髪」を招くNG習慣セルフチェック
ふんわりとしたセンター分けを目指すなら、まずはボリュームダウンを招く日々の「NG習慣」を見直すことが重要です。ご自身の行動と照らし合わせてチェックしてみましょう。
洗髪時の間違った洗い方
シャンプーの目的は、髪の汚れではなく「頭皮の汚れ」を落とすことです。髪ばかりをゴシゴシとこすり合わせるように洗っていませんか。
これは髪のキューティクルを傷つけるだけでなく、頭皮の毛穴汚れが十分に落ちていない可能性があります。
また、すすぎ残しも重大なNG習慣です。シャンプー剤やトリートメント剤が頭皮に残ると、毛穴詰まりや炎症を引き起こし、健康な髪の成長を妨げます。結果として髪が細くなり、ぺたんこの原因になります。
シャンプー選びと洗い方の見直し
| チェック項目 | NGな状態 | 正しいケア |
|---|---|---|
| シャンプーの泡立て | 頭皮の上で直接泡立てている | 手のひらで十分に泡立ててから髪に乗せる |
| 洗い方 | 爪を立ててゴシゴシ洗っている | 指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗う |
| すすぎ | シャワーを短時間で済ませている | 泡が完全になくなるまで、時間をかけて丁寧にすすぐ |
ドライヤーの当て方がボリュームを奪う
髪を乾かす工程は、ボリューム感を決定づける最も重要な時間です。多くの人がやりがちな間違いは、髪を乾かしやすい「毛先」から乾かしてしまうことです。
毛先が乾いても、最も乾きにくい「根元」が湿ったままだと、その水分の重みで髪は立ち上がれません。
また、髪を上から下に向かって一方的に乾かすのもNGです。髪の生えている方向(毛流れ)に沿って風を当てると、髪はそのまま素直に寝てしまい、ぺたんこな仕上がりになってしまいます。
生活習慣の乱れと頭皮への影響
髪は「血余(けつよ)」とも呼ばれ、健康状態が顕著に現れる部分です。栄養バランスの偏った食事、睡眠不足、過度なストレスは、すべて頭皮への血流を悪化させます。
髪の毛は、毛母細胞が毛細血管から栄養を受け取って成長します。血流が悪化すれば、髪に十分な栄養が届かず、細く弱い髪しか育たなくなります。
いくら外側からのケア(ドライヤーやスタイリング)を頑張っても、土台となる髪自体が弱ければ、ふんわり感を出すのは難しくなります。
スタイリング剤の選び方と使い方
ボリュームを出したいからといって、重たいオイルやクリーム系のスタイリング剤を髪の根元からつけていませんか。
これらの油分が多いスタイリング剤は、髪をコーティングする力は強いですが、その重みでせっかく立ち上げた根元を潰してしまいます。
センター分けの「ぺたんこ」を防ぐには、スタイリング剤の種類と、それをつける「場所」と「量」を正しく見極める必要があります。
印象激変!根元をふんわりさせるドライヤー術
ここからは、センター分けを「ぺたんこ」にしないための具体的な乾かし方を解説します。髪の根元は「温めることで形がつき、冷ますことで形が固定される」という性質を利用します。
この技術を習得すれば、毎朝の仕上がりが格段に変わります。
タオルドライでしっかり水分を取る
ドライヤーの時間を短縮し、髪へのダメージを減らすためにも、タオルドライは非常に重要です。ただし、ゴシゴシと強くこするのは厳禁です。
髪が濡れている時はキューティクルが開いており、非常にデリケートな状態です。
頭皮を指の腹で優しくマッサージするように水分を拭き取り、髪の毛はタオルで挟み込むようにして「ポンポン」と優しく叩きながら水分を吸い取ります。特に根元の水分を重点的に取り除きましょう。
ドライヤーは根元から乾かすのが鉄則
タオルドライが終わったら、すぐにドライヤーを使います。自然乾燥は頭皮に雑菌が繁殖する原因にもなり、髪の根元が寝た状態で乾いてしまうためNGです。
ドライヤーの風は、まず「根元」に集中させます。毛先はすぐに乾くため、意識しなくても大丈夫です。
頭皮全体を指の腹でわしゃわしゃと動かしながら、髪の根元に多方向から風が当たるように乾かしていきます。
分け目と逆方向からの温風
根元が8割ほど乾いてきたら、ここからがボリュームアップの本番です。まず、自分が作りたいセンター分けのラインとは「逆」の方向、あるいは「横」から髪をかき上げます。
例えば、右側(あるいは左側)に髪をすべて寄せた状態で、髪の生え際(根元)に向かって下から温風を当てます。
髪の生えている方向と逆らうように風を送ることで、根元が立ち上がる「クセ」をつけていきます。
これを左右両方、そして時には後ろから前(前髪を下ろすように)に向かっても行い、根元をあらゆる方向に一度立ち上げます。
ふんわりドライヤー術のポイント
| 乾かす部位 | 風の当て方 | 目的 |
|---|---|---|
| 根元(全体) | 多方向から強温風 | 全体の水分を飛ばし、髪を立ち上げる準備をする |
| 分け目の根元 | 分け目と逆方向から温風 | 毛流れに逆らい、根元を強制的に立ち上げる |
| 分け目(仕上げ) | 根元に当てた後、冷風 | 立ち上がりを形状記憶させ、スタイルを固定する |
仕上げの冷風でスタイルを固定
根元が十分に立ち上がったら、最後にセンター分けのラインを決めます。そして、立ち上げた根元部分にドライヤーの「冷風」を当てます。
髪はタンパク質でできているため、温められると柔らかく(形がつきやすく)なり、冷やされると硬く(形が固定)なります。
この温風と冷風の使い分けこそが、プロの仕上がりとセルフスタイリングの最大の差です。冷風を当てることで、ふんわりとした立ち上がりが一日中キープされやすくなります。
ふんわり感をキープするスタイリングのコツ
ドライヤーで完璧な土台を作っても、その後のスタイリングでボリュームを潰してしまっては意味がありません。ぺたんこを防ぎ、ふんわり感を一日中キープするためのテクニックを紹介します。
スタイリング剤は根元を避けて毛先中心に
最も重要なルールは、「スタイリング剤を根元につけないこと」です。特にワックスやバームなどの固形タイプは、その重さで根元が寝てしまいます。
スタイリング剤は、まず手のひら全体に薄く透明になるまで伸ばします。そして、髪の中間から毛先にかけて、髪を握り込むようにして馴染ませます。
センター分けの毛先の流れを作ったり、束感を出したりするのはこの段階です。根元には、手のひらに最後に残った、ごくわずかな量で触れる程度にしましょう。
ボリュームアップ系ワックスの選び方
センター分けのスタイリングには、重たいオイル系やツヤが出過ぎるグリース系よりも、軽くてセット力のあるワックスが適しています。
特に「クレイ(マット)タイプ」や「ドライタイプ」と呼ばれるワックスは、油分が少なく軽い仕上がりが特徴で、ふんわり感を損なわずにスタイルを作れます。
少量で高いセット力を発揮するため、つけすぎを防ぐ意味でも有効です。
スタイリング剤の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | センター分けへの適性 |
|---|---|---|
| クレイ(マット)ワックス | 油分が少なく軽い。ツヤ消し。 | ◎(ふんわり感を維持しやすい) |
| ファイバーワックス | 繊維入りで束感が作りやすい。 | ○(毛先に動きを出すのに適している) |
| ヘアオイル/バーム | 重く、ツヤが出やすい。保湿力が高い。 | △(根元を避け、毛先にのみ少量なら可) |
スプレーでふんわり感を長時間持続
ワックスで毛流れを整えたら、仕上げはヘアスプレーです。スプレーは、立ち上げた根元を固定し、湿気などによる「へたり」を防ぐために重要です。
髪から20cmほど離し、固定したい根元部分(分け目の内側)に「シュッ」と短くスプレーします。この時、髪の表面全体にスプレーをかけすぎると、スプレーの重みで逆にぺたんこになるため注意が必要です。
あくまで根元を狙って、内側から支えるイメージで使いましょう。
ぺたんこになった時の応急処置
日中、汗や湿気でどうしてもボリュームがダウンしてきた時は、指の腹を使って対処します。分け目部分の髪を指でつまみ、根元を優しくこするようにして頭皮から髪を離します。
その後、髪全体を一度かき上げるようにして空気を入れ、再度センター分けに戻します。
この時、手のひらで髪の表面を撫でてしまうと、手の皮脂が髪に移り、さらにぺたんこになるため、必ず「指の腹」や「指先」で操作してください。
センター分けが似合う髪型と似合わない髪型
センター分けは、カットの仕方によって「ぺたんこ」に見えやすくも、ボリュームがあるように見せやすくもなります。
乾かし方やスタイリングと合わせて、ベースとなるヘアカットも見直してみましょう。
ぺたんこに見えやすいセンター分けのパターン
最もぺたんこに見えやすいのは、髪の表面にレイヤー(段差)がまったく入っていない、重めのワンスタイルのセンター分けです。髪の重さがすべて根元にかかるため、トップが潰れやすくなります。
また、髪が長すぎると、それだけ髪の重みが増すため、根元の立ち上がりを維持するのが難しくなります。ぺたんこに悩む方は、ある程度の長さを保ちつつも、軽さを出す工夫が必要です。
ボリュームを出しやすいヘアカットとは
逆に、ボリュームを出しやすいのは、トップ(頭頂部)やハチ(頭の側面)の部分にレイヤーを入れて、上の髪を短く、軽くしたスタイルです。
上の髪が短くなることで重みが減り、根元が立ち上がりやすくなります。
また、全体的に髪の量を「すく」ことで、髪と髪の間に空気が入りやすくなり、ふんわりとした質感を作りやすくなります。
ただし、すきすぎると毛先がスカスカになり、かえって貧相に見えるため、美容師さんとの相談が重要です。
ヘアカットによるボリューム感の違い
| カットのポイント | ぺたんこに見えやすい(重い) | ふんわりしやすい(軽い) |
|---|---|---|
| レイヤー(段差) | 少ない(ワンレングス) | 多い(特にトップ) |
| 髪の量(毛量調整) | あまりすいていない | 適度にすいて軽さを出している |
| 全体の長さ | 長すぎる(重みで潰れる) | ミディアム~ショート(根元が支えやすい) |
美容師に相談する時のポイント
美容室でオーダーする際は、単に「センター分けにしてください」と伝えるだけでは不十分です。「根元がぺたんこになりやすい」「トップにボリュームが欲しい」という具体的な悩みを必ず伝えましょう。
プロの美容師であれば、あなたの髪質や骨格、生え方を見た上で、ボリュームが出やすいレイヤーの入れ方や、毛量調整を提案してくれます。
また、自宅での乾かし方やスタイリングについても、その場でアドバイスをもらうと良いでしょう。
- 悩みを具体的に伝える(ぺたんこになる、薄毛に見える)
- ボリュームが欲しい部分を明確にする(トップ、分け目)
- 普段のスタイリング方法を共有する
頭皮環境を整えて健康な髪を育む
ドライヤーやスタイリングは、今ある髪を「ふんわり見せる」技術です。しかし、センター分けのぺたんこや薄毛の悩みに根本から向き合うには、髪そのものを太く、強く育てることが大切です。
そのためには、土台となる「頭皮環境」の改善が欠かせません。
毎日のシャンプーを見直す
前述の通り、シャンプーは頭皮ケアの基本です。自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選びましょう。
乾燥肌の人が洗浄力の強いシャンプーを使うと乾燥が進みますし、脂性肌の人がマイルドすぎるシャンプーを使うと皮脂が落としきれません。
特に薄毛やぺたんこ髪が気になる方は、「アミノ酸系」や「ノンシリコン」の、頭皮への刺激が少ないシャンプーを選ぶことをお勧めします。
シリコンが毛穴に詰まることは稀ですが、ノンシリコンシャンプーは仕上がりが軽くなる傾向があるため、ボリュームアップを実感しやすい場合があります。
頭皮タイプ別シャンプー選びの目安
| 頭皮タイプ | 悩み | おすすめの洗浄成分 |
|---|---|---|
| 乾燥肌 | フケ、かゆみ、髪のパサつき | アミノ酸系(ココイル~など) |
| 脂性肌(オイリー肌) | ベタつき、ニオイ、ぺたんこ | 高級アルコール系(ラウレス硫酸~など)※ただし洗いすぎに注意 |
| 敏感肌 | 炎症、赤み、かゆみ | アミノ酸系、またはベタイン系 |
頭皮マッサージの正しいやり方
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに有効です。血流が改善すれば、髪の成長に必要な栄養素が毛母細胞に届きやすくなります。
シャンプー中や、お風呂上がりの頭皮が清潔な状態で行うのが効果的です。指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすイメージで行います。爪を立てたり、強くこすったりしないよう注意してください。
頭皮マッサージの基本
両手の指の腹を使い、生え際から頭頂部へ、また側頭部から頭頂部へと、頭皮全体をゆっくりと円を描くように動かします。「気持ちいい」と感じる程度の強さで、毎日続けることが大切です。
食生活で内側からケア
髪の毛の主成分は「ケラチン」というタンパク質です。丈夫な髪を育てるためには、まずタンパク質を豊富に含む食品(肉、魚、卵、大豆製品)をしっかり摂取することが必要です。
さらに、タンパク質の合成を助ける「亜鉛」(牡蠣、レバー、ナッツ類)や、頭皮の血行を促進する「ビタミンE」(アーモンド、アボカド)、頭皮の新陳代謝をサポートする「ビタミンB群」(豚肉、マグロ)などもバランス良く摂ることが重要です。
健康な髪のための栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝をサポート | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ |
育毛剤の活用も選択肢に
セルフケアを行っても、なかなか髪のハリ・コシが戻らない、あるいは薄毛の進行が気になるという場合は、育毛剤の使用を検討するのも一つの方法です。
育毛剤は、頭皮の血行を促進したり、毛母細胞の働きを活性化させたりすることで、今ある髪を健康に育て、抜け毛を予防することを目的としています。
センター分けがぺたんこになる原因が、髪の細さやボリューム不足にある場合、育毛剤による頭皮ケアは根本的な対策の一環となり得ます。
自分の頭皮の状態や悩みに合った成分が配合されている製品を選び、正しい用法・用量を守って継続的に使用することが大切です。
よくある質問
- ドライヤー以外でボリュームを出す方法はありますか?
-
いくつか方法があります。一つは、ヘアアイロンやコテ(カールアイロン)を使い、根元部分だけを軽く立ち上げるように熱を通す方法です。
ただし、髪へのダメージがあるため毎日の使用には注意が必要です。もう一つは、カーラーをトップ(分け目)の部分に巻いて、しばらく時間をおく方法です。
熱を使わないためダメージは少ないですが、固定力は弱めです。どちらも、スタイリング剤でのキープが必要です。
- 髪が細くてもセンター分けはできますか?
-
可能です。ただし、髪が細い方は「ぺたんこ」になりやすいため、この記事で紹介した「根元からのドライヤー術」と「レイヤーを入れたカット」が特に重要になります。
重たいスタイリング剤を避け、マット系ワックスやスプレーで軽さを保ちながらスタイリングすることが成功の鍵です。
無理に長いスタイルを目指さず、ショートやミディアムショートのセンター分けから挑戦するのも良いでしょう。
- 育毛剤を使えば髪は太くなりますか?
-
育毛剤の主な目的は、頭皮環境を整え、血行を促進し、抜け毛を防ぎ、今ある髪の毛を健康に「育てる」ことです。
育毛剤に含まれる成分が毛母細胞に働きかけることで、ヘアサイクルが正常化し、結果として髪にハリやコシが戻り、太く丈夫に育つことが期待できます。
ただし、効果の実感には個人差があり、数ヶ月単位での継続的な使用が必要です。
- パーマをかけるのは有効ですか?
-
非常に有効な手段の一つです。
特に根元だけに立ち上がりをつける「根元パーマ」や、全体的に緩くかけてボリュームを出す「ニュアンスパーマ」は、毎日のスタイリングを劇的に楽にしてくれます。
乾かすだけで自然なふんわり感が出るため、ぺたんこ髪に悩む方には適しています。
ただし、髪へのダメージは避けられないため、信頼できる美容師に相談し、パーマ後のヘアケア(トリートメントなど)もしっかり行うことが重要です。
Reference
BIRCH, M. P.; MESSENGER, J. F.; MESSENGER, A. G. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2001, 144.2: 297-304.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
OLSEN, Elise A., et al. Central hair loss in African American women: incidence and potential risk factors. Journal of the American Academy of Dermatology, 2011, 64.2: 245-252.
HUTCHINSON, P. E. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British journal of dermatology, 2002, 146.5: 922-923.
USTUNER, E. Tuncay. Baldness may be caused by the weight of the scalp: gravity as a proposed mechanism for hair loss. Medical hypotheses, 2008, 71.4: 505-514.
PRICE, Vera H. Treatment of hair loss. New England Journal of Medicine, 1999, 341.13: 964-973.
VAN ZUUREN, Esther J.; FEDOROWICZ, Zbys; SCHOONES, Jan. Interventions for female pattern hair loss. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, 5.