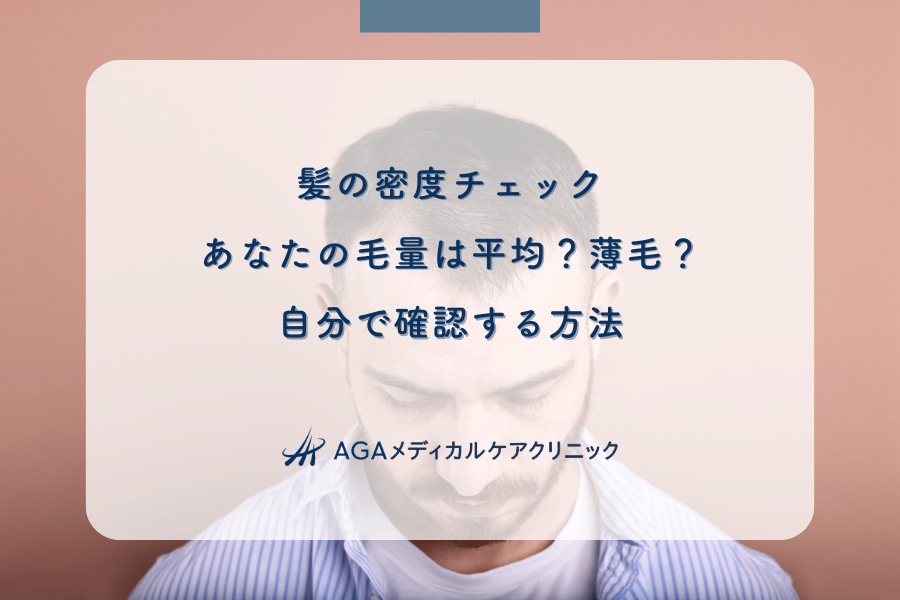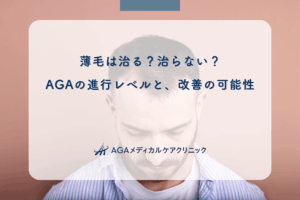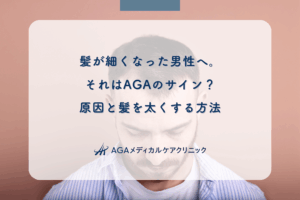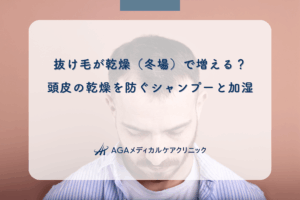「最近、髪の分け目が目立つようになった気がする」「風呂場の排水溝に溜まる抜け毛が増えた」など、ご自身の髪の毛量や薄毛の兆候について不安を感じていませんか?
特に男性の場合、薄毛の進行はデリケートな問題であり、人知れず悩みを抱えている方も少なくありません。
しかし、漠然とした不安を抱え続けるよりも、現状の髪の密度を正しく把握し、適切な対策を講じることが何よりも大切です。
この記事は、「髪密度チェック」というキーワードで検索された方の疑問を解消するために、髪の密度とは何かという基礎知識から、誰でも簡単にできるセルフチェック方法、さらに専門的な測定手法や、密度を維持・改善するための具体的な生活習慣や育毛剤の選び方までを、親切丁寧に解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪の密度とは?薄毛との関連性を理解する
髪の密度とは、簡単に言えば「頭皮の一定の面積あたりに生えている髪の毛の本数」を指します。この密度は、毛量の多寡を決定づける非常に重要な要素です。
多くの方が「薄毛」という言葉でイメージするのは、髪の毛が全体的に少なくなっている状態ですが、厳密にはこの髪の密度が低下している状態を意味します。
毛髪の総本数だけでなく、髪一本一本の太さも影響しますが、ここではまず、髪の「本数」が薄毛とどう関連するのかを深く掘り下げていきましょう。
毛髪密度の基本的な定義
毛髪密度は、専門的には1平方センチメートルあたりに存在する毛包(髪の毛を生成する器官)の数や、実際に生えている毛幹(目に見える髪の毛)の本数で定義されます。
新生児の頭皮には約1,100本/cm²の毛包が存在すると言われますが、これは成長とともに減少し、成人では一般的に約250〜350本/cm²程度になります。
この毛包の数は、一度減ってしまうと自然に増えることはほとんどありません。
したがって、成人における「髪の密度」とは、残された毛包からどれだけ健康な髪の毛が継続的に生え続けているか、という活動的な指標でもあります。
平均的な髪の密度とその測定単位
日本人の成人男性における平均的な髪の密度は、頭頂部で約180本〜220本/cm²、側頭部や後頭部ではこれよりも多くなる傾向があります。
この数値はあくまで平均であり、人種や遺伝によって大きな個人差があります。
測定単位は通常「本/cm²」で表され、この数値が若年層の平均値よりも著しく低い場合に、薄毛やAGA(男性型脱毛症)の可能性を考える必要が出てきます。
密度が200本/cm²を大きく下回り始めると、視覚的にも「薄くなった」と感じやすくなります。
密度が低下すると薄毛に見える理由
髪の密度が低下する主な原因は、毛髪の成長サイクルである「毛周期」の乱れです。
本来、数年かけて太く長く成長するはずの髪の毛(成長期)が、ホルモンの影響などにより短期間で抜け落ちてしまう(休止期への移行が早まる)ことで、毛包から生えている髪の本数が相対的に減ります。
また、一本一本の髪の毛が細くなる「軟毛化」も同時に起こることが多いため、密度が低下すると、頭皮の地肌が透けて見えるようになり、薄毛として認識されます。
つまり、薄毛とは「密度が減る現象」と「髪が細くなる現象」が複合的に進行した状態と言えるのです。この視覚的な変化は、特に光の当たり方によって顕著になるため、セルフチェックの際には注意が要ります。
自分でできる髪の密度チェック方法
専門の機器がなくても、日々の生活の中でご自身の髪の密度の変化を把握する方法はいくつかあります。早期に変化に気づくことは、薄毛対策の成功に極めて重要です。
ここでは、自宅で簡単に、しかし正確に現状を把握できるセルフチェックの手法を詳しく紹介します。
視覚と触覚によるセルフチェック
最も手軽なのは、鏡を使って頭皮の状態を観察し、指で髪を触って確認する方法です。観察は、明るい自然光の下で行うことが大切です。
特にチェックすべき箇所は、生え際(M字部分)と頭頂部(つむじ周辺)です。薄毛はこれらの部位から進行することが多いため、他の部位と比較して地肌の見える面積が広がっていないかを確認します。
触覚によるチェックでは、髪全体を指で掴んで、過去の毛量と比較してボリュームが減っていないか、髪の弾力やハリが失われていないかを確かめます。
急激な変化ではなく、数ヶ月単位での「なんとなく減った」という感覚を大切にしましょう。
指で測る簡易的な髪の隙間チェック
「指幅チェック」は、密度を数字で測れない分、客観的な基準を持つために有効な方法です。髪をかき分け、地肌が見える部分に指を添えてみましょう。
健康な髪の密度を維持している場合、指一本分の幅の隙間を作るのが難しいか、あるいは隙間を作ってもすぐに髪で覆われて地肌が見えにくくなります。
もし、指二本分の幅を広げても地肌がはっきりと見え続けたり、分け目の一本線が非常に太くなっていたりする場合は、密度が低下しているサインかもしれません。
このチェックは、定期的に同じ場所で行い、変化を記録することが大切です。
指幅チェックの具体的な手順
- 鏡の前で、光が地肌に直接当たらないように角度を調整します。
- 利き手ではない方の指で、頭頂部または生え際の髪を優しくかき分けます。
- 地肌が見えた部分に、人差し指一本を垂直に当ててみます。
- 指をゆっくりと横にずらし、地肌がどの程度の範囲で見え続けているかを観察します。
写真記録を活用した変化の把握
人間の記憶は曖昧になりがちですが、写真は最も客観的な記録となります。毎月一度、決まった場所、決まった照明、決まった角度で頭頂部と生え際の写真を撮影する習慣をつけましょう。
特に、薄毛の進行は緩やかなため、過去の写真と見比べることで、数ヶ月前や一年前との密度の違いを明確に把握できます。
写真記録は、対策の効果を測る際にも役立つため、今日からでも開始することが重要です。
髪の密度をチェックする際の注意点
セルフチェックを行う際、照明や髪の濡れ具合によって結果が大きく異なってしまう点に注意が必要です。真上からの強い光は、地肌を必要以上に透けて見せてしまうため、正確な判断を妨げます。
また、洗髪直後の濡れた髪は、髪の毛同士がくっついてしまい、密度が低く見えがちです。必ず乾いた状態の髪で、鏡と自然光を利用して確認してください。
さらに、朝と夜、体調によっても頭皮の状態は変わるため、チェックは毎日同じ時間帯に行うことで、より信頼性の高い結果を得ることができます。
セルフチェックにおける毛量判断の目安
| 項目 | 良好な状態 | 注意が必要な状態 |
|---|---|---|
| 分け目の幅 | 細く、地肌が見えにくい | 太く、地肌がはっきりと見える |
| 髪の弾力 | コシがあり、指に抵抗感がある | 柔らかく、全体的にボリュームがない |
| 透け具合 | 頭頂部の地肌がほとんど見えない | 頭頂部の地肌が広範囲にわたり透ける |
見分け方について詳しく見る
正常な分け目と、薄い分け目の見分け方|地肌の幅と毛量をチェック
薄毛のサインを見逃さないで!密度の低下以外のチェックポイント
髪の密度低下は薄毛の主要な指標ですが、薄毛はそれ単独で始まるわけではありません。密度の変化に先行して、毛髪や頭皮環境にいくつかのサインが現れることが一般的です。
これらの初期サインを見逃さず、複合的な視点でご自身の状態をチェックすることが、対策を始める上で非常に重要です。ここでは、密度低下の予兆となるその他の変化について解説します。
一日の抜け毛の本数を数える
健康な髪の毛でも、毛周期によって毎日一定数は自然に抜け落ちます。通常、日本人の成人では一日に約50本から100本の抜け毛があると言われています。
しかし、これが100本を継続的に超える場合、特に洗髪時や起床時に抜け毛が明らかに増えたと感じる場合は、毛周期が乱れ、髪の成長期が短縮されている可能性が高いです。
抜け毛の本数を数える際は、排水溝ネットを活用したり、白い紙の上で集めたりするなど、客観的な方法で計測すると正確です。
髪の毛一本一本の太さの変化
薄毛、特にAGAの初期段階では、髪の密度がすぐに低下するのではなく、まず毛髪一本一本が細くなる「軟毛化」が起こります。
元気な髪の毛は直径約0.08mm〜0.1mm程度ですが、軟毛化が進行すると0.06mm以下になることもあります。
これは、視覚的には毛量は変わっていないように見えても、髪全体のボリュームが失われ、「ぺたんこ」に見える現象を引き起こします。
指先で抜け毛を触ってみて、以前よりも細く、短い毛が増えていると感じたら、注意信号と捉えてください。この変化は、AGAの典型的な初期症状です。
髪の軟毛化をチェックする際のポイント
洗髪後に抜けた髪の毛を数本取り、他の健康な部位(側頭部や後頭部)の髪の毛と比較してみましょう。
特に頭頂部や生え際から抜けた毛で、毛先に向かって極端に細くなっていたり、全体の長さが短いものが増えている場合は、成長期が短縮されている証拠です。
これらの変化は、密度低下の前に必ず現れるため、早期の対策を可能にする重要な判断材料となります。
生え際や頭頂部の皮膚の透け具合
髪の密度が低下すると、物理的に地肌を覆う力が弱まるため、頭皮の色が露出しやすくなります。
生え際や頭頂部の地肌が、他の部位よりも赤みを帯びて見えたり、白く光って見えるようになったら、密度の低下が進んでいるサインです。
また、頭皮の血行不良や炎症も、毛髪の成長を妨げ、結果的に密度を低下させる原因となります。
地肌の透け具合だけでなく、フケやかゆみ、過剰な皮脂といった頭皮環境の乱れがないかも同時にチェックすることが大切です。
密度低下以外の具体的な初期兆候
以下の兆候が同時に現れている場合は、薄毛対策を本格的に検討する時期かもしれません。
- 朝起きたとき、枕に残る抜け毛が増加した
- 髪をセットしても、すぐにボリュームが失われる
- 額が広くなったように感じる、生え際が後退している
専門家が行う髪の密度測定の具体的手法
セルフチェックは変化の早期発見に役立ちますが、より客観的かつ正確に髪の密度や健康状態を把握するためには、専門クリニックや毛髪専門サロンで精密な検査を受けることが重要です。
専門家は、単に本数を数えるだけでなく、毛髪の太さや成長段階までを総合的に評価し、薄毛の原因特定に役立てます。
ここでは、専門的な場で用いられる主な測定手法について詳しく紹介します。
デンシトメーターを用いた精密測定
デンシトメーターは、頭皮の一部を専用の機器で拡大し、その画像をコンピューターに取り込んで解析することで、正確な毛髪密度(本/cm²)を測定する機器です。
この測定の優れている点は、髪一本一本の太さ(毛径)まで同時に計測できることです。これにより、毛量は保たれていても髪が細くなっている軟毛化の進行度合いを数値として把握できます。
測定結果は数値で記録されるため、治療やケアの前後でどれだけ密度が改善したかを客観的に評価する際の基準となります。
トリコグラム検査と毛周期の関連
トリコグラム検査は、頭皮から数十本の髪の毛を採取し、顕微鏡で根元(毛根)の状態を観察する検査です。
この検査により、毛周期における「成長期」「退行期」「休止期」の毛髪がどの程度の割合で存在しているかを調べることができます。
健康な頭皮では、約85%〜90%が成長期の毛髪ですが、薄毛が進行している頭皮では、成長期の割合が減少し、休止期の毛髪の割合が増加します。
この比率を知ることで、薄毛の原因が毛周期の乱れにあるのかどうかを判断し、適切な対策を立てるための重要な手がかりを得ることができます。
専門クリニックで受けるメリット
専門クリニックでは、これらの精密な測定に加え、医師による問診や血液検査などを組み合わせて、薄毛の原因を多角的に分析します。
単なる密度の数値だけでなく、遺伝的な要因、生活習慣、病気の影響など、複合的な原因を特定できる点が最大のメリットです。
また、薄毛の種類(AGA、円形脱毛症、脂漏性脱毛症など)に応じた、医学的に根拠のある治療計画を立ててもらうことができます。
セルフチェックで不安を感じた方は、一度専門家の意見を聞くことが大切です。
セルフと専門家の密度測定方法の比較
| 測定方法 | 測定できる項目 | 客観性 |
|---|---|---|
| セルフチェック | 地肌の透け具合、主観的なボリューム | 低い(主観的) |
| デンシトメーター | 正確な本数/cm²、毛髪の太さ | 高い(数値化) |
| トリコグラム | 成長期と休止期の比率(毛周期) | 高い(医学的根拠) |
髪の密度を平均値に近づけるための生活習慣
髪の密度を改善し、健康な毛髪を育てるためには、薄毛の原因に対処するだけでなく、髪が育ちやすい土壌、つまり身体全体の健康状態を整えることが重要です。
生活習慣の小さな見直しが、頭皮環境と毛髪の成長に大きな影響を与えます。ここでは、今日から実践できる具体的な生活習慣の改善点について深掘りします。
栄養バランスを考慮した食事の重要性
髪の毛は、主にタンパク質で構成されています。そのため、良質なタンパク質の摂取は、毛髪の生成に欠かすことができません。
しかし、タンパク質だけを摂取すれば良いわけではなく、それを効率よく髪の毛に変換するためには、ビタミンやミネラルが補助的な役割を果たします。
特に、亜鉛はタンパク質の合成を助けるミネラルであり、ビタミンB群やビタミンEは頭皮の血行を促進し、栄養を毛根に運ぶのをサポートします。
特定の栄養素に偏るのではなく、様々な食材をバランス良く取り入れる食生活が大切です。
毛髪の成長を支える主要な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 毛髪の主成分(ケラチン)を構成 | 鶏肉、魚、大豆製品、卵 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンE | 抗酸化作用、血行を促進 | アボカド、アーモンド、かぼちゃ |
質の高い睡眠と成長ホルモンの関係
髪の毛の成長は、夜間の睡眠中に分泌される成長ホルモンに大きく依存しています。成長ホルモンは、細胞の修復や再生を促す働きがあり、毛母細胞の分裂を活性化させるために重要です。
特に、午後10時から午前2時の間の深い睡眠時に最も多く分泌されると言われているため、この時間帯を含む十分な睡眠時間を確保することが、毛髪の密度維持に直結します。
睡眠不足は、ホルモンバランスの乱れを引き起こし、薄毛の原因となるDHT(ジヒドロテストステロン)の感受性を高める可能性も指摘されています。
ストレス管理が毛髪に与える影響
慢性的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させることで頭皮の血行不良を引き起こします。
血行が悪くなると、毛根に必要な栄養や酸素が届きにくくなり、結果として毛髪の成長が阻害され、密度の低下につながります。
また、ストレスは円形脱毛症など、他の脱毛症を引き起こす引き金にもなり得ます。
適度な運動や趣味、リラックスできる時間を意識的に作り、日々のストレスを効果的に解消する習慣を身につけることが、健康な毛髪を育てる上で大変重要です。
密度低下の原因となりやすい間違ったヘアケア
日々のヘアケアは、髪の健康を保つために欠かせませんが、間違った方法で行うと、かえって頭皮環境を悪化させ、毛髪の密度低下を早めてしまうことがあります。
特に、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、誤ったドライヤーの使い方などは、頭皮と髪に大きな負担をかけます。
ここでは、多くの方がやりがちな間違ったヘアケアを見直し、頭皮環境を健やかに保つための正しい方法を解説します。
シャンプーや洗髪方法の見直し
市販されているシャンプーの中には、洗浄力が強すぎて必要な皮脂まで取り去ってしまい、頭皮を乾燥させてしまうものがあります。
乾燥した頭皮は、フケやかゆみを引き起こすだけでなく、バリア機能が低下し、炎症を起こしやすくなります。
シャンプーを選ぶ際は、アミノ酸系など洗浄力が穏やかなものを選び、指の腹を使って優しくマッサージするように洗いましょう。
最も大切なのは、シャンプーの泡を頭皮に残さないように、3分以上かけてしっかりと洗い流すことです。洗い残しは毛穴の詰まりや炎症の原因となります。
正しいシャンプーの手順
| 手順 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1.予洗い | シャンプー前に38℃程度のぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと濡らす | 汚れの約8割を落とすことが大切 |
| 2.泡立て | シャンプーを手のひらでよく泡立ててから髪に乗せる | 泡がクッションとなり摩擦を防ぐ |
| 3.洗髪 | 指の腹で頭皮を優しくマッサージするように洗う | 爪を立てると頭皮を傷つける |
| 4.すすぎ | 洗い残しがないよう、しっかりと3分以上洗い流す | シャンプーカスは炎症の原因になる |
ドライヤーや整髪料の正しい使い方
髪を濡れたまま放置すると、頭皮の温度が下がり、雑菌が繁殖しやすい環境を作り出し、薄毛を助長します。
洗髪後は、すぐにドライヤーで乾かすことが重要ですが、この時、熱風を一点に集中させたり、頭皮に近づけすぎたりするのは厳禁です。
ドライヤーは、頭皮から20cm程度離し、低温または中温設定で、全体に風が行き渡るように動かしながら乾かしましょう。
また、整髪料を多量に使用したり、頭皮に直接塗布したりすることも、毛穴を詰まらせる原因となるため、毛先に少量つける程度に留めることが望ましいです。
頭皮環境を整えるマッサージのやり方
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養が行き渡りやすくするために非常に効果があります。指の腹を使い、頭皮全体を動かすイメージで優しく揉みほぐしましょう。
特に、薄毛が気になる頭頂部だけでなく、血行が滞りやすい耳の上や後頭部の付け根も意識的にマッサージすることが大切です。
力を入れすぎると頭皮を傷つけたり、逆に皮脂腺を刺激しすぎることもあるため、リラックスできる程度の心地よい力加減で行うのが適切です。
原因について詳しく見る
男のぺたんこ髪の原因は?薄毛?髪質?今すぐできるボリュームアップ法
育毛剤を活用するメリットと選び方
生活習慣の見直しや正しいヘアケアは、髪の密度維持の土台作りには欠かせませんが、すでに密度の低下を感じている場合、育毛剤を併用することで、より積極的な対策を行うことができます。
育毛剤は、頭皮環境の改善や、毛髪の成長をサポートする成分を直接届けるための大変有効な手段です。
ここでは、育毛剤がどのように働くのか、そしてご自身の状態に合った製品を選ぶためのポイントを解説します。
育毛剤の主な作用と期待できる効果
育毛剤は、主に以下の3つの作用を通じて髪の密度の改善を目指します。
一つ目は、血行促進作用です。頭皮の血管を広げ、毛根に必要な栄養分や酸素を効率よく供給します。
二つ目は、毛母細胞の活性化作用です。毛髪を作る細胞の働きを活発にし、成長期を延長させることで、髪が太く長く育つのをサポートします。
三つ目は、頭皮環境の改善作用です。炎症を抑えたり、フケやかゆみを防いだりすることで、健康な髪が育ちやすい土壌を整えます。
これらの作用により、休止期に入る毛髪を減らし、髪全体のボリュームと密度を高める効果が期待できます。
髪の密度向上を目指す成分の種類
育毛剤に含まれる成分は多岐にわたりますが、髪の密度向上に特に関連の深い主要成分を理解しておくことは、製品選びの基準となります。
例えば、血行促進に特化した成分、頭皮の炎症を抑える成分、そして毛母細胞に働きかける成分など、それぞれの目的によって配合されている成分が異なります。
主要な育毛・頭皮ケア成分とその作用
| 成分名 | 主な作用 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| センブリエキス | 血行を促進する | 毛根への栄養供給を助ける |
| グリチルリチン酸2K | 抗炎症作用を持つ | 頭皮の炎症やフケを防ぎ、環境を整える |
| アデノシン誘導体 | 毛乳頭細胞に働きかけ成長因子を促す | 発毛を促進し、成長期を延長させる |
育毛剤の効果を最大限に引き出す使用法
育毛剤は、ただ塗布すれば良いというものではありません。その効果を最大限に引き出すためには、正しいタイミングと方法で使用することが大切です。
最も効果的なのは、洗髪後の清潔な頭皮に、頭皮マッサージと組み合わせて使用することです。洗髪後は頭皮の汚れが落ち、成分が浸透しやすい状態になっています。
塗布する際は、薄毛が気になる部分だけでなく、頭皮全体に均等に行き渡るようにすることが重要です。
また、育毛剤は即効性のあるものではなく、毛周期に合わせて数ヶ月単位で継続して使用することで、初めてその効果が現れます。
焦らず、毎日欠かさずに使用し続ける継続性が成功の鍵を握ります。
対策について詳しく見る
男性の分け目はげは治る?原因と、今すぐできる対策(AGA・育毛剤)
髪の密度を増やす(濃くする)には?自力は無理?毛量を増やす対策
よくある質問
髪の密度チェックや薄毛対策に関して、多くの方が抱える疑問についてお答えします。
- 髪の密度は年齢とともに自然に低下するのでしょうか?
-
はい、一般的に加齢に伴い、毛包の活動が弱まることで毛髪密度は緩やかに低下します。
これは自然な生理現象の一部ですが、生活習慣や遺伝、ホルモンバランスの影響で、平均的な速度よりも速く密度が低下する場合があります。
特に20代から30代にかけて急激な変化を感じる場合は、AGAなどの病的な原因を疑う必要があります。
- 髪の密度を増やすために、シャンプーの回数を減らすべきですか?
-
一概にシャンプーの回数を減らすのが良いとは限りません。シャンプーの目的は、頭皮の過剰な皮脂や汚れを落とし、毛穴を清潔に保つことです。
皮脂が過剰な方が洗髪回数を減らすと、毛穴が詰まり、かえって薄毛を進行させる原因になります。大切なのは、回数よりも「洗い方」と「シャンプーの種類」です。
ご自身の頭皮の皮脂量に合わせた頻度で、正しい方法で優しく洗うことが重要です。
- 髪の密度チェックで薄毛の可能性が高いとわかった場合、最初に何をすべきですか?
-
まずは、食生活、睡眠、ストレス管理といった生活習慣の根本的な見直しから始めるべきです。
その上で、ご自身の薄毛の原因を正確に特定するために、毛髪専門のクリニックを受診することを強くお勧めします。
自己判断で市販薬や効果が不明なケアを行うよりも、専門家のアドバイスに基づいた対策を講じる方が、時間と費用の節約になり、確実な改善につながります。
- 帽子をかぶると髪の密度が低下したり、薄毛になったりしますか?
-
帽子をかぶること自体が直接的な薄毛の原因になるという医学的な根拠は現在のところありません。
しかし、通気性の悪い帽子を長時間着用し、汗や湿気で頭皮が蒸れると、雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮環境が悪化します。
この悪化した頭皮環境が、間接的に髪の成長を妨げ、結果として密度の低下を招く可能性があります。適度に脱ぎ、頭皮を清潔に保つことが大切です。
- 育毛剤はどれくらいの期間使い続ければ、密度の改善が見込めますか?
-
髪の毛には毛周期があり、新しい毛が生え、成長し、抜け落ちるまでに時間がかかります。そのため、育毛剤の効果を実感するには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続的な使用が必要です。
効果の現れ方には個人差がありますが、毛周期全体に作用させるためには、諦めずに半年以上使用し続けることが大切です。
密度低下・ボリュームダウン・分け目の記事
Reference
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
BIRCH, M. P.; MESSENGER, J. F.; MESSENGER, A. G. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. British Journal of Dermatology, 2001, 144.2: 297-304.
OLSEN, Elise A. Current and novel methods for assessing efficacy of hair growth promoters in pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2003, 48.2: 253-262.
VAN NESTE, M. D. Assessment of hair loss: clinical relevance of hair growth evaluation methods. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 358-365.
GAN, Desmond CC; SINCLAIR, Rodney D. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2005. p. 184-189.
ROJHIRUNSAKOOL, Salinee; SUCHONWANIT, Poonkiat. Parietal scalp is another affected area in female pattern hair loss: an analysis of hair density and hair diameter. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2017, 7-12.
SINCLAIR, Rodney, et al. Hair loss in women: medical and cosmetic approaches to increase scalp hair fullness. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 12-18.
CHEN, Xi, et al. Female pattern hair loss in female and male: a quantitative trichoscopic analysis in Chinese han patients. Frontiers in Medicine, 2021, 8: 649392.
LEE, Bryan Shiu Lun, et al. Assessment of hair density and caliber in Caucasian and Asian female subjects with female pattern hair loss by using the Folliscope. Journal of the American Academy of Dermatology, 2012, 66.1: 166.
HARRIES, Matthew, et al. Towards a consensus on how to diagnose and quantify female pattern hair loss–The ‘Female Pattern Hair Loss Severity Index (FPHL‐SI)’. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2016, 30.4: 667-676.