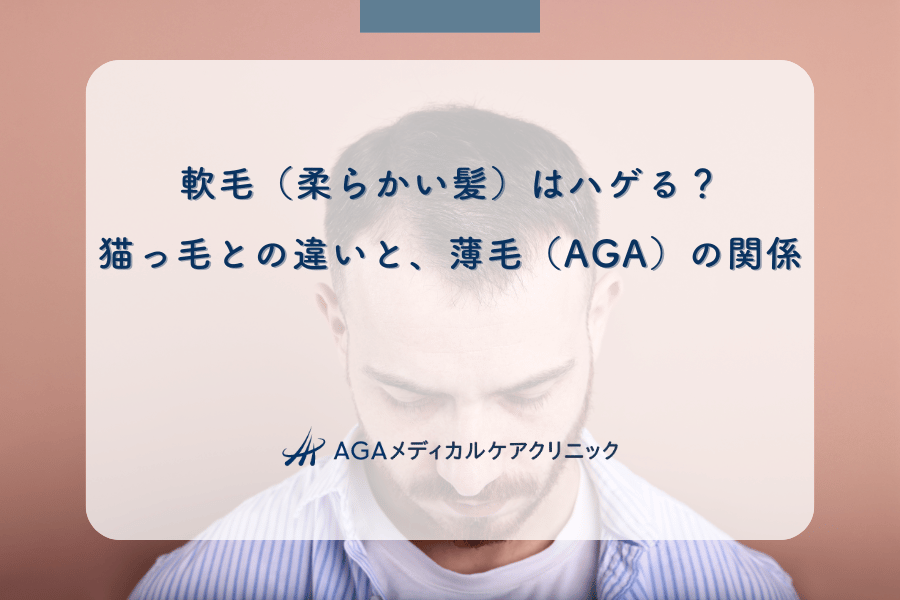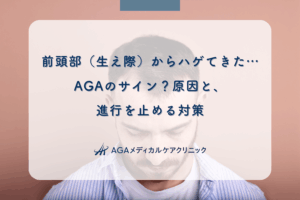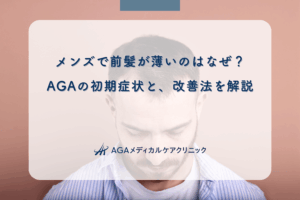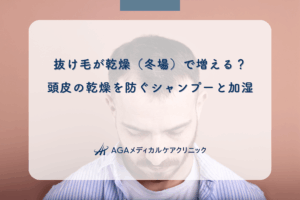「髪が柔らかいと将来ハゲやすいのではないか?」そのように感じ、不安を抱えている男性は少なくありません。
ご自身の髪質が細くて柔らかい「軟毛」の場合、見た目のボリュームが出にくいことから、薄毛(AGA)と結びつけて心配になるのも当然でしょう。
しかし、結論から言うと、軟毛であることそのものが薄毛の直接的な原因になるわけではありません。
軟毛は遺伝的な要素で決まる髪質の一つであり、薄毛は別の要因、特に男性ホルモンや生活習慣が大きく影響します。
この記事では、「軟毛はハゲる」という一般的な誤解を解消しつつ、軟毛と猫っ毛の違い、そして軟毛化が薄毛(AGA)のサインである可能性について、医学的な見地も踏まえて詳しく解説します。
軟毛という髪質を正しく理解し、ご自身の髪を守るための具体的な予防と対策を学び、自信を持って日々を過ごすための知識を身につけましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
軟毛と薄毛の関係性 誤解を解き正しい知識を伝える
軟毛に対する一般的な誤解
軟毛を持つ方が抱きがちな最大の誤解は、「髪が細いから将来ハゲる」という思い込みです。
これは、髪が細く柔らかいことで、地肌が透けて見えやすくなり、相対的に薄毛に見えやすいという視覚的な錯覚からきています。
また、軟毛は一本一本の髪の毛にコシがないため、ボリュームが出にくく、分け目が目立ったり、セットが崩れやすかったりすることで、薄毛の印象を強めてしまうのです。
しかし、髪の太さは生まれ持った遺伝的な要素が強く、軟毛自体が薄毛を引き起こす原因物質ではありません。
重要なのは、現在の髪質(軟毛)と、進行性の脱毛症であるAGAによる「軟毛化」を区別することです。
なぜ「軟毛=ハゲる」という説が広まったのか
この説が広まった背景には、薄毛の初期段階で起こる「軟毛化」の現象があります。男性型脱毛症(AGA)が進行すると、健康な太い髪の毛が、細く短い産毛のような髪に変化します。
この状態はまさに「軟毛」と同じように見えます。そのため、軟毛という髪質そのものが薄毛の原因だと誤って認識され、「髪が細い=ハゲる」という単純な図式が定着してしまいました。
この認識は、薄毛の兆候と髪質を混同したことから生じたものです。
この記事でわかること
この記事を通して、読者は軟毛に関する以下の正しい知識を獲得できます。
軟毛に関する正しい知識
軟毛とは、髪の太さが細いという「体質」であり、ハゲるという「病気」ではないことが理解できます。
また、軟毛と混同されやすい「猫っ毛」との違いを明確にし、それぞれの髪質に合った正しいヘアケアや薄毛予防の方法を知ることができます。
特に、ご自身の軟毛が遺伝的な髪質なのか、それともAGAによる進行性の軟毛化なのかを見極めるための判断材料と、具体的な対策を把握することが、薄毛に対する不安を解消するための重要な鍵となります。
軟毛(柔らかい髪)の定義と特徴
髪の毛の太さの基準
軟毛とは、医学的にも美容学的にも、主に毛髪一本あたりの太さが平均よりも細い髪質を指します。日本人の毛髪の平均的な太さは約80mm(マイクロメートル)程度とされています。
軟毛の場合、この平均値よりも細く、例えば60mm以下となることが一般的です。髪の太さは、遺伝や毛母細胞の活動によって決まり、体質的な要素が大きいです。
髪の太さを決める要素
髪の太さは、毛根の深部にある毛乳頭が毛母細胞に指令を出し、毛母細胞が分裂を繰り返して髪の毛を形成する際に決定されます。毛の太さを決める主な要素は、以下の通りです。
- 毛乳頭の大きさ: 毛乳頭が大きいほど、髪の生成に必要な栄養や指令が豊富になり、太い髪が作られやすいです。
- 毛母細胞の分裂回数: 分裂回数が多いほど、髪の直径が太くなります。
- 遺伝: 髪の太さは両親や祖父母からの遺伝的影響を強く受けます。
生まれつき軟毛の人は、これらの要素が複合的に作用し、細い髪が生成されていると考えられます。
軟毛の構造的な特徴
軟毛が細く柔らかいのは、髪の毛の約90%を占めるコルテックスという層の量や密度が関係しています。コルテックスは髪の強度や弾力性、水分保持能力を担っています。
軟毛の場合、このコルテックス層の占める割合が普通毛や硬毛に比べて少なく、個々のコルテックス細胞の密度も低い傾向があります。
軟毛と普通毛・硬毛の比較
| 項目 | 軟毛 | 普通毛 | 硬毛 |
|---|---|---|---|
| 太さの目安 | 約60mm未満 | 約7mmから90mm | 約100mm以上 |
| コルテックス量 | 少ない | 平均的 | 多い |
| 特徴 | 柔らかい、ボリュームが出にくい、ハリ・コシが弱い | バランスが良い、セットしやすい | 硬い、太い、ボリュームが出やすい |
軟毛がもたらす見た目の印象
軟毛は細いため、髪の毛全体の密度が高くても、一本一本が細いため光を通しやすく、地肌が透けて見えやすいという特徴があります。
これが、特に頭頂部や分け目などで薄毛のように見えてしまう主な原因です。
また、軟毛は重力に逆らう力が弱いため、ペタッとしやすく、セットしてもすぐにボリュームを失いやすいことも、薄毛に見える要因の一つです。
軟毛と猫っ毛の違いを明確に理解する
「軟毛」と「猫っ毛」の言葉の使い分け
「軟毛」と「猫っ毛」はしばしば同じ意味で使われますが、厳密には区別されることもあります。
「軟毛」は主に毛髪の太さに着目した科学的な表現(細い毛)であるのに対し、「猫っ毛」は柔らかく、コシやハリがないという毛髪の「質感」や「手触り」に着目した表現です。
ただし、一般的には、細い髪は柔らかくコシがないため、「軟毛=猫っ毛」として扱われることがほとんどです。
毛髪の太さと量による分類
髪の毛の印象は、太さだけでなく、髪の密度(毛量)によっても大きく左右されます。
軟毛と猫っ毛の特徴
軟毛かつ毛量が少ない場合、地肌が透けやすく、薄毛の印象が強くなります。
一方、軟毛でも毛量が多い場合は、地肌は透けにくいものの、髪が柔らかすぎるためにボリュームが出ず、セットしにくいという悩みを抱えることが多いです。
猫っ毛という表現を使う場合、多くはこの「細くて柔らかく、コシがない」という複合的な特徴を持つ髪質を指します。
軟毛と猫っ毛の主な特徴比較
| 分類 | 定義 | 見た目の印象 |
|---|---|---|
| 軟毛 | 毛髪一本の直径が平均より細い(体質的なもの) | 地肌が透けやすい、全体的にペタッとしやすい |
| 猫っ毛 | 毛髪が柔らかく、コシやハリが極端に弱い(質感的なもの) | 手触りが柔らかい、すぐにセットが崩れる |
軟毛や猫っ毛は、薄毛に見られやすいというデメリットばかりではありません。
この髪質特有のメリットを理解し、活かすことで、日々のケアやスタイリングを前向きに取り組むことができます。
軟毛の主なメリット
軟毛は、パーマやカラーリングの薬剤が浸透しやすく、比較的短時間で変化を出しやすいというメリットがあります。また、手触りが柔らかいため、女性ウケが良いと感じる人もいます。
軟毛の主なデメリット
デメリットとしては、前述の通りボリュームが出にくく、外部からのダメージを受けやすい点が挙げられます。
特に、紫外線や乾燥といった環境要因、摩擦によるダメージは、髪が細い分、硬毛よりも深刻になりやすい傾向があります。
軟毛が「ハゲやすい」と言われる理由と真実
髪のボリュームが出にくいことによる錯覚
軟毛が「ハゲやすい」という認識の根源は、やはり視覚的な錯覚にあります。毛髪一本の直径が細い軟毛は、同じ本数でも硬毛と比べて頭皮を覆う力が弱いです。
これにより、頭皮が露出する面積が広がり、実際の毛量が変わらなくても薄毛に見えてしまいます。
この錯覚が、軟毛を持つ人の薄毛への不安を増幅させ、「軟毛だからハゲる」という説を信じ込ませる結果につながっています。
軟毛の人が陥りがちな薄毛対策の誤解
| 誤解 | 真実 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 髪を太くすれば薄毛は治る | 軟毛は体質であり、太さは根本的には変えられない | ボリュームアップのためのスタイリングと頭皮環境の改善 |
| シャンプーの洗浄力を上げれば治る | 洗浄力が強すぎると頭皮を乾燥させ、逆に薄毛を促進する | マイルドなアミノ酸系シャンプーで頭皮を優しく洗浄する |
| 育毛剤は軟毛には効果がない | 軟毛でも頭皮環境を整えることで、抜け毛予防や髪の成長をサポートする | 頭皮の状態に合わせた成分を選ぶことが重要 |
軟毛は構造的にデリケートなため、外部からの刺激に対して弱いという特徴があります。ダメージが蓄積すると、髪のキューティクルが剥がれやすくなり、内部のタンパク質や水分が流出します。
これがさらに髪を細く、弱く見せる要因となります。
特に軟毛が影響を受けやすい外部ダメージは以下の通りです。これらを理解し、日々のケアで避けるように注意を払う必要があります。
- 摩擦によるダメージ: 寝具との摩擦や、タオルでゴシゴシと拭く行為がキューティクルを傷つけます。
- 紫外線によるダメージ: 髪のタンパク質を変性させ、髪全体を弱く、パサつかせます。
- 熱によるダメージ: ドライヤーの熱を一点に集中させると、髪の水分が急激に失われます。
細い髪は寿命が短いのか
髪の毛には「ヘアサイクル」という寿命があります。健康な髪は成長期(2から6年)、退行期(数週間)、休止期(数ヶ月)を経て生え変わります。
生まれつきの軟毛の場合、普通毛や硬毛と比べてヘアサイクルが極端に短いという医学的な根拠はありません。
つまり、体質的な軟毛は、それだけで抜け毛が増える、あるいはハゲるという直接的な原因にはならないということです。
しかし、薄毛であるAGAが進行している場合は話が異なります。AGAが原因で軟毛化が起きている場合、ヘアサイクルの「成長期」が短縮され、髪が十分に太く長く成長する前に抜け落ちてしまいます。
この「成長期の短縮」こそが薄毛の根本原因であり、単なる髪質の細さとは全く異なる問題であると認識するべきです。
軟毛とAGA(男性型脱毛症)の関連性
AGAの進行と髪の軟毛化の関係
軟毛と薄毛(AGA)の関連性を考える上で、最も重要なのが「AGAによる軟毛化」の認識です。
AGAは、進行性の脱毛症であり、その初期サインとして、頭髪全体、特に前頭部や頭頂部の髪が徐々に細く、短くなる現象(軟毛化)が現れます。
これは、健康な軟毛とは異なり、一度太かった髪が細くなっていくという変化を伴います。
AGA軟毛化の進行プロセス
AGAによる軟毛化は、毛包(髪の根元)がダメージを受けることで、髪の毛を太く成長させるための成長期が短縮されることで起こります。
髪は成長期が短縮されるほど、十分に太く成長する前に退行期に移行して抜け落ちてしまいます。その結果、生えている髪のほとんどが細く短い軟毛のような状態になってしまうのです。
AGAによる軟毛化のプロセス
| 段階 | 状態 | 毛髪の変化 |
|---|---|---|
| 初期 | DHTが毛乳頭に作用 | 成長期が徐々に短縮し始める |
| 中期 | 成長期が短縮 | 髪が十分に太くならず、細く短くなる(軟毛化) |
| 進行期 | 毛包のミニチュア化 | ほとんどの髪が産毛のような状態になり、薄毛が進行する |
AGAの軟毛化の主要な原因物質は、男性ホルモンであるテストステロンが体内の酵素($5\alpha$-リダクターゼ)と結合して生成されるDHT(ジヒドロテストステロン)です。
DHTは、毛乳頭細胞に存在する男性ホルモン受容体と結合し、「髪の成長を止める」という指令を出します。
DHTの影響を受けるのは特定の人
DHTによる影響を受けやすいかどうかは、主に以下の$2$つの要因で決まります。
- 5αリダクターゼの活性度: 活性が高い人ほどDHTが多く生成されます。
- アンドロゲンレセプター(受容体)の感受性: 感受性が高い人ほど、少量のDHTでも強い影響を受けてしまいます。
これらの要因は遺伝によって決定されるため、ご自身の家系に薄毛の人が多い場合、軟毛化は単なる髪質ではなく、AGAの兆候である可能性を真剣に考える必要があります。
軟毛化に気づいた時のAGA対策
ご自身の軟毛が生まれつきの体質ではなく、徐々に細くなってきた「軟毛化」だと気づいた場合、それはAGAの早期サインである可能性が非常に高いです。この段階で対策を始めることが、最も効果的です。
早期対策の重要性
AGAは進行性の疾患であるため、自然に治ることはありません。
早期に専門のクリニックを受診し、DHTの生成を抑制する内服薬(フィナステリドやデュタステリドなど)や、発毛を促進する外用薬(ミノキシジルなど)による治療を開始することで、軟毛化の進行を食い止め、再び髪を太く成長させられる可能性を高めます。
軟毛化は体質ではなく「変化」であり、その変化を見逃さないことが大切です。
軟毛を活かして薄毛予防・対策をするための具体的な方法
生活習慣の改善と栄養摂取
薄毛予防の基本は、髪の成長を支える土台である身体と頭皮の環境を整えることです。特に軟毛の人は、髪が細いため、毛母細胞の活動を最大限に高めるための栄養と血行促進が重要です。
髪の成長を支える$3$つの習慣
- 質の良い睡眠: 髪の成長を促す成長ホルモンは、深い睡眠時、特に夜10時から深夜2時の間に多く分泌されます。最低でも6から7時間の質の高い睡眠を心がけましょう。
- 適度な運動: 有酸素運動は血行を促進し、頭皮への栄養供給をスムーズにします。ストレス解消にもつながり、自律神経のバランスを整えます。
- バランスの取れた食事: 髪の主成分であるタンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルをバランス良く摂取することが求められます。
軟毛の人が摂るべき主要な栄養素
| 栄養素 | 働き | 含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質(ケラチンの原料) | 髪の主成分を構成し、健康な髪を育てる | 鶏むね肉、卵、大豆製品(納豆など) |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、細胞の代謝に関与する | 牡蠣、牛肉、レバー、ナッツ類 |
| ビタミンB群(特にビオチン) | 頭皮の新陳代謝を活発にし、髪の成長をサポートする | マグロ、カツオ、バナナ、緑黄色野菜 |
軟毛の人が薄毛予防を行う上で、頭皮環境の改善は特に重要です。頭皮の血行不良や炎症、皮脂の過剰分泌は、毛母細胞の働きを弱め、軟毛化を加速させる可能性があります。
正しいスカルプケアの基本
シャンプーは指の腹で優しく行い、頭皮の汚れをしっかりと落としつつ、必要な皮脂まで洗い流しすぎないことが大切です。
洗髪後は、化粧水のように頭皮に潤いを与えるスカルプローションを使用し、頭皮の乾燥を防ぎましょう。乾燥はフケやかゆみ、炎症の原因となり、結果的に健康な髪の成長を妨げてしまいます。
軟毛のための育毛剤の選び方
育毛剤は、頭皮環境を整え、血行を促進することで、今ある髪を健康に保ち、抜け毛を予防する目的で使用します。
軟毛の人が育毛剤を選ぶ際は、頭皮への刺激が少なく、保湿成分や血行促進成分が豊富に含まれているものを選ぶのが良いでしょう。
育毛剤選びの$3$つのポイント
育毛剤を選ぶ際には、頭皮に優しく、髪の毛を支える土台作りに特化した成分が含まれているかを確認します。
- 保湿成分の有無: 頭皮の乾燥は軟毛をさらに弱く見せるため、ヒアルロン酸やコラーゲンなどの保湿成分を含むものが適しています。
- 血行促進成分: センブリエキスやタマサキツヅラフジエキスなど、頭皮の血行を促す成分は、毛乳頭へ栄養を届けるのに役立ちます。
- 低刺激性: アルコールや添加物の刺激が強い育毛剤は、デリケートな軟毛の頭皮には避けた方が無難です。
育毛剤は、発毛剤とは異なり、髪を太くする効果を謳うものではありませんが、軟毛の人が薄毛へ移行するのを防ぐための予防策として有効です。
軟毛の人が実践すべき正しいヘアケア習慣
シャンプーやトリートメントの選び方と使用方法
軟毛の人は、髪の毛の太さが細いため、洗浄力の強すぎるシャンプーや、重すぎるトリートメントは避けるべきです。
シャンプー選びの重要性
シャンプーは、頭皮に優しいアミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を主とするものを選びましょう。
これらのシャンプーは洗浄力がマイルドで、頭皮に必要な皮脂を残しながら、余分な汚れだけを落とします。
軟毛の人が選ぶべきシャンプーの系統
| 系統 | 特徴 | 推奨度 |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | 洗浄力がマイルドで頭皮に優しい。保湿力もある | 非常に高い |
| ベタイン系 | ベビーシャンプーにも使われる低刺激性。泡立ちが良い | 高い |
| 高級アルコール系 | 洗浄力が強く、皮脂を落としすぎる可能性がある | 低い(避けるべき) |
トリートメントやコンディショナーは、軟毛の場合、髪の毛を重くし、さらにボリュームを失わせてしまうことがあります。使用する際は、毛先を中心につけ、頭皮にはつけないようにしましょう。
また、髪をコーティングしすぎない、軽めのテクスチャのものを選ぶことが大切です。
ドライヤーのかけ方とスタイリングの工夫
軟毛の人が薄毛に見えないようにボリュームを出すためには、ドライヤーのかけ方とスタイリングの工夫が重要です。
ボリュームを出すためのドライヤーテクニック
軟毛は濡れているときに特にデリケートです。タオルドライは優しく行い、ドライヤーで素早く乾かす必要がありますが、熱によるダメージを与えないように注意しなければなりません。
軟毛のためのドライヤーテクニック
| 手順 | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 根元を乾かす | 髪の立ち上がりをサポートする | 乾かす方向とは逆向きに髪をかきあげて熱風を当てる |
| 冷風を使う | キューティクルを引き締める | 髪が8割程度乾いたら冷風を当て、ボリュームを固定する |
| 仕上げの温度 | 熱による乾燥を防ぐ | ドライヤーを20cm以上離し、低温を維持する |
頭皮マッサージの正しいやり方
頭皮マッサージは、軟毛の人にとって血行を促進し、髪の成長をサポートする非常に有効な方法です。特に血行不良になりがちな頭頂部を中心に、指の腹を使って優しく行いましょう。
マッサージの注意点と効果
マッサージは、爪を立てず、頭皮をこすらないように、指の腹で頭皮を動かすイメージで行います。これにより、頭皮の硬さが和らぎ、毛細血管の血流が改善され、毛根に栄養が行き渡りやすくなります。
また、リラックス効果もあり、ストレス軽減にもつながります。
よくある質問
軟毛に関する読者の皆様から寄せられることが多い疑問について、解説します。
- 軟毛だとパーマやカラーリングは避けるべきですか?
-
軟毛は細くデリケートなため、パーマやカラーリングの薬剤が強く作用しすぎることがあります。
薬剤の浸透が早いため、施術時間を短くしたり、刺激の少ない薬剤を選んだりするなどの工夫を美容師に相談することが重要です。
特にパーマは、髪が傷むとさらに細く見えてしまうため、頻繁に行うことは推奨しません。適切なケアと間隔を空けて行うことで、軟毛でも楽しむことは可能です。
- 軟毛の人が薄毛をカバーするためのスタイリング材は何が良いですか?
-
軟毛は油分の多いワックスやジェルを使うと、重さで髪がペタッとしてしまい、薄毛が目立ちやすくなります。
軽いつけ心地で、髪の根元を立ち上げる効果のあるスプレーや、パウダータイプのスタイリング剤が適しています。
ワックスを使う場合は、ファイバー系など、セット力が強く、かつ軽いテクスチャのものを選び、少量ずつ使うことを心がけましょう。
- 軟毛の人が薄毛になっていないか自分でチェックするにはどうすれば良いですか?
-
最も分かりやすいチェックポイントは、「以前の髪の毛と比べて細くなってきたか」という変化です。
特に頭頂部や前髪の生え際で、髪の毛一本一本の太さが、後頭部や側頭部の髪と比べて明らかに細くなっていたり、短い髪が増えていたりする場合、AGAによる軟毛化が始まっている可能性が高いです。
また、抜け毛の中に細くて短い毛が増えていないかを確認するのも有効です。
- 軟毛は女性ホルモンが関係していますか?
-
軟毛は主に遺伝的な体質と、毛母細胞の活動によって決まるものであり、女性ホルモンの分泌量が直接的な原因となることはほとんどありません。
髪の太さは、思春期以降の男性ホルモンの影響を受けることがありますが、生まれつきの軟毛は性ホルモンのバランスとは別の要因で決定されます。
ただし、軟毛化がAGAによるものである場合は、男性ホルモンのテストステロンから生成されるDHTが深く関与します。
- 軟毛の人が増毛パウダーやウィッグを使うのは効果的ですか?
-
増毛パウダーやウィッグは、軟毛によるボリューム不足や、初期の薄毛を視覚的にカバーするために非常に有効な手段です。
特に軟毛は光を通しやすいため、増毛パウダーを使用することで地肌の透け感を自然に隠すことができます。
これらのアイテムは、日々の自信を取り戻す上で役立ちますが、根本的な薄毛治療にはならないため、AGAの進行が疑われる場合は治療と並行して使用することが重要です。
Reference
SINCLAIR, Rodney. Male pattern androgenetic alopecia. Bmj, 1998, 317.7162: 865-869.
LEE, Won-Soo; LEE, Hae-Jin. Characteristics of androgenetic alopecia in asian. Annals of dermatology, 2012, 24.3: 243.
SINCLAIR, Rodney D.; DAWBER, Rodney PR. Androgenetic alopecia in men and women. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 167-178.
BAZARGAN, Afsaneh Sadeghzadeh, et al. Investigating the Relationship Between Androgenetic Alopecia and Hair Shape, Color, and Thickness: A Case‐Control Study. Health Science Reports, 2025, 8.5: e70764.
LOLLI, Francesca, et al. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine, 2017, 57.1: 9-17.
OIWOH, Sebastine Oseghae, et al. Androgenetic alopecia: A review. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2024, 31.2: 85-92.
RATHNAYAKE, Deepani; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. Expert opinion on pharmacotherapy, 2010, 11.8: 1295-1304.
ASFOUR, Leila; CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. Endotext [Internet], 2023.
CRANWELL, William; SINCLAIR, Rodney. Male androgenetic alopecia. 2015.
TRÜEB, Ralph M.; LEE, Won-Soo. Male alopecia. Guide to successful management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2014.