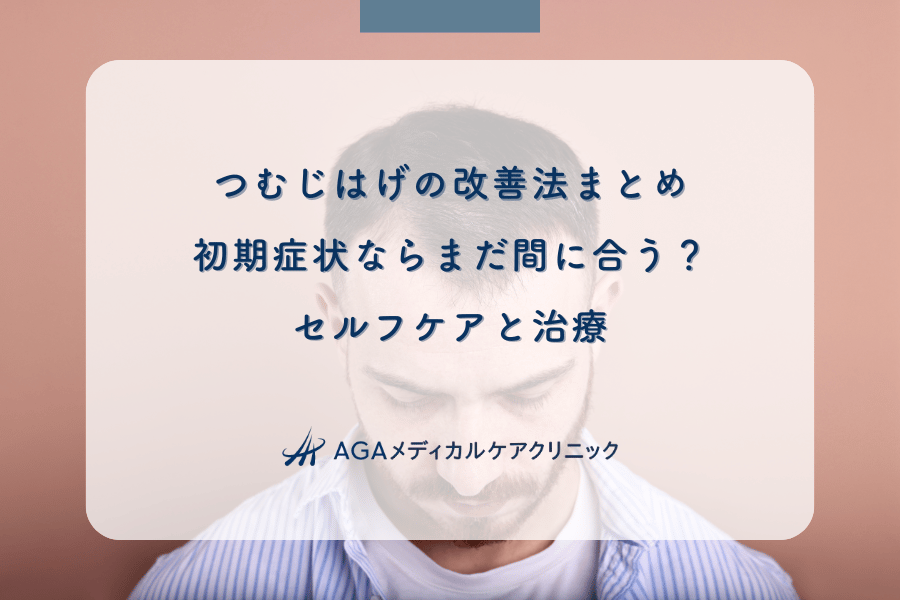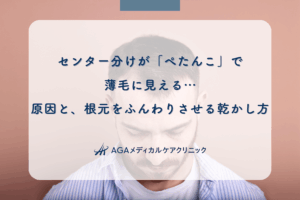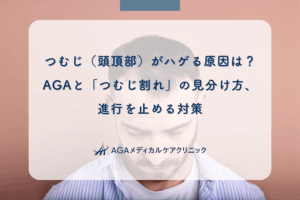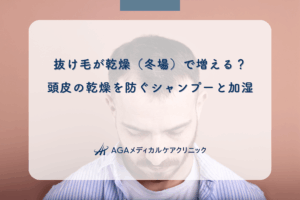ふと鏡を見たり、他人からの視線を感じたりしたときに「もしかして、つむじが薄くなっている?」と不安に感じていませんか。
つむじはげは、自分では確認しにくい場所だからこそ、悩みが深くなりがちです。しかし、初期症状であれば、セルフケアや適切な対策によって改善を目指せる可能性は十分にあります。
この記事では、つむじはげの初期症状の見分け方から、考えられる原因、自宅でできる改善法、そして専門的な治療に至るまで、あなたの不安に寄り添いながら詳しく解説します。
まだ間に合う対策を一緒に見つけていきましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
もしかして「つむじはげ」?初期症状と見分け方
「つむじが薄い」と感じても、それが生まれつきのつむじの形状なのか、それとも脱毛症の初期症状なのか、判断するのは難しいものです。
ここでは、つむじはげの初期症状を見分けるためのいくつかのポイントを紹介します。
つむじと「つむじはげ」の基本的な違い
通常のつむじは、髪の毛が渦を巻いている中心点であり、地肌が見えるのは自然なことです。髪の流れによって地肌が見える範囲は変わります。
特定の方向に髪が強く流れていたり、寝ぐせによって根元がつぶれると地肌が目立つ「つむじ割れ」の状態になりますが、実際には1本1本の髪はしっかりしていて、はげではありません。
一方、つむじはげ(主にAGA:男性型脱毛症によるもの)の初期症状では、つむじ周辺の髪の毛そのものが細く、弱々しくなっていきます。
その結果、以前よりも広範囲にわたって地肌が透けて見えるようになります。単に地肌が見える面積だけでなく、その部分の髪質に変化がないかを確認することが重要です。
つむじ割れについて詳しく見る
「つむじ割れ」とは?20代でも目立つ原因と、「つむじはげ」との見分け方
つむじが「縦割れ」して地肌が見える…原因は薄毛?生え癖?対策と乾かし方
頭皮の色で判断する危険サイン
健康な頭皮は、青白い色をしています。これは血行が良好で、頭皮環境が整っている証拠です。
しかし、つむじ周辺の頭皮が赤みを帯びていたり、茶色っぽくくすんでいたりする場合は注意が必要です。赤みは炎症や血行不良、皮脂の過剰分泌を示している可能性があります。
頭皮環境の悪化は、抜け毛や薄毛を促進する要因となるため、頭皮の色は重要な判断材料となります。
頭皮の色と状態の目安
| 頭皮の色 | 状態 | 考えられる影響 |
|---|---|---|
| 青白い | 健康 | 血行が良く、髪が育ちやすい環境 |
| 赤い | 炎症・血行不良 | かゆみ、フケ、抜け毛のリスク |
| 茶色・黄色っぽい | 皮脂の酸化・血行不良 | 毛穴の詰まり、髪の成長阻害 |
髪の毛の太さや密度の変化
つむじはげの典型的な初期症状は、髪の毛の「軟毛化」です。これは、髪の毛が太く長く成長する前に抜け落ち、細く短いうぶ毛のような髪(軟毛)の割合が増える現象を指します。
つむじ周辺の髪の毛を触ってみて、他の部位(側頭部や後頭部)の髪と比べて、明らかに細くなったり、コシがなくなったりしていないかを確認しましょう。
また、全体的なボリュームが減り、地肌が透けやすくなったと感じる場合も、密度が低下しているサインかもしれません。
自分で確認しにくい場合のチェック方法
つむじは頭頂部にあるため、自分で直接状態を把握するのは困難です。最も確実な方法は、スマートフォンやデジタルカメラで、つむじ周辺の写真を定期的に撮影し、比較することです。
同じ照明、同じ角度で撮影することで、わずかな変化にも気づきやすくなります。
また、信頼できる家族や友人、あるいは行きつけの理容室・美容室で、客観的に見てもらうのも良い方法です。「最近、つむじ周りが気になるのだけど、どう思う?」と尋ねてみましょう。
第三者の視点は、自分では気づかない変化を発見するきっかけになります。
見分け方について詳しく見る
あなたのつむじは正常?20代で注意すべき「つむじはげ(O字はげ)」との見分け方
つむじはげが進行する主な原因
つむじはげがなぜ起こるのか、その背景にはいくつかの要因が関わっています。最も一般的な原因はAGA(男性型脱毛症)ですが、それ以外にも生活習慣が大きく影響します。
AGA(男性型脱毛症)の影響
成人男性の薄毛の多くは、AGA(Androgenetic Alopecia)が原因であると考えられています。
AGAは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、5αリダクターゼという酵素の働きによって、より強力な「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることで発生します。
このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結合すると、髪の成長期が短縮されます。髪が十分に成長する前に休止期に入り、抜け落ちてしまうのです。
この影響は特に前頭部(生え際)と頭頂部(つむじ)に現れやすいため、つむじはげの直接的な原因となることが多いのです。
生活習慣の乱れと頭皮環境
髪の毛は、私たちが摂取する栄養素から作られ、頭皮の毛細血管を通じて栄養を受け取っています。生活習慣の乱れは、この髪の成長を妨げる大きな要因となります。
頭皮環境を悪化させる生活習慣
| 乱れた生活習慣 | 頭皮・髪への主な影響 |
|---|---|
| 偏った食事(脂質・糖質の過剰摂取) | 皮脂の過剰分泌、毛穴の詰まり、血行不良 |
| 睡眠不足 | 成長ホルモンの分泌低下、細胞修復の遅れ |
| 運動不足 | 全身の血行不良、頭皮への栄養不足 |
特に脂っこい食事やインスタント食品の多い食生活は、皮脂の分泌を過剰にし、頭皮の毛穴を詰まらせる原因となります。
また、睡眠不足は髪の成長に欠かせない成長ホルモンの分泌を妨げます。
ストレスと血行不良の関係
精神的なストレスは、自律神経のバランスを崩します。自律神経には交感神経と副交感神経があり、ストレス状態が続くと交感神経が優位になります。
交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、頭皮の毛細血管も収縮し、血行不良を引き起こします。
血行が悪くなると、髪の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。これが、髪の成長を妨げ、抜け毛や薄毛を助長する一因となります。
遺伝的要因はどの程度関わるか
つむじはげ(AGA)の発症には、遺伝的な要因が強く関わっていることが知られています。具体的には、「5αリダクターゼの活性度」と「男性ホルモン受容体の感受性」の2つが遺伝しやすいとされています。
特に、母方の家系に薄毛の人がいる場合(母方の祖父や曽祖父など)、男性ホルモン受容体の感受性が遺伝しやすいと言われています。
ただし、遺伝的要因があるからといって必ずしも発症するわけではなく、あくまで「発症しやすい体質」を受け継ぐということです。
生活習慣などの環境要因と組み合わさることで、発症のリスクが高まると理解しておきましょう。
原因について詳しく見る
若はげが頭頂部(つむじ)から…O字はげの原因と、今すぐできる対策
初期症状ならまだ間に合う?自宅でできるセルフケア改善法
つむじはげの進行が初期段階であれば、日々のセルフケアを見直すことで、頭皮環境を整え、進行を遅らせることが期待できます。ここでは、今日から始められる具体的な改善法を紹介します。
頭皮環境を整えるシャンプー選びと正しい洗い方
頭皮環境の改善は、まず毎日のシャンプーから始まります。
洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい、乾燥やかゆみ、逆に皮脂の過剰分泌を招くことがあります。
つむじはげが気になる方は、頭皮への刺激が少ない「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を使用したシャンプーを選ぶことをおすすめします。
正しいシャンプーの手順
洗い方も重要です。以下の手順で、頭皮を優しく洗い上げましょう。
- ブラッシング:乾いた髪の状態でブラッシングし、ほこりや汚れを浮かせます。
- 予洗い:シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度程度)で1〜2分かけて頭皮と髪をしっかり濡らし、汚れの大半を洗い流します。
- 泡立て:シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。
- 洗う:指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。
- すすぎ:最も重要な工程です。シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて(洗いの倍以上の時間)丁寧にすすぎます。
すすぎ残しは、フケやかゆみ、炎症の原因となるため、特につむじ周りや生え際は念入りに行いましょう。
食生活の見直しと栄養バランス
髪は「ケラチン」というタンパク質からできています。健康な髪を育てるためには、バランスの取れた食事が欠かせません。
髪の成長をサポートする主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身) |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、皮脂分泌の調整 | 豚肉、レバー、マグロ、納豆 |
これらの栄養素を偏りなく摂取することが大切です。特に亜鉛は不足しがちなミネラルであり、タンパク質の合成に重要な役割を果たします。
外食やインスタント食品が多い方は、意識してこれらの食材を取り入れましょう。
良質な睡眠の確保と成長ホルモン
髪の毛の成長や頭皮の細胞修復は、私たちが寝ている間に行われます。
特に、入眠後(特にノンレム睡眠中)に多く分泌される「成長ホルモン」は、毛母細胞の分裂を促し、髪の成長を助ける重要なホルモンです。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低かったりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。
毎日6〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保し、就寝前はスマートフォンやパソコンの使用を控えるなど、リラックスできる環境を整えて良質な睡眠を心がけましょう。
頭皮マッサージによる血行促進の試み
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに役立ちます。血流が改善すれば、毛根に栄養が届きやすくなります。
シャンプー中や、入浴後で体が温まっているときに行うのが効果的です。指の腹を使い、頭皮全体を優しく動かすようにマッサージします。特に血流が滞りやすい頭頂部(つむじ周辺)は丁寧に行いましょう。
ただし、爪を立てたり、強くこすりすぎたりすると頭皮を傷つける原因になるため、力加減には注意が必要です。
セルフケアの限界と育毛剤の活用
生活習慣の改善は頭皮環境を整える上で非常に重要ですが、つむじはげの原因がAGAである場合、セルフケアだけで進行を止め、改善させるのは難しい側面があります。
そこで選択肢となるのが、育毛剤の使用です。
育毛剤と発毛剤の違いを理解する
まず、「育毛剤」と「発毛剤」の違いを正しく理解しておく必要があります。これらは目的と含まれる成分が異なります。
育毛剤と発毛剤の比較
| 種類 | 分類 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 育毛剤 | 医薬部外品 | 抜け毛予防・育毛促進 | 今ある髪を健康に育て、頭皮環境を整える |
| 発毛剤 | 第1類医薬品 | 発毛促進 | 新しい髪を生やし、髪を太くする(ミノキシジル等) |
つむじはげの初期症状で、「抜け毛が増えた」「髪が細くなった」と感じる段階であれば、まずは「育毛剤」で頭皮環境を整え、抜け毛を予防することから始めるのが一般的です。
つむじはげ対策としての育毛剤の選び方
育毛剤には様々な種類がありますが、つむじはげ(AGA)の兆候を考慮する場合、以下のような成分に着目して選ぶと良いでしょう。
- 血行促進成分:センブリエキス、ビタミンE誘導体など。頭皮の血流を改善し、毛根に栄養を届けます。
- 抗炎症成分:グリチルリチン酸2Kなど。頭皮の炎症を抑え、フケやかゆみを防ぎます。
- 皮脂分泌抑制成分:ビタミンC誘導体など。過剰な皮脂を抑え、毛穴の詰まりを防ぎます。
また、AGAの原因である5αリダクターゼの働きを抑制するとされる成分(例:ノコギリヤシエキス、オウゴンエキスなど)が含まれている製品もあります。
自分の頭皮の状態(乾燥肌か、脂性肌か)や悩みに合わせて選びましょう。
効果的な育毛剤の使用タイミングと塗布方法
育毛剤の効果を最大限に引き出すためには、正しい使い方を継続することが重要です。
使用する最適なタイミングは、洗髪後です。シャンプーで頭皮の汚れや皮脂をしっかり落とし、タオルドライで水分を拭き取った後、頭皮が清潔な状態で使用します。
髪が濡れすぎていると成分が薄まってしまうため、ドライヤーで7〜8割程度乾かしてから塗布するのがおすすめです。
塗布する際は、ボトルのノズルを頭皮に直接つけ、気になるつむじ周辺を中心に、頭皮全体に行き渡るように塗布します。
その後、指の腹を使って、育毛剤を頭皮に揉み込むように優しくマッサージします。
医療機関(クリニック)での専門的な治療法
セルフケアや育毛剤を試しても、つむじはげの進行が止まらない、あるいは明らかに薄毛が進行していると感じる場合は、AGAの可能性が高いです。
その際は、皮膚科やAGA専門クリニックなど、医療機関での専門的な治療を検討する段階です。
専門医によるカウンセリングの重要性
まず大切なのは、専門医による正しい診断を受けることです。つむじはげの原因が本当にAGAなのか、あるいは他の脱毛症(円形脱毛症など)や皮膚疾患ではないかを判断してもらう必要があります。
カウンセリングでは、頭皮の状態をマイクロスコープで確認したり、生活習慣や家族歴などをヒアリングしたりします。自分の状態を正確に把握することで、最適な治療法を選択できます。
内服薬によるAGA治療
AGA治療の基本となるのが内服薬です。主に2種類の薬が用いられます。
一つは、AGAの原因であるDHTの生成を抑制する薬(フィナステリドやデュタステリド)です。これらは5αリダクターゼの働きを阻害し、抜け毛を減らし、ヘアサイクルの乱れを正常化する働きがあります。
もう一つは、血行を促進し発毛を促す薬(ミノキシジルのタブレット)です。毛母細胞の活性化を助けるとされています。
これらの薬は医師の処方が必要であり、副作用のリスクもゼロではないため、必ず医師の指導のもとで正しく服用することが求められます。
外用薬(塗り薬)による治療
内服薬と並行して、あるいは内服薬に抵抗がある場合に用いられるのが外用薬(塗り薬)です。
代表的な成分は「ミノキシジル」です。ミノキシジル外用薬は、頭皮の血流を改善し、毛母細胞に直接働きかけて発毛を促進する効果があります。
日本国内では、市販の発毛剤(第1類医薬品)にも配合されていますが、クリニックではより高濃度のミノキシジル外用薬を処方してもらえる場合があります。
つむじはげの部分に直接塗布することで、局所的な改善を期待します。
その他の治療選択肢(注入治療など)
内服薬や外用薬の補助的な治療として、あるいはより積極的な改善を求める場合に、注入治療(メソセラピー)が行われることもあります。
これは、ミノキシジルや成長因子(グロースファクター)、ビタミン、ミネラルなど、髪の成長に有効とされる成分を、注射や専用の機器を使って頭皮に直接注入する治療法です。
薬物治療と組み合わせることで、より早い効果実感を期待できる場合がありますが、治療法や費用はクリニックによって異なります。
主なAGA治療法の比較
| 治療法 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内服薬(DHT抑制系) | 抜け毛の抑制・AGA進行遅延 | AGAの根本原因にアプローチ |
| 内服薬(血行促進系) | 発毛促進 | 内側から血流を改善 |
| 外用薬(ミノキシジル) | 発毛促進 | 気になる部分に直接塗布 |
| 注入治療 | 発毛促進・頭皮環境改善 | 有効成分を頭皮に直接導入 |
つむじはげ改善のために避けるべきNG習慣
改善のための努力を無駄にしないためにも、頭皮や髪に悪影響を与える可能性のある習慣は避けるべきです。日々の生活の中で、無意識にNG習慣を行っていないかチェックしてみましょう。
頭皮に負担をかけるヘアスタイル
つむじはげを隠そうとして、特定のヘアスタイルを続けることが、かえって頭皮に負担をかけている場合があります。
例えば、髪を強く引っ張るようなヘアスタイル(ポニーテールやお団子ヘアなど、男性では少ないですが)は「牽引性脱毛症」の原因となります。
また、毎日同じ分け目を続けていると、その部分の頭皮が紫外線を浴びやすくなり、ダメージが蓄積することもあります。
つむじ周辺の血流を妨げないよう、時には分け目を変えたり、頭皮に負担の少ない髪型を心がけたりすることも大切です。
過度な飲酒や喫煙のリスク
適度な飲酒はリラックス効果もありますが、過度なアルコール摂取は肝臓に負担をかけます。髪の毛の主成分であるタンパク質は肝臓で合成されるため、肝機能が低下すると健康な髪の育成に影響が出ます。
喫煙は、ニコチンの作用によって血管を収縮させ、全身の血行を悪化させます。当然、頭皮の毛細血管も収縮し、毛根への栄養供給が著しく妨げられます。
また、喫煙は体内のビタミンCを大量に消費します。ビタミンCは頭皮の健康維持にも関わるため、喫煙はつむじはげの改善にとって大きな障害となります。
間違ったヘアケアと頭皮へのダメージ
良かれと思って行っているヘアケアが、実は頭皮にダメージを与えているケースもあります。
注意したいヘアケア習慣
| NG習慣 | 頭皮への影響 |
|---|---|
| 熱すぎるお湯でのシャンプー | 必要な皮脂を奪い、頭皮を乾燥させる |
| シャンプー後の自然乾燥 | 雑菌が繁殖しやすくなり、臭いやかゆみの原因に |
| ドライヤーの当てすぎ | 頭皮の乾燥や、髪のタンパク質変性を招く |
シャンプーはぬるま湯で行い、洗髪後は放置せず、速やかにドライヤーで乾かしましょう。
ただし、ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が集中しないよう、こまめに動かしながら乾かすことが重要です。
最後は冷風で仕上げると、キューティクルが引き締まり、頭皮の熱も冷ますことができます。
Q&A
最後につむじはげの改善法に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめます。
- つむじはげはどの年代から始まりますか?
-
つむじはげ、特にAGA(男性型脱毛症)が始まる時期には個人差が非常に大きいです。
早い方では10代後半から20代前半で初期症状が現れ始めることもありますし、30代、40代になってから気になりだす方も多くいます。
遺伝的な要因や生活習慣によって、発症時期は異なります。年代に関わらず、「以前と違う」と感じたら、早めに頭皮の状態をチェックすることが大切です。
- セルフケアだけで改善は可能ですか?
-
原因によって異なります。
生活習慣の乱れやストレス、不適切なヘアケアによる一時的な抜け毛や頭皮環境の悪化であれば、セルフケア(食生活、睡眠、シャンプーの見直しなど)を徹底することで、頭皮環境が整い、改善する可能性はあります。
しかし、原因がAGA(男性型脱毛症)である場合、セルフケアはあくまで「進行を遅らせる」「頭皮環境を良好に保つ」ための補助的な役割が主となります。
AGAは進行性の脱毛症であるため、セルフケアだけで薄毛の進行を完全に止め、元の状態に戻すことは難しいのが実情です。
- 育毛剤はいつまで続ける必要がありますか?
-
育毛剤の主な目的は、頭皮環境を整え、今ある髪を健康に育て、抜け毛を予防することです。使用をやめると、再び頭皮環境が悪化し、抜け毛が増える可能性があります。
そのため、効果を実感し、良い状態を維持したいのであれば、継続して使用することが推奨されます。
育毛剤は、日々のスキンケアと同じように、頭皮のケア習慣として取り入れると良いでしょう。
- クリニックでの治療をやめるとどうなりますか?
-
AGA治療(特に内服薬)は、AGAの進行を抑制するための治療です。そのため、治療を中断すると、抑制されていたAGAの作用が再び活発になり、薄毛が再度進行し始める可能性が高いです。
多くの場合、治療によって改善した状態を維持するためには、医師の指導のもとで治療を継続する必要があります。
自己判断で中断せず、減薬や休薬を希望する場合は、必ず担当の医師に相談してください。
O字・頭頂部・つむじハゲの記事
Reference
PRAVITASARI, Dwi Nurwulan; SETYANINGRUM, Trisniartami. The Profile Of New Androgenic Alopecia Patients At Dermato-Venereology Outpatient Clinic Of Dr. Soetomo Hospital Surabaya In 2009-2011. In: The 3 rd International Symposium of Public Health (The 3 rd ISoPH)“Challenging Public Health Roles Towards Global Health Issues”. 2011. p. 113.
MOHAN, Sunitha. An Observational Study to Establish an Association Between Early Onset Androgenetic Alopecia and Prostatic Abnormalities. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
VILLANI, Alessia, et al. Hair aging and hair disorders in elderly patients. International journal of trichology, 2022, 14.6: 191-196.
HE, Fanping, et al. Epidemiology and disease burden of androgenetic alopecia in college freshmen in China: A population-based study. PLoS One, 2022, 17.2: e0263912.
MEHER, Arpita, et al. Hair loss–A growing problem among medical students. CosmoDerma, 2023, 3.
PUDASAINI, Prajwal, et al. Prevalence and Clinical Characteristics of Androgenetic Alopecia in Nepalese Patients: A Cross-sectional Observational Study. Civil Medical Journal, 2023, 1.1: 29-34.
HARVEY, Kevin. Medicalisation, pharmaceutical promotion and the Internet: A critical multimodal discourse analysis of hair loss websites. Social Semiotics, 2013, 23.5: 691-714.
POLANCO-LLANES, Alondra Saray, et al. Plica Neuropathica (Polonica) Secondary to Diffuse Alopecia: A Case Report and Literature Review. Cureus, 2025, 17.9.
ROBERTS, J. L. Geriatric hair and scalp disorders. Geriatr Dermatol, 2001.
NAWTON, Gail D.; PRAY, W. Steven; POPOVICH, Nicholas G. New OTC Drugs and Devices 1998: A Selective Review. Journal of the American Pharmaceutical Association (1996), 1999, 39.2: 207-216.
PUDASAINI, Prajwal, et al. Prevalence and Clinical Characteristics of Androgenetic Alopecia in Nepalese Patients: A Cross-sectional Observational Study. Civil Medical Journal, 2023, 1.1: 29-34.
HARVEY, Kevin. Medicalisation, pharmaceutical promotion and the Internet: A critical multimodal discourse analysis of hair loss websites. Social Semiotics, 2013, 23.5: 691-714.
POLANCO-LLANES, Alondra Saray, et al. Plica Neuropathica (Polonica) Secondary to Diffuse Alopecia: A Case Report and Literature Review. Cureus, 2025, 17.9.
ROBERTS, J. L. Geriatric hair and scalp disorders. Geriatr Dermatol, 2001.
NAWTON, Gail D.; PRAY, W. Steven; POPOVICH, Nicholas G. New OTC Drugs and Devices 1998: A Selective Review. Journal of the American Pharmaceutical Association (1996), 1999, 39.2: 207-216.