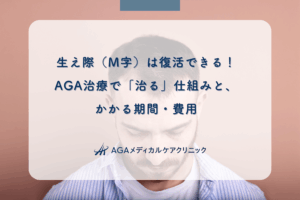冬になると枕元に落ちる抜け毛の量が増えて不安になることはありませんか。実はその抜け毛、冬特有の「乾燥」が大きく関係しているかもしれません。
空気の乾燥は肌だけでなく頭皮の水分も奪い、バリア機能を低下させて抜け毛を引き起こす原因となります。しかし正しい知識を持って対策を行えば、乾燥による抜け毛は十分に防ぐことが可能です。
この記事では冬の抜け毛の原因から、頭皮に優しいシャンプーの選び方、効果的な保湿ケアまで、今すぐ実践できる具体的な方法を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
冬場に抜け毛が増える原因は乾燥にある
寒い季節になると抜け毛が気になり始める方が多くいますが、その背景には、冬ならではの環境変化が頭皮に大きな負担をかけている事実があります。
気温と湿度が低下するこの時期は、頭皮にとって非常に過酷な環境です。乾燥は単なる肌荒れにとどまらず、髪の成長サイクルにも悪影響を及ぼしかねません。
冬の抜け毛増加の主要な要因である「乾燥」と、それに関連する様々な要素について深く理解することから対策を始めましょう。
頭皮の乾燥が抜け毛を引き起こす理由
頭皮が乾燥すると、なぜ抜け毛につながるのでしょうか。健康な頭皮は適度な水分と皮脂によって守られており、外部の刺激から内部の組織を保護するバリア機能が働いています。
しかし乾燥が進むとこのバリア機能が低下し、わずかな刺激でも炎症を起こしやすい状態になります。炎症が続くと毛根周辺の組織がダメージを受け、髪を支える力が弱まってしまいます。
その結果、成長途中の髪が抜け落ちてしまったり、次に生えてくる髪が細く弱くなってしまったりするのです。
また乾燥はフケやかゆみの原因にもなり、頭皮を掻いてしまうことで物理的に髪を引き抜いてしまうリスクも高まります。
健やかな髪を育てる土台である頭皮が砂漠のように乾いていては、丈夫な作物が育たないのと同じように、太く強い髪は育ちにくくなるのです。
冬特有の環境が頭皮に与える影響
冬は一年の中で最も空気が乾燥する季節です。気象庁のデータを見ても冬場の湿度は著しく低下することがわかります。
外気の乾燥に加えて、室内では暖房器具を使用するため、空気はさらに乾いた状態になります。
私たちは一日の大半をこのような乾燥した環境下で過ごすことになり、知らず知らずのうちに頭皮から水分が奪われ続けているのです。
また、気温の低下は皮脂の分泌量を減少させます。皮脂は天然の保湿クリームとしての役割も果たしていますが、その分泌が減ることで頭皮はより乾燥しやすい無防備な状態にさらされます。
冷たい外気と暖房の効いた室内との激しい寒暖差も頭皮にとってはストレスとなり、自律神経の乱れを引き起こして頭皮環境を悪化させる一因となります。
乾燥以外の冬の抜け毛要因
冬の抜け毛増加は乾燥だけが原因ではありません。寒さによる体の冷えも大きく関係しています。気温が下がると人間の体は体温を逃がさないように血管を収縮させます。
頭皮には細い毛細血管が張り巡らされており、髪の成長に必要な栄養や酸素は血液によって運ばれています。
血管が収縮して血行が悪くなると、毛根に十分な栄養が届きにくくなり、髪の成長が妨げられて抜け毛が増えてしまうのです。
さらに冬は風邪やインフルエンザなどの感染症が流行しやすく、体調を崩しやすい季節でもあります。免疫力の低下や体調不良は髪の成長サイクルを乱す原因となり得ます。
年末年始の忙しさやイベント続きによる生活リズムの乱れ、暴飲暴食なども、間接的に頭皮環境に悪影響を与える要因として見逃せません。
あなたの頭皮は大丈夫?乾燥レベルセルフチェック
自分の頭皮が今どのような状態にあるのかを正確に把握することは、適切なケアを行う上で非常に大切です。顔の肌タイプに乾燥肌や脂性肌があるように、頭皮にもタイプがあります。
特に冬場は自分が思っている以上に乾燥が進んでいるケースも少なくありません。日々のちょっとしたサインを見逃さず、早めに対処することで深刻なトラブルを防ぐことができます。
簡単なセルフチェックで、現在の頭皮の乾燥レベルを確認してみましょう。
フケの種類で見分ける頭皮の状態
フケは頭皮からのSOSサインですが、その状態によって原因が異なります。あなたのフケはどのようなタイプでしょうか。
乾燥が原因の「乾性フケ」と、皮脂の過剰分泌が原因の「脂性フケ」では対策が真逆になることもあるため、正しく見極める必要があります。
乾性フケはパラパラと乾燥しており、肩に落ちやすいのが特徴です。一方、脂性フケは湿り気があり、頭皮や髪の根元に張り付くような特徴があります。
フケのタイプ別特徴比較
| 特徴 | 乾性フケ(乾燥が原因) | 脂性フケ(皮脂が原因) |
|---|---|---|
| 見た目 | 細かく、白い粉状 | 大きく、黄色っぽい塊状 |
| 触感 | カサカサしている | ベタベタ、湿っている |
| 主な発生原因 | 頭皮の乾燥、洗いすぎ | 皮脂過多、真菌の増殖 |
かゆみや赤みは危険信号
頭皮にかゆみを感じる場合、それは乾燥による炎症の初期段階である可能性が高いです。乾燥して敏感になった頭皮は、少しの刺激でもかゆみを感じやすくなります。
無意識のうちに爪を立てて掻いてしまうと、頭皮に細かい傷がつき、そこから雑菌が入り込んでさらに炎症が悪化するという悪循環に陥ります。
また、鏡で頭皮を見たときに赤くなっている部分があれば要注意です。健康な頭皮は青白く透き通るような色をしていますが、赤みがある場合は炎症を起こしている証拠です。
この状態を放置すると抜け毛が急増する危険性があるため、なるべく早く炎症を鎮めるケアが必要になります。
かゆみや赤みは頭皮からの危険信号と捉え、決して軽視しないようにしましょう。
頭皮の硬さと血行不良の関係
頭皮の硬さも乾燥レベルを知る重要な指標です。両手の指の腹を使って、頭皮を前後左右に動かしてみてください。健康な頭皮は適度な弾力があり、柔軟に動きます。
しかし乾燥して血行が悪くなっている頭皮は、突っ張ったように硬く、動きが悪くなっていることが多いのです。頭皮が硬い状態は、土壌が硬く痩せ細っている畑のようなものです。
これでは太く丈夫な髪は育ちません。乾燥すると皮膚は柔軟性を失い硬くなりやすいですが、同時に血行不良も頭皮を硬くする要因です。
冬場は特に冷えによって血行が悪くなりやすいので、意識的に頭皮の柔軟性をチェックし、マッサージなどで血流を促すことが大切です。
頭皮の乾燥セルフチェックリスト
- シャンプー後、すぐに頭皮が突っ張る感じがする
- パラパラとした細かいフケが肩によく落ちている
- 日中、頭が無性にかゆくなることがある
- 頭皮を触るとカサカサしていて潤いがない
- 以前より抜け毛が増え、髪が細くなってきた気がする
頭皮の乾燥を防ぐシャンプーの選び方と使い方
毎日のシャンプーは頭皮環境を大きく左右する最も基本的なケアです。しかし良かれと思って行っているその洗髪が、実は乾燥を加速させている原因になっているかもしれません。
特に冬場は、夏場と同じ洗浄力の強いシャンプーを使い続けると、必要な皮脂まで奪いすぎてしまう可能性があります。
乾燥を防ぐためには、季節や自分の頭皮状態に合わせたシャンプー選びと、正しい洗い方を実践することが何よりも重要です。
洗浄力が強すぎるシャンプーは避ける
市販されている男性用シャンプーの中には、爽快感を重視して非常に強い洗浄成分が配合されているものがあります。
これらは「高級アルコール系」と呼ばれる洗浄成分が使われていることが多く、パッケージの成分表示に「ラウレス硫酸Na」や「ラウリル硫酸Na」といった記載があるのが特徴です。
脂性肌の方や夏場の汗をたくさんかく時期には適していることもありますが、乾燥しやすい冬場に使用すると頭皮のうるおいを保つために必要な皮脂まで根こそぎ洗い流してしまいます。
皮脂が極端に不足すると、頭皮は無防備になり、急激に乾燥が進んでしまいます。冬場の抜け毛が気になる時期は、洗浄力がマイルドなものへと切り替えることを検討しましょう。
アミノ酸系など保湿成分配合のものを選ぶ
乾燥が気になる冬の頭皮におすすめなのが「アミノ酸系」の洗浄成分を配合したシャンプーです。
アミノ酸は私たちの皮膚や髪を構成するタンパク質の元となる成分であり、頭皮への刺激が少なく、優しく洗い上げることができます。
必要な皮脂やうるおいを適度に残しながら汚れを落としてくれるため、乾燥対策には最適です。
成分表示では「ココイルグルタミン酸TEA」や「ラウロイルメチルアラニンNa」などが代表的なアミノ酸系洗浄成分です。
少し価格は高くなる傾向にありますが、頭皮への投資と考えて選んでみる価値は十分にあります。
主なシャンプー洗浄成分の比較
| 洗浄成分タイプ | 洗浄力 | 頭皮への刺激 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 高級アルコール系 | 非常に強い | やや強い | 脂性肌、整髪料を多用する人 |
| 石鹸系 | 強い | やや強い | さっぱり洗いたい健康毛の人 |
| アミノ酸系 | マイルド | 弱い | 乾燥肌、敏感肌、抜け毛が気になる人 |
正しい洗髪方法で乾燥リスクを減らす
良いシャンプーを選んでも、洗い方が間違っていては効果が半減してしまいます。
まず大切なのはお湯の温度です。熱すぎるお湯は皮脂を過剰に溶かし出してしまうため、38度前後の少しぬるいと感じるくらいの温度が適しています。
洗う際は、爪を立てずに指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。ゴシゴシと強くこする必要はありません。そして最も重要なのが「すすぎ」です。
シャンプー剤が頭皮に残ると、それが刺激となって炎症やかゆみの原因になります。洗う時間の倍以上の時間をかけて、丁寧に洗い流すことを心がけてください。
また、朝シャンは頭皮の保護膜である皮脂を洗い流した状態で外出することになり、紫外線や乾燥した外気の影響をダイレクトに受けてしまうため、夜に洗髪することをおすすめします。
育毛剤の効果を最大化する頭皮の保湿ケア
抜け毛対策として育毛剤を使用している方も多いと思いますが、乾燥した硬い頭皮にいくら高価な育毛剤を使っても、その成分は十分に浸透していきません。
乾いた土に水が染み込みにくいのと同じ原理です。育毛剤の効果を最大限に引き出すためには、まず頭皮環境を整え、成分を受け入れる態勢を作ることが重要です。
ここでは、育毛剤と併用したい保湿ケアについて解説します。
育毛剤をつける前の土台作り
育毛剤は、洗髪後の清潔な頭皮に使用するのが基本です。毛穴の汚れや余分な皮脂が取り除かれた状態であれば、有効成分が毛根まで届きやすくなります。
洗髪後はタオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで髪の根元を中心に8割程度乾かした状態が、育毛剤を塗布するベストなタイミングと言われています。
完全に乾かしすぎると頭皮も乾燥してしまうため、少し湿り気が残る程度が良いでしょう。
この状態で育毛剤を塗布し、指の腹で優しくなじませながらマッサージを行うことで、血行が促進され、成分の浸透も良くなります。
頭皮用保湿ローションの活用
顔に化粧水をつけるように、頭皮にも専用の保湿ローションを使う習慣を取り入れてみましょう。特に冬場の乾燥が激しい時期は、育毛剤だけでは保湿が不十分な場合があります。
頭皮用保湿ローションは、乾燥によるフケやかゆみを抑え、頭皮にうるおいを与えることに特化したアイテムです。
使用する順番は製品によって異なる場合もありますが、一般的には「育毛剤」を先に使い、その有効成分を浸透させた後に、「保湿ローション」で蓋をするという使い方が効果的です。
ただし、両方を一度に使うとベタつきが気になる場合は、朝は保湿ローション、夜は育毛剤といったように使い分けるのも一つの方法です。
オイルケアで水分蒸発を防ぐ
さらに強力な保湿を求める場合は、頭皮用のオイルを活用するのも有効です。
ホホバオイルや椿油など、人間の皮脂に近い成分を持つ天然オイルは、頭皮になじみやすく、水分の蒸発を防ぐ強力な保護膜を作ってくれます。
シャンプー前の頭皮マッサージにオイルを使用すれば、毛穴に詰まった頑固な皮脂汚れを浮かし出すクレンジング効果も期待できます。
また、洗髪後の濡れた頭皮にごく少量を薄くなじませることで、ドライヤーの熱から頭皮を守る効果もあります。
ただし、つけすぎるとベタつきや毛穴詰まりの原因になるため、使用量には十分注意し、自分の頭皮に合うかどうか様子を見ながら取り入れてください。
生活習慣から見直す乾燥対策
頭皮の乾燥は、外部からのケアだけでなく、日々の生活習慣も大きく影響しています。
いくら高価なシャンプーや育毛剤を使っていても、生活環境が乾燥を招くものであれば、その効果は限定的になってしまいます。
体の内側と外側の両面からアプローチすることで、乾燥に負けない強い頭皮を育てることができます。
部屋の加湿で適切な湿度を保つ
冬の室内は、暖房の使用により砂漠並みに乾燥していることも珍しくありません。湿度が40%を下回ると、肌や頭皮の乾燥スピードは急激に加速します。
頭皮にとって快適な湿度は50%〜60%程度と言われています。加湿器を有効活用して、部屋の湿度を適切に保つように心がけましょう。
特に就寝中は長時間無防備な状態になるため、寝室の加湿は非常に重要です。
加湿器がない場合でも、濡れたタオルを部屋に干したり、コップに水を入れて置いておいたりするだけでも、一定の加湿効果は期待できます。
湿度を保つための工夫比較
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 加湿器の使用 | 安定して高い加湿効果が得られる | 定期的な清掃が必要、電気代がかかる |
| 濡れタオルを干す | 手軽にすぐ実践できる、コストゼロ | 加湿範囲が狭い、こまめな交換が必要 |
| 観葉植物を置く | 自然な蒸散作用、インテリア性 | 劇的な加湿効果は期待できない |
内側からの水分補給と栄養摂取
体の水分不足は直ちに頭皮の乾燥につながります。冬は夏に比べて喉の渇きを感じにくいため、水分摂取量が減りがちです。意識的に水や白湯などをこまめに飲み、体の内側から水分を補給しましょう。
また、頭皮や髪の材料となる栄養素を食事からしっかり摂ることも大切です。
髪の主成分である「タンパク質」、血行を促進し抗酸化作用もある「ビタミンE」、皮膚や粘膜を健康に保つ「ビタミンA」や「ビタミンB群」、髪の成長に欠かせない「亜鉛」などをバランスよく摂取することで、乾燥に負けない健やかな頭皮を作ることができます。
頭皮環境を整えるおすすめ食材
| 栄養素 | 期待できる効果 | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪や頭皮の原料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、レバー、納豆、マグロ |
| ビタミンA・C・E | 血行促進、抗酸化作用 | 緑黄色野菜、ナッツ類、柑橘類 |
質の高い睡眠で頭皮のターンオーバーを整える
睡眠は最高の美容液と言われるように、頭皮にとっても非常に大切なメンテナンス時間です。睡眠中、特に深い眠りについている間に成長ホルモンが多く分泌され、頭皮の細胞が修復・再生されます。
このターンオーバーが正常に行われることで、頭皮のバリア機能が保たれ、乾燥しにくい状態が作られます。
睡眠不足が続くとターンオーバーのサイクルが乱れ、バリア機能が低下して乾燥や炎症を引き起こしやすくなります。
就寝前のスマホ使用を控える、温かいお風呂にゆっくり浸かるなどして、質の高い睡眠を確保するように努めましょう。
注意すべき間違った頭皮ケア
良かれと思ってやっていたケアが、実は頭皮の乾燥を悪化させているというケースは少なくありません。自己流のケアは時に危険を伴います。
ここで改めて、やりがちな間違ったケアを確認し、正しい方法へと軌道修正していきましょう。
熱すぎるシャワー温度
寒い冬は熱々のシャワーで温まりたい気持ちはよくわかります。しかし、42度を超えるような熱いお湯は、頭皮に必要な皮脂を一瞬で溶かし流してしまいます。
食器洗いの際、お湯を使うと油汚れがよく落ちるのと同じ原理です。頭皮の皮脂は、悪者扱いされがちですが、乾燥や外部刺激から頭皮を守る大切な役割を持っています。
これを必要以上に取り除いてしまうと、頭皮は極度の乾燥状態に陥ります。少し物足りないと感じるかもしれませんが、38度〜40度程度のぬるま湯で洗う習慣をつけましょう。
ドライヤーの当てすぎと自然乾燥の弊害
洗髪後、ドライヤーの熱が髪や頭皮を傷めることを心配して、自然乾燥させている方がいます。
しかし、これは逆効果です。濡れた頭皮は雑菌が繁殖しやすい高温多湿な環境であり、長時間放置するとニオイやかゆみ、炎症の原因になります。
また、水分が蒸発する際に頭皮の熱を奪い、血行不良を招くこともあります。逆に、ドライヤーを近づけすぎて長時間熱風を当てるのも、頭皮を「火傷」に近い乾燥状態にしてしまいます。
正しい方法は、タオルでしっかりと水分を取った後、頭皮から20cm以上離してドライヤーを当て、温風と冷風を切り替えながら、根元を中心に8割〜9割程度乾かすことです。
過剰な洗髪回数
「清潔にしなければ」という意識が強すぎて、1日に2回も3回もシャンプーをするのは洗いすぎです。過剰な洗髪は、頭皮のバリア機能を破壊する行為に他なりません。
一度失われた皮脂が元の状態に戻るまでには一定の時間が必要です。その間、頭皮は無防備な状態にさらされてしまいます。基本的にシャンプーは1日1回、夜に行えば十分です。
乾燥がひどい場合は、2日に1回はシャンプー剤を使わずにお湯だけで汚れを落とす「湯シャン」を取り入れるのも有効な手段の一つです。
やりがちなNGケアと正しいケア
| ケア項目 | NGケア(乾燥を招く) | 正しいケア(乾燥を防ぐ) |
|---|---|---|
| シャワー温度 | 42度以上の熱いお湯 | 38度〜40度のぬるま湯 |
| 洗髪後の乾燥 | 自然乾燥、ドライヤーの近すぎ | タオルドライ後、離して乾かす |
| 洗髪回数 | 朝晩2回以上のシャンプー | 1日1回、夜のみ |
乾燥による抜け毛が改善しない場合の対処法
これまで紹介した対策を実践しても抜け毛が減らない、あるいは頭皮の状態が悪化していると感じる場合は、自分だけの力で解決しようとせず、専門家の助けを借りることも検討すべきです。
抜け毛の背後には、単なる乾燥だけでなく、治療が必要な皮膚疾患や脱毛症が隠れている可能性もあります。
皮膚科など専門医への相談目安
頭皮のトラブルは、初期段階で適切な治療を受ければ早期に改善することが多いものです。
しかし、「たかが乾燥」「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、慢性化して治りにくくなり、深刻な薄毛につながるリスクもあります。
以下のような症状が見られる場合は、決して自己判断せず、早めに皮膚科や専門のクリニックを受診することをおすすめします。
専門医であれば、あなたの頭皮状態を正確に診断し、適切な薬の処方やアドバイスをしてくれます。
専門医受診を検討すべきサイン
- 強いかゆみや赤みが2週間以上続いている
- フケが大量に出て、市販のシャンプーでは改善しない
- 頭皮に湿疹、ただれ、膿(うみ)などがみられる
- 短期間で急激に抜け毛の量が増えたと感じる
- 円形脱毛症のように、部分的に髪が抜けている箇所がある
他の脱毛症の可能性も疑う
冬の乾燥が引き金となっていたとしても、根本的な原因が「男性型脱毛症(AGA)」や「脂漏性脱毛症」である可能性も否定できません。AGAは進行性の脱毛症であり、早期の対策が重要です。
また脂漏性脱毛症は、皮脂の過剰分泌とそれに伴う常在菌の異常繁殖が原因で起こります。これらは一般的な乾燥対策だけでは改善が難しく、それぞれの原因に合わせた専門的な治療が必要です。
自己流のケアに限界を感じたら、これらの脱毛症を疑ってみる視点も大切です。
ストレス管理の重要性
現代社会においてストレスは避けられないものですが、過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こして頭皮環境を悪化させます。
「ストレスで髪が抜ける」というのは決して迷信ではありません。冬は寒さ自体が身体的なストレスとなるほか、年末年始の忙しさなどで精神的なストレスも溜まりやすい時期です。
趣味の時間を持つ、適度な運動をする、ゆっくり入浴するなど、自分なりのリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないように上手に管理することも、立派な抜け毛対策の一つです。
季節・ストレス・生活習慣に戻る
よくある質問
- 乾燥したフケと脂性のフケの違いは何ですか?
-
乾燥したフケ(乾性フケ)は細かくパラパラとしており、肩に落ちやすいのが特徴です。頭皮のカサつきや強いかゆみを伴うことが多いです。
一方、脂性のフケ(脂性フケ)は大きくて湿り気があり、髪の根元や頭皮にベタっと張り付く傾向があります。こちらは皮脂の過剰分泌が主な原因です。
- シャンプーは1日何回が理想ですか?
-
基本的には1日1回、夜の洗髪で十分です。洗いすぎは必要な皮脂まで奪い、乾燥を悪化させる原因になります。
乾燥がひどい場合は、2日に1回はお湯だけで洗う「湯シャン」にするなど、頭皮の状態に合わせて調整することをおすすめします。
- 加湿器がない場合の部屋の加湿方法はありますか?
-
濡れたバスタオルを部屋に干す、洗濯物を室内干しにする、洗面器にお湯を張って置くなどの方法で、ある程度の加湿効果が得られます。
また、定期的に霧吹きで空中に水をスプレーするのも一時的ですが効果があります。
- 頭皮の乾燥はどのくらいで改善しますか?
-
個人差はありますが、頭皮の細胞が生まれ変わるサイクル(ターンオーバー)は約28日〜40日程度と言われています。
正しいケアを始めてから効果を実感できるまでには、最低でも1ヶ月程度は継続して様子を見る必要があります。焦らずじっくりとケアを続けることが大切です。
- 冬が終われば自然に抜け毛は減りますか?
-
冬の乾燥や寒さだけが原因であれば、春になって環境が改善すれば抜け毛は減る可能性があります。
しかし、冬の間に頭皮が受けたダメージが蓄積していたり、生活習慣が乱れたままだったりすると、季節が変わっても抜け毛が続くことがあります。
油断せず、年間を通して適切なケアを心がけることが重要です。
Reference
EAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.
LANJEWAR, Ameya, et al. Review on Hair Problem and its Solution. Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 2020, 10.3: 322-329.
TRÜEB, Ralph M.; GAVAZZONI DIAS, Maria Fernanda Reis. Fungal diseases of the hair and scalp. In: Hair in infectious disease: recognition, treatment, and prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 151-195.
RAJPUT, R. Understanding hair loss due to air pollution and the approach to management. Hair Ther Transplant, 2015, 5.133: 2.
KINGSLEY, Philip. The Hair Bible: A Complete Guide to Health and Care. Aurum, 2014.
MOLLOY, Hugh; EGGER, Garry. Lifestyle and Environmental. Lifestyle Medicine: Lifestyle, the Environment and Preventive Medicine in Health and Disease, 2017, 411.
FREEMAN, Amy Krupnick; GORDON, Marsha. Dermatologic diseases and problems. In: Geriatric Medicine: An Evidence-Based Approach. New York, NY: Springer New York, 2003. p. 869-881.
MARSH, Jennifer Mary, et al. Healthy hair. New York: Springer International Publishing, 2015.