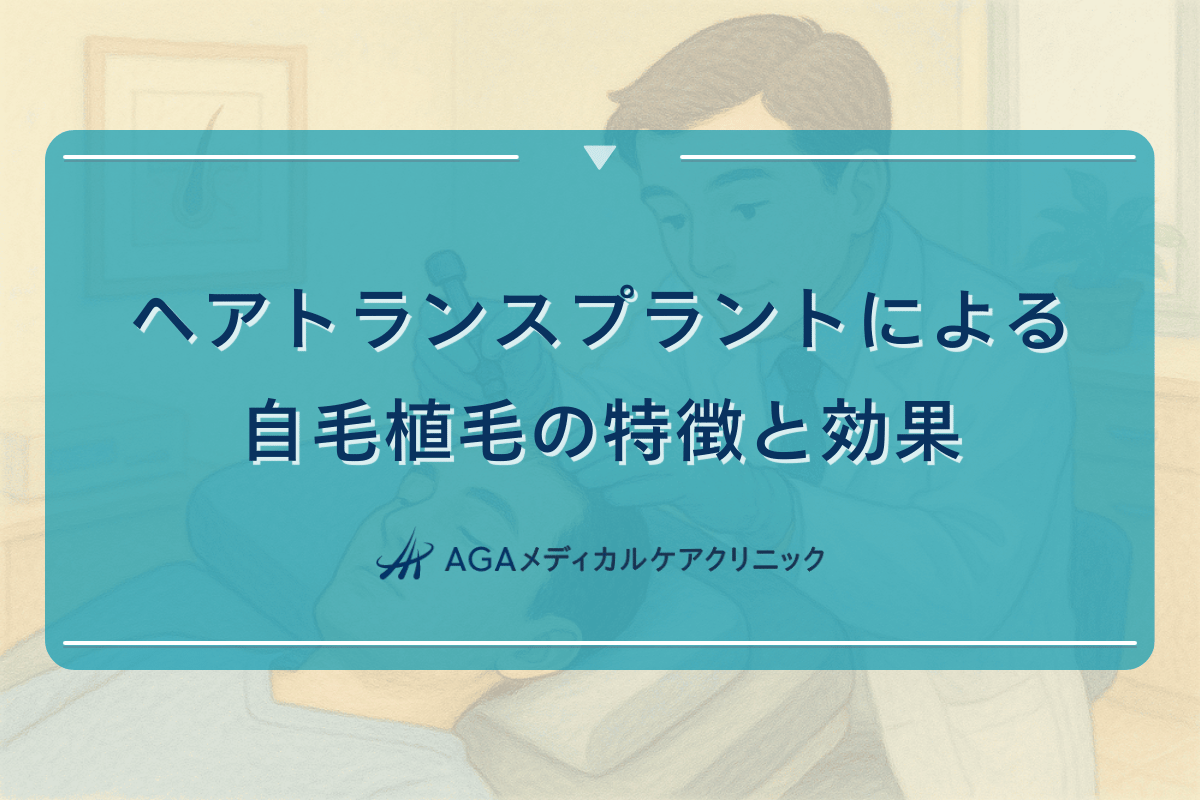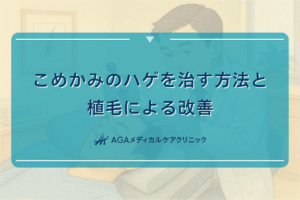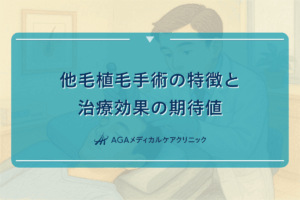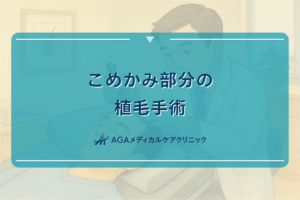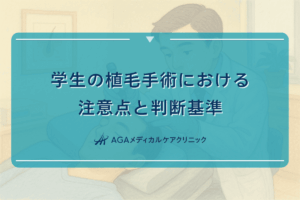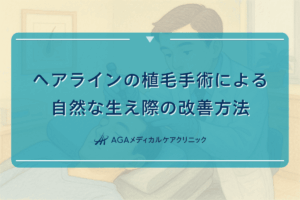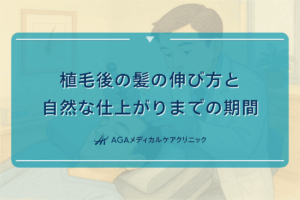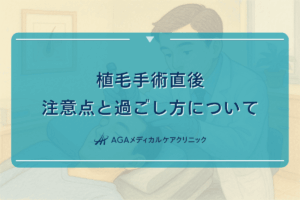ヘアトランスプラントは、自身の後頭部や側頭部に残っている健康な毛髪を薄毛が進行している箇所へと外科的に移動させる医療技術であり、一度生着すれば生涯にわたり髪が生え続ける恒久的な解決策となります。
薬物療法では効果が実感できなかった方や、かつらのメンテナンスに煩わしさを感じている方にとって、自分の髪が再び蘇るという事実は大きな希望となり得ます。
本記事では、このヘアトランスプラントの具体的な手法の違い、必要となる費用の目安、手術に伴うリスクや術後の経過について、専門的な視点から包み隠さず詳細に解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ヘアトランスプラントの基礎知識と医学的根拠
ヘアトランスプラントとは、男性ホルモンの影響を受けにくい後頭部の毛包組織を薄毛部位へ再配置する外科手術です。
拒絶反応のリスクがなく、生着後は本来のヘアサイクルを取り戻して半永久的に生え変わり続ける確実性の高い治療法です。
男性型脱毛症に対する外科的アプローチの有効性
男性型脱毛症(AGA)は進行性の症状であり、放置すると徐々に髪の密度が低下していきます。
内服薬や外用薬は進行を遅らせたり、今ある髪を太くしたりする点において一定の役割を果たしますが、すでに毛根が機能を停止してしまった部位に対しては発毛効果を期待することは困難です。
ここで外科的アプローチであるヘアトランスプラントが重要な選択肢として浮上します。物理的に毛根が存在しない場所に、元気な毛根を「引っ越し」させることで、髪の土台そのものを再構築できるからです。
医学的に見ても、自分自身の組織を使用するため安全性は高く、薬物療法で限界を感じた場合でも、外見上の劇的な改善を見込める手段として確立されています。
後頭部の毛根が持つドナー優位説の重要性
ヘアトランスプラントが成功する最大の理由は、「ドナー・ドミナンス(ドナー優位説)」という医学的法則に基づいている点にあります。
AGAの原因物質であるジヒドロテストステロン(DHT)の影響を受けやすいのは、前頭部や頭頂部の毛根に限られます。
一方で、後頭部や側頭部の毛根は遺伝的にDHTの影響を受けにくい性質を持っています。この性質は、場所を移動しても変わりません。
つまり、後頭部の毛根を前頭部に移植した場合、その毛根は「後頭部の性質」を維持したまま成長を続けます。
そのため、移植された髪はAGAの影響を受けて再び抜け落ちてしまう可能性が極めて低く、長期的に豊かな髪を維持することが可能になります。
人工毛植毛との決定的な違いと生着率
植毛には合成繊維で作られた人工毛を使用する方法も存在しますが、現在の主流は圧倒的に自毛植毛です。
人工毛は異物であるため、体が生体防御反応を示し、炎症や感染症を引き起こすリスクが常に伴います。また、時間の経過とともに抜け落ちてしまうため、定期的なメンテナンスと追加手術が必要です。
対照的に、ヘアトランスプラント(自毛植毛)は自分の細胞であるため、免疫反応による拒絶が起こりません。
熟練した医師が執筆を行えば、移植した毛髪の生着率は90%以上、場合によっては95%以上という高い数値を叩き出します。
一度生着してしまえば特別な手入れは不要で、パーマやカラーリングも自由に楽しめる点は、自毛ならではの大きな利点です。
移植手術が推奨される進行レベルと適応判断
すべてのAGA患者に対してヘアトランスプラントが無条件に推奨されるわけではありません。
一般的には、生え際の後退が顕著な「M字型」や、頭頂部が薄くなる「O字型」がある程度進行し、かつ後頭部に十分なドナー(移植するための元気な髪)が残っている場合が良い適応となります。
若年層で進行がまだ初期段階の場合、将来的な脱毛範囲の予測が難しいため、まずは薬物療法から開始し、様子を見ることが賢明な場合もあります。
医師はマイクロスコープを用いて頭皮の状態や毛髪の密度を詳細に観察し、将来の進行予測まで含めた上で、手術を行うべきか、どの程度の範囲をカバーすべきかを慎重に判断します。
主要な術式の分類と具体的な手技の違い
現在主流の術式は、メスを使って頭皮を帯状に切り取るFUT法と、専用のパンチで毛根を個別にくり抜くFUE法に大別されます。
それぞれ採取時の傷跡の残り方や採取可能な毛量に明確な違いがあるため、自身の優先順位に合わせて選択する必要があります。
メスを使用するFUT法の利点と縫合技術
FUT法(ストリップ法)は、後頭部の頭皮を帯状に薄く切り取り、そこから顕微鏡を使って丁寧に株(グラフト)を切り分けていく手法です。
この方法の最大の利点は、毛根組織を直視下で確認しながら分離できるため、毛根切断のリスク(ドナーロス)を最小限に抑えられることです。
また、一度に大量のグラフトを採取できるため、広範囲の薄毛を一度の手術でカバーしたい場合に適しています。
頭皮を切り取ることに抵抗を感じる方もいますが、熟練した医師によるトリコフィティック縫合などの特殊な縫合技術を用いれば傷跡から髪が生えるようになり、最終的には一本の細い線状の傷跡として目立たなくなります。
パンチブレードを用いるFUE法の低侵襲性
FUE法は、直径1mm以下の極細のチューブ状パンチを用いて、毛根を一つひとつくり抜いて採取する方法です。メスを使わないため術後の痛みが少なく、縫合の必要もありません。
傷跡は小さな点状となり、髪を短く刈り上げても目立ちにくいという特長があります。患者さんの身体的負担が少ないことから、現在多くのクリニックで採用されている人気の術式です。
ただし、一つひとつ手作業で採取するため手術時間が長くなる傾向があり、医師の集中力と技術力が結果に直結します。
また、採取部分の髪を刈り上げる必要がある場合が多いため、術後の見た目をどうカバーするかの計画も重要です。
ロボット支援による採取精度の向上と限界
近年ではFUE法の一部をロボットが支援する技術も登場しています。画像解析システムを用いて良質な毛根を瞬時に見分け、ロボットアームが正確にパンチングを行うことで、人為的なミスや疲労による精度の低下を防ぎます。
特に大量の採取が必要な場合でも、一定のクオリティを保ちやすい点が評価されています。
しかし、頭皮の柔らかさや毛の生える向きは人によって千差万別であり、ロボットだけでは対応しきれない微妙な調整が必要な場面も多々あります。
また、側頭部などロボットアームが届きにくい部位の採取は苦手とするため、最終的には医師の手技とのハイブリッドで行われることが一般的です。
機械任せにするのではなく、それを操る医師の判断力が結果を左右します。
術式ごとの特徴比較
| 比較項目 | FUT法(ストリップ法) | FUE法(ダイレクト法) |
|---|---|---|
| 傷跡の状態 | 後頭部に細い線状の傷が残る | 小さな点状の傷が多数残る |
| 毛根切断率 | 非常に低い(顕微鏡で分離) | 医師の技術により変動する |
| 刈り上げ | 不要(周囲の髪で隠せる) | 採取範囲の刈り上げが必要 |
自身のライフスタイルに合わせた術式の選定基準
どの術式を選ぶべきかは、費用や痛みだけでなく、術後の生活スタイルを考慮して決定することが大切です。
例えば普段から髪を短く刈り上げている、あるいは将来的に短髪にしたいと考えている場合は線状の傷が残るFUT法よりも、点状の傷で済むFUE法が適しています。
逆に髪をある程度伸ばしており、一度の手術で最大限の密度を出したい、そして費用を比較的抑えたいと考えるならば、FUT法が良い選択肢となる場合があります。
仕事の休暇がどれくらい取れるか、術後の髪型をどうするかなど社会的な事情も加味しながら、医師と相談して納得のいく方法を選ぶことが成功への近道です。
期待できる発毛効果とデザインの自然さ
ヘアトランスプラントの真価は単に髪が増えることだけでなく、既存の毛髪の流れや密度に合わせて違和感のない生え際を再構築できる点です。
術後1年ほどで完成するヘアスタイルは、かつての状態と見分けがつかないほど自然なものとなります。
生え際のライン形成における美的センスの必要性
前頭部の生え際(ヘアライン)のデザインは、顔の印象を劇的に変える重要な要素です。単に額を狭くすれば良いというものではありません。
自然界の法則として、生え際は一直線ではなく、微細な凹凸を持っています。また、産毛のような細い毛から徐々に太い毛へと移行するグラデーションも存在します。
優れた医師は、こうした自然な法則を熟知しており、一人ひとりの顔の骨格、筋肉の動き、年齢に応じた適切なラインを描きます。
まるで絵画を描くような芸術的センスと、それを実現する緻密な移植技術が融合して初めて、誰が見ても違和感のない美しい生え際が完成します。
既存の髪と移植毛の密度調整による自然な仕上がり
移植した髪だけが濃く、周囲の既存毛が薄いといった状態になっては、不自然さが際立ってしまいます。
これを防ぐために既存の髪の間にも移植を行う「既存毛間移植」という高度なテクニックが用いられることがあります。
また、部位によって移植する密度を変えることも重要です。生え際の最前列は密度をあえて下げて柔らかさを出し、奥に行くに従って密度を高めてボリューム感を出すといった立体的な計算が必要です。
どの角度から見ても地肌の透け方が均一で自然に見えるよう、医師は一本一本の配置を計算し尽くして植え込んでいきます。
生涯にわたる生着とヘアサイクルの正常化
移植された毛髪は、一度抜け落ちた後、3ヶ月から4ヶ月程度の休止期を経て再び生え始めます。
この新しい髪は正常なヘアサイクル(成長期・退行期・休止期)を取り戻しており、数年から6年程度の長い成長期を維持します。
つまり、一度生着してしまえば、他の部位の髪と同じように成長し、抜け、また生えてくるという自然な営みを繰り返します。
AGAの影響を受けにくい性質は一生涯続くため、加齢によって全体的な毛量が減ることはあっても、移植した部分だけが極端に薄くなるという現象は起きにくくなります。
この永続性が、多くの人がヘアトランスプラントを選ぶ最大の動機となっています。
薄毛対策ごとの特徴比較
| 対策方法 | 自然さ・見た目 | メンテナンス頻度 | 長期的なコスト |
|---|---|---|---|
| 自毛植毛 | 非常に自然・地毛そのもの | 基本的に不要 | 初期費用のみで済む |
| 投薬治療 | 効果に個人差がある | 毎日の服用が必要 | 継続する限り発生 |
| かつら・増毛 | 製品により不自然な場合も | 定期的な交換・調整が必要 | ランニングコスト高 |
施術に伴うリスクと副作用
外科手術である以上、術後の一時的な脱毛(ショックロス)や、まぶたの腫れ、知覚鈍麻といった副作用が発生する可能性はゼロではありませんが、これらは時間の経過とともに自然治癒する一過性のものが大半です。
術後に発生するショックロス現象の正体
手術を受けてから数週間から数ヶ月の間に、移植した周辺の既存の髪が一時的に抜け落ちる現象を「ショックロス」と呼びます。
せっかく髪を増やしたのに逆に減ってしまったように見えるため、多くの患者さんが不安を抱くポイントです。
しかし、これは手術による局所麻酔の影響や、血流の一時的な変化による炎症反応が原因で起こるヘアサイクルの乱れであり、毛根が死滅したわけではありません。抜けた髪は休止期に入っただけであり、数ヶ月後には再び新しい髪が生えてきます。
ショックロスは必ず起こるわけではなく、個人差が大きい現象ですが、事前にこの知識を持っておくことで無用なパニックを防ぐことができます。
採取部と移植部に残る傷跡の目立ちにくさ
どのような外科手術であっても、皮膚を切開したり穴を開けたりすれば必ず組織の修復過程で傷跡(瘢痕)が形成されます。ヘアトランスプラントも例外ではありません。
しかし、頭皮は血流が良く治癒能力が高い部位であること、そして髪の毛で覆われていることから、他の部位の手術痕に比べて目立ちにくいという利点があります。
FUE法であれば1mm以下の点状の白い痕、FUT法であれば細い線状の痕が残りますが、髪を数センチ伸ばしていれば外見からはほとんど判別できません。
ただし、ケロイド体質の方などは傷が盛り上がるリスクがあるため、事前の診察で医師に体質を伝えておくことが大切です。
まぶたや額に現れる腫れと痛みの管理方法
手術中には痛みを抑えるために大量の麻酔液を頭皮に注入します。手術後、この麻酔液や炎症による水分が重力に従って下がってくることで、額やまぶたに腫れが出ることがあります。
特に生え際の手術を行った場合に起こりやすく、ひどい場合は目が開けにくくなることもあります。
しかし、この腫れは術後3日目あたりをピークに、1週間程度で自然に吸収されて消滅します。痛みに関しては、処方される鎮痛剤でコントロール可能な範囲であることがほとんどです。
術後数日間は頭を高くして寝る、患部を冷やすなどの対策を行うことで、腫れや痛みを軽減することができます。
主な一時的副作用
- 術後数日間の顔の腫れ(特にまぶた)
- 移植部位のかゆみやかさぶた形成
- 後頭部のつっぱり感や知覚鈍麻
必要な費用と移植株数の相場感
ヘアトランスプラントの費用は「基本治療費」と「移植するグラフト(株)数」によって算出されることが一般的です。
M字修正のような小規模なものであれば、数十万円、広範囲のカバーであれば200万円以上と、薄毛の進行度によって大きく変動します。
薄毛の進行度合いによる必要グラフト数の試算
費用を決定する最大の要因は「グラフト数」です。1グラフトとは毛穴の単位のことで、通常1つの毛穴から1本から4本の髪が生えています。
例えば、M字部分の軽い後退を埋める程度であれば400グラフトから600グラフト、生え際を全体的に下げたり密度を高めたりする場合は800グラフトから1000グラフト程度が必要になります。
前頭部から頭頂部にかけて広範囲に薄毛が進行している場合は2000グラフトから3000グラフト以上の採取が必要になることもあります。
自身の薄毛レベルがどの程度で、どれくらいの密度を目指すのかによって、必要なグラフト数は変わるため、正確な見積もりには医師による直接の診察が必要です。
基本料金とグラフト単価による総額の構成要素
多くのクリニックでは料金体系を「基本手術料 + (グラフト単価 × グラフト数)」としています。基本手術料は設備費やスタッフの人件費、消耗品費などが含まれ、一律20万円前後が相場です。
グラフト単価は術式によって異なり、手間の掛かるFUE法やロボット植毛の方がメスを使うFUT法よりも高めに設定されている傾向があります。
また、刈り上げないで行うノンシェーブンFUE法などは、さらに技術料が上乗せされ単価が高くなります。
安さだけで選ぶと実はグラフト単価が高かったり、必要な密度に満たないグラフト数で提案されたりすることもあるため、総額と内容のバランスを見ることが重要です。
複数回の施術が必要になるケースとコスト変動
一度の手術で採取・移植できるグラフト数には限界があります。後頭部のドナーの密度や頭皮の柔軟性にもよりますが、安全に行えるのは1回あたり3000グラフトから4000グラフト程度までです。
これを超える広範囲の薄毛の場合や、一度移植した後にさらに密度を高めたいと希望する場合は、2回目の手術を検討することになります。
2回に分けることで費用は倍近くになる可能性がありますが、一度に無理をして採取すると後頭部が薄くなりすぎるリスクがあるため、計画的に回数を分けることは安全性の観点からも理にかなっています。
将来的な進行も見据えて、予算計画を立てることが求められます。
グラフト数別・費用目安(FUE法の場合)
| グラフト数 | 想定される施術範囲 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 500G〜800G | M字部分の軽微な修正 | 60万円 〜 90万円 |
| 1000G〜1500G | 生え際全体の形成 | 100万円 〜 160万円 |
| 2000G以上 | 前頭部から頭頂部への広範囲 | 200万円以上 |
術後の経過と日常生活への復帰タイムライン
移植した毛根が完全に定着するまでの最初の1週間が最も重要な期間です。
その後一時的な脱落期を経て、約1年をかけて完成形へと向かう長期的なプロセスを理解し、焦らず経過を見守る姿勢が必要です。
手術直後から抜糸までの創部ケアの徹底
手術直後の頭皮は非常にデリケートな状態にあります。移植したばかりのグラフトはまだ皮膚にしっかりと固定されておらず、少しの摩擦や衝撃で抜け落ちてしまう危険性があります。
そのため術後翌日から1週間程度は、移植部位を絶対に擦らないように注意が必要です。多くのクリニックでは、術後の洗髪方法について詳細な指導が行われます。
通常、移植部は指で触れずに泡を乗せる程度にし、お湯を優しく掛けて洗い流す方法が推奨されます。この期間のケアの質が、最終的な生着率を大きく左右すると言っても過言ではありません。
かさぶた形成期における洗髪と保護の注意点
術後3日から1週間ほど経過すると、移植部位にかさぶたができ始めます。これは傷が治ろうとしている証拠ですが、無理に剥がそうとすると定着しかけた毛根ごと抜けてしまう恐れがあります。
かさぶたは自然に剥がれ落ちるのを待つのが鉄則です。術後2週間ほど経てば毛根は完全に組織に定着するため、通常のシャンプーのように指の腹を使って洗うことが可能になります。
この時期になると、かゆみを感じることもありますが、爪を立てて掻くことは避け、保湿ローションなどで頭皮環境を整えるケアが推奨されます。
運動や喫煙などの制限事項と解除のタイミング
血流が良くなりすぎると、傷口からの出血や腫れを助長する可能性があるため、激しい運動や飲酒、長時間の入浴は術後1週間程度控える必要があります。
軽いウォーキングやシャワー程度であれば翌日から可能な場合が多いですが、医師の指示に従うことが大切です。
また、喫煙は毛細血管を収縮させ、移植した毛根への酸素や栄養の供給を阻害するため、生着率を下げる大きな要因となります。
少なくとも術前後2週間、できれば術後は禁煙することが、手術の成功率を高めるためには強く推奨されます。
術後の生活制限スケジュール
| 期間 | 洗髪・シャワー | 運動・飲酒 |
|---|---|---|
| 手術当夜 | 不可(首から下のみ可) | 厳禁 |
| 術後1日〜3日 | ぬるま湯で流す程度 | 控える |
| 術後1週間以降 | 指の腹で優しく洗浄可 | 徐々に再開可能 |
失敗を防ぐためのクリニック選定と医師の技量
クリニック選びにおいて最も重視すべきは価格の安さよりも担当医の症例経験数や技術力、そしてリスクまで含めた説明を行う誠実さです。
複数の医療機関でカウンセリングを受けることで比較検討することが成功への近道です。
症例数の多さが示す技術力とデザインの引き出し
ヘアトランスプラントは、医師の技術が結果にダイレクトに反映される職人技のような側面を持っています。
豊富な症例数を持つ医師は様々な髪質、頭皮の状態、進行パターンに対応してきた経験値があります。これは単に毛を植える技術だけでなく、自然に見えるデザインの引き出しが多いことを意味します。
どのような生え際を作ればその人の顔立ちに似合うのか、将来の加齢変化をどう予測するかといった判断は、教科書的な知識だけでは養われません。
クリニックを選ぶ際はHP上の症例写真を見るだけでなく、実際に担当する医師がどれくらいの執刀経験を持っているかを確認することが大切です。
カウンセリングでのリスク説明と誠実な対応
良いクリニックは、メリットばかりを強調しません。手術には必ずリスクや限界が存在します。「絶対にフサフサになる」「副作用はない」といった甘い言葉だけを並べるクリニックは警戒すべきです。
逆に、ショックロスの可能性、既存毛への影響、思ったような密度にならない可能性など、ネガティブな情報も含めて包み隠さず説明してくれる医師こそ信頼に値します。
また、カウンセラー任せにせず、医師自身が時間をかけて診察し、患者さんの悩みや希望に耳を傾けてくれるかどうかも、その後の信頼関係を築く上で重要なチェックポイントとなります。
衛生管理体制とアフターフォローの充実度
外科手術である以上、感染症のリスクは常に考慮しなければなりません。手術室の清潔さ、使用する器具の滅菌管理など衛生管理が徹底されているかは基本中の基本です。
また、手術は「やりっぱなし」では成立しません。術後の検診制度が整っているか、万が一生着率が悪かった場合の保証制度はあるか、夜間や休日にトラブルが起きた際の連絡体制はどうなっているかなど、アフターフォローの充実度も確認が必要です。
長く付き合っていく自分の髪のことだからこそ、手術後のケアまで責任を持ってくれる医療機関を選ぶことが大切です。
クリニック確認リスト
- 医師が直接カウンセリングを行っているか
- 料金体系が明確で追加費用の説明があるか
- 術後の検診や保証制度が明記されているか
植毛の仕組みに戻る
ヘアトランスプラントに関するよくある質問
手術を検討する際、多くの方が抱く痛みや年齢制限、2回目の手術に関する疑問について専門的な見地から回答します。
- 手術中の痛みはどの程度ですか?
-
手術中は局所麻酔を使用するため、痛みを感じることはほとんどありません。
最初の麻酔注射の際にチクリとした痛みを感じることはありますが、その後は感覚が鈍くなるため、リラックスして手術を受けることができます。多くの患者さんが手術中に眠ってしまうほどです。
術後も処方される鎮痛剤でコントロールできる範囲の痛みで済むことが一般的です。
- 何歳まで手術を受けることができますか?
-
ヘアトランスプラントに厳密な年齢制限の上限はありません。健康状態が良好で、後頭部に十分なドナーが存在すれば、70代や80代の方でも手術を受けることが可能です。
ただし、若年層(特に20代前半)の場合は将来の薄毛進行範囲が予測しづらいため、まずは薬物療法を優先し、慎重に手術時期を見極めることが推奨される場合があります。
- 女性でも自毛植毛を受けることは可能ですか?
-
はい、女性でも可能です。女性の薄毛(びまん性脱毛症や牽引性脱毛症など)に対しても、自毛植毛は有効な手段となります。
ただし、女性の薄毛は男性とは原因や進行パターンが異なるため、ホルモンバランスや頭皮の状態を詳しく診断する必要があります。
特に生え際のデザインや全体的なボリュームアップなど、女性特有のニーズに合わせた繊細な技術が求められます。
- 一度手術を受けた後、密度を増やすために2回目の手術はできますか?
-
可能です。実際に、より高い密度を求めたり、将来的に薄毛範囲が拡大した場合のカバーを目的に2回目以降の手術を受ける方は少なくありません。
ただし、後頭部のドナーには限りがあるため、採取可能な毛量の上限を考慮する必要があります。
また、1回目の手術から最低でも8ヶ月から1年程度空け、頭皮の状態が回復し、前回の移植毛が生え揃った段階で検討するのが一般的です。
参考文献
INOUE, Shogo, et al. Longitudinal analysis of laparoendoscopic single-site adrenalectomy and conventional laparoscopic adrenalectomy regarding patient-reported satisfaction and cosmesis outcomes. Asian journal of surgery, 2019, 42.3: 514-519.
KANAYAMA, Koji, et al. Robotically assisted recipient site preparation in hair restoration surgery: surgical safety and clinical outcomes in 31 consecutive patients. Dermatologic Surgery, 2021, 47.10: 1365-1370.
NAKAMURA, Kouki, et al. Degree of Alignment Between Japanese Patients and Physicians on Alopecia Areata Disease Severity and Treatment Satisfaction: A Real-World Survey. Dermatology and Therapy, 2024, 14.1: 151-167.
MACEY, Jake, et al. Dermatologist and patient perceptions of treatment success in alopecia areata and evaluation of clinical outcome assessments in Japan. Dermatology and Therapy, 2021, 11.2: 433-447.
ROSATI, P., et al. A systematic review of outcomes and patient satisfaction following surgical and non-surgical treatments for hair loss. Aesthetic Plastic Surgery, 2019, 43.6: 1523-1535.
IGLESIA, Cheryl B.; YURTERI-KAPLAN, Ladin; ALINSOD, Red. Female genital cosmetic surgery: a review of techniques and outcomes. International urogynecology journal, 2013, 24.12: 1997-2009.