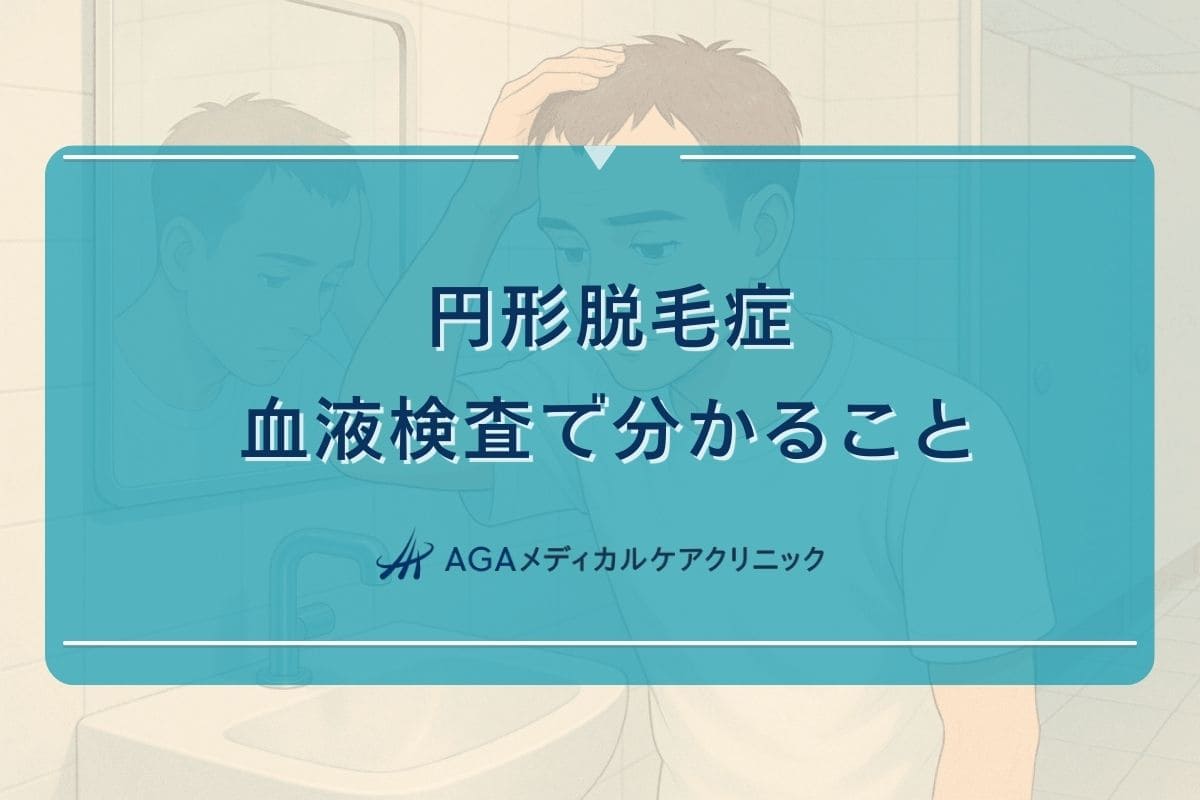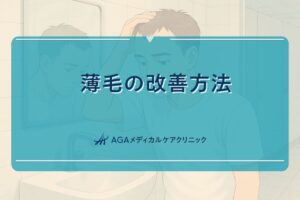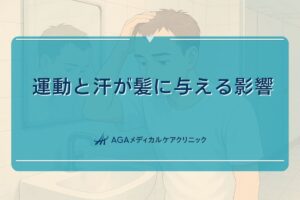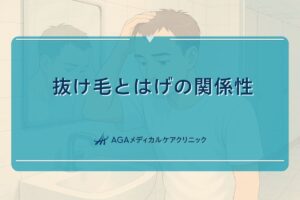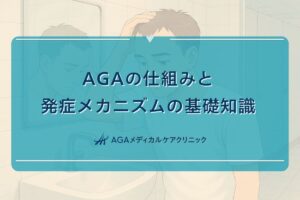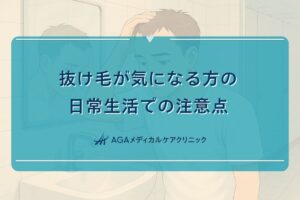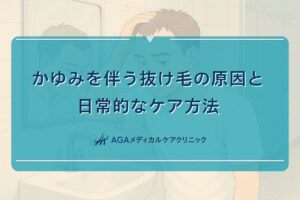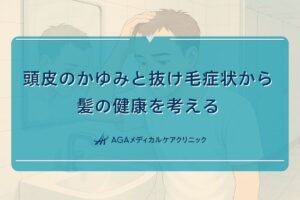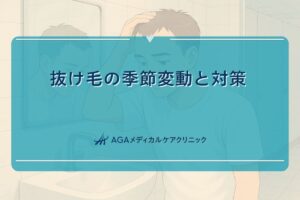ある日突然、円形に髪が抜けてしまう円形脱毛症。
その診断の過程で医師から血液検査を勧められ、「なぜ髪の毛のことで血液を調べるのだろう?」と不思議に思ったり、何か重い病気が隠れているのではないかと不安になったりする方は少なくありません。
この記事では円形脱毛症の診療で血液検査を行う目的と、それによって何が分かるのかを具体的な検査項目を挙げながら詳しく解説します。
検査が持つ意味を正しく理解することでご自身の状態を把握し、安心して治療に臨むための一助となれば幸いです。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
そもそも円形脱毛症とはどのような病気か
血液検査の意味を知る前に、まず円形脱毛症がどのような病気であるかを理解することが重要です。
一般的に考えられているストレス性の脱毛とは少し異なる側面があります。
自己免疫疾患としての一面
円形脱毛症は免疫機能の異常によって起こる「自己免疫疾患」の一つと考えられています。
本来は体外から侵入するウイルスや細菌などを攻撃するはずの免疫細胞(Tリンパ球)が、何らかの間違いで正常な毛根を異物と見なして攻撃してしまうのです。
この攻撃により、毛根がダメージを受けて髪の毛が抜けてしまいます。
ストレスとの関係性
精神的なストレスや肉体的な疲労が免疫機能のバランスを乱し、円形脱毛症の発症や悪化の引き金になることはあります。
しかし、ストレスはあくまで誘因の一つであり、直接的な原因は免疫機能の異常にあるという点を理解することが大切です。
AGA(男性型脱毛症)との明確な違い
薄毛の症状としてよく知られるAGAは男性ホルモンの影響でヘアサイクルが乱れることが原因です。一方、円形脱毛症は免疫系の攻撃によるもので、原因が全く異なります。
そのため、治療法も当然異なり、正確な診断が求められます。
円形脱毛症とAGAの比較
| 項目 | 円形脱毛症 | AGA(男性型脱毛症) |
|---|---|---|
| 主な原因 | 自己免疫機能の異常 | 男性ホルモンの影響 |
| 脱毛の仕方 | 境界明瞭な円形・楕円形に突然抜ける | 生え際や頭頂部から徐々に薄くなる |
| 性別・年齢 | 男女問わず、子供にも発症する | 主に成人男性に発症する |
なぜ円形脱毛症で血液検査を行うのか
円形脱毛症の診断は、主に視診やダーモスコピー(拡大鏡)による頭皮の観察で行います。
では、なぜ血液検査を追加で行うことがあるのでしょうか。それにはいくつかの重要な目的があります。
合併しやすい他の自己免疫疾患の確認
円形脱毛症の患者さんは、甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病)や膠原病(SLE)、尋常性白斑など、他の自己免疫疾患を合併していることがあります。
血液検査はこれらの病気が隠れていないかを確認するために行います。特に甲状腺ホルモンの異常は脱毛に影響を与えることがあるため、重要なチェック項目です。
治療方針を決定するための情報収集
これから行う治療が体に与える影響を考慮し、全身の健康状態を把握しておくことは非常に重要です。
例えばステロイド治療などを行う場合、肝臓や腎臓の機能、血糖値などを事前に確認しておく必要があります。安全に治療を進めるための大切な情報収集です。
脱毛の原因となりうる他の要因の除外
脱毛の原因は円形脱毛症だけではありません。鉄欠乏性貧血や亜鉛不足といった栄養障害も、抜け毛や髪質の低下を引き起こすことがあります。
血液検査によってこれらの要因がないかを確認し、もし見つかればその治療も並行して行うことで、より効果的な改善を目指します。
自己免疫の状態を調べる主要な検査項目
円形脱毛症と関連の深い、自己免疫疾患の合併を調べるための検査項目です。これらの数値が高い場合、他の病気が隠れている可能性を考慮します。
抗核抗体(ANA)
抗核抗体は自己の細胞の核成分に対して反応してしまう自己抗体の一種です。
膠原病などの自己免疫疾患で陽性を示すことが多いため、全身性の自己免疫疾患の合併をスクリーニングする目的で測定します。
甲状腺関連の自己抗体
甲状腺に対する自己抗体には、抗サイログロブリン抗体(TgAb)や抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)などがあります。
これらの抗体が陽性の場合、橋本病(慢性甲状腺炎)などの甲状腺疾患を合併している可能性が高まります。
主な自己免疫関連の検査項目
| 検査項目 | 何を示しているか | 関連する主な疾患 |
|---|---|---|
| 抗核抗体(ANA) | 全身性の自己免疫疾患の存在を示唆 | 全身性エリテマトーデス(SLE)など |
| 抗TPO抗体 | 甲状腺組織への攻撃を示唆 | 橋本病など |
| 抗サイログロブリン抗体 | 甲状腺組織への攻撃を示唆 | 橋本病など |
リウマトイド因子(RF)
主に関節リウマチの診断で用いられる自己抗体ですが、他の膠原病でも陽性になることがあります。
関節のこわばりなどの症状がある場合に、参考にすることがあります。
甲状腺機能やホルモンバランスの評価
甲状腺ホルモンは全身の新陳代謝をコントロールする重要なホルモンであり、髪の毛の健康にも深く関わっています。
機能の亢進(上がりすぎ)や低下(下がりすぎ)がないかを確認します。
甲状腺刺激ホルモン(TSH)
脳の下垂体から分泌され、甲状腺に「ホルモンを出せ」と指令を送るホルモンです。甲状腺自体の機能が低下すると、それを補おうとしてTSHの値が高くなります。
甲状腺機能のスクリーニングで最も重要な項目です。
甲状腺ホルモン(FT3, FT4)
甲状腺から直接分泌されるホルモンです。FT4(サイロキシン)とFT3(トリヨードサイロニン)の量を測定し、甲状腺機能が正常に働いているかを評価します。
TSHと合わせて総合的に判断します。
甲状腺機能の評価項目
| 検査項目 | 機能低下時(橋本病など) | 機能亢進時(バセドウ病など) |
|---|---|---|
| TSH | 高値 | 低値 |
| FT4 | 低値 | 高値 |
| FT3 | 低値 | 高値 |
性ホルモン関連の検査
男性ホルモンや女性ホルモンのバランスが崩れることも、脱毛の一因となることがあります。
特に女性で月経不順などの症状を伴う場合には、これらのホルモン値を測定することがあります。
髪の栄養状態を反映する検査項目
髪の毛は日々の食事から摂取する栄養素を元に作られています。特定の栄養素が不足すると、髪が細くなったり、抜けやすくなったりすることがあります。
鉄(Fe)・フェリチン
鉄は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担います。鉄が不足すると貧血になり、頭皮への酸素供給が滞ってしまいます。
フェリチンは「貯蔵鉄」とも呼ばれ、体内にどれだけ鉄がストックされているかを示す指標です。特に女性は月経により鉄を失いやすいため、重要な検査項目です。
- 鉄(Fe):血液中を流れている鉄
- フェリチン:体内に貯蔵されている鉄
亜鉛(Zn)
亜鉛は髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)の合成に欠かせないミネラルです。また、細胞分裂を活発にする働きもあり、毛母細胞が分裂して髪を成長させる上で重要な役割を果たします。
不足すると脱毛だけでなく、皮膚炎や味覚障害などを引き起こすこともあります。
髪の健康に関わる栄養素
| 栄養素 | 役割 | 不足による影響 |
|---|---|---|
| 鉄 | 酸素を全身に運ぶ | 頭皮の酸欠、貧血による抜け毛 |
| 亜鉛 | 髪のタンパク質の合成を助ける | 髪の成長不良、脱毛 |
| ビタミンD | 免疫機能の調整に関与 | 自己免疫疾患との関連が示唆されている |
ビタミンD、ビタミンB群
ビタミンDは免疫機能を正常に保つ働きがあることが分かっており、自己免疫疾患との関連が研究されています。
また、ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促し、皮脂のバランスを整えるなど、頭皮環境の維持に役立ちます。
検査結果の数値だけでは見えない、あなたの心と体の声
血液検査を受けると、どうしても基準値と自分の数値を比べることに一喜一憂してしまいがちです。しかし、私たちは検査結果という「数字」だけを診ているわけではありません。
その数字の背景にあるあなたの生活や心の状態にも、私たちは耳を傾けたいと考えています。
数字が正常でも「つらい」という実感
血液検査の結果がすべて基準値内であっても、あなたが感じている脱毛への恐怖や、他人からの視線に対する不安が消えるわけではありません。
「検査では異常なしと言われたけれど、現実に髪は抜けている」という事実は、時として患者さんをより一層孤独にさせます。
私たちは、その「つらい」という実感こそが、最も大切な情報だと考えています。
検査結果と自覚症状のギャップ
例えば、フェリチン(貯蔵鉄)の値が基準値の下限ギリギリだったとします。医学的には「貧血ではない」と判断されるかもしれませんが、髪にとっては十分な栄養が届いていないサインかもしれません。
このように、基準値という枠組みだけでは捉えきれないあなた自身の体からの小さな悲鳴を、私たちは見逃さないようにしたいのです。
検査数値と心身の状態
| 視点 | 検査結果が示すもの | 私たちが大切にしたいこと |
|---|---|---|
| 医学的データ | 客観的な体の状態、病気の有無 | データに基づいた正確な診断 |
| 患者さんの実感 | 脱毛への不安、ストレス、生活背景 | 数値に表れない心と体の声、悩みの共有 |
治療とは、数値を改善するだけの作業ではない
円形脱毛症の治療は薬を処方して終わりではありません。あなたが安心して日常生活を送れるように、精神的なサポートをすることも私たちの重要な役割です。
検査結果を一緒に見ながら、最近の生活でストレスに感じていること、食事や睡眠で困っていることなどを、ぜひお話しください。
治療とは医師と患者さんが手を取り合って、心と体の両面から健康を取り戻していく共同作業なのです。
全身の健康状態を把握するための基本項目
特定の疾患を調べる項目だけでなく、体の基本的な状態を確認する一般的な血液検査も行います。
これは治療の安全性を確保し、隠れた体調不良を見つけるために重要です。
血球算定(CBC)
赤血球、白血球、血小板の数や状態を調べる検査です。
貧血の有無(赤血球)、体内に炎症や感染がないか(白血球)、血が止まりやすいか(血小板)などを評価します。
- 赤血球:貧血の指標
- 白血球:炎症や感染の指標
- 血小板:止血能力の指標
肝機能・腎機能検査
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの項目で、肝臓に負担がかかっていないかを調べます。また、BUN(尿素窒素)やクレアチニン(Cre)で、腎臓の働きが正常であるかを確認します。
薬の代謝や排泄に関わる重要な臓器の状態を把握します。
血糖値・HbA1c
糖尿病の有無を調べる検査です。血糖値は採血時の血糖の値を、HbA1cは過去1〜2ヶ月の血糖の平均的な状態を示します。
糖尿病があると感染症にかかりやすくなったり、血行が悪くなったりするため、確認が必要です。
検査結果の解釈と診断への活用
血液検査の結果は単独の項目だけで判断するのではなく、複数の項目や症状、診察所見などを総合して、医師が専門的な視点から解釈します。
基準値(参考基準範囲)の考え方
検査結果の用紙には「基準値」が記載されていますが、これは健康な人の95%が含まれる範囲を示したものです。
そのため、わずかに基準値を外れたからといって、直ちに異常があるとは限りません。年齢や性別、その日の体調によっても数値は変動します。
複数の検査結果を組み合わせた総合的な判断
例えばTSHが高値で、かつ抗TPO抗体が陽性であれば、橋本病の合併を強く疑います。一方で、抗核抗体だけがわずかに陽性で、他に症状や異常所見がなければ、経過観察となることもあります。
このように、パズルのピースを組み合わせるように、全体像を捉えて診断します。
検査結果に基づいた治療方針の決定
検査によって甲状腺疾患や鉄欠乏性貧血などが見つかった場合は、まずその治療を優先、あるいは並行して行います。
円形脱毛症の治療だけでなく、その背景にある全身の状態を整えることが、結果的に脱毛症状の改善につながるのです。
円形脱毛症の血液検査に関するよくある質問
- 血液検査の前に食事を抜く必要はありますか?
-
血糖値や中性脂肪の項目を調べる可能性があるため、検査前の食事については、事前にクリニックの指示に従ってください。
一般的には検査前10時間程度の絶食をお願いすることが多いですが、水やお茶などの糖分を含まない水分は摂取しても構いません。
- 検査結果はどのくらいで分かりますか?
-
検査項目によって異なります。一般的な生化学検査や血球算定は数日で結果が出ますが、特殊な自己抗体の検査などは1週間から10日ほど時間がかかる場合があります。
結果については、次回の診察時に医師から直接説明します。
- 血液検査で異常がなければ、円形脱毛症は心配ないということですか?
-
いいえ、そうとは限りません。円形脱毛症の患者さんの多くは、血液検査で明らかな異常が見つからないことの方が一般的です。
検査はあくまで合併症の有無などを確認するためのものであり、検査結果に異常がないからといって円形脱毛症が軽度であるとか、治療が不要であるということにはなりません。
- 血液検査は毎回行う必要がありますか?
-
初診時に基本的な検査を行った後は毎回行う必要はありません。
ただし、治療薬の副作用をチェックするためや、症状に変化が見られた場合などに、特定の項目について再度検査を行うことがあります。
治療方針に応じて、医師が必要と判断した場合に行います。
以上
参考文献
ONO, Sachiko, et al. Serum granulysin as a possible key marker of the activity of alopecia areata. Journal of dermatological science, 2014, 73.1: 74-79.
UEKI, Rie, et al. Phototrichogram analysis of Japanese female subjects with chronic diffuse hair loss. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2003. p. 116-120.
SATO, Yohei, et al. Development of a scoring system to predict outcomes of iv corticosteroid pulse therapy in rapidly progressive alopecia areata adopting digital image analysis of hair recovery. The Journal of Dermatology, 2021, 48.3: 301-309.
ARANISHI, Toshihiko, et al. Prevalence of alopecia areata in Japan: Estimates from a nationally representative sample. The Journal of dermatology, 2023, 50.1: 26-36.
HAGINO, Teppei, et al. Dietary habits in Japanese patients with alopecia areata. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2021, 1579-1591.
ITO, Taisuke. Recent advances in the pathogenesis of autoimmune hair loss disease alopecia areata. Journal of Immunology Research, 2013, 2013.1: 348546.