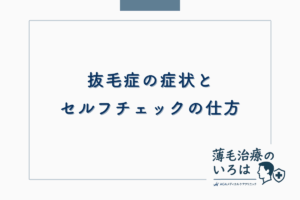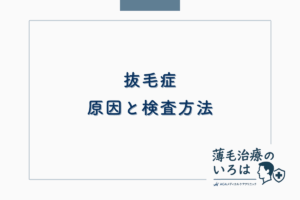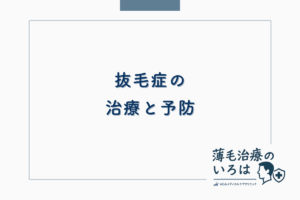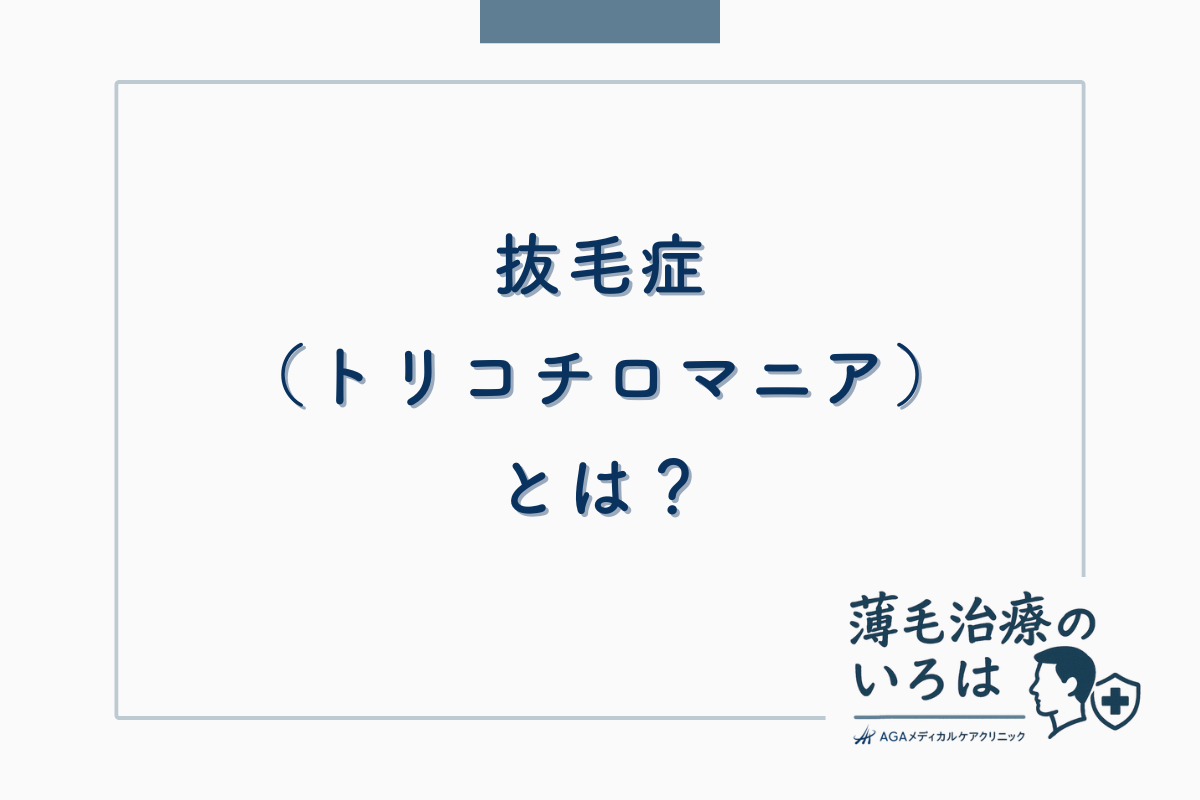「気づいたら髪を抜いていた」「やめたいのに、どうしても抜いてしまう」そんな悩みを抱えていませんか?
抜毛症(トリコチロマニア)は、自分の毛髪を繰り返し引き抜いてしまう精神疾患の一つです。この行為は無意識に行われることもあり、頭皮や眉毛、まつげなどに脱毛斑が生じ、薄毛の原因となることがあります。
この記事では、抜毛症の症状、原因、そして治療法について、薄毛治療の観点も踏まえながら、男性患者さんに向けて分かりやすく解説します。
一人で悩まず、正しい知識を得て、回復への一歩を踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
抜毛症(トリコチロマニア)とは – あなたの悩みには名前があります

抜毛症、医学的にはトリコチロマニアと呼ばれるこの状態は、単なる「癖」として片付けられるものではありません。自分の体毛、特に頭髪、眉毛、まつげなどを繰り返し引き抜いてしまう衝動制御の困難さを特徴とする精神疾患です。
この行為によって顕著な脱毛が生じ、ご本人の苦痛や社会生活への支障を引き起こします。
多くの場合、抜毛行為の前には緊張感や強い衝動があり、行為後には一時的な満足感や解放感が得られる一方で、後には罪悪感や羞恥心に苛まれることも少なくありません。
男性の場合、薄毛の悩みが抜毛症の症状と結びついていることに気づきにくいケースもあります。しかし、特定の部位だけが不自然に薄くなっていたり、短い切れ毛が多かったりする場合、抜毛症の可能性を考えることが重要です。
抜毛症の定義と基本的な理解
抜毛症は、国際的な診断基準であるDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)においても独立した疾患として記載されています。主な特徴は以下の通りです。
- 体毛を繰り返し引き抜くことによる脱毛。
- 抜毛行為をやめようと繰り返し試みるが、うまくいかない。
- 抜毛行為が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
この定義からも分かるように、抜毛症は本人の意思の弱さや性格の問題ではなく、治療的な介入が必要な状態です。特に、無意識のうちに抜いてしまうこともあり、自分でもコントロールが難しいと感じる方が多くいます。
衝動制御障害の一つとしての位置づけ
抜毛症は、衝動制御障害群に分類されます。これは、自分自身や他人にとって有害となりうる行為への衝動や欲求、誘惑に抵抗できないことを繰り返す一群の精神疾患を指します。
抜毛行為そのものが目的となる場合や、緊張や不安を和らげるための対処行動として行われる場合があります。この衝動をコントロールする難しさが、抜毛症の治療における重要なポイントの一つです。
単なる癖ではない医学的な状態
髪をいじる癖や、時折数本の毛を抜いてしまうことと、抜毛症は異なります。抜毛症では、抜毛行為が持続的かつ反復的であり、それによって明らかな脱毛が生じ、本人が苦痛を感じたり、日常生活に支障が出たりします。
例えば、抜毛による見た目の変化を気にして、帽子が手放せなくなったり、人と会うのを避けたりするようになることもあります。これは医学的な介入を要する状態であり、適切な治療によって改善が期待できます。
抜毛行為の背景にあるもの
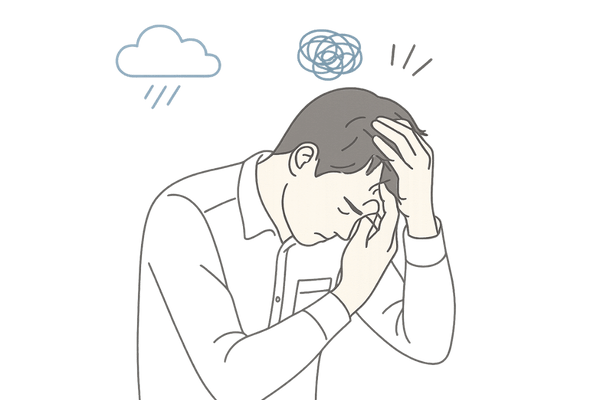
抜毛行為の背景には、複雑な心理的要因が絡み合っていることが多いです。一概に「これ」と特定できる原因があるわけではなく、個々人によってその背景は異なります。
なぜ特定の毛髪を抜くのか
抜毛の対象となる毛髪は、頭髪が最も多いですが、眉毛、まつげ、陰毛、体毛など多岐にわたります。特定の質感の毛(例えば、太い毛、縮れた毛)を選んで抜く人もいれば、特に区別なく抜く人もいます。
抜く毛髪の部位や種類に特定のこだわりが見られることもあり、これは抜毛行為が一種の儀式的な行動となっている可能性を示唆します。この行動パターンを理解することは、治療戦略を立てる上で役立ちます。
抜毛行為がもたらす一時的な安堵感と自己嫌悪
多くの場合、抜毛行為の前には強い緊張感や不安、あるいは退屈感などが存在し、毛を抜くことでこれらの不快な感情が一時的に和らぐ、あるいは一種の快感が得られると報告されています。
この「緊張の高まり→抜毛→解放感」というサイクルが、抜毛行為を強化し、習慣化させる一因と考えられます。
しかし、その直後には「またやってしまった」という自己嫌悪や後悔の念に襲われることが多く、この感情の揺り動きがさらなるストレスとなり、悪循環を生むこともあります。
抜毛症に関する誤解と事実

| よくある誤解 | 医学的な事実 | 理解のポイント |
|---|---|---|
| 意志が弱いからやめられない | 衝動制御に関わる精神疾患であり、意志の力だけでコントロールするのは困難 | 専門的な治療やサポートが必要 |
| 子供だけの問題である | 思春期に発症することが多いが、成人や子供にも見られる | 年齢に関わらず誰にでも起こりうる |
| 単なる悪い癖だ | 顕著な脱毛や苦痛、機能障害を伴う医学的な状態 | 放置せず、専門家への相談を検討する |
気づいていますか?これらの症状があなたの日常を奪っています
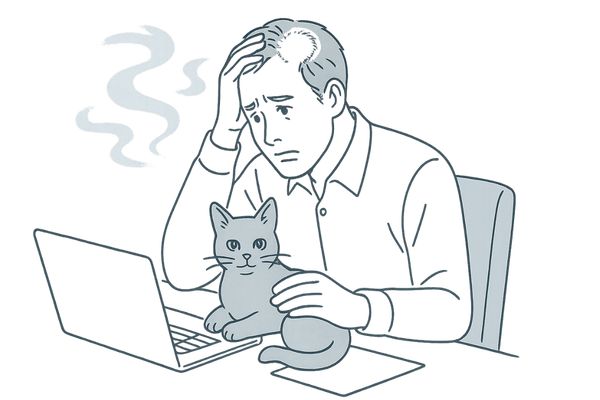
抜毛症の症状は、身体的なサインだけでなく、精神的な苦痛や日常生活への影響も伴います。ご自身の状態を客観的に把握することが、解決への第一歩です。
身体的な症状のサイン
最も分かりやすいのは、毛髪が失われることによる外見上の変化です。しかし、それ以外にも注意すべきサインがあります。
頭皮の脱毛斑や薄毛
頭頂部、側頭部など、特定の部位に不規則な形の脱毛斑が生じることが多いです。脱毛の程度は様々で、わずかに地肌が透けて見える程度から、広範囲にわたって毛髪が失われるケースまであります。
抜かれた毛の断面が不揃いであることや、短い新生毛が混在していることも特徴です。男性の場合、AGA(男性型脱毛症)との区別がつきにくいこともありますが、脱毛のパターンや進行の仕方が異なる場合があります。
眉毛やまつげの欠損
頭髪だけでなく、眉毛やまつげも抜毛の対象となりやすい部位です。眉毛が部分的に、あるいは全体的に薄くなったり、まつげがまばらになったりします。
これにより、顔の印象が大きく変わるため、ご本人の精神的な負担は非常に大きくなることがあります。アイブロウペンシルやつけまつげで隠そうとすることも多いですが、根本的な解決にはなりません。
抜いた毛髪を食べる行為(食毛症)の併発リスク
抜毛症の方の中には、抜いた毛髪を口にしたり、食べてしまったりする「食毛症(トリコファジア)」を併発するケースがあります。
これは稀ですが、大量に毛髪を飲み込むと、胃や腸の中で毛髪が塊(毛髪胃石・毛髪腸石)を形成し、腹痛、吐き気、嘔吐、便秘、さらには腸閉塞などの深刻な消化器系の問題を引き起こす可能性があります。
このような症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。
身体的・精神的症状の概要
| 症状のカテゴリ | 具体的な症状例 | セルフケアのヒント(初期対応) |
|---|---|---|
| 身体的症状 | 頭皮のまだらな脱毛、眉毛・まつげの減少、短い切れ毛、頭皮の炎症や痒み | 頭皮を清潔に保つ、刺激の少ないシャンプーを選ぶ、抜毛部位を隠す工夫(帽子など) |
| 精神的症状 | 抜毛衝動、行為後の罪悪感・羞恥心、不安感、抑うつ気分、孤立感 | 信頼できる人に話す、リラックスできる時間を作る、専門家への相談を検討する |
| 行動の変化 | 一人でいる時に抜きやすい、特定の道具を使う(ピンセット等)、抜いた毛を観察する | 抜毛しやすい環境を避ける、手持ち無沙汰にならない工夫をする |
精神的な症状と行動の変化
抜毛症は、目に見える脱毛だけでなく、心の中にも様々な影響を及ぼします。
抜毛行為への強い衝動と抑えられない感覚
「抜きたい」という強い衝動が突然、あるいは徐々に湧き上がり、それに抵抗することが非常に難しく感じられます。
この衝動は、特定の感情(ストレス、不安、退屈など)や状況(一人でいる時、テレビを見ている時など)と結びついていることが多いです。一度抜き始めると、やめられずに長時間続けてしまうこともあります。
行為後の罪悪感や羞恥心
抜毛行為の後には、一時的な解放感とは裏腹に、「またやってしまった」「自分はダメだ」といった強い罪悪感や羞恥心に襲われることが一般的です。
このネガティブな感情が、さらに自己評価を下げ、症状を悪化させる悪循環につながることもあります。
他人の目を気にするあまりの社会的孤立
脱毛斑や薄毛を他人に気づかれるのではないかという不安から、人の視線を過剰に意識するようになります。
その結果、帽子やウィッグで隠したり、美容院に行くのをためらったり、友人との付き合いや社会的な活動を避けるようになったりするなど、孤立感を深めてしまうことがあります。
これはQOL(生活の質)を著しく低下させる要因となります。
日常生活への影響
抜毛症は、学業、仕事、対人関係など、日常生活の様々な側面に影響を及ぼす可能性があります。
学業や仕事への集中困難
抜毛衝動に気を取られたり、抜毛行為に時間を費やしてしまったりすることで、勉強や仕事に集中できなくなることがあります。
また、外見へのコンプレックスから自信を失い、本来の能力を発揮できなくなることもあります。
対人関係の悩みと孤立感
友人や恋人、家族に対して、抜毛症であることを隠し続けることに精神的な負担を感じたり、理解されないのではないかという恐れから、親密な関係を築くことをためらったりすることがあります。
これにより、孤独感が深まり、精神的なサポートが得られにくくなるという悪循環に陥ることもあります。
今すぐできる5つのセルフチェック – あなたの状態を知る第一歩
「もしかして自分も抜毛症かもしれない」と感じたら、まずはセルフチェックをしてみましょう。これは確定診断ではありませんが、ご自身の状態を客観的に把握し、専門家への相談を考えるきっかけになります。
セルフチェックリストの活用
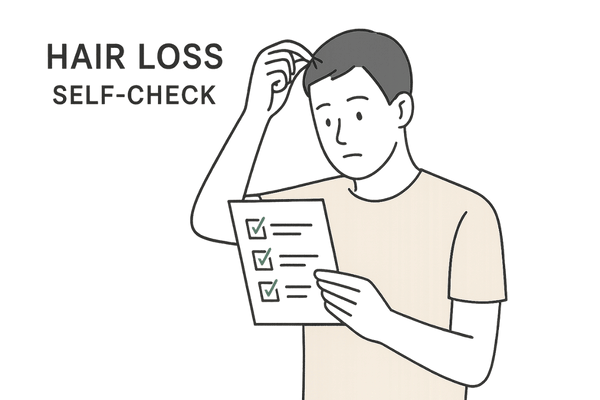
以下の項目に、過去数ヶ月間のご自身の状態を振り返って答えてみてください。「はい」が多く当てはまるほど、抜毛症の可能性や、何らかの対策・治療が必要な状態であると考えられます。
抜毛症セルフチェックリスト
| No. | チェック項目 | はい / いいえ |
|---|---|---|
| 1 | 特定の部位の毛(頭髪、眉毛、まつげなど)を繰り返し抜いてしまうことがありますか? | |
| 2 | 毛を抜く前に、強い衝動や緊張感を感じることがありますか? | |
| 3 | 毛を抜いた後に、満足感や解放感、あるいは快感を感じることがありますか? | |
| 4 | 毛を抜く行為をやめようとしたり、回数を減らそうとしたりしても、うまくいかないことが多いですか? | |
| 5 | 抜毛によって、目に見える脱毛(薄毛、脱毛斑など)がありますか? | |
| 6 | 抜毛行為やそれによる脱毛について、悩みや苦痛を感じていますか? | |
| 7 | 抜毛行為や脱毛が原因で、仕事、学業、対人関係、その他の社会生活に支障が出ていますか?(例:集中できない、人と会うのが億劫など) | |
| 8 | 無意識のうちに毛を抜いていることがありますか?(例:テレビを見ている時、読書中など) | |
| 9 | 抜いた毛を調べたり、並べたり、口に入れたりすることがありますか? | |
| 10 | ストレスや不安を感じると、特に毛を抜きやすくなりますか? |
チェック結果の解釈と次の行動
このチェックリストはあくまで目安です。いくつかの項目に「はい」が当てはまったからといって、すぐに抜毛症と断定されるわけではありません。
しかし、「はい」の数が多い場合、特に5つ以上当てはまる場合は、専門家(精神科医、心療内科医、あるいは抜毛症に詳しい皮膚科医)に相談することを強く推奨します。
どの程度の項目が当てはまると注意が必要か
一般的に、上記のチェックリストで5つ以上の項目に「はい」と答えた場合、抜毛症の可能性があり、専門的な評価を受けることが望ましいと考えられます。
特に、「繰り返し抜いてしまう」「やめようとしてもやめられない」「脱毛がある」「苦痛を感じている」「生活に支障が出ている」といった項目が重要です。
たとえ「はい」の数が少なくても、ご自身で悩んでいる、生活に影響が出ていると感じる場合は、専門家の助けを求める価値があります。
専門機関への相談を考えるタイミング
セルフチェックの結果に関わらず、以下のような場合は専門機関への相談を検討しましょう。
- 抜毛行為がやめられず、自分ではコントロールできないと感じる。
- 抜毛による脱毛が目立ち、外見に悩んでいる。
- 抜毛行為や脱毛について、強い罪悪感、羞恥心、不安、抑うつ気分などを感じている。
- 日常生活(仕事、学業、対人関係など)に支障が出ている。
- 抜いた毛を食べてしまう(食毛症の疑い)。
早期に相談することで、症状の悪化を防ぎ、より効果的な治療や対策を始めることができます。一人で抱え込まず、勇気を出して専門家の扉を叩いてみましょう。
なぜ髪を抜いてしまうのか – 脳の働きと心理的要因を解明
抜毛症の発症には、単一の原因があるわけではなく、脳の機能的な側面、心理的な要因、遺伝的素因、環境などが複雑に関与していると考えられています。
これらの要因を理解することは、ご自身の状態を受け入れ、適切な治療法を選択する上で役立ちます。
脳科学的観点からの原因
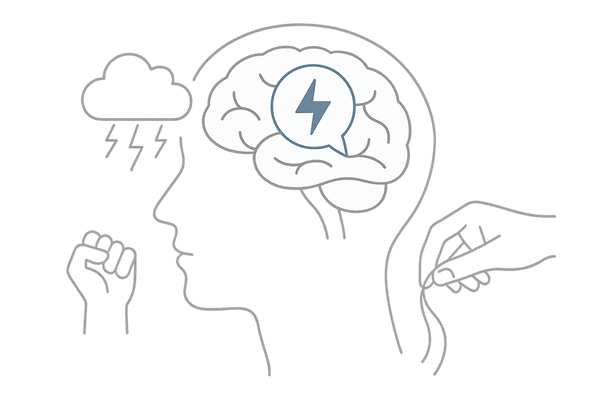
近年の研究により、抜毛症と関連する脳の働きについて少しずつ明らかになってきています。
衝動制御に関わる脳の部位
私たちの脳には、行動の計画、実行、抑制などを司る前頭前野という部位があります。
抜毛症の方では、この前頭前野の機能や、報酬系と呼ばれる快感や満足感に関わる神経回路の働きに何らかの偏りがある可能性が指摘されています。
これにより、抜毛したいという衝動を抑えることが難しくなったり、抜毛行為によって過剰な満足感を得やすくなったりするのではないかと考えられています。
報酬系と習慣形成の関連
抜毛行為が一時的な緊張緩和や快感をもたらす場合、脳の報酬系が活性化されます。
この「行為→快感」という結びつきが繰り返されることで、抜毛行為が強化され、一種の習慣として定着してしまうことがあります。無意識のうちに抜いてしまう行動も、この習慣形成と深く関連していると考えられます。
一度形成された習慣を変えるには、意識的な努力と適切な介入が必要です。
心理的要因
抜毛行為の引き金となったり、症状を維持・悪化させたりする心理的な要因は多岐にわたります。
ストレスや不安
多くの場合、ストレスや不安は抜毛行為の最も一般的な引き金の一つです。
仕事のプレッシャー、対人関係の悩み、試験前の緊張など、精神的な負荷が高まると、無意識に、あるいは意識的に毛を抜くことで、その不快な感情を紛らわそうとすることがあります。
この対処行動が繰り返されることで、ストレスを感じると自動的に抜毛してしまうというパターンが形成されることがあります。
特定の状況下で症状が悪化するケース
例えば、プレゼンテーションの前夜や、重要な会議中など、特定の緊張を強いられる状況で抜毛衝動が強まることがあります。
また、逆に何もすることがなく手持ち無沙汰な時や、リラックスしているはずの就寝前などに、無意識に抜毛行為をしてしまう人もいます。
ご自身がどのような状況や感情の時に抜毛しやすいかを把握することは、対策を立てる上で非常に重要です。
退屈や孤独感が引き金になることも
強い感情だけでなく、退屈感や孤独感、刺激の欠如といった状態も、抜毛行為の引き金となることがあります。何か手慰みに、あるいは自分自身に刺激を与えるために、無意識に毛を抜き始めてしまうのです。
特に一人でいる時間が長いと、この傾向が強まることがあります。
完璧主義や自己評価の低さとの関連
完璧主義的な傾向が強い人や、自己評価が低い人は、抜毛症になりやすいという指摘もあります。自分に対する厳しい要求や、達成できないことへの不満感がストレスとなり、抜毛行為につながることがあります。
また、抜毛行為そのものや、それによる脱毛が自己評価をさらに下げ、悪循環に陥ることもあります。
抜毛の引き金となりうる心理的要因
| 心理的要因 | 具体例 | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| ストレス | 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、経済的な問題 | ストレスマネジメント技法の習得、相談 |
| 不安 | 将来への不安、失敗への恐れ、人前での緊張 | リラクゼーション法の実践、認知行動療法 |
| 退屈・孤独感 | 手持ち無沙汰、一人でいる時間が多い、社会的なつながりの希薄さ | 趣味や活動への参加、人との交流機会を増やす |
| 抑うつ気分 | 気分の落ち込み、興味・関心の喪失、無気力 | 専門医への相談、適切な治療 |
| 完璧主義 | 自分に厳しすぎる、失敗を許せない | 認知の歪みの修正、現実的な目標設定 |
遺伝的要因と環境要因
抜毛症の発症には、個人の素因や育ってきた環境も影響すると考えられています。
家族歴が影響する可能性
抜毛症の患者さんの家族や親族にも、同様の症状や他の強迫関連障害が見られることがあるという報告があり、何らかの遺伝的な要因が関与している可能性が示唆されています。
ただし、特定の遺伝子が原因であると特定されているわけではなく、複数の遺伝子と環境要因が複雑に絡み合って発症に至ると考えられています。
幼少期のトラウマや環境ストレス
幼少期のトラウマ体験(虐待、ネグレクトなど)や、家庭内の不和、過度な期待といった持続的な環境ストレスが、抜毛症の発症リスクを高める可能性も指摘されています。
これらの経験が、感情調節の困難さやストレスへの脆弱性につながり、抜毛行為という形で現れることがあるのです。ただし、全ての抜毛症の方がこのような経験をしているわけではありません。
専門医による検査で分かること
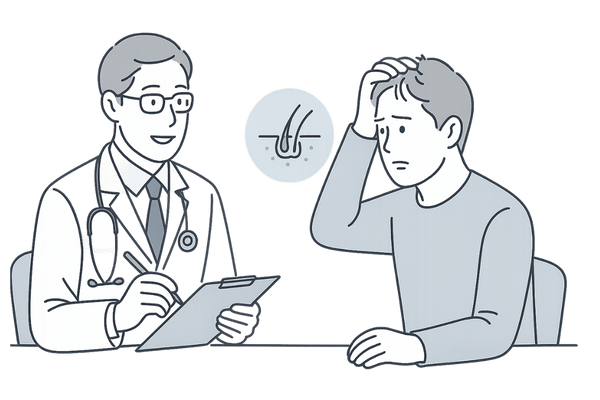
抜毛症の診断は、主に問診と視診によって行われます。他の脱毛症との鑑別や、併存する可能性のある精神疾患の評価も重要です。
正確な診断を受けることは、適切な治療法を選択し、回復への道を歩むための第一歩です。
診断基準と評価方法
医師は、患者さんの症状や悩み、生活状況などを詳しく聞き取り、国際的な診断基準に基づいて診断します。
DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)における診断基準
精神科医や心療内科医は、米国精神医学会が作成したDSM-5などの診断基準を用います。主な診断基準には以下のようなものがあります。
- 体毛(通常は頭髪、眉毛、まつげ)を繰り返し引き抜くことによる、明らかな脱毛。
- 抜毛行為を減らそう、またはやめようと繰り返し試みる。
- 抜毛行為が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害(例:対人関係の問題)を引き起こしている。
- 抜毛行為や脱毛は、他の医学的状態(例:皮膚疾患)によるものではない。
- 抜毛行為は、他の精神疾患(例:醜形恐怖症における外見上の欠陥と思い込んでいるものへの反応)ではうまく説明されない。
これらの基準を満たす場合に、抜毛症と診断されます。
問診の重要性と内容
問診では、いつ頃から抜毛行為が始まったか、どのような状況で抜きやすいか、抜く前にどんな気持ちになるか、抜いた後にどう感じるか、日常生活への影響はどうか、といったことを詳しく尋ねます。
また、抜毛行為の頻度、時間、抜く毛の部位や本数、抜いた毛の処理方法(捨てる、集める、食べるなど)についても確認します。
家族歴や既往歴、現在服用中の薬なども重要な情報です。正直に話すことが、正確な診断と適切な治療につながります。
他の脱毛症との鑑別
脱毛を引き起こす疾患は抜毛症以外にも様々あります。特に男性の場合、AGA(男性型脱毛症)との区別が重要になることがあります。
他の脱毛症との主な違い
| 脱毛症の種類 | 主な特徴 | 抜毛症との識別ポイント |
|---|---|---|
| AGA(男性型脱毛症) | 前頭部や頭頂部の毛が徐々に細く短くなり、薄毛が進行。遺伝や男性ホルモンが関与。 | 特徴的な脱毛パターン(M字型、O字型など)。抜毛衝動や行為そのものはない。毛根が残っていることが多い。 |
| 円形脱毛症 | 境界明瞭な円形・楕円形の脱毛斑が突然出現。自己免疫疾患の一種と考えられている。 | 脱毛斑の形状が典型的。抜毛の痕跡(途中で切れた毛、引き抜かれた毛根など)がない。痒みや軽い痛みがあることも。 |
| 脂漏性脱毛症 | 頭皮の過剰な皮脂分泌や炎症に伴う脱毛。フケや痒みを伴うことが多い。 | 頭皮の赤み、湿疹、脂っぽいフケなどが見られる。抜毛行為は直接の原因ではない。 |
| 機械的脱毛症 | 牽引や圧迫など物理的な力が長期間加わることで生じる脱毛(例:ポニーテール脱毛)。 | 原因となる物理的要因が特定できる。抜毛衝動とは異なる。 |
皮膚科医は、視診やダーモスコピー(拡大鏡を用いた頭皮や毛髪の観察)などを行い、毛髪の状態や毛根の様子を詳しく調べることで、これらの疾患と抜毛症を鑑別します。
必要に応じて、精神科医や心療内科医と連携して診断を進めます。
併存しやすい精神疾患
抜毛症は、他の精神疾患を併存していることが少なくありません。これらの併存疾患の有無を評価し、必要であれば同時に治療を行うことが、抜毛症の症状改善にもつながります。
うつ病や不安障害との関連
抜毛症の患者さんには、うつ病や全般性不安障害、社交不安障害などの不安障害が高い確率で併存すると報告されています。
抜毛行為が抑うつ気分や不安感を一時的に和らげるために行われている場合もあれば、抜毛症による悩みや生活への支障が、うつ病や不安障害を引き起こしたり悪化させたりすることもあります。
これらの感情面の症状に対しても、適切なアプローチが必要です。
強迫性障害(OCD)との類似点と相違点
抜毛症は、かつて強迫性障害(OCD)の関連疾患と考えられていましたが、DSM-5では独立した疾患として分類されています。
OCDは、強迫観念(繰り返し頭に浮かぶ不快な考え)と強迫行為(それを打ち消すための反復行動)を特徴としますが、抜毛症では必ずしも明確な強迫観念があるわけではありません。
しかし、抜毛行為が儀式的であったり、特定のルールに従って行われたりする点など、類似する部分もあります。併存することも稀ではありません。
回復への具体的な治療法 – 認知行動療法から薬物療法まで
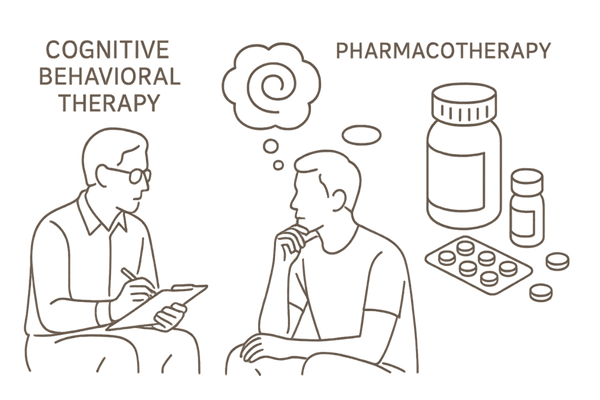
抜毛症の治療は、一人ひとりの症状や背景、希望に合わせて、様々なアプローチを組み合わせて行います。主な治療法としては、認知行動療法(CBT)や薬物療法があります。
治療の目標は、抜毛行為を減らし、最終的には止めること、そしてそれに伴う苦痛や生活への支障を軽減することです。
認知行動療法(CBT)の役割
認知行動療法は、抜毛症の治療において中心的な役割を果たす心理療法です。考え方(認知)や行動のパターンに働きかけることで、問題となる症状の改善を目指します。
特に「ハビットリバーサル訓練(HRT)」という技法が有効とされています。
ハビットリバーサル訓練(HRT)
ハビットリバーサル訓練(Habit Reversal Training)は、抜毛行為のような望ましくない習慣的な行動を、より適切な行動に置き換えることを目的とした行動療法の一種です。HRTは主に以下の要素から構成されます。
- 気づきの訓練(Awareness Training)自分がいつ、どのような状況で、どんな気持ちの時に毛を抜いているのかを詳細に記録し、抜毛行為とその前後の状況に対する「気づき」を高めます。無意識の行動を意識化することが第一歩です。
- 拮抗反応訓練(Competing Response Training)抜毛衝動を感じたり、抜きそうになったりした時に、抜毛行為と両立しない、別の行動(拮抗反応)をとる練習をします。例えば、手を握りしめる、ストレスボールを握る、編み物をするなど、手を使う別の行動に置き換えます。
- 動機づけと般化(Motivation and Generalization)治療への動機づけを高め、HRTで学んだスキルを日常生活の様々な場面で活用できるように般化を促します。家族や周囲の人のサポートも重要になります。
アクセプタンス&コミットメントセラピー(ACT)
ACTは、抜毛衝動やそれに伴う不快な感情を無理に消そうとするのではなく、それらをあるがままに受け入れ(アクセプタンス)、その上で自分にとって価値のある目標に向かって行動していくこと(コミットメント)を重視する比較的新しい認知行動療法の一派です。
抜毛衝動があっても、それに振り回されず、自分の人生を豊かにするための行動を選択できるようになることを目指します。
薬物療法の選択肢
薬物療法は、主に抜毛衝動の軽減や、併存するうつ病・不安障害などの症状改善を目的として行われます。認知行動療法と併用されることが多いです。
主な薬物療法の種類と特徴
| 薬剤の種類 | 主な作用・期待される効果 | 注意点・副作用の例 |
|---|---|---|
| SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) | 脳内のセロトニン濃度を調整し、不安や抑うつ気分、衝動性を和らげる。フルボキサミン、パロキセチンなど。 | 効果発現までに数週間かかる。吐き気、眠気、性機能障害など。医師の指示通りに服用。 |
| クロミプラミン(三環系抗うつ薬) | セロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害。強迫症状への効果が期待される。 | 口渇、便秘、眠気、めまいなど。SSRIより副作用が多い傾向。 |
| N-アセチルシステイン(NAC) | アミノ酸の一種。グルタミン酸系の神経伝達を調整し、衝動性を抑える可能性が研究されている。サプリメントとして用いられることも。 | 比較的安全性が高いとされるが、効果には個人差が大きい。胃腸症状など。 |
| 非定型抗精神病薬(少量) | ドパミンなどの神経伝達物質に作用。他の治療で効果不十分な場合に検討されることがある。リスペリドン、オランザピンなど。 | 眠気、体重増加、代謝系の副作用など。少量からの開始が原則。 |
薬物療法は、医師が患者さんの状態や症状、副作用のリスクなどを総合的に判断して処方します。自己判断で中断したり、量を調整したりせず、必ず医師の指示に従ってください。
その他のアプローチ
上記の治療法に加えて、以下のようなアプローチが補助的に用いられることもあります。
支持的精神療法
患者さんの悩みや苦痛に耳を傾け、共感的に支えることで、精神的な安定を図り、治療へのモチベーションを維持する手助けをします。
信頼できる治療者との対話を通じて、自己理解を深め、問題解決能力を高めることを目指します。
生活習慣の改善指導
ストレス管理、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動など、健康的な生活習慣は、心身の安定に繋がり、抜毛衝動をコントロールしやすくする上で重要です。
個々の生活スタイルに合わせた具体的なアドバイスを行います。
再発を防ぐ予防策 – 日常生活で実践できる7つの習慣

抜毛症の治療によって症状が改善した後も、再発を防ぐためには日常生活での工夫が大切です。ここでは、再発予防に役立つ7つの習慣を紹介します。
これらを意識して取り入れることで、より安定した状態を維持しやすくなります。
ストレス管理の重要性
ストレスは抜毛行為の大きな引き金となるため、日頃から上手に付き合っていく方法を身につけることが重要です。
リラクゼーション技法の習得
心身の緊張を和らげるリラクゼーション技法は、ストレス対処に有効です。以下のようなものが挙げられます。
- 深呼吸法(腹式呼吸)
- 漸進的筋弛緩法
- 瞑想やマインドフルネス
これらの技法を日常的に練習し、ストレスを感じた時にすぐ実践できるようにしておくと良いでしょう。
趣味や運動を通じたストレス発散
自分が楽しめる趣味や、心地よいと感じる運動は、効果的なストレス発散法となります。没頭できる時間を持つことで、抜毛衝動から意識をそらす効果も期待できます。
ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳、音楽鑑賞、読書、ガーデニングなど、自分に合ったものを見つけましょう。
トリガー(引き金)への対策
自分がどのような時に抜毛行為をしてしまいやすいか(トリガー)を把握し、それらに対処する方法を準備しておくことが予防につながります。
抜毛行為につながりやすい状況や感情の特定
日記をつけたり、意識的に自分の行動や感情を観察したりすることで、抜毛のトリガーが見えてきます。
「一人でテレビを見ている時」「仕事で強いプレッシャーを感じた後」「退屈な時」など、具体的な状況や感情をリストアップしてみましょう。
トリガーとなりやすい状況と対策の例
| トリガーとなる状況・感情 | 具体的な対策例 | ポイント |
|---|---|---|
| 一人でいる時、手持ち無沙汰 | 手袋をする、指サックをつける、手を使う趣味(編み物、模型作りなど)に取り組む | 物理的に抜きにくくする、手を別の活動で忙しくする |
| ストレスや不安を感じた時 | リラクゼーション法を実践する、信頼できる人に話を聞いてもらう、気分転換になる活動をする | 感情を適切に処理するスキルを身につける |
| 鏡を見る時、特定の毛が気になる時 | 鏡を見る時間を減らす、拡大鏡を使わない、気になる毛は抜かずにハサミで短く切る | 抜毛衝動を刺激する機会を減らす |
| 就寝前、リラックスしている時 | 寝る前に軽いストレッチをする、リラックスできる音楽を聴く、寝室に抜毛の道具を置かない | 入眠儀式として別のリラックス行動を取り入れる |
健康的な生活習慣の確立
心身の健康は、衝動コントロール能力にも影響します。規則正しい生活を送ることは、抜毛症の再発予防の基本です。
十分な睡眠とバランスの取れた食事
睡眠不足や栄養の偏りは、精神的な不安定さやストレス耐性の低下につながります。毎日同じ時間に寝起きし、質の高い睡眠を確保するよう心がけましょう。
また、ビタミンやミネラルを豊富に含むバランスの取れた食事は、頭皮や毛髪の健康にも良い影響を与えます。
頭皮環境を整えるケア
抜毛行為によってダメージを受けた頭皮をいたわることも大切です。刺激の少ないシャンプーを選び、優しく洗髪しましょう。頭皮マッサージなども、血行を促進し、リラックス効果が期待できます。
ただし、マッサージが抜毛のトリガーにならないよう注意が必要です。薄毛治療専門クリニックでは、頭皮環境を改善するためのアドバイスやケアも受けられます。
周囲の理解とサポート
一人で抱え込まず、信頼できる人に自分の状況を話し、理解と協力を得ることも再発予防に繋がります。
家族や友人へのカミングアウトと協力依頼
抜毛症について理解してもらい、サポートをお願いすることは勇気がいるかもしれませんが、孤立感を和らげ、治療へのモチベーションを維持する上で大きな助けとなります。
具体的にどのようなサポートをしてほしいか(例:抜いているのを見たら優しく声をかけてほしい、一緒に気分転換に出かけてほしいなど)を伝えると良いでしょう。
一人で悩まないで – サポートグループと相談窓口の活用法

抜毛症の悩みは、一人で抱え込んでいると深刻化しやすいものです。同じ悩みを持つ仲間と繋がったり、専門的な支援を受けたりすることで、心の負担を軽減し、回復への道を歩みやすくなります。
サポートグループの利点
サポートグループは、抜毛症の当事者やその家族が集まり、体験や情報を共有し、互いに支え合う場です。参加することで以下のような利点があります。
- 同じ悩みを持つ仲間と出会い、共感を得られることで孤立感が和らぐ。
- 他の人の体験談や対処法を聞くことで、新たな気づきやヒントが得られる。
- 自分の気持ちを安心して話せる場があることで、精神的な安定につながる。
- 病気に対する正しい知識や最新情報を得られることがある。
オンラインで参加できるグループもありますので、お住まいの地域に関わらず情報を探してみると良いでしょう。
専門機関や相談窓口の情報
抜毛症の治療や相談に対応している専門機関はいくつかあります。ご自身の状況や希望に合わせて、適切な窓口を選びましょう。
主な相談窓口と機関
| 機関の種類 | 主な役割・相談内容 | 見つけ方の例 |
|---|---|---|
| 精神科・心療内科 | 抜毛症の診断、認知行動療法、薬物療法、カウンセリングなど専門的な治療 | かかりつけ医からの紹介、インターネット検索(「地域名 抜毛症 精神科」など) |
| 皮膚科(抜毛症に詳しい医師) | 脱毛の状態の診察、他の脱毛症との鑑別、頭皮ケアのアドバイス | 日本皮膚科学会HP、口コミサイト、クリニックHPで専門分野を確認 |
| 薄毛治療専門クリニック | 抜毛による薄毛の改善、頭皮環境のケア、発毛・育毛治療の相談(抜毛行為がコントロールされた後) | インターネット検索(「地域名 男性 薄毛治療 抜毛症」など) |
| 公的な相談窓口(保健所・精神保健福祉センター) | 精神保健に関する相談、医療機関や支援制度の情報提供 | お住まいの自治体のホームページ、電話帳 |
| NPO法人・患者会 | 当事者や家族への情報提供、サポートグループの運営、啓発活動 | インターネット検索(「抜毛症 NPO」「トリコチロマニア 患者会」など) |
これらの機関は、それぞれ専門性や提供するサービスが異なります。まずは情報を集め、ご自身に合った相談先を見つけることが大切です。
薄毛治療クリニックでも抜毛症に関するご相談を受け付けている場合がありますので、お問い合わせください。
よくある質問
抜毛症の具体的な症状や、ご自身でできるセルフチェックの方法について、さらに詳しい情報をまとめています。あなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。
ぜひ以下の記事もご覧ください。
Reference
TAY, Yong-Kwang; LEVY, Moise L.; METRY, Denise W. Trichotillomania in childhood: case series and review. Pediatrics, 2004, 113.5: e494-e498.
CHANDRAN, Nisha Suyien, et al. Trichotillomania in children. Skin appendage disorders, 2015, 1.1: 18-24.
MELO, Daniel Fernandes, et al. Trichotillomania: what do we know so far?. Skin appendage disorders, 2022, 8.1: 1-7.
WALSH, Kelda H.; MCDOUGLE, Christopher J. Trichotillomania: Presentation, etiology, diagnosis and therapy. American journal of clinical dermatology, 2001, 2: 327-333.
DUKE, Danny C., et al. Trichotillomania: a current review. Clinical psychology review, 2010, 30.2: 181-193.
MANNINO, FORTUNE V.; DELGADO, RAFAEL A. Trichotillomania in children: a review. American Journal of Psychiatry, 1969, 126.4: 505-511.
BRUCE, Travis O.; BARWICK, Lori W.; WRIGHT, Harry H. Diagnosis and management of trichotillomania in children and adolescents. Pediatric Drugs, 2005, 7: 365-376.
ENOS, Stephanie; PLANTE, Thomas. Trichotillomania: An overview and guide to understanding. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 2001, 39.5: 10-18.
MCGUIRE, Joseph F., et al. Evidence-based assessment of compulsive skin picking, chronic tic disorders and trichotillomania in children. Child Psychiatry & Human Development, 2012, 43: 855-883.
抜毛症(トリコチロマニア)の関連記事