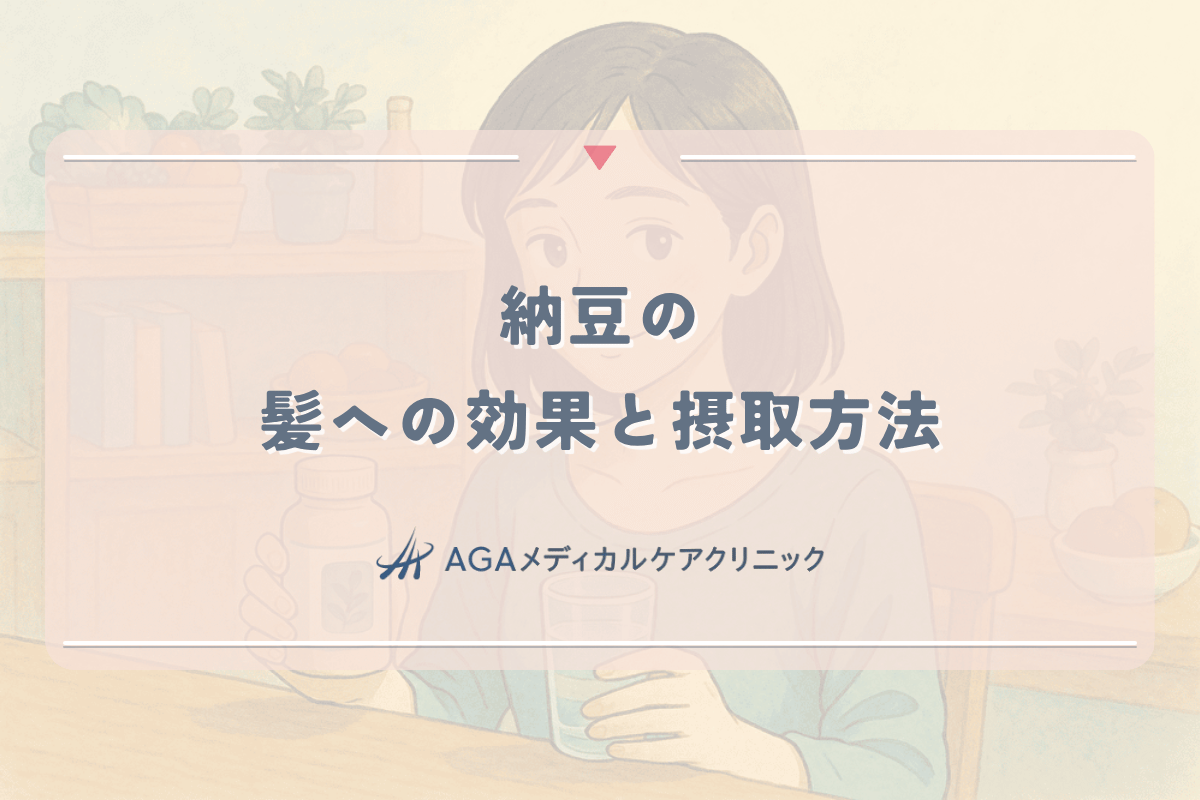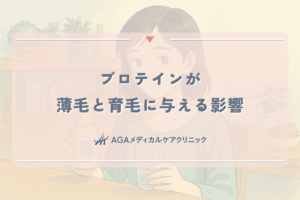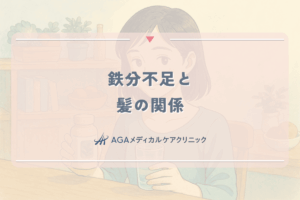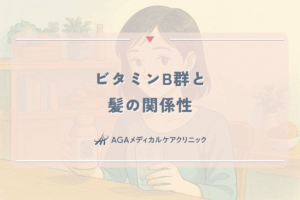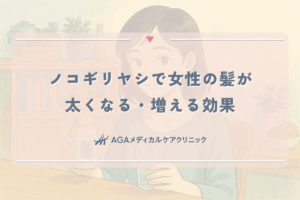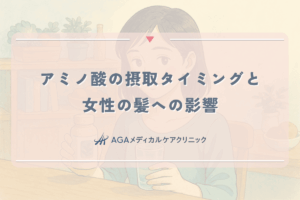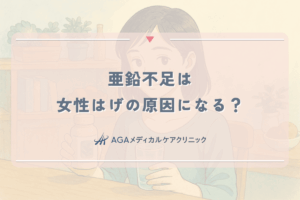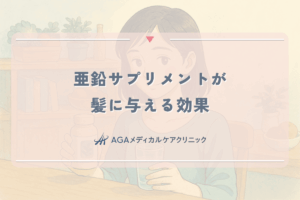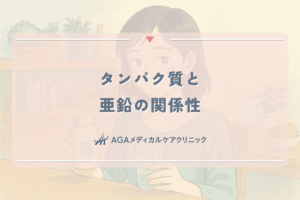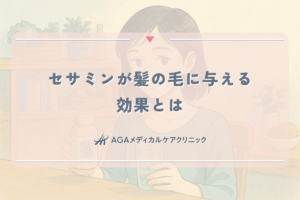日本の伝統的な食品である納豆が、実は女性の薄毛や髪の悩みに嬉しい効果を与えるのをご存知でしょうか。
しかし、具体的にどのような栄養素がどう作用するのか、また、どのように食べればその効果を最大限に引き出せるのか、詳しい情報はあまり知られていません。
この記事では、納豆が持つ髪への素晴らしい力を医学的な観点から解き明かし、日々の食生活で実践できる効果的な摂取方法を詳しく解説します。
内側から健やかな髪を育むための知識を深め、自信の持てる美しい髪を目指しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ女性の髪に納豆が良いと言われるのか?
納豆が髪に良いとされる背景には、髪の成長と健康維持に必要な要素が豊富に含まれているからです。
単に栄養価が高いだけでなく、その栄養素が女性の体や髪の悩みに特有の要因へ効果的に働きかける点に注目が集まります。
髪の主成分「ケラチン」と納豆の関係
私たちの髪の毛は、その約90%が「ケラチン」というたんぱく質で構成されています。
つまり、良質なたんぱく質の摂取は、美しい髪を作るための基本中の基本です。
納豆は植物性食品でありながら、肉や魚に匹敵するほどの豊富なたんぱく質を含んでいます。
このたんぱく質が体内でアミノ酸に分解され、ケラチンの再合成に使われて、強くしなやかな髪の土台を築きます。
頭皮の血行促進と栄養供給
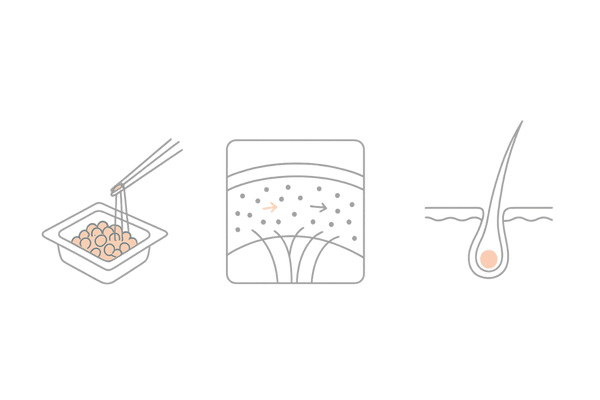
健康な髪を育てるには、髪の毛を作る毛母細胞へ十分な栄養を届けることが重要です。
納豆特有の酵素である「ナットウキナーゼ」は、血液をスムーズにする働きを持ちます。
この働きにより、頭皮の毛細血管の血流が改善し、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根までしっかりと運ばれるようになります。
栄養が隅々まで行き渡ると毛母細胞の活動が活発になり、健康な髪が生えやすい頭皮環境が整います。
栄養素を運ぶ血流のイメージ
| 血流の状態 | 頭皮への影響 | 髪の状態 |
|---|---|---|
| スムーズ | 栄養や酸素が十分に行き渡る | ハリ・コシのある健康な髪が育つ |
| 滞りがち | 栄養不足、老廃物が溜まる | 細毛、抜け毛、白髪の原因に |
女性ホルモンと髪のサイクルの安定化
女性の髪の健康は、女性ホルモン「エストロゲン」と深く関わっています。エストロゲンは髪の成長期を維持し、ハリやツヤを与える働きがあります。
納豆に含まれる「大豆イソフラボン」は、このエストロゲンと似た構造と働きを持つことで知られています。
加齢やストレスで女性ホルモンのバランスが乱れるとヘアサイクルが短くなり薄毛の原因となりますが、大豆イソフラボンを摂取するとホルモンバランスを補い、健やかなヘアサイクルをサポートする効果が期待できます。
納豆に含まれる髪に嬉しい5大栄養素とその働き

納豆には、たんぱく質やイソフラボン以外にも、髪の健康を多角的にサポートする栄養素が凝縮されています。
ここでは、特に重要な5つの栄養素とその働きについてみていきましょう。
たんぱく質|髪の土台を作る基本の栄養素
前述の通り、たんぱく質は髪の主成分です。納豆に含まれる大豆たんぱくは、必須アミノ酸をバランス良く含んだ良質なものです。
毎日の食事での十分なたんぱく質の確保が、髪の材料不足を防ぎ、細毛や切れ毛を予防する第一歩となります。
ビタミンB群|代謝を助け頭皮環境を整える
ビタミンB群は、エネルギー代謝を円滑にし、皮脂の分泌をコントロールする働きがあります。
特にビタミンB2は皮脂の過剰な分泌を抑え、頭皮のべたつきやフケを防ぎます。また、ビタミンB6はたんぱく質の代謝を助け、ケラチンの合成をサポートします。
これにより頭皮環境を健やかに保ち、健康な髪が育つ土壌を守ります。
髪の健康に関わる主要なビタミンB群
| ビタミンの種類 | 主な働き | 不足した場合の影響 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂分泌の調整、細胞の再生 | 頭皮の炎症、フケ、抜け毛 |
| ビタミンB6 | たんぱく質の代謝、ケラチン合成補助 | 健康な髪の育成阻害 |
| ビオチン | 皮膚や髪の健康維持 | 脱毛、白髪 |
亜鉛|ケラチンの合成をサポート
亜鉛は、たんぱく質を髪の毛(ケラチン)へ再合成する際に必要不可欠なミネラルです。
いくらたんぱく質を摂取しても、亜鉛が不足していると効率的に髪を作れません。
亜鉛は体内で作れず、汗などでも失われやすいため、意識して食事から摂取することが大切です。
納豆にはこの亜鉛も含まれており、髪の生成を縁の下で支えています。
ポリアミン|細胞の生まれ変わりを促進
ポリアミンは細胞分裂や増殖に欠かせない成分で、新陳代謝を活発にする働きがあります。
納豆菌が大豆を発酵させる過程で生成され、他の大豆製品よりも豊富に含まれています。
毛母細胞の活動を活発にし、新しい髪の毛が生まれるのを助けて、ヘアサイクルの成長期をサポートする効果が期待されます。
大豆イソフラボンが女性の薄毛に与える影響
女性の薄毛は、男性とは異なる要因が複雑に絡み合っています。その中でも女性ホルモンの変動は非常に大きな影響を与えます。
大豆イソフラボンがなぜ女性の薄毛対策として注目されるのか、その理由をさらに詳しく見ていきましょう。
女性ホルモン「エストロゲン」との類似性
大豆イソフラボンは、化学構造が女性ホルモンのエストロゲンと非常によく似ています。
そのため、体内でエストロゲンを受け入れる受容体と結合し、あたかもエストロゲンのように振る舞います。
この「エストロゲン様作用」により、加齢などが原因で減少したエストロゲンの働きを補い、ホルモンバランスの乱れを穏やかに整える手助けをします。
年代別エストロゲン分泌量の変化と薄毛リスク
| 年代 | エストロゲン分泌の状態 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 20代〜30代前半 | ピークに達し、安定している | 最も髪が健康的で美しい時期 |
| 30代後半〜40代 | 徐々に減少し始める(更年期プレ期) | 髪のうねり、パサつき、細毛が出始める |
| 50代以降 | 急激に減少し、閉経を迎える | 分け目が目立つ、全体のボリュームダウン |
ヘアサイクルを正常に保つ働き
髪には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルがあります。
エストロゲンには、髪が太く長く成長する「成長期」を維持する重要な役割があります。
エストロゲンが減少すると成長期が短くなり、髪が十分に育たないまま抜け落ちてしまうため、薄毛が進行します。
大豆イソフラボンがエストロゲンの働きを補うと、成長期を長く保ち、一本一本の髪を健康に育てて抜け毛を減らす効果が期待できます。
過剰な男性ホルモンの影響を抑制
女性の体内にも男性ホルモンは存在し、ホルモンバランスが崩れて男性ホルモンが優位になると、薄毛を引き起こす場合があります。
大豆イソフラボンには、男性ホルモンの影響を強める酵素「5αリダクターゼ」の働きを阻害する作用があることも報告されています。
この作用により、女性の薄毛(FAGA)の要因の一つを抑制する可能性があります。
納豆キナーゼだけじゃない!知られざる納豆の健康パワー
納豆といえば「ナットウキナーゼ」が有名ですが、それ以外にも髪と全身の健康に貢献する成分が含まれています。
これらの相乗効果によって、納豆は強力なヘアケア食品となり得るのです。
血液サラサラ効果で頭皮へ栄養を届ける
ナットウキナーゼの最も知られた効果は、血栓(血の塊)を溶かす強力な線溶酵素であることです。
血栓を予防し、血液の流れを良くするため全身の血行が改善します。もちろん、頭皮にある無数の毛細血管も例外ではありません。
頭皮の隅々まで栄養が届きやすい環境を作ることは、美髪育成の基盤となります。
ナットウキナーゼの主な働き
| 働き | 期待される効果 |
|---|---|
| 血栓溶解作用 | 血流をスムーズにする |
| 血圧降下作用 | 血管への負担を軽減する |
| 血流改善作用 | 冷えや肩こりの改善、頭皮への栄養供給促進 |
ビタミンK2が骨の健康と頭皮の弾力を維持
納豆には、ビタミンK2が他の食品に比べて群を抜いて多く含まれています。
ビタミンK2はカルシウムが骨に沈着するのを助け、丈夫な骨を作るのに役立ちます。また、血管の石灰化を防ぎ、しなやかさを保つ働きもあります。
健康な頭皮は適度な弾力を持っていますが、この弾力維持にも全身の血行や健康状態が関わっています。
納豆菌が作り出す多様な酵素の力
納豆菌は大豆を発酵させる過程で、ナットウキナーゼ以外にもプロテアーゼ(たんぱく質分解酵素)やアミラーゼ(デンプン分解酵素)など、多種多様な酵素を生成します。
これらの酵素は消化吸収を助け、腸内環境を整えるのに役立ちます。
腸内環境が整うと栄養素の吸収効率が高まるだけでなく、有害物質の発生が抑えられ、結果として肌や髪の健康にも良い影響を与えます。
効果を最大化する納豆の食べ方とタイミング
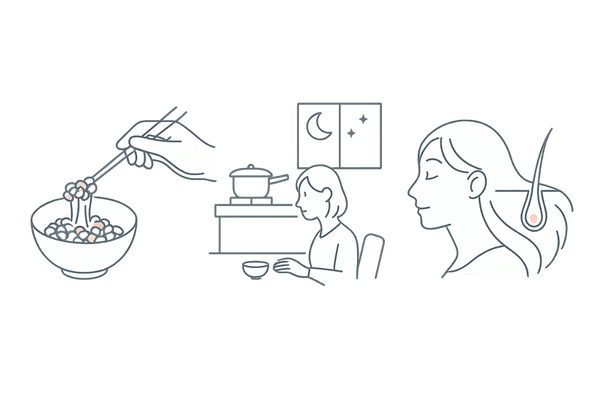
せっかく納豆を食べるなら、その栄養を余すことなく吸収し、効果を最大限に引き出したいものです。
ここでは、少しの工夫で効果を高める食べ方のポイントを確認していきましょう。
加熱はNG?栄養を逃さない調理法
納豆の代名詞ともいえるナットウキナーゼは、熱に弱い性質を持っています。一般的に70℃以上でその働きが大きく低下すると言われています。
そのため、納豆の血行促進効果を期待するのであれば、加熱せずにそのまま食べるのが最も効果的です。
チャーハンやパスタなどの加熱調理に使うと、たんぱく質などの栄養は摂れますが、ナットウキナーゼの恩恵は受けにくくなります。
食べるベストタイミングは「夜」
納豆を食べるタイミングは、朝食のイメージが強いかもしれませんが、髪や健康のためには「夜」に食べるほうがおすすめです。
理由は主に2つあり、1つはナットウキナーゼの効果が食後10〜12時間持続するため、血栓ができやすいとされる就寝中に血流をサポートしてくれる点です。
2つ目は、髪の成長を促す成長ホルモンが夜22時〜深夜2時の間に最も分泌されるため、その時間帯に合わせて髪の材料となる栄養素を補給できる点です。
時間帯別に見る納豆摂取のメリット
| 摂取タイミング | 主なメリット | 目的 |
|---|---|---|
| 朝 | 良質なたんぱく質で一日の活動エネルギーを補給 | エネルギー補給、代謝アップ |
| 夜 | 就寝中の血流サポート、成長ホルモン分泌時間に栄養補給 | 血行促進、育毛サポート |
1日の摂取量の目安
納豆は健康に良い食品ですが、食べ過ぎは禁物です。大豆イソフラボンの過剰摂取はホルモンバランスに影響を与える可能性も指摘されています。
内閣府の食品安全委員会は、大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限値を70〜75mgとしています。
納豆1パック(約50g)に含まれるイソフラボンは約35mgなので、1日1〜2パック程度を目安にすると良いでしょう。
よく混ぜるのも大切
納豆をよくかき混ぜると、ネバネバ成分である「グルタミン酸ポリマー」が増加し、旨味が増すと言われています。
このネバネバ成分には、胃の粘膜を保護したり、血糖値の急上昇を抑えたりする効果もあります。
また、よく混ぜるとタレも絡みやすくなり、美味しく食べられます。
ストレスや生活習慣の乱れも薄毛の原因?納豆だけでは解決しない髪の悩み
ここまで納豆の素晴らしい効果について解説してきましたが、「毎日納豆を食べているのに、髪の悩みが改善しない…」と感じる方もいるかもしれません。
それは、女性の薄毛の原因が食事だけでなく、生活習慣全体が複雑に影響しているからです。
髪は「血余」栄養が最後に届く場所
東洋医学には「髪は血の余り(血余)」という言葉があります。
体に取り入れられた栄養がまず生命維持に重要な心臓や脳などの臓器に使われ、最後に余った分が髪や爪に回される、という考え方です。
つまり、体全体が栄養で満たされていなければ、いくら髪に良いとされるものを食べても髪まで栄養が届きにくいのです。
睡眠不足が髪の成長を妨げる理由
髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。眠り始めの深いノンレム睡眠時に最も多く分泌されます。
睡眠時間が不足したり眠りの質が低かったりすると成長ホルモンの分泌が減少し、毛母細胞の分裂が滞り、髪の成長が妨げられてしまいます。
健やかな髪のためには、毎日6〜7時間程度の質の良い睡眠が必要です。寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、安眠できる環境を整えましょう。
薄毛につながる生活習慣チェック
| チェック項目 | 髪への影響 |
|---|---|
| 睡眠時間が6時間未満の日が多い | 成長ホルモンの分泌が低下し、髪の成長を妨げる |
| 強いストレスを感じることが頻繁にある | 血管が収縮し頭皮の血行が悪化。ホルモンバランスも乱れる |
| 食事を抜いたり、偏った食事をしたりすることがある | 髪の材料となる栄養素そのものが不足する |
| 過度なダイエットを繰り返している | 栄養不足とホルモンバランスの乱れを招く |
心の健康と髪の密接な関係
強いストレスは自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させます。血行不良は、髪に必要な栄養が届かなくなる直接的な原因です。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れも引き起こし、抜け毛を増やす一因となります。
適度な運動や趣味の時間を持つなど、自分なりのストレス解消法を見つけ、心穏やかに過ごす時間を作ると巡り巡って髪の健康にも繋がるのです。
食事だけでない総合的なケアの重要性
納豆は確かに髪に良い影響を与える優れた食品です。しかし、納豆さえ食べていれば大丈夫、というわけではありません。
バランスの取れた食事や十分な睡眠、ストレス管理といった生活習慣全体を整える工夫が、健やかな髪を育むための土台となります。
もし、セルフケアだけでは改善が見られないときは、専門クリニックへの相談も一つの選択肢です。
専門家の視点から原因を特定し、適切な治療を行うことが悩み解決への近道となるでしょう。
納豆を食べる際の注意点とデメリット
多くのメリットがある納豆ですが、いくつか注意すべき点もあります。
ご自身の体調や服用している薬に合わせて、適切に取り入れましょう。
食べ過ぎによる過剰摂取のリスク
前述の通り、大豆イソフラボンの過剰摂取は推奨されていません。
また、納豆にはセレンというミネラルも含まれており、これも過剰に摂取すると胃腸障害などを起こす可能性があります。
何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。1日1〜2パックを目安に、バランスの良い食事の一部として楽しみましょう。
特定の薬との相互作用(ワーファリンなど)
血液を固まりにくくする薬「ワーファリン」を服用している方は、納豆の摂取を避ける必要があります。
納豆に非常に多く含まれるビタミンK2には血液を凝固させる作用があり、ワーファリンの効果を弱めてしまうからです。
この薬を処方されている方は、必ず主治医や薬剤師に相談してください。
納豆摂取を注意すべきケース
| ケース | 理由 | 対応 |
|---|---|---|
| ワーファリンを服用中 | ビタミンK2が薬の効果を妨げる | 摂取を完全に控える |
| 痛風・高尿酸血症 | プリン体を比較的多く含む | 食べ過ぎに注意し、医師に相談 |
| 大豆アレルギー | アレルギー症状を引き起こす | 摂取を避ける |
プリン体の含有量と痛風への配慮
納豆には、尿酸値を上げる原因となるプリン体も含まれています。1パックあたり約57mgと、食品の中では中程度の含有量です。
健康な人が通常の量を食べる分には問題ありませんが、すでに尿酸値が高い方や痛風の治療中の方は、食べ過ぎに注意が必要です。
納豆と組み合わせたい!髪に良い食材
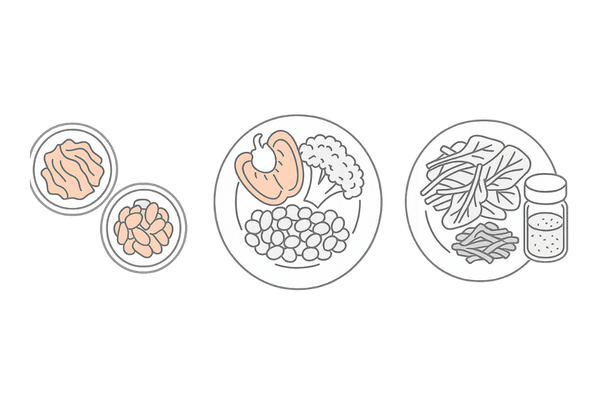
納豆単体でも栄養豊富ですが、他の食材と組み合わせると、さらに髪に良い相乗効果が期待できます。いつもの納豆に一品加えて、育毛効果を高めましょう。
ビタミンC豊富な野菜・果物
亜鉛の吸収率を高めるビタミンCは、ぜひ一緒に摂りたい栄養素です。
また、ビタミンC自体も頭皮のコラーゲン生成を助け、健康な血管を維持するのに役立ちます。
刻んだパプリカやピーマンを混ぜたり、食後に柑橘類を食べたりするのがおすすめです。
鉄分を多く含む食材
特に女性は月経により鉄分が不足しがちです。鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担います。
鉄分が不足すると頭皮も酸欠状態になり、髪の成長に影響が出ます。
ほうれん草のおひたしに納豆をかける、などの工夫をしてみても良いでしょう。
納豆との食べ合わせ相乗効果
| 組み合わせる食材 | 主な栄養素 | 期待できる相乗効果 |
|---|---|---|
| キムチ、漬物 | 乳酸菌 | 発酵食品同士で腸内環境をさらに改善 |
| パプリカ、ブロッコリー | ビタミンC | 亜鉛の吸収率アップ、コラーゲン生成促進 |
| ごま、アボカド | ビタミンE | 抗酸化作用で血行促進、頭皮の老化防止 |
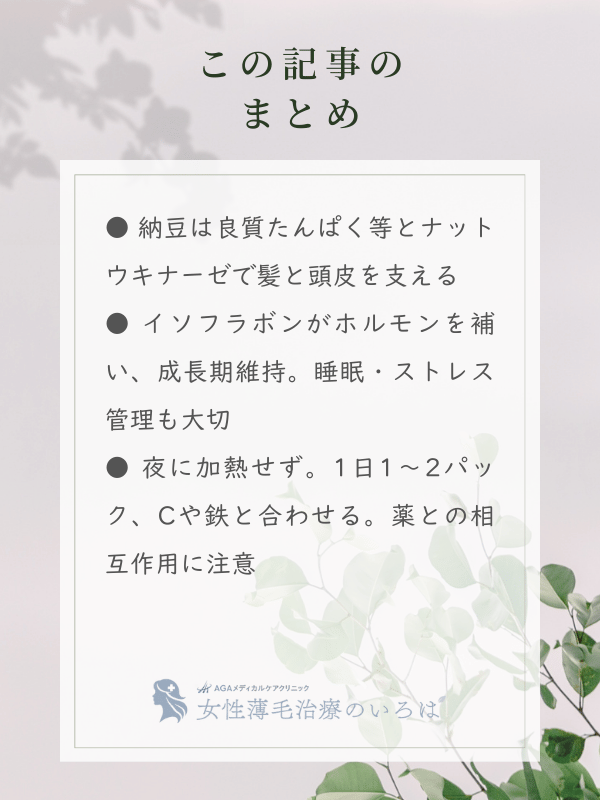
納豆と薄毛に関するよくある質問(Q&A)
さいごに、患者さんからよくいただく納豆と薄毛に関する質問にお答えします。
- 毎日食べないと効果はありませんか?
-
毎日食べ続けるのが理想的ではありますが、義務感でストレスになっては逆効果です。
まずは週に3〜4回からでも、継続して食生活に取り入れることが大切です。無理のない範囲で習慣にしていきましょう。
- 納豆が苦手です。代わりになる食品はありますか?
-
大豆イソフラボンやたんぱく質を摂取するという点では、豆腐や豆乳、味噌などの他の大豆製品も有効です。
ただし、ナットウキナーゼやポリアミンなど納豆菌由来の成分は納豆特有のものです。
どうしても苦手な場合は、他の食品でバランス良く栄養を補うことを考えましょう。
- 効果はどれくらいで実感できますか?
-
髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びません。また、ヘアサイクル全体が入れ替わるには数年かかります。
食事による体質改善の効果が髪に現れるには、最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかると考えてください。焦らず、気長に続けていきましょう。
- ひきわり納豆と普通の納豆、どちらが良いですか?
-
栄養価に大きな違いはありませんが、ひきわり納豆の方が皮がない分、消化吸収が良いとされています。
また、製造工程で砕かれるため、納豆菌が繁殖する表面積が広くなり、ビタミンK2の含有量がやや多くなる傾向があります。
どちらを選んでも問題ありませんので、お好みで選んでください。
参考文献
TRÜEB, Ralph M.; TRÜEB, Ralph M. Value of Nutrition-Based Therapies for Hair Growth, Color, and Quality. Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice, 2020, 225-255.
GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.
LIU, Yanchun, et al. Analysis of main components and prospects of natto. Advances in Enzyme Research, 2021, 9.1: 1-9.
CHOI, Ji-Hye, et al. Effects of black soybean and fermented black soybean extracts on proliferation of human follicle dermal papilla cells. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 2017, 46.6: 671-680.
KNAPEN, M. H. J., et al. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women. Osteoporosis International, 2013, 24.9: 2499-2507.
MESSINA, Mark, et al. The health effects of soy: A reference guide for health professionals. Frontiers in Nutrition, 2022, 9: 970364.
STEINKRAUS, Keith H. Nutritional significance of fermented foods. Food Research International, 1994, 27.3: 259-267.