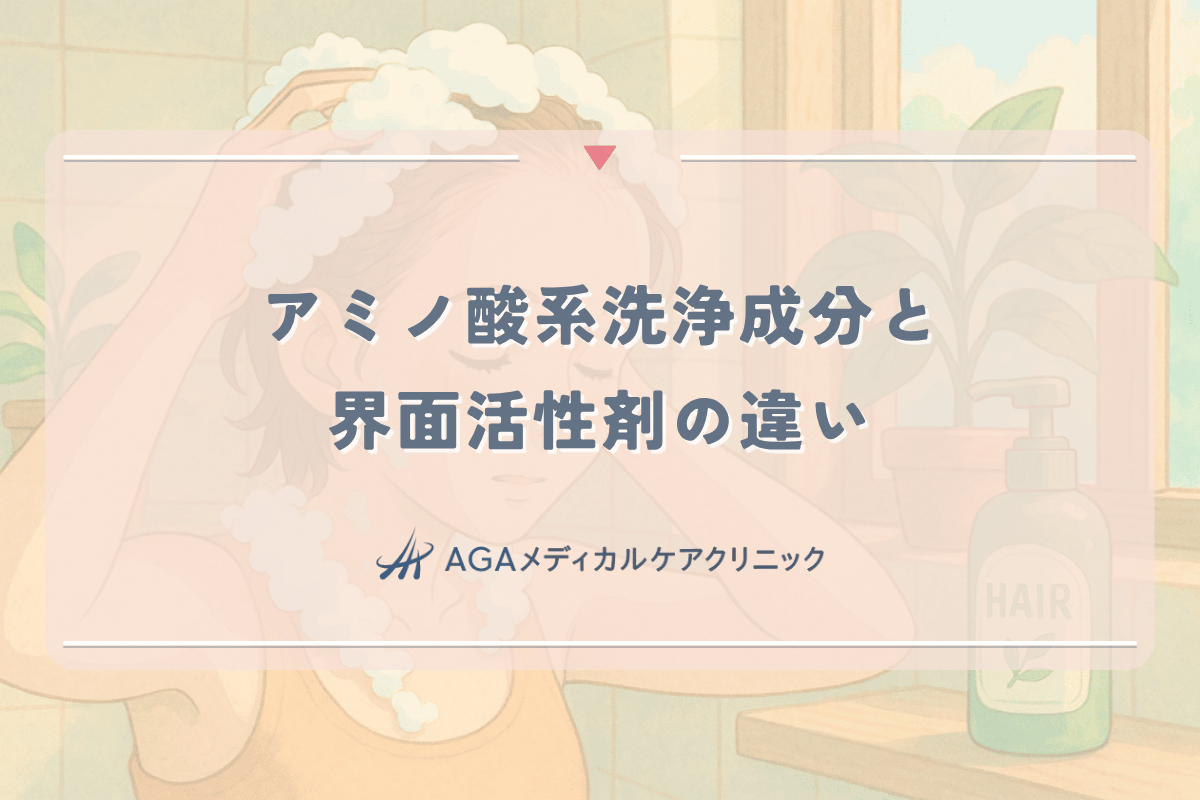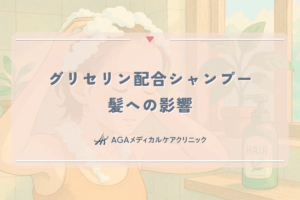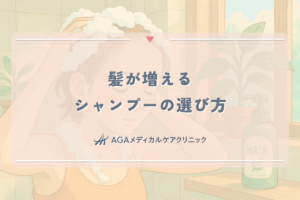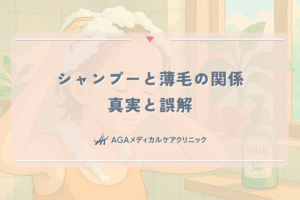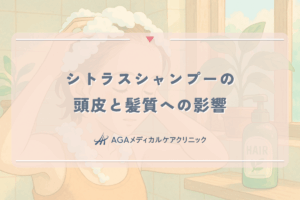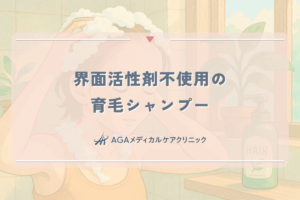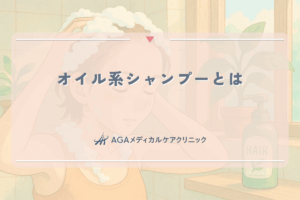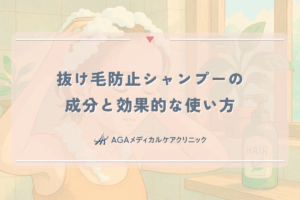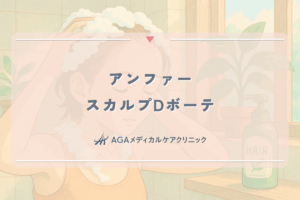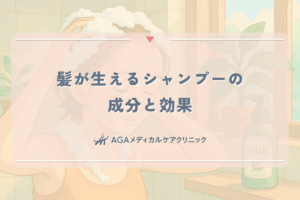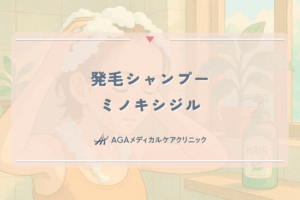女性の薄毛や抜け毛、頭皮のかゆみの原因の一つは、毎日使うシャンプーにあるかもしれません。
なかでも洗浄成分である「界面活性剤」の種類は、頭皮環境に大きな影響を与えます。
この記事では、数ある界面活性剤の中でも、なぜ「アミノ酸系洗浄成分」が頭皮に優しいと言われるのか、その理由を専門的な視点から詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
まずは基本から|シャンプーと界面活性剤の役割
健やかな髪を育む土台は、健康な頭皮です。毎日のシャンプーは、その頭皮環境を整えるための基本的なスキンケアと言えます。
まずは、シャンプーがどのような働きをするのか、そしてその中心的な役割を担う「界面活性剤」について理解を深めましょう。
シャンプーの基本的な働き
シャンプーの最も重要な役割は、頭皮と髪の汚れを落とすことです。
一言で汚れと言っても、その種類は様々です。汗やホコリといった水で洗い流せる汚れもあれば、皮脂や整髪料などの油性の汚れもあります。
油性の汚れは水だけでは落とすのが難しく、放置すると毛穴の詰まりや酸化を招き、かゆみやフケ、抜け毛といった頭皮トラブルの原因となります。
シャンプーはこれらの多様な汚れを効率的に除去し、頭皮を清潔な状態に保つためにあります。
「界面活性剤」とは何か
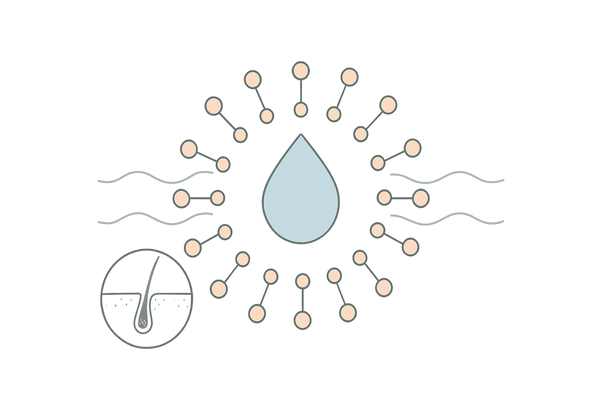
水と油のように、本来混じり合わない物質の境界面(界面)に作用して、その性質を変化させる物質の総称が「界面活性剤」です。石けんをイメージすると分かりやすいでしょう。
油汚れが付いた手を水だけで洗ってもなかなか落ちませんが、石けんを使うと綺麗に落ちます。
これは、界面活性剤が持つ「水になじむ部分(親水基)」と「油になじむ部分(親油基)」の2つの性質によるものです。
親油基が油汚れを取り囲み、親水基がその全体を水に溶け込ませ、汚れを浮かせて洗い流します。
なぜシャンプーに界面活性剤が必要なのか
頭皮から分泌される皮脂や、スタイリングに使うワックスやオイルは油性の汚れです。これらを水だけで洗い流すことはできません。そこで界面活性剤の力が必要になります。
界面活性剤が皮脂などの油性汚れを頭皮から引き離し、お湯と一緒に洗い流せる状態に変えて、頭皮をさっぱりと洗い上げられます。
洗浄力をはじめ、泡立ちや使用感を決定づける、シャンプーの心臓部とも言える成分なのです。
界面活性剤の主な働き
| 働き | 内容 | シャンプーにおける役割 |
|---|---|---|
| 浸透作用 | 物質の表面張力を弱め、液体を染み込みやすくする | 洗浄成分が頭皮や髪の隅々まで行き渡るのを助ける |
| 乳化作用 | 水と油のように混じり合わないものを混ぜ合わせる | 皮脂や整髪料(油性)を水分と混ぜ、洗い流しやすくする |
| 分散作用 | 固体や液体の粒子を均一に分散させる | フケやホコリなどの汚れを水中に分散させ、再付着を防ぐ |
界面活性剤の主な種類とそれぞれの特徴
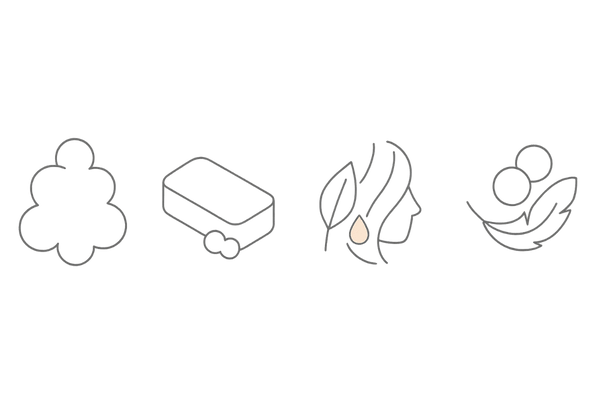
シャンプーに使用される界面活性剤は、一つではありません。原料や製法の違いからいくつかの系統に分類され、それぞれ洗浄力や刺激性、洗い上がりの質感が異なります。
高級アルコール系(ラウレス硫酸Naなど)
石油や油脂を原料とする界面活性剤で、市販のシャンプーに最も広く使われているタイプです。非常に高い洗浄力と豊かな泡立ちが特徴で、洗い上がりに強いさっぱり感を得られます。
皮脂分泌が多い方やしっかりとした洗い心地を好む方には向いていますが、その反面、洗浄力が強力なため、頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまう可能性があります。
これが乾燥やかゆみ、あるいは皮脂の過剰分泌を招く場合もあるため、乾燥肌や敏感肌の方は注意が必要です。
石けん系
天然の油脂とアルカリを反応させて作られる、古くからある洗浄成分です。洗浄力は比較的高く、さっぱりとした洗い上がりが特徴です。
天然由来で環境に優しいイメージがありますが、アルカリ性の性質を持ちます。
髪や頭皮は本来、弱酸性であるため、石けん系シャンプーで洗うと髪のキューティクルが開き、きしみやゴワつきを感じやすくなります。
そのため、酸性のリンスやコンディショナーで中和するケアが一般的です。
アミノ酸系
天然のヤシ油などから抽出した脂肪酸と、グルタミン酸やグリシンなどのアミノ酸を結合させて作られる洗浄成分です。
人の皮膚や髪のタンパク質を構成するアミノ酸から作られているため生体親和性が高く、頭皮への刺激が非常に穏やかです。
洗浄力はマイルドで、頭皮の潤いを保ちながら優しく洗い上げられます。このため、乾燥肌や敏感肌の方、薄毛や抜け毛にお悩みの方に適した洗浄成分と言われます。
ベタイン系(両性界面活性剤)
ベビーシャンプーにもよく使用される、非常に低刺激な洗浄成分です。
アミノ酸系よりもさらにマイルドで、単体で主成分として使われるケースは少なく、高級アルコール系やアミノ酸系のシャンプーに配合して刺激を緩和したり、泡立ちを補助したりする目的で用いられる場合が多いです。
コンディショニング効果も持ち合わせているのが特徴です。
洗浄成分の種類別特徴
| 系統 | 代表的な成分名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 高級アルコール系 | ラウレス硫酸Na、ラウリル硫酸Na | 高洗浄力、高起泡性、安価。脱脂力が強く刺激の懸念も。 |
| 石けん系 | 石ケン素地、カリ石ケン素地 | 高洗浄力、さっぱり。アルカリ性で髪がきしみやすい。 |
| アミノ酸系 | ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNa | 低刺激、マイルドな洗浄力。保湿力がありしっとり仕上がる。 |
アミノ酸系洗浄成分が頭皮に優しいと言われる理由
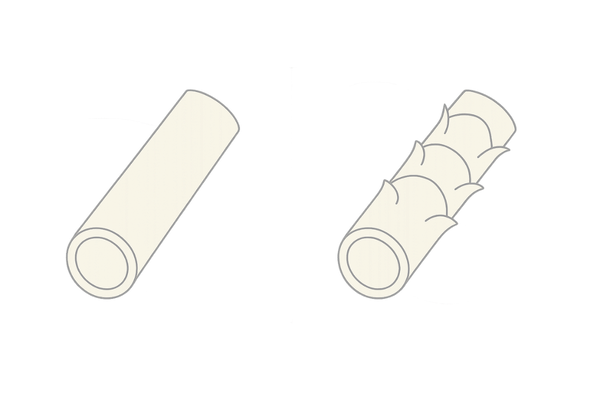
薄毛や頭皮トラブルをケアする上で、アミノ酸系シャンプーが注目されるのには明確な理由があります。
洗浄力だけでなく、頭皮環境そのものを健やかに保つための性質をいくつも備えているからです。その秘密を詳しく見ていきましょう。
人の皮膚や髪と同じ弱酸性
健康な人の皮膚や髪の表面は、pH(ペーハー)値が4.5~6.0の弱酸性に保たれています。
この弱酸性の状態は、皮膚の常在菌バランスを整え、外部の雑菌の繁殖を防ぐバリア機能の役割を担っています。
アミノ酸系洗浄成分はこの弱酸性の性質を持っているため、洗浄後も頭皮のpHバランスを大きく崩すことがありません。頭皮本来の防御機能を維持しながら洗える点が、大きな利点です。
洗浄成分のpH(ペーハー)比較
| 洗浄成分 | 性質 | 頭皮への影響 |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | 弱酸性 | 頭皮のpHバランスを保ちやすく、バリア機能を損ないにくい。 |
| 石けん系 | アルカリ性 | 一時的にアルカリ性に傾き、キューティクルが開く。きしみの原因に。 |
| 高級アルコール系 | 中性~弱アルカリ性 | 製品によるが、洗浄力が高いためpH以外の影響も考慮が必要。 |
適度な洗浄力と保湿力
アミノ酸系洗浄成分の魅力は、その絶妙な洗浄力にあります。汚れはきちんと落としながらも、頭皮の健康維持に必要な皮脂(皮脂膜)は奪いすぎないのです。
皮脂膜は頭皮の水分蒸発を防ぎ、外部の刺激から守る天然の保湿クリームのような役割を果たしています。
この皮脂膜を適度に残すため洗い上がりのつっぱり感が少なく、しっとりとした潤いを保てます。この保湿力が、乾燥によるフケやかゆみを防ぐことにつながります。
洗いすぎによる頭皮トラブルを防ぐ
洗浄力の強いシャンプーで毎日ゴシゴシ洗っていると、頭皮は必要な潤いを失い、乾燥状態に陥ります。すると、体は失われた潤いを補おうとして、かえって皮脂を過剰に分泌するときがあります。
この状態が「インナードライ」と呼ばれるもので、頭皮がベタつくのにフケも出る、といった悪循環を招きかねません。
アミノ酸系のマイルドな洗浄は、このような「洗いすぎ」によるトラブルを未然に防ぎ、皮脂バランスの整った健やかな頭皮環境へと導きます。
アミノ酸系シャンプーのメリットとデメリット
頭皮に優しいアミノ酸系シャンプーですが、万能というわけではありません。
メリットを最大限に活かすためには、デメリットも正しく理解し、ご自身の髪質や頭皮の状態に合わせて選びましょう。
メリット|低刺激で頭皮と髪を健やかに保つ
最大のメリットは、これまで述べてきた通り「低刺激性」です。
洗浄力が穏やかで頭皮の潤いを守りながら洗えるため、乾燥肌や敏感肌、アトピー性皮膚炎などで悩む方でも安心して使用しやすい点が挙げられます。
また、髪の主成分であるタンパク質の流出を抑えながら洗えるため、カラーリングやパーマでダメージを受けた髪のケアにも適しています。
継続して使用すると頭皮環境が整い、ハリやコシのある健康な髪が育ちやすくなります。
アミノ酸系シャンプーの利点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 低刺激性 | 皮膚への刺激が少なく、敏感な頭皮にも使いやすい。 |
| 保湿性 | 必要な皮脂を残し、頭皮と髪の潤いを保つ。 |
| ダメージケア | 髪のタンパク質流出を抑え、ダメージ毛を優しく洗い上げる。 |
デメリット|洗浄力や泡立ちが穏やかな場合も
メリットであるマイルドな洗浄力は、時としてデメリットにもなります。
皮脂分泌が非常に多い方や、普段からワックスやオイルなどの整髪料を多めに使用する方の場合、一度のシャンプーでは洗浄力が物足りず、すっきりしないと感じるときがあります。
また、高級アルコール系に比べて泡立ちが控えめな製品も多く、豊かな泡で洗うことに慣れている方は、物足りなさを感じるかもしれません。
価格が比較的高めになる傾向
アミノ酸系洗浄成分は石油を主原料とする高級アルコール系成分に比べて、製造に手間とコストがかかります。このため、製品の価格も高めに設定される傾向があります。
毎日使うものだからこそ、コストパフォーマンスを重視する方にとっては、デメリットと感じられるかもしれません。しかし、これは頭皮の健康への投資とも考えられます。
シャンプー選びで「失敗した」と感じる本当の理由
「評判の良いアミノ酸系シャンプーを試したのに、なんだか合わなかった…」といった方もいるでしょう。
実は、シャンプー選びの失敗には、単なる成分の種類だけでは語れない、いくつかの落とし穴が存在します。
「アミノ酸系なら何でも良い」という誤解
「アミノ酸系」と表示されていても、その品質や配合は製品によって様々です。
例えば、アミノ酸系洗浄成分を少し配合しただけで「アミノ酸系シャンプー」と謳っている製品も存在します。
洗浄力の強い高級アルコール系成分を主成分とし、アミノ酸系成分を補助的に加えているケースです。
これではアミノ酸系のメリットを十分に享受するのは難しいでしょう。製品選びでは、単語に惑わされず、成分表示全体を見る意識が大切です。
自分の皮脂量と洗浄力のバランスを見極める
シャンプー選びで最も重要なのは、ご自身の頭皮の皮脂量と、シャンプーの洗浄力のバランスです。
例えば、皮脂が少ない乾燥肌の方が洗浄力の高いシャンプーを使えば乾燥が進みますし、逆に皮脂が多い脂性肌の方がマイルドすぎるシャンプーを使うと、皮脂が落としきれず毛穴詰まりやベタつきの原因になります。
ご自身の頭皮タイプを知り、それに合った洗浄力を持つシャンプーを選ぶことが失敗しないための鍵です。
頭皮タイプと洗浄力の目安
| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨される洗浄力バランス |
|---|---|---|
| 乾燥肌 | 洗髪後につっぱり感があり、細かいフケが出やすい。 | アミノ酸系やベタイン系主体のマイルドな洗浄力。 |
| 脂性肌 | 日中になると髪がベタつく。頭皮のニオイが気になることも。 | 適度な洗浄力を持つアミノ酸系、または石けん系。洗いすぎには注意。 |
| 混合肌 | ベタつくのにフケも出る。Tゾーンは脂っぽいのに頬は乾燥するなど。 | アミノ酸系を基本に、週1〜2回、少し洗浄力の高いものを使うなど工夫。 |
成分表示の「順番」でわかること
化粧品の成分表示は、配合量の多い順に記載するというルールがあります。これはシャンプーも同様です。
成分表示の先頭に記載されている「水」の次に何が来ているかを確認してみましょう。そこに「ラウレス硫酸Na」などの高級アルコール系成分があれば、それが洗浄の主成分です。
一方、「ココイルグルタミン酸TEA」や「ラウロイルメチルアラニンNa」などのアミノ酸系成分が上位にあれば、それを主成分としたマイルドなシャンプーであると判断できます。
シリコン・ノンシリコン論争の先へ
「ノンシリコン」という言葉が流行しましたが、シリコン(ジメチコンなど)は髪の指通りを滑らかにし、摩擦によるダメージを防ぐ有用なコーティング成分です。
毛穴に詰まるという説も、現在の化粧品技術ではほとんど心配ないと考えられています。
大切なのはシリコンの有無ではなく、洗浄成分が自分に合っているか、そして頭皮の健康をサポートする成分が含まれているかです。
表面的な言葉に惑わされず、本質的な部分で製品を見極めましょう。
薄毛に悩む女性のためのアミノ酸系シャンプー選びのポイント
では、具体的にどのような視点でシャンプーを選べば良いのでしょうか。
ここでは、特に薄毛や抜け毛が気になる女性が、アミノ酸系シャンプーを選ぶ際にチェックすべき具体的なポイントを解説します。
成分表示でチェックすべきアミノ酸系洗浄成分
成分表示の上位に、以下のようなアミノ酸由来の洗浄成分が記載されているかを確認しましょう。
- グルタミン酸系(例:ココイルグルタミン酸Na、ココイルグルタミン酸TEA)
- アラニン系(例:ラウロイルメチルアラニンNa、ココイルメチルアラニンTEA)
- グリシン系(例:ココイルグリシンK)
- タウリン系(例:ココイルメチルタウリンNa)
これらが主成分となっているものが、いわゆる本格的なアミノ酸系シャンプーです。
代表的なアミノ酸系洗浄成分
同じアミノ酸系でも、成分によって特徴が異なります。
| 成分系統 | 特徴 | 洗い上がりの質感 |
|---|---|---|
| グルタミン酸系 | 非常にマイルド。コンディショニング効果が高い。 | しっとり、なめらか |
| アラニン系 | 適度な洗浄力と泡立ち。さっぱり感もある。 | 比較的さっぱり、軽い |
| グリシン系 | アミノ酸系の中では洗浄力が高め。泡立ちも良い。 | さっぱり、すっきり |
頭皮ケアをサポートする保湿・補修成分
優れた洗浄成分に加えて、頭皮環境を整え、髪を健やかに保つための補助成分が配合されているかも重要なチェックポイントです。
特に女性の薄毛は、頭皮の乾燥や血行不良が関係しているケースも多いため、保湿成分や血行促進成分、抗炎症成分などに注目しましょう。
- 保湿成分(例:ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン、グリセリン)
- 抗炎症成分(例:グリチルリチン酸2K、アラントイン)
- 血行促進成分(例:センブリエキス、ショウガ根エキス)
避けた方が良い可能性のある添加物
すべての添加物が悪いわけではありませんが、頭皮が敏感になっている時は、刺激となる可能性のある成分は避けるほうが賢明です。
製品の品質を安定させるために必要な場合もありますが、以下の成分が多く含まれるものは、慎重に選びましょう。
注意したい成分
| 成分カテゴリー | 考えられる影響 |
|---|---|
| 合成香料・合成着色料 | アレルギー反応や頭皮刺激の原因になることがある。 |
| 防腐剤(パラベンなど) | 接触性皮膚炎の原因になることがあるが、安全性は確立されている。肌に合わない場合のみ避ける。 |
| エタノール(アルコール) | 清涼感を与えるが、揮発する際に水分を奪い、乾燥を助長することがある。 |
正しいシャンプー方法で頭皮環境を整える

どんなに良いシャンプーを選んでも、洗い方が間違っていては効果が半減してしまいます。
頭皮への負担を最小限に抑え、洗浄効果を最大限に引き出すための正しいシャンプーの手順を身につけましょう。
洗う前にはブラッシングを
シャンプー前に髪が乾いた状態でブラッシングを行い、髪の絡まりをほどいて表面に付着したホコリやフケを浮き上がらせます。
このひと手間で、シャンプー時の泡立ちが良くなり、髪への摩擦を減らせます。頭皮の血行促進にも役立ちます。
予洗いで汚れの7割は落ちる
シャンプー剤をつける前に、38℃程度のぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと洗い流します。これを「予洗い」と呼びます。
実は、汗やホコリなどの水溶性の汚れは、この予洗いだけで7割程度が落ちると言われます。
予洗いを丁寧に行うと、使用するシャンプーの量を減らせて、頭皮への負担を軽減できます。
指の腹で優しくマッサージするように洗う
シャンプーを手のひらで軽く泡立ててから、髪ではなく頭皮に均一につけていきます。洗う際は、決して爪を立てず、指の腹を使って頭皮を優しくマッサージするように洗いましょう。
下から上へ、ジグザグに動かすように洗うと毛穴の汚れが落ちやすくなります。ゴシゴシと力を入れる必要は全くありません。
すすぎ残しは頭皮トラブルのもと
シャンプーで最も重要な工程が「すすぎ」です。シャンプー剤が頭皮に残っていると、かゆみや炎症、フケ、毛穴の詰まりといった様々なトラブルの原因になります。
洗う時にかけた時間の2倍以上の時間をかけるつもりで、髪の生え際や耳の後ろ、襟足など、すすぎ残しが多い部分を特に意識して、ぬるま湯で丁寧に洗い流してください。
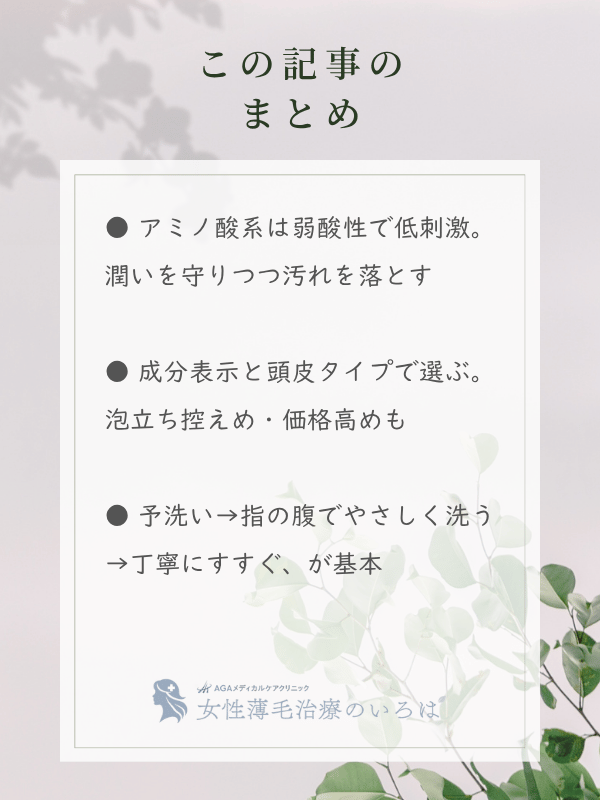
よくある質問
アミノ酸系シャンプーに関する、患者さんからよくいただくご質問にお答えします。
- アミノ酸系シャンプーは毎日使っても大丈夫?
-
問題ありません。アミノ酸系シャンプーは洗浄力がマイルドで低刺激なため、毎日の洗髪に適しています。
むしろ、頭皮の汚れはその日のうちにリセットする習慣が、健やかな頭皮環境を保つ上で重要です。汗をかいた日や整髪料を使った日は、毎日洗うのを基本としましょう。
- 洗い上がりが物足りない時はどうすればいい?
-
皮脂が多い方や整髪料を多用した日など、一度洗いで物足りなさを感じる場合は、二度洗いを試してみてください。
一度目は髪全体の汚れを軽く落とし、二度目で頭皮を中心に丁寧に洗うと、すっきりと洗い上がります。
また、洗浄力が少し高めのアラニン系やグリシン系のアミノ酸シャンプーを選ぶのも一つの方法です。
- 他のシャンプーと併用しても良い?
-
基本的には問題ありませんが、目的を明確にすることが大切です。
例えば、「普段はアミノ酸系で優しく洗い、週に1〜2回、皮脂が気になる時だけ少し洗浄力の高いシャンプーを使う」といった使い分けは有効な場合があります。
ただし、異なる成分が頭皮に与える影響を考慮し、ご自身の頭皮の状態をよく観察しながら行ってください。
- 子供や敏感肌の家族も一緒に使えますか?
-
多くの場合でご家族と一緒にお使いいただけます。アミノ酸系シャンプーは、もともと皮膚への刺激が少ないため、デリケートな子供の肌や、敏感肌の方にも適しています。
ただし、すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
特に香料や植物エキスなどに反応する可能性もゼロではないため、初めて使用する際は、念のため腕の内側などで試してから使うとより安心です。
参考文献
OKASAKA, Mana, et al. Evaluation of anionic surfactants effects on the skin barrier function based on skin permeability. Pharmaceutical Development and Technology, 2019, 24.1: 99-104.
VU, Trang. Rheology control mechanisms for amino acid-based surfactant systems. 2021. PhD Thesis. University of Cincinnati.
TRIPATHY, Divya B., et al. Synthesis, chemistry, physicochemical properties and industrial applications of amino acid surfactants: A review. Comptes Rendus. Chimie, 2018, 21.2: 112-130.
TAKEHARA, Masahiro. Properties and applications of amino acid based surfactants. Colloids and surfaces, 1989, 38.1: 149-167.
XIA, JIDING. Amino Acid Surfactants: Chemistry. Protein-Based Surfactants: Synthesis: Physicochemical Properties, and Applications, 2001, 75.
BARTKUTĖ, Erlita. Formulation and Evaluation of Herbal Shampoo. 2024. Master’s Thesis. Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania).
BEZERRA, Káren GO, et al. Application of plant surfactants as cleaning agents in shampoo formulations. Processes, 2023, 11.3: 879.
MIRAJKAR, Yelloji-Rao K. Applications of surfactants in shampoos. Handbook of Detergents. Part E: Applications, Ed. U. Zoller, CRS Press: Boca Raton, 2008, 151-179.