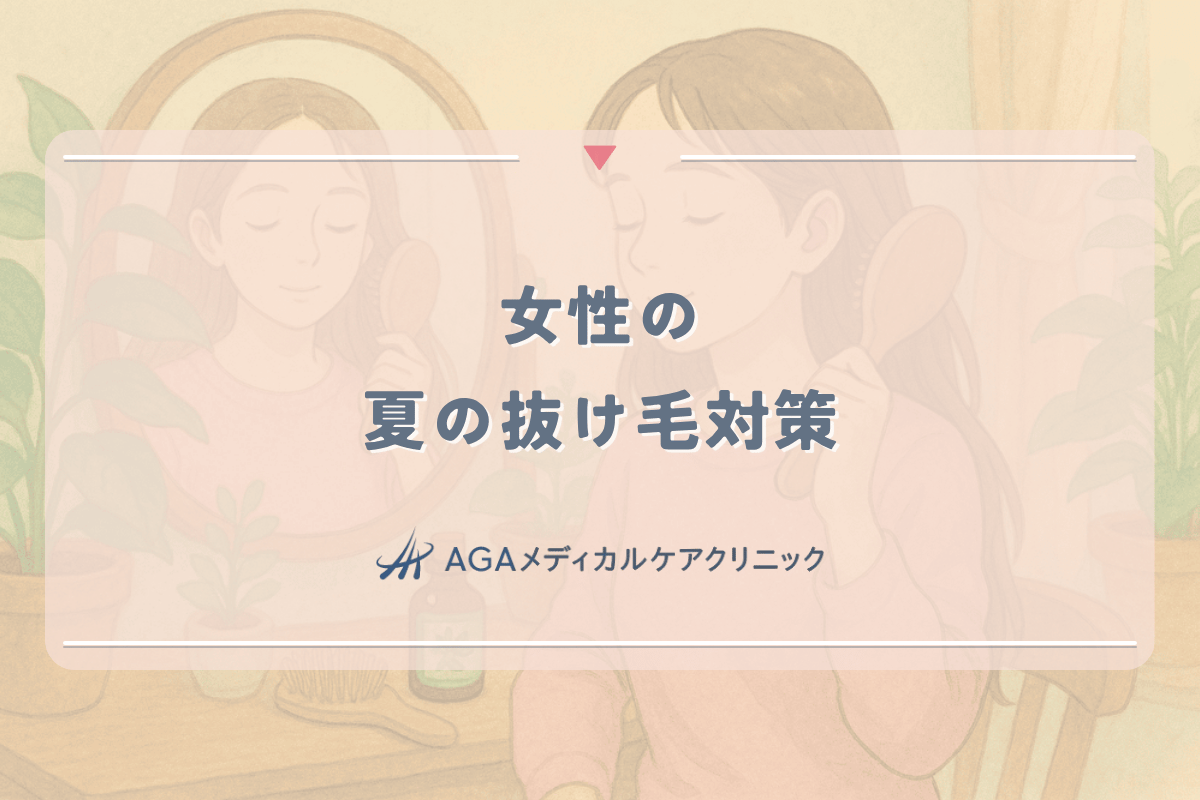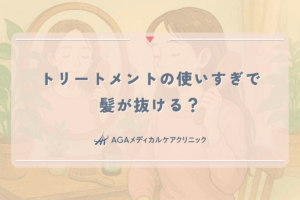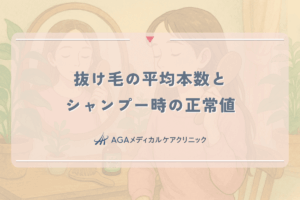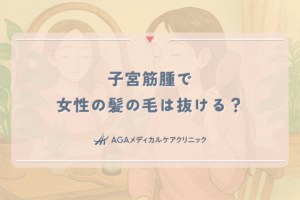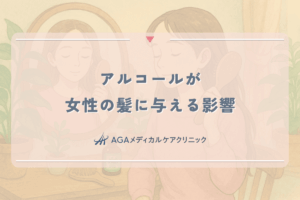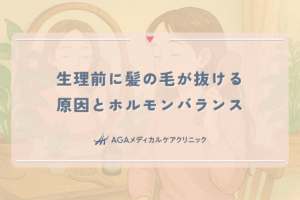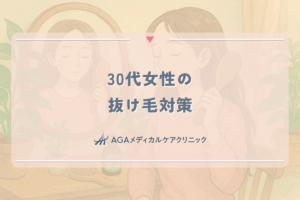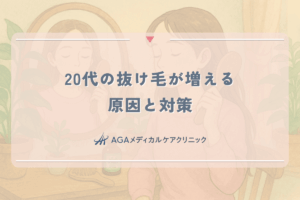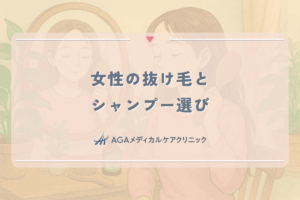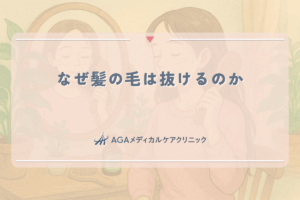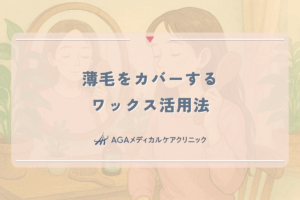夏になると抜け毛の多さが気になる方もいるのではないでしょうか。ブラッシングやシャンプーの際に、ごそっと抜ける髪の毛を見て不安になるのも無理はありません。
夏の強い日差しや汗、冷房の効いた室内環境は、知らず知らずのうちに頭皮に大きな負担をかけています。
この記事では、なぜ夏に女性の抜け毛が増えるのか、その原因を詳しく解説し、今日から始められる具体的な予防方法とヘアケアのポイントを専門的な視点からご紹介します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
夏に抜け毛が増えるのはなぜ?女性特有の要因
夏は他の季節に比べて抜け毛が増加傾向にあると感じる方が多い季節です。その背景には、夏特有の過酷な環境が複合的に影響しています。
特に女性は、ホルモンバランスの変動も相まって、これらの影響を受けやすい状態にあります。
強い紫外線が頭皮に与えるダメージ
夏に最も警戒すべきは、容赦なく降り注ぐ紫外線です。肌の日焼けは気にしていても、頭皮の紫外線対策は怠りがちではないでしょうか。
頭皮は体の最も高い位置にあり、直接紫外線を浴びやすい部位です。
紫外線は髪の毛を作る毛母細胞の働きを低下させるだけでなく、頭皮の乾燥や炎症を引き起こし、頭皮環境を悪化させる直接的な原因となります。
これによって髪の成長期が短くなったり、健康な髪が育ちにくくなったりして、抜け毛の増加につながります。
汗や皮脂による頭皮環境の悪化
高温多湿の夏は、汗や皮脂の分泌が活発になります。分泌された汗や皮脂をそのまま放置すると空気中のホコリや汚れと混ざり合い、毛穴を詰まらせる原因となります。
毛穴が詰まると常在菌であるマラセチア菌などが異常繁殖し、かゆみやフケ、脂漏性皮膚炎といった頭皮トラブルを引き起こしやすいです。
このような不衛生な状態は健康な髪が育つ土壌を損ない、抜け毛を促進してしまいます。
夏の主な頭皮トラブルとその原因
| トラブル要因 | 主な症状 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 紫外線 | 乾燥、赤み、炎症、硬化 | 毛母細胞の機能低下、成長阻害 |
| 汗・皮脂 | 毛穴詰まり、かゆみ、フケ、べたつき | 炎症による脱毛、髪のハリ・コシ低下 |
| 冷房 | 血行不良、乾燥、ターンオーバーの乱れ | 栄養不足、髪の成長遅延 |
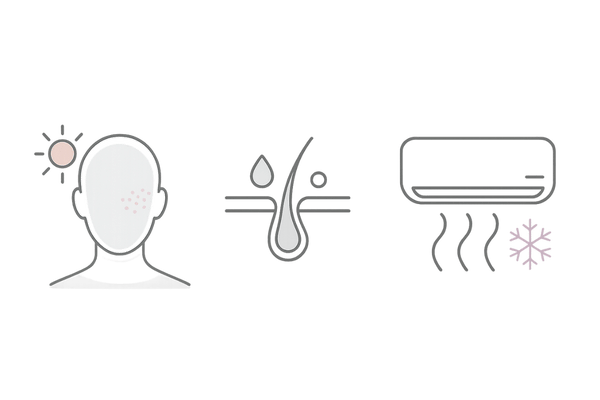
冷房による血行不良と乾燥
屋外の暑さから逃れるための冷房ですが、これもまた抜け毛の一因です。体が冷えすぎると自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮して血行不良に陥ります。
頭皮の毛細血管は非常に細いため、血行不良の影響を真っ先に受けやすい場所です。
血流が滞ると髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで十分に行き渡らなくなり、髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。
また、冷房の効いた室内は空気が乾燥しており、頭皮の水分を奪って乾燥を招くケースもあります。
夏バテによる栄養不足
暑さによる食欲不振や、そうめん・アイスクリームといった冷たくて簡単な食事ばかりに偏ることで起こる「夏バテ」も髪の健康に深刻な影響を与えます。
髪の主成分はケラチンというタンパク質です。タンパク質をはじめ、ビタミンやミネラルといった栄養素が不足すると、健康な髪を作れません。
食事から摂取する栄養が偏ると、生命維持に直接関係のない髪への栄養供給は後回しにされるため、栄養不足の影響が顕著に現れやすいのです。
紫外線は頭皮の老化を招く最大の敵
夏の抜け毛対策を語る上で、紫外線の影響は避けて通れません。
紫外線は単に日焼けを引き起こすだけでなく、頭皮の細胞レベルにまでダメージを与え、長期的に見て薄毛の原因となる「光老化」を進行させます。
ここでは、紫外線がもたらす具体的な影響と、その対策について深掘りします。
紫外線が毛母細胞に与える影響
髪の毛は、毛根の奥にある毛母細胞が分裂を繰り返すことで作られます。
紫外線のなかでも波長の長いUVAは、頭皮の深部(真皮層)にまで到達し、この毛母細胞に直接ダメージを与えます。
細胞のDNAが傷つけられると正常な細胞分裂が妨げられ、健康で太い髪の毛を作れなくなります。これが、髪のハリやコシが失われたり、成長途中で抜けてしまったりする原因です。
顔のシワやたるみを引き起こす光老化と同じ現象が、頭皮でも起きていると考えると分かりやすいでしょう。
頭皮の日焼けが引き起こす炎症と乾燥
強い紫外線を浴びた頭皮は、軽いやけど(サンバーン)を起こした状態になります。赤みやヒリヒリとした痛みを感じるのは、皮膚が炎症を起こしているサインです。
炎症が起きると頭皮のバリア機能が低下し、わずかな刺激にも敏感になります。
さらに、炎症を鎮めようと体の防御反応が働く過程で、活性酸素が大量に発生します。この活性酸素が毛母細胞を攻撃し、抜け毛をさらに助長するという悪循環に陥ります。
また、日焼け後の頭皮は水分が失われ、乾燥して硬くなりがちです。硬い土壌では良い作物が育たないように、硬い頭皮では健康な髪が育ちません。
効果的な紫外線対策グッズの選び方
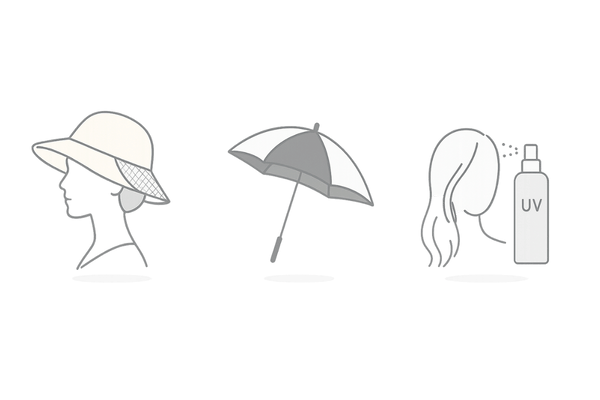
頭皮を紫外線から守るためには、物理的に紫外線を遮断するのが最も効果的です。
外出時には、帽子や日傘を活用する習慣をつけましょう。グッズを選ぶ際には、デザインだけでなく機能性にも注目すると良いです。
頭皮を守る紫外線対策グッズ
| グッズ | 選ぶポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 帽子 | UVカット加工、通気性の良い素材(麻、メッシュ) | 長時間かぶり続けると蒸れるため、時々脱いで換気する |
| 日傘 | 遮光率99%以上、内側が黒いもの(照り返し防止) | 風の強い日や人混みでは使いにくい場合がある |
| 頭皮・髪用UVスプレー | SPF/PA値が高いもの、石けんで落とせるタイプ | 汗で流れやすいため、2〜3時間おきに塗り直す |
日焼けしてしまった後の頭皮ケア
万が一、頭皮が日焼けしてしまった場合は迅速なアフターケアが重要です。
まずは冷たいタオルや保冷剤をタオルで包んだもので優しく頭皮を冷やし、炎症を鎮めます。
ヒリヒリ感が落ち着いたら保湿を徹底しましょう。頭皮用の化粧水や、刺激の少ない保湿ローションを使って、失われた水分を補給します。
このとき、アルコール成分やメントールが多く含まれる製品は、かえって刺激になる場合があるため避けるのが賢明です。
- アロエベラジェル
- ヘパリン類似物質配合ローション
- セラミド配合の敏感肌用化粧水
夏の食生活が髪の健康を左右する
美しい髪は日々の食事から作られます。特に、体力を消耗しやすく食生活が乱れがちな夏は、意識して髪に良い栄養を摂ることが抜け毛予防に繋がります。
内側からのケアで、健やかな頭皮環境の土台を築きましょう。
髪の成長に必要な栄養素とは
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、まずは良質なタンパク質を十分に摂取するのが基本です。
そして、摂取したタンパク質を効率よく髪の毛に変えるためには、ビタミンやミネラルの働きが欠かせません。
これらの栄養素がチームのように連携して働くことで初めて健康な髪が育まれるのです。
髪の成長を支える主要な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンを構成する | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、毛母細胞の分裂を促す | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌を調整する | 豚肉、うなぎ、レバー、玄米 |
夏に積極的に摂りたい食材
夏バテ気味で食欲がない時でも、工夫次第で必要な栄養を摂ることは可能です。例えば、喉越しの良い豆腐や納豆、ヨーグルトは手軽にタンパク質を補給できます。
また、夏野菜であるトマトやパプリカ、カボチャには、抗酸化作用のあるビタミンAやビタミンC、ビタミンEが豊富に含まれています。
これらのビタミンは、紫外線によって発生する活性酸素から頭皮の細胞を守る働きをします。旬の食材を上手に取り入れて、美味しく抜け毛対策を行いましょう。
冷たい飲み物や食べ物がもたらす内臓への負担
暑いとつい手が伸びる冷たい飲み物やアイスクリームですが、摂りすぎには注意が必要です。
冷たいものが胃腸に入ると内臓の温度が急激に下がり、機能を低下させます。消化機能が弱まると、せっかく食事から摂った栄養素を十分に吸収できなくなり、結果として髪への栄養も不足してしまいます。
また、体の冷えは血行不良を招き、頭皮への栄養供給を妨げる原因にもなります。
飲み物はできるだけ常温のものを選んだり、温かいスープを取り入れたりするなど、内臓を冷やさない工夫をしていきましょう。
間違いだらけ?夏のヘアケア常識を疑う
「私のヘアケア、本当に合っているのかな?」そう感じる方もいるでしょう。良かれと思って行っているケアが、実は頭皮や髪にダメージを与えているケースが少なくありません。
ここでは、多くの女性が陥りがちな夏のヘアケアに関する誤解を解き、本当に髪のためになる知識を解説します。ご自身の習慣を一度見直してみましょう。
「汗をかいたらすぐシャンプー」の落とし穴
汗をかいた後のべたつきが気になり、1日に何度もシャンプーをする方がいます。清潔を保つのは重要ですが、過度なシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまいます。
皮脂は、頭皮を乾燥や外部刺激から守る天然のバリアの役割を担っています。
このバリアが失われると頭皮は無防備な状態になり、かえって乾燥やかゆみを引き起こしたり、失われた皮脂を補おうと過剰に皮脂を分泌したりする場合があります。
シャンプーは基本的には1日1回、夜に行うのが理想です。日中の汗が気になるときは、水やお湯で軽く洗い流す程度にしましょう。
「自然乾燥が髪に優しい」という誤解
ドライヤーの熱は髪を傷めるというイメージから、夏は自然乾燥で済ませる方も多いようです。
しかし、髪が濡れたままの状態はキューティクルが開いており、非常にデリケートで傷つきやすい状態です。また、湿った頭皮は雑菌が繁殖しやすい環境を作り出し、臭いやかゆみ、フケの原因となります。
洗髪後はまず吸水性の高いタオルで優しく水分を拭き取り、その後すぐにドライヤーで乾かすことが重要です。
頭皮から20cmほど離し、同じ場所に熱が集中しないようにドライヤーを動かしながら、根元から先に乾かしていきましょう。
夏のやりがちNGヘアケア
| NGケア | 理由 | 正しいケア |
|---|---|---|
| 1日複数回のシャンプー | 必要な皮脂まで奪い、頭皮の乾燥や皮脂の過剰分泌を招く | シャンプーは1日1回。夜に丁寧に行う |
| 自然乾燥 | 雑菌の繁殖を促し、キューティクルが開いたままになり傷みやすい | タオルドライ後、すぐにドライヤーで根元から乾かす |
| 強い力でのブラッシング | 頭皮を傷つけ、切れ毛や抜け毛の原因になる | 毛先から優しくとかし、クッション性のあるブラシを選ぶ |
「夏はトリートメント不要」は本当か
「夏はべたつくから」という理由で、トリートメントやコンディショナーを省略している方も見受けられます。これは大きな間違いです。
紫外線や海水、プールの塩素などで、夏の髪は一年で最もダメージを受けています。
トリートメントには、髪の内部に栄養を補給し、ダメージを補修する役割があります。コンディショナーは、髪の表面をコーティングし、キューティクルを整えて外部刺激から守る役割をします。
べたつきが気になるときは毛先を中心に塗布し、頭皮には直接つけないように工夫しましょう。夏こそ、丁寧なダメージケアが必要です。
良かれと思ってやっているNGヘアアレンジ
暑い夏は、髪をすっきりとまとめたくなります。しかし、毎日同じ場所で髪をきつく結ぶポニーテールやお団子ヘアは、特定の毛根に継続的に負担をかけ「牽引性脱毛症」を引き起こす原因となります。
髪が濡れたままの状態で強く結ぶのは、髪へのダメージがとくに大きいため、絶対に避けてください。
ヘアアレンジを楽しむ際は分け目や結ぶ位置を日によって変えたり、シュシュや緩めのヘアゴムを使ったりするなど、頭皮への負担を軽減する工夫をしましょう。
自宅でできる夏の頭皮マッサージ

夏の厳しい環境で凝り固まった頭皮をほぐし、血行を促進するためには、頭皮マッサージが有効です。
特別な道具は必要なく、毎日の習慣に手軽に取り入れられます。リラックス効果も期待できるため、心身の疲れが出やすい夏にこそ試してほしいケアです。
頭皮マッサージが血行促進に繋がる理由
頭頂部には筋肉がなく、自力で動かすことができません。そのため、血行が滞りやすい部位です。
マッサージによって外部から物理的な刺激を与えると、硬くなった頭皮を柔らかくして毛細血管の血流を促せます。
血流が改善されると髪の成長に必要な栄養素が毛根の隅々まで行き渡るようになり、抜け毛の予防や健康な髪の育成に繋がります。
冷房による冷えやストレスで血行不良になりがちな夏には、意識的なマッサージが重要です。
頭皮マッサージの効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 血行促進 | 頭皮の血管を刺激し、毛根への栄養供給をサポートする |
| リラックス効果 | 頭部の筋肉の緊張をほぐし、自律神経のバランスを整える |
| リフトアップ効果 | 頭皮と顔の皮膚は繋がっているため、顔のたるみ予防にも繋がる |
リラックス効果も高めるマッサージのタイミング
頭皮マッサージを行うのに最も適した時間は、体が温まりリラックスしているバスタイムです。シャンプーの際に、泡で滑りを良くしながら行うと頭皮への摩擦を減らせます。
また、就寝前に行うのもおすすめです。1日の終わりに頭皮の緊張をほぐすことで、心身がリラックスモードに切り替わり、睡眠の質を高める効果も期待できます。
テレビを見ながらなど、「ながら時間」を活用するのも習慣化するコツです。
- 爪を立てない
- 強い力でこすらない
- 1回5分程度を目安にする
簡単なマッサージ方法の紹介
指の腹を使って、気持ち良いと感じる程度の圧で行いましょう。
まず、両手の指の腹で、こめかみから頭頂部に向かって円を描くようにゆっくりと揉みほぐします。次に、耳の上あたりから頭頂部へ、同様に引き上げるようにマッサージします。
最後に、後頭部の首の付け根あたり(盆の窪)を親指で優しく指圧します。
頭全体がじんわりと温かくなるのを感じられたら、血行が良くなっているサインです。
正しいシャンプー方法で夏の頭皮トラブルを防ぐ

夏の頭皮ケアの基本は、毎日のシャンプーです。しかし、ただ洗うだけでは不十分です。
汗や皮脂、スタイリング剤などの汚れをきちんと落としつつ、頭皮に必要な潤いを奪わない洗い方が必要となります。シャンプーの選び方から洗い方まで、一連の流れを見直してみましょう。
夏のシャンプー選びのポイント
夏の頭皮は紫外線や汗でダメージを受け、敏感に傾きがちです。洗浄力が強すぎるシャンプーは必要な皮脂まで奪い、バリア機能の低下を招く可能性があります。
おすすめは、アミノ酸系の洗浄成分を主とした、マイルドな洗い上がりのシャンプーです。
頭皮の炎症を抑える成分(グリチルリチン酸2Kなど)や、保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が配合されているものを選ぶと、より効果的です。
清涼感を謳うメントール系のシャンプーは使い心地は良いですが、刺激に感じる方もいるため、肌質に合わせて選びましょう。
シャンプーの洗浄成分タイプ別特徴
| タイプ | 特徴 | こんな方におすすめ |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | 洗浄力がマイルドで、頭皮への刺激が少ない | 乾燥肌、敏感肌、ダメージが気になる方 |
| 高級アルコール系 | 洗浄力が高く、泡立ちが良い。市販品に多い | 皮脂が多い方、さっぱりした洗い上がりが好きな方 |
| 石けん系 | 洗浄力は高いが、アルカリ性で髪がきしみやすい | 頭皮のべたつきが非常に強い方(要リンス) |
予洗いとすすぎの重要性
シャンプーの効果を最大限に引き出すには、洗う前の「予洗い」が非常に重要です。
シャンプー剤をつける前に、38度前後のぬるま湯で1〜2分かけて頭皮と髪をしっかりと濡らします。これだけで、髪についたホコリや余分な皮脂などの汚れの7割程度は落ちると言われています。
予洗いを丁寧に行うとシャンプーの泡立ちが良くなり、少ない量でも効率的に洗えます。
同様に、シャンプー後の「すすぎ」も大切です。洗浄成分が頭皮に残ると、かゆみやフケの原因になります。
泡が完全になくなってからさらに1〜2分、髪の根元や生え際にシャワーを当てて、念入りにすすぎましょう。
頭皮を傷つけない洗い方の手順
シャンプーは直接頭皮につけず、一度手のひらでよく泡立ててから髪全体になじませます。
洗う際は爪を立てずに指の腹を使います。耳の上、襟足、生え際から頭頂部に向かって、頭皮を優しく動かすようにマッサージしながら洗いましょう。
皮脂の分泌が多い頭頂部や、汗をかきやすい生え際はとくに丁寧に洗うように意識してください。
髪の毛自体は泡を行き渡らせるだけで汚れは十分に落ちますので、ゴシゴシとこすり合わせる必要はありません。
生活習慣の見直しで内側から抜け毛を予防
ヘアケアや食事だけでなく、日々の生活習慣も髪の健康に深く関わっています。睡眠や運動、ストレス管理は、健やかな髪を育むための土台となる要素です。
夏は生活リズムが乱れやすい季節だからこそ、意識的に生活習慣を整えていきましょう。
質の良い睡眠が髪を育てる
髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。
入眠後最初の深い眠り(ノンレム睡眠)の時間帯に最も多く分泌されるため、単に長く眠るだけでなく、「睡眠の質」を高める工夫が重要です。
寝苦しい夏の夜は寝室の温度や湿度を快適に保ち、就寝前はスマートフォンやパソコンの画面を見るのを避けるなど、リラックスして入眠できる環境を整えましょう。
睡眠の質を高めるためのポイント
| 項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 就寝環境 | 室温26〜28℃、湿度50〜60%を目安にエアコンや除湿器を活用する |
| 入浴 | 就寝の90分前に38〜40℃のぬるめのお湯に浸かる |
| 食事・飲酒 | 就寝3時間前までに夕食を済ませ、就寝前のアルコールは控える |
夏の運動習慣と頭皮の健康
適度な運動は全身の血行を促進し、頭皮への栄養供給をスムーズにします。また、心地よい疲労感は質の良い睡眠にも繋がります。
ただし、夏の炎天下での激しい運動は、熱中症のリスクや紫外線によるダメージを高めるため避けるべきです。
比較的涼しい早朝や夕方以降に、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を30分程度行うのがおすすめです。室内でできるストレッチやヨガも、血行促進やリラックスに効果的です。
- ウォーキング
- ヨガ・ストレッチ
- 水中ウォーキング
ストレスと抜け毛の深い関係
精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。これにより頭皮環境が悪化し、抜け毛が増える場合があります(円形脱毛症など)。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにも繋がり、女性の薄毛に影響を与えやすいです。
暑さによるイライラや夏休みのイベント疲れなど、夏は知らず知らずのうちにストレスが溜まりやすい季節ですので、自分なりのリラックス方法を見つけて上手にストレスを発散させると良いです。
趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したり、ゆっくりと音楽を聴いたりする時間を大切にしましょう。
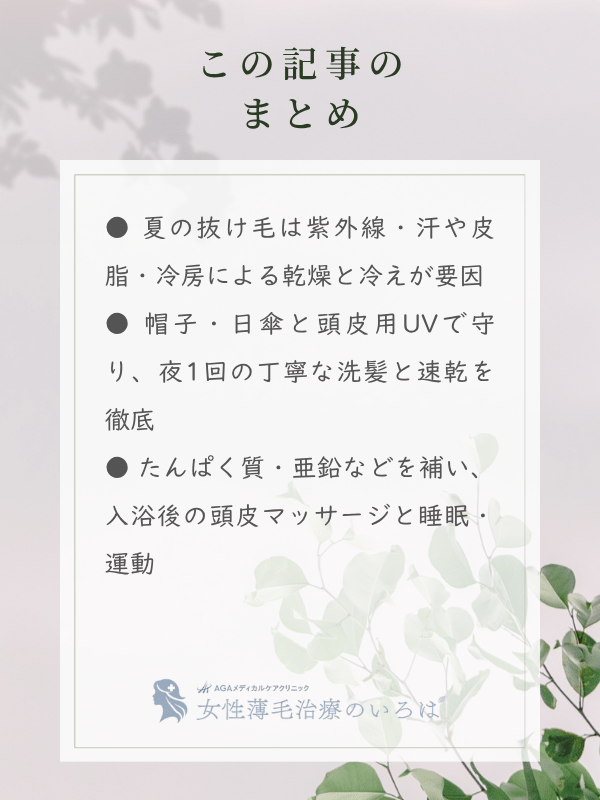
夏の抜け毛に関するよくある質問
さいごに、夏の抜け毛に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 秋になると抜け毛は落ち着きますか?
-
一般的に、夏の間に受けたダメージが表面化し、秋に抜け毛が増える傾向があります。「秋は抜け毛の季節」と言われるのはこのためです。
夏に蓄積された紫外線ダメージや夏バテによる栄養不足の影響が、1〜2ヶ月遅れて現れるのです。
そのため、夏のうちからしっかり対策を行っておくことが、秋の抜け毛を最小限に抑える鍵となります。
もし、季節が変わっても抜け毛が減らない、あるいは増加し続ける場合は、他の原因が隠れている可能性も考えられます。
- プールや海の塩素・塩水は髪に悪いですか?
-
影響があります。プールの水に含まれる塩素は、髪の表面を覆うキューティクルを傷つけ、タンパク質を破壊してしまいます。これにより髪のパサつきや切れ毛、色落ちの原因となります。
また、海水の塩分は乾くと結晶化し、髪の水分を奪って乾燥を招きます。
プールや海に入った後はできるだけ早くシャワーで真水を浴び、髪と頭皮を十分に洗い流すことが大切です。その後は、トリートメントでしっかりと保湿ケアを行いましょう。
- どのくらい抜けたら危険信号ですか?
-
健康な人でも、1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜けています。これはヘアサイクル(毛周期)による正常な現象です。
しかし、明らかに以前より抜け毛が増えたと感じる場合、例えばシャンプー時の排水溝に詰まる髪の量が倍になったり、枕に付着する髪の毛が目立ったりするようであれば注意が必要です。
1日に150本以上抜ける状態が続く場合は、何らかの脱毛症が進行している可能性があります。
- 対策をしても改善しない場合はどうすれば良いですか?
-
セルフケアを2〜3ヶ月続けても抜け毛の量が減らない、あるいは頭皮のかゆみや赤み、薄毛が進行しているように感じる場合は自己判断で対処を続けるのではなく、一度専門のクリニックに相談することをおすすめします。
女性の薄毛の原因は多岐にわたり、中にはFAGA(女性男性型脱毛症)や他の疾患が隠れている場合もあります。
専門医による正確な診断のもと、ご自身の状態に合った適切な治療やアドバイスを受けるのが、健やかな髪を取り戻すための最も確実な方法です。
参考文献
KUNZ, Michael; SEIFERT, Burkhardt; TRÜEB, Ralph M. Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss. Dermatology, 2009, 219.2: 105-110.
HSIANG, E. Y., et al. Seasonality of hair loss: a time series analysis of Google Trends data 2004–2016. British Journal of Dermatology, 2018, 178.4: 978-979.
GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.
RANDALL, VALERIE A.; EBLING, F. J. G. Seasonal changes in human hair growth. British Journal of Dermatology, 1991, 124.2: 146-151.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
COURTOIS, M., et al. Periodicity in the growth and shedding of hair. British Journal of Dermatology, 1996, 134.1: 47-54.
RANDALL, Valerie Anne. Hormonal regulation of hair follicles exhibits a biological paradox. In: Seminars in Cell & Developmental Biology. Academic Press, 2007. p. 274-285.
RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 2008, 21.5: 314-328.