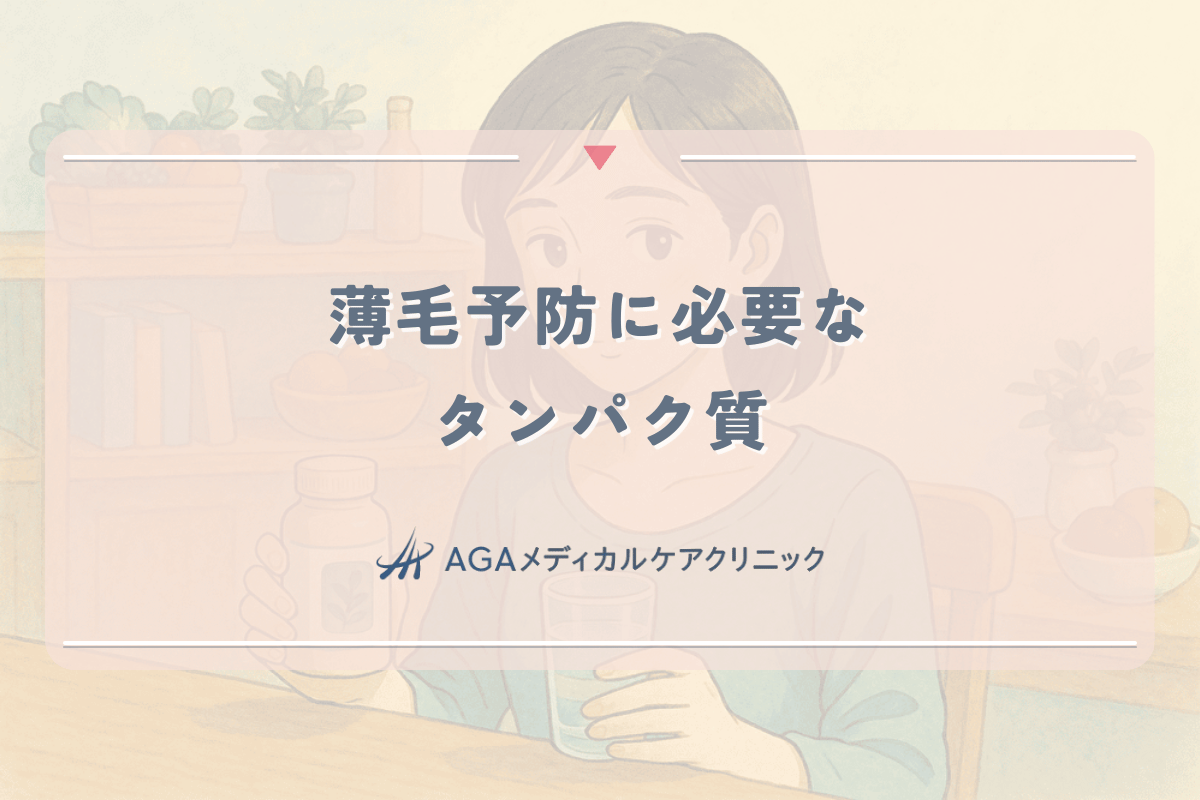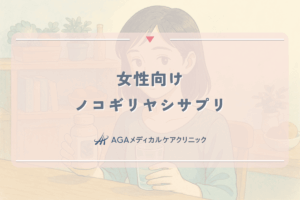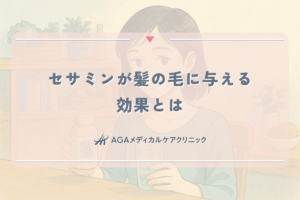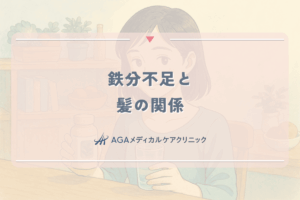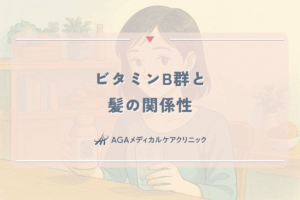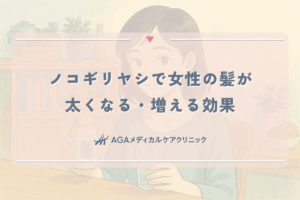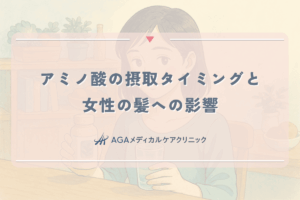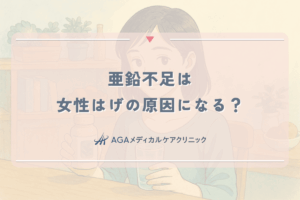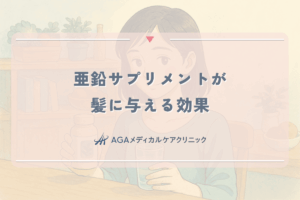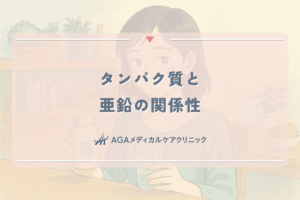女性の薄毛の悩みは多くの場合、生活習慣や栄養状態と深く関わっています。
なかでも、私たちの体を作る基本の栄養素である「タンパク質」は、髪の健康を維持するために非常に重要です。
この記事では、なぜタンパク質が女性の髪に必要なのか、ご自身の体格や活動量に合わせた適切な摂取量、そして日々の食事で無理なくタンパク質を補うための具体的な方法を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
女性の薄毛にタンパク質が重要な理由
髪の健康を語る上で、タンパク質の存在は欠かせません。毎日の食事で何気なく摂取しているタンパク質が、実は髪の毛そのものを作り、その成長を支える土台となっています。
タンパク質が不足すると、体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を送るため、髪への供給は後回しにされます。これが髪質の低下や薄毛につながるのです。
髪の主成分はケラチンというタンパク質
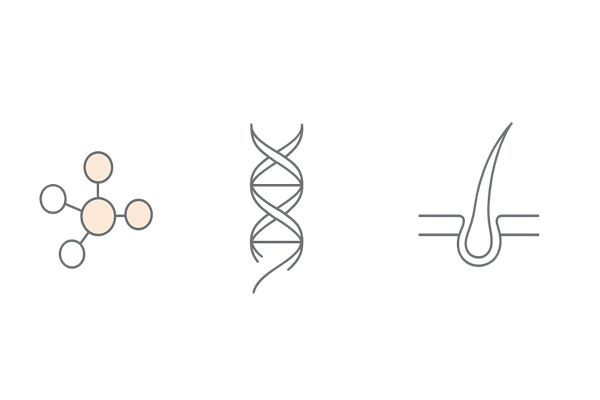
私たちの髪の毛は、その約90%が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。ケラチンは18種類のアミノ酸が結合してできており、丈夫でしなやかな髪を作る源です。
つまり、食事から摂取するタンパク質が不足するとケラチンの生成が滞り、新しく生えてくる髪が細くなったり、弱くなったりする原因となります。
美しい髪を育むためには、その材料となるタンパク質を十分に体に供給するのが基本です。
タンパク質不足が引き起こす髪への影響
タンパク質が不足した状態が続くと体は髪の成長を一時的に止め、栄養を節約しようとします。
この結果、成長期にある毛髪が休止期へと移行しやすくなり、抜け毛が増える一因となります。
また、髪のツヤやハリ、コシが失われ、全体的に元気がなく見えるようになります。切れ毛や枝毛が増えるのも、タンパク質不足による髪の強度の低下が考えられます。
これらのサインは、体が栄養不足を訴えている証拠とも言えるでしょう。
ホルモンバランスとタンパク質の関係
女性の体は、月経や妊娠、更年期など、ライフステージの変化に伴いホルモンバランスが大きく変動します。
女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、髪の成長を促進し、その寿命を延ばす働きがあります。
タンパク質はホルモンの生成や調節にも関与しており、栄養バランスの取れた食事は、ホルモンバランスを整える上でも大切です。
タンパク質が不足するとホルモンバランスが乱れやすくなり、間接的に薄毛に影響を与える可能性も指摘されています。
あなたに本当に必要なタンパク質の摂取量
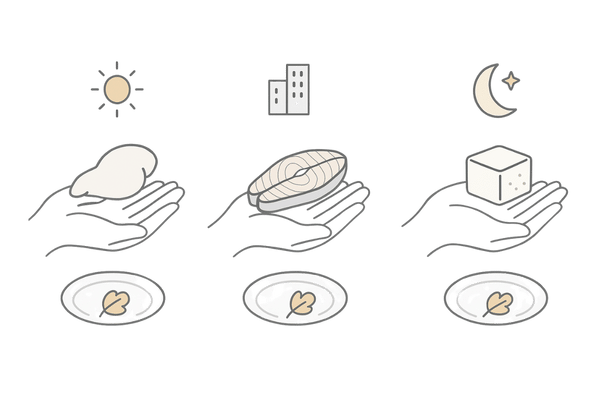
タンパク質が重要であると分かったところで、「具体的にどれくらい摂れば良いのか」という疑問が湧くかもしれません。
必要なタンパク質量は、個人の体重や年齢、日々の活動レベルによって異なります。
体重から計算する基本的な摂取目安
一般的に、健康な成人女性に推奨されるタンパク質の摂取量は、体重1kgあたり1.0gです。
例えば、体重50kgの女性であれば、1日に50gのタンパク質を摂取するのが一つの目安となります。
ただ、これはあくまで基本的な数値であり、個々の状況に応じて調整が必要です。
体重別のタンパク質摂取目安量
| 体重 | 1日のタンパク質摂取目安量 | 食品での目安例 |
|---|---|---|
| 45kg | 45g | 鶏むね肉100g + 卵1個 + 納豆1パック |
| 55kg | 55g | 鮭1切れ + 豆腐半丁 + 牛乳200ml |
| 65kg | 65g | 豚ロース100g + 卵2個 + ヨーグルト1個 |
年齢や活動量で変わる必要量
タンパク質の必要量は、年齢によっても変化します。特に、筋肉量が減少しやすい高齢期には、意識して多めに摂ることが推奨される場合があります。
また、日常的に運動をする習慣がある方は、筋肉の修復と成長のためにより多くのタンパク質を必要とします。
デスクワーク中心の方と、定期的にジムでトレーニングをする方とでは、必要量が1.2倍から1.5倍ほど異なるケースもあります。
ご自身の生活スタイルを振り返り、摂取量を調整すると良いです。
摂取量の上限と過剰摂取のリスク
タンパク質は重要ですが、摂りすぎも体に負担をかける可能性があります。過剰に摂取したタンパク質は、分解される過程で腎臓に負担をかける場合があります。
また、動物性タンパク質に偏ると、脂質の摂取量も増え、カロリーオーバーにつながるケースもあります。
特別な運動をしていない方は、体重1kgあたり2.0gを超えるような極端な摂取を続けるのは避け、バランスを重視しましょう。
食事でタンパク質を効率よく摂るための基本
必要なタンパク質量を確認したら、次は日々の食事にどう取り入れるかが課題です。
タンパク質は様々な食品に含まれていますが、その種類や組み合わせ方によって、体内での利用効率が変わってきます。効率的な摂取方法をチェックして、賢く食事を組み立てましょう。
動物性タンパク質と植物性タンパク質の違い

タンパク質は、肉や魚、卵などに含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品や穀物に含まれる「植物性タンパク質」に大別されます。
動物性タンパク質は、体内で合成できない必須アミノ酸をバランス良く含んでいるため、吸収効率が良いという特徴があります。
一方、植物性タンパク質は、低脂質で食物繊維やビタミン、ミネラルも同時に摂取できる点が利点です。
動物性・植物性タンパク質の特徴
| 種類 | 主な食品 | 特徴 |
|---|---|---|
| 動物性タンパク質 | 肉、魚、卵、乳製品 | 必須アミノ酸バランスが良く、吸収効率が高い。 |
| 植物性タンパク質 | 大豆製品、豆類、穀物 | 低脂質で、食物繊維なども一緒に摂取できる。 |
これらのタンパク質は、どちらか一方に偏るのではなく、両方をバランス良く食事に取り入れるのが理想です。
例えば、朝はヨーグルト(動物性)、昼は鶏肉(動物性)、夜は豆腐(植物性)といったように、多様な食品から摂取するように心がけましょう。
バランスの良い食事の組み立て方
タンパク質を意識するあまり、他の栄養素がおろそかになっては意味がありません。
主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル)をそろえる「一汁三菜」の考え方は、栄養バランスを整える上で非常に有効です。
毎食、手のひらサイズのタンパク質源を主菜として取り入れるのを目標にしてみましょう。
タンパク質の吸収を高める栄養素
摂取したタンパク質を効率よく体内で利用するためには、助けとなる栄養素を一緒に摂ることが重要です。
特にビタミンB6は、タンパク質の分解や合成を助ける働きがあります。また、ビタミンCは、髪のケラチンを構成するアミノ酸の生成をサポートします。
タンパク質の吸収を助ける栄養素
| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | アミノ酸の代謝を助ける | にんにく、マグロ、鶏肉、バナナ |
| ビタミンC | コラーゲンの生成を助ける | パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ |
薄毛が気になる女性におすすめのタンパク質源
髪の健康を考えるなら、タンパク質の種類にもこだわりたいところです。
同じタンパク質源でも、脂質の量や含まれる他の栄養素は異なります。髪に良い影響を与える、良質なタンパク質を積極的に選びましょう。
美髪に導く高タンパク質・低脂質な食材
髪のためには、良質なタンパク質を摂りつつ、頭皮の血行を妨げる可能性のある過剰な脂質は避けたいものです。
鶏のささみや胸肉(皮なし)、赤身の魚や卵、豆腐や納豆などの大豆製品は、高タンパク質でありながら脂質が比較的少ないため、積極的に取り入れたい食材です。
高タンパク質・低脂質な食材例
| 食材(100gあたり) | タンパク質量(約) | 特徴 |
|---|---|---|
| 鶏ささみ | 23g | 非常に低脂質で、ダイエット中にも適している。 |
| 鮭 | 22g | アスタキサンチンやDHA・EPAも豊富。 |
| 豆腐(木綿) | 7g | イソフラボンを含み、植物性タンパク質の代表。 |
コンビニや外食で賢くタンパク質を補う方法
忙しい毎日の中で、自炊が難しい日もあるでしょう。コンビニエンスストアや外食を利用する際も、少しの工夫でタンパク質を補うことが可能です。
サラダチキンやゆで卵、ギリシャヨーグルト、豆乳などは手軽にタンパク質をプラスできる便利なアイテムです。
定食を選ぶ際は、焼き魚や生姜焼きなど、タンパク質が主役のメニューを選ぶと良いでしょう。丼ものや麺類単品で済ませず、小鉢で冷奴や卵料理を追加するのも賢い方法です。
調理法で変わる栄養吸収率
同じ食材でも、調理法によって栄養の吸収率は変わります。
例えば、肉や魚は「煮る」「蒸す」といった調理法を選ぶと余分な脂を落としつつ、タンパク質を効率よく摂取できます。
揚げる、炒めるといった油を多く使う調理法は、カロリーや脂質の過剰摂取につながりやすいので、頻度を考えることが大切です。
また、タンパク質は加熱すると消化しやすくなるという側面もあります。
プロテインは薄毛対策に有効?正しい知識と選び方
食事だけで十分なタンパク質を摂るのが難しいと感じる方にとって、「プロテイン」は便利な選択肢の一つです。
しかし、プロテインと聞くと「筋肉増強のため」というイメージが強く、女性や薄毛対策には縁遠いと感じるかもしれません。
ここでは、女性の薄毛対策におけるプロテインの役割と、正しい選び方について解説します。
プロテインの種類と特徴(ホエイ、カゼイン、ソイ)
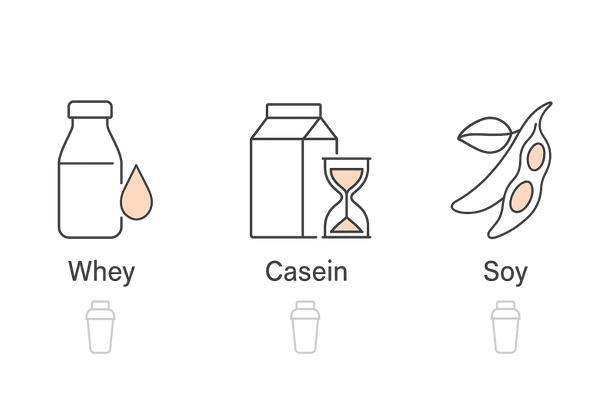
プロテインにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。自分の目的や体質に合わせて選びましょう。
プロテインの種類と特徴
| 種類 | 原料 | 特徴 |
|---|---|---|
| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収が速く、運動後の栄養補給に向いている。 |
| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収がゆっくりで、満腹感が持続しやすい。 |
| ソイプロテイン | 大豆 | 植物性。イソフラボンを含み、女性におすすめ。 |
薄毛が気になる女性向けのプロテインの選び方
女性が髪の健康を目的としてプロテインを選ぶ場合、特に「ソイプロテイン」がおすすめです。
ソイプロテインの原料である大豆に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることが知られており、ホルモンバランスのサポートが期待できます。
また、髪の健康に必要なビタミンやミネラル(鉄分、亜鉛など)が添加されている製品を選ぶと、より効率的に栄養を補給できます。
プロテインを飲むタイミングと注意点
プロテインはあくまで食事の補助として考え、3食の食事を基本とするのが大切です。
飲むタイミングとしては、タンパク質が不足しがちな朝食時や、小腹が空いた間食として取り入れるのが良いでしょう。
ただし、プロテインにもカロリーがあります。食事にプラスする形で無計画に飲むと、カロリーオーバーになる可能性もあるため、1日の総摂取カロリーを考慮しながら活用しましょう。
製品に記載されている推奨量を守るのも重要です。
食事制限ダイエットによる髪へのサイン
「美しくなりたい」という思いから始める食事制限ダイエットは、その方法が間違っていると、体重は落ちても髪のツヤやボリュームが失われるという、悲しい結果を招く場合があります。
特に女性は、無理なダイエットが薄毛の引き金になるケースが少なくありません。ご自身の経験と照らし合わせながら、髪からの危険なサインを見逃さないようにしましょう。
カロリー不足が招くタンパク質欠乏
極端に食事量を減らすダイエットは、総摂取カロリーの不足に直結します。体がエネルギー不足に陥ると、筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとします。
この時、食事から摂取した貴重なタンパク質もエネルギー源として使われてしまい、本来の目的である髪や肌、爪などを作るための材料が不足してしまいます。
結果として、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりするのです。
特定の栄養素だけを抜く食事の危険性
「糖質制限」や「脂質制限」など、特定の栄養素を極端にカットするダイエットも注意が必要です。
例えば、炭水化物(糖質)を完全に抜くと、体はタンパク質を分解してエネルギーを得ようとします。
また、良質な脂質は細胞膜の材料であり、ホルモンの生成にも関わるため、不足すると頭皮の乾燥やホルモンバランスの乱れにつながる可能性があります。
- リンゴだけダイエット
- 炭水化物抜きダイエット
- 過度なファスティング(断食)
上記のような偏った食事法は、一時的に体重が減っても、髪の健康を著しく損なうリスクをはらんでいます。
「髪も栄養失調になる」という事実
体と同様に、髪も栄養がなければ健やかに育ちません。
無理なダイエットによって栄養が不足すると、体は生命維持に直接関係のない髪への栄養供給を真っ先に止めます。これが「髪の栄養失調」状態です。
髪がパサつく、ツヤがなくなる、切れやすくなる、抜け毛が増えるといった症状は、まさに髪が栄養を求めている悲鳴です。
このサインに気づかずにダイエットを続けると、薄毛が進行してしまう可能性があります。
美しく痩せながら髪を守る食事法
健康的に痩せ、かつ美しい髪を維持するためには、「抜く」のではなく「選ぶ」意識が大切です。
摂取カロリーを消費カロリーより少し低く設定しつつ、タンパク質やビタミン、ミネラルをしっかり確保します。
白米を玄米に変える、脂身の多い肉を赤身肉や魚に変える、間食をスナック菓子からナッツやヨーグルトに変えるなど、質を高める工夫をしましょう。
急激な体重減少は体に大きな負担をかけるため、1ヶ月に体重の5%以内の減少を目標に、長期的な視点で取り組むと良いです。これにより体も髪も健康な状態を保ちながら、理想の体型を目指せます。
タンパク質だけじゃない!髪の健康を支える他の栄養素
健康な髪を育むためには、タンパク質が土台となることは間違いありません。しかし、その土台の上でしっかりと髪を育てるには、他の栄養素のサポートも必要です。
なかでも亜鉛や鉄分、ビタミンB群は、タンパク質と協力して美しい髪を作るために重要な役割を果たします。
亜鉛の役割と多く含む食品
亜鉛は、タンパク質(ケラチン)を髪の毛に合成する際に必要不可欠なミネラルです。
亜鉛が不足すると、せっかく摂取したタンパク質をうまく髪に作り変えられず、髪の成長が滞ったり抜け毛が増えたりする原因になります。
また、亜鉛は新しい細胞を作り出す働きも担っているため、頭皮の健康維持にも関わっています。
亜鉛を多く含む食品
| 食品 | 特徴 | 摂取のポイント |
|---|---|---|
| 牡蠣 | 亜鉛の含有量が非常に多い。 | 生でも加熱しても良い。 |
| 豚レバー | 鉄分も豊富。 | レバニラ炒めなどがおすすめ。 |
| 牛肉(赤身) | タンパク質も同時に摂れる。 | ステーキやローストビーフで。 |
鉄分不足と女性の薄毛の関係
鉄分は、血液中のヘモグロビンの成分となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。頭皮も例外ではなく、毛母細胞が活発に細胞分裂を行うためには十分な酸素が必要です。
鉄分が不足して貧血状態になると、頭皮に届く酸素の量が減少し、毛母細胞の働きが低下してしまいます。これが髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする一因となります。
特に女性は月経により鉄分を失いやすいため、意識的な摂取が大切です。
鉄分を多く含む食品
| 食品 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| レバー、赤身肉 | ヘム鉄 | 吸収率が高い。 |
| ほうれん草、小松菜 | 非ヘム鉄 | ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ。 |
| あさり、しじみ | ヘム鉄 | 味噌汁や酒蒸しなどで。 |
ビタミンB群と頭皮環境
ビタミンB群は、エネルギー代謝を助け、皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあります。
中でもビタミンB2は皮脂の分泌をコントロールし、頭皮のベタつきやフケを防ぎます。ビタミンB6はタンパク質の代謝を助けるだけでなく、皮脂の過剰分泌を抑える働きもあります。
これらのビタミンB群が不足すると頭皮環境が悪化し、健康な髪が育ちにくい状態になってしまいます。
食生活を見直すための具体的な献立例
理論はわかっても、毎日の献立に落とし込むのは難しいと感じるかもしれません。
ここでは、タンパク質やその他の重要な栄養素をバランス良く摂取できる、1日の献立例を紹介します。
朝食で摂りたいタンパク質メニュー
一日の始まりである朝食は、睡眠中に消費されたエネルギーとタンパク質を補給する重要な機会です。
時間がない朝でも、手軽にタンパク質を摂る工夫をしましょう。
和食ならご飯と味噌汁に納豆や焼き魚をプラス、洋食なら全粒粉パンに卵料理とヨーグルトを添えるのがおすすめです。
昼食で意識したいバランス
昼食は外食やコンビニで済ませる方も多いでしょう。単品メニューは避け、主食・主菜・副菜がそろう定食スタイルを選ぶのが理想です。
麺類や丼ものを選ぶ場合はゆで卵やサラダ、おひたしなどのサイドメニューを追加して、タンパク質と野菜を補いましょう。この一手間が、午後の活力と髪の健康につながります。
夕食で髪を育てる一工夫
夕食は、一日の栄養バランスを調整する時間です。日中に不足した栄養素を補うように意識しましょう。
髪の成長は夜間に行われるため、就寝前に髪の材料となるタンパク質や亜鉛、ビタミンなどをしっかり摂っておくことが大切です。
鶏肉と野菜の蒸し料理や、豆腐とキノコのあんかけなど、消化が良く栄養価の高いメニューが適しています。
髪を育てる1日の献立例
| 食事 | メニュー例 | ポイント |
|---|---|---|
| 朝食 | 玄米ご飯、わかめと豆腐の味噌汁、鮭の塩焼き、ほうれん草のおひたし | 魚と大豆からタンパク質を摂取。 |
| 昼食 | 鶏そぼろ弁当(鶏そぼろ、炒り卵、ブロッコリー)、ミニサラダ | 鶏肉と卵でタンパク質を確保。緑黄色野菜もプラス。 |
| 夕食 | 豚肉とパプリカの生姜焼き、ひじきの煮物、あさりのすまし汁 | 豚肉(ビタミンB群)、パプリカ(ビタミンC)、あさり(鉄分)をバランス良く。 |
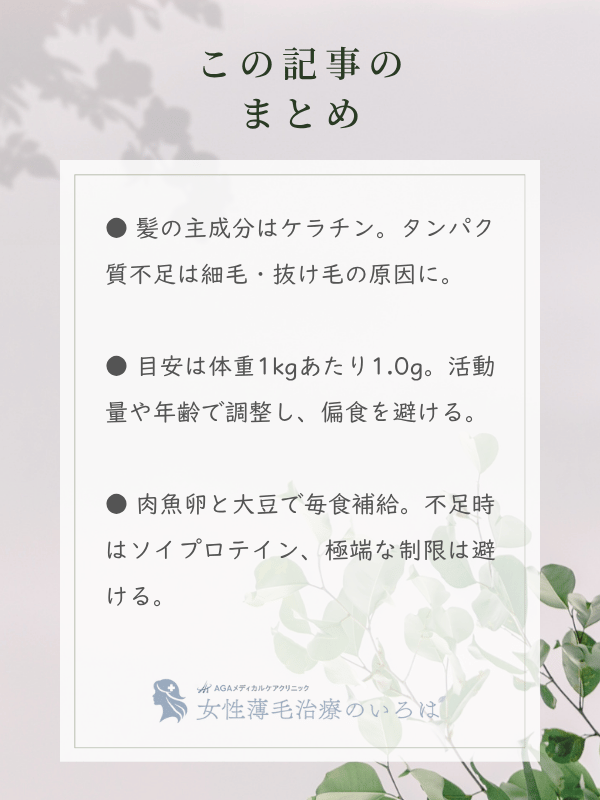
よくある質問
さいごに、タンパク質の摂取や薄毛対策に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- プロテインを飲むと太りませんか?
-
プロテイン自体が直接太る原因になるわけではありません。太るかどうかは、1日の総摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。
食事内容を見直さずにプロテインを追加すれば、その分カロリーオーバーになり、体重増加につながる可能性があります。
食事の一部をプロテインに置き換えたり、間食をプロテインに変えたりするなど、1日の総カロリーを管理しながら上手に活用すれば太る心配は少ないでしょう。
- 髪に良いと思って毎日同じものばかり食べています。
-
特定の食品が髪に良いからといって、そればかりを食べるのはおすすめできません。栄養はチームで働くため、様々な食品から多様な栄養素をバランス良く摂ることが重要です。
例えば、タンパク質を摂るにしても、肉や魚、大豆製品を日替わりで取り入れると、それぞれに含まれる異なる種類のビタミンやミネラルも摂取できます。
この多様性が体全体の健康、そして髪の健康につながります。
- 効果はどれくらいで現れますか?
-
食生活の改善による髪への効果は、すぐには現れません。
髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、食事改善の効果が新しい髪に反映され、それを実感できるようになるまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の時間が必要です。
髪にはヘアサイクル(毛周期)があるため、すぐに結果が出なくても諦めずに、まずは健康な髪が育つ土台となる頭皮環境を整える気持ちで気長に続けていきましょう。
- サプリメントだけでタンパク質を補っても良いですか?
-
サプリメントはあくまで栄養補助食品であり、食事の代わりにはなりません。
食事からはタンパク質以外にも、ビタミンやミネラル、食物繊維など、私たちが健康を維持するために必要な様々な栄養素を複合的に摂取できます。
これらの栄養素が互いに協力し合って働くため、まずはバランスの取れた食事を基本とし、それでも不足する分をサプリメントで補うという考え方が正しいです。
タンパク質も、できる限り食品から摂ることを優先しましょう。
参考文献
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.
GARG, Suruchi; SANGWAN, Ankita. Dietary protein deficit and deregulated autophagy: a new clinico-diagnostic perspective in pathogenesis of early aging, skin, and hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2019, 10.2: 115-124.
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.