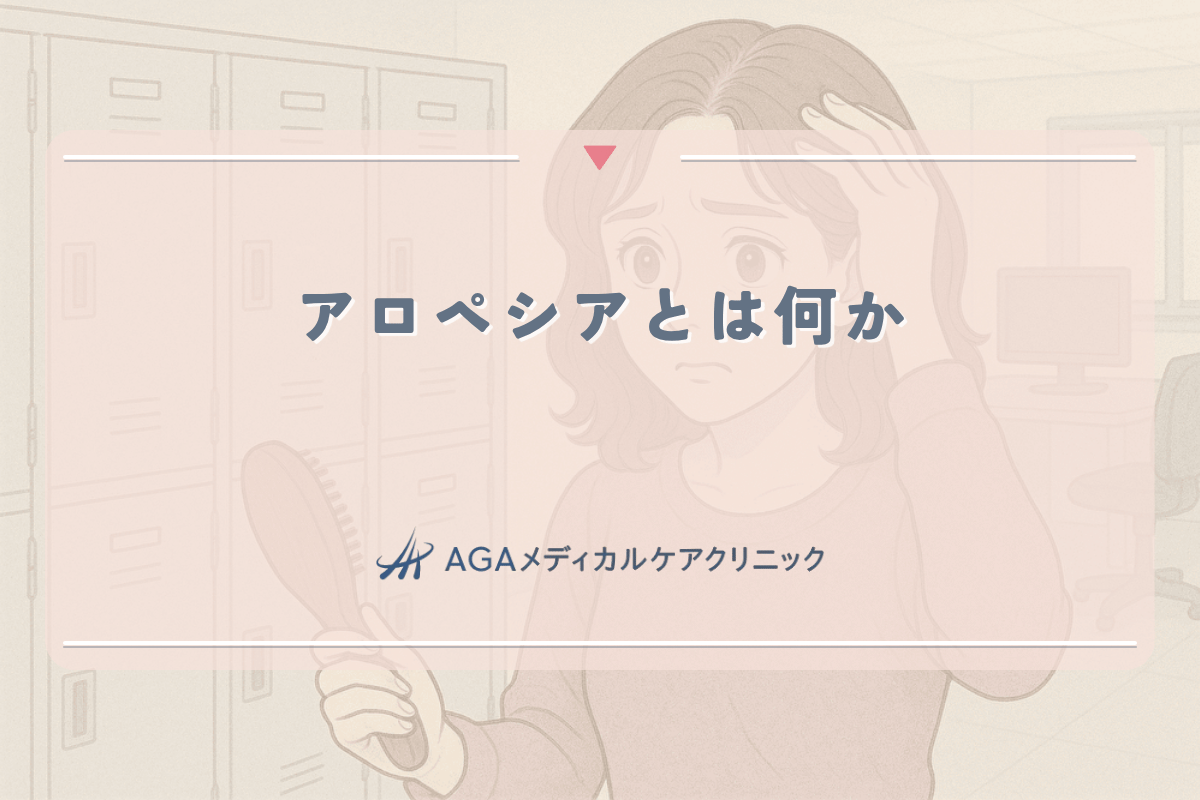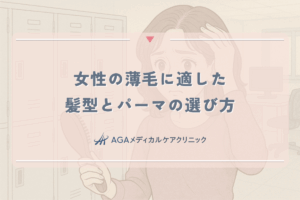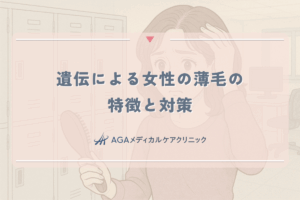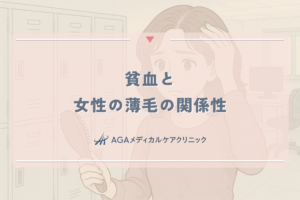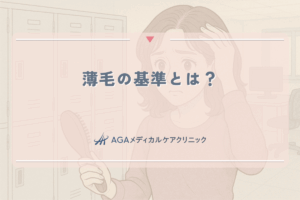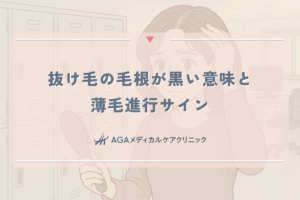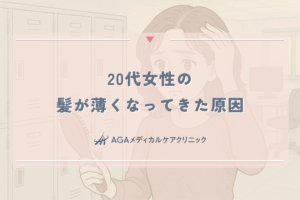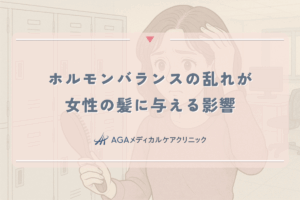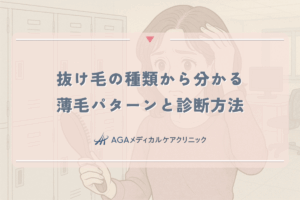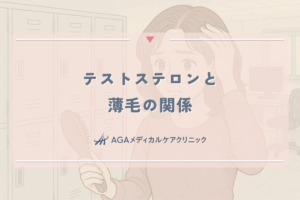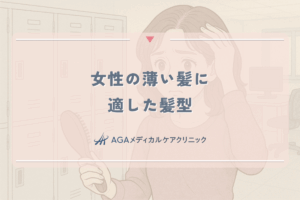「アロペシア」という言葉を耳にして、不安を感じる方もいるようです。この言葉は単に「脱毛症」を指す医学用語であり、特別な病名ではありません。
女性の薄毛の悩みは非常にデリケートであり、正しい知識を持つことが、不安を和らげてご自身に適したケアを見つける第一歩です。
この記事では、アロペシアとは何か、その種類や原因、そして女性特有の症状について、専門的な観点から分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
アロペシアとは?脱毛症を意味する言葉
クリニックで「アロペシアの可能性があります」と告げられたら、多くの方が驚き、深刻に受け止めるかもしれません。
しかし、アロペシアは何か恐ろしい特定の病気を指すものではありません。まずはこの言葉の正確な意味を知り、冷静に自分の状態と向き合いましょう。
アロペシアの基本的な定義
アロペシア(Alopecia)とは、医学の世界で「脱毛症」全般を指す言葉です。髪の毛が抜ける、あるいは薄くなるといった症状の総称として用います。
そのため、アロペシアという診断は、具体的な原因や脱毛のパターンを特定する前の広い意味での状態を示しているに過ぎません。
原因や症状によって、このアロペシアはさらに細かく分類されます。
例えば、円形に毛が抜ける場合は「円形脱毛症」、男性ホルモンの影響が考えられる場合は「男性型脱毛症」というように、具体的な診断名が付いていきます。
「脱毛症」と「薄毛」の違い
日常生活で使う「薄毛」と、医学用語の「脱毛症(アロペシア)」は、似ているようで少しニュアンスが異なります。
「薄毛」は、髪の密度が低くなった状態を指す主観的な表現です。
一方、「脱毛症」は毛髪の量が正常な範囲を超えて減少している、あるいは成長サイクルに異常が生じている状態を指す客観的な医学的判断です。
専門家は、脱毛のパターンや進行度、頭皮の状態などを総合的に評価し、脱毛症かどうかを判断します。
脱毛症と薄毛の捉え方
| 項目 | 薄毛 | 脱毛症(アロペシア) |
|---|---|---|
| 意味合い | 主観的・美容的な表現 | 客観的・医学的な状態 |
| 判断基準 | 見た目の印象、本人の感覚 | 脱毛のパターン、毛髪の密度、毛周期 |
| 対応 | セルフケア、美容的アプローチ | 医学的診断、専門的な治療 |
なぜ専門用語を知ることが大切なのか
専門用語を理解することは、ご自身の状態を正確に把握し、医師との対話を円滑に進めるために重要です。
医師の説明を正しく理解できれば、治療方針に納得して臨めます。
また、インターネットなどで情報を集める際にも正確な用語を知っていると、信頼性の高い情報を見分けやすくなります。
漠然とした不安を解消し、主体的に治療に取り組むためにも、基本的な知識は大きな助けとなります。
女性にみられるアロペシアの主な種類と特徴

女性のアロペシアは、男性とは異なる特徴を持つものが多くあります。ここでは、女性によく見られる代表的なアロペシアの種類を解説します。
びまん性脱毛症(FAGA/FPHL)
女性の薄毛で最も多いのが「びまん性脱毛症」です。これは、頭部全体で均等に髪が薄くなるのが特徴で、特定の部位だけが禿げるわけではありません。
分け目が目立つようになった、髪のボリュームが減った、地肌が透けて見える、といった症状で気づくケースが多いです。
女性男性型脱毛症(FAGA)や女性型脱毛症(FPHL)とも呼ばれ、加齢やホルモンバランスの変化が主な原因と考えられています。
円形脱毛症
円形脱毛症は、前触れなく円形や楕円形に髪が抜ける症状です。
一般的に自己免疫疾患の一種と考えられており、免疫機能が誤って自身の毛包を攻撃するために発症します。大きさは10円玉程度のものから、頭部全体に広がるものまで様々です。
ストレスが引き金になる場合もありますが、必ずしもストレスだけが原因ではありません。年齢や性別を問わず誰にでも起こる可能性があります。
牽引性脱毛症
牽引性脱毛症は、髪が長時間にわたって強く引っ張られて、毛根に負担がかかり発生する脱毛症です。
特に、毎日同じ分け目で髪を結んでいる方や、エクステンションをつけている方に見られます。
生え際や分け目部分の髪が薄くなるのが典型的な症状です。この脱毛症は、原因となる髪型をやめると改善が期待できます。
牽引性脱毛症の原因となりやすい髪型
- ポニーテール
- お団子ヘア
- 編み込み
- エクステンション
粃糠性脱毛症と脂漏性脱毛症
これらは頭皮環境の悪化が原因で起こる脱毛症です。
粃糠(ひこう)性脱毛症は乾いたフケが大量に発生し、毛穴を塞いで髪の成長を妨げます。
一方、脂漏(しろう)性脱毛症は皮脂の過剰な分泌によって頭皮に炎症が起き、抜け毛が増加します。
どちらも、かゆみや赤みを伴うケースが多く、適切な頭皮ケアが必要です。
主なアロペシアの種類と特徴
| 種類 | 主な症状 | 考えられる原因 |
|---|---|---|
| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が薄くなる | 加齢、ホルモンバランスの変化 |
| 円形脱毛症 | 円形・楕円形に脱毛する | 自己免疫疾患、ストレス |
| 牽引性脱毛症 | 生え際や分け目が薄くなる | 髪への物理的な負担 |
アロペシアの症状とそのサイン
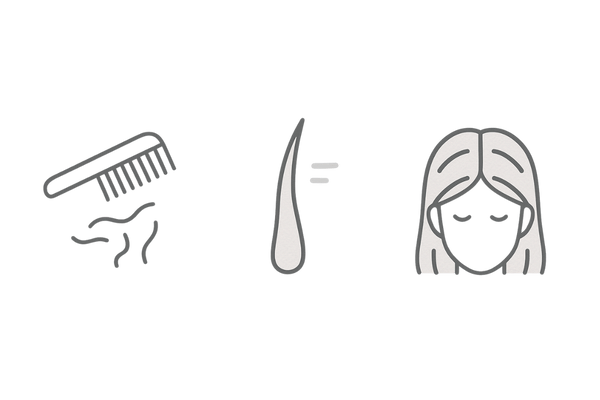
アロペシアは、ある日突然始まるわけではなく、多くの場合、徐々に進行します。
ここでは、注意して観察したいアロペシアのサインを具体的に紹介します。
初期症状を見逃さないために
抜け毛の量が急に増えたと感じたら、それは注意すべきサインかもしれません。
特に、シャンプーやブラッシングの際に、以前よりも明らかに多くの髪が抜ける場合は要注意です。
また、「髪にハリやコシがなくなった」「髪が細く、柔らかくなった」といった髪質の変化も、毛髪の成長サイクルに何らかの異常が起きている可能性を示唆します。
アロペシアの初期症状チェック
| チェック項目 | 詳細 |
|---|---|
| 抜け毛の増加 | 排水溝や枕に付着する毛の量が目に見えて増えた |
| 髪質の変化 | 髪が細く、弱々しくなり、スタイリングがしにくくなった |
| 分け目の広がり | いつもの分け目が以前より地肌が目立つようになった |
頭皮の状態からわかること
健康な髪は、健康な頭皮から育ちます。頭皮の色も健康のバロメーターです。
青白い頭皮は健康な状態ですが、赤みがかっている場合は炎症、黄色っぽい場合は血行不良や皮脂の酸化が考えられます。
かゆみやフケ、湿疹やべたつきといった症状も、頭皮環境が悪化しているサインであり、アロペシアに繋がる可能性があります。
抜け毛の量や質の変化
1日に50本から100本程度の抜け毛は、正常なヘアサイクルの範囲内です。しかし、この数を大幅に超える状態が続く場合は注意が必要です。
また、抜けた毛の状態を観察することも大切です。毛根部分にふくらみ(毛球)がない、あるいは毛が細く短い場合は、髪が十分に成長しきる前に抜けてしまっている証拠です。
このような「未熟な」抜け毛が多い場合は、脱毛症が進行しているサインと考えます。
なぜ女性のアロペシアは起こるのか

女性のアロペシアの原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているケースがほとんどです。
ホルモンバランスや生活習慣、ストレスや遺伝など、様々な角度から原因を理解すると、ご自身に合った対策を見つけやすくなります。
ホルモンバランスの変動
女性の体は、一生を通じてホルモンバランスが大きく変動します。特に、髪の成長を促進する女性ホルモン「エストロゲン」の減少は、薄毛に直結する大きな要因です。
妊娠・出産後や更年期に抜け毛が増えるのは、このエストロゲンが急激に減少するためです。
このホルモンの変動により相対的に男性ホルモンの影響が強まり、髪の成長期が短縮され、薄毛が進行する場合があります。
女性ホルモン(エストロゲン)と髪の主な関係
| 作用 | 詳細 |
|---|---|
| 成長期の維持 | 髪が太く長く成長する期間を延ばす |
| 髪のハリ・ツヤ | コラーゲンの生成を助け、髪の質を向上させる |
| 頭皮の健康 | 頭皮の血行を促進し、潤いを保つ |
生活習慣と栄養状態
髪は私たちが食べたものから作られます。偏った食事による栄養不足は、健康な髪の育成を妨げる直接的な原因となります。
髪の主成分であるタンパク質(ケラチン)や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足すると、髪は細く弱々しくなります。
また、過度なダイエットは急激な栄養不足を招き、アロペシアを引き起こす大きなリスク要因です。
睡眠不足や喫煙、運動不足といった不健康な生活習慣も頭皮の血行を悪化させ、髪の成長に悪影響を与えます。
髪の成長に特に重要な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す | 豚肉、うなぎ、玄米 |
ストレスが与える影響
精神的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱す大きな要因です。
強いストレスを感じると、血管が収縮して頭皮の血行が悪化し、毛根に十分な栄養が届かなくなります。この状態が続くと髪の成長が阻害され、抜け毛が増加します。
円形脱毛症の引き金として知られていますが、びまん性脱毛症を悪化させる一因にもなります。
ストレスが体に与える影響の例
- 自律神経の乱れ
- 血管の収縮(血行不良)
- ホルモンバランスの変動
- 睡眠の質の低下
遺伝的要因について
薄毛には遺伝的な側面があるのも事実です。特に、男性ホルモンに対する感受性の高さは遺伝しやすいと考えられています。
ご家族に薄毛の方がいる場合、ご自身もその体質を受け継いでいる可能性はあります。
しかし、遺伝はあくまで「なりやすさ」の一因であり、遺伝的素因があっても必ず発症するわけではありません。
生活習慣やヘアケアなど、後天的な要因を整えると、発症を遅らせたり症状を軽減したりすることは十分に可能です。
専門クリニックでの診断の流れ
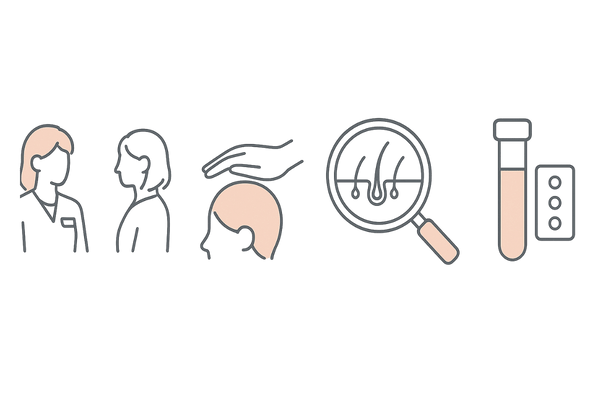
「クリニックに行くのは少し勇気がいる」と感じるかもしれません。しかし、専門家による正確な診断は、効果的な治療への最短ルートです。
初診で行うカウンセリング
診断は、まず丁寧なカウンセリングから始まります。医師や専門のカウンセラーが、患者さんのお話をじっくりと伺います。
いつから症状が気になり始めたか、どのような変化があったか、生活習慣や既往歴、ご家族のことなど、一見関係ないように思えることも含めて詳しくお聞きします。
この対話を通して、アロペシアの原因を探るための重要な手がかりを得ます。
カウンセリングで聞かれる項目
- 症状(いつから、どこが、どのように)
- 生活習慣(食事、睡眠、喫煙、飲酒)
- ストレスの有無
- 既往歴、服用中の薬
- 出産経験、月経周期など
視診と触診
カウンセリングの後は、医師が実際に頭皮と毛髪の状態を観察します。マイクロスコープなどの機器を使い、頭皮の色や毛穴の状態、髪の毛の太さや密度などを拡大して詳しく確認します。
脱毛の範囲やパターンを視診し、頭皮を直接触って硬さや弾力、炎症の有無などを確かめる触診も行います。
これらの診察により、アロペシアの種類を判断していきます。
血液検査やその他の検査
視診や問診だけでは原因が特定できない場合や、全身性の疾患が疑われる場合には、追加の検査を提案するときがあります。
最も一般的なのが血液検査です。貧血の有無や甲状腺機能、ホルモン値などを調べ、体内に潜む薄毛の原因を特定するのに役立ちます。
この検査により、より的確な治療方針を立てられるようになります。
血液検査で確認する項目の一例
| 検査項目 | 調べる内容 | 髪との関連 |
|---|---|---|
| 鉄、フェリチン | 貧血の有無、鉄分の貯蔵量 | 鉄分不足は抜け毛の要因となる |
| 甲状腺ホルモン | 甲状腺機能の異常 | 機能低下・亢進ともに脱毛の原因に |
| 女性ホルモン | ホルモンバランスの状態 | エストロゲンの減少は薄毛に直結 |
日常生活でできるアロペシア対策とセルフケア
専門的な治療と並行して、日々の生活習慣を見直すことは、アロペシアの改善と予防において非常に重要です。
ここでは、今日から始められる具体的なセルフケアの方法を紹介します。健康な髪を育む土台作りとして、ぜひ取り入れてみてください。
バランスの取れた食事の基本
髪の健康は、体の内側から作られます。特定の食品だけを食べるのではなく、多様な食材のバランス良い摂取が大切です。
なかでも髪の主成分であるタンパク質、健やかな頭皮を保つビタミン類、血行を促進するミネラルを意識して摂りましょう。
無理な食事制限は避け、一日三食、規則正しく食べるように心がけてください。
正しいヘアケア方法
毎日のシャンプーもやり方次第で頭皮への負担になったり、逆に良いケアになったりします。
洗浄力の強すぎるシャンプーは避け、アミノ酸系などのマイルドなものを選びましょう。
洗う際は、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗います。すすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、時間をかけて丁寧に洗い流してください。
また、ドライヤーの熱も髪を傷める原因になるため、頭皮から20cm以上離し、同じ場所に長く当て続けないように注意します。
正しいシャンプーの基本手順
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. ブラッシング | 洗う前に髪のもつれを解き、汚れを浮かせる |
| 2. 予洗い | ぬるま湯で髪と頭皮を十分に濡らし、汚れを落とす |
| 3. シャンプー | よく泡立て、指の腹で頭皮をマッサージするように洗う |
| 4. すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧に流す |
ストレス管理と良質な睡眠
現代社会でストレスを完全になくすのは困難ですが、上手に付き合っていく方法を見つけることは可能です。
適度な運動や趣味の時間、リラックスできる入浴など、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。
また、良質な睡眠は、体の修復と髪の成長に欠かせません。髪の成長を促す成長ホルモンは、特に夜10時から深夜2時の間に多く分泌されます。
できるだけ日付が変わる前には就寝し、十分な睡眠時間を確保するように心がけてください。
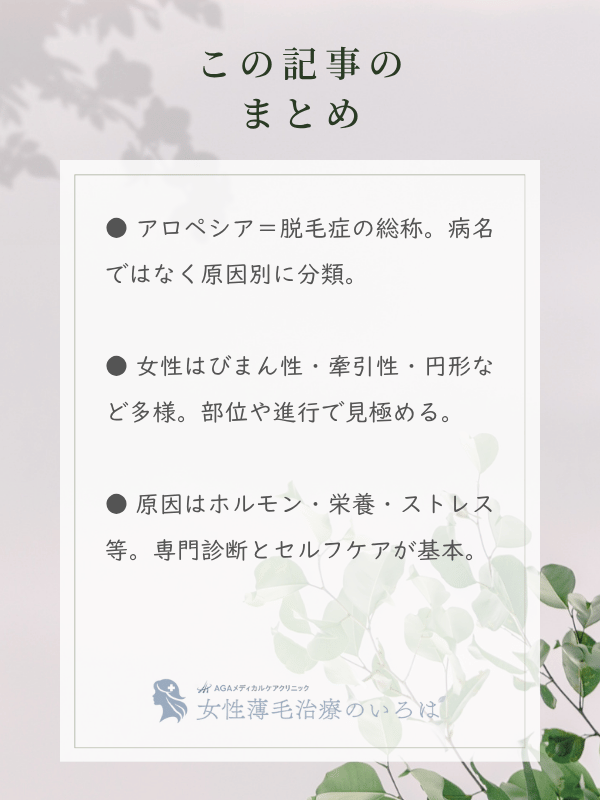
よくある質問
さいごに、アロペシアに関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- アロペシアは完治しますか?
-
アロペシアの種類や原因、進行度によって異なります。牽引性脱毛症や出産後の脱毛のように、原因が明確で一時的なものであれば、原因を取り除くと改善し、完治も期待できます。
びまん性脱毛症(FAGA)のように、加齢や体質が関わるものは、完治というより「症状をコントロールし、良好な状態を維持する」のが治療の目標となります。
早期に適切な治療を開始すると、進行を食い止め、改善させることは十分に可能です。
- どのタイミングでクリニックに行くべきですか?
-
「抜け毛が増えた」「分け目が目立つ」など、ご自身で少しでも変化に気づいた時が、受診の適切なタイミングです。
多くの方が「もう少し様子を見よう」と考えがちですが、アロペシアは進行性のものが多いため、早期発見・早期治療が何よりも重要です。
自己判断でケア用品を試す前に、まずは専門家による正確な診断を受けることを推奨します。
- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
毛髪には成長サイクル(毛周期)があるため、治療効果を実感するまでにはある程度の時間が必要です。一般的に、目に見える変化を感じ始めるまでに最低でも3ヶ月から6ヶ月はかかります。
治療法や個人の反応によって期間は異なりますが、根気強く治療を続ける姿勢が大切です。医師と相談しながら、焦らずに取り組んでいきましょう。
- 自己判断で育毛剤を使っても良いですか?
-
市販の育毛剤や発毛剤には様々な種類がありますが、ご自身の脱毛症の原因やタイプに合っていないものを使用しても、期待する効果は得られません。
それどころか、頭皮に合わずに炎症を起こすなど、症状を悪化させてしまう可能性もあります。
まずはクリニックでご自身の状態を正確に診断してもらい、医師の指導のもとで適切なケアや治療を選択するのが改善への最も確実な道です。
参考文献
HOSKING, Anna-Marie; JUHASZ, Margit; ATANASKOVA MESINKOVSKA, Natasha. Complementary and alternative treatments for alopecia: a comprehensive review. Skin appendage disorders, 2019, 5.2: 72-89.
CHEN, Shuang, et al. Comorbidities in androgenetic alopecia: a comprehensive review. Dermatology and therapy, 2022, 12.10: 2233-2247.
DAVIS, D. S.; CALLENDER, V. D. Review of quality of life studies in women with alopecia. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.1: 18-22.
LEE, Harrison H., et al. Epidemiology of alopecia areata, ophiasis, totalis, and universalis: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2020, 82.3: 675-682.
CASH. The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: a review of the research literature. British Journal of Dermatology, 1999, 141.3: 398-405.
LEVY, Lauren L.; EMER, Jason J. Female pattern alopecia: current perspectives. International journal of women’s health, 2013, 541-556.
VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.
HARRIES, Matthew, et al. Towards a consensus on how to diagnose and quantify female pattern hair loss–The ‘Female Pattern Hair Loss Severity Index (FPHL‐SI)’. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2016, 30.4: 667-676.