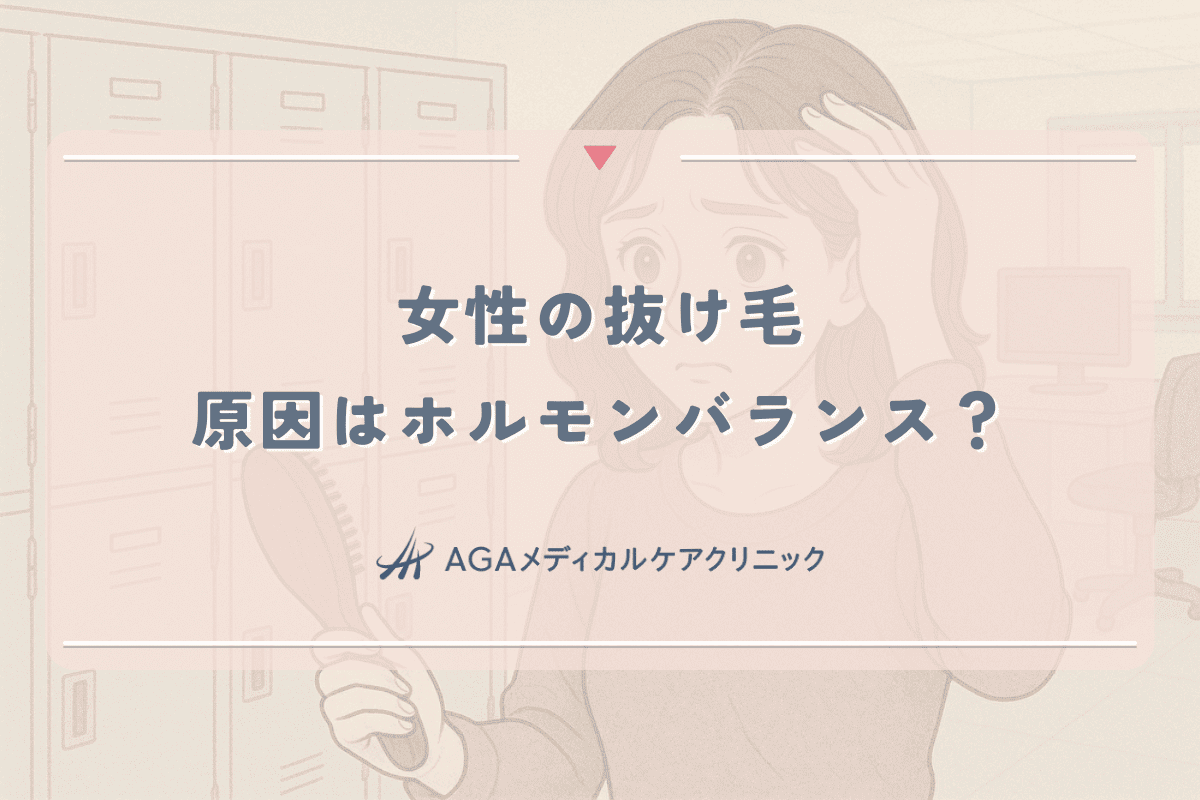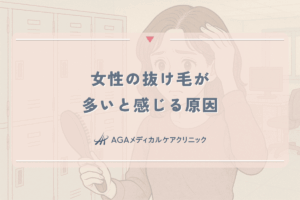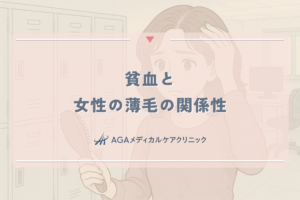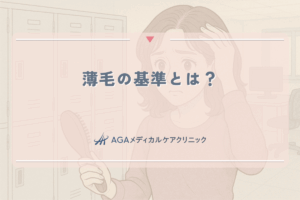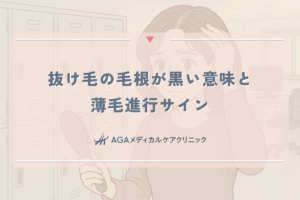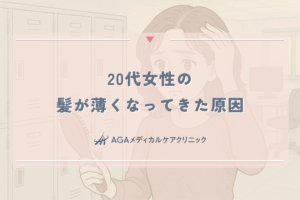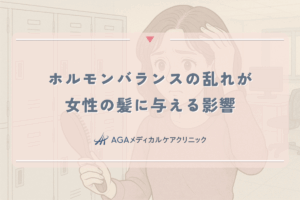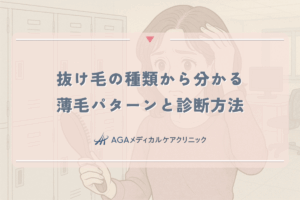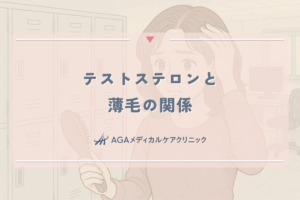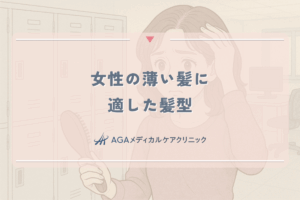鏡を見るたびに気になる抜け毛に、「もしかしてホルモンバランスの乱れ?」と不安に感じる女性は少なくないようです。
女性の髪はホルモンの影響を受けやすく、ライフステージの変化によって抜け毛が増えることもあります。しかし、原因はホルモンバランスだけではありません。
この記事では、女性の抜け毛のさまざまな原因を解説し、ご自身でできる対策から専門的な治療まで、髪の悩みに寄り添う情報をお届けします。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
女性ホルモンの変動と抜け毛の関係
女性の体と心に深く関わる女性ホルモンは、髪の健康にも大きな影響を与えます。
特にエストロゲンとプロゲステロンという二つのホルモンのバランスが、髪の成長サイクルに関与しています。
エストロゲンとプロゲステロンの役割
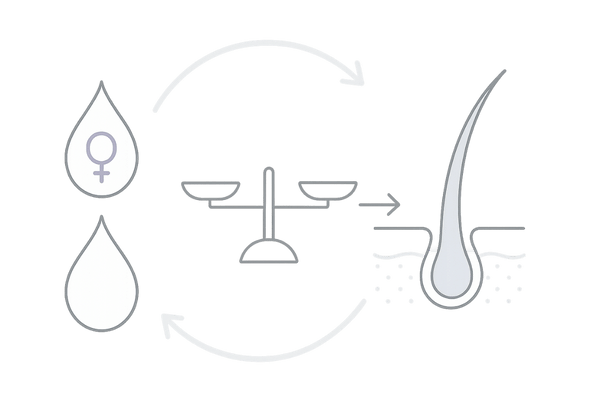
エストロゲンは、髪の成長期を維持して髪を太く長く育てる働きを助けます。髪にハリやコシを与え、つややかに保つ効果も期待できます。
一方、プロゲステロンはエストロゲンの働きを調整し、ヘアサイクルの維持をサポートします。また、頭皮環境を整える働きもあります。
女性ホルモンの主な働き
| ホルモン名 | 髪への主な働き | その他の働き |
|---|---|---|
| エストロゲン | 成長期の維持、髪のハリ・コシ向上 | 女性らしい体つきの形成、自律神経の安定 |
| プロゲステロン | ヘアサイクルの維持、頭皮環境の整備 | 妊娠の維持、体温上昇 |
ライフステージによるホルモンバランスの変化(妊娠・出産、更年期)
女性の生涯において、ホルモンバランスは大きく変動します。
妊娠中はエストロゲンが増加して髪が抜けにくい状態になりますが、出産後には急激に減少し、「産後脱毛」と呼ばれる一時的な抜け毛が増える場合があります。
また、更年期を迎えるとエストロゲンの分泌量が全体的に減少し、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする傾向が見られます。
ホルモンバランスの乱れが引き起こす髪への影響
過度なストレスや不規則な生活、無理なダイエットなどは、ホルモンバランスの乱れを招く要因となります。
ホルモンバランスが乱れるとヘアサイクルが短縮されたり、髪の成長が妨げられたりして、抜け毛や薄毛につながりやすいです。
ホルモン補充療法と抜け毛
更年期障害の治療などで行われるホルモン補充療法(HRT)は、減少したエストロゲンを補って、抜け毛や薄毛の改善が期待できる場合があります。
ただし、全ての方に適応となるわけではなく、医師との相談が必要です。治療による影響は個人差があります。
ホルモンバランス以外の抜け毛の原因
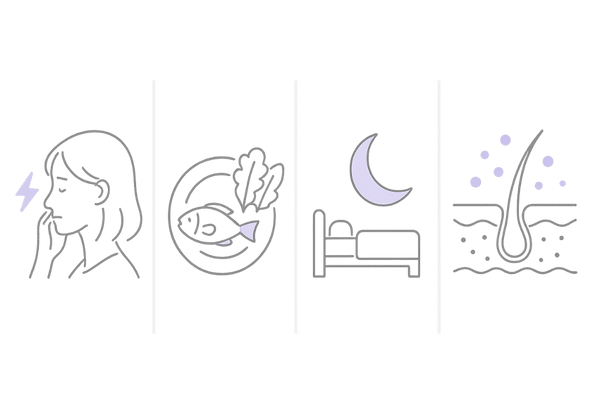
女性の抜け毛の原因は、ホルモンバランスの変動だけではありません。日常生活の中に潜む様々な要因が、髪の健康を脅かしている可能性があります。
ストレスの影響
精神的なストレスや身体的なストレスは、自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こします。
これにより頭皮の血行が悪くなったり、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなったりして、抜け毛が増える方もいます。
円形脱毛症などもストレスが関与すると考えられています。
栄養不足と食生活の偏り
髪は主にタンパク質でできており、その成長にはビタミンやミネラルも必要です。
偏った食事や過度なダイエットは髪に必要な栄養素の不足を招き、髪が細くなったり、抜けやすくなったりする原因となります。
髪の成長に必要な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮環境の維持、代謝促進 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ |
睡眠不足と生活習慣の乱れ
睡眠中には成長ホルモンが分泌され、髪の成長や修復が行われます。睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられる可能性があります。
また、喫煙や過度の飲酒なども、頭皮の血行を悪化させて抜け毛の原因となり得ます。
頭皮環境の問題(乾燥、皮脂過剰、血行不良)
頭皮が乾燥しすぎるとかゆみやフケが発生し、炎症を起こしやすくなります。逆に、皮脂が過剰に分泌されると毛穴が詰まり、これも炎症や抜け毛の原因となります。
また、頭皮の血行不良は髪の毛根に十分な栄養を届けられなくなり、髪の成長を妨げます。
抜け毛を引き起こす可能性のある病気や状態
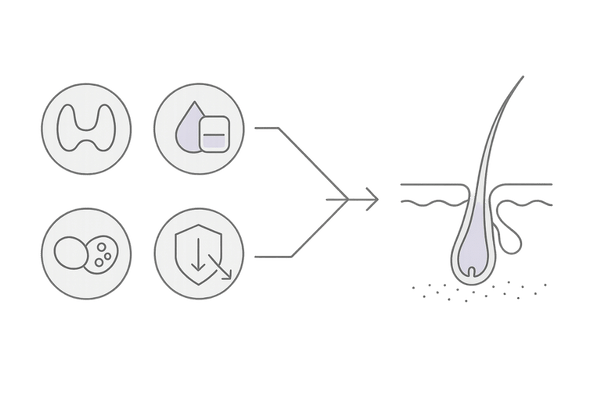
抜け毛が続く場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
甲状腺機能の異常
甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を活発にする働きがあり、髪の成長にも関わっています。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)でも、甲状腺機能低下症(橋本病など)でも、どちらの場合も抜け毛が症状として現れるケースがあります。
髪全体のボリュームが減るびまん性脱毛が特徴です。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
PCOSは、卵巣内で男性ホルモンが過剰に作られることなどが原因で、排卵が起こりにくくなる疾患です。
男性ホルモンの影響で頭頂部や生え際から薄くなる男性型脱毛症(AGA)に似た症状が出る場合があります。
また、月経不順やにきびなどの症状を伴う方も多いです。
鉄欠乏性貧血
鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。
鉄分が不足すると頭皮への酸素供給も滞り、毛母細胞の働きが低下して抜け毛が増えやすいです。特に月経のある女性は鉄欠乏になりやすい傾向があります。
鉄欠乏のサイン
- 疲れやすい
- 顔色が悪い
- 動悸・息切れ
- 爪がもろくなる
自己免疫疾患
自己免疫疾患の中には、免疫系が自身の毛包を攻撃してしまい、円形脱毛症などを引き起こすものがあります。
全身性エリテマトーデス(SLE)などでも、脱毛が症状の一つとして現れるケースがあります。
その抜け毛、本当に「年のせい」だけ?見過ごされがちなサイン
「最近抜け毛が増えたけど、まあ年齢のせいかな…」そう考えて、見過ごしていませんか?確かに加齢も抜け毛の一因ですが、それだけではないかもしれません。
体が発している、髪や頭皮、そして他の部分からのサインに気づくことが、早期対策への第一歩です。
髪質の変化は初期サインかもしれない
抜け毛の量だけでなく、「髪が細くなった」「ハリやコシがなくなった」「うねりが出てきた」といった髪質の変化も注意が必要です。
これらは、毛根の活力が低下していたり、ヘアサイクルが乱れ始めていたりするサインである可能性があります。
以前と比べてスタイリングが決まりにくくなったと感じるときも、髪質の変化が影響しているかもしれません。
頭皮のかゆみやフケが示すこと
頭皮のかゆみやフケは、単なる乾燥や不潔さだけが原因とは限りません。
脂漏性皮膚炎や接触性皮膚炎など、何らかの頭皮トラブルが起きている可能性があります。
頭皮環境の悪化は健康な髪の成長を妨げ、抜け毛につながるときがあります。赤みや湿疹を伴う場合は、特に注意が必要です。
頭皮トラブルのサイン
| サイン | 考えられる状態 | 抜け毛との関連 |
|---|---|---|
| かゆみ・フケ(乾燥) | 乾燥性皮膚炎 | バリア機能低下、炎症 |
| かゆみ・フケ(ベタつき) | 脂漏性皮膚炎 | 毛穴詰まり、炎症 |
| 赤み・湿疹 | 接触性皮膚炎、アレルギー | 炎症による毛根へのダメージ |
全体的なボリュームダウンと分け目の広がり
特定の箇所だけではなく、髪全体が薄くなったように感じる「びまん性脱毛」は女性の薄毛の特徴の一つです。
また、いつも同じ分け目にしていると、その部分の頭皮が目立ちやすくなる場合があります。
髪をかき上げた時に地肌が透けて見える範囲が広がったと感じるときも、薄毛が進行しているサインかもしれません。
抜け毛以外の身体のサインとの関連性
抜け毛は、髪だけの問題ではないケースがあります。
例えば、急激な体重減少や増加、月経不順や過度の疲労感、気分の落ち込みたむくみなどは、ホルモンバランスの乱れや甲状腺機能の異常、栄養不足など抜け毛の原因となりうる全身的な問題を示唆している可能性があります。
髪の変化と合わせて、体全体の調子にも目を向けてみましょう。
今日から始められるセルフケア対策
抜け毛や薄毛の悩みに対して、日常生活の中でできることはたくさんあります。
専門的な治療と並行して、あるいは予防のために、セルフケアを見直してみましょう。
バランスの取れた食事と栄養摂取
髪の健康を保つためには、栄養バランスの取れた食事が基本です。髪の主成分であるタンパク質、亜鉛やビタミンB群、ビタミンEなどを意識して摂取しましょう。
偏りなくさまざまな食材を取り入れるのがポイントです。
ストレスケアとリラクゼーション法
ストレスは抜け毛の大敵です。自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身をリラックスさせる時間を作りましょう。
軽い運動や趣味への没頭、友人との会話やアロマテラピーなどが有効です。深呼吸をするだけでも、自律神経のバランスを整える助けになります。
質の高い睡眠を確保する工夫
髪の成長と修復に欠かせない質の高い睡眠をとるために、生活リズムを整えましょう。
毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のカフェインやアルコール摂取を控える、スマートフォンやパソコンの使用を就寝1時間前までに終える、寝室の環境(温度、湿度、光、音)を整えるなどの工夫が有効です。
正しいヘアケアと頭皮マッサージ
頭皮を清潔に保ち、血行を促進する工夫も重要です。シャンプーは爪を立てずに指の腹で優しく洗い、すすぎ残しがないように注意します。
洗髪後は、ドライヤーで頭皮から乾かしましょう。また、指の腹を使った頭皮マッサージは、血行を促進してリラックス効果も期待できます。
頭皮マッサージのポイント
- 指の腹を使う
- 強くこすらない
- 頭皮全体を動かすように
食生活で見直したいポイント
健やかな髪を育むためには、毎日の食事が非常に重要です。髪に必要な栄養素を理解し、食生活を見直して抜け毛対策につなげましょう。
髪の成長に必要な栄養素
髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質からできています。そのため、良質なタンパク質の摂取が基本です。
さらに、タンパク質を髪の毛に変える働きを助ける亜鉛や、頭皮の血行を良くするビタミンE、新陳代謝を促すビタミンB群なども、髪の成長に欠かせない栄養素です。
| 栄養素 | 意識したいこと |
|---|---|
| タンパク質 | 毎食、肉・魚・卵・大豆製品などを取り入れる |
| ビタミン・ミネラル | 野菜、果物、海藻類を積極的に食べる |
| 脂質 | 良質な油(青魚、ナッツ類、オリーブオイルなど)を選ぶ |
避けるべき食品や食習慣
一方で、髪の健康のために控えたい食品や食習慣もあります。
脂肪分や糖分の多い食品の摂りすぎは皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。インスタント食品や加工食品に偏った食事は、栄養バランスを崩しがちです。
また、過度なアルコール摂取や喫煙も、血行不良や栄養吸収の妨げになるため注意が必要です。
サプリメント活用の考え方
食事だけで十分な栄養素を摂取するのが難しいときは、サプリメントを活用するのも一つの方法です。特に、鉄分や亜鉛、ビタミンB群などは不足しがちな栄養素です。
ただし、サプリメントはあくまで補助的なものと考え、基本はバランスの取れた食事を心がけると良いでしょう。
過剰摂取にならないよう摂取量を守り、必要であれば医師や管理栄養士に相談するのがおすすめです。
ヘアケア製品の選び方と使い方

毎日のヘアケアは、頭皮と髪の健康を保つ上で欠かせません。自分の髪質や頭皮の状態に合った製品を選び、正しく使うことが大切です。
シャンプー・トリートメントの選び方
シャンプーは、頭皮の汚れを落とすことが主な目的です。洗浄力が強すぎるものは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥を招く場合があります。
アミノ酸系など、マイルドな洗浄成分のものを選ぶとよいでしょう。フケやかゆみが気になる場合は、有効成分が配合された薬用シャンプーも選択肢になります。
トリートメントは髪のダメージを補修し、保護する役割があります。髪の悩みに合わせて選びましょう。
シャンプーの種類と特徴
| 種類 | 主な特徴 | おすすめのタイプ |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | マイルドな洗浄力、低刺激 | 乾燥肌、敏感肌 |
| 石けん系 | さっぱりした洗い上がり | 脂性肌(洗いすぎに注意) |
| 高級アルコール系 | 洗浄力が高い、泡立ちが良い | 普通肌、脂性肌(乾燥肌は注意) |
頭皮ケア製品の種類と効果
頭皮の環境を整えるための専用製品も多くあります。頭皮用ローションや美容液は保湿や血行促進、抗炎症などの効果が期待できます。
育毛剤や発毛剤は、毛母細胞の活性化やヘアサイクルの改善を目的とした有効成分が配合されています。
自分の頭皮の状態や目的に合わせて選びましょう。
主な頭皮ケア製品
- 頭皮用ローション・美容液
- 育毛剤(医薬部外品)
- 発毛剤(医薬品)
正しい洗髪方法とドライヤーの使い方
正しい洗髪は、まずブラッシングで髪の絡まりをほどき、ホコリを落とすことから始めます。
つぎに、ぬるま湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、シャンプーを手のひらで泡立ててから指の腹で頭皮をマッサージするように優しく洗います。すすぎは時間をかけて、シャンプー剤が残らないようにしっかり行います。
洗髪後はタオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで頭皮を中心に乾かしますが、熱風を当てすぎないように注意しましょう。
スタイリング剤との付き合い方
ヘアスプレーやワックスなどのスタイリング剤は髪型を整えるのに役立ちますが、頭皮に直接付着すると毛穴を塞いだり、刺激になったりするときがあります。
できるだけ頭皮につかないように使用し、その日のうちにシャンプーでしっかり洗い流すことが大切です。肌に合わないと感じたら、使用を中止しましょう。
専門クリニックでの相談と治療
セルフケアを続けても抜け毛が改善しない場合や、急激に抜け毛が増えた場合、原因が特定できない場合などは、専門のクリニックへの相談を検討しましょう。
クリニックを受診するタイミング
抜け毛が以前より明らかに増えた、髪のボリュームが減って地肌が透けて見える、特定の箇所だけ薄くなってきた、フケやかゆみ、赤みなどの頭皮トラブルが続く、といった状態が数ヶ月以上続く場合は専門医への相談をおすすめします。
特に、急激な脱毛が見られるときは、早めの受診が重要です。
診察と検査の内容
クリニックでは、まず問診で抜け毛の状態や生活習慣、既往歴や家族歴などを詳しく伺います。次に、視診や触診で頭皮や髪の状態を確認します。
マイクロスコープを使って毛穴の状態や髪の太さを詳細に観察する場合もあります。
必要に応じて血液検査を行い、ホルモンバランスや甲状腺機能、栄養状態(鉄分など)を調べて抜け毛の原因を特定します。
主な検査項目
| 検査の種類 | 調べる内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 問診 | 症状、生活習慣、病歴など | 原因の推定、方針決定 |
| 視診・触診 | 頭皮の色、硬さ、髪の状態 | 脱毛のパターン、頭皮環境の確認 |
| 血液検査 | ホルモン値、甲状腺機能、鉄分など | 全身的な原因の特定 |
主な治療法の選択肢
女性の薄毛治療には、原因や症状に応じてさまざまな選択肢があります。
内服薬や外用薬、栄養療法や頭皮への注入療法、自毛植毛などが代表例です。医師が診察結果に基づいて、適した治療法を提案します。
女性の薄毛治療の選択肢
- 内服薬
- 外用薬
- 注入療法
- 栄養療法
治療期間と費用の目安
薄毛治療は、効果が現れるまでに時間がかかるのが一般的です。多くの場合、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。治療法によって効果の現れ方や期間は異なります。
費用も、治療内容や期間によって大きく変わります。内服薬や外用薬は月々数千円から数万円、注入療法や植毛はより高額になる傾向があります。多くの場合、保険適用外の自由診療です。
治療を開始する前に期間や費用について十分に説明を受け、納得した上で進めるようにしましょう。
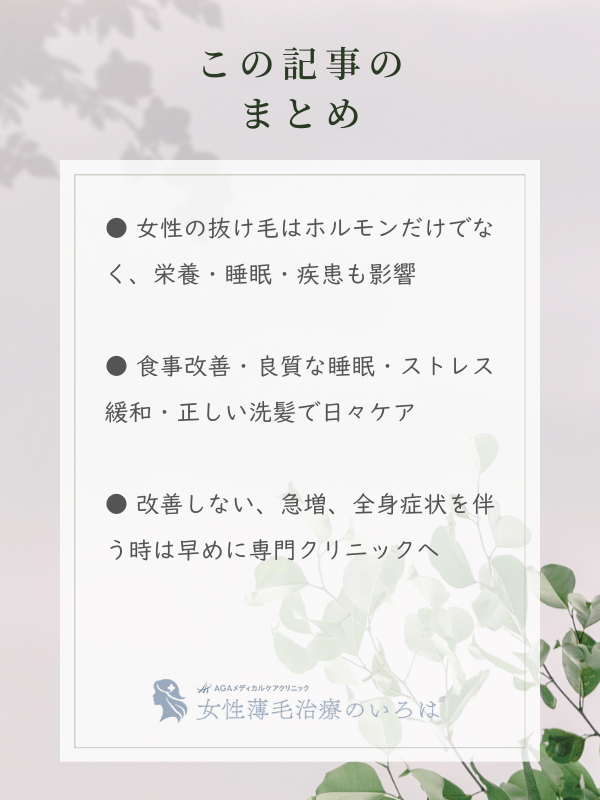
女性の抜け毛に関するよくある質問
さいごに、女性の抜け毛に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- 抜け毛は何本から心配すべきですか?
-
髪の毛にはヘアサイクルがあり、健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜け落ちています。この範囲内であれば、通常は心配ありません。
ただし、以前と比べて明らかに抜け毛の量が増えたと感じる場合や、特定の箇所だけが薄くなる、髪全体のボリュームが急に減ったなどの変化が見られる場合は注意が必要です。
本数だけでなく、抜け毛の質(細い毛が多いなど)やご自身の感覚的な変化も判断材料になります。
- 市販の育毛剤は効果がありますか?
-
市販の育毛剤(医薬部外品)は、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりすることで抜け毛を予防し、育毛をサポートする効果が期待できるものがあります。
しかし、発毛効果が医学的に認められている成分を含む「発毛剤」(第一類医薬品)とは異なります。ご自身の抜け毛の原因や状態によっては、市販の育毛剤だけでは十分な効果が得られない場合もあります。
効果を感じられないときや、より積極的な治療を望む方は、専門クリニックへの相談を検討しましょう。
- 髪を頻繁に洗うと抜け毛が増えますか?
-
基本的に適切な方法で洗髪する限り、洗髪の頻度が直接的に抜け毛を増やす原因にはなりません。
洗髪時に抜ける毛は、すでにヘアサイクルの休止期に入っていた毛が物理的な刺激で抜け落ちるものがほとんどです。
むしろ、頭皮を不潔にしておくと毛穴の詰まりや炎症を引き起こし、抜け毛の原因となる可能性があります。
ただし、洗浄力の強すぎるシャンプーを使ったりゴシゴシと強く洗いすぎたりすると、頭皮を傷つけ、乾燥やダメージにつながるため注意が必要です。
1日1回の洗髪で、優しく丁寧に洗うことを心がけましょう。
- 遺伝は女性の抜け毛に関係しますか?
-
男性型脱毛症(AGA)ほどではありませんが、女性の薄毛(FAGA/FPHL)にも遺伝的な要因が関与する可能性は指摘されています。
家族に薄毛の方がいる場合、体質的に薄毛になりやすい傾向があるかもしれません。
しかし、女性の薄毛はホルモンバランスの変化や生活習慣、ストレスや栄養状態など、遺伝以外の要因も複雑に関係しているケースが多いため、遺伝だけが原因とは限りません。
遺伝的な素因があると感じる場合でも、適切なケアや治療によって進行を抑えたり、改善したりすることは可能です。
参考文献
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
CARMINA, Enrico, et al. Female pattern hair loss and androgen excess: a report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019, 104.7: 2875-2891.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
REDLER, Silke; MESSENGER, Andrew G.; BETZ, Regina C. Genetics and other factors in the aetiology of female pattern hair loss. Experimental Dermatology, 2017, 26.6: 510-517.
CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.
RAMOS, Paulo Müller; MIOT, Hélio Amante. Female pattern hair loss: a clinical and pathophysiological review. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90: 529-543.
SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.
GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.