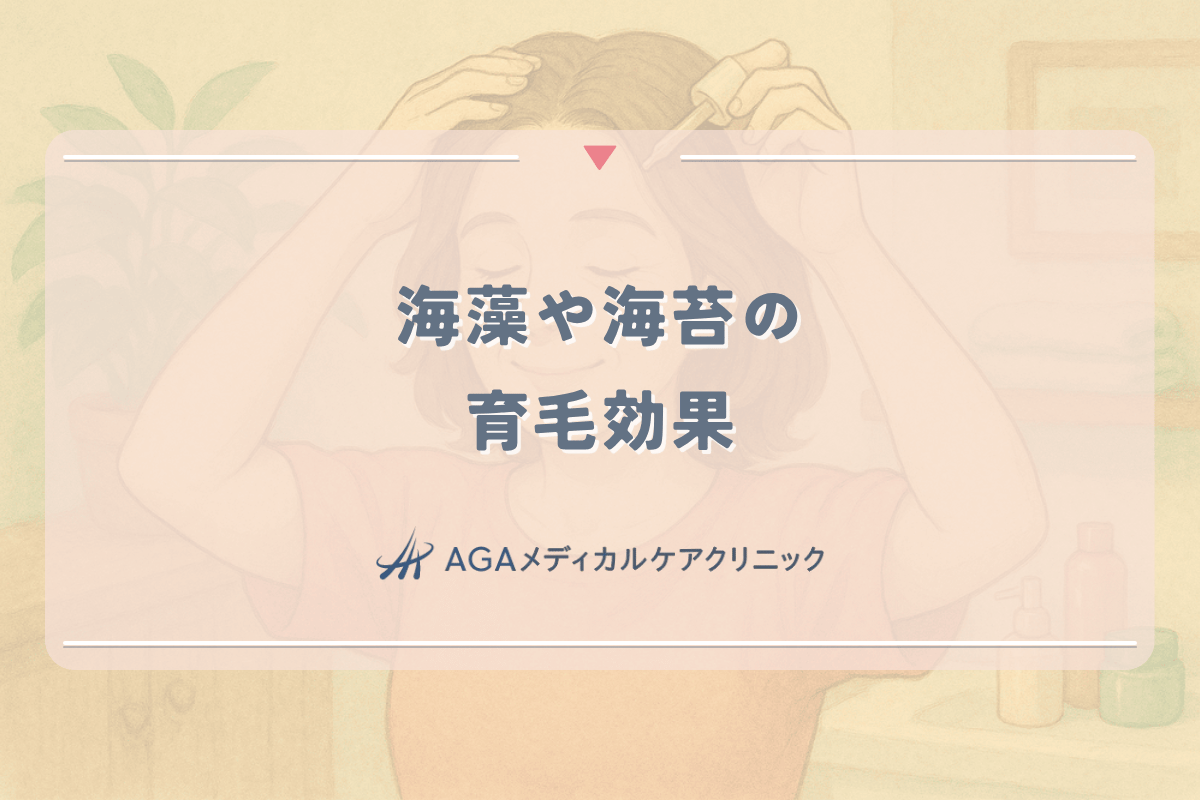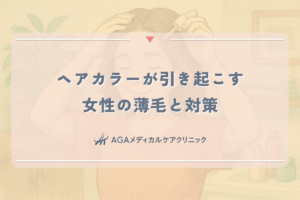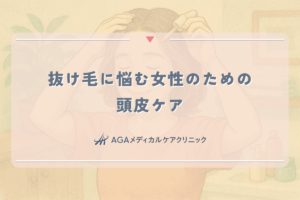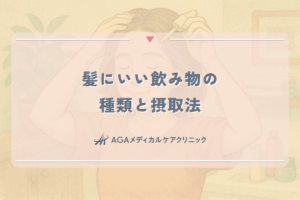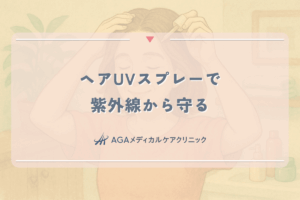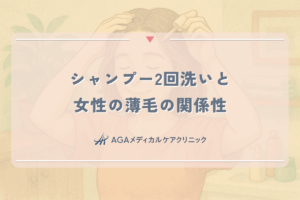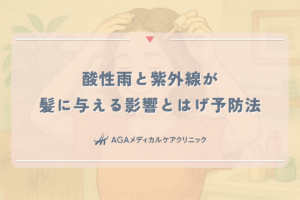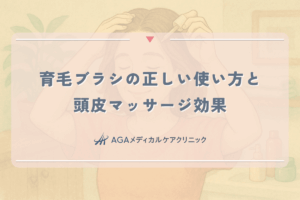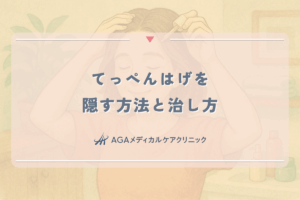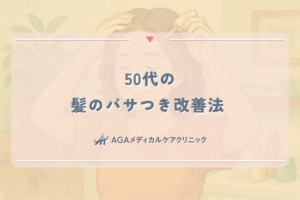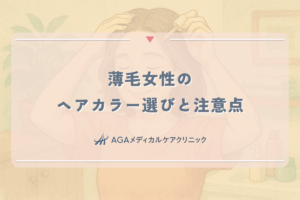「海藻を食べると髪がきれいになる」という話は有名です。古くから伝わるこの言葉は、多くの女性が一度は耳にしたことがあるでしょう。
特に、髪のボリュームやハリ、コシの変化を感じやすい女性にとって、身近な食材である海藻や海苔が持つ力は非常に興味深いものです。
この記事では、なぜ海藻類が髪に良いとされるのか、その科学的な根拠となる栄養素を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ「海藻は髪に良い」と言われるのか?その真相
昔からの言い伝えとして広く知られている「海藻は髪に良い」という説。この背景には、単なるイメージだけではない、科学的な理由が存在します。
黒く、つややかな海藻の見た目が、そのまま美しい髪を連想させますが、その本質は含まれる栄養素にあります。
現代の栄養学の観点から、この言い伝えの真相を解き明かしていきましょう。
古くからの言い伝えと現代科学の視点
日本では古来、昆布やわかめなどが食生活に深く根付いてきました。その中で、経験的に「海藻をよく食べる地域の人の髪は豊かである」といった認識が広まり、言い伝えとして定着したと考えられます。
現代科学は、この経験則を裏付ける成分を次々と明らかにしています。
髪の健康維持に必要なミネラルやビタミンが海藻には豊富に含まれており、これらが頭皮環境を整え、髪の成長をサポートするのです。
髪の主成分「ケラチン」と海藻の栄養素の関係
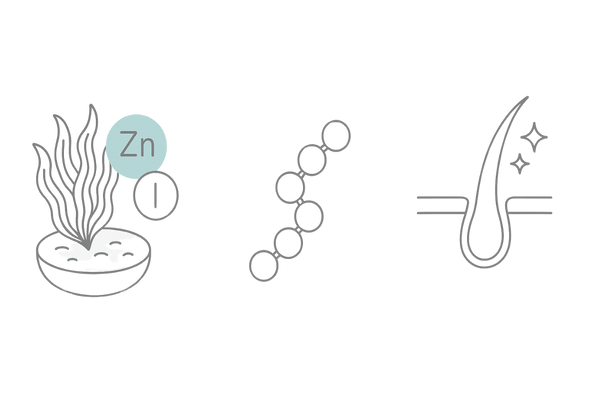
私たちの髪の毛は、その約90%が「ケラチン」というタンパク質で構成されています。
ケラチンは18種類のアミノ酸から成り立っており、この合成過程でビタミンやミネラルが補助的な役割を果たします。
特に、海藻に豊富な亜鉛やヨウ素といったミネラルは、タンパク質の合成を助け、新陳代謝を活発にする働きを持ちます。
つまり、海藻は髪の「材料」そのものではありませんが、材料を効率よく使って丈夫な髪を作るための「サポーター」として重要なのです。
髪の健康を支える栄養素の連携
| 栄養素カテゴリ | 主な役割 | 海藻に含まれる代表例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | アミノ酸(少量) |
| ミネラル | タンパク質の合成補助、新陳代謝の促進 | ヨウ素、亜鉛、鉄 |
| ビタミン | 頭皮の健康維持、血行促進 | ビタミンA、ビタミンB群 |
海藻だけでは髪は生えない?育毛の全体像
海藻が髪に良い影響を与えるのは事実ですが、「海藻だけを食べていれば髪の悩みがすべて解決する」というわけではありません。
育毛は、食事や睡眠、運動やストレス管理といった生活習慣全体が関わる総合的な取り組みです。
海藻の摂取は、あくまで健康な髪を育むための食生活の一部と捉えましょう。
タンパク質をはじめとする他の栄養素とバランス良く組み合わせて初めて、海藻の持つ力が最大限に発揮されます。
髪の成長を支える海藻の三大栄養素
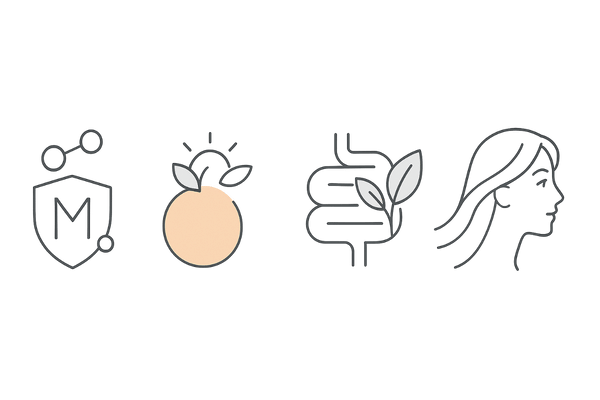
海藻が髪の健康に寄与する理由は、そこに含まれる豊富な栄養素にあります。特に「ミネラル」「ビタミン」「食物繊維」は、健やかな髪を育む上で欠かせない三大栄養素と言えます。
これらの成分が体内でどのように働き、髪の成長に貢献するのかを具体的に見ていきましょう。
ミネラル(ヨウ素・亜鉛)の役割
ミネラルは、体の機能を正常に保つために微量ながらも必要とされる栄養素です。
なかでもヨウ素は甲状腺ホルモンの主成分であり、このホルモンは全身の新陳代謝を活発にする働きがあります。
毛母細胞の活動も新陳代謝の一部であるため、ヨウ素が不足すると髪の成長が滞り、抜け毛や薄毛の原因となる場合があります。
また、亜鉛は前述の通り、髪の主成分であるケラチンを合成する際に重要な役割を担います。
亜鉛が不足すると新しい髪が作られにくくなるだけでなく、髪質がもろくなる可能性も指摘されています。
髪に重要なミネラルの働き
| ミネラル | 主な働き | 不足した場合の影響 |
|---|---|---|
| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの構成成分、新陳代謝の促進 | 髪の成長遅延、脱毛 |
| 亜鉛 | ケラチン(タンパク質)の合成補助 | 髪の生成不良、髪質の低下 |
| 鉄 | 全身への酸素運搬、頭皮の血行維持 | 頭皮の栄養不足、抜け毛 |
ビタミン群(A・B群)の効果
ビタミンもまた、髪の健康に深く関わっています。
ビタミンAは頭皮の潤いを保ち、乾燥やフケを防ぐ働きがあります。健康な頭皮環境は、丈夫な髪が育つための土台です。
ビタミンB群、特にビオチンやパントテン酸は皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素であり、毛母細胞の活性化にも関与します。
これらのビタミンが不足すると、頭皮のトラブルや髪の成長不良につながりやすいです。
食物繊維と頭皮環境
意外に思われるかもしれませんが、海藻に豊富な水溶性食物繊維も、巡り巡って髪の健康に貢献します。
食物繊維は腸内環境を整え、善玉菌を増やす働きがあります。腸内環境が改善すると栄養素の吸収効率が高まるだけでなく、血行も促進されます。
これによって髪の成長に必要な栄養が頭皮の毛細血管までしっかりと届けられるようになり、健康な髪が育ちやすい環境が作られるのです。
その不調、ミネラル不足かも?女性のライフステージと髪の関係
女性の髪の悩みは単純なヘアケアの問題だけではなく、一生を通じて変化する女性ホルモンやライフイベントと密接に結びついています。
月経や妊娠・出産、更年期のような節目で体内の栄養バランスは大きく変動し、特にミネラルの需要と供給のアンバランスが髪の状態に直接的な影響を与える場合があります。
「最近、髪に元気がない」と感じるなら、それは体からのサインかもしれません。
月経・妊娠・授乳期に失われがちな栄養素
月経がある女性は、毎月の出血によって鉄分を失いやすい状態にあります。
鉄は血液中のヘモグロビンの主成分で、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担います。鉄分が不足すると頭皮の毛根部への酸素供給が滞り、髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。
さらに、妊娠・授乳期には胎児や母乳を通じて多くの栄養素が赤ちゃんへ移行するため、母体は亜鉛やカルシウムといったミネラルも不足しがちになります。
この時期の抜け毛の増加はホルモンバランスの変化に加え、こうした栄養不足も一因と考えられます。
女性のライフステージと特に注意したい栄養素
| ライフステージ | 特に不足しやすい栄養素 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 月経期 | 鉄 | 抜け毛、髪の細り |
| 妊娠・授乳期 | 鉄、亜鉛、カルシウム、葉酸 | 産後脱毛、髪質の変化 |
| 更年期 | カルシウム、イソフラボン、亜鉛 | ハリ・コシの低下、うねり、薄毛 |
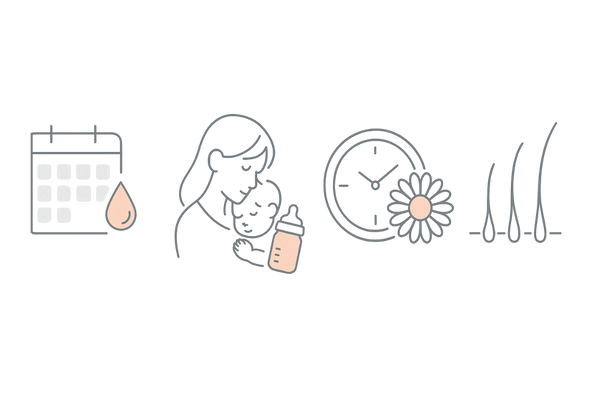
更年期における女性ホルモンの変化と髪への影響
40代後半から50代にかけて迎える更年期は、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少する時期です。
エストロゲンは髪の成長期を維持し、ハリやツヤを与える働きがあるため、その減少は髪のサイクルに直接影響します。
成長期が短くなり休止期に入る髪の割合が増えるため、全体的にボリュームがダウンしたり、一本一本の髪が細くなったりします。
この時期に海藻類などでミネラルを意識的に補う工夫は、ホルモンバランスの変化に揺らぐ体を内側から支え、髪の健康を保つ上で重要です。
食生活の乱れが招く「新型栄養失調」と薄毛リスク
現代女性の中には、カロリーは足りていても、ビタミンやミネラルといった特定の栄養素が不足する「新型栄養失調」の状態にある人が少なくありません。
過度なダイエット、外食や加工食品中心の食生活は、このリスクを高めます。
特に髪の成長に必要な亜鉛や鉄、ビオチンなどが不足すると、年齢に関わらず薄毛や抜け毛の悩みにつながる可能性があります。
バランスの取れた食事の基本に立ち返り、海藻のような栄養価の高い食材を取り入れると、美しい髪を守れます。
ストレスとミネラル消費の悪循環
仕事や家庭など、現代社会で多くの役割を担う女性は、慢性的なストレスにさらされがちです。
人がストレスを感じると体内では抗ストレスホルモンが分泌されますが、この生成過程でビタミンCやマグネシウム、亜鉛といった栄養素が大量に消費されます。
つまり、ストレスが多い生活は髪の成長に必要なミネラルをどんどん奪っていくのです。
これにより髪の健康が損なわれ、それがまた新たなストレスになるという悪循環に陥るケースもあります。
代表的な海藻の種類とそれぞれの育毛効果
「海藻」と一括りに言っても、その種類は様々です。
スーパーマーケットで手軽に購入できる昆布やわかめ、食卓でおなじみの海苔など、それぞれに特徴的な栄養素と期待できる効果があります。
昆布・わかめ・ひじきに含まれる栄養素の違い
昆布は、特にヨウ素の含有量が全食品の中でもトップクラスです。だしとして使うだけでも、その栄養の一部を摂取できます。
わかめはヨウ素に加え、フコキサンチンという抗酸化作用のある成分を含みます。ひじきは、鉄分やカルシウムが豊富で、特に女性が不足しがちなミネラルを補うのに適しています。
これらの海藻を日替わりで食事に取り入れると、バランスよく栄養を摂取できます。
主要な海藻の栄養的特徴
| 海藻の種類 | 特に豊富な栄養素 | 期待される主な効果 |
|---|---|---|
| 昆布 | ヨウ素、アルギン酸 | 新陳代謝の促進 |
| わかめ・めかぶ | ヨウ素、フコイダン、アルギン酸 | 頭皮の保湿、血行促進 |
| ひじき | 鉄、カルシウム、食物繊維 | 貧血予防、骨の健康維持 |
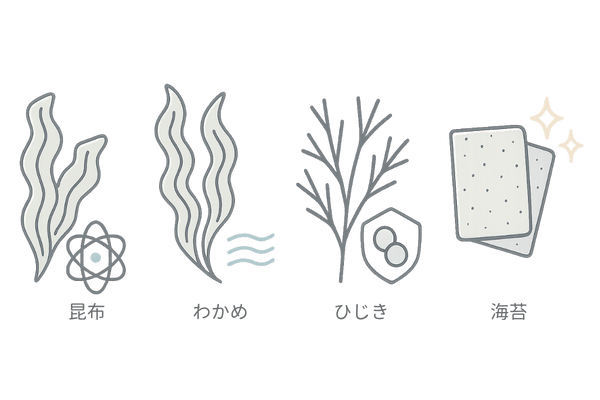
海苔(のり)が持つ特有の栄養価
おにぎりや巻き寿司に使う海苔も、実は非常に栄養価の高い海藻です。特に、タンパク質やビタミンA、ビタミンCや鉄分、葉酸などをバランス良く含んでいます。
板海苔2枚(約6g)で、1日に必要なビタミンAの大部分を補えるほどです。
ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、頭皮の健康を保つ上で重要です。
手軽に食べられる海苔を日常的にプラスするだけで、髪に必要な栄養素を手軽に強化できます。
もずくやアカモクの「フコイダン」とは
近年、健康成分として注目を集めているのが、もずくやわかめの「ぬめり」の主成分である「フコイダン」です。
フコイダンは水溶性食物繊維の一種で、高い保湿力を持つことが知られています。この保湿効果は、頭皮の乾燥を防ぎ、健康な状態に保つのに役立ちます。
また、毛母細胞の増殖をサポートする働きや、血行を促進する作用も研究で示唆されており、育毛への貢献が期待される成分です。
同じくネバネバ成分を持つアカモクもフコイダンを豊富に含みます。
効果的な海藻の摂取方法と一日の目安量
髪に良い栄養素が豊富な海藻ですが、その効果を最大限に引き出すためには、食べ方に少し工夫が必要です。
調理法による栄養素の変化や、適切な摂取量を知っておくと、より効率的に髪の健康をサポートできます。
また、何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」ですので、過剰摂取のリスクについても正しく理解しておきましょう。
加熱や調理法による栄養素の変化
海藻に含まれる栄養素の中には、水に溶けやすかったり、熱に弱かったりするものがあります。
例えば、ビタミンB群やC、カリウムなどは水溶性のため、茹でたり長時間水にさらしたりすると失われやすい性質があります。
これらの栄養素を効率よく摂るには、味噌汁やスープのように煮汁ごといただける調理法がおすすめです。
また、油と一緒に摂ると吸収率が高まるビタミンA(β-カロテン)は、炒め物などにすると良いでしょう。
調理法と栄養素の吸収
| 調理法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 生で食べる(酢の物など) | 水溶性ビタミンを逃しにくい | 消化に時間がかかることがある |
| 汁物(味噌汁、スープ) | 溶け出た栄養素も丸ごと摂れる | 塩分の摂りすぎに注意 |
| 炒め物 | 油で脂溶性ビタミンの吸収率アップ | カロリーが高くなりやすい |
食べ過ぎは逆効果?ヨウ素の過剰摂取リスク
髪に良いからといって、海藻を大量に食べるのは避けるべきです。ヨウ素は不足しても問題ですが、過剰に摂取し続けると甲状腺の機能低下を引き起こす可能性があります。
甲状腺機能が低下するとかえって新陳代謝が悪くなり、抜け毛や倦怠感などの症状が現れる場合があります。
日本の食生活では不足するケースは稀で、むしろ過剰摂取に注意が必要です。
サプリメントなどで安易に補うのではなく、食事から適量を摂るように心がけましょう。
海藻の1日の摂取目安
| 海藻の種類 | 1日の摂取目安量(乾燥) | 備考 |
|---|---|---|
| 昆布 | 1g程度(だし用なら問題なし) | ヨウ素が特に多いため注意 |
| わかめ | 5g程度(味噌汁のお椀1杯分) | 日常的に摂りやすい |
| ひじき | 5-10g程度(小鉢1杯分) | 鉄分補給に良い |
毎日少しずつ続けるための簡単レシピ例
育毛のための食生活は、毎日続けられることが何よりも重要です。海藻を無理なく食生活に取り入れるための簡単な方法をいくつか紹介します。
- いつもの味噌汁に乾燥わかめをプラスする
- ご飯に刻み海苔やとろろ昆布をふりかける
- サラダに海藻サラダをミックスする
- もずく酢を食前の一品にする
こうした小さな工夫を習慣にすると、継続的に髪に必要な栄養を補給できます。
海藻パワーを最大化する食事の組み合わせ
海藻に含まれる栄養素をより効果的に体内で働かせるためには、他の食材との「食べ合わせ」が鍵となります。
髪の主成分であるタンパク質や、ミネラルの吸収を助けるビタミンなど、相互に作用し合う栄養素を意識して組み合わせると育毛効果をさらに高められるでしょう。
タンパク質(肉・魚・大豆製品)との相乗効果
髪はケラチンというタンパク質からできています。いくら海藻でミネラルやビタミンを補っても、主材料であるタンパク質が不足していては丈夫な髪が作れません。
肉や魚、卵や大豆製品といった良質なタンパク質を毎食しっかりと摂るのが基本です。
例えば、わかめと豆腐の味噌汁、ひじきと鶏肉の煮物、海苔で巻いた納豆ごはんなどは、タンパク質と海藻のミネラルを同時に摂取できる理想的な組み合わせです。
ビタミンC(野菜・果物)で亜鉛の吸収率アップ
ケラチンの合成に欠かせない亜鉛は、実は体に吸収されにくいミネラルの一つです。しかし、ビタミンCやクエン酸と一緒に摂ると、その吸収率を高められます。
ビタミンCはピーマンやブロッコリーなどの緑黄色野菜や、柑橘系の果物に豊富です。
海藻サラダにレモンベースのドレッシングをかけたり、食後のデザートに果物を添えたりする工夫で、効率よく亜鉛を体内に取り込めます。
育毛をサポートする食べ合わせ例
| 海藻 | 組み合わせる食材 | 期待される相乗効果 |
|---|---|---|
| わかめ、もずく | きゅうり、しらす(酢の物) | 酢のクエン酸がミネラルの吸収を促進 |
| ひじき | 大豆、人参、鶏肉(煮物) | タンパク質と鉄分、ビタミンAを同時に摂取 |
| 海苔 | チーズ、アボカド | タンパク質と良質な脂質、ビタミンEを補給 |
育毛を妨げる可能性のある食べ物
一方で、育毛の観点から摂取を控えめにしたい食べ物もあります。
糖質や脂質の多い食事、スナック菓子、インスタント食品などは、皮脂の過剰な分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
また、過度なアルコール摂取は、体内で分解される際にビタミンやミネラルを大量に消費してしまうため、髪に必要な栄養が不足する原因となります。
バランスの取れた食事を基本とし、これらの食品は適度に楽しむ程度に留めましょう。
海藻由来成分を含むヘアケア製品の選び方
美しい髪を育むためには食事による内側からのケアと同時に、シャンプーや育毛剤などによる外側からのケアも重要です。
多くのヘアケア製品に「海藻エキス」が配合されているのは、海藻が持つ保湿効果や血行促進効果が、頭皮環境の改善に役立つと考えられているからです。
内側からと外側からの働きかけの重要性
食事で摂取した栄養が髪に届くまでには時間がかかりますし、全身で使われるため、すべてが髪に行くわけではありません。
そこで、頭皮に直接働きかけるヘアケア製品を併用すると、より直接的に頭皮環境を整えられます。
内側からの栄養補給と外側からの頭皮ケアは、いわば車の両輪のようなものです。両方をバランスよく行うのが健やかな髪への近道です。
育毛剤やシャンプーに含まれる海藻エキスの効果
ヘアケア製品に配合される海藻エキスには、様々な種類があります。
例えば、褐藻(かっそう)エキス(昆布やわかめなど)は、ぬめり成分であるアルギン酸やフコイダンを含み、頭皮に潤いを与えて乾燥を防ぎます。
紅藻(こうそう)エキス(テングサなど)や緑藻(りょくそう)エキス(クロレラなど)も、保湿や細胞の活性化をサポートする成分として利用されます。
これらのエキスが硬くなった頭皮を柔らかくし、毛根に栄養が届きやすい環境を作る手助けをします。
ヘアケア製品の成分表示で確認したいポイント
| 成分カテゴリ | 主な成分例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 保湿成分 | 褐藻エキス、紅藻エキス、グリセリン | 頭皮の乾燥防止、フケ・かゆみの抑制 |
| 血行促進成分 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 | 毛根への栄養供給サポート |
| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸2K | 頭皮の炎症を抑え、健やかな状態に保つ |
製品選びで注意したいポイント
海藻エキス配合の製品を選ぶ際は、エキスが入っているだけで判断しないようにしましょう。自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌など)に合っているかが最も重要です。
また、洗浄力の強すぎるシャンプーは必要な皮脂まで奪ってしまい、かえって頭皮環境を悪化させる場合があります。アミノ酸系の洗浄成分など、マイルドな洗い心地のものを選ぶと良いでしょう。
もしフケやかゆみ、抜け毛が続くときは自己判断でケアを続けるのではなく、専門クリニックへの相談をおすすめします。
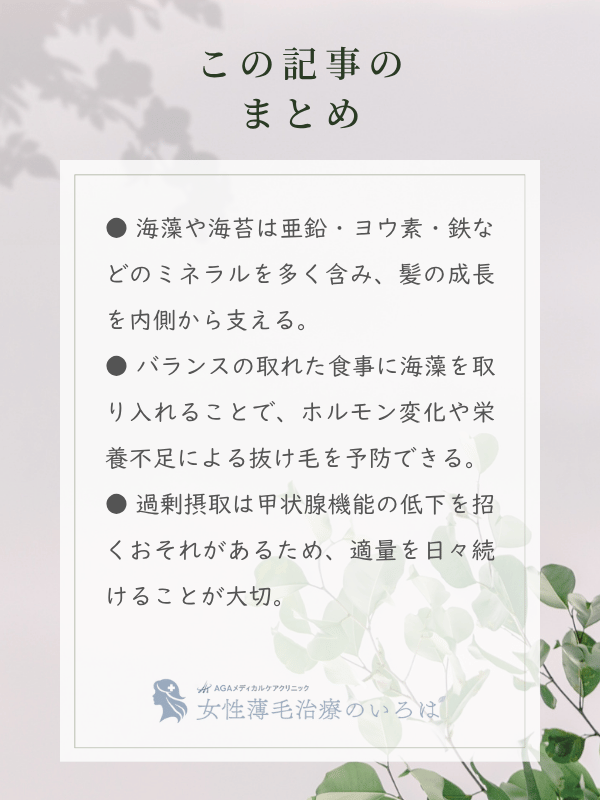
よくある質問
海藻と髪に関する様々な情報について、患者さんから寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
- 海藻アレルギーでも髪に良い栄養を摂る方法はありますか?
-
可能です。海藻に含まれる髪に良い栄養素は、他の食品からも摂取できます。
例えば、亜鉛は牡蠣や赤身肉、ナッツ類に、鉄分はレバーやほうれん草に豊富です。ヨウ素は魚介類にも含まれます。
海藻アレルギーの方は、これらの食品をバランスよく食事に取り入れると必要な栄養を補えます。特定の食品に偏らず、多様な食材から栄養を摂るように意識してください。
- サプリメントで海藻の栄養を補っても良いですか?
-
基本的には食事から栄養を摂るのが最も望ましいですが、食生活が不規則になりがちな場合や、特定の栄養素が不足している場合には、サプリメントを補助的に利用するのも一つの方法です。
ただし、前述の通り、特にヨウ素の過剰摂取には注意が必要です。サプリメントを利用する際は、成分表示をよく確認し、推奨される摂取量を必ず守ってください。
不安なときは、医師や管理栄養士などの専門家に相談すると良いでしょう。
- 効果を実感できるまで、どのくらいの期間が必要ですか?
-
食生活やヘアケアの改善による効果は、すぐには現れません。髪には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、新しい髪が生まれてから成長し、抜け落ちるまでには数年かかります。
食生活の改善によって影響を受けるのは、これから新しく生えてくる髪です。そのため、目に見える変化を実感するまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月の継続が大切です。
焦らず、長期的な視点でじっくりと体質改善に取り組んでいきましょう。
- 白髪予防にも海藻は効果がありますか?
-
白髪の主な原因は、加齢や遺伝、ストレスなどにより、髪を黒くする色素「メラニン」を作る細胞(メラノサイト)の働きが低下することです。
海藻に含まれるヨウ素は新陳代謝を活発にし、細胞の働きをサポートするため、間接的に白髪予防に良い影響を与える可能性はあります。
また、ミネラルの一種である銅は、メラニンを生成する酵素の働きに必要です。
しかし、海藻を食べれば白髪が黒くなるという直接的な効果は、現在のところ科学的には証明されていません。
白髪対策としては、バランスの取れた食事とストレスのない生活を心がけるのが基本となります。
参考文献
HA, Won Ho; PARK, Dae Hwan. Effect of seaweed extract on hair growth promotion in experimental study of C57BL/6 mice. Archives of Craniofacial Surgery, 2013, 14.1: 1-10.
BAK, S. S., et al. Ecklonia cava promotes hair growth. Clinical and Experimental Dermatology, 2013, 38.8: 904-910.
QUIÑONES, Stephanie. Sea Moss for Hair: Discover How You Can Solve Hair Loss, Hair Damage, Hair Breakage, Frizz, Split-ends, Scalp Irritation, and Much More Using Dr. Sebi’s Guide on how to Use Sea Moss on Hair. Stephanie Quiñones, 2021.
MURAI, Utako, et al. Impact of seaweed intake on health. European journal of clinical nutrition, 2021, 75.6: 877-889.
ABLON, Glynis. A 3‐month, randomized, double‐blind, placebo‐controlled study evaluating the ability of an extra‐strength marine protein supplement to promote hair growth and decrease shedding in women with self‐perceived thinning hair. Dermatology research and practice, 2015, 2015.1: 841570.
PEREIRA, Leonel. Seaweeds as source of bioactive substances and skin care therapy—cosmeceuticals, algotheraphy, and thalassotherapy. Cosmetics, 2018, 5.4: 68.
PHILPOTT, Jane; BRADFORD, Montse. Seaweed: Nature’s Secret for. Nutrition, 2006, 2.
MURALEEDHARAN, Vijayalakshmi, et al. Advantages of functional foods in supporting and maintaining hair and skin health. In: Evidence-based Functional Foods for Prevention of Age-related Diseases. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. p. 223-244.