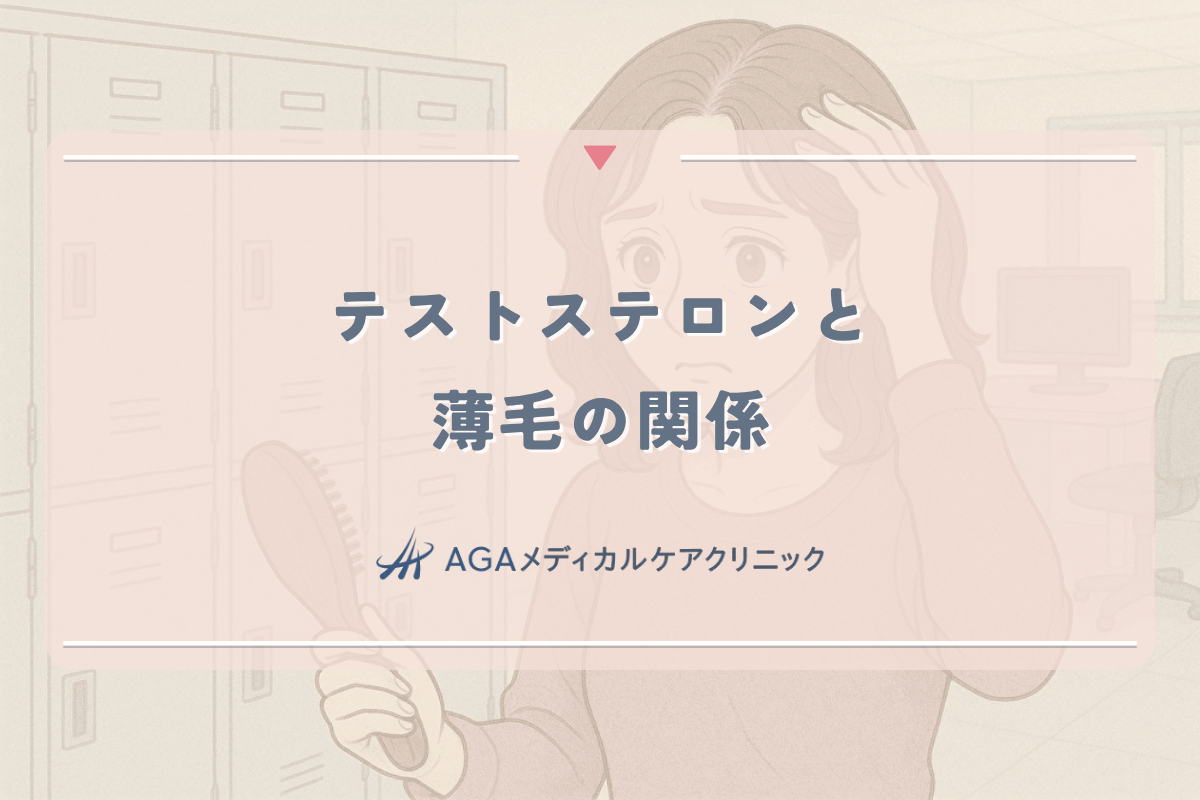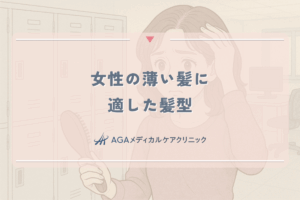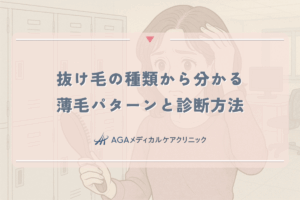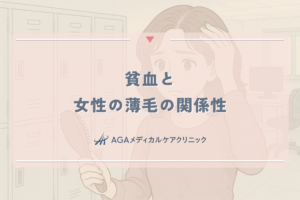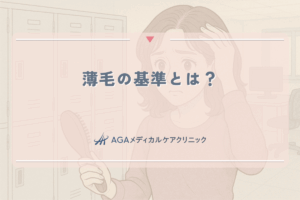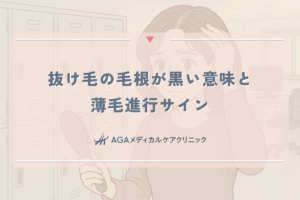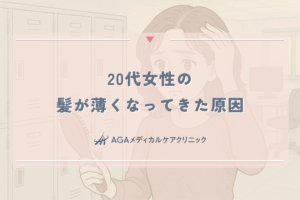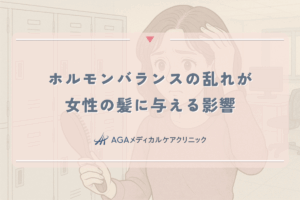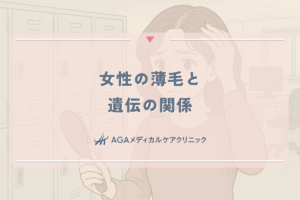髪のパサつきやボリューム低下といった悩みを抱える女性は少なくありません。
原因は一つではありませんが、ホルモンバランスの乱れ、特に男性ホルモンである「テストステロン」が関係している可能性があります。
テストステロンは男性のイメージが強いですが、女性の体内でも作られ、心身の健康維持に重要な役割を担っています。
しかし、そのバランスが崩れると髪の成長に影響を与え、薄毛を引き起こす一因となるのです。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
女性の薄毛とテストステロンの基本
女性の薄毛は、男性ホルモンであるテストステロンが、ある物質に変化することで引き起こされる場合があります。
テストステロンは女性の体にも必要なホルモンですが、そのバランスが崩れると髪の成長に影響を与えます。
テストステロンは男性ホルモンだけではない
テストステロンは一般的に「男性ホルモン」として知られ、筋肉や骨格の発達、性機能の維持など、男性的な特徴を形成する働きを持ちます。
しかし、このホルモンは男性だけのものではありません。女性の体内でも、副腎や卵巣で男性の約5~10%の量が作られています。
女性にとってテストステロンは、意欲や記憶力の維持、健康な骨の形成、そして性欲の維持など、心と体の両面で大切な役割を果たしています。
女性の体内でテストステロンが果たす役割
女性の体内でのテストステロンは、決して悪者というわけではありません。
適度な量のテストステロンは日々の活力を生み出し、社会的な活動への意欲を高める助けとなります。
また、脂肪の燃焼を助けて筋肉量を維持する働きもあり、健康的な体作りをサポートします。
女性ホルモンであるエストロゲンと協調しながら、心身のバランスを保っているのです。
女性の健康に関わる主なホルモン
| ホルモンの種類 | 主な働き | 髪への影響 |
|---|---|---|
| テストステロン | 意欲向上、筋肉・骨の維持 | 過剰になると薄毛の原因物質に変化 |
| エストロゲン | 女性らしい体の形成、自律神経の安定 | 髪の成長を促し、ハリ・コシを保つ |
| プロゲステロン | 妊娠の維持、体温上昇 | ヘアサイクルの成長期を維持する |
なぜテストステロンが女性の薄毛に関係するのか
問題となるのはテストステロンそのものではなく、ホルモンバランスが崩れてテストステロンの作用が相対的に強くなった状態です。
特に、髪の成長を支える女性ホルモン「エストロゲン」が減少すると、テストステロンの影響が目立つようになります。
この状態になると、テストステロンが特定の酵素と結びつき、髪の成長を妨げる強力な物質に変化してしまうのです。
この物質が、女性の薄毛、特に「FAGA(女性男性型脱毛症)」の引き金となります。
テストステロンが髪に与える影響の仕組み
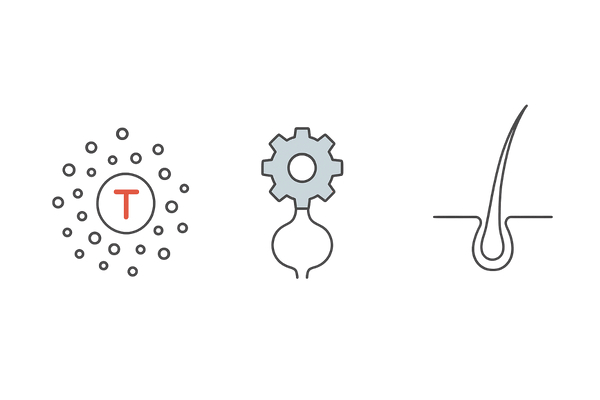
テストステロンは、頭皮に存在する「5αリダクターゼ」という酵素と結びつくことで、薄毛の直接的な原因となるDHT(ジヒドロテストステロン)に変化します。
このDHTが髪の成長サイクルを短縮させ、薄毛を進行させます。
5αリダクターゼとDHT(ジヒドロテストステロン)
薄毛の直接的な原因となるのは、テストステロンが「5αリダクターゼ」という還元酵素と結びついて生成される、より強力な男性ホルモン「DHT(ジヒドロテストステロン)」です。
5αリダクターゼは、頭皮の皮脂腺に多く存在します。
ホルモンバランスが乱れ、テストステロンの量が増えたり、エストロゲンの量が減ったりすると、このDHTの生成が活発になります。
DHTが毛乳頭細胞に与える作用
生成されたDHTは、髪の毛を作り出す「毛母細胞」に栄養を送る「毛乳頭細胞」の受容体と結合します。
この結合が、毛母細胞に対して「髪の成長を止めなさい」という脱毛シグナルを送る引き金になります。
シグナルを受け取った毛母細胞は、分裂・増殖活動を停止してしまい、髪の毛が太く長く成長する前に抜け落ちてしまいます。
DHTが生成される流れ
| 段階 | 物質 | 場所・役割 |
|---|---|---|
| ステップ1 | テストステロン | 血流に乗って全身を巡る |
| ステップ2 | 5αリダクターゼ(還元酵素) | 頭皮の皮脂腺などに存在する |
| ステップ3 | DHT(ジヒドロテストステロン) | テストステロンと酵素が結合して生成される |
ヘアサイクルの乱れと薄毛の進行
健康な髪は、「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルを繰り返しています。成長期は通常2~6年続き、この間に髪は太く長く成長します。
しかし、DHTが脱毛シグナルを出すと、この成長期が数ヶ月から1年程度に短縮されます。
その結果、髪が十分に育たないまま退行期・休止期へと移行し、細く短い毛が増え、抜け毛が目立つようになるのです。
この状態が続くと頭皮全体のボリュームが失われ、地肌が透けて見えるようになります。
女性ホルモン(エストロゲン)との重要な関係
髪の健康は、女性ホルモン「エストロゲン」とテストステロンのバランスによって大きく左右されます。
エストロゲンには髪の成長を促してハリやコシを保つ働きがあり、このホルモンが減少するとテストステロンの影響が強まり、薄毛につながります。
エストロゲンの髪を守る働き
エストロゲンは「美のホルモン」とも呼ばれ、女性らしい丸みのある体つきを作ったり、肌の潤いを保ったりする働きがあります。
髪に対してはヘアサイクルの「成長期」を維持し、髪を長く、太く育てる作用があります。
また、髪のハリやコシ、ツヤを生み出すコラーゲンの生成を促す働きもあり、豊かで美しい髪を保つためには必要不可欠なホルモンです。
ホルモンバランスが崩れるとどうなるか
女性の体内では、エストロゲンとテストステロンが絶妙なバランスを保っています。
しかし、加齢やストレス、生活習慣の乱れなどによってエストロゲンの分泌量が減少すると、このバランスが崩れます。
エストロゲンが減ると相対的にテストステロンの作用が強まり、前述したDHTが生成されやすい環境が生まれてしまうのです。
ホルモンバランスと髪の状態
| ホルモンバランスの状態 | 髪への影響 | 頭皮の状態 |
|---|---|---|
| エストロゲン優位(正常) | ハリ・コシがあり、成長期が長い | 血行が良く、健康的 |
| テストステロン優位(乱れ) | 髪が細くなり、成長期が短い | 皮脂分泌が過剰になりやすい |

テストステロン優位の状態が引き起こすこと
エストロゲンの保護作用が弱まり、テストステロンが優位になると、薄毛の進行だけでなく他にも様々な変化が現れる場合があります。
例えば、皮脂の分泌が活発になり頭皮がべたついたり、ニキビができやすくなったりします。
また、髪質そのものが変化し、うねりやパサつきが気になるようになる方もいます。
これらはすべて、ホルモンバランスの変化が体に与えるサインと捉えられます。
女性のホルモンバランスが乱れる原因
女性のホルモンバランスは、主に加齢(更年期)やストレス、そして睡眠不足や偏った食事といった生活習慣の乱れによって崩れます。
これらの要因は、髪の成長を支える女性ホルモンの減少を招きます。
年齢による変化(更年期など)
女性のライフステージにおいて、ホルモンバランスが最も大きく変動するのが更年期です。40代半ば頃から卵巣機能が低下し始め、エストロゲンの分泌量が急激に減少します。
このエストロゲンの減少が相対的なテストステロン優位の状態を招き、更年期における薄毛(FAGA)の大きな原因となります。
また、産後の抜け毛も、妊娠中に増加していた女性ホルモンが出産後に急減するために起こる一時的なホルモンバランスの乱れが原因です。
ストレスとホルモン分泌
精神的、身体的なストレスは、ホルモンバランスを乱す大きな要因です。
強いストレスを感じると、体はそれに対抗するために「コルチゾール」というホルモンを分泌します。
コルチゾールの分泌が続くとホルモン分泌を指令する脳の視床下部や下垂体の働きが乱れ、エストロゲンの正常な分泌が妨げられてしまうのです。
また、ストレスは血管を収縮させるため頭皮の血行不良を引き起こし、髪の成長に必要な栄養が届きにくくなるという悪影響もあります。
ストレスが髪に与える影響
| 影響の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ホルモンバランスの乱れ | 自律神経が乱れ、エストロゲンの分泌が減少する |
| 血行不良 | 血管が収縮し、頭皮に栄養が届きにくくなる |
| 活性酸素の増加 | 細胞を傷つけ、毛母細胞の働きを低下させる |
睡眠不足や食生活の乱れ
睡眠は体の修復とホルモン分泌の調整に重要な時間です。特に、成長ホルモンは深い眠りの間に最も多く分泌され、髪の毛を含む細胞の修復や再生を促します。
睡眠不足が続くとホルモンバランスが乱れるだけでなく、髪の成長に必要な時間も奪われてしまいます。
同様に、食生活の乱れも深刻な影響を与えます。
髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、血行を促進するビタミンEなどの栄養素が不足すると健康な髪を作れません。
過度なダイエットの影響
美しさを求めて行うダイエットも、方法を間違えると薄毛の原因になります。
なかでも食事を極端に制限するような過度なダイエットは、髪の成長に必要な栄養素が絶対的に不足する事態を招きます。
また、急激な体重減少は体に大きなストレスを与え、ホルモンバランスを著しく乱します。
その結果、生理不順や無月経を引き起こし、エストロゲンの分泌が止まってしまう場合もあり、髪へのダメージは計り知れません。
髪の悩みは本当にテストステロンだけが原因?
髪の悩みはテストステロンだけでなく、心と体の全体的な状態が反映された結果です。
髪の変化を体からのサインと捉え、食生活や精神的なストレスといった、見過ごされがちな根本原因にも目を向けるようにしましょう。
髪の変化は体からのサイン
抜け毛が増える、髪が細くなる、地肌が透けて見える、といった変化は、単に「髪の問題」として片付けるべきではありません。
それは、あなたの体が「ホルモンバランスが乱れているよ」「栄養が足りていないよ」「少し休んで」と送っている重要なメッセージかもしれません。髪は健康のバロメーターとも言われます。
そのサインに耳を傾け、ご自身の生活習慣や心身の状態を振り返る良い機会と捉えてみましょう。
- 睡眠は足りていますか?
- 食事は楽しんでいますか?
- 心から笑う時間はありますか?
- 仕事や家庭で無理をしていませんか?
見過ごされがちな「隠れ男性ホルモン」の影響
テストステロンの量自体は正常でも、その働きを強めてしまうような生活習慣が存在します。これは「隠れ男性ホルモン」を増やす行動といえます。
例えば、血糖値を急激に上げる食事はインスリンの分泌を促し、それが男性ホルモンの働きを活発にさせてしまう場合があります。
また、常に競争やプレッシャーにさらされる環境、過度な筋力トレーニングなども、交感神経を優位にし、体を男性ホルモンが働きやすい状態に傾けてしまう可能性があります。
注意したい生活習慣の例
| カテゴリ | 具体的な行動例 | 体への影響 |
|---|---|---|
| 食事 | 菓子パンや甘いジュースを頻繁に摂る | 血糖値の乱高下を招き、ホルモンバランスを崩す |
| 運動 | 負荷の強すぎる筋力トレーニング中心 | テストステロンの分泌を過剰に刺激する可能性がある |
| メンタル | 常に時間に追われ、緊張状態が続く | 交感神経が優位になり、体を戦闘モードにする |
心と体のつながりと髪への影響
特に女性は、心と体の状態が密接に結びついています。
頑張り屋さんで常に完璧を目指してしまう方は、知らず知らずのうちに心身を緊張させ、男性ホルモンが優位な状態を作り出しているケースがあります。
「女性らしさ」を支えるエストロゲンは、リラックスした副交感神経が優位な状態で分泌されやすい性質があります。
時には肩の力を抜き、自分をいたわる時間を持つ工夫が、巡り巡って健やかな髪を育むことにつながるのです。
ホルモンバランスを整えるセルフケア

ホルモンバランスを整えるためには、栄養バランスの取れた食事や質の高い睡眠、そして上手なストレス解消が基本となります。
日々のセルフケアを意識すると、健やかな髪を育む土台を作れます。
栄養バランスの取れた食事のポイント
髪は私たちが食べたものから作られます。特に、女性ホルモンの働きをサポートし、髪の材料となる栄養素を積極的に摂ることが大切です。
大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、エストロゲンと似た働きをすることで知られています。
また、髪の主成分であるケラチン(タンパク質)や、その合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を良くするビタミンEなどをバランス良く摂取しましょう。
髪の健康をサポートする栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| 大豆イソフラボン | 女性ホルモン様作用 | 豆腐、納豆、豆乳、味噌 |
| タンパク質 | 髪の主成分となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身) |
質の高い睡眠をとるための工夫
睡眠中には、髪の成長を促す「成長ホルモン」や、ホルモンバランスを整える「メラトニン」が分泌されます。単に長く眠るだけでなく、質の高い睡眠の確保が重要です。
就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は、ブルーライトが脳を覚醒させてしまうため控えましょう。
ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、リラックスできる音楽を聴いたりして、心身を休息モードに切り替える習慣をつけるのがおすすめです。
- 就寝1〜2時間前に入浴する
- 寝室の照明を暗くする
- カフェインの摂取は午後に控える
効果的なストレス解消法
ストレスをゼロにするのは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけることはできます。
軽い運動は血行を促進し、気分転換にもなります。ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、心地よいと感じるものを生活に取り入れてみましょう。
また、趣味に没頭する時間や、信頼できる友人と話す時間も、心を解放しストレスを軽減するのに役立ちます。
自分に合った解消法をいくつか持っておくと、心のバランスを保ちやすくなります。
専門クリニックでの検査と治療

セルフケアで改善しない場合は、専門クリニックでの検査が有効です。
血液検査などでホルモン状態を正確に把握し、その結果に基づいて内服薬や外用薬などを組み合わせた、一人ひとりに合った治療を進めます。
どのような検査でホルモン状態を調べるのか
クリニックでは詳細な問診を行い、生活習慣や既往歴などを伺います。その上で、薄毛の原因を探るために必要な検査を実施します。
ホルモンバランスを調べるためには、血液検査が一般的です。
血液中のテストステロンやエストラジオール(エストロゲンの一種)などの値を測定し、ホルモンバランスの状態を客観的に評価します。
クリニックで行う主な検査
| 検査の種類 | 目的 | わかること |
|---|---|---|
| 血液検査 | ホルモン値や栄養状態の確認 | テストステロン値、エストロゲン値、鉄、亜鉛など |
| マイクロスコープ検査 | 頭皮や毛穴の状態を拡大して観察 | 頭皮の色、毛穴の詰まり、毛髪の太さなど |
| 問診 | 生活習慣や悩みの詳細なヒアリング | 薄毛の背景にある要因の推測 |
検査結果に基づく治療の考え方
検査結果が出たら、そのデータと問診の内容を総合的に判断し、一人ひとりの状態に合わせた治療方針を立てます。
例えば、テストステロンの影響が強いと判断された場合は、その働きを抑制する内服薬(スピロノラクトンなど)の使用を検討します。
同時に、髪の成長を直接促すミノキシジルの外用薬や、不足している栄養素を補うサプリメントなどを組み合わせるケースもあります。
大切なのは、一つの方法に頼るのではなく、多角的な方法で根本原因に働きかける取り組みです。
専門医に相談する重要性
薄毛の悩みは非常にデリケートであり、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方が多くいます。
しかし、女性の薄毛には様々な原因が考えられ、正しい診断なくして適切な対策はできません。
専門医に相談すると科学的根拠に基づいた診断を受けられるだけでなく、心理的な不安を軽減し、前向きに治療に取り組めます。
そのために、安心して相談できる、信頼できるクリニックを見つけましょう。
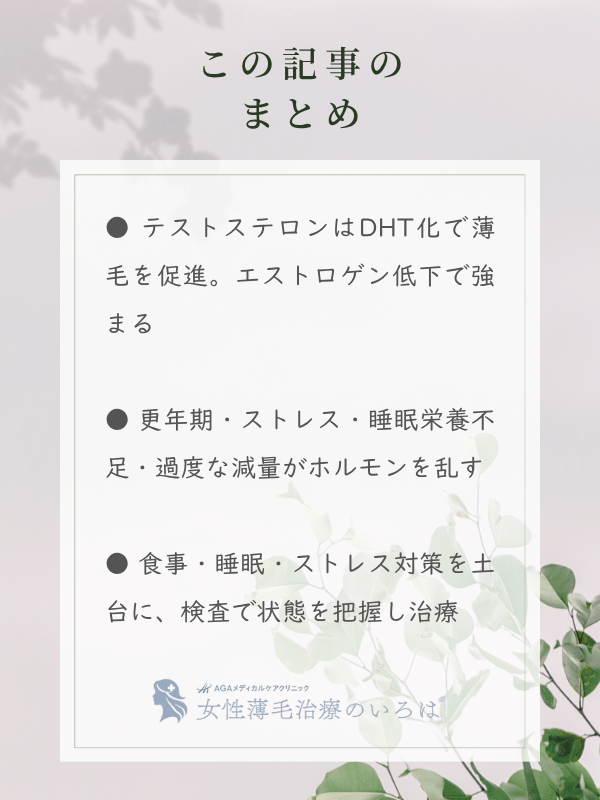
よくある質問
女性の薄毛やホルモン治療について、患者さんから頻繁にいただくご質問にお答えします。
- ピルを飲むと薄毛は改善しますか?
-
低用量ピルには、女性ホルモンを安定させて男性ホルモンの働きを抑制する作用があるため、一部の女性の薄毛(FAGA)に対して改善効果が期待できる場合があります。
ピルに含まれるエストロゲンがヘアサイクルの成長期を維持し、アンドロゲン(男性ホルモン)活性を低下させるため、抜け毛を減らす可能性があります。
ただし、ピルの種類や個人の体質によって効果は異なり、副作用のリスクもあります。必ず医師の診断のもとで処方してもらう必要があります。
- 男性用の育毛剤は女性が使ってもいいですか?
-
男性用育毛剤の中には、女性の使用が推奨されない成分が含まれているものがあります。
なかでもフィナステリドやデュタステリドといった成分は、男性のAGA(男性型脱毛症)治療薬であり、女性、特に妊娠中の女性が使用すると胎児に影響を及ぼす危険性があるため禁忌とされています。
ミノキシジル配合の育毛剤は女性も使用できますが、男性用と女性用では推奨される濃度が異なります。自己判断で使用せず、女性の薄毛に適した製品を医師に相談の上で選びましょう。
- サプリメントでホルモンバランスは整いますか?
-
サプリメントは、あくまで食事で不足しがちな栄養素を補う補助的な役割です。
大豆イソフラボンやチェストベリーといった成分が女性ホルモンのバランスをサポートすると言われていますが、サプリメントだけでホルモンバランスを完全に整えるのは困難です。
また、過剰摂取が逆にバランスを崩す場合もあります。
基本はバランスの取れた食事であり、サプリメントを利用する際は、医師や専門家に相談してからにしましょう。
- 治療を始めたらすぐに効果は出ますか?
-
薄毛治療の効果を実感するには、ある程度の時間が必要です。乱れたヘアサイクルが正常に戻り、新しい髪が成長して目に見える長さになるまでには、少なくとも3~6ヶ月はかかります。
効果の現れ方には個人差があるため、焦らず、医師と相談しながら治療を継続していきましょう。
途中で不安になったり、変化を感じられなかったりする場合も、遠慮なく医師に相談してください。
参考文献
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
CARMINA, Enrico, et al. Female pattern hair loss and androgen excess: a report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019, 104.7: 2875-2891.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.
SKALNAYA, Margarita G.; TKACHEV, Vladislav P. Trace elements content and hormonal profiles in women with androgenetic alopecia. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2011, 25: S50-S53.
VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.
RITTMASTER, Roger S. Clinical relevance of testosterone and dihydrotestosterone metabolism in women. The American journal of medicine, 1995, 98.1: S17-S21.