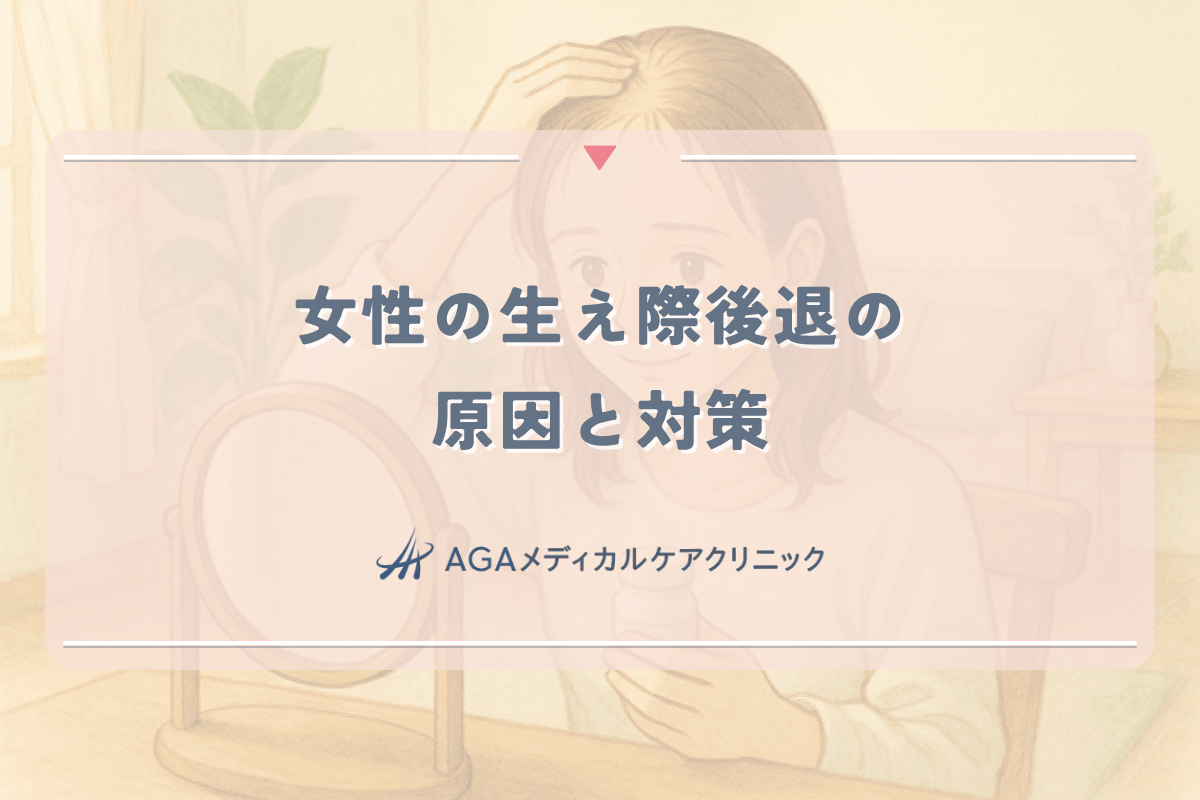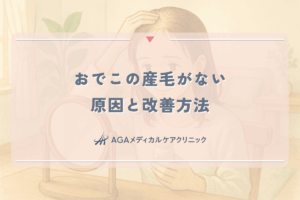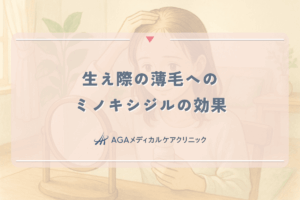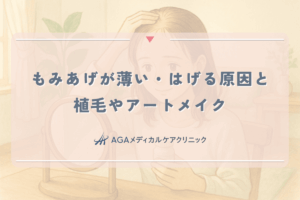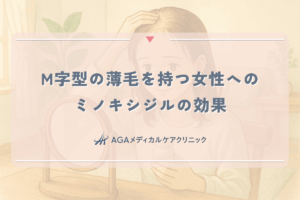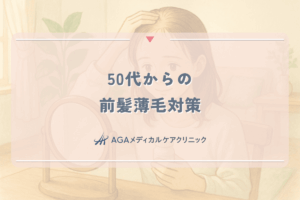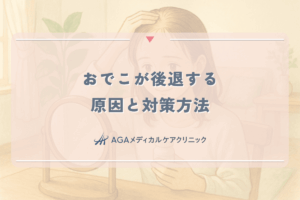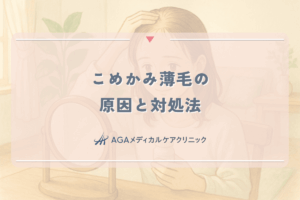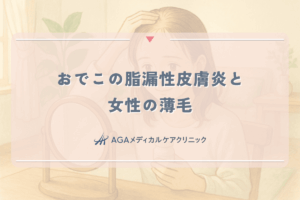生え際の後退は男性特有の悩みと思われがちですが、実は多くの女性が抱える深刻な問題です。
この問題は見た目の印象を大きく左右するため、一人で悩み続けてしまう方も少なくありません。
この記事では、女性の生え際が後退する原因を詳しく解説し、ご自身でできる対策から専門クリニックでの治療法まで分かりやすく紹介します。正しい知識を得て、早期発見と適切な対処につなげましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
女性の生え際後退は珍しくない?M字・U字型だけではない後退のサイン
生え際の後退というと、男性に見られるM字型やU字型の脱毛を想像する方が多いかもしれません。
しかし、女性の生え際後退は、男性とは異なる特徴を持って進行する場合があります。
生え際後退のセルフチェック方法

ご自身の生え際の状態を客観的に把握するために、いくつかの点を確認してみましょう。
鏡を見ながら、以下の項目に当てはまるものがないかチェックしてみてください。一つでも当てはまる場合は、注意が必要なサインかもしれません。
生え際後退のセルフチェック項目
| チェック項目 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| おでこが広くなった | 以前の写真と比べて、眉毛から生え際までの距離が長くなったように感じる。 | 髪型や体重の増減でも印象は変わるため、総合的に判断します。 |
| 生え際の毛が細くなった | 生え際の髪が、他の部分の髪に比べて細く、うぶ毛のようになっている。 | 髪全体のハリやコシの低下も同時に見られることがあります。 |
| 頭皮が透けて見える | 髪をかき上げたときや、分け目から生え際にかけての頭皮が以前より目立つ。 | 特に照明の下で確認すると分かりやすいです。 |
男性とは異なる女性の生え際後退の特徴
男性の薄毛が局所的に進行しやすいのに対し、女性の場合は全体的に髪の密度が低下する「びまん性脱毛症」が一般的です。
生え際に関しても特定の形に後退するのではなく、生え際のラインが全体的に薄くなり、後方へ下がっていくという特徴があります。
このため、初期段階では変化に気づきにくいです。
女性に多い薄毛のパターン
| 薄毛のパターン | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| びまん性脱毛症 | 頭部全体の髪が均等に薄くなる。分け目が目立つようになる。 | 加齢、ホルモンバランスの乱れ、ストレスなど。 |
| 牽引性脱毛症 | 生え際や分け目など、髪が強く引っ張られる部分が薄くなる。 | ポニーテールなど特定の髪型を続けること。 |
| FAGA(女性男性型脱毛症) | 頭頂部を中心に薄くなるが、男性のように完全に禿げることは少ない。 | 女性ホルモンの減少、男性ホルモンの影響。 |
産後の抜け毛との違い
出産を経験した多くの女性が「産後脱毛症」に悩みます。
これは、妊娠中に増加していた女性ホルモンが出産後に急激に減少するために起こる一時的な現象です。通常は産後半年から1年ほどで自然に回復します。
一方、生え際の後退を伴う薄毛はホルモンバランスの乱れが原因であっても、他の要因が複雑に関わっているケースが多く、自然な回復が難しい場合があります。
抜け毛が1年以上続く、あるいは生え際が明らかに後退してきたと感じるときは、産後脱毛症とは異なる原因を考える必要があります。
なぜ生え際が後退するの?考えられる原因
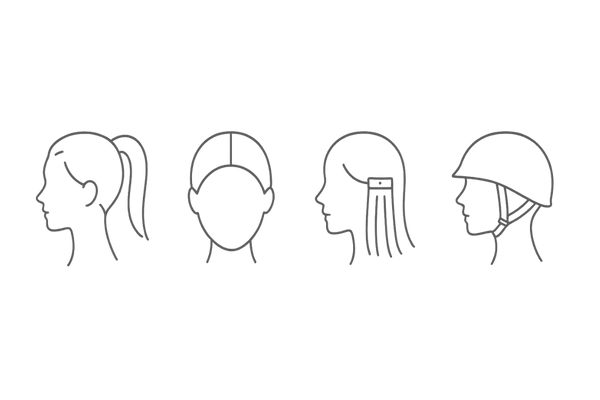
女性の生え際が後退する背景には、様々な原因が潜んでいます。一つの原因だけでなく、複数の要因が絡み合っているケースも少なくありません。
ご自身の生活習慣や体調と照らし合わせながら、原因を探っていきましょう。
牽引性(けんいんせい)脱毛症|ポニーテールが招くリスク
毎日同じ髪型、特にポニーテールやアップスタイルなど髪を強く引っ張るヘアスタイルを続けていると、毛根に継続的な負担がかかります。
この物理的なダメージが原因で、生え際や分け目の髪が抜けやすくなり、薄毛が進行する状態を「牽引性脱毛症」と呼びます。
仕事柄、髪を結ぶ必要がある方や、いつも同じ分け目にしている方は特に注意が必要です。
FAGA(女性男性型脱毛症)とホルモンバランスの乱れ
FAGAは女性男性型脱毛症とも呼ばれ、女性の薄毛の最も一般的な原因の一つです。
加齢などにより女性ホルモンである「エストロゲン」が減少し、相対的に男性ホルモンの影響が強まるために発症します。
エストロゲンは髪の成長を促進してその期間を維持する働きがあるため、このホルモンが減少すると髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまい、薄毛が進行します。
特に頭頂部や生え際に影響が出やすい傾向があります。
生活習慣の乱れが頭皮環境に与える影響
健康な髪は健康な頭皮から生まれます。しかし、不規則な生活や栄養バランスの偏った食事、睡眠不足などは頭皮環境を悪化させる直接的な原因となります。
脂っこい食事や過度なダイエットは髪の成長に必要な栄養素の不足を招き、頭皮の血行不良を引き起こします。
この結果、毛根に十分な栄養が届かなくなり、髪が細くなったり抜けやすくなったりするのです。
頭皮環境を悪化させる生活習慣
| 要因 | 髪への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 栄養の偏り | 髪の主成分であるタンパク質や、成長を助けるビタミン・ミネラルが不足する。 | バランスの取れた食事を心がける。 |
| 睡眠不足 | 髪の成長を促す成長ホルモンの分泌が減少し、頭皮の修復が妨げられる。 | 質の良い睡眠を6〜8時間確保する。 |
| 過度な飲酒・喫煙 | 血行不良を招き、毛根への栄養供給を阻害する。 | 飲酒は適量にし、禁煙を検討する。 |
ストレスと血行不良の関係性
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させる原因となります。
血管が収縮すると頭皮の血行が悪化し、毛根にある毛母細胞の働きが低下します。
毛母細胞は髪の毛を作り出す工場のようなもので、ここへの栄養供給が滞ると健康な髪を育てられなくなり、抜け毛や薄毛につながります。
- 交感神経の優位化
- 血管の収縮
- ホルモンバランスの乱れ
- 睡眠の質の低下
その髪型、大丈夫?生え際への負担を考える
毎日何気なくしているヘアスタイルが、知らず知らずのうちに生え際へダメージを与えている可能性があります。
ここでは、特に注意したいヘアスタイルや習慣について掘り下げていきます。ご自身の髪型が、長期的に見て頭皮にどのような影響を与えるかを考えるきっかけにしましょう。
毎日同じ分け目にしていると起こること
いつも同じ場所で髪を分けていると、その部分の頭皮は紫外線を直接浴びやすくなります。紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こす原因となり、毛根にダメージを与えます。
また、分け目の部分は髪の重みで常に引っ張られている状態にあり、牽引性脱毛症のリスクも高まります。
定期的に分け目を変えるだけで、これらのリスクを分散させられます。
ヘアエクステンションやきつい帽子の影響
おしゃれのために楽しむヘアエクステンションも地毛に重さを加えるため、毛根に大きな負担をかけます。
長期間つけ続け、牽引性脱毛症の原因になっている方も見受けられます。
同様に、サイズの合わないきつい帽子やヘルメットの長時間着用も頭皮の血行を妨げ、蒸れによる頭皮環境の悪化を招くため注意が必要です。
生え際に負担をかける可能性のあるもの
| 項目 | 負担の原因 | 推奨される対策 |
|---|---|---|
| きついポニーテール | 継続的な牽引力 | 結ぶ位置を日によって変える、緩めに結ぶ。 |
| ヘアエクステンション | 重さによる牽引力 | 定期的に休ませる期間を設ける。 |
| きつい帽子・ヘルメット | 圧迫による血行不良、蒸れ | 通気性の良いものを選び、こまめに着脱する。 |
前髪のスタイリングと頭皮への負担
前髪を立ち上げたりカールをつけたりするために、ヘアアイロンやコテを頻繁に使用する方も注意が必要です。
高温が頭皮に近づきすぎると、やけどや乾燥の原因になります。
また、スタイリング剤が毛穴に詰まると炎症を引き起こし、健康な髪の育成を妨げる場合があります。
スタイリング後は、その日のうちにシャンプーでしっかりと洗い流しましょう。
生え際に優しいヘアアレンジの工夫
生え際への負担を減らすためには、少しの工夫が効果的です。
髪を結ぶ際はシュシュなどの柔らかい素材のものを選んだり、結ぶ強さを加減したりするだけでも、毛根への負担が大きく変わります。
休日など、人と会う予定がない日は髪を下ろして頭皮を休ませる日を作るのも良いでしょう。
- 結ぶ位置を毎日変える
- 緩めのヘアアレンジを楽しむ
- 頭皮を休ませる日を作る
早期発見が鍵を握る!生え際後退の進行度

生え際の後退はゆっくりと進行するため、初期の変化に気づくのは難しいかもしれません。
しかし、どのような症状も早期発見・早期対応が改善への近道です。
ここでは、進行度合いを把握するためのポイントと、専門家への相談を考えるべきタイミングについて解説します。
初期症状を見逃さないために
初期段階では、抜け毛の量が少し増えたり、生え際の髪にハリやコシがなくなったように感じたりする程度の変化です。
「疲れているだけかな」と見過ごしてしまいがちですが、このような小さなサインに気づくことが重要です。
シャンプーやブラッシングの際の抜け毛の量、枕についた髪の毛などを意識して確認する習慣をつけましょう。
進行度別の見た目の変化
生え際の後退は、いくつかの段階を経て進行します。
ご自身の状態がどの段階にあるのかを客観的に把握すると、適切な対策を立てる上で役立ちます。
生え際後退の進行度と目安
| 進行度 | 見た目の変化 | 自覚症状 |
|---|---|---|
| 初期 | 生え際のうぶ毛が増え、髪が細くなる。おでこが少し広くなったように感じる。 | 抜け毛の増加、髪のボリュームダウンを感じる。 |
| 中期 | 生え際のラインが明らかに後退し、地肌が透けて見える範囲が広がる。 | 髪型で隠すのが難しくなってくる。他人から指摘されることもある。 |
| 後期 | 生え際から頭頂部にかけて、全体的に地肌が目立つようになる。 | ウィッグの使用などを検討する段階。 |
専門医への相談を検討するタイミング
セルフケアを続けても改善が見られないときや、抜け毛が急激に増えた場合、地肌が明らかに目立つようになってきたと感じる場合は専門クリニックへの相談をおすすめします。
自己判断で誤ったケアを続けると、かえって症状を悪化させてしまう可能性もあります。
専門医はマイクロスコープで頭皮の状態を詳しく診察し、原因を特定した上で、一人ひとりに合った治療法を提案します。
自宅でできる生え際後退のセルフケアと予防法

専門的な治療と並行して、あるいは予防のために、日々の生活の中でできることはたくさんあります。
今日から始められるセルフケアで、健康な髪を育む土台となる頭皮環境を整えましょう。
頭皮マッサージの正しい方法
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐして血行を促進するのに効果的です。
ただし、爪を立てたり強くこすりすぎたりすると、かえって頭皮を傷つけてしまうので注意が必要です。
指の腹を使い、優しく頭皮を動かすようなイメージで行いましょう。シャンプーの際に行うとリラックス効果も高まります。
- 指の腹を使う
- 頭皮全体を優しく動かす
- 気持ち良いと感じる強さで
栄養バランスの取れた食事の重要性
髪は、私たちが食べたものから作られます。なかでも髪の主成分であるタンパク質、頭皮の健康を保つビタミン、そして血行を促進するミネラルは意識して摂取したい栄養素です。
特定の食品だけを食べるのではなく、様々な食材をバランス良く取り入れるようにしましょう。
健やかな髪を育む栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の毛の主成分となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、毛母細胞の分裂を促す。 | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を活発にし、皮脂の分泌を調整する。 | 豚肉、うなぎ、玄米 |
質の高い睡眠と成長ホルモン
睡眠中には、体の細胞を修復して髪の成長を促す「成長ホルモン」が分泌されます。特に、入眠後の最初の3時間は、成長ホルモンの分泌が最も活発になるゴールデンタイムと言われています。
睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長に悪影響を及ぼします。
就寝前にスマートフォンを見るのをやめる、リラックスできる環境を整えるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
育毛剤の選び方と使い方
市販の女性用育毛剤には、頭皮の血行を促進する成分や、毛根に栄養を与える成分が含まれています。
選ぶ際は、ご自身の頭皮の状態(乾燥肌、脂性肌など)に合ったものを選ぶと良いです。
また、育毛剤は薬ではないため、即効性を期待するのではなく毎日継続して使用することが重要です。使用する際は頭皮が清潔な状態で、用法用量を守って正しく使いましょう。
クリニックでの専門的な治療法
セルフケアだけでは改善が難しいときや、より積極的に治療を進めたい方は、専門クリニックでの治療が選択肢となります。
クリニックでは、医師の診断のもと医学的根拠に基づいた効果的な治療を受けられます。
内服薬・外用薬による治療
女性の薄毛治療では、主にミノキシジルを含む外用薬や、スピロノラクトンなどの内服薬が用いられます。
ミノキシジルは毛母細胞を活性化させ、発毛を促進する効果が認められている成分です。スピロノラクトンは男性ホルモンの働きを抑制し、抜け毛を防ぐ効果が期待できます。
これらの医薬品は、医師の処方が必要です。
クリニックで処方される主な治療薬
| 治療薬の種類 | 主な効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| ミノキシジル外用薬 | 血行を促進し、発毛を促す。 | 初期脱毛が起こることがある。継続的な使用が必要。 |
| スピロノラクトン内服薬 | 男性ホルモンの影響を抑え、抜け毛を減らす。 | 医師の診断のもと、副作用に注意しながら服用する。 |
| サプリメント | 髪の成長に必要な栄養素を補給する。 | 治療の補助として用いられる。 |
メソセラピーなどの注入治療
注入治療は、発毛・育毛に有効な成分を注射や特殊な機器を用いて頭皮に直接注入する方法です。
内服薬や外用薬と比べて、有効成分を直接毛根に届けられるため、より効果を実感しやすいです。
治療法によって注入する成分や費用、痛みの感じ方などが異なりますので、医師とよく相談して決定します。
治療法の選択と費用感
薄毛治療は原因や進行度、そしてご自身の生活スタイルや予算に合わせて、適した方法を選択するのが重要です。
一般的に薄毛治療は健康保険の適用外となり、自由診療となります。そのため、クリニックによって費用は異なります。
治療を始める前にカウンセリングで治療内容や期間、総額の費用について十分に説明を受け、納得した上で進めましょう。
治療効果を高めるために知っておきたいこと
クリニックでの治療を始めれば、すぐに髪が生えてくるわけではありません。効果を実感するまでには、ある程度の時間が必要です。
治療効果を最大限に引き出し、途中で挫折しないためにも、知っておきたいポイントがいくつかあります。
治療期間の目安と心構え
ヘアサイクル(毛周期)の関係上、治療効果を実感し始めるまでには、早くても3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。
すぐに変化が見られないからといって自己判断で治療を中断してしまうと、それまでの努力が無駄になってしまいます。焦らず、根気強く治療を続けるという心構えが重要です。
初期脱毛の理解と対処
ミノキシジルなどの治療薬を開始した初期段階で、一時的に抜け毛が増える場合があります。これを「初期脱毛」と呼びます。
乱れたヘアサイクルが正常に戻る過程で、古い髪が新しい強い髪に押し出されるために起こる好転反応です。
通常は治療開始後1〜2ヶ月で収まりますが、不安に感じる場合は、ためらわずにクリニックに相談しましょう。
生活習慣改善との相乗効果
専門的な治療は非常に効果的ですが、その効果を最大限に高めるためには、日々の生活習慣の見直しが欠かせません。
バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動やストレス管理などを心がけると、体の中から髪が育ちやすい環境を整えられます。
これによって治療効果が出やすくなるだけでなく、治療終了後も健康な状態を維持しやすくなります。
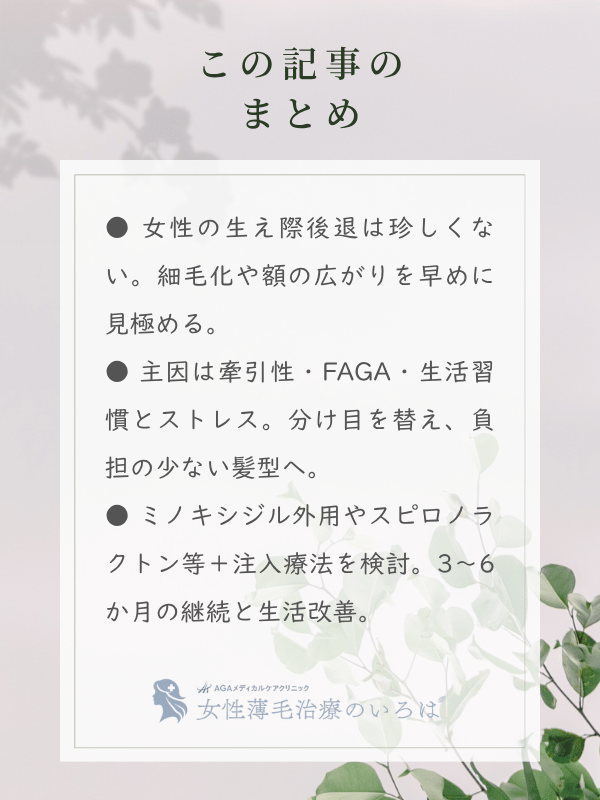
よくある質問
さいごに、女性の生え際後退や薄毛治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 治療をやめると元に戻りますか?
-
FAGAなどの進行性の脱毛症の場合、治療を完全にやめてしまうと、時間をかけて元の状態に戻っていく可能性があります。
そのため、症状が改善した後も、良い状態を維持するためのメンテナンス治療(薬の量を減らす、通院頻度を減らすなど)を続けるのが一般的です。
生活習慣の改善を継続することも、再発防止に役立ちます。
- 遺伝はどのくらい関係しますか?
-
薄毛になりやすい体質が遺伝することは、研究で示されています。ご家族に薄毛の方がいる場合、ご自身もその体質を受け継いでいる可能性はあります。
しかし、遺伝が全てではありません。発症には、ホルモンバランスや生活習慣、ストレスなど後天的な要因が大きく関わります。
遺伝的素因があっても早期から適切なケアを行うと、発症を遅らせたり、進行を緩やかにしたりできます。
- 市販の育毛剤とクリニックの薬の違いは何ですか?
-
最も大きな違いは、配合されている有効成分とその濃度です。市販の育毛剤は、医薬部外品に分類され、主に「抜け毛の予防」や「育毛」を目的としています。
一方、クリニックで処方される薬は医薬品であり、「発毛」を促す効果が医学的に認められています。
- 治療に痛みはありますか?
-
メソセラピーなどの注入治療は、注射針によるチクッとした痛みを感じる場合がありますが、痛みを最小限に抑えるための冷却や麻酔クリームなどの工夫を行います。
痛みの感じ方には個人差がありますので、不安な方はカウンセリングの際に遠慮なくご相談ください。
参考文献
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.
MOUNSEY, Anne L.; REED, Sean W. Diagnosing and treating hair loss. American family physician, 2009, 80.4: 356-362.