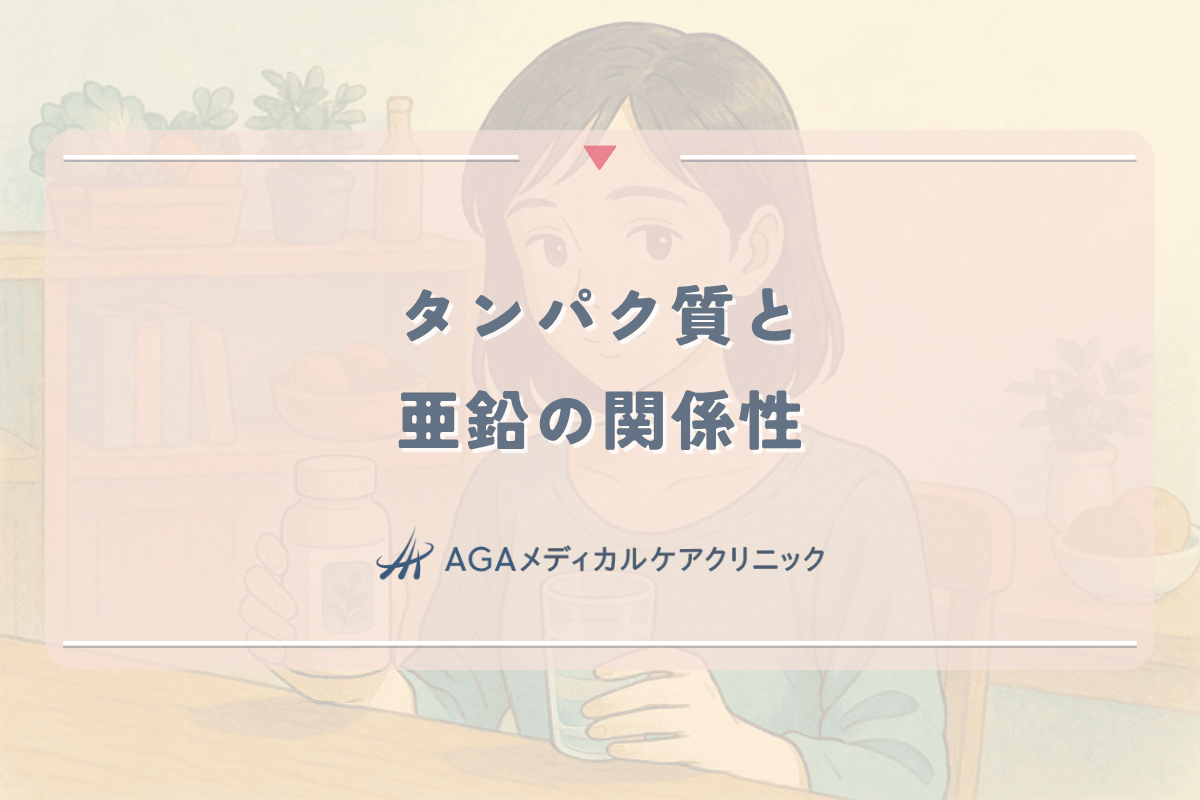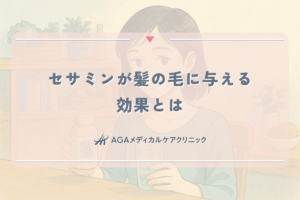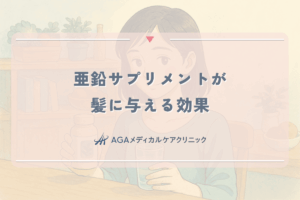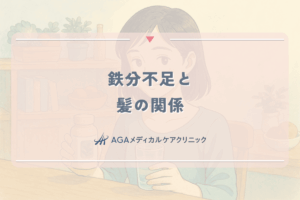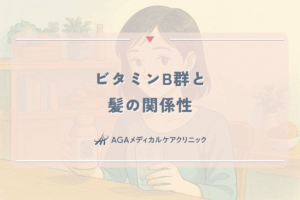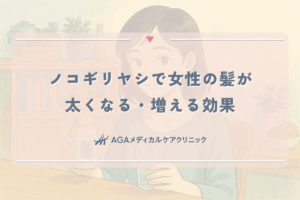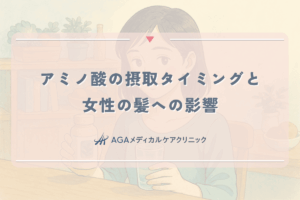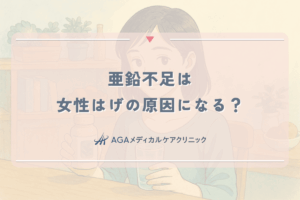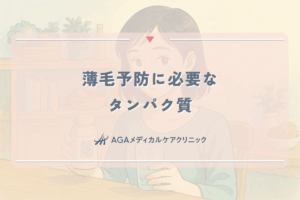女性の薄毛や髪質の変化は、加齢だけでなく、日々の栄養状態が深く関わっています。
美しく健やかな髪を育む上で、タンパク質と亜鉛は車の両輪のような存在です。
この記事では、なぜこの二つの栄養素が女性の髪にとってこれほど重要なのか、その関係性を紐解きながら、日々の生活で実践できる具体的な食事のポイントを解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪の栄養素として「タンパク質」と「亜鉛」が注目され理由
多くの栄養素が体の健康を支えていますが、髪の悩みに関しては、タンパク質と亜鉛の重要性を訴える専門家が多いです。
これらは、単に体に良いというだけでなく、髪の生成サイクルに直接的に関与するからです。
女性の薄毛の悩みは食事から見直せる
女性の薄毛の原因はホルモンバランスの変化や遺伝、ストレスなど多岐にわたりますが、栄養不足が根本的な原因、あるいは状態を悪化させる一因となっているケースは少なくありません。
髪は生命維持に直接関わる組織ではないため、体内の栄養が不足すると、まず髪への供給が後回しにされます。このため、食生活の乱れが髪の状態に顕著に現れるのです。
逆に言えば、食事内容の見直しは、ご自身で取り組める最も基本的で重要な薄毛対策の一つです。
多くの栄養素の中でも特に重要な二つの柱
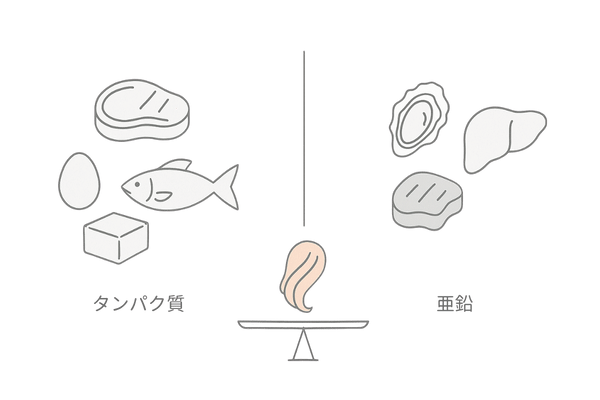
髪の健康にはビタミンや鉄分など様々な栄養素が必要ですが、その中でもタンパク質は髪そのものを作る材料であり、亜鉛はその材料を使って髪を組み立てるための「職人」のような役割を担います。
どちらが欠けても、健やかな髪は育ちません。この二つを「髪の栄養の二大柱」として意識するのが、効果的なヘアケアの基本です。
髪の健康を支える主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、細胞分裂を促す | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| 鉄分 | 頭皮に酸素を運び、栄養を行き渡らせる | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
髪のサイクルと栄養のタイミング
髪は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。栄養状態が良好であれば、成長期が長く保たれ、太く健康な髪が育ちます。
しかし、タンパク質や亜鉛が不足すると髪が十分に成長できずに早く退行期や休止期へ移行し、結果として細く弱い髪が増え、薄毛が進行する原因となります。
日々の栄養摂取が、このサイクルを正常に保つために重要です。
髪の主成分「ケラチン」とタンパク質の深い関係
私たちの髪の材料は「ケラチン」というタンパク質です。実に髪の99%がこのケラチンで構成されています。
つまり、タンパク質の摂取は、美しい髪を維持するための土台作りそのものと言えます。良質なタンパク質を十分に摂る習慣が、ハリとコシのある髪への第一歩です。
髪の99%はタンパク質でできている
ケラチンは18種類のアミノ酸が結合して作られる硬いタンパク質です。
食事から摂取したタンパク質は一度体内でアミノ酸に分解され、その後、ケラチンとして再合成されて髪となります。
このため、日々の食事でタンパク質が不足すると髪の材料が足りなくなり、髪が細くなったり、伸びるのが遅くなったり、切れ毛や枝毛の原因になったりします。
ケラチンを構成するアミノ酸とは
ケラチンを構成するアミノ酸の中でも、特に重要なのが「メチオニン」や「シスチン」といった含硫アミノ酸です。これらは髪の強度や弾力性に関わる重要な成分です。
メチオニンは体内で合成できない必須アミノ酸のため、食事から必ず摂取する必要があります。
これらのアミノ酸がバランス良く含まれているかどうかが、タンパク質の質を決めます。
ケラチンを構成する代表的なアミノ酸
| アミノ酸の種類 | 特徴 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| メチオニン(必須) | 含硫アミノ酸。体内でシスチンの材料になる。 | 鶏肉、牛肉、マグロ、牛乳 |
| シスチン(非必須) | 含硫アミノ酸。髪の強度や硬さに関わる。 | 牛肉、羊肉、オートミール |
| グルタミン酸 | ケラチンに最も多く含まれるアミノ酸。 | 肉類、魚介類、乳製品 |
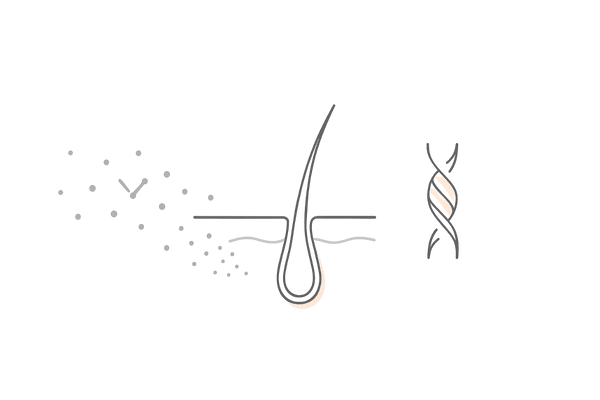
良質なタンパク質を選ぶポイント
良質なタンパク質とは、必須アミノ酸をバランス良く含むものを指します。
一般的に、肉や魚、卵などの動物性タンパク質はアミノ酸バランスに優れています。しかし、植物性タンパク質も、複数の食品を組み合わせるとアミノ酸バランスを補えます。
大切なのは、動物性と植物性を偏りなく、多様な食品から摂取することです。
- 動物性タンパク質(肉、魚、卵、乳製品)
- 植物性タンパク質(大豆製品、穀物、ナッツ)
タンパク質の働きを支える縁の下の力持ち「亜鉛」
十分なタンパク質を摂取しても、それだけでは髪は作られません。摂取したタンパク質(アミノ酸)を髪の毛という形に作り変える過程で、亜鉛が極めて重要な役割を果たします。
亜鉛は、いわば建設現場の監督のような存在です。材料であるタンパク質があっても、亜鉛という監督がいなければ、髪という建物は完成しないのです。
亜鉛がなければタンパク質は髪になれない
亜鉛の最も重要な働きのひとつが、タンパク質の合成です。
食事で摂ったタンパク質がアミノ酸に分解された後、ケラチンとして再合成される際に、亜鉛を必要とする酵素が働きます。
このため亜鉛が不足すると、せっかくタンパク質を摂っても効率よく髪に変えられず、結果として髪の成長が滞ってしまいます。
酵素の活性化と亜鉛の役割
私たちの体内には数千種類の酵素が存在し、生命活動を支えています。
亜鉛は、そのうちの約300種類もの酵素の構成成分となったり、働きを活性化させたりします。髪の生成に関わる酵素もその一つです。
亜鉛は髪だけでなく、皮膚や爪の健康維持にも関わるため、不足すると全身に影響が現れる可能性があります。
細胞分裂を促し、頭皮環境を整える
髪は、毛根にある毛母細胞が分裂を繰り返して成長します。亜鉛には、この細胞分裂を正常に促す働きがあります。
亜鉛が不足すると毛母細胞の分裂が滞り、新しい髪が作られにくくなったり、髪の成長期が短くなったりします。これは、抜け毛の増加や髪の細毛化に直結します。
亜鉛の吸収を左右する要因
| 分類 | 要因 | 詳細 |
|---|---|---|
| 吸収を助ける | ビタミンC、クエン酸 | 亜鉛を水に溶けやすい形に変え、吸収しやすくする。(例:レモン、梅干し) |
| 吸収を助ける | 動物性タンパク質 | 亜鉛と一緒に摂取することで吸収率が向上する。 |
| 吸収を妨げる | フィチン酸、タンニン | 穀物や豆類、コーヒーやお茶に含まれ、亜鉛と結合して吸収を阻害する。 |
タンパク質と亜鉛が不足すると髪に起こるサイン

体は正直です。特にタンパク質や亜鉛のような重要な栄養素が不足すると、髪や爪、肌といった部分にサインが現れやすくなります。
これらのサインに早めに気づき、食生活の見直すことが、深刻な状態になるのを防ぐ鍵です。ご自身の髪や体に、以下のような変化がないかチェックしてみましょう。
髪が細くなる、ハリやコシが失われる
これは最もよく見られる初期サインの一つです。髪の主成分であるケラチンの生成がうまくいかないため、一本一本の髪が十分に太く成長できません。
以前と比べて髪に力強さがなくなり、スタイリングがまとまりにくくなったと感じる場合は、栄養不足を疑う必要があります。
抜け毛が増える、ヘアサイクルへの影響
亜鉛不足は髪の成長期を短くし、休止期にとどまる髪の割合を増やします。これにより、シャンプーやブラッシングの際の抜け毛が目立つようになります。
1日の抜け毛が100本程度であれば正常範囲ですが、明らかにそれ以上増えたと感じる場合は注意が必要です。
タンパク質・亜鉛不足による身体のサイン
| 部位 | 主なサイン | 栄養素との関連 |
|---|---|---|
| 髪 | 細毛、抜け毛、ツヤの低下 | ケラチン合成の低下、毛母細胞の分裂不全 |
| 爪 | 白い斑点、割れやすい、凹凸 | 爪もケラチンが主成分であり、亜鉛不足で異常が出やすい |
| 肌 | 肌荒れ、傷の治りが遅い | 皮膚のターンオーバー(新陳代謝)に亜鉛が必要 |
髪以外の身体からのサイン(爪や肌の不調)
髪の変化と同時に、爪や肌の不調が現れる場合もあります。
爪は髪と同じくケラチンでできているため、タンパク質が不足すると割れやすくなります。また、爪に白い斑点ができるのは、典型的な亜鉛不足のサインと言われています。
さらに、亜鉛は皮膚の新陳代謝にも関わるため、不足すると肌荒れや傷の治りが遅くなる方も多いです。
ストレス社会で生きる女性へ|栄養素だけでは語れない髪の悩み
私たちは日々、仕事や家庭、人間関係など様々なストレスにさらされています。実は、この「心」の状態が、髪の健康に予想以上に大きな影響を与えています。
どんなに優れた栄養を摂っても、心が疲弊していると、その効果は半減してしまうかもしれません。
心の不調が身体と髪に与える影響
強いストレスを感じると、私たちの体は緊張状態になります。このとき、自律神経のうち交感神経が優位になり、血管が収縮します。
特に頭皮の毛細血管は細いため、この影響を受けやすく、血行不良に陥りがちです。
血行が悪くなると、せっかく食事から摂ったタンパク質や亜鉛などの栄養素が、髪を育てる毛母細胞まで十分に届かなくなってしまいます。
自律神経の乱れと頭皮の血行不良
慢性的なストレスは、自律神経のバランスそのものを乱します。
リラックスしているときに働く副交感神経への切り替えがうまくいかず、常に体がこわばり、血行が悪い状態が続いてしまうのです。
この状態は頭皮が硬くなる原因にもなり、栄養を運ぶルートが滞るだけでなく、髪が育つ土壌である頭皮環境そのものが悪化してしまいます。
心と髪の健康をつなぐセルフケア
| ケアの種類 | 具体的な方法 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| リラクゼーション | 深呼吸、瞑想、アロマテラピー | 副交感神経を優位にし、心身の緊張を和らげる |
| 適度な運動 | ウォーキング、ヨガ、ストレッチ | 全身の血行を促進し、ストレスホルモンを減少させる |
| 質の良い睡眠 | 就寝前のスマホを控える、寝室環境を整える | 成長ホルモンの分泌を促し、細胞の修復を助ける |
食事を楽しむ心の余裕が栄養吸収を高める
「髪のためにこれを食べなければ」と義務感で食事をしている方も見受けられます。
実は、リラックスして「おいしい」と感じながら食事をすることは、栄養の吸収率を高める上でとても重要です。食事を楽しむと副交感神経が優位になり、消化器官の働きが活発になります。
栄養を摂ること自体をストレスにせず、心から食事を楽しむ時間を持つ工夫が、結果的に髪への最高の栄養補給となるのです。
毎日の食事で賢く摂取|タンパク質と亜鉛が豊富な食品
髪の健康は、日々の食生活の積み重ねによって作られます。タンパク質と亜鉛を意識的に食事に取り入れると、内側から髪を育てられます。
幸い、これらの栄養素は特別な食材ではなく、私たちの身近な食品に多く含まれています。毎日の献立に上手に組み込むための具体的な食品を確認していきましょう。
動物性タンパク質を多く含む食品
動物性タンパク質は、髪の材料となる必須アミノ酸をバランス良く含んでいるのが特徴です。
特に赤身の肉や魚は、タンパク質と同時に亜鉛や鉄分も摂取できるため、髪にとっては非常に効率の良い食材です。
脂肪分の少ない部位を選ぶと、よりヘルシーに摂取できます。
動物性タンパク質が豊富な食品例
| 食品カテゴリー | 具体的な食品名 | ポイント |
|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉(赤身)、豚ヒレ肉、鶏むね肉 | 亜鉛や鉄分も豊富。皮や脂身は控えめに。 |
| 魚介類 | マグロ、カツオ、サケ、アジ | 良質な油(EPA・DHA)も同時に摂取できる。 |
| 卵・乳製品 | 鶏卵、牛乳、チーズ、ヨーグルト | 完全栄養食品と呼ばれる卵はビタミンも豊富。 |
植物性タンパク質を多く含む食品
植物性タンパク質は、低脂肪で食物繊維が豊富な点が魅力です。
なかでも大豆製品は「畑の肉」と呼ばれるほどタンパク質が豊富で、女性ホルモンと似た働きをするイソフラボンも含まれています。
動物性タンパク質と組み合わせて、バランス良く摂ると良いでしょう。
- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳、きな粉)
- 穀物(オートミール、玄米、キヌア)
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)
亜鉛を効率的に摂れる食品群
亜鉛は体内で作り出せないミネラルで、吸収率も比較的低いので、意識して摂取する必要があります。
「海のミルク」と呼ばれる牡蠣は、亜鉛の含有量が突出して多いことで知られています。
また、レバーや牛肉の赤身など、動物性食品に多く含まれる傾向があります。
亜鉛が豊富な食品例
| 食品カテゴリー | 具体的な食品名 | 100gあたりの亜鉛含有量の目安 |
|---|---|---|
| 魚介類 | 牡蠣(生) | 約14.5mg |
| 肉類 | 豚レバー、牛レバー | 約6.9mg / 約3.8mg |
| 肉類 | 牛肉(赤身) | 約4.0mg |
栄養素を効率よく髪に届けるための食事の工夫
良い栄養素をただ摂取するだけでなく、それを体がしっかりと吸収し、髪まで届けるための「食べ方」を工夫するのも重要です。
少しの知識と工夫で、同じ食事でも栄養の効率は大きく変わります。
バランスの良い食事の基本「まごわやさしい」
日本の伝統的な食生活に基づいた、バランスの良い食事の合言葉です。
これらの食材を意識して食事に取り入れるとタンパク質や亜鉛だけでなく、ビタミンやミネラル、食物繊維など、髪と体の健康に必要な栄養素を自然と網羅できます。
| 合言葉 | 食材 | 栄養素 |
|---|---|---|
| ま | 豆類(タンパク質、ミネラル) | タンパク質、ミネラル |
| ご | ごま・ナッツ類 | 良質な脂質、ビタミンE |
| わ | わかめなど海藻類 | ミネラル、ヨウ素 |
| や | 野菜類 | ビタミン、ミネラル |
| さ | 魚 | タンパク質、EPA・DHA |
| し | しいたけなどきのこ類 | ビタミンD、食物繊維 |
| い | いも類 | 炭水化物、ビタミンC |
吸収率を上げる食べ合わせのコツ

栄養素には、一緒に摂ると吸収率が上がる組み合わせがあります。
例えば、亜鉛はビタミンCやクエン酸と一緒に摂ると吸収されやすくなります。また、鉄分はビタミンCや動物性タンパク質と一緒に摂るのが効果的です。
これらの組み合わせを意識すると、無駄なく栄養を体に取り込めます。
調理法で変わる栄養素の摂取効率
調理法によっても、摂取できる栄養素の量は変わります。
水溶性のビタミンは茹でるとお湯に溶け出してしまいますが、スープごといただく調理法なら無駄なく摂取できます。
亜鉛などのミネラルは比較的熱に強いですが、食材の組み合わせを工夫すると、より効率的な摂取が可能です。
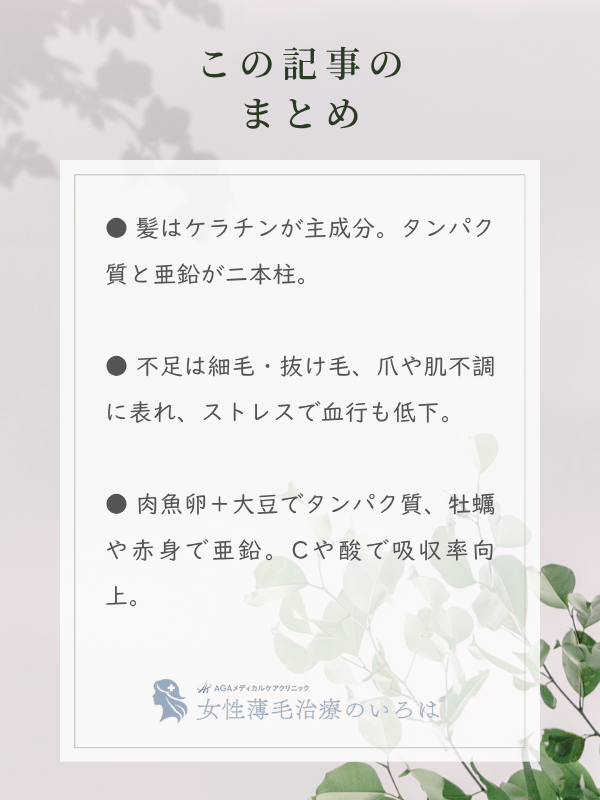
よくある質問(Q&A)
タンパク質や亜鉛の摂取に関して、患者さんからよくいただく質問とその回答をまとめました。日々の食生活の参考にしてください。
- プロテインを飲めば髪は増えますか?
-
プロテインはタンパク質を手軽に補給できる便利な補助食品ですが、プロテインを飲むだけで髪が直接的に増えるわけではありません。
髪の成長にはタンパク質だけでなく、亜鉛やビタミン、ミネラルなど多様な栄養素が関わるバランスの取れた食事が基本です。
食事全体のバランスを見直した上で、タンパク質が不足しがちな場合に補助として利用するのが良いでしょう。
- 亜鉛はどのくらい摂取すれば良いですか?
-
亜鉛の摂取推奨量は、年齢や性別によって異なります。18~74歳の女性は8mgが推奨量で、耐容上限量は35mgです。
過剰に摂取すると、他のミネラル(特に銅)の吸収を妨げるなどの副作用が出る可能性もあるため、サプリメントなどで補う場合は注意が必要です。まずは食事からの摂取を基本としましょう。
- 食事改善を始めてから効果が出るまでの期間は?
-
髪にはヘアサイクルがあるため、食事改善の効果が目に見えて現れるまでには、早くても3ヶ月から6ヶ月程度の時間が必要です。
髪は1ヶ月に約1cmしか伸びないため、栄養状態が改善されてから生えてくる新しい髪が、ある程度の長さになるまで待つ必要があります。焦らず、根気強く続けていきましょう。
- 白髪の予防にも効果はありますか?
-
白髪の主な原因は、メラニン色素を作る細胞(メラノサイト)の働きの低下や消失です。
亜鉛は、このメラノサイトの働きを活性化させる酵素に関与していると考えられています。また、タンパク質は健康な頭皮環境の維持に必要です。
タンパク質と亜鉛は今ある白髪を黒くできるわけではないものの、これから生えてくる髪を健康に保ち、白髪の増加を緩やかにする一助となる可能性があります。
参考文献
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GONZALEZ-REIMERS, E., et al. Hair zinc, copper and iron: relationships with quality of diet, tobacco smoking and nutritional status. Trace Elements & Electrolytes, 2008, 25.1.
GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.
GOLDBERG, Lynne J.; LENZY, Yolanda. Nutrition and hair. Clinics in dermatology, 2010, 28.4: 412-419.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
O’CONNOR, Kelly; GOLDBERG, Lynne J. Nutrition and hair. Clinics in Dermatology, 2021, 39.5: 809-818.