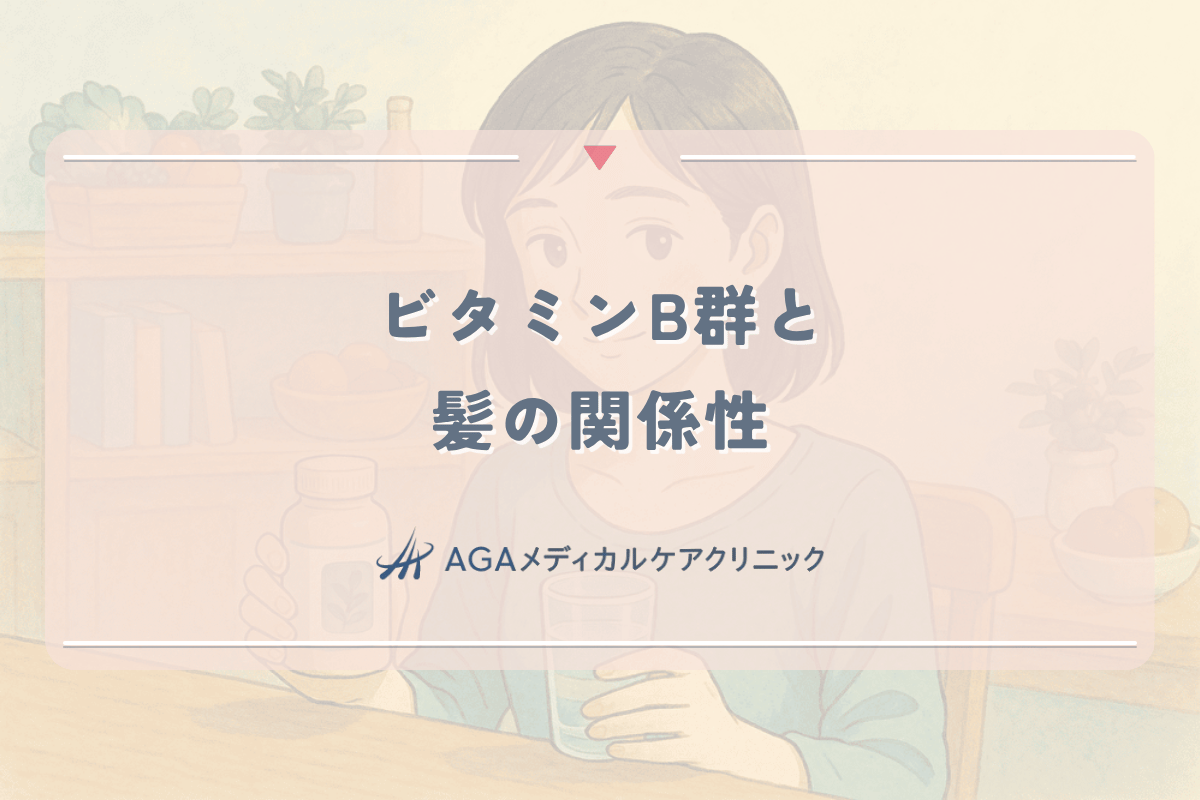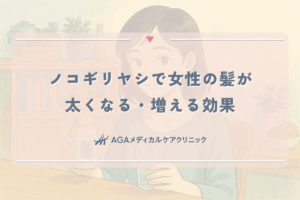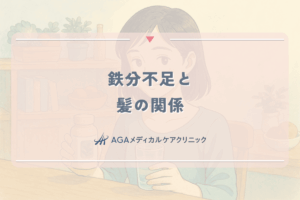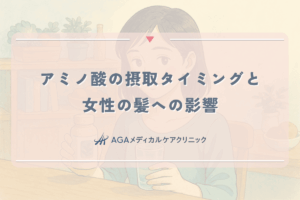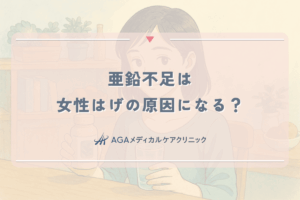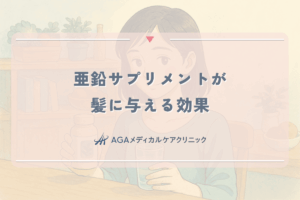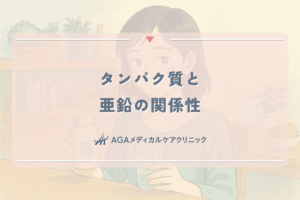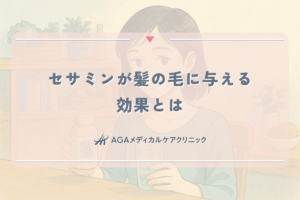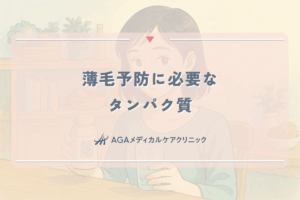髪質の変化やボリュームの低下、抜け毛の増加には、もしかしたら食生活の乱れによる栄養不足が関係しているかもしれません。
特に「ビタミンB群」は、健康な髪を育む上で非常に重要な役割を担う栄養素です。
この記事では、なぜビタミンB群が髪に必要なのか、不足するとどのような影響があるのかを詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
ビタミンB群とは?髪の成長を支える重要な栄養素
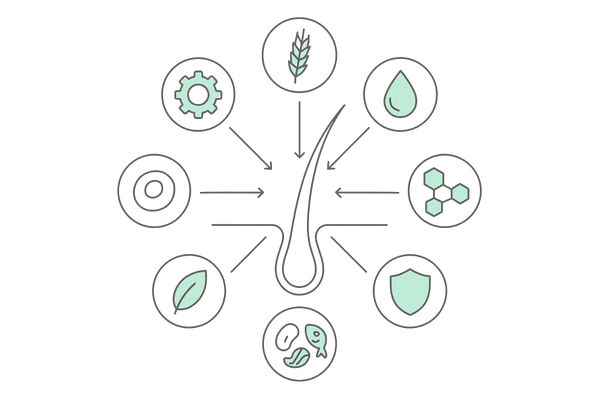
ビタミンB群とは、髪の主成分であるタンパク質の代謝や頭皮の健康維持に重要な8種類の水溶性ビタミンの総称です。
髪の成長を支えるエネルギー生成の過程で補酵素として働き、不足すると抜け毛や髪質の低下に直接つながります。
8種類の栄養素からなるビタミンB群
「ビタミンB群」と一括りに呼ばれますが、これは単一のビタミンではありません。ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの8種類の栄養素の総称です。
これらはそれぞれ異なる働きを持ちながらも、互いに協力し合って体内で機能する特徴があります。
そのため、どれか一つだけを摂取するのではなく、バランスよく全てのB群ビタミンを摂取する工夫が重要です。
ビタミンB群の種類と主な働き
| ビタミンB群の種類 | 主な働き |
|---|---|
| ビタミンB1 | 糖質の代謝を助け、エネルギーを生成する |
| ビタミンB2 | 脂質の代謝を助け、皮膚や粘膜の健康を維持する |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助け、髪の主成分の生成に関わる |
| ビタミンB12 | 赤血球の生成を助け、毛母細胞へ酸素を運ぶ |
| ナイアシン | 血行を促進し、頭皮の健康を保つ |
| パントテン酸 | ストレスへの抵抗力を高め、髪の健康をサポートする |
| 葉酸 | 細胞分裂を助け、新しい髪の毛の生成を促す |
| ビオチン | アミノ酸の代謝に関わり、ケラチンの生成を助ける |
水に溶けやすい水溶性ビタミンの性質
ビタミンB群はすべて「水溶性ビタミン」に分類されます。これは、水に溶けやすく、体内に長時間蓄積できないという性質を意味します。
一度にたくさん摂取しても、余分な量は尿として体外に排出されてしまいます。そのため、健康な髪を維持するためには、毎日こまめに食事から補給し続ける必要があります。
この性質への理解が、ビタミンB群と上手に付き合う第一歩です。
エネルギー代謝の補酵素としての役割
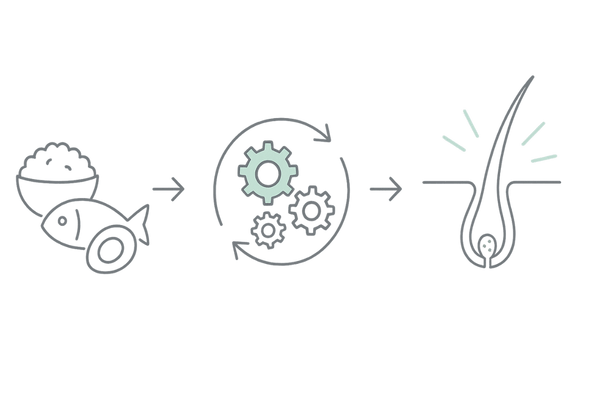
私たちの体は、食事から摂取した糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変えて活動しています。このエネルギー代謝の過程で、ビタミンB群は「補酵素」として働きます。
補酵素とは、代謝をスムーズに進めるための潤滑油のようなものです。ビタミンB群が不足すると、エネルギーが効率よく作られなくなり、体のさまざまな機能に影響が出ます。
もちろん、髪の毛を作る毛母細胞の活動もエネルギーを必要とするため、ビタミンB群の不足は抜け毛や髪質の低下に直結します。
ビタミンB群の不足が引き起こす髪への影響
ビタミンB群が不足すると髪の主成分であるケラチンの生成が滞り、頭皮環境が悪化します。
その結果、毛母細胞へ十分な栄養が届かなくなり、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする直接的な原因となります。
髪の主成分「ケラチン」の生成が滞る
髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。このケラチンは、食事から摂取したタンパク質が体内でアミノ酸に分解され、再合成されることで作られます。
特にビタミンB6は、このアミノ酸の代謝を助ける重要な役割を担っています。
ビタミンB6が不足するとケラチンの合成がスムーズに行われなくなり、髪が細くなったり、弱くなったり、成長が遅れたりする原因となります。
ビタミンBと髪の毛の関係において、このタンパク質合成のサポートは中心的な役割です。
ケラチン生成に関わる主なビタミンB群
| ビタミン | 役割 | 不足による影響 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | アミノ酸の代謝を促進 | 髪の成長遅延、細毛 |
| ビオチン | アミノ酸の働きを補助 | 髪質の低下、抜け毛 |
| 葉酸 | 細胞分裂を活性化 | 新しい髪の生成が滞る |
頭皮環境の悪化を招く
健康な髪は健康な頭皮から生まれます。ビタミンB2やナイアシンは、皮膚や粘膜の健康を維持し、頭皮のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つ働きがあります。
これらのビタミンが不足すると頭皮の皮脂バランスが崩れやすくなります。皮脂が過剰に分泌されると毛穴が詰まり、炎症やかゆみを引き起こす場合があります。
逆に、皮脂が不足すると頭皮が乾燥し、フケの原因となります。このような頭皮環境の悪化は健康な髪の成長を妨げ、ビタミンBと抜け毛の問題に直接つながります。
毛母細胞への栄養供給が不十分になる
髪の毛は、毛根にある「毛母細胞」が分裂を繰り返して成長します。毛母細胞が活発に働くためには、血液を通じて十分な酸素と栄養が供給される必要があります。
ビタミンB12と葉酸は、血液中の赤血球を作る上で重要な役割を果たします。これらのビタミンが不足すると貧血気味になり、全身への酸素供給能力が低下します。
その結果、頭皮の血行も悪化して毛母細胞が必要な栄養を受け取れなくなり、髪の成長が阻害されたり、抜け毛が増えたりする原因となります。
美髪育成に特に重要な3つのビタミンB群
ビタミンB群は8種類すべてが大切ですが、その中でも特に髪の健康との関連が深いとされる3つのビタミンがあります。ビオチン、パントテン酸、そしてビタミンB6です。
ケラチンの合成サポートやストレスへの対抗、タンパク質の代謝促進といった、健康な髪を維持するための中心的な役割を担っています。
ビオチン(ビタミンB7)|髪の構成成分をサポート
ビオチンは皮膚や髪の健康を保つビタミンとして知られ、「美のビタミン」とも呼ばれる場合があります。
主な働きは、髪の主成分であるケラチンの合成を助けることです。アミノ酸の代謝をサポートし、強くしなやかな髪を作る土台を支えます。
また、頭皮の血行を促進する効果も期待でき、毛根に栄養を届けやすくします。
ビオチンは腸内細菌によっても合成されますが、食生活の乱れや抗生物質の服用などで不足するケースがあります。
ビオチンを多く含む食品
| 食品カテゴリ | 具体的な食品例 |
|---|---|
| 卵類 | 鶏卵(特に卵黄) |
| レバー類 | 鶏レバー、豚レバー |
| ナッツ類 | アーモンド、くるみ、ピーナッツ |
| 魚介類 | アサリ、イワシ、サバ |
パントテン酸(ビタミンB5)|ストレス対策と代謝の正常化
パントテン酸はストレスに対抗するためのホルモン(副腎皮質ホルモン)の合成に関わっています。
ストレスは血管を収縮させ、頭皮の血行を悪化させるため、髪の成長にとって大敵です。パントテン酸を十分に摂取すると、ストレスによる髪へのダメージを和らげるのに役立ちます。
また、糖質、脂質、タンパク質の三大栄養素すべての代謝に関与し、細胞のエネルギー生成を助けて毛母細胞の働きを活性化させます。
ビタミンB6|タンパク質の再合成に必要
前述の通り、ビタミンB6はタンパク質の代謝に深く関わる栄養素です。食事から摂ったタンパク質をアミノ酸に分解し、それを材料にして髪の毛(ケラチン)を再合成する過程で中心的な役割を果たします。
ビタミンB6が不足すると、いくらタンパク質を摂取しても効率よく髪の材料として利用できません。また、皮脂の分泌をコントロールする働きもあり、頭皮の健康を保つためにも重要です。
ビタミンbと髪の問題を考える上で、摂取した栄養を「使える形」にするビタミンB6の働きは忘れてはなりません。
ストレス社会で生きる女性とビタミンB群の深い関係

ストレスの多い現代社会で生きる女性は、髪の健康に重要なビタミンB群を大量に消費しやすい傾向にあります。
ストレス対抗ホルモンの生成にビタミンB群が使われるため、髪を育てるための栄養が不足しがちになり、抜け毛や髪質の低下につながるのです。
ストレスがビタミンB群を大量に消費する現実
ストレスを感じると、私たちの体はそれに対抗するために「抗ストレスホルモン」を分泌します。
実は、このホルモンを合成する過程で、ビタミンB群(特にパントテン酸やビタミンB6)が大量に消費されます。
つまり、精神的なプレッシャーや多忙な毎日が続くと、髪を育てるために使われるはずだったビタミンB群がストレス対策に優先的に使われてしまうのです。
これが、頑張っている女性ほど髪の悩みを抱えやすい一因と考えられます。
「しっかり栄養を摂っているはずなのに髪の状態が良くならない」と感じる方は、ストレスによる栄養素の消費量を考慮する必要があるかもしれません。
ストレスを感じた時に消費されやすい栄養素
| 栄養素 | 理由 |
|---|---|
| ビタミンB群 | 抗ストレスホルモンの合成に必要 |
| ビタミンC | 抗ストレスホルモンの合成に必要 |
| マグネシウム | 神経の興奮を鎮めるために消費される |
乱れがちな食生活が追い打ちをかける
忙しい日々の中では、食事を簡単なもので済ませてしまうときも少なくないでしょう。
しかし、精製された炭水化物(白米、パン、麺類)や加工食品中心の食事では、ビタミンB群が不足しがちです。特に、糖質をエネルギーに変える際にはビタミンB1が大量に消費されます。
甘いものや炭水化物が好きな方は、知らず知らずのうちにビタミンB1を消耗し、エネルギー不足から毛母細胞の働きが鈍ってしまう可能性があります。
このように、ストレスによる消費と食事からの摂取不足という二重の要因が、髪の栄養状態を悪化させているのです。
心と髪のつながりを理解し自分をいたわることが大切
髪は「血余(けつよ)」とも呼ばれ、東洋医学では血液の状態を反映するものと考えられています。
心身のストレスは自律神経を乱し、血行を悪化させます。つまり、心の状態が直接的に髪の健康に影響を与えるのです。
ビタミンB群の摂取を心がけるのはもちろん重要ですが、同時に、ご自身の心が何を感じているかに耳を傾け、リラックスする時間を持つ工夫も同じくらい大切なヘアケアです。
栄養面からの働きかけと、心身をいたわるセルフケアの両方に取り組むと、根本的な改善へつながります。
食事から効率よく摂取する!ビタミンB群が豊富な食品
ビタミンB群を効率よく摂取するには、レバーや豚肉、青魚などの動物性食品と、玄米や豆類といった植物性食品をバランスよく食事に取り入れましょう。
多様な食材から摂取すると、8種類のビタミンB群を過不足なく補給できます。
動物性食品に多いビタミンB群
ビタミンB群のなかでもビタミンB12は、主に動物性食品に含まれています。肉類や魚介類、卵や乳製品などを食事に取り入れると効果的です。
- 豚肉(特にヒレやモモ)
- レバー(鶏、豚、牛)
- 魚類(うなぎ、かつお、まぐろ)
- 卵
特にレバーは「ビタミンの宝庫」とも呼ばれ、ほとんどのビタミンB群を豊富に含んでいます。
代表的な動物性食品と含まれる主要なビタミンB群
| 食品 | 特に豊富なビタミンB群 |
|---|---|
| 豚レバー | B2, B6, B12, ナイアシン, パントテン酸, 葉酸, ビオチン |
| うなぎ | B1, B2, B12, ナイアシン |
| かつお | B6, B12, ナイアシン |
植物性食品からの摂取も忘れずに
動物性食品だけでなく、植物性食品にもビタミンB群は含まれています。玄米や全粒粉パンなどの精製されていない穀物、豆類、ナッツ類、緑黄色野菜は良い供給源です。
これらの食品は食物繊維も豊富なため、腸内環境を整え、栄養素の吸収を助ける効果も期待できます。
調理法による栄養素の損失に注意
ビタミンB群は水溶性であり、熱に弱い性質を持つものもあります。そのため、調理法によってはせっかくの栄養素が失われてしまう場合があります。
煮込み料理の場合は、栄養素が溶け出した煮汁ごと食べられるスープやシチューなどがおすすめです。
また、炒め物のような加熱時間が短く、水分を使わない調理法も効率的です。生で食べられる野菜はサラダなどで積極的に取り入れましょう。
調理法によるビタミンB群の損失比較(イメージ)
| 調理法 | 栄養素の残りやすさ | ポイント |
|---|---|---|
| 生 | ◎ | 損失が最も少ない |
| 蒸す・炒める | ○ | 短時間加熱で損失を抑える |
| 茹でる・煮る | △ | 煮汁ごと摂取する工夫を |
サプリメントを上手に活用するポイント
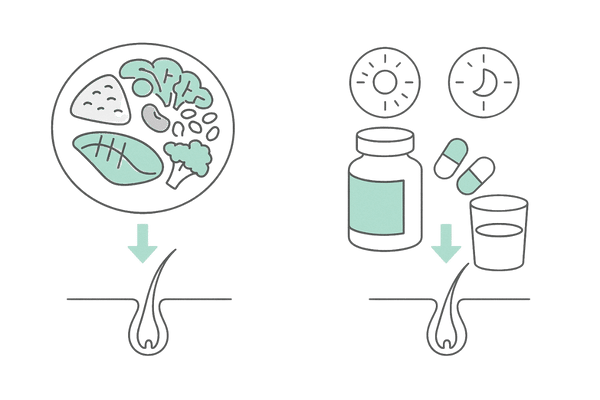
食事から十分にビタミンB群を摂取するのが理想ですが、多忙な生活の中では難しい場合もあります。そのような時には、サプリメントを補助的に活用するのも一つの方法です。
ただし、やみくもに摂取するのではなく、ポイントを押さえて賢く利用することが大切です。
単体ではなく「ビタミンBコンプレックス」を選ぶ
ビタミンB群は、互いに協力し合って働くという性質があります。
そのため、ビオチンだけ、葉酸だけといった単体のサプリメントを摂取するよりも、8種類のビタミンB群がバランスよく配合された「ビタミンBコンプレックス」と呼ばれるタイプの製品を選ぶのがおすすめです。
製品を選ぶ際は成分表示を確認し、複数のB群ビタミンが含まれているかチェックしましょう。
摂取のタイミングと量
ビタミンB群は水溶性で体内に蓄積できないため、一度に大量に摂取するよりも、複数回に分けて摂取するほうが効果的です。
多くの製品では1日の摂取目安量が記載されていますが、可能であれば朝食後と夕食後など、2回に分けて飲むと体内の濃度を一定に保ちやすくなります。
エネルギー代謝を助ける働きがあるため、活動が始まる朝に摂取するのも良いでしょう。必ず製品に記載された目安量を守り、過剰摂取は避けてください。
サプリメント選びのチェック
- 複数のビタミンB群が含まれているか
- 添加物が少なく、品質が信頼できるか
- 1日の摂取目安量が適切か
まずは医師や専門家に相談を
サプリメントは手軽に利用できますが、個人の体質や健康状態によっては合わない場合もあります。すでに何らかの治療を受けている方や、他の薬を服用している方は、飲み合わせに注意が必要です。
薄毛や抜け毛の悩みが深い場合は、自己判断でサプリメントに頼る前に、まずはクリニックで医師に相談すると良いでしょう。
血液検査などで栄養状態を正確に把握し、一人ひとりに合ったアドバイスを受けると改善しやすいです。
ビタミンB群の効果を高める生活習慣
ビタミンB群の効果を最大限に引き出すためには、栄養補給に加えて生活習慣の改善が欠かせません。
質の良い睡眠、血行を促進する適度な運動、そして腸内環境を整える食生活を心がけると、摂取した栄養が効率よく髪に届くようになります。
質の良い睡眠を確保する
髪の毛は私たちが眠っている間に成長します。特に、入眠後最初に訪れる深いノンレム睡眠中に成長ホルモンが多く分泌され、細胞の修復や再生が活発に行われます。
睡眠不足が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられます。
毎日決まった時間に就寝・起床し、寝る前はスマートフォンなどの強い光を避けるなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。
適度な運動で血行を促進する
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な運動は、全身の血行を促進する効果があります。
血行が良くなるため頭皮の末端にある毛細血管まで酸素と栄養が届きやすくなり、毛母細胞の働きが活発になります。
また、運動はストレス解消にもつながり、ビタミンB群の無駄な消費を防ぐことにも役立ちます。無理のない範囲で、日常生活に運動を取り入れる習慣をつけましょう。
血行促進におすすめの栄養素
運動と同時に、血行を促進する栄養素の摂取もおすすめです。
| 栄養素 | 働き | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| ビタミンE | 血管を広げ、血流を改善する | アーモンド、アボカド、かぼちゃ |
| EPA/DHA | 血液をサラサラにする | 青魚(サバ、イワシ、アジ) |
| 鉄分 | 酸素を運ぶヘモグロビンの材料 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |
腸内環境を整える
ビタミンB群の中には、腸内細菌によって合成されるものもあります。そのため、腸内環境を良好に保つと、ビタミンB群の安定した供給につながります。
発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など)や食物繊維(野菜、きのこ、海藻など)を積極的に摂取し、善玉菌が優位な腸内環境を目指しましょう。
腸の健康は、栄養素の吸収率を高める上でも非常に重要です。
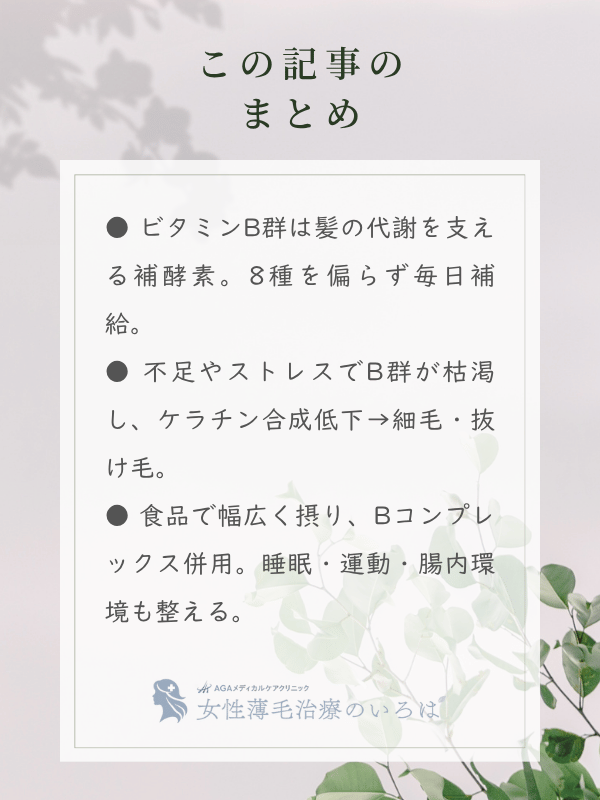
ビタミンB群と髪に関するよくある質問
さいごに、患者さんからよく寄せられるビタミンB群と髪に関する質問にお答えします。
- ビタミンB群を摂取しすぎると副作用はありますか
-
過剰摂取による副作用の心配は少ないです。ビタミンB群は水溶性ビタミンのため、体内で余った分は尿として排出される性質があります。
そのため、通常の食事や一般的なサプリメントの利用で過剰症になるリスクは低いと考えられています。
ただし、一部のビタミン(ナイアシン、ビタミンB6など)を極端に大量摂取した場合には、一時的な皮膚の赤みや神経障害などが報告されています。
サプリメントを利用する際は、必ず製品に記載された1日の摂取目安量を守りましょう。
- 効果はどのくらいの期間で感じられますか
-
効果を実感できるまでの期間には個人差があります。髪の毛には「ヘアサイクル」という成長の周期があり、新しい髪が生まれてから抜け落ちるまでには数年かかります。
栄養状態が改善されても、すぐに全ての髪が入れ替わるわけではありません。一般的には、食生活や生活習慣を見直してから、早くても3ヶ月から6ヶ月程度の継続が推奨されます。
まずは、新しく生えてくる髪の根元部分のハリやコシの変化に注目してみてください。焦らずに、じっくりと体質改善に取り組む努力が重要です。
- 他の栄養素との組み合わせで気をつけることはありますか
-
亜鉛やタンパク質との組み合わせを意識することをおすすめします。髪の主成分であるケラチンはタンパク質から作られますので、まずは十分なタンパク質を摂取するのが基本です。
そして、そのタンパク質を髪の毛に再合成する過程で、ビタミンB群と共に「亜鉛」も重要な役割を果たします。
亜鉛が不足すると、せっかく摂取したタンパク質やビタミンB群がうまく活用されません。
ビタミンB群を意識する際は、タンパク質(肉、魚、大豆製品など)と亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉など)もバランスよく食事に取り入れるように心がけてください。
参考文献
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.
TRÜEB, Ralph M. Nutrition for Healthy Hair. New York: Springer, 2020.
TURLIER, Virginie, et al. Assessment of the effects of a hair lotion in women with acute telogen effluvium: a randomized controlled study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35: 12-20.
WANG, Ruilong, et al. Micronutrients and Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. Molecular Nutrition & Food Research, 2024, 68.22: 2400652.
NICHOLS, Anna J., et al. An open-label evaluator blinded study of the efficacy and safety of a new nutritional supplement in androgenetic alopecia: a pilot study. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2017, 10.2: 52.
KLEIN, Elizabeth J., et al. Supplementation and hair growth: a retrospective chart review of patients with alopecia and laboratory abnormalities. JAAD international, 2022, 9: 69-71.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
ARIAS, Eva Maria, et al. A Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Clinical Trial to Assess the Efficacy of a Nutritional Supplement in Female Androgenic Alopecia. Dermatologic Therapy, 2023, 2023.1: 3527895.