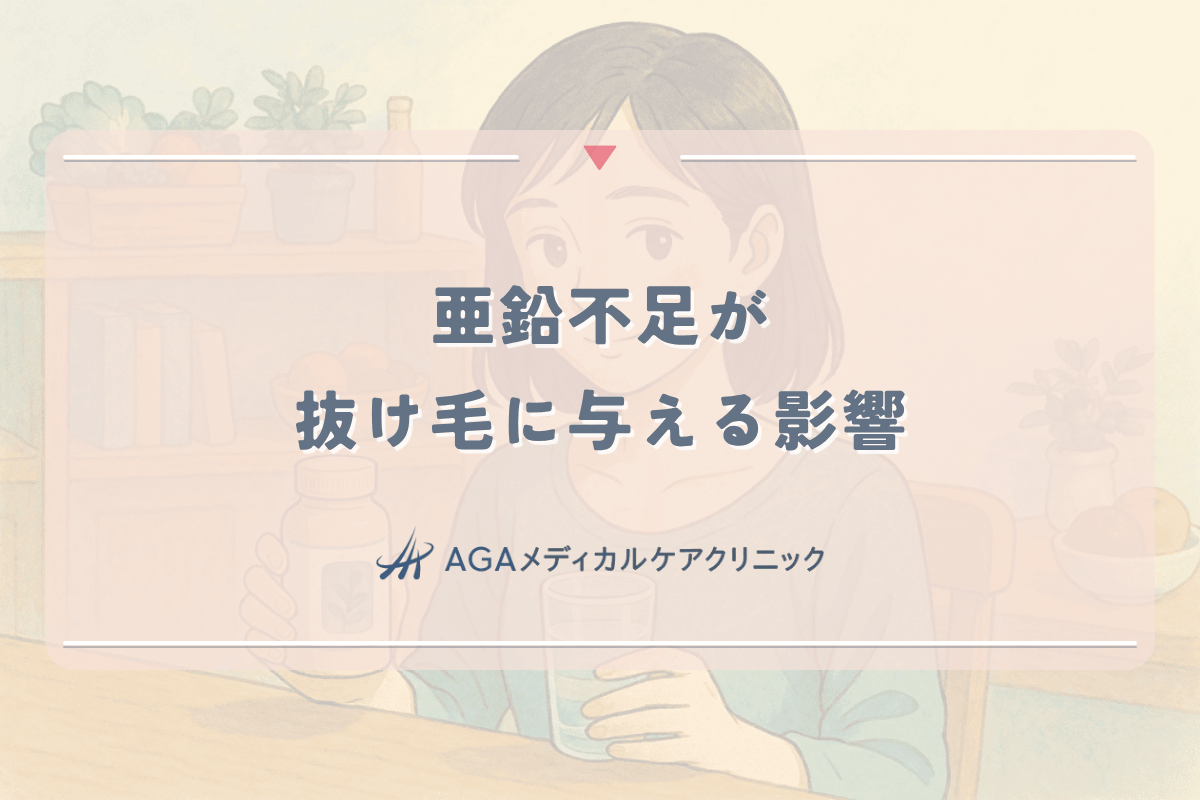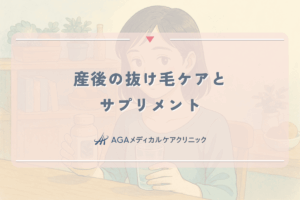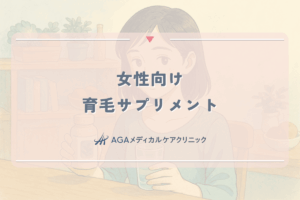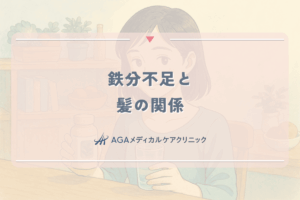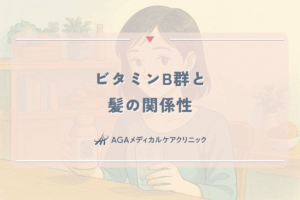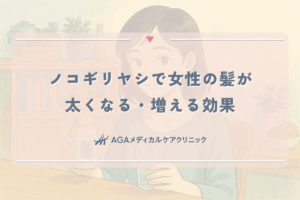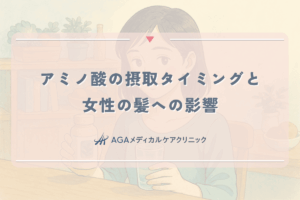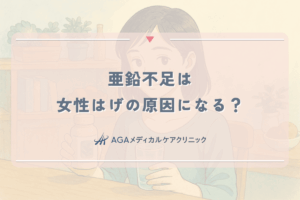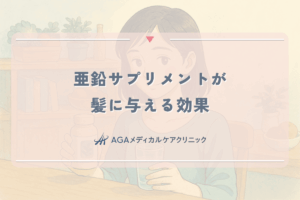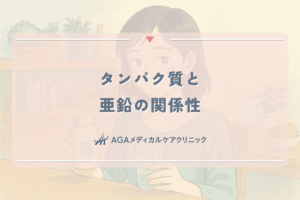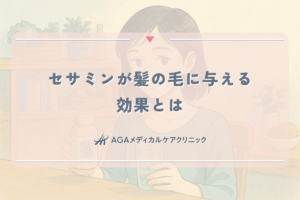シャンプーやブラッシング時の抜け毛が増えた、髪のボリュームが減ってきたと感じる方もいるでしょう。そのお悩みは、もしかしたら「亜鉛不足」が原因かもしれません。
亜鉛は美しい髪を育むために必要不可欠な栄養素ですが、特に女性は日々の生活の中で不足しがちです。
この記事では、なぜ亜鉛が女性の髪にとって重要なのか、不足するとどのような症状が現れるのか、そして今日から始められる効果的な対策方法まで、専門的な知見から詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
そもそも亜鉛とは?女性の体と髪に大切な働き
亜鉛は私たちの体内に存在する「必須ミネラル」の一つです。
体重60kgの成人女性の体内には約1.5gの亜鉛が存在し、筋肉や骨、皮膚や肝臓、脳など、全身の細胞に分布しています。体内で作り出せないため、食事から継続的に摂取することが重要です。
新しい細胞が作られる場所で重要な役割を果たしており、美しい髪や肌、健康な体を維持するために欠かせない栄養素なのです。
美しい髪を育む「必須ミネラル」
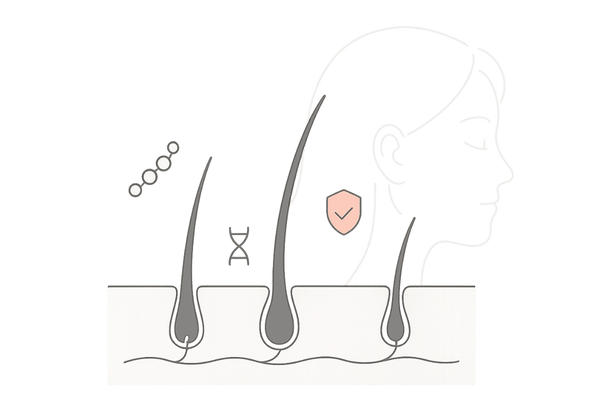
亜鉛が「必須ミネラル」と呼ばれる理由は、生命維持や体の成長に欠かせないにもかかわらず、体内で合成できないためです。
タンパク質の合成や細胞分裂など、300種類以上もの酵素を活性化させる働きを担っています。
この酵素の働きが、私たちが食べたものをエネルギーに変えたり、新しい細胞に生まれ変わらせたりする上で中心的な役割を果たします。
髪の毛も日々新しく生まれ変わる細胞の集まりですから、亜鉛の働きが直接的に髪の健康状態に影響を与えるのです。
髪の主成分「ケラチン」の合成をサポート
私たちの髪の毛の約90%は、「ケラチン」というタンパク質で構成されています。
食事から摂取したタンパク質は一度アミノ酸に分解され、体内で再びケラチンとして再合成されます。この再合成の工程で、亜鉛は接着剤のような重要な役割を担います。
どれだけ良質なタンパク質を摂取しても亜鉛が不足しているとアミノ酸を効率よくケラチンに変換できず、結果として作られる髪の毛は細くもろく、抜けやすいものになってしまいます。
正常なヘアサイクルを維持する細胞分裂の促進
髪の毛は、毛根の奥にある「毛母細胞」が分裂を繰り返して成長します。この細胞分裂が活発に行われると髪が伸び、健康な状態が保たれます。
亜鉛は、この細胞分裂を正常に行うために必要な酵素の働きを助けます。
亜鉛が不足すると毛母細胞の活動が鈍くなり、髪の成長期が短縮されたり、休止期が長引いたりします。このヘアサイクルの乱れが、薄毛や抜け毛の直接的な原因となるのです。
亜鉛の主な働き
| 働き | 内容 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| タンパク質の合成 | アミノ酸からタンパク質を組み立てる際の酵素の構成成分となる。 | 髪の主成分であるケラチンの生成を促し、丈夫な髪を育む。 |
| 細胞分裂の促進 | DNAの合成に関わり、新しい細胞が生まれるのを助ける。 | 毛母細胞の分裂を活発にし、髪の成長とヘアサイクルを正常に保つ。 |
| 抗酸化作用 | 体内の活性酸素を除去する酵素の構成成分となる。 | 頭皮の老化を防ぎ、健康な頭皮環境を維持する。 |
なぜ?多くの女性が「隠れ亜鉛不足」に陥る理由
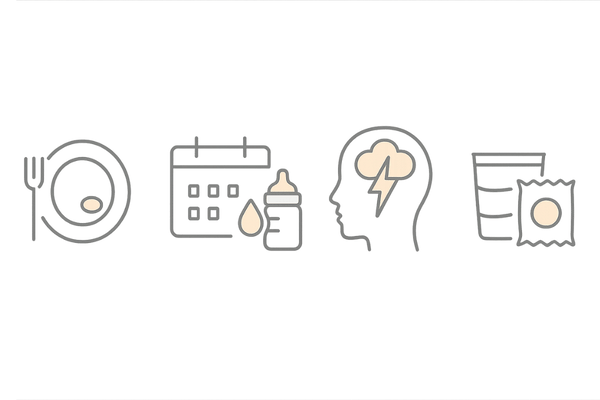
亜鉛は健康と美容に重要な栄養素ですが、意識しないとすぐに不足してしまう傾向があります。
特に女性は生活スタイルや体の特性から、知らず知らずのうちに「隠れ亜鉛不足」に陥っているケースが少なくありません。
ご自身の生活習慣と照らし合わせて、当てはまるものがないか確認してみましょう。
無理なダイエットや偏った食生活
美しい体型を維持したいという思いから行うダイエットですが、極端な食事制限は亜鉛不足の大きな原因です。
なかでも肉や魚などの動物性食品を避ける食事法は、亜鉛の摂取量を大幅に減らしてしまいます。
亜鉛は肉類、特に赤身肉やレバー、魚介類では牡蠣などに豊富に含まれています。野菜や穀物にも亜鉛は含まれますが、含有量が少なく、吸収率も動物性食品に比べて低い傾向があります。
健康的な食事バランスを心がけることが大切です。
女性特有のライフステージの変化(月経・妊娠・授乳)
女性はライフステージによって、体が必要とする亜鉛の量が変わります。月経時には経血とともに一定量の亜鉛が失われます。
また、妊娠中は胎児の成長のために、授乳期は母乳を通して赤ちゃんに栄養を分け与えるために、通常よりも多くの亜鉛が必要となります。
この需要の増加に摂取が追いつかないと母体の亜鉛が欠乏し、抜け毛や肌荒れといった不調として現れやすくなります。
日常的なストレスによる亜鉛の大量消費
現代社会でストレスを完全に避けるのは正直に言って困難です。仕事や家事、育児や人間関係など、女性が日々直面するストレスは多岐にわたります。
体がストレスを感じると、それに対抗するために様々なホルモンを分泌しますが、この過程で亜鉛が大量に消費されます。
つまり、慢性的なストレス状態にある方は食事から亜鉛を十分に摂っていても、消費量が上回ってしまい結果的に不足状態に陥るケースがあるのです。
食生活の欧米化と加工食品の問題点
手軽で便利な加工食品やインスタント食品、ファストフードの多用も亜鉛不足の一因です。
これらの食品は、製造の過程でミネラルが失われがちです。さらに、食品添加物の中には、リン酸塩のように亜鉛の吸収を妨げる性質を持つものがあります。
日々の食事が加工食品に偏っている方は、知らず知らずのうちに亜鉛の吸収が阻害され、摂取しているつもりでも有効に活用できていない可能性があります。
女性が亜鉛不足に陥りやすい要因
| 要因 | 具体的な内容 | 亜鉛への影響 |
|---|---|---|
| 食事制限 | 過度なダイエット、朝食抜き、菜食中心の食生活など。 | 亜鉛の摂取量そのものが減少する。 |
| 女性特有の理由 | 月経による出血、妊娠・授乳期の需要増大。 | 体内の亜鉛が通常より多く必要になる。 |
| ストレス | 仕事や家庭の精神的・肉体的ストレス。 | ストレス対抗ホルモンの生成で亜鉛が大量に消費される。 |
抜け毛だけじゃない!亜鉛不足が発する危険信号
亜鉛不足の影響は、抜け毛や薄毛だけに留まりません。体は様々なサインを発して、栄養が足りていないことを知らせてくれます。
髪の変化とあわせて、ご自身の体に以下のような症状がないかチェックしてみてください。複数の症状が当てはまる場合、亜鉛不足の可能性がより高いと考えられます。
髪質の変化(細くなる・パサつく・ハリコシの低下)
抜け毛の増加に気づく前に、まず髪質の変化として現れる場合が多いです。
以前と比べて髪の毛一本一本が細くなった、ツヤがなくパサパサする、全体的にハリやコシが失われスタイリングがまとまらない、といった変化は、亜鉛が不足して健康なケラチンを十分に生成できていないサインかもしれません。
髪の成長の土台が弱っている状態です。
明らかに増えるシャンプー時やブラッシング時の抜け毛
健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けますが、排水溝に溜まる髪の量や、ブラシにつく髪の量が明らかに増えた場合は注意が必要です。
亜鉛不足によってヘアサイクルが乱れ、本来ならまだ成長期にあるはずの髪が早く休止期に入り抜けてしまっている可能性があります。
この状態を放置すると徐々に髪全体の密度が低下し、薄毛へと進行します。
頭皮トラブル(フケ・かゆみ・炎症)
亜鉛は、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)を正常に保つ働きも担っています。
亜鉛が不足すると頭皮のターンオーバーが乱れ、古くなった角質がうまく剥がれずにフケとして目立ったり、乾燥してかゆみが出たりするときがあります。
また、皮膚のバリア機能も低下するため外部からの刺激に弱くなり、炎症や湿疹を引き起こしやすくなります。健康な髪は、健康な頭皮から育ちます。
亜鉛不足で起こりうる髪以外のサイン
| 部位 | 症状 | 解説 |
|---|---|---|
| 爪 | 白い斑点ができる、割れやすい、凹凸ができる | 爪も髪と同じケラチンでできているため、異常が現れやすい。 |
| 肌 | 肌荒れ、ニキビ、傷の治りが遅い | 皮膚のターンオーバーが乱れ、バリア機能が低下するため。 |
| その他 | 味覚がおかしい、免疫力の低下(風邪をひきやすい) | 味覚を感じる細胞(味蕾)の代謝や、免疫細胞の活性化に亜鉛が必要なため。 |
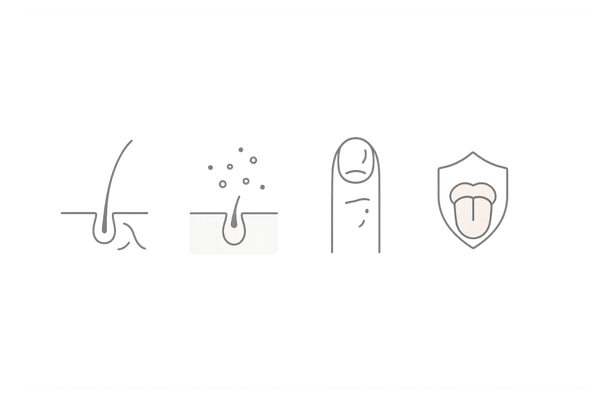
その不調、本当に亜鉛不足?思い込みの前に知るべきこと
抜け毛や体の不調を感じると「亜鉛不足かもしれない」と自己判断でサプリメントに頼りがちですが、少し立ち止まってみましょう。
女性の薄毛の原因は一つとは限りません。他の栄養素の不足や、思いもよらない病気が隠れている可能性もあります。
やみくもに対策を始める前に、ご自身の状態を客観的に見つめ、原因を正しく突き止めることが改善への近道です。
まずはご自身の食生活をチェック
サプリメントを検討する前に、まずは日々の食生活を振り返ることが大切です。
以下の項目にどれくらい当てはまるか、正直にチェックしてみましょう。
- 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 肉や魚を食べる機会が少ない(週に2回以下)
- 食事はパンや麺類、丼ものなど単品で済ませる機会が多い
- インスタント食品や加工食品をよく利用する
- 過度な食事制限によるダイエットを繰り返している
3つ以上心当たりのある方は、食事からの亜鉛摂取量が不足している可能性があります。まずは食生活の改善から取り組みましょう。
鉄分不足など他の栄養不足との見分け方
女性の抜け毛の原因として、亜鉛不足と並んで多いのが「鉄分不足」です。鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。
鉄分が不足すると頭皮の毛母細胞に十分な酸素が届かず、髪の成長が妨げられて抜け毛につながります。
めまいや立ちくらみ、倦怠感、顔色が悪いといった症状が伴う場合は、鉄分不足の可能性も考えられます。
甲状腺機能低下症など他の病気の可能性
抜け毛は、特定の病気のサインである場合もあります。
特に女性に見られる「甲状腺機能低下症」は、甲状腺ホルモンの分泌が減少し、全身の代謝が低下する病気です。この影響でヘアサイクルが乱れ、びまん性(広範囲)の脱毛が起こる場合があります。
抜け毛の他に、異常な疲労感やむくみ、冷えや体重増加などの症状があれば、自己判断せずに内科や内分泌科の受診を検討してください。
専門クリニックを受診するべきタイミング
セルフケアを1〜2ヶ月続けても抜け毛が改善しない、または悪化する一方である場合、あるいは抜け毛の量が異常で精神的にも辛いと感じる場合は、専門クリニックへの相談をおすすめします。
専門医は詳細な問診や視診、血液検査などを通して、抜け毛の根本原因を正確に診断します。
原因が亜鉛不足であれば適切な補充療法を、他の原因であればそれに合った治療法を提案してくれます。一人で悩み込まず、専門家の力を借りる勇気が大切です。
毎日の食事から始める!亜鉛を効率よく摂るための食事術
亜鉛不足を解消するための基本は、毎日の食事です。
特定の食品だけを食べるのではなく、様々な食材をバランス良く組み合わせると、亜鉛だけでなく他の栄養素も同時に摂取でき、相乗効果が期待できます。
亜鉛が豊富な食材リスト
亜鉛は幅広い食品に含まれていますが、特に含有量が多く、吸収率も高いのが動物性食品です。
植物性食品からも摂取できますが、意識して食事に取り入れることが重要です。
亜鉛を多く含む食品(100gあたり)
| 食品カテゴリー | 食品名 | 亜鉛含有量(目安) |
|---|---|---|
| 魚介類 | 牡蠣(生) | 14.5mg |
| うなぎ(蒲焼) | 2.7mg | |
| ほたて(生) | 2.7mg | |
| 肉類 | 豚レバー | 6.9mg |
| 牛肉(赤身) | 4.0mg~6.0mg | |
| ラム肉 | 4.0mg~5.0mg | |
| その他 | カシューナッツ | 5.4mg |
| 高野豆腐 | 5.2mg |
亜鉛の吸収率を格段に上げる食べ合わせ
亜鉛は、一緒に摂取する栄養素によって体内での吸収率が大きく変わります。せっかく亜鉛を多く含む食品を摂っても、吸収されなければ意味がありません。
以下の栄養素を組み合わせると効率よく亜鉛を体に届けられます。
亜鉛の吸収を助ける栄養素
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 亜鉛を水に溶けやすい形(キレート作用)に変え、吸収を助ける。 | パプリカ、ブロッコリー、キウイ、レモン |
| クエン酸 | ビタミンCと同様に、亜鉛の吸収を促進する。 | レモン、梅干し、酢 |
| 動物性タンパク質 | 亜鉛と結合し、吸収しやすい形に保つ。 | 肉、魚、卵 |
例えば、牛肉のステーキにレモンを絞ったり、牡蠣にレモン汁をかけたりするのは、味だけでなく栄養学的にも理にかなった食べ方です。
食事の際には、これらの組み合わせを意識してみると良いでしょう。
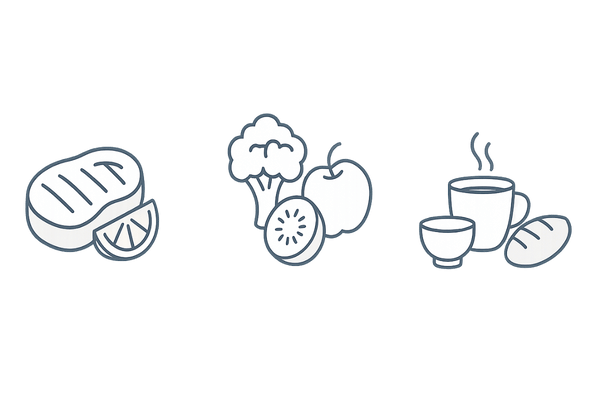
逆に吸収を妨げてしまう食品と注意点
一方で、亜鉛の吸収を阻害する成分も存在します。
吸収を妨げる成分を多く含む食品を、亜鉛が豊富な食品と同時に大量に摂取するのは避けたほうが賢明です。
亜鉛の吸収を妨げる主な成分
- フィチン酸(玄米、豆類、全粒粉パンなど)
- タンニン(コーヒー、紅茶、緑茶など)
- 食物繊維(過剰摂取した場合)
- リン酸(加工食品、スナック菓子など)
これらの食品を完全に避ける必要はありません。例えば、コーヒーや緑茶は食事中ではなく、食後30分以上経ってから飲むようにするだけでも、亜鉛の吸収への影響を減らせます。
玄米や豆類も健康に良い食品ですが、食べ過ぎには注意し、バランスを考えていきましょう。
忙しい女性の味方!サプリメントの上手な活用法
食生活の改善が基本ですが、多忙な毎日の中で常にバランスの取れた食事を続けるのが難しい場合や、すでに深刻な亜鉛不足に陥っている場合には、サプリメントの活用も有効な選択肢となります。
ただし、やみくもに摂取するのではなく、正しく選んで適切に利用することが重要です。
亜鉛サプリメントを選ぶ際の3つのポイント
市場には多くの亜鉛サプリメントがありますが、選ぶ際にはいくつかのポイントを押さえておきましょう。
含有量と形態を確認する
製品によって亜鉛の含有量は様々です。1日の摂取目安量(成人女性で8mg)を大きく超えないものを選びましょう。
また、亜鉛の形態には「グルコン酸亜鉛」や「クエン酸亜鉛」などがあり、後者の方が吸収率が高いとされています。
余計な添加物が少ないものを選ぶ
着色料や甘味料、保存料などの添加物が極力少ない、シンプルな成分構成の製品が望ましいです。
信頼できるメーカーの製品を選ぶ
品質管理が徹底されている、国内のGMP認定工場で製造されているなど、製品の安全性や品質が保証されているメーカーを選ぶと安心です。
知っておきたい過剰摂取のリスク
亜鉛は不足も問題ですが、過剰に摂取しても体に害を及ぼします。
サプリメントを利用する際は、必ず製品に記載されている1日の摂取目安量を守ってください。
亜鉛の過剰摂取による主な副作用
| 症状 | 原因 |
|---|---|
| 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛 | 消化器系への直接的な刺激。 |
| 銅欠乏症 | 亜鉛が腸管での銅の吸収を阻害するため。貧血や白血球減少につながる。 |
| 免疫機能の低下 | 長期的な過剰摂取により、免疫細胞の働きが逆に抑制されることがある。 |
日本の厚生労働省が定める成人女性の亜鉛の耐容上限量は1日40mgです。
通常の食事でこの量を超えることは稀ですが、複数のサプリメントを併用している場合などは注意が必要です。
効果的な摂取タイミングと飲み方
亜鉛サプリメントの効果を最大限に引き出すには、飲むタイミングも大切です。
一般的に、亜鉛は胃酸がある状態で吸収されやすいため、食後の摂取が推奨されます。空腹時に飲むと、胃腸への刺激で吐き気などを催す場合があるため避けましょう。
また、前述したように、コーヒーや紅茶に含まれるタンニンは亜鉛の吸収を妨げるため、サプリメントを飲む際は水かぬるま湯で飲むようにし、お茶やコーヒーとは時間を空けるのが賢明です。
亜鉛補給とあわせて行いたい健やかな髪を育む生活習慣
亜鉛不足の解消は健やかな髪を取り戻すための重要な柱ですが、それだけでは十分といえません。
髪の健康は食事や睡眠、ストレス管理やヘアケアといった生活全体の総合的なバランスの上に成り立っています。亜鉛の補給と並行して、以下の生活習慣も見直してみましょう。
髪の成長を促す「睡眠」の質を高める
髪の毛の成長を促す「成長ホルモン」は、私たちが眠っている間、特に夜10時から深夜2時の間に最も多く分泌されます。
この時間帯に深い眠りについていることが、髪の健やかな成長には大切です。単に長く寝るだけでなく、「睡眠の質」を高めるように意識しましょう。
就寝前のスマートフォン操作を控えたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってリラックスしたり、自分に合った寝具を選んだりする工夫が有効です。
血行を促進し頭皮環境を整える
髪の毛を育てる栄養は、血液によって頭皮の毛母細胞まで運ばれます。そのため、頭皮の血行が悪いと、いくら食事やサプリで栄養を補給しても、髪に届きにくくなってしまいます。
適度な運動(ウォーキングやストレッチなど)を習慣づけ、全身の血行を良くしましょう。
また、シャンプー時の頭皮マッサージも効果的です。指の腹を使って優しく頭皮を動かすようにマッサージし、血行を促進させましょう。
ストレスを溜めない自分なりの発散法を見つける
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させます。また、ストレス対抗のために亜鉛を大量に消費してしまうことは既に述べたとおりです。
完璧を目指さず、時には「まあいいか」と物事を受け流す心の余裕も大切です。
趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したり、アロマを焚いたり、自然の中で過ごしたりと、自分が心からリラックスできる方法を見つけ、上手にストレスを発散させましょう。
ストレスケアの具体例
- 深呼吸や瞑想
- ヨガや軽いストレッチ
- 好きな音楽を聴く、映画を観る
- 親しい友人や家族との対話
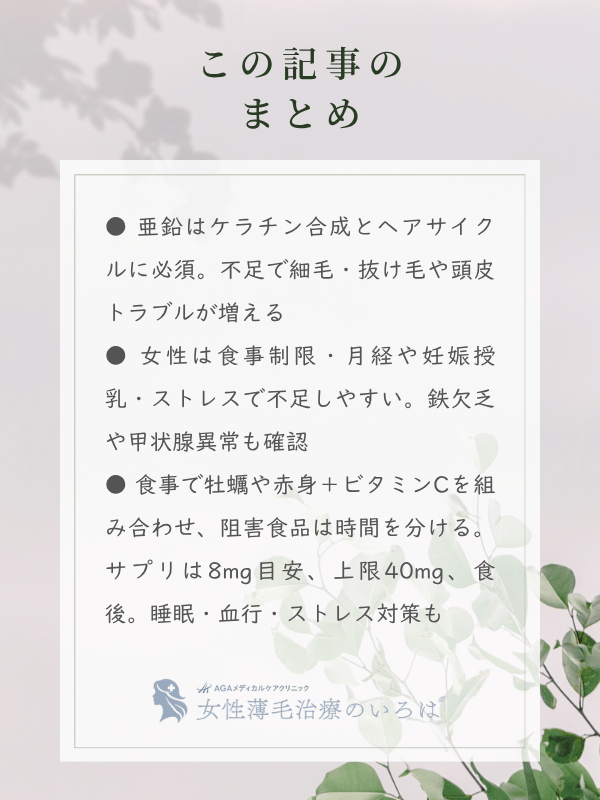
亜鉛と女性の薄毛に関するよくある質問
さいごに、患者さんからよく寄せられる亜鉛と抜け毛に関する質問とその回答をまとめました。
- 亜鉛を摂取し始めてから、どのくらいで髪への効果を実感できますか?
-
髪の毛にはヘアサイクルがあるため、効果を実感するまでには時間がかかります。髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びません。
亜鉛の摂取を始めてから新しく生えてくる髪が健康になり、それが目に見える長さになるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月は必要と考えるのが一般的です。
すぐに効果が出ないからと諦めず、まずは継続していきましょう。
- 亜鉛のサプリメントは、いつまで飲み続ける必要がありますか?
-
血液検査などで亜鉛不足が確認された場合、医師の指導のもとで2〜3ヶ月程度継続するケースが多いです。
その後、症状の改善が見られれば、徐々に食事からの摂取に切り替えていくのが理想的です。
根本的な原因である食生活が改善されない限り、サプリメントを止めると再び不足状態に戻ってしまう可能性があります。
サプリメントはあくまで補助的なものと考え、食生活の改善を基本としましょう。
- 亜鉛を摂りすぎると、どのような副作用がありますか?
-
サプリメントなどによる長期的な過剰摂取は、吐き気や腹痛などの消化器症状のほか、他の必須ミネラルである「銅」の吸収を阻害してしまう副作用が知られています。
銅が欠乏すると貧血や免疫力の低下、毛髪の色素異常などを引き起こす可能性があります。
サプリメントを利用する際は、必ず製品に記載された摂取目安量を守り、自己判断で量を増やさないようにしてください。
- クリニックでは、亜鉛不足に対してどのような検査や治療を行うのですか?
-
専門のクリニックでは問診で食生活や生活習慣、抜け毛の状態などを詳しくお伺いします。その上で血液検査を行い、血中の亜鉛濃度を測定して客観的に不足の有無を診断します。
亜鉛不足が確認された場合は食事指導とあわせて、必要に応じて医療用の亜鉛製剤(サプリメントよりも高濃度のもの)を処方するケースがあります。
また、他の原因が考えられる場合は、さらに詳しい検査や、その原因に応じた治療法(外用薬や内服薬、注入治療など)を提案します。
参考文献
GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.
KIL, Min Seong; KIM, Chul Woo; KIM, Sang Seok. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. Annals of Dermatology, 2013, 25.4: 405.
KIL, Min Seong; KIM, Chul Woo; KIM, Sang Seok. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. Annals of Dermatology, 2013, 25.4: 405.
ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
PRASAD, Ananda S. Zinc deficiency: its characterization and treatment. Metal ions in biological systems, 2004, 41: 103-138.
FARAH, HUSNI S., et al. The association between the levels of Ferritin, TSH, Zinc, Hb, vitamin B12, vitamin D and the hair loss among different age groups of women: A retrospective study. International J Pharmaceut Res, 2021, 13: 143-8.
TROST, Leonid Benjamin; BERGFELD, Wilma Fowler; CALOGERAS, Ellen. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 824-844.