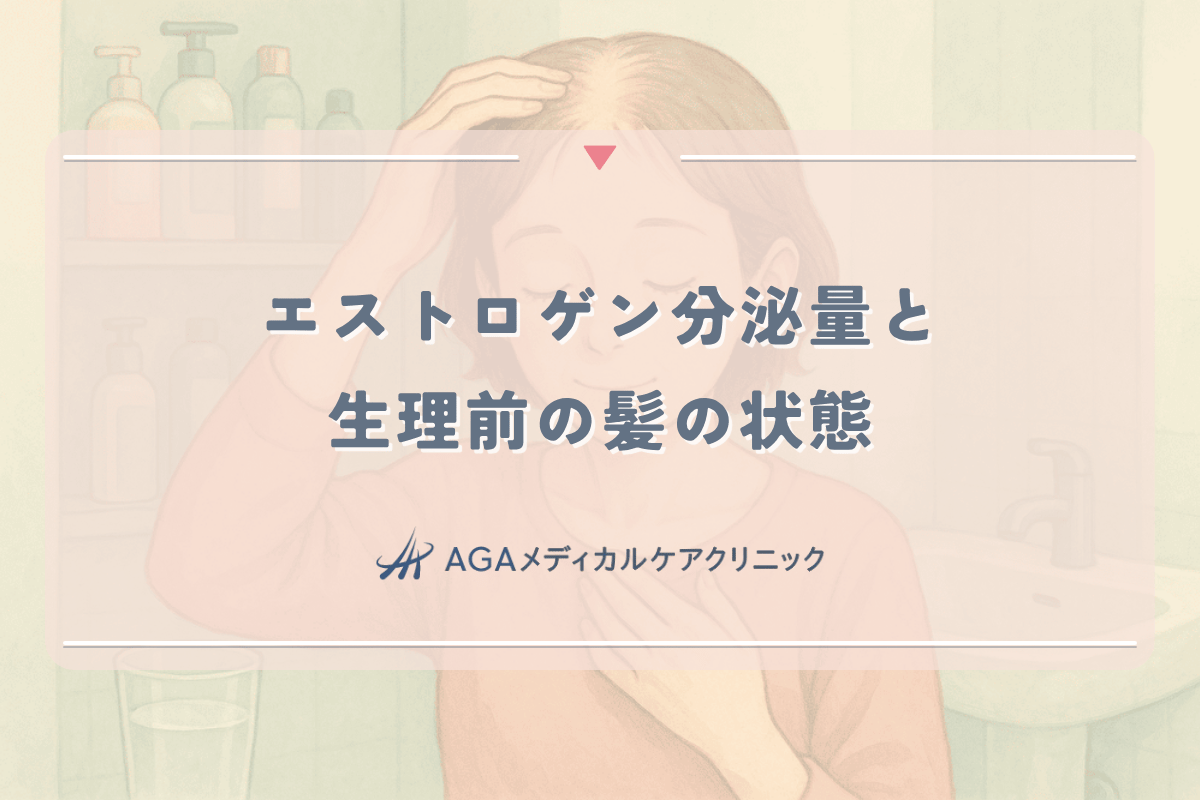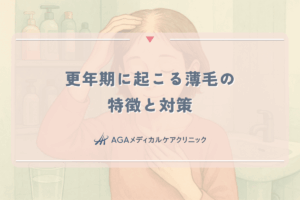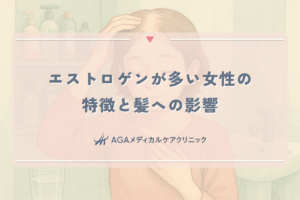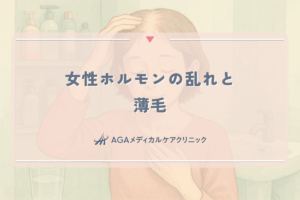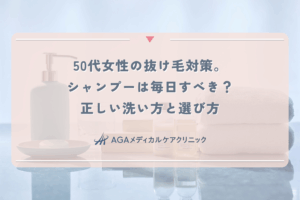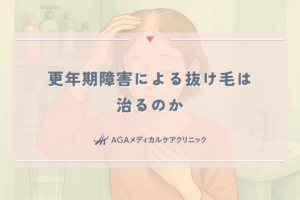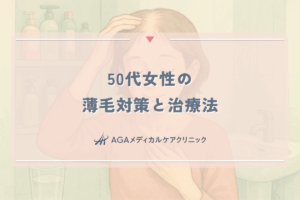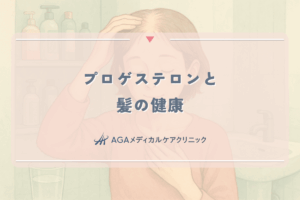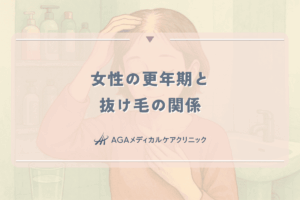「生理前になると、なんだか髪がべたつくな…」「いつもより抜け毛が多い気がする」と感じている方も多いのではないでしょうか。
女性の月経周期に伴う心身の変化は、実は髪の健康にも深く関わっています。
女性らしさを作るホルモンとして知られる「エストロゲン」の分泌量の波は、髪のハリやコシ、ツヤ、そして頭皮環境にまで影響を与えます。
この記事では、なぜ生理前に髪のコンディションが変化するのか、その背景にあるエストロゲンの働きから、年齢による変化、日々のケア方法までを詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
エストロゲンとは?女性の心と体に与える影響
エストロゲンは、一般に「女性ホルモン」として知られ、女性の健康と美しさを支える重要な役割を果たします。
このホルモンが私たちの体にどのような影響を与えているのかを理解することは、髪の悩みを解決する第一歩です。
エストロゲンの基本的な役割
エストロゲンは、主に卵巣で作られるステロイドホルモンの一種です。思春期に分泌量が増え、丸みを帯びた体つきや、きめ細やかな肌など、女性らしい特徴を形成します。
また、子宮内膜を厚くして妊娠の準備をしたり、骨密度を維持したり、自律神経のバランスを整えたりと、その働きは多岐にわたります。
精神面にも作用し、気分を安定させて前向きな気持ちを保つ手助けをします。
エストロゲンの種類とそれぞれの働き
一口にエストロゲンと言っても、実は3つの種類が存在し、それぞれ異なる時期に異なる役割を担っています。
女性のライフステージを通じて、これらのエストロゲンがバランスを取りながら体を支えています。
エストロゲンの3つのタイプ
| 種類 | 主な分泌時期 | 主な働き |
|---|---|---|
| エストラジオール (E2) | 性成熟期(月経のある時期) | 最も作用が強く、排卵や妊娠に深く関わる。 |
| エストロン (E1) | 閉経後 | 閉経後に主に脂肪組織で作られる。作用は穏やか。 |
| エストリオール (E3) | 妊娠中 | 妊娠中に胎盤で大量に作られる。作用は非常に穏やか。 |
エストロゲンが髪の健康にどう関わるか
エストロゲンは「美髪ホルモン」とも呼ばれるほど、髪の健康に直接的な影響を与えます。
特に、最も作用の強いエストラジオールは髪の成長期を維持し、髪そのものを太くしなやかに育てる働きがあります。
このホルモンの分泌が活発な時期は、髪にツヤとハリが生まれ、最も美しい状態を保ちやすいのです。
さらに、コラーゲンの生成を促す作用もあり、頭皮の弾力と潤いを保ち、健康な髪が育つ土台を整えます。
女性ホルモンの周期的な変動|生理前のエストロゲン

女性の体は約1ヶ月の月経周期の中で、ホルモン分泌量がダイナミックに変動します。この波を理解すると、生理前に起こる髪の変化の理由が見えてきます。
月経周期とホルモンバランスの波
月経周期は、卵胞期、排卵期、黄体期、月経期という4つの期間に分けられます。
それぞれの期間で、エストロゲンと、もう一つの女性ホルモンであるプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が変化します。
排卵後から生理前にかけての「黄体期」は、ホルモンバランスが大きく揺れ動く時期です。
月経周期とホルモンの変動
| 期間 | エストロゲン量 | プロゲステロン量 |
|---|---|---|
| 卵胞期(生理後~排卵前) | 増加 | 低水準 |
| 排卵期 | ピーク | 増加し始める |
| 黄体期(排卵後~生理前) | 減少し始める | ピーク |
| 月経期(生理中) | 低水準 | 低水準 |
なぜ生理前にエストロゲンは減少するのか
排卵が終わると、体は妊娠に備えるためにプロゲステロンの分泌を増やします。
このプロゲステロンが優位になる黄体期後半、つまり生理前にかけて、妊娠が成立しなかった場合にエストロゲンとプロゲステロンの両方の分泌量が急激に減少します。
この急激なエストロゲンの減少が心身のさまざまな不調、そして髪の状態の変化を引き起こす主な原因となります。
エストロゲン減少が引き起こす心身の変化
生理前にエストロゲンが減少すると、心と体にさまざまな変化が現れます。
精神的には、気分の落ち込みやイライラ、不安感などを感じやすくなります。身体的には、頭痛やむくみ、乳房の張り、そして肌荒れや髪のトラブルなどが起こりやすくなります。
これらは月経前症候群(PMS)の症状としても知られています。
生理前に髪の悩みが増える具体的な理由
エストロゲンの減少が具体的にどのように髪に影響を与えるのでしょうか。
髪の成長サイクルや頭皮環境との関わりから、その理由を詳しく見ていきましょう。
髪の成長サイクルとエストロゲンの関係
髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクル(毛周期)があります。エストロゲンは、このうち髪が太く長く成長する「成長期」を維持する働きを担っています。
しかし、生理前にエストロゲンが減少すると成長期が短くなり、髪が十分に育たないまま退行期や休止期へと移行しやすくなります。これが、髪のボリュームダウンや抜け毛の一因となります。
頭皮環境への影響|皮脂の増加とべたつき
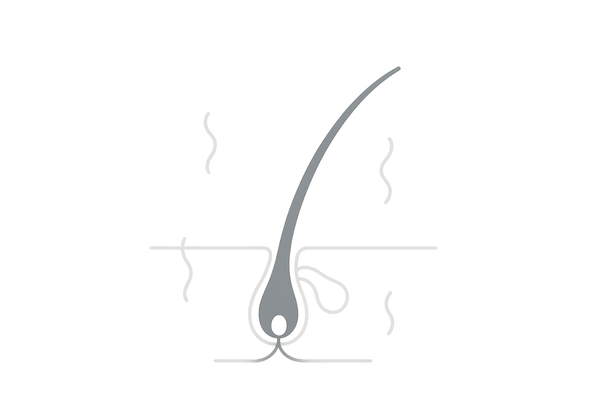
生理前はエストロゲンが減少する一方で、男性ホルモンと似た働きを持つプロゲステロンが優位になります。
プロゲステロンには皮脂の分泌を活発にする作用があるため、頭皮が脂っぽくなり、べたつきやニオイ、かゆみといったトラブルが起こりやすいです。
過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、健康な髪の成長を妨げる可能性もあります。
生理前に起こりやすい髪と頭皮のトラブル
| トラブル | 主な原因 | 具体的な状態 |
|---|---|---|
| 抜け毛の増加 | エストロゲン減少 | シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が増える。 |
| べたつき・ニオイ | プロゲステロン優位 | 夕方になると髪がぺたんとし、頭皮のニオイが気になる。 |
| ハリ・コシ低下 | エストロゲン減少 | 髪に元気がなく、スタイリングが決まりにくい。 |
髪のハリ・コシ・ツヤの低下
エストロゲンは髪の内部で水分やタンパク質を保持し、キューティクルを整える働きも持っています。
そのため、エストロゲンが減少すると髪の水分量が減ってパサついたり、キューティクルが乱れてツヤが失われたりします。
髪一本一本が細く弱々しくなり、全体的にハリやコシがない印象になります。
抜け毛の増加はホルモン変動のサイン?
生理前に一時的に抜け毛が増えるのは、多くの場合、ホルモンバランスの自然な変動によるものです。
髪の成長期を支えていたエストロゲンが減るため休止期に入る髪の毛が増え、その結果として抜け毛が目立つようになります。
通常は生理が始まるとホルモンバランスがリセットされ、抜け毛も落ち着きます。
しかし、この状態が長く続いたり、明らかに量が多かったりする場合は注意が必要です。
エストロゲンだけじゃない!生理前の不調が髪に与える複合的な影響
生理前の髪の悩みは、単にエストロゲンの減少だけが原因ではありません。
多くの女性が経験するPMS(月経前症候群)に伴うさまざまな不調が、複合的に髪の健康を損なっている可能性があります。
ホルモンの変動という視点だけでなく、ご自身の体全体で何が起きているのかを確認すると、根本的なケアに繋がります。
PMS(月経前症候群)と髪の健康
イライラや気分の落ち込み、だるさや頭痛など、PMSの症状は多岐にわたります。
これらの精神的・身体的なストレスは自律神経のバランスを乱し、全身の血行を悪化させます。
頭皮への血流が滞ると、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで届きにくくなり、結果として髪が弱ったり抜け毛が増えたりする原因となります。
PMSの症状が髪に与える悪影響
| PMSの症状 | 髪への影響 |
|---|---|
| 精神的ストレス(イライラ、不安) | 血行不良、活性酸素の増加 |
| 身体的ストレス(頭痛、だるさ) | 血行不良、睡眠の質の低下 |
| 食欲の変化(過食、甘いものへの渇望) | 栄養バランスの乱れ |

睡眠の質の低下による髪へのダメージ
生理前はホルモンバランスの変化により、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりと、睡眠の質が低下しがちです。
髪の成長を促す「成長ホルモン」は、深い睡眠中に最も多く分泌されます。
そのため、睡眠不足や質の悪い睡眠が続くと成長ホルモンの分泌が減少し、髪の修復や再生が十分に行われず、ダメージを受けやすい状態になってしまいます。
食生活の乱れと栄養不足
生理前になると、無性に甘いものやジャンクフードが食べたくなるという経験のある方も多いでしょう。
これはホルモンの影響によるものですが、糖質や脂質の多い食事に偏ると皮脂の過剰分泌を招くだけでなく、髪の主成分であるタンパク質や、健やかな成長を支えるビタミン、ミネラルが不足しがちになります。
栄養バランスの乱れは、直接的に髪の質を低下させます。
ストレスと血行不良
PMSによる不快な症状そのものがストレスとなり、血管を収縮させて血行を悪化させます。
特に頭頂部などは毛細血管が多いため、血行不良の影響を受けやすい部位です。
栄養が届きにくくなった毛根は健康な髪を育てられなくなり、薄毛や抜け毛のリスクを高めてしまいます。
年齢によるエストロゲン分泌量の変化と髪への影響
エストロゲンの分泌量は、一生を通じて一定ではありません。
ライフステージによって大きく変化し、その変化は髪の状態にも深く関わってきます。
20代・30代のホルモンバランス
20代から30代半ばはエストロゲンの分泌量がピークに達し、最も安定している時期です。そのため、基本的には健康で美しい髪を保ちやすい年代と言えます。
しかし、過度なダイエットやストレス、不規則な生活などによってホルモンバランスが乱れると、生理周期に関わらず抜け毛や髪質の低下といったトラブルが起こる場合もあります。
40代以降のプレ更年期・更年期
40代に入ると卵巣機能が徐々に低下し始め、エストロゲンの分泌量は大きく揺らぎながら減少していきます。この時期を「プレ更年期」と呼びます。
そして閉経を迎える前後5年間(合計10年間)が「更年期」です。
この時期はエストロゲンの減少が顕著になり、髪のハリやコシが失われ、うねりやパサつき、白髪、そして「びまん性脱毛症」と呼ばれる頭部全体の髪が薄くなる症状が現れやすくなります。
年代別のエストロゲンレベルと髪の状態
| 年代 | エストロゲンレベル | 主な髪の状態 |
|---|---|---|
| 20代~30代 | ピーク・安定期 | ハリ、コシ、ツヤがあり健康的。 |
| 40代(プレ更年期) | 揺らぎながら減少 | うねり、パサつき、ボリュームダウンが出始める。 |
| 50代以降(更年期・閉経後) | 急激に減少し、低水準に | 薄毛、白髪、髪質の変化が顕著になる。 |
閉経後のエストロゲンと髪の変化
閉経後はエストロゲンの分泌がごくわずかになり、髪の成長期を維持する力が弱まります。
ヘアサイクルにおける成長期が短くなり、休止期にとどまる毛包の割合が増えるため、髪全体のボリュームが減少しやすいです。
髪を守ってくれていたエストロゲンのバリアがなくなるため髪がより細く弱々しくなり、外部からのダメージも受けやすくなります。
生理周期に合わせたセルフケアで髪を守る
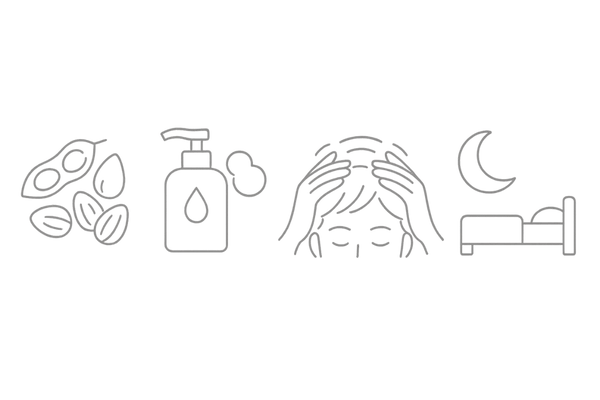
ホルモンバランスの変動は避けられませんが、日々の少しの工夫で、髪への影響を最小限に抑えることは可能です。
特に不調が出やすい生理前に試したいセルフケアを見ていきましょう。
生理前の食事で心がけたいこと
髪の主成分であるタンパク質はもちろん、ホルモンバランスを整える働きのある栄養素を意識的に摂取することが大切です。
女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンや、血行を促進するビタミンE、ストレスを緩和するカルシウムやマグネシウムなどを積極的に食事に取り入れましょう。
髪とホルモンバランスをサポートする栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| イソフラボン | エストロゲン様作用 | 納豆、豆腐、豆乳 |
| ビタミンE | 血行促進 | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ |
頭皮に優しいヘアケア方法
皮脂分泌が増えて頭皮が敏感になりがちな生理前は、洗浄力の強すぎるシャンプーを避け、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選ぶと良いでしょう。
洗髪時は爪を立てず、指の腹で優しくマッサージするように洗い、血行を促進します。
また、ドライヤーの熱も刺激になるため、頭皮から離して乾かし、最後は冷風でキューティクルを引き締めるのがおすすめです。
リラックスできる時間の作り方
ストレスは血行を悪化させ、髪に悪影響を与えます。意識的にリラックスする時間を作る工夫が重要です。
ぬるめのお湯にゆっくり浸かる、好きな香りのアロマを焚く、軽いストレッチをするなど、自分に合った方法で心と体を休ませてあげましょう。
質の良い睡眠を確保すると、最高のヘアケアに繋がります。
リラックス方法
- 半身浴
- アロマテラピー
- ヨガ・ストレッチ
- 音楽鑑賞
薄毛治療専門クリニックに相談するタイミング
セルフケアを続けても髪の状態が改善しない、あるいは悪化する場合は、専門家の視点からの診断が必要です。
一人で悩まず、専門クリニックへの相談を検討しましょう。
セルフケアで改善しない場合
食事やヘアケア、生活習慣を見直しても抜け毛や髪質の低下に変化が見られないtは、ホルモンバランスの乱れだけでなく、他の原因が隠れている可能性があります。
専門的な検査を通じて、根本的な原因を特定することが改善への近道です。
抜け毛が明らかに増えたと感じる時
生理周期による一時的なものではなく、数ヶ月にわたって抜け毛が多い状態が続く場合や、排水溝にたまる髪の量が明らかに増えたと感じる場合は、脱毛症が進行しているサインかもしれません。
早期に相談すると、治療の選択肢も広がります。
クリニック受診を検討すべきサイン
| サイン | 具体的な状態 |
|---|---|
| 抜け毛の持続 | 3ヶ月以上、1日100本以上の抜け毛が続く。 |
| 頭皮の透け感 | 分け目や頭頂部の地肌が以前より目立つ。 |
| 髪質の急激な変化 | 急に髪が細く、弱々しくなった。 |
髪質の変化が著しい時
髪が細くなり、ハリやコシが失われ、地肌が透けて見えるようになってきたら、それは女性の薄毛(FAGA/FPHL)の可能性があります。
専門クリニックではホルモンバランスの検査や頭皮の状態を詳細に診察し、一人ひとりの状態に合わせた治療法を提案します。
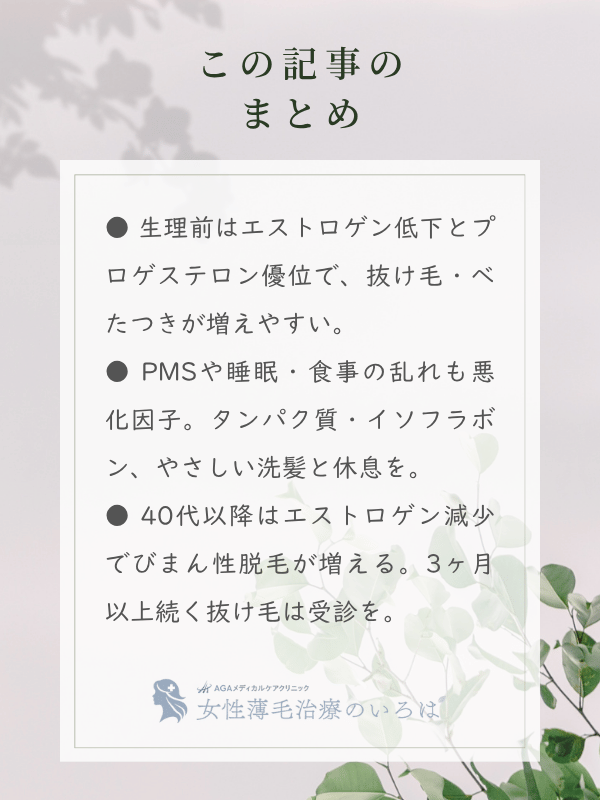
よくある質問
エストロゲンや生理と髪の関係について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- ピルを飲むと髪質は変わりますか?
-
低用量ピルは、ホルモンバランスを安定させる目的で処方されます。
エストロゲンとプロゲステロンの量を人為的にコントロールするため、生理前の急激なホルモン減少が抑えられ、結果として抜け毛や皮脂の過剰分泌が改善する場合があります。
一方で、ピルの種類や体質によっては、服用開始後に一時的に抜け毛が増えるなど、変化を感じる方もいます。変化が気になる場合は、処方した医師に相談しましょう。
- 生理不順だと髪への影響も大きいですか?
-
生理不順はホルモンバランスが乱れているサインです。エストロゲンの分泌が不安定になるため、ヘアサイクルが乱れやすくなり、髪の成長に影響が出ることが考えられます。
慢性的な生理不順は、抜け毛や薄毛のリスクを高める可能性があります。まずは婦人科で生理不順の原因を特定して治療すると、健やかな髪を取り戻すためにも繋がります。
- 食事でエストロゲンを増やすことはできますか?
-
特定の食品を食べるだけで、体内のエストロゲン分泌量を直接的に、かつ大幅に増やすのは困難です。
しかし、先述した大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」のように、体内でエストロゲンと似た働きをする成分を摂取する工夫は、ホルモンバランスをサポートする上で有効と考えられています。
何よりも、バランスの取れた食事で体全体の健康を維持することが、ホルモンバランスを整え、ひいては髪の健康を守る上で最も大切です。
参考文献
KADOUR-PEERO, E., et al. Determination of estradiol and progesterone concentrations in human scalp hair. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 2020, 47.2: 268-271.
GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.
OHNEMUS, Ulrich, et al. The hair follicle as an estrogen target and source. Endocrine reviews, 2006, 27.6: 677-706.
ZOUBOULIS, C. C., et al. Skin, hair and beyond: the impact of menopause. Climacteric, 2022, 25.5: 434-442.
SILBERSTEIN, Stephen D.; MERRIAM, George R. Estrogens, progestins, and headache. Neurology, 1991, 41.6: 786-786.
SAGILI, Haritha; RAJAN, Saroj. Cutaneous manifestations of estrogen excess and deficiency. Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism, 2021, 2.3: 162-167.
KAMP, Erin, et al. Menopause, skin and common dermatoses. Part 1: hair disorders. Clinical and experimental dermatology, 2022, 47.12: 2110-2116.
LEPHART, Edwin D. Human scalp hair: Modulation by various factors and hormones do estrogens inhibit or stimulate—A perplexing perspective. Journal of cosmetic dermatology, 2019, 18.6: 1860-1865.