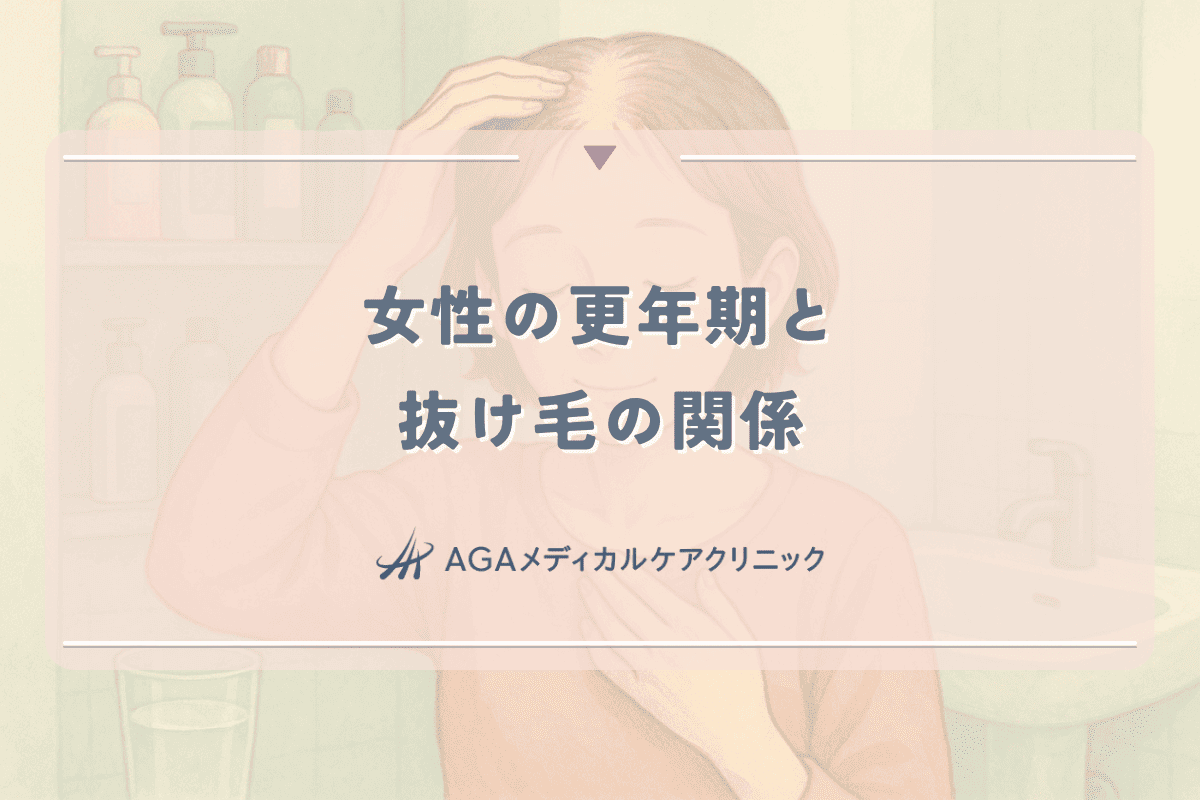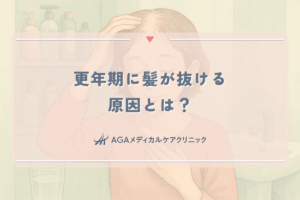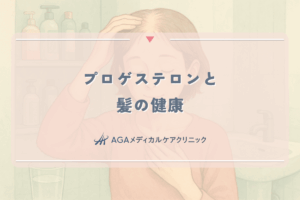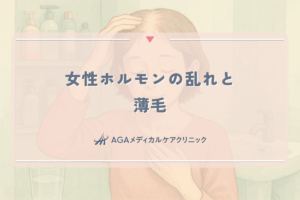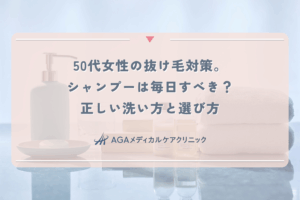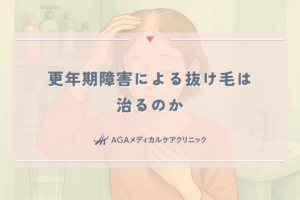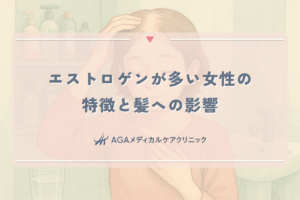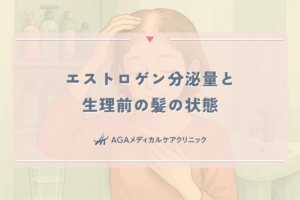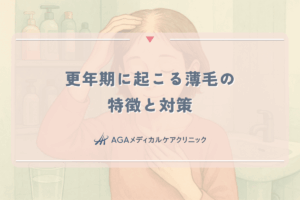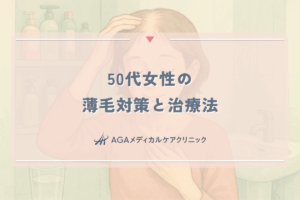髪がぺたんとしてきた、分け目が目立つようになった、などの悩みは、女性ホルモン「エストロゲン」の減少が関係しているかもしれません。
エストロゲンは、女性の心と体の健康を支える重要なホルモンであり、その減少は髪の毛の成長にも深く関わっています。
この記事では、エストロゲンがなぜ減少するのか、その原因から、髪や体に現れるサイン、そしてご自身でできる対処法まで、専門的な観点から詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
エストロゲンとは?女性の体で果たす大切な役割
エストロゲンは、一般に「女性ホルモン」として知られるステロイドホルモンの一種です。
主に卵巣で生成され、女性らしい体つきの形成、妊娠・出産のコントロール、そして心身の健康維持に多岐にわたる働きをします。
その影響は、髪の毛の健康にも及んでいます。
女性らしさを作るホルモン
エストロゲンは第二次性徴期に分泌量が増加し、乳房の膨らみや丸みを帯びた体つきなど、女性特有の身体的な特徴を形成します。
また、子宮内膜を厚くして妊娠の準備を整え、月経周期をコントロールする重要な役割を担います。
これらの働きは、女性が健康な生殖能力を維持するために必要です。
髪の成長とハリ・コシを保つ
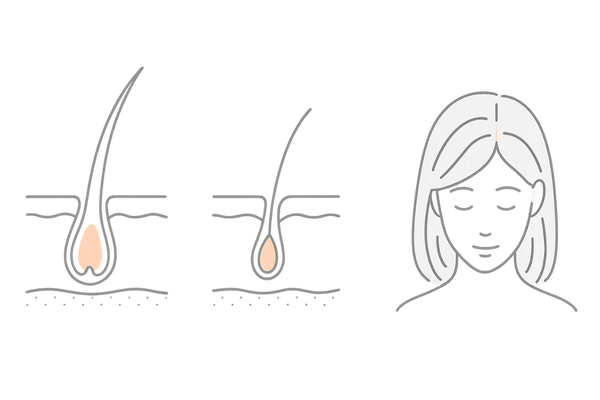
髪の毛に対して、エストロゲンは成長期を維持し、髪が太く長く成長するのを助ける働きがあります。
髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、エストロゲンはこの「成長期」の期間を延ばす作用を持ちます。
このため、エストロゲンの分泌が活発な時期は、髪にハリやコシ、ツヤが生まれやすくなります。
エストロゲンの種類と主な働き
| 種類 | 主な分泌時期 | 特徴的な働き |
|---|---|---|
| エストロン (E1) | 閉経後 | 閉経後の主要なエストロゲン。脂肪組織などで作られる。 |
| エストラジオール (E2) | 性成熟期 | 最も作用が強いエストロゲン。髪の健康や肌の潤いを保つ。 |
| エストリオール (E3) | 妊娠中 | 妊娠中に胎盤で多く作られ、作用は穏やか。 |
心と体の健康を支える多面的な効果
エストロゲンの影響は、見た目や生殖機能だけにとどまりません。
骨の密度を維持して骨粗しょう症を防いだり、血管のしなやかさを保って動脈硬化を予防したりする働きがあります。
さらに、脳内では記憶力や集中力に関与し、自律神経のバランスを整えて精神的な安定にも貢献しています。
エストロゲンが減少する原因
女性の生涯を通じてエストロゲンの分泌量は変動します。
特にその減少は、薄毛を含むさまざまな心身の変化を引き起こす要因となります。
加齢による自然な変化(更年期)
エストロゲン減少の最も代表的な原因は、加齢に伴う卵巣機能の低下です。
日本の女性の平均閉経年齢は約50歳ですが、その前後5年間、合計10年間を「更年期」と呼びます。
この時期になると卵巣からのエストロゲン分泌が急激に減少し、ホルモンバランスが大きく揺らぎます。
そのため、薄毛の進行を感じる方が増える傾向にあります。
年代別エストロゲン分泌量の変化(イメージ)
| 年代 | エストロゲン分泌量 | 主な体の状態 |
|---|---|---|
| 思春期 (10代) | 急増 | 初経を迎え、体が成熟する |
| 性成熟期 (20〜30代) | ピーク | 心身ともに安定し、妊娠・出産に適した時期 |
| 更年期 (40代後半〜) | 急減 | 閉経を迎え、様々な不調が現れやすい |
過度なダイエットと栄養不足
若い世代でもエストロゲンの減少は起こりえます。特に、極端な食事制限を伴うダイエットは危険信号です。
ホルモンの原料となるコレステロールや、生成を助けるビタミン・ミネラルが不足すると脳は生命維持を優先し、生殖機能に関わるホルモンの生成を後回しにします。
その結果、月経不順や無月経に至り、エストロゲンが著しく減少する場合があります。
ストレスがホルモンバランスに与える影響
心身のストレスもホルモンバランスを乱す大きな要因です。ストレスを感じると、体はそれに対抗するためにコルチゾールというホルモンを分泌します。
このコルチゾールの過剰な分泌をコントロールしようと、脳の視床下部や下垂体が疲弊します。
視床下部や下垂体はエストロゲンの分泌を指令する司令塔でもあるため、その機能が乱れると卵巣への指令がうまく伝わらず、エストロゲンの分泌が低下してしまうのです。
睡眠不足や不規則な生活
睡眠は、ホルモンバランスの調整や体の修復を行うための重要な時間です。慢性的な睡眠不足や昼夜逆転の生活は、自律神経の乱れを引き起こします。
自律神経と女性ホルモンの分泌をコントロールする中枢は、どちらも脳の視床下部にあるため、一方が乱れるともう一方も影響を受けやすい関係にあります。
このため、不規則な生活はエストロゲンの正常な分泌を妨げる原因となります。
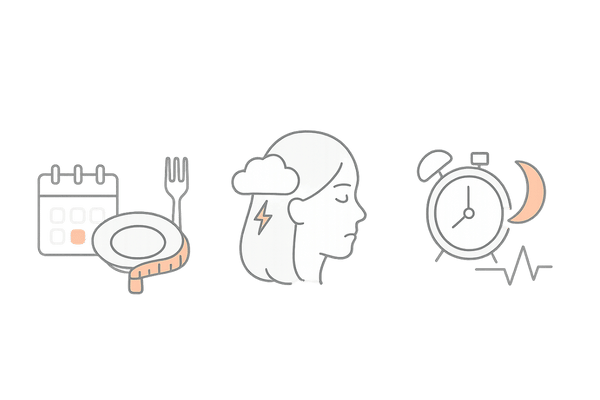
エストロゲン減少と薄毛の直接的な関係
エストロゲンの減少が、なぜ直接的に薄毛につながるのでしょうか。
そこには、髪の成長サイクルと、男性ホルモンとのバランスの変化という、2つの主要な関わりがあります。
髪の成長期(アナゲン)の短縮
前述の通り、エストロゲンは髪の成長期を長く保つ働きがあります。エストロゲンが減少すると成長期が短縮され、髪が十分に太く長く成長する前に退行期・休止期へと移行してしまいます。
結果として、一本一本の髪が細く(軟毛化)、抜けやすい状態になり、全体としてボリュームダウンした印象を与えます。
ヘアサイクルの変化
| 状態 | 成長期の期間 | 髪の状態 |
|---|---|---|
| エストロゲンが十分 | 長い (2〜6年) | 太く、長く成長し、ハリ・コシがある |
| エストロゲンが減少 | 短い (数ヶ月〜1年) | 細く、短いままで抜け落ち、ボリュームが減る |
相対的な男性ホルモンの影響
女性の体内にも、ごく微量の男性ホルモン(アンドロゲン)が存在します。エストロゲンが十分に分泌されている間は、その影響はほとんど現れません。
しかし、エストロゲンが減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が優位になります。
男性ホルモンの一種であるテストステロンが特定の酵素と結びついてジヒドロテストステロン(DHT)に変換されると、このDHTが毛乳頭細胞に作用し、髪の成長を抑制する信号を出します。
これが女性における男性型脱毛症(FAGA)の一因と考えられています。
頭皮の血行不良と乾燥
エストロゲンには血管を拡張し、血流を促進する作用があります。また、コラーゲンの生成を助け、肌や頭皮の潤いを保つ働きも担います。
エストロゲンが減少すると頭皮の血行が悪化し、髪の成長に必要な栄養が毛根まで届きにくくなります。
同時に、頭皮が乾燥しやすくなり、フケやかゆみなどの頭皮トラブルを引き起こして健康な髪が育ちにくい環境になってしまいます。
見過ごしがちなエストロゲン減少のサイン
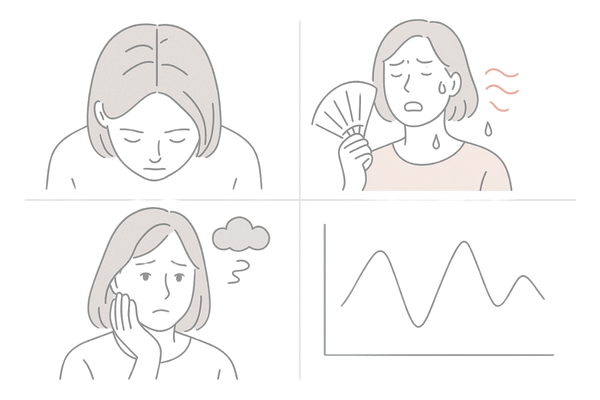
薄毛が気になり始めたとき、それはエストロゲン減少のサインの一つかもしれません。
しかし、体は髪以外にも様々な信号を発しています。これらのサインに気づくと、より早期の対策が可能になります。
髪以外の身体的な変化
エストロゲンは全身に作用するため、その減少は様々な身体的変化として現れます。
特に、月経周期の乱れは分かりやすい指標の一つです。周期が短くなったり長くなったり、経血量が変化したりした場合は注意が必要です。
その他、肌の乾燥やシワの増加、膣の乾燥感やホットフラッシュ(のぼせ・ほてり)、肩こりや関節痛なども代表的な症状です。
エストロゲン減少による身体的サイン
| 部位 | 症状の例 | エストロゲンとの関連 |
|---|---|---|
| 皮膚・粘膜 | 肌の乾燥、かゆみ、膣の乾燥 | コラーゲン生成の低下、潤い保持能力の低下 |
| 血管運動神経系 | ホットフラッシュ、発汗、動悸 | 自律神経の乱れによる血管の収縮・拡張コントロールの不調 |
| 骨・関節 | 肩こり、腰痛、関節痛 | 骨密度の低下、関節周りの組織の変化 |
月経周期の変化と基礎体温
基礎体温を記録するのは、ホルモンバランスの状態を知る上で有効な方法です。
正常な月経周期では、排卵を境に低温期と高温期の二相に分かれます。エストロゲンが減少してくると、排卵が不規則になったり起こらなくなったりするため、この二相性が不明瞭になります。
グラフがガタガタになったり、高温期が短くなったりしたときは卵巣機能の低下が考えられます。
コレステロール値の上昇
健康診断の結果も重要な手がかりになります。エストロゲンにはLDL(悪玉)コレステロールの増加を抑え、HDL(善玉)コレステロールを増やす働きがあります。
そのため、閉経期以降の女性はエストロゲンの保護作用が失われ、LDLコレステロール値が上昇しやすいです。
食事内容は変わらないのにコレステロール値が上がってきた場合、エストロゲンの減少が背景にある可能性があります。
「髪の変化」だけではない。心が感じるエストロゲン減少のサイン
薄毛の悩みは見た目の問題だけでなく、女性の心に深い影を落とすことがあります。
感情の揺らぎ自体も、エストロゲン減少によるサインの一つなのです。
理由のない不安感や気分の落ち込み
エストロゲンは、脳内で「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの働きを助ける作用があります。セロトニンは精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質です。
エストロゲンが減少するとセロトニンの活動も低下しやすくなり、理由もなく不安になったり、イライラしたり、気分が沈んでやる気が出なくなったりします。
これは決して性格の問題ではなく、ホルモンバランスの変化による生理的な現象なのです。
集中力や記憶力の低下
「最近、物忘れが多い」「仕事に集中できない」といった悩みもエストロゲン減少と関連があります。
エストロゲンは、脳の記憶を司る「海馬」という部分の働きを活性化させます。
そのため、エストロゲンが減ると新しいことを覚えにくくなったり、人の名前がすぐに出てこなかったりと、認知機能の低下を感じるときがあります。
これらの変化が、さらに自信を失わせる悪循環につながるケースもあります。
心と体に現れるサインの比較
| サインの種類 | 具体的な症状例 | 背景にあるホルモンの働き |
|---|---|---|
| 身体的サイン | 薄毛、ホットフラッシュ、肌の乾燥 | 髪の成長促進、自律神経調整、コラーゲン生成 |
| 精神的サイン | 不安感、イライラ、集中力低下 | セロトニン活性化、記憶・認知機能のサポート |
社会的な活動へのためらい
薄毛や体調の変化は、女性の社会的な自信を揺るがします。
髪型がうまく決まらないと外出が億劫になったり、仕事のパフォーマンスが落ちてキャリアへの不安を感じたり、友人との集まりや趣味の活動からも足が遠のいてしまう方も少なくありません。
このような社会的な孤立感はさらにストレスを増大させ、ホルモンバランスを乱す原因にもなりかねません。
自分でできるエストロゲン対策生活習慣の見直し
ホルモンの減少は避けられない部分もありますが、日々の生活習慣を見直すと、その影響を緩やかにし、心身の健康をサポートできます。
まずはご自身でできることから始めてみましょう。
バランスの取れた食事を心掛ける
体は食べたもので作られます。ホルモンのバランスを整えるためにも、特定の食品に偏るのではなく多様な食材から栄養を摂るのが基本です。
特に、タンパク質やビタミン、ミネラルは健康な髪と体を作る上で欠かせません。1日3食、規則正しく食べるのを目標にしましょう。
質の良い睡眠を確保する
睡眠中には、成長ホルモンをはじめとする様々なホルモンが分泌され、体の修復や調整が行われます。
なかでも夜10時から深夜2時は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、ホルモン分泌が活発になる時間帯です。
毎日同じ時間に就寝・起床する習慣をつけ、寝る前はスマートフォンやパソコンの光を避けるなど、リラックスできる環境を整えましょう。
睡眠の質を高めるための工夫
| カテゴリ | 就寝前の行動 | 避けるべき行動 |
|---|---|---|
| リラックス | ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる | 熱いシャワーで済ませる |
| 環境 | 照明を暗くし、静かな環境を作る | スマートフォンやテレビを見る |
| 飲食 | 温かいハーブティーなどを飲む | カフェインやアルコールを摂取する |
適度な運動を習慣にする
運動は血行を促進し、ストレス解消にもつながるため、ホルモンバランスを整える上で非常に有効です。
激しい運動である必要はなく、ウォーキングやヨガ、ストレッチなど、心地よいと感じる程度の有酸素運動を継続することが大切です。
週に3回、30分程度から始めてみましょう。運動習慣は、気分のリフレッシュにも役立ちます。
- ウォーキング
- ジョギング
- ヨガ・ピラティス
- 水泳
上手なストレス管理
現代社会でストレスを完全になくすのは困難です。大切なのは、ストレスを溜め込まずに上手に発散する方法を見つけることです。
趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したり、自然の中で過ごしたりと、自分なりのリラックス方法をいくつか持っておくと良いでしょう。
意識的に心と体を休ませる時間を作ると、ホルモンバランスの安定につながります。
エストロゲン対策をサポートする栄養素と食事

日々の食事内容を少し意識すると、女性ホルモンの働きをサポートし、髪の健康に必要な栄養を補えます。
特定の成分だけを大量に摂るのではなく、バランス良く取り入れると良いです。
大豆イソフラボンを摂取する
大豆製品に含まれる「大豆イソフラボン」は、化学構造がエストロゲンに似ており、体内でエストロゲンのような働きをすることが知られています。
エストロゲンの減少を補い、ホルモンバランスの乱れによる不調を和らげる効果が期待できます。
納豆や豆腐、味噌や豆乳などを日常の食事に積極的に取り入れましょう。
大豆イソフラボンを多く含む食品
| 食品名 | 1食あたりの目安量 | 手軽な取り入れ方 |
|---|---|---|
| 納豆 | 1パック (約40g) | 朝食や夕食の一品に加える |
| 豆腐 | 1/4丁 (約100g) | 冷奴や味噌汁の具材として |
| 豆乳 | コップ1杯 (200ml) | そのまま飲むか、料理に使う |
髪の主成分「タンパク質」を十分に
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、質の良いタンパク質の十分な摂取は、健康な髪を育てるための基本です。
肉や魚、卵や大豆製品など、動物性と植物性のタンパク質をバランス良く摂るように意識してください。
- 赤身肉
- 青魚(サバ、イワシなど)
- 鶏むね肉
- 卵
ビタミンとミネラルで頭皮環境を整える
ビタミンやミネラルは、タンパク質が髪の毛に変わるのを助けたり、頭皮の健康を保ったりする重要な役割を担います。
特に、亜鉛はケラチンの合成に必要で、ビタミンB群は頭皮の代謝を促進し、ビタミンEは血行を良くする働きがあります。
これらの栄養素は緑黄色野菜やナッツ類、玄米などに豊富に含まれています。
体を温める食材を選ぶ
体の冷えは血行不良を招き、頭皮に必要な栄養が届きにくくなる原因となります。
ショウガやネギ、カボチャや根菜類など、体を内側から温める効果のある食材を食事に取り入れるのも良い方法です。
温かいスープや飲み物で、体を冷やさない工夫も大切です。
専門クリニックに相談するタイミング
セルフケアは非常に重要ですが、症状が改善しない場合や急激に薄毛が進行して強い不安を感じる場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。
自己判断で悩みを抱え込まず、専門家の助けを借りるのも大切な選択です。
セルフケアで改善が見られないとき
食事や運動、睡眠などの生活習慣を2〜3ヶ月続けてみても抜け毛が減らなかったり、薄毛の範囲が広がったりするなど、改善の兆しが見られないときは、いちど専門医の診察を受けることを検討しましょう。
背景に他の原因が隠れている可能性もあります。
抜け毛の量が急に増えたとき
シャンプーやブラッシングの際に明らかに以前より抜け毛の量が増えたと感じる場合や、特定の部位が急に薄くなった場合は、早めの受診が重要です。
脱毛症には様々な種類があり、早期の対応がその後の経過に大きく影響する場合があります。
クリニック受診を検討する目安
| 症状・状態 | 期間の目安 | 考えられること |
|---|---|---|
| セルフケアを続けても変化なし | 3ヶ月以上 | 生活習慣以外の要因が強い可能性 |
| 抜け毛の量が明らかに増加 | 1ヶ月以内 | 活動性の高い脱毛症の可能性 |
| 頭皮のかゆみや痛みを伴う | 症状出現時 | 皮膚疾患や炎症の併発 |
精神的なストレスが大きいとき
薄毛の悩みで日常生活に支障が出ている、人と会うのがつらい、常に気分が落ち込んでいるなど、精神的な負担が大きい場合も専門家への相談が助けになります。
悩みを話すだけでも気持ちが軽くなるときがありますし、医学的な観点からのアドバイスは、漠然とした不安を和らげることにつながります。
一人で抱え込まずに、専門のクリニックを頼ってください。
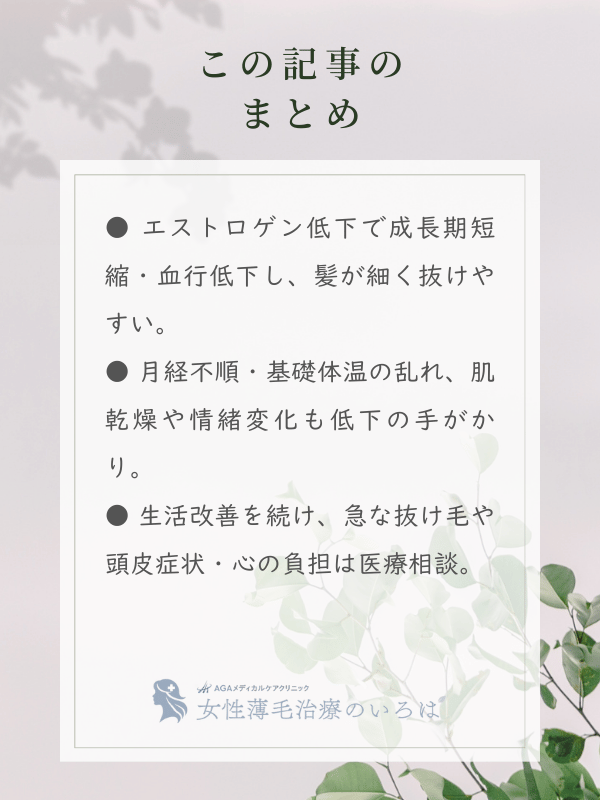
よくある質問
さいごに、エストロゲンや薄毛に関してよくいただく質問をまとめます。
- 大豆製品をたくさん食べればエストロゲンは増えますか?
-
大豆イソフラボンはエストロゲン様の作用を持ちますが、体内で直接エストロゲンに変わるわけではなく、また摂取した分だけ効果が無限に増えるものでもありません。
あくまでホルモンバランスをサポートする役割と捉え、バランスの取れた食事の一部として適量を摂取することが大切です。
サプリメントなどで過剰に摂取すると、かえってバランスを崩す可能性も指摘されているため、食事から摂ることを基本にしてください。
- 母親が更年期に薄毛で悩んでいました。遺伝しますか?
-
薄毛になりやすい体質(髪の太さや毛量の多さなど)が遺伝する可能性はあります。
また、ホルモンの影響の受けやすさにも個人差があり、それには遺伝的な要因も関わると考えられています。しかし、必ずしも同じ経過をたどるわけではありません。
生活習慣やストレスなど後天的な要因も大きく影響するため、ご自身の体と向き合い、早期から適切なケアを行うのが重要です。
- ピルを飲むと薄毛は改善しますか?
-
低用量ピルには、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)が含まれており、ホルモンバランスを安定させる作用があります。
この作用により、ホルモンバランスの乱れが原因である一部の薄毛症状が改善する可能性はあります。
しかし、ピルには血栓症などのリスクもあり、全ての女性に適しているわけではありません。薄毛治療を目的とした安易な自己判断での服用は絶対に避けるべきです。
必ず医師の診察を受け、薄毛の原因を正確に診断した上で、治療法の一つとして適切かどうかを判断してもらう必要があります。
参考文献
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.
VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.
REDLER, Silke; MESSENGER, Andrew G.; BETZ, Regina C. Genetics and other factors in the aetiology of female pattern hair loss. Experimental Dermatology, 2017, 26.6: 510-517.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.
RAMOS, Paulo Müller; MIOT, Hélio Amante. Female pattern hair loss: a clinical and pathophysiological review. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90: 529-543.
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
YIP, Leona; RUFAUT, Nick; SINCLAIR, Rod. Role of genetics and sex steroid hormones in male androgenetic alopecia and female pattern hair loss: an update of what we now know. Australasian Journal of Dermatology, 2011, 52.2: 81-88.