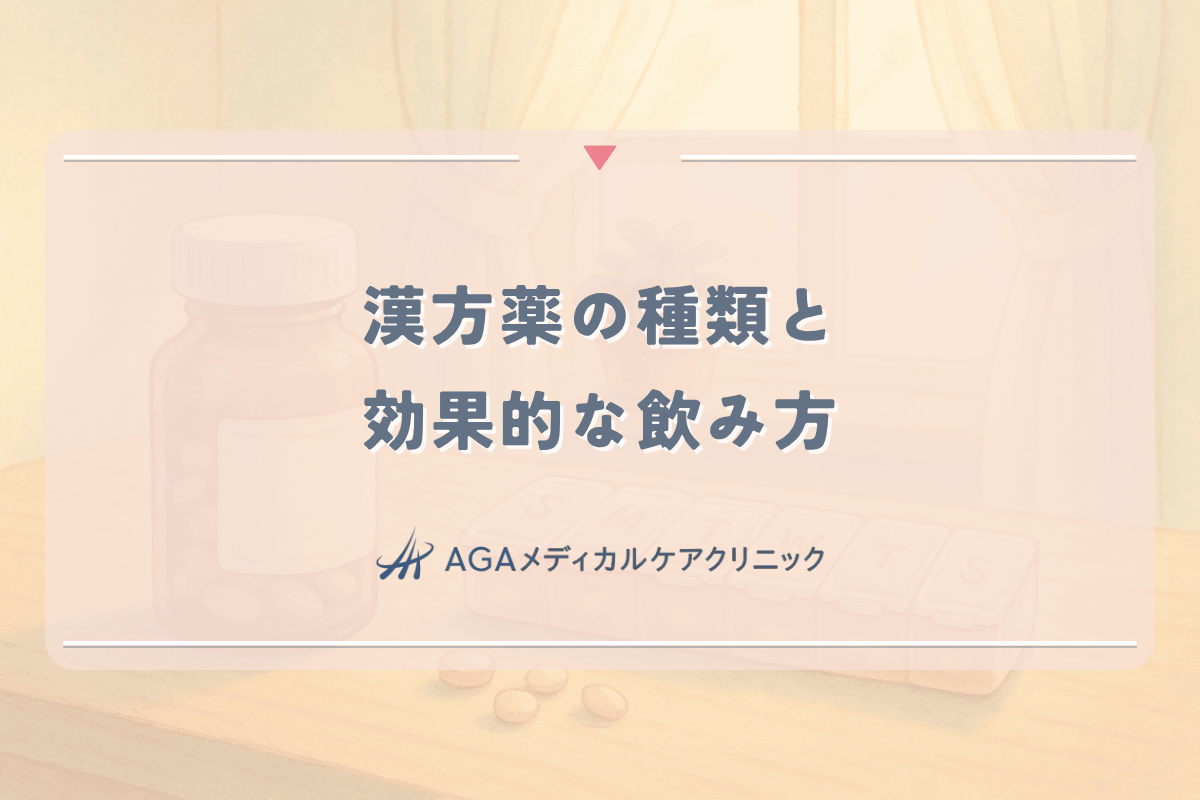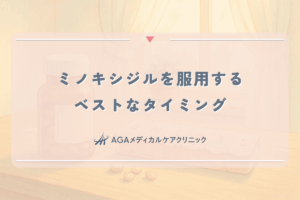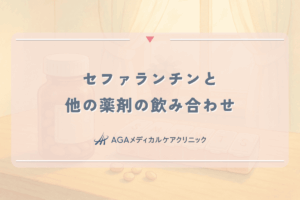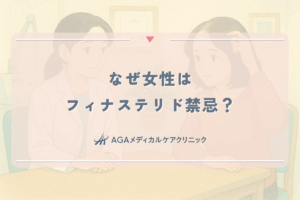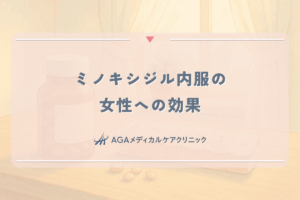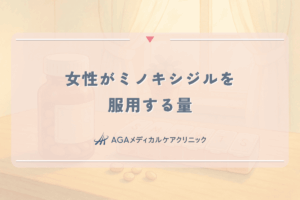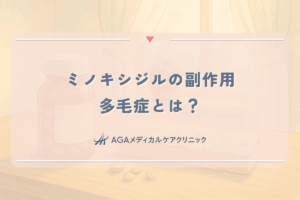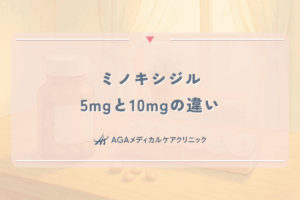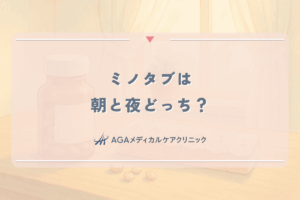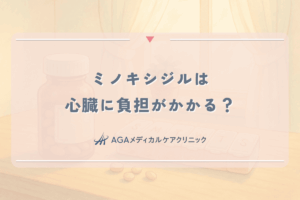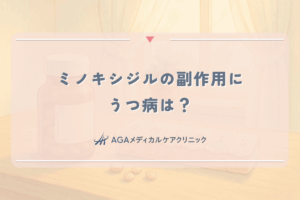鏡を見るたびに気になる髪のボリュームダウンや地肌の透け感に「何とかしたい」と悩む女性は少なくありません。
さまざまな治療法がある中で、体質から改善を目指す漢方薬が注目されています。
この記事では、女性の抜け毛や薄毛治療になぜ漢方薬が用いられるのか、その理由から、体質別に使われる漢方薬の種類、効果を高める飲み方、注意点までを詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
女性の抜け毛になぜ漢方薬が注目されるのか
近年、女性の抜け毛や薄毛の悩みに対して、漢方薬を用いた治療を選択する方が増えています。
西洋医学の治療が直接的な症状に作用するのに対し、漢方薬は体全体のバランスを整えて、根本的な原因に働きかけます。
髪は体の一部であり、その健康は全身の状態と深く関わっているという考え方が、漢方治療の根底にあります。
髪は「血の余り」という考え方
漢方医学には「髪は血余(けつよ)」という言葉があります。これは、髪が体内の「血(けつ)」が充実して初めて、その余りで作られるという考え方です。
血が不足したり巡りが悪くなったりすると、髪に十分な栄養が届かなくなり、抜け毛や白髪、髪のパサつきなどのトラブルが現れます。
特に女性は月経や妊娠、出産、更年期などで血を消耗しやすいため、血の不足が抜け毛の大きな原因となりやすいのです。
漢方における「血」の役割
| 役割 | 解説 | 不足した場合の髪への影響 |
|---|---|---|
| 栄養運搬 | 全身の組織や器官に栄養を届ける。 | 髪が細くなる、ツヤがなくなる |
| 精神安定 | 精神活動を支え、心を穏やかに保つ。 | ストレス性の抜け毛 |
| 潤い保持 | 皮膚や髪に潤いを与える。 | 頭皮の乾燥、フケ、髪のパサつき |
心と体のバランスを整える
漢方では心と体は一体であると捉えます。過度なストレスや悩みは、「気(き)」の流れを滞らせ、血の巡りを悪化させます。
この気の滞りが自律神経の乱れやホルモンバランスの崩れを引き起こし、結果として頭皮環境の悪化や抜け毛につながります。
漢方薬は、気の巡りを改善して精神的な緊張を和らげ、心身両面から抜け毛の起こりにくい状態へと導きます。
一人ひとりの体質に合わせたアプローチ
同じ抜け毛の悩みでも、その原因は人それぞれ異なります。漢方治療の大きな特徴は、個々の体質や症状に合わせて処方を細かく調整する点にあります。
専門家が「証(しょう)」と呼ばれる体質を見極め、その人に最も合った漢方薬を選びます。
このオーダーメイドの取り組みにより、抜け毛だけでなく、冷えや疲労感、月経不順といった全身の不調も同時に改善することが期待できます。
漢方医学が捉える女性の抜け毛の主な原因
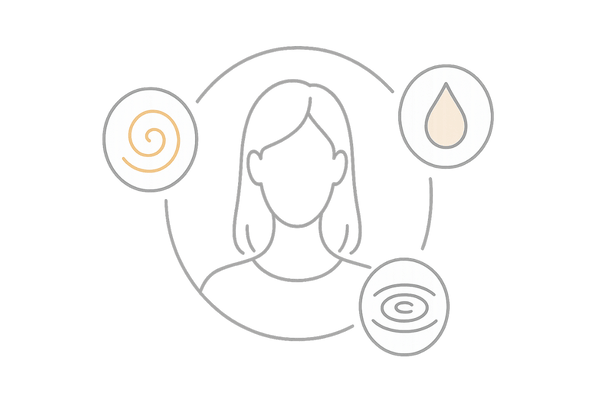
漢方医学では抜け毛の原因を一つの要因に絞るのではなく、「気・血・水(き・けつ・すい)」という3つの要素のバランスの乱れから考えます。
これらは生命活動を維持するための基本的な物質であり、互いに影響し合っています。
女性の抜け毛では、特にこれらのうちの複数が関係しているケースが少なくありません。
気血両虚(きけつりょうきょ)
「気」は生命エネルギー、「血」は栄養と潤いの源です。気血両虚とは、この両方が不足している状態を指します。
エネルギー不足で血を作り出す力も弱まり、作られた血も少ないため、頭皮や髪に栄養が十分に行き渡りません。
産後の抜け毛や、過度なダイエット、慢性的な疲労がある方に見られやすいタイプです。
気血両虚の主なサイン
| 項目 | 具体的な症状 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 全身症状 | 疲れやすい、顔色が悪い、めまい、立ちくらみ | 全体的に髪が薄くなる、髪が細く弱々しい |
| 精神症状 | 不安感、動悸、眠りが浅い | 抜け毛が増える |
| その他 | 爪がもろい、皮膚が乾燥する | 髪のツヤがなくなる |
腎虚(じんきょ)
漢方における「腎(じん)」は成長や発育、生殖機能を司り、生命力の源を蓄える場所と考えられています。
加齢とともに腎の働きは自然と衰えますが、若くても過労や睡眠不足、性生活の不摂生などによって腎虚になる場合があります。
腎の衰えは髪の健康に直結し、白髪や抜け毛の大きな原因となります。
瘀血(おけつ)
瘀血とは、血の流れが滞り、ドロドロになった状態です。ストレスや冷え、運動不足などが原因で起こります。
血流が悪化すると頭皮の毛細血管まで新鮮な栄養が届かず、毛根が栄養不足に陥り、髪が抜けやすくなります。
肩こりや頭痛、月経痛がひどい方に多いタイプです。
抜け毛タイプ別に見る代表的な漢方薬

女性の抜け毛治療で使われる漢方薬は、原因となる体質(証)に合わせて選ばれます。ここでは、先ほど解説した主な原因タイプごとに、代表的な処方を紹介します。
ただし、自己判断での服用は避け、必ず専門の医師や薬剤師に相談してください。
気血両虚タイプ向けの漢方薬
エネルギーと栄養の両方を補うことが治療の主眼となります。胃腸の働きを助け、効率よく栄養を吸収できる体作りを目指します。
- 人参養栄湯(にんじんようえいとう)
- 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
- 加味帰脾湯(かみきひとう)
代表的な気血双補剤
| 漢方薬名 | 特徴 | 抜け毛以外の適応症状 |
|---|---|---|
| 人参養栄湯 | 気血を補い、特に疲労倦怠感が強い場合に用いる。 | 食欲不振、寝汗、手足の冷え |
| 十全大補湯 | 気血を強力に補う。手術後や病後の体力低下にも。 | 貧血、皮膚の乾燥、疲労感 |
腎虚タイプ向けの漢方薬
生命力の源である「腎」を補い、アンチエイジングを目指す処方が中心です。体を温め、生殖機能を高める生薬が含まれる場合が多いです。
代表的な補腎薬
| 漢方薬名 | 特徴 | 抜け毛以外の適応症状 |
|---|---|---|
| 七宝美髯丹(しちほうびぜんたん) | 腎を補い、血を養う。白髪や若白髪にも用いられる。 | 足腰のだるさ、精力減退 |
| 八味地黄丸(はちみじおうがん) | 体を温めながら腎を補う。特に高齢者や冷えが強い方に。 | 頻尿、むくみ、かすみ目 |
瘀血タイプ向けの漢方薬
滞った血の流れをスムーズにするのが目標です。血行を促進する生薬を中心に構成された処方が選ばれます。
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 桃核承気湯(とうかくじょうきとう)
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
特に当帰芍薬散は、血を補いながら水の巡りも整えるため、冷え症でむくみやすい女性の抜け毛によく用いられます。
ストレスが強いタイプ向けの漢方薬
ストレスによって乱れた「気」の流れを整えるのが重要です。自律神経のバランスを調整し、心身の緊張をほぐします。
代表的な理気剤
| 漢方薬名 | 特徴 | 抜け毛以外の適応症状 |
|---|---|---|
| 加味逍遙散(かみしょうようさん) | 気の巡りを改善し、血を補う。イライラや不安感に。 | 月経不順、更年期障害、肩こり |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう) | 精神的な不安が強く、動悸や不眠がある場合に用いる。 | 高血圧、神経症、円形脱毛症 |
漢方薬の効果を高めるための正しい飲み方
せっかく漢方薬を服用するなら、その効果を最大限に引き出したいものです。
漢方薬は飲み方や飲むタイミングにも少し工夫が必要です。基本的なポイントを押さえて、治療効果を高めましょう。
飲むタイミングは「食前」または「食間」
漢方薬は、空腹時に服用するのが基本です。胃に食べ物が入っていると、生薬の吸収が妨げられる場合があるためです。
「食前」は食事の約30分前、「食間」は食事と食事の間のことで、食後2時間後くらいが目安となります。
飲み忘れを防ぐためにも、ご自身の生活リズムに合わせてタイミングを決めておくとよいでしょう。
白湯(さゆ)で飲むのがおすすめ
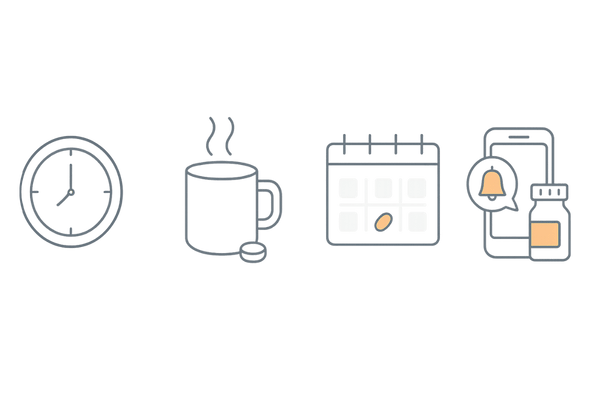
漢方薬は水または白湯で服用します。体を温める効果のある生薬が含まれている場合も多いため、白湯で飲むと胃腸に優しく、吸収も助けます。
お茶やコーヒー、ジュースなどで飲むと、成分の吸収に影響を与える可能性があるため避けてください。
飲み忘れた場合の対処法
もし飲み忘れてしまった場合は、気づいた時点で服用してください。
ただし、次の服用時間が近い場合は、1回分は抜かして次のタイミングで服用します。絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。
飲み忘れが多いと期待する効果が得られにくくなるため、習慣化していきましょう。
漢方治療と西洋医学の治療はどう違うのか
抜け毛治療には、漢方薬だけでなく西洋医学的な方法もあります。それぞれに得意な領域があり、どちらか一方が優れているというわけではありません。
両者の違いを理解し、必要に応じて組み合わせるのも有効な選択肢となります。
働きかけの違い
西洋医学は、症状の原因となっている特定の物質(例えば男性ホルモンなど)に直接作用する薬を用いて、症状を抑えることを得意とします。
一方、漢方医学は、症状を引き起こしている体全体のバランスの乱れ(体質)を整え、根本的な改善を目指します。
この働きかけ方の違いが、治療法や効果の現れ方に差を生みます。
治療法の働きかけ比較
| 項目 | 西洋医学の治療 | 漢方医学の治療 |
|---|---|---|
| 治療の対象 | 症状そのもの(例 抜け毛) | 症状を引き起こす体質(例 気血両虚) |
| 治療の考え方 | 原因物質の抑制、血行促進など局所への働きかけ | 気・血・水のバランスを整える全身への働きかけ |
| 効果の現れ方 | 比較的早く効果を実感しやすいことがある | 穏やかに、時間をかけて体質から変化する |
得意とする領域
例えば、AGA(男性型脱毛症)のように原因が比較的はっきりしているときは、西洋医学の治療薬の効果を実感しやすい場合があります。
一方で、原因が一つに特定しにくいびまん性脱毛症や、産後の抜け毛、更年期に伴う抜け毛など、体全体のホルモンバランスや心身の状態が複雑に関わる場合は、漢方治療が非常に有効です。
治療法の併用について
西洋医学の治療と漢方治療は、互いに補完し合う関係にあります。
例えば、西洋薬で抜け毛を抑えつつ、漢方薬で抜けにくい健康な髪が生えるための土台となる体作りを進める、といった併用も可能です。
ただし、薬の飲み合わせの問題もあるため、併用を希望する場合は必ず両方の治療に詳しい医師に相談しましょう。
漢方薬選びで陥りやすい「自己判断の落とし穴」
最近ではインターネットで手軽に情報が手に入り、ドラッグストアでも多くの漢方薬が販売されています。
しかし、その手軽さがかえって「自己判断による誤った漢方薬選び」という落とし穴につながることがあります。
ご自身の体を大切にするためにも、漢方薬との正しい向き合い方を知っておきましょう。
「有名な漢方薬」が自分に合うとは限らない
「女性の抜け毛にはこの漢方が良い」といった情報を見かけるときがあります。
例えば「当帰芍薬散」や「加味逍遙散」は婦人科系の悩みで有名ですが、これらが誰にでも効くわけではありません。
漢方の本質は「同病異治(どうびょういち)」にあります。同じ「抜け毛」という病(症状)でも、原因となる体質(証)が異なれば、治療法(処方)も全く異なります。
冷え性の方向けの漢方薬を、体に熱がこもっている方が飲むと、かえって症状が悪化することさえあります。
一つの症状だけで判断する危険性
抜け毛という一つの症状だけで漢方薬を選ぶのは非常に危険です。
漢方の専門家は、抜け毛以外にも、顔色や舌の状態、脈やお腹の張り、睡眠や食事、月経の状態など、全身の状態を総合的に診察して「証」を決定します。
これらの情報がパズルのピースのように組み合わさって、初めてあなたに本当に合った処方が見つかるのです。
ネットの情報だけでピースを一つだけ見て全体を判断すると、間違った結論に至る可能性が非常に高いと言えます。
漢方選びの比較
| 判断方法 | 判断材料 | 結果 |
|---|---|---|
| 自己判断 | ネット情報、抜け毛という単一の症状 | 体質に合わず効果が出ない、または副作用のリスク |
| 専門家の診断 | 問診、舌診、腹診など全身の状態 | 体質に合った処方で、根本改善が期待できる |
効果が出ない時に「量が足りない?」と誤解する
自己判断で選んだ漢方薬を飲んで効果が出ないと、「飲む量が足りないのかもしれない」と考えて量を増やしてしまう方がいます。しかし、これは大変危険です。
効果が出ない本当の理由は、量が足りないのではなく「そもそもその漢方薬が体質に合っていない」ケースがほとんどです。
間違った処方を多く飲めば、それだけ副作用のリスクも高まります。効果を実感できない場合は量を増やすのではなく、処方そのものを見直す必要があります。
漢方薬の副作用と注意すべき点

「漢方薬は自然由来だから安全」というイメージを持つ方も多いですが、医薬品である以上、副作用のリスクはゼロではありません。
正しく服用し、万が一の時に適切に対処するためにも、副作用について確認しておきましょう。
起こりうる副作用
漢方薬の副作用で比較的多いのは、胃もたれや食欲不振、下痢、便秘などの消化器症状です。
また、発疹やかゆみなどの皮膚症状が現れる場合もあります。
まれに、間質性肺炎や肝機能障害、偽アルドステロン症(高血圧、むくみ、低カリウム血症など)といった重篤な副作用が起こる可能性もあります。
- 消化器症状(胃もたれ、食欲不振、下痢など)
- 皮膚症状(発疹、かゆみなど)
- その他(むくみ、動悸、血圧上昇など)
副作用が起きた時の対応
漢方薬を服用し始めて何かいつもと違う体調の変化を感じた場合はまず服用を中止し、処方を受けた医師や薬剤師に速やかに相談してください。
「好転反応(良くなる過程での一時的な悪化)」ではないかと自己判断して服用を続けるのは危険です。
専門家が症状を詳しく聞き取り、副作用なのか、あるいは別の原因なのかを判断します。
特定の生薬に対する注意
一部の生薬には、特に注意が必要なものがあります。
例えば、「甘草(かんぞう)」は多くの漢方薬に含まれていますが、大量に長期間服用すると偽アルドステロン症を引き起こすケースがあります。
また、「麻黄(まおう)」は交感神経を興奮させる作用があるため、高血圧や心臓に持病のある方は注意が必要です。
複数の漢方薬を併用すると特定の生薬を過剰摂取してしまう可能性もあるため、服薬中の薬はすべて医師に伝えるようにしてください。
漢方治療を始める前に知っておきたいこと
漢方による抜け毛治療は、じっくりと自分の体と向き合う治療法です。
始める前にいくつかのポイントを知っておくと、よりスムーズに、そして効果的に治療を進められます。
効果を実感するまでの期間
漢方治療は、体質そのものを時間をかけて改善していく方法です。そのため、西洋薬のようにすぐに劇的な変化が現れるわけではありません。
効果の実感には個人差がありますが、一般的にはまず2〜3ヶ月間は継続して服用することが推奨されます。
抜け毛の改善だけでなく、冷えや疲労感など、髪以外の不調が先に改善してくる方も多く、それが体質が変わり始めたサインとなります。
保険適用の可否
医療機関で医師の診断のもとに処方される漢方薬の多くは、健康保険が適用されます。これにより、治療費の負担を抑えながら治療を続けられます。
ただし、すべての漢方薬や治療が保険適用となるわけではないため、治療を始める前にクリニックで確認するとよいでしょう。
治療と並行して行いたい生活習慣の見直し
漢方薬の効果を最大限に引き出すためには、日々の生活習慣の見直しも非常に重要です。
薬だけに頼るのではなく、食事や睡眠、運動といった生活の基本を整えると、相乗効果が期待できます。
髪の健康を支える生活習慣
| 項目 | ポイント | 漢方的な意味合い |
|---|---|---|
| 食事 | バランスの取れた食事。特に黒い食材(黒ごま、黒豆、海藻類)を意識する。 | 血を補い、腎を養う。 |
| 睡眠 | 質の良い睡眠を十分にとる。夜更かしを避ける。 | 血を養い、気を回復させる。 |
| 運動 | 適度な運動を習慣にする。ウォーキングなど軽いものから。 | 気の巡りを良くし、血行を促進する。 |
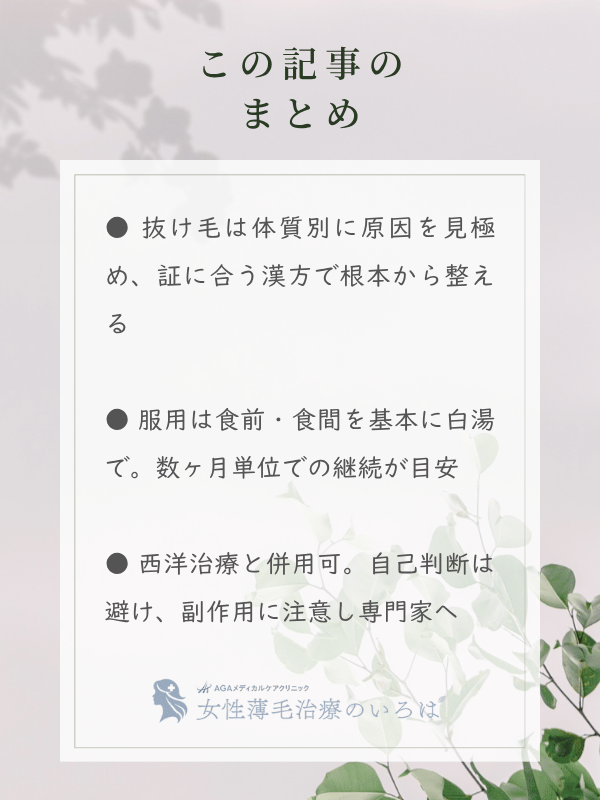
女性の抜け毛と漢方に関するよくある質問
さいごに、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- どのくらいの期間、漢方薬を飲み続ける必要がありますか
-
治療期間は、その方の症状の重さや体質、生活習慣によって大きく異なります。
まずは3ヶ月程度を目安に体質の変化を見て、その後は症状の改善度合いに応じて、医師と相談しながら継続の可否や処方の変更を検討していきます。
状態が安定すれば、徐々に薬の量を減らしたり、服用を終了したりすることも可能です。
- 妊娠中や授乳中でも漢方薬は飲めますか
-
妊娠中や授乳中は、使用できる漢方薬が限られます。胎児や乳児への影響を考慮する必要があるため、自己判断での服用は絶対に避けてください。
産後の抜け毛に対しては授乳中でも安全に使える処方がありますので、必ず専門の医師に相談の上、適切な漢方薬を処方してもらうようにしてください。
- 漢方薬の費用はどのくらいかかりますか
-
医療機関で処方されるエキス剤(粉薬や錠剤)の場合、健康保険が適用されれば、自己負担額は3割(年齢や所得による)となります。
1ヶ月あたりの薬剤費は処方内容によって異なりますが、数千円程度になるのが一般的です。詳しい費用については、受診するクリニックにお問い合わせください。
- ドラッグストアの漢方薬との違いは何ですか
-
ドラッグストアで販売されている漢方薬は、比較的多くの人に使えるように作られた「一般用医薬品」です。
一方、医師が処方する漢方薬は「医療用医薬品」であり、より専門的な判断に基づいて、個人の体質に合わせてきめ細かく選ばれます。
根本的な体質改善を目指すのであれば、専門医の診断のもとで処方される医療用漢方薬を選ぶことを推奨します。
参考文献
USHIROYAMA, Takahisa, et al. Clinical efficacy of EH0202, a Kampo formula, on the health of middle-aged women. The American Journal of Chinese Medicine, 2004, 32.05: 755-770.
YAMADA, Haruki. Japanese kampo medicine. Writing in plain English, 2010, 225.
MOTOO, Yoshiharu; ARAI, Ichiro; TSUTANI, Kiichiro. Use of Kampo diagnosis in randomized controlled trials of Kampo products in Japan: a systematic review. PLoS One, 2014, 9.8: e104422.
SADGROVE, Nicholas John. The new paradigm for androgenetic alopecia and plant-based folk remedies: 5α-reductase inhibition, reversal of secondary microinflammation and improving insulin resistance. Journal of ethnopharmacology, 2018, 227: 206-236.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
ASNAASHARI, Solmaz; JAVADZADEH, Yousef. Herbal Medicines For Treatment of Androgenic Alopecia. Alternative Therapies in Health & Medicine, 2020, 26.4.
HOSKING, Anna-Marie; JUHASZ, Margit; ATANASKOVA MESINKOVSKA, Natasha. Complementary and alternative treatments for alopecia: a comprehensive review. Skin appendage disorders, 2019, 5.2: 72-89.
CHO, Eun Chai; KIM, Kyuseok. A comprehensive review of biochemical factors in herbs and their constituent compounds in experimental studies on alopecia. Journal of ethnopharmacology, 2020, 258: 112907.