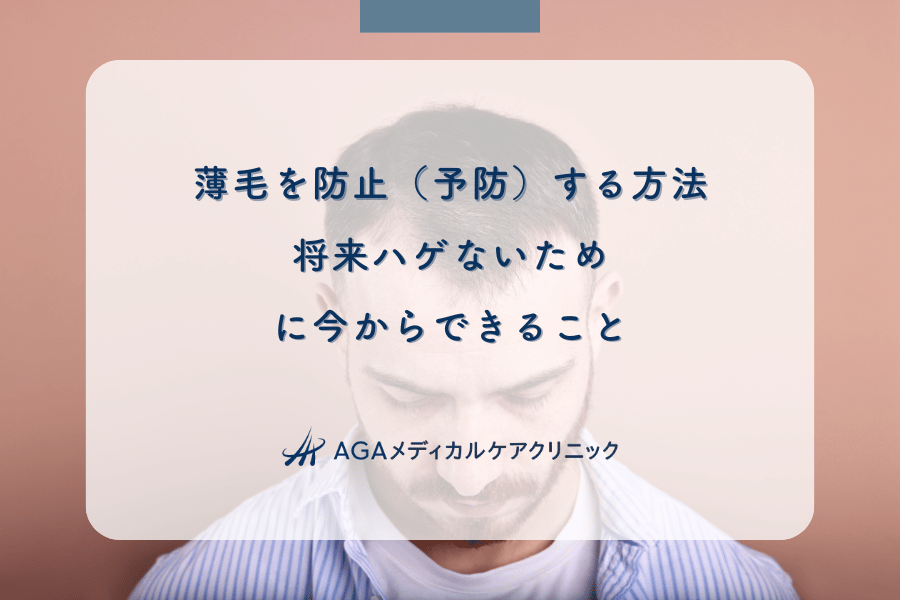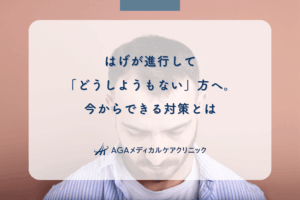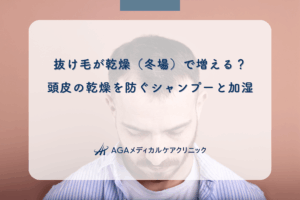「最近、抜け毛が増えた気がする」「将来、薄毛になるのではないか心配だ」と感じていませんか。薄毛の悩みは非常にデリケートですが、多くの場合、そのサインは早い段階から現れています。
薄毛を防止(予防)するためには、特別なことをするよりも、日々の生活習慣やヘアケアを見直すことが重要です。
この記事では、将来の髪のために今からできる具体的な薄毛の防止(予防)方法を、原因から対策まで詳しく解説します。手遅れになる前に、今日からできることから始めてみましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
まずは知っておきたい 薄毛が進行する主な原因
薄毛を効果的に防止(予防)するためには、まずなぜ薄毛が進行するのか、その原因を理解することが大切です。薄毛の原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。
自分の生活習慣や体質と照らし合わせながら、主な原因を探っていきましょう。
男性ホルモンの影響(AGA)
成人男性の薄毛で最も多い原因が「AGA(男性型脱毛症)」です。
これは、男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、頭皮に存在する「5αリダクターゼ」という酵素の働きによって「DHT(ジヒドロテストステロン)」に変換されることで引き起こされます。
このDHTが、髪の毛の成長サイクル(毛周期)を短縮させ、髪の毛が太く長く成長する前に抜け落ちるように指示を出します。その結果、髪の毛が細く短くなり、地肌が目立つようになるのです。
AGAは遺伝的な要因も関与しており、特に前頭部や頭頂部から薄毛が進行しやすい特徴があります。
生活習慣の乱れ
髪の毛は、私たちが日々摂取する栄養素から作られています。そのため、食生活の乱れは髪の健康に直接影響を与えます。偏った食事や無理なダイエットは、髪の成長に必要な栄養素の不足を招きます。
また、睡眠不足は髪の成長を促す「成長ホルモン」の分泌を妨げ、髪の毛の修復や再生が十分に行われなくなります。
喫煙や過度な飲酒も、血行不良や体内の栄養バランスの乱れを引き起こし、薄毛のリスクを高める要因となります。
頭皮環境の悪化
髪の毛が育つ土壌である頭皮の環境が悪化することも、薄毛の大きな原因となります。皮脂の過剰な分泌や、逆に乾燥しすぎている状態は、頭皮の健康を損ないます。
間違ったシャンプーの方法や、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用は、頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい、乾燥やかゆみ、フケの原因となります。
また、洗い残したシャンプー剤や皮脂が毛穴に詰まると、炎症を引き起こし、健康な髪の成長を妨げることにつながります。
ストレスと血行不良
精神的なストレスも薄毛と深く関係しています。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮します。
これにより、頭皮への血流が悪化し、髪の毛の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで届きにくくなります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こすこともあり、間接的に薄毛を促進する可能性があります。
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けることも、首や肩のコリを引き起こし、頭部への血行不良を招く一因となります。
将来のために今日から実践 食生活で見直す薄毛予防
健康な髪の毛は、日々の食事から作られます。薄毛を防止(予防)するためには、外側からのケアだけでなく、内側から、つまり食生活から見直すことが非常に重要です。
バランスの取れた食事を心がけ、髪の成長に必要な栄養素をしっかり補給しましょう。
髪の毛の成長に必要な栄養素
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、良質なタンパク質の摂取は、薄毛予防の基本中の基本です。しかし、タンパク質だけを摂っていても髪は作られません。
摂取したタンパク質をケラチンに再合成する際には、「亜鉛」が重要な役割を果たします。
また、「ビタミン類」は頭皮の血行を促進したり、皮脂のバランスを整えたりと、頭皮環境を健やかに保つために必要です。
髪の成長をサポートする主な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の毛の主成分「ケラチン」の材料となる | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の再合成を助け、毛母細胞の分裂を促す | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ、アーモンド |
| ビタミンB群 | 皮脂の分泌調整、血行促進、タンパク質の代謝を助ける | レバー、うなぎ、マグロ、カツオ、納豆、卵 |
薄毛予防のために積極的に摂りたい食品
特定の食品だけを食べれば薄毛が防げるわけではありませんが、先に挙げた栄養素を効率よく摂取できる食品を意識的に取り入れることは有効です。
例えば、大豆製品に含まれる「イソフラボン」は、AGAの原因となるDHTの生成を抑制する働きが期待されています。
また、緑黄色野菜に含まれるビタミンAやビタミンCは、頭皮の健康維持に役立ちます。海藻類に含まれるミネラルも、髪の成長をサポートします。
控えるべき食習慣
健康な髪を育てるためには、避けるべき食習慣も知っておくことが大切です。特に、高脂肪食や高カロリー食は、皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
また、塩分や糖分の過剰摂取も、血行不良や体内の炎症を引き起こす可能性があり、髪の成長にとって良い環境とは言えません。
注意したい食習慣と髪への影響
| 控えるべき食習慣 | 髪への主な影響 |
|---|---|
| 高脂肪・高カロリー食(揚げ物、ジャンクフードなど) | 皮脂の過剰分泌を招き、毛穴の詰まりや炎症の原因となる |
| 糖分の過剰摂取(甘いお菓子、ジュースなど) | 皮脂の分泌を増加させ、頭皮環境の悪化につながる |
| 塩分の過剰摂取(加工食品、スナック菓子など) | 血行不良を引き起こし、頭皮への栄養供給を妨げる可能性がある |
バランスの取れた食事の組み立て方
薄毛予防のための食事は、主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル)を揃える「一汁三菜」の和食スタイルが理想的です。
毎食完璧に揃えるのが難しくても、1日の中でバランスが取れるように意識しましょう。
例えば、朝食に卵や納豆でタンパク質を補給し、昼食は外食でも野菜の多いメニューを選び、夕食で魚や海藻を取り入れるなど、工夫次第で栄養バランスは改善できます。
健やかな髪を育む生活習慣の改善ポイント
食事と同様に、日々の生活習慣も髪の健康に深く関わっています。質の高い睡眠、適度な運動、そして禁煙や節度ある飲酒。これら一つひとつの積み重ねが、薄毛を防止(予防)する大きな力となります。
忙しい毎日の中でも、意識的に生活リズムを整えていきましょう。
質の高い睡眠を確保する
髪の毛は、私たちが寝ている間に成長します。
特に、入眠してから最初の3時間程度(ノンレム睡眠中)に多く分泌される「成長ホルモン」が、毛母細胞の分裂を活発にし、髪の毛の修復と成長を促します。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、この成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長に悪影響が出ます。
毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きる規則正しい生活を心がけ、寝る前のスマートフォン操作を控えるなど、質の高い睡眠を確保するための工夫をしましょう。
適度な運動で血行を促進する
運動不足は、全身の血行不良を招きます。頭皮は心臓から遠い位置にあるため、血行が悪くなると真っ先に栄養不足に陥りやすい部位です。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な有酸素運動は、全身の血行を促進し、頭皮の毛細血管までしっかりと血液(栄養)を届けるのに役立ちます。
また、運動はストレス解消にも効果的であり、心身両面から薄毛予防にアプローチできます。週に2〜3回、30分程度からでも良いので、継続的に体を動かす習慣をつけましょう。
喫煙と飲酒のリスク
喫煙は、薄毛予防の観点からは百害あって一利なしと言えます。タバコに含まれるニコチンには強力な血管収縮作用があり、頭皮の血行を著しく悪化させます。
また、体内のビタミンCを大量に消費するため、髪の健康維持に必要な栄養素が奪われてしまいます。過度な飲酒も同様です。
アルコールが体内で分解される際には、髪の毛の材料となるアミノ酸や、代謝を助けるビタミンB群が消費されます。さらに、過度な飲酒は肝臓に負担をかけ、タンパク質の合成能力を低下させる可能性があります。
お酒は適量を守り、休肝日を設けるなど、節度ある付き合い方を心がけましょう。
毎日の習慣が鍵 正しいヘアケアと頭皮環境の整え方
頭皮は髪の毛が育つための土壌です。この土壌が荒れていては、健康な髪は育ちません。毎日のシャンプーやヘアケアの方法を見直すことは、薄毛を防止(予防)するための非常に重要なステップです。
頭皮を清潔に保ちつつ、必要な潤いを守るケアを学びましょう。
自分に合ったシャンプーの選び方
シャンプーは、頭皮の汚れや余分な皮脂を洗い流すために必要ですが、自分の頭皮タイプに合っていないものを使うと、かえって頭皮環境を悪化させる原因になります。
例えば、乾燥肌の人が洗浄力の強いシャンプーを使うと、必要な皮脂まで奪われてさらに乾燥が進みます。
逆に、脂性肌の人がマイルドすぎるシャンプーを使うと、皮脂や汚れが落としきれず、毛穴の詰まりを引き起こす可能性があります。
頭皮タイプ別 シャンプー選びの目安
| 頭皮タイプ | 特徴 | シャンプー選びのポイント |
|---|---|---|
| 普通肌 | 適度な皮脂と水分があり、トラブルが少ない | アミノ酸系など、マイルドな洗浄力のもの |
| 脂性肌 | 皮脂分泌が多く、ベタつきやすい | 適度な洗浄力があり、さっぱりと洗い上がるもの |
| 乾燥肌 | 皮脂が少なく、カサつきやフケが出やすい | 保湿成分配合で、洗浄力がマイルドなもの |
| 敏感肌 | 刺激に弱く、赤みやかゆみが出やすい | 無添加・低刺激処方で、アレルギーテスト済みのもの |
頭皮を傷つけないシャンプーの手順
シャンプーは「髪を洗う」というよりも「頭皮を洗う」という意識が大切です。間違った洗い方は、頭皮を傷つけたり、必要な皮脂を奪いすぎたりする原因となります。
以下の手順を参考に、正しいシャンプー方法をマスターしましょう。
正しいシャンプーの手順
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. ブラッシング | 洗う前に髪のもつれを解き、ホコリや汚れを浮かせます。 |
| 2. 予洗い(湯洗い) | シャンプーをつける前に、ぬるま湯で頭皮と髪をしっかり濡らし、汚れの7割程度を落とします。 |
| 3. シャンプーを泡立てる | シャンプーを手のひらで軽く泡立ててから、頭皮に均等につけます。(直接頭皮につけない) |
| 4. 頭皮を洗う | 指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立ててゴシゴシ洗うのは厳禁です。 |
| 5. すすぎ | 洗い残しがないよう、時間をかけて丁寧にすすぎます。特に生え際や耳の後ろは残りやすいので注意します。 |
| 6. 乾燥 | タオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで根本から乾かします。自然乾燥は雑菌の繁殖や頭皮の冷えの原因となります。 |
頭皮マッサージの効果と方法
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに有効な方法です。血流が改善されることで、毛根に栄養が届きやすくなり、健康な髪の成長をサポートします。
シャンプー中や、入浴後などのリラックスしたタイミングで行うのがおすすめです。
自宅でできる簡単頭皮マッサージ
| 部位 | マッサージ方法 |
|---|---|
| 側頭部 | 両手の指の腹を耳の上に当て、円を描くように優しく揉みほぐしながら、頭頂部に向かって引き上げます。 |
| 前頭部 | 両手の指の腹を生え際に当て、頭皮を動かす意識で、ジグザグに動かしながら頭頂部へ向かいます。 |
| 頭頂部・後頭部 | 両手の指を組み、頭頂部を包み込むように掴み、頭皮全体を優しく圧迫したり、持ち上げたりします。後頭部も同様に行います。 |
マッサージを行う際は、爪を立てず、指の腹を使うことが重要です。頭皮を擦るのではなく、頭皮そのものを動かすイメージで行いましょう。1回あたり3〜5分程度を目安に、心地よいと感じる強さで続けてください。
紫外線対策の重要性
顔や肌と同じように、頭皮も紫外線のダメージを受けます。紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こすだけでなく、髪の毛の主成分であるタンパク質を破壊することもあります。
特に髪の分け目や頭頂部は紫外線を浴びやすいため注意が必要です。
外出時には帽子をかぶる、日傘を使う、頭皮用の日焼け止めスプレーを利用するなど、季節を問わず紫外線対策を心がけることが、薄毛予防につながります。
心の健康も髪に影響 ストレスとの上手な付き合い方
現代社会においてストレスを完全になくすことは難しいですが、ストレスが体に与える影響を理解し、上手にコントロールすることは、薄毛を防止(予防)するためにも重要です。
心の健康が、髪の健康にも直結していることを意識しましょう。
ストレスが髪に与える影響
前述の通り、強いストレスは自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させます。これにより頭皮の血行が悪化し、毛根が栄養不足に陥ります。
また、ストレスはホルモンバランスにも影響を及ぼし、皮脂の過剰分泌を促すこともあります。皮脂が増えると頭皮環境が悪化し、抜け毛が増える原因となり得ます。
このように、ストレスは複数の経路から髪の成長を妨げる要因となります。
日常でできるリラックス方法
ストレスを感じたときに、自分なりの解消法を持っておくことが大切です。深刻に考えすぎず、手軽にできることから試してみましょう。
リラックスのための簡単な方法
- 深呼吸をする(ゆっくりと鼻から吸い、口から吐く)
- 軽いストレッチやヨガで体をほぐす
- 好きな音楽を聴く
- アロマやお香でリラックスできる香りを楽しむ
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
- 短時間でも目を閉じて休息する
趣味や休息の時間を大切にする
仕事や日々のタスクに追われていると、知らず知らずのうちにストレスが蓄積します。
意識的に仕事や悩み事から離れる時間を作り、自分の好きなことや趣味に没頭する時間は、心をリフレッシュさせるために非常に重要です。
また、何もしない時間、ぼーっとする時間を設けることも、脳と心を休ませる上では効果的です。オンとオフの切り替えをしっかり行い、心に余裕を持たせることが、結果として髪の健康にもつながります。
薄毛予防における育毛剤の役割と選び方
薄毛の防止(予防)を目的とする場合、育毛剤の使用は有効な選択肢の一つです。育毛剤は、現在の髪の毛を健康に保ち、抜け毛を防ぐことで、薄毛の進行を遅らせることを目的としています。
ここでは、育毛剤の正しい知識と選び方について解説します。
育毛剤と発毛剤の違い
「育毛剤」と「発毛剤」は、しばしば混同されがちですが、その目的と役割は明確に異なります。薄毛予防の段階で使うべきものと、すでに進行した薄毛に対応するものです。
自分の目的に合ったものを選ばないと、期待した効果は得られません。
育毛剤と発毛剤の比較
| 育毛剤(医薬部外品) | 発毛剤(第1類医薬品) | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防する | 髪の毛を新たに生やし、成長させる |
| 主な役割 | 頭皮環境の改善、血行促進、毛根への栄養補給 | 毛母細胞の働きを活性化させ、発毛を促す |
| 向いている人 | 薄毛を予防したい人、抜け毛が気になり始めた人 | すでに薄毛が進行している人 |
育毛剤に期待できる効果
育毛剤には、頭皮環境を整えるための様々な成分が含まれています。
例えば、血行を促進する成分(センブリエキスなど)、毛根に栄養を与える成分(ビタミン類など)、皮脂の過剰分泌を抑える成分、フケやかゆみを防ぐ抗炎症成分などです。
これらが複合的に作用し、髪の毛が育ちやすい健やかな頭皮環境を作り出すことで、抜け毛を防ぎ、ハリやコシのある髪を育む手助けをします。
薄毛予防のための育毛剤選びのポイント
市場には多くの育毛剤があり、どれを選べばよいか迷うかもしれません。薄毛を防止(予防)する目的で育毛剤を選ぶ際は、自分の頭皮の状態や悩みに合った成分が含まれているかを確認することが大切です。
また、毎日継続して使用するものなので、使い心地(テクスチャー、香り、刺激の有無)も重要な選択基準となります。
育毛剤選びの着目点
- 悩みに合った有効成分が含まれているか(例:乾燥が気になるなら保湿成分)
- 頭皮への刺激が少ないか(アルコールフリー、無香料など)
- 継続しやすい価格帯か
- 使い心地(ベタつかないか、香りはどうか)
効果的な使い方と注意点
育毛剤は、使えばすぐに効果が出るものではありません。髪の毛の成長サイクル(毛周期)を考えると、効果を実感するまでには最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続使用が必要です。
また、最も重要なのは「正しく使うこと」です。使用するタイミングは、頭皮が清潔な状態であるシャンプー後(ドライヤーで乾かした後)が最も効果的です。
説明書に記載されている適量を守り、頭皮に直接塗布し、指の腹で優しくマッサージするように馴染ませましょう。頭皮に傷や湿疹がある場合は、使用を控えるか、専門家に相談してください。
もしかして? と思ったら 早めのセルフチェックと対策
薄毛の防止(予防)は、早ければ早いほど効果的です。「まだ大丈夫だろう」と油断せず、自分の髪や頭皮の状態に日々関心を持つことが、将来の髪を守る第一歩となります。
日常生活の中で、薄毛の初期サインを見逃していないかセルフチェックしてみましょう。
薄毛の初期サインを見逃さない
薄毛は、ある日突然始まるわけではありません。多くの場合、徐々に進行し、以下のような初期サインが現れます。
- シャンプーやブラッシング時の抜け毛が増えた
- 枕につく抜け毛が目立つようになった
- 髪の毛が以前より細く、柔らかくなった(ハリ・コシがなくなった)
- 髪の毛のボリュームが減り、スタイリングがしにくくなった
- 頭頂部や前頭部の地肌が透けて見えるようになった気がする
- 頭皮が脂っぽくベタつく、または逆に乾燥してフケやかゆみが出る
これらのサインが複数当てはまる場合は、頭皮環境や生活習慣に何らかの問題がある可能性が高いです。現状を客観的に把握することが、対策のスタートラインです。
自分でできる簡単な頭皮チェック
自分の頭皮の状態を鏡で直接見るのは難しいですが、指で触ったり、スマートフォンのカメラを使ったりすることである程度のチェックは可能です。
まず、指の腹で頭皮全体を触ってみましょう。健康な頭皮は青白く、適度な弾力があります。
もし頭皮が赤みを帯びていたり、カチカチに硬くなっていたり、逆にブヨブヨとむくんでいる感じがしたりする場合は、血行不良や炎症、老廃物の蓄積が疑われます。
また、頭皮を軽くこすった時に、フケが大量に出たり、指が脂っぽくなったりする場合も、頭皮環境が悪化しているサインです。
気になり始めた時の第一歩
セルフチェックで「もしかして?」と感じたら、まずはこれまで解説してきた生活習慣(食事、睡眠、運動)やヘアケアの方法を見直すことから始めましょう。
特に、偏った食事や睡眠不足が続いている場合は、そこを改善するだけでも頭皮環境が良くなる可能性があります。また、正しいシャンプー方法を実践し、頭皮を清潔に保つこともすぐに取り組める対策です。
これらのセルフケアと並行して、予防的な観点から育毛剤の使用を開始するのも良い選択です。
それでも不安が続く場合や、抜け毛が明らかに多い場合は、一人で悩まずに皮膚科や薄毛専門のクリニックに相談することも検討しましょう。
季節・ストレス・生活習慣に戻る
よくある質問
- 薄毛予防はいつから始めるべきですか?
-
薄毛の予防に「早すぎる」ということはありません。一般的に、髪の毛の成長や男性ホルモンの影響は20代から始まっています。
そのため、薄毛の家系であるなど、将来的な不安がある場合はもちろん、特に不安がない人でも、20代から生活習慣やヘアケアに気をつけることが、将来の健康な髪を維持するために重要です。
抜け毛が気になり始めてから慌てて対策するよりも、日々の積み重ねが最も効果的な予防となります。
- 遺伝による薄毛は予防できますか?
-
AGA(男性型脱毛症)には遺伝的な要因が強く関与していることが分かっています。そのため、遺伝的な要因を持つ場合、持たない人と比較して薄毛になりやすい傾向はあります。
しかし、「遺伝だから必ず薄毛になる」と決まっているわけではありませんし、「諦めるしかない」というわけでもありません。
遺伝的な要因を持っていても、食生活や睡眠、ストレス管理、適切なヘアケアといった日々の予防策を徹底することで、薄毛の進行を遅らせたり、発症のリスクを軽減させたりすることは可能です。
- 食事や生活習慣を改善すれば必ず薄毛は防げますか?
-
食事や生活習慣の改善は、健康な髪を育むための土台作りであり、薄毛予防において非常に重要です。
しかし、薄毛の原因がAGAのように男性ホルモンや遺伝的要因が強く関わっている場合、生活習慣の改善「だけ」で進行を完全に食い止めることは難しい場合があります。
生活習慣の改善は、あくまで頭皮環境を最良の状態に保つための「守りの対策」です。
もし生活習慣を改善しても抜け毛が減らない、あるいは薄毛が進行すると感じる場合は、育毛剤の使用や、専門のクリニックへの相談も併せて検討する必要があります。
- 頭皮マッサージはやりすぎると逆効果ですか?
-
はい、その可能性があります。頭皮マッサージは血行促進に有効ですが、やり方が間違っていたり、過度に行ったりすると逆効果になることがあります。
例えば、爪を立ててゴシゴシと強く擦ると、頭皮が傷つき、炎症や乾燥を引き起こす原因となります。また、1日に何度も長時間行うと、かえって頭皮に負担をかけてしまいます。
マッサージは、指の腹を使い、頭皮を優しく動かすように、1回3〜5分程度を目安に心地よい強さで行うのが適切です。
Reference
RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
KO, Hee-La, et al. Effects of Adult Men’s Lifestyle on Scalp Health. Asian Journal of Beauty and Cosmetology, 2024, 22.2: 357-369.
RAJPUT, Rajendrasingh J. Influence of nutrition, food supplements and lifestyle in hair disorders. Indian Dermatology Online Journal, 2022, 13.6: 721-724.
ZANZOTTERA, F., et al. Efficacy of a nutritional supplement, standardized in fatty acids and phytosterols, on hair loss and hair health in both women and men. J Cosmo Trichol, 2017, 3.121: 2.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. Diet, Lifestyle, and AGA/FPHL. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 2 Drugs, Herbs, Nutrition and Supplements. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 255-267.
TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. In: Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 37-109.