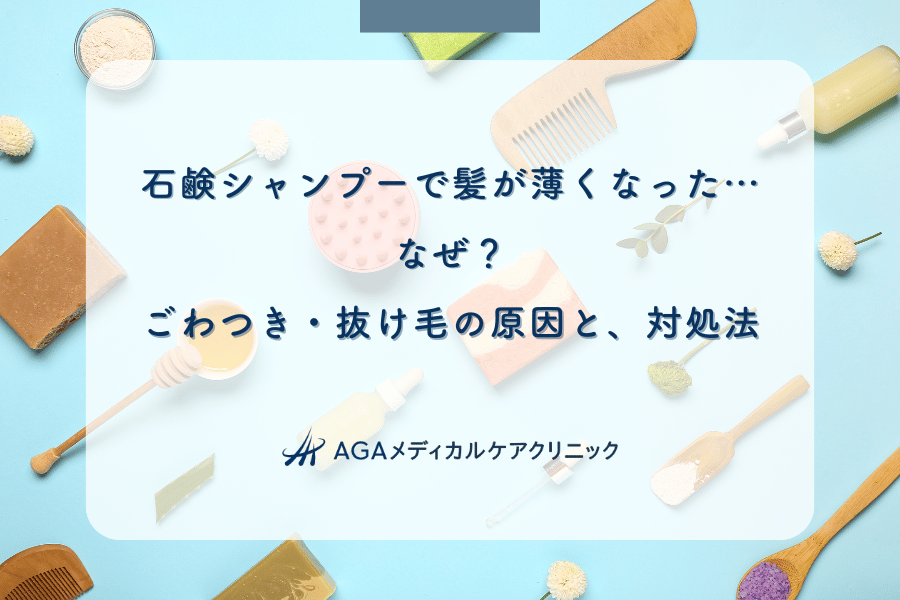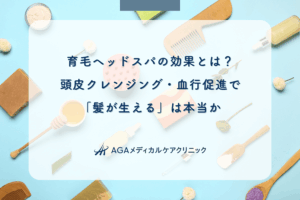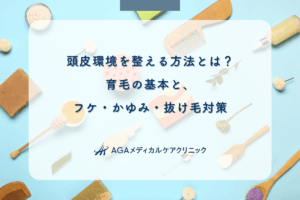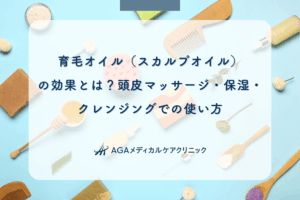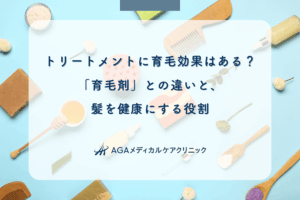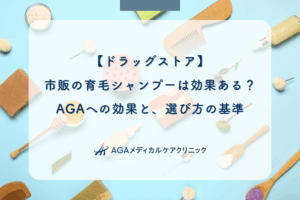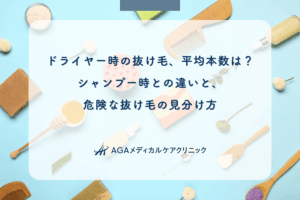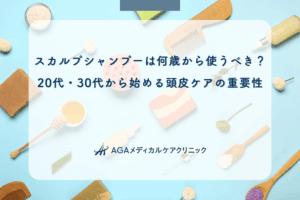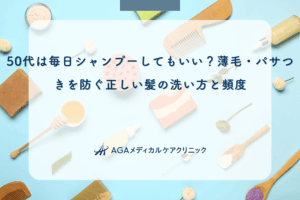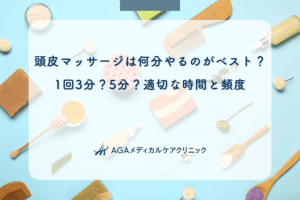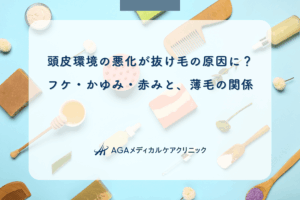石鹸シャンプーに変えたら「髪が薄くなった気がする」「ごわつきや抜け毛が増えた」…そんな不安を抱えていませんか。
環境や肌に優しいイメージのある石鹸シャンプーですが、実は髪質や使い方によってはトラブルの原因になることもあります。
この記事では、なぜ石鹸シャンプーで薄くなったと感じるのか、ごわつきや抜け毛が起こる原因を詳しく解説します。
さらに、正しいケア方法や、もし合わなかった場合の対処法、シャンプーの見直し方まで、あなたの疑問に答えます。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
石鹸シャンプーで「髪が薄くなった」と感じる主な理由
石鹸シャンプーを使い始めて「薄くなった」と感じる背景には、いくつかの要因が考えられます。
必ずしも髪が実際に減少しているわけではなく、見た目や感触の変化がそう感じさせている可能性もあります。
ごわつき・きしみがボリュームダウンに見える
石鹸シャンプーの最も顕著な特徴の一つが、洗い上がりの「きしみ」や「ごわつき」です。これは、石鹸のアルカリ性の性質により、髪の表面を覆うキューティクルが開くために起こります。
キューティクルが開くと、髪同士が引っかかりやすくなり、指通りが悪くなります。
この結果、髪がまとまりにくくなり、全体的なボリュームが失われたように感じることが、「薄くなった」という印象につながる一因です。
石鹸カスによる頭皮環境の悪化
石鹸シャンプーは、水道水に含まれるミネラル(カルシウムやマグネシウム)と反応して「石鹸カス(金属石鹸)」を生成しやすい性質があります。
この石鹸カスが髪や頭皮に残留すると、いくつかの問題を引き起こします。
髪に付着すればごわつきの原因になりますし、頭皮の毛穴周辺に残ると、毛穴を塞いだり、刺激を与えたりして頭皮環境を悪化させる可能性があります。
健康な髪は健康な頭皮から育つため、頭皮環境の悪化は抜け毛の間接的な原因にもなり得ます。
洗浄力が強すぎることによる乾燥
石鹸シャンプーは、一般的に洗浄力が高い製品が多いです。皮脂や汚れをしっかり落とす力がある一方で、必要な皮脂まで取りすぎてしまうことがあります。
頭皮の皮脂は、外部の刺激から守るバリア機能や、水分蒸発を防ぐ保湿機能を持っています。この皮脂が過剰に失われると、頭皮が乾燥しやすくなります。
乾燥した頭皮は、かゆみやフケの原因になるだけでなく、バリア機能が低下して敏感な状態になり、健康な髪の成長を妨げる可能性があります。
「薄くなった」は本当か?抜け毛との関係
石鹸シャンプーを使い始めた時期に抜け毛が増えたと感じる人もいます。
これは、前述の頭皮環境の悪化(乾燥、石鹸カスの詰まり)や、洗髪時のきしみによる摩擦や引っかかりが、切れ毛や抜け毛を助長している可能性が考えられます。
ただし、石鹸シャンプーそのものが直接的に薄毛(AGAなど)を引き起こすという科学的根拠は明確ではありません。多くの場合、使用感の変化や一時的な頭皮トラブルが原因です。
石鹸シャンプーの基本的な特徴
石鹸シャンプーがなぜ上記のような影響を与えるのかを理解するために、その基本的な特徴を知っておくことが重要です。
一般的な合成シャンプーとは根本的に異なる点が多くあります。
成分と洗浄の仕組み
石鹸シャンプーの主成分は「石鹸素地」や「カリ石鹸素地」と表記される「脂肪酸ナトリウム」や「脂肪酸カリウム」です。
これらは、天然の油脂(ヤシ油、オリーブ油、牛脂など)とアルカリ(苛性ソーダや苛性カリ)を反応させて作ります。
石鹸は「界面活性剤」の一種であり、油(皮脂や汚れ)と水をなじませて洗い流す働きをします。非常にシンプルな成分構成の製品が多いのが特徴です。
メリット 肌や環境への配慮
石鹸シャンプーの大きなメリットは、その生分解性の高さです。排水として流された後、水と二酸化炭素に比較的短時間で分解されやすいため、環境への負荷が少ないとされます。
また、成分がシンプルなため、合成シャンプーに含まれる特定の化学物質(一部の防腐剤や香料、着色料など)を避けたいと考える人や、肌が敏感な人に選ばれることもあります。
デメリット アルカリ性と中和の必要性
健康な髪や頭皮は弱酸性(pH4.5~5.5程度)です。しかし、石鹸シャンプーはアルカリ性(pH9~11程度)です。アルカリ性の液体に触れると、髪のキューティクルは開く性質があります。
これが、きしみやごわつきの直接的な原因です。
そのため、石鹸シャンプーで洗った後は、酸性のリンス(クエン酸やお酢を薄めたもの)を使って髪の状態を弱酸性に戻し、キューティクルを引き締める「中和」という手入れが必要になる場合がほとんどです。
一般的なシャンプー(合成シャンプー)との違い
私たちが普段「シャンプー」として認識している製品の多くは、合成界面活性剤を主成分とする「合成シャンプー」です。
石鹸シャンプーとは、成分、性質、使用感が大きく異なります。
一般的なシャンプーとの比較
| 項目 | 石鹸シャンプー | 一般的な合成シャンプー |
|---|---|---|
| 主な洗浄成分 | 脂肪酸ナトリウム・カリウム | 高級アルコール系、アミノ酸系など |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 弱酸性~中性 |
| 洗い上がりの髪 | きしみやすい(キューティクルが開く) | なめらか(コーティング剤配合も多い) |
| 石鹸カスの発生 | ミネラルと反応して発生しやすい | 発生しにくい |
| 必要なケア | 酸性リンスによる中和推奨 | コンディショナーやトリートメント |
ごわつき・抜け毛を引き起こす原因とは
石鹸シャンプーによる「薄くなった」という感覚は、ごわつきや抜け毛と密接に関連しています。これらの症状がなぜ起こるのか、さらに詳しく見ていきましょう。
髪のキューティクルが開く仕組み
髪の毛の表面は、うろこ状のキューティクルが何層にも重なって覆っています。このキューティクルは、髪内部のタンパク質や水分を守る鎧のような役割を果たしています。
弱酸性の状態ではキューティクルはキュッと閉じていますが、アルカリ性に傾くと開いてしまいます。石鹸シャンプーのアルカリ性が、このキューティクルを開かせる主な原因です。
開いたキューティクルは無防備な状態で、外部からの刺激を受けやすく、内部の水分も蒸発しやすくなります。これがごわつきやパサつき、ツヤのなさにつながります。
石鹸カスが毛穴に詰まる?
前述の通り、石鹸カスは石鹸と水道水のミネラルが結合したものです。これが頭皮や髪に残留すると、洗い上がりがベタついたり、フケのように見えたりすることがあります。
特にすすぎが不十分だと、石鹸カスが毛穴の周りに蓄積しやすくなります。
毛穴が詰まると、皮脂の排出がスムーズに行われなくなったり、毛根の活動が妨げられたりする可能性があり、頭皮環境の悪化から抜け毛の一因となると考えられています。
石鹸カスとは
石鹸カスは、主に以下の成分から成ります。これらが髪や頭皮に付着し、問題を引き起こします。
- 脂肪酸カルシウム
- 脂肪酸マグネシウム
すすぎ残しによる頭皮トラブル
石鹸シャンプーは、泡立ちが良い一方で、泡切れが悪いと感じることもあります。洗浄成分である石鹸分や、発生した石鹸カスを徹底的にすすぎ流すことが非常に重要です。
すすぎが不十分でこれらの成分が頭皮に残ると、頭皮を刺激し、かゆみ、炎症、フケなどを引き起こすことがあります。
頭皮が炎症を起こすと、髪の毛が正常に成長できなくなり、抜け毛が増える可能性があります。
過度な洗浄による皮脂の取りすぎ
石鹸シャンプーの強い洗浄力で必要な皮脂まで洗い流してしまうと、頭皮は「皮脂が足りない」と認識し、かえって皮脂を過剰に分泌しようとすることがあります。
これを「過剰皮脂分泌」と呼びます。皮脂が過剰になると、頭皮がベタつき、毛穴が詰まりやすくなるなど、石鹸カスとは別の原因で頭皮環境が悪化します。
また、乾燥と皮脂過剰が混在する不安定な頭皮状態は、健康な髪の育成には適していません。
石鹸シャンプーが合わない可能性のある人
石鹸シャンプーは、その特性から、すべての人に適しているわけではありません。特に以下のような特徴を持つ人は、合わない可能性があり、使用に注意が必要です。
髪が細い・猫っ毛の人
髪が細く柔らかい、いわゆる「猫っ毛」の人は、石鹸シャンプーのアルカリ性によるキューティクルの開きや、石鹸カスの付着による影響を受けやすい傾向があります。
髪が絡まりやすくなったり、ごわつきが強く出たりして、かえって扱いにくくなることがあります。ボリュームダウンがより顕著に感じられるかもしれません。
乾燥肌・敏感肌の人
石鹸シャンプーの洗浄力の高さが、乾燥肌や敏感肌の人には刺激となることがあります。必要な皮脂まで奪われることで頭皮の乾燥が進み、バリア機能が低下しやすいためです。
肌がヒリヒリしたり、かゆみが強く出たりする場合は、使用を見直す必要があります。「肌に優しい」というイメージだけで選ぶと、逆効果になる可能性もあります。
カラーやパーマをしている髪
ヘアカラーやパーマは、薬剤によって髪のキューティクルを開いたり、内部の結合を変化させたりする施術です。これらによって髪はすでにダメージを受け、デリケートな状態になっています。
そこにアルカリ性の石鹸シャンプーを使うと、キューティクルがさらに開きやすくなり、ダメージを助長します。
色落ちが早まったり、パーマが取れやすくなったり、きしみが非常に強く出る可能性があります。
ダメージヘアへの影響
| 髪の状態 | 石鹸シャンプーによる主な懸念 | 推奨される対応 |
|---|---|---|
| 健康毛 | きしみ・ごわつき | 酸性リンスでの中和 |
| カラー・パーマ毛 | ダメージ進行、色落ち、きしみ強 | 弱酸性シャンプーを推奨 |
| 乾燥毛 | パサつき、乾燥の悪化 | 保湿系シャンプーを推奨 |
硬水の地域に住んでいる人
石鹸カスは、水道水中のミネラル分と反応して発生します。ミネラル分が多い水、いわゆる「硬水」の地域では、軟水の地域に比べて石鹸カスが非常に多く発生しやすくなります。
ヨーロッパなどの硬水地域で石鹸シャンプーが一般的でないのはこのためです。日本はほとんどが軟水ですが、地域によっては硬度が高い場所もあります。
ご自宅の水道水の硬度が高い場合、石鹸カスによるトラブルが起こりやすくなります。
石鹸シャンプーを上手に使うための対処法
もし石鹸シャンプーが体質に合っており、今後も使い続けたいと考える場合、トラブルを最小限に抑えるための工夫が必要です。
以下の対処法を試してみてください。
正しい洗い方とすすぎの徹底
石鹸シャンプーを上手に使う最大のコツは「予洗い」と「すすぎ」です。まず、シャンプーをつける前に、お湯だけで頭皮と髪をしっかりと洗い流します(予洗い)。
これだけで汚れの7割程度は落ちると言われています。予洗いをしっかり行うことで、石鹸シャンプーの使用量を減らし、泡立ちを良くすることができます。
洗う際は、頭皮を指の腹でマッサージするように優しく洗い、髪の毛同士をこすり合わせないように注意します。そして、すすぎは「これでもか」というくらい時間をかけて徹底的に行います。
特に生え際や襟足は残りやすいので意識して流しましょう。
酸性リンス(クエン酸など)での中和
アルカリ性に傾いた髪を弱酸性に戻すため、専用の酸性リンス、または自宅で作ったクエン酸リンス(洗面器一杯のお湯にクエン酸小さじ一杯程度)を使用します。
シャンプーをしっかりすすいだ後、髪全体になじませ、再度軽くすすぎます。これによりキューティクルが引き締まり、きしみやごわつきが大幅に軽減されます。
石鹸シャンプーを使う上では、ほぼ必須の工程と言えます。
酸性リンスの役割
| 項目 | 石鹸シャンプー直後 | 酸性リンス使用後 |
|---|---|---|
| 髪の液性 | アルカリ性 | 弱酸性(中和) |
| キューティクル | 開いている | 引き締まる |
| 髪の感触 | きしむ、ごわつく | なめらかになる |
洗髪後の保湿ケア
洗浄力が高い石鹸シャンプーを使った後は、頭皮も髪も乾燥しやすい状態です。タオルドライの後、髪には洗い流さないトリートメントやヘアオイルをつけて保湿し、ドライヤーの熱から守ることが大切です。
また、頭皮が乾燥すると感じる場合は、頭皮用のローションやエッセンスで保湿ケアを行うことも検討しましょう。
使い始めの「移行期間」を知る
これまで合成シャンプー(特にコーティング剤入りのもの)を使っていた人が石鹸シャンプーに切り替えると、髪を覆っていたコーティングが剥がれ、髪本来の状態(ダメージなど)が現れることで、一時的にきしみが強く感じられることがあります。
また、頭皮の皮脂バランスが整うまでにも時間がかかると言われています。この「移行期間」は個人差がありますが、数週間から数ヶ月続くこともあります。
この期間を乗り越えられるかどうかも、石鹸シャンプーを続けられるかの分かれ道です。
もし石鹸シャンプーが合わないと感じたら
様々な対処法を試しても、ごわつきや抜け毛、頭皮のかゆみなどが改善しない場合、その石鹸シャンプーはあなたの髪質や頭皮の状態に合っていない可能性が高いです。
無理して使い続けない勇気
「環境に良いから」「肌に優しいと思ったから」という理由で、合わないものを無理して使い続けるのは本末転倒です。頭皮環境が悪化し続ければ、抜け毛や薄毛の悩みが深刻化してしまう恐れもあります。
合わないと感じたら、使用を中止し、別の選択肢を探す勇気を持ちましょう。
アミノ酸系シャンプーへの切り替え
石鹸シャンプーが合わなかった人の次の選択肢として、まず挙げられるのが「アミノ酸系シャンプー」です。アミノ酸系洗浄成分は、髪や頭皮と同じ弱酸性で、洗浄力がマイルドなのが特徴です。
必要な皮脂を残しつつ、優しく洗い上げるため、乾燥肌や敏感肌の人、髪のダメージが気になる人にも適しています。石鹸シャンプーのような強いきしみもありません。
主なシャンプー洗浄成分の比較
| 洗浄成分の種類 | 特徴 | 適した人 |
|---|---|---|
| 石鹸系 | 弱アルカリ性、洗浄力高い、きしむ | 健康毛、皮脂が多い人 |
| 高級アルコール系 | 弱酸性、洗浄力高い、安価 | 皮脂が多い人、コスト重視の人 |
| アミノ酸系 | 弱酸性、洗浄力マイルド、保湿性 | 乾燥肌、敏感肌、ダメージ毛 |
頭皮ケア成分配合シャンプーの検討
抜け毛や頭皮環境の悪化が気になる場合は、洗浄成分だけでなく、配合されている成分にも注目しましょう。
頭皮の炎症を抑える「グリチルリチン酸2K」や、血行を促進する「センブリエキス」など、頭皮環境を整えることを目的とした有効成分が配合された薬用シャンプー(医薬部外品)も多くあります。
これらは「スカルプシャンプー」と呼ばれることもあります。
生活習慣の見直しも同時に行う
髪や頭皮の健康は、シャンプーだけで決まるものではありません。日々の生活習慣も大きく影響します。シャンプーを見直すと同時に、ご自身の生活も振り返ってみることが大切です。
髪の健康に関わる生活習慣
特に以下の点に注意し、改善を心がけましょう。
- バランスの取れた食事
- 十分な睡眠時間
- ストレスの管理
- 適度な運動
抜け毛や薄毛が深刻な場合の選択肢
シャンプーを石鹸シャンプーから変えても、抜け毛が減らない、あるいは「薄くなった」という感覚が気のせいではなく、実際に進行していると感じる場合、それは男性型脱毛症(AGA)など、別の原因が潜んでいる可能性があります。
その場合は、シャンプー選びとは別の、より積極的な対処法が必要です。
育毛剤の使用を検討する
育毛剤は、今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防することを目的とした医薬部外品です。頭皮の血行を促進したり、毛根に栄養を与えたり、頭皮環境を整えたりする成分が含まれています。
抜け毛が増えてきた、髪にハリやコシがなくなってきたと感じる初期段階での使用が推奨されます。発毛剤とは異なるため、違いを理解しておくことが重要です。
育毛剤と発毛剤の違い
| 項目 | 育毛剤 | 発毛剤 |
|---|---|---|
| 分類 | 医薬部外品 | 第1類医薬品 |
| 主な目的 | 抜け毛予防、毛髪の成長促進 | 新たな毛髪の成長(発毛) |
| 主な有効成分 | グリチルリチン酸、センブリエキスなど | ミノキシジルなど |
頭皮マッサージの習慣化
頭皮の血行が悪くなると、髪の毛の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなります。頭皮マッサージは、物理的に頭皮を動かすことで血行を促進するのに役立ちます。
シャンプー中や、育毛剤を塗布した後などに、指の腹を使って頭皮全体を優しく揉みほぐす習慣をつけましょう。リラックス効果も期待できます。
専門クリニックへの相談
抜け毛が止まらない、明らかに地肌が透けて見える範囲が広がってきたなど、薄毛の進行が明らかな場合は、自己判断でケアを続けるよりも、皮膚科や薄毛治療専門のクリニックに相談することが最も確実な対処法です。
専門医の診断により、抜け毛の根本的な原因(AGA、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎など)を特定し、状態に合わせた適切な治療(内服薬、外用薬など)を受けることができます。
食生活と栄養バランスの改善
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。偏った食生活では、健康な髪は育ちません。特に、髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮環境を整えるビタミン類は重要です。
日々の食事内容を見直し、バランスの取れた栄養摂取を心がけることは、育毛剤の使用やクリニックでの治療と並行して行うべき基本的なケアです。
髪の成長に必要な栄養素
| 栄養素 | 主な役割 | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、皮脂分泌の調整 | 豚肉、レバー、青魚、納豆 |
シャンプー・洗い方に戻る
よくある質問
石鹸シャンプーと薄毛に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
- 石鹸シャンプーをやめたら髪は元に戻りますか?
-
もし、ごわつきやきしみ、乾燥が原因で「薄くなったように見えていた」あるいは「一時的に抜け毛が増えていた」場合、シャンプーを自分に合ったもの(例:アミノ酸系シャンプー)に変え、頭皮環境が改善すれば、髪の状態は本来の姿に戻っていく可能性が高いです。
ごわつきが解消されれば、ボリューム感も戻るでしょう。
ただし、石鹸シャンプーの使用が引き金となって悪化した頭皮トラブルが長引いている場合や、AGAなど別の要因で薄毛が進行している場合は、シャンプーをやめるだけでは完全には元に戻らないこともあります。
- 石鹸シャンプーと抜け毛の直接的な因果関係は?
-
現時点で、石鹸シャンプーそのものが男性型脱毛症(AGA)のような薄毛症を直接引き起こす、あるいは進行させるという明確な医学的根拠はありません。
しかし、これまでに解説した通り、「洗浄力が強すぎることによる乾燥」「石鹸カスや皮脂による毛穴詰まり」「アルカリ性による刺激」などが頭皮環境を悪化させる可能性はあります。
悪化した頭皮環境は、健康な髪の成長を妨げ、抜け毛や切れ毛を増やす間接的な原因にはなり得ます。
- 子どもにも石鹸シャンプーは使えますか?
-
子どもの肌は大人よりもデリケートですが、皮脂分泌は活発な場合もあります。石鹸シャンプーは成分がシンプルなため、合成添加物を避けたいという理由で子どもに使用する方もいます。
ただし、大人と同様に洗浄力が強すぎると乾燥を招く可能性もありますし、アルカリ性によるきしみを子どもが嫌がる場合もあります。
もし使用する場合は、すすぎを徹底し、酸性リンスでの中和を行うか、初めから子ども用の弱酸性シャンプーを選ぶ方が無難な場合もあります。
- 育毛剤と石鹸シャンプーは併用できますか?
-
併用すること自体は可能です。ただし、注意点がいくつかあります。育毛剤は、清潔な頭皮に使用することで成分が浸透しやすくなります。
石鹸シャンプーを使用した場合、石鹸カスが頭皮に残っていると、育毛剤の浸透を妨げる可能性があります。
また、頭皮がアルカリ性に傾いた状態や、乾燥しすぎている状態も、育毛剤の効果を十分に発揮させるためには好ましくありません。
もし併用する場合は、すすぎを徹底し、酸性リンスで中和し、頭皮が乾いた状態になってから育毛剤を使用するようにしてください。
育毛剤の使用を本格的に考えるならば、頭皮環境を整えやすい弱酸性のアミノ酸系シャンプーなどと組み合わせる方が、より相性が良いと考えられます。
Reference
BEAUQUEY, Bernard. Scalp and hair hygiene: shampoos. The science of hair care, 2005, 83-127.
ROBBINS, Clarence R. Chemical and physical behavior of human hair. New York, NY: Springer New York, 2002.
T. CHIU, Chin-Hsien; HUANG, Shu-Hung; D. WANG, Hui-Min. A review: hair health, concerns of shampoo ingredients and scalp nourishing treatments. Current pharmaceutical biotechnology, 2015, 16.12: 1045-1052.
DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni, et al. The shampoo pH can affect the hair: myth or reality?. International journal of trichology, 2014, 6.3: 95-99.
DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni, et al. The shampoo pH can affect the hair: myth or reality?. International journal of trichology, 2014, 6.3: 95-99.
GRAY, John. Hair care and hair care products. Clinics in dermatology, 2001, 19.2: 227-236.
CRUZ, Célia F., et al. Human hair and the impact of cosmetic procedures: a review on cleansing and shape-modulating cosmetics. Cosmetics, 2016, 3.3: 26.
SURFACTANTS, Anionic. Hair Cosmeceuticals. Alopecia, 2018, 285.
GUBITOSA, Jennifer, et al. Hair care cosmetics: From traditional shampoo to solid clay and herbal shampoo, a review. Cosmetics, 2019, 6.1: 13.
DUBIEF, C., et al. Hair care products. In: The Science of Hair Care. CRC Press, 1986. p. 155-196.