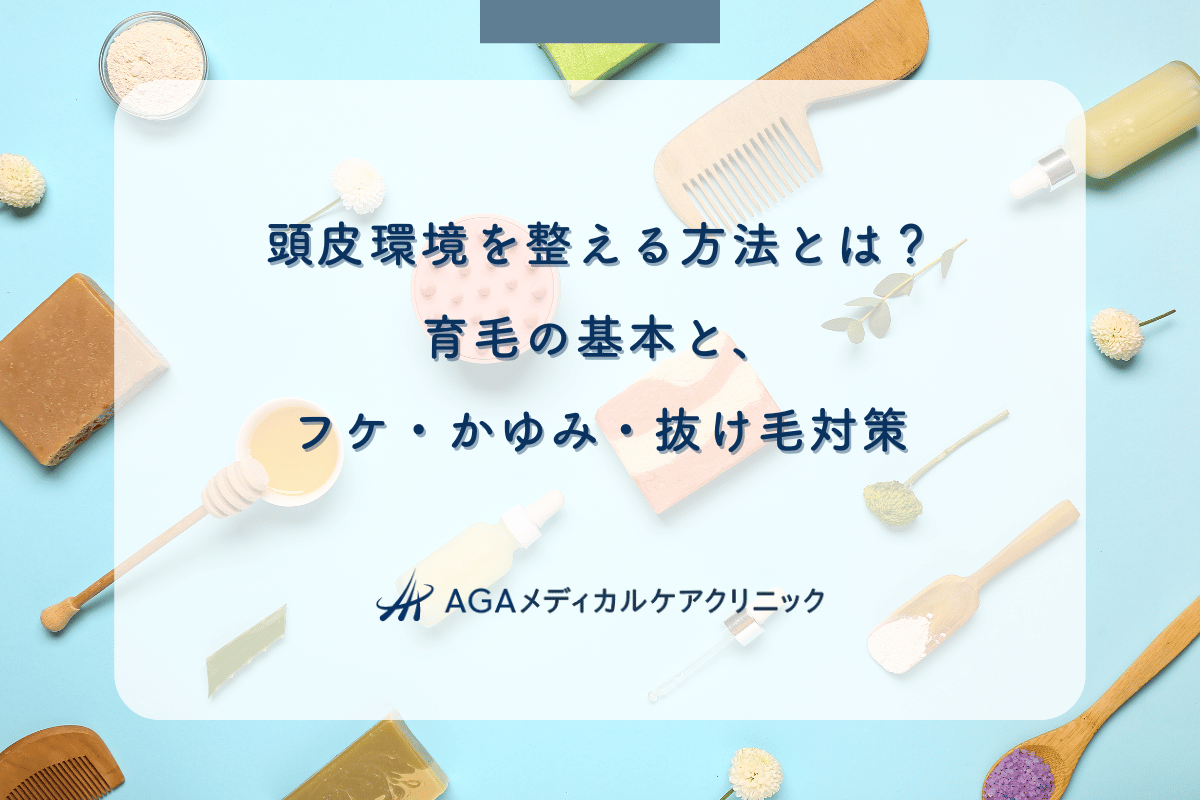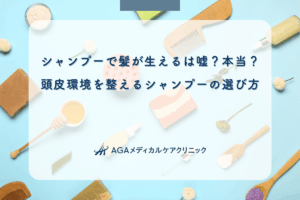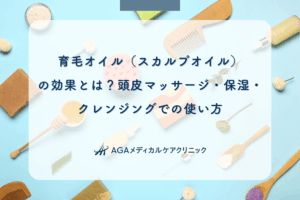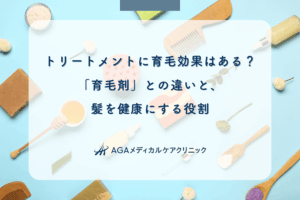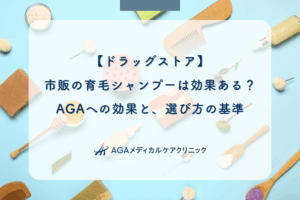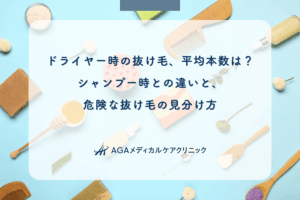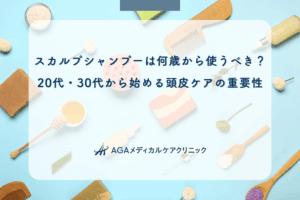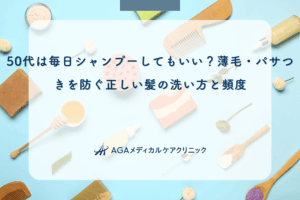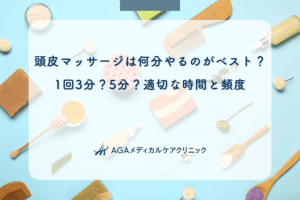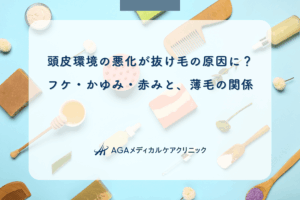フケやかゆみ、抜け毛の増加に悩んでいませんか。それらの多くは、頭皮環境の乱れが原因かもしれません。健康な髪は、健康な土壌である頭皮から育ちます。
この記事では、育毛の基本となる「頭皮環境を整える」とは具体的にどういうことなのか、なぜそれが重要なのかを深掘りします。
そして、フケ、かゆみ、抜け毛といった具体的な悩みに対し、日常生活で見直すべきポイントや正しいケア方法を分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ頭皮環境を整えることが重要なのか
頭皮環境という言葉をよく耳にしますが、なぜそれを整えることが髪の健康、ひいては育毛にとって重要なのでしょうか。
ここでは、頭皮と髪の基本的な関係性、そして環境が悪化した場合に起こり得る問題について解説します。
頭皮は髪の「土壌」
健康な植物が豊かな土壌から育つように、美しく丈夫な髪は健康な頭皮から育ちます。頭皮は、髪の毛を作り出す「毛包(もうほう)」が存在する場所です。
毛包の奥深くにある「毛乳頭(もうにゅうとう)」や「毛母細胞(もうぼさいぼう)」が、血管から栄養を受け取り、細胞分裂を繰り返すことで髪の毛は成長します。
もし頭皮が乾燥していたり、逆に皮脂で詰まっていたり、炎症を起こしていたりすると、この髪の成長サイクルに悪影響が及びます。
栄養が十分に行き渡らなくなったり、毛穴が塞がれたりすることで、髪が細くなったり、成長が妨げられたりするのです。
したがって、頭皮を常に清潔で潤いのある、柔軟な状態に保つことが、健やかな髪を育むための大前提となります。
頭皮環境の悪化が招くトラブル
頭皮環境が悪化すると、様々なトラブルが表面化します。最も分かりやすい例が「フケ」と「かゆみ」です。
これらは、頭皮のターンオーバー(新陳代謝)の乱れや、皮脂の過剰分泌、あるいは乾燥によって引き起こされます。
ターンオーバーが早すぎると、未熟な角質が剥がれ落ちてフケとなり、バリア機能が低下することで外部からの刺激に敏感になり、かゆみを感じやすくなります。
また、皮脂が多いと、それをエサにする常在菌(マラセチア菌など)が異常繁殖し、その代謝物が頭皮を刺激して炎症(脂漏性皮膚炎など)を引き起こすこともあります。
さらに、毛穴に皮脂や古い角質が詰まると、髪の成長を物理的に妨げるだけでなく、炎症の原因にもなります。
これらのトラブルは、見た目の不快感だけでなく、抜け毛や薄毛の直接的・間接的な原因となるため、早期の対策が重要です。
育毛と頭皮環境の密接な関係
育毛を考える上で、頭皮環境の整備は避けて通れません。男性型脱毛症(AGA)のように遺伝的・ホルモン的な要因が強い場合でも、頭皮環境が良好であるに越したことはありません。
なぜなら、頭皮環境の悪化は、AGAの進行を早めたり、育毛剤の効果を妨げたりする可能性があるからです。
例えば、育毛剤を使用しても、頭皮が硬く血行不良であったり、毛穴が汚れで詰まっていたりすれば、有効成分が毛根まで十分に浸透しない可能性があります。また、頭皮に炎症があれば、育毛どころか、さらなる抜け毛を招くことにもなりかねません。
つまり、育毛とは「髪を生やす」ことと「今ある髪を守り育てる」ことの両面から考える必要があり、そのどちらにおいても「頭皮環境を整える」ことが全ての基本となるのです。
あなたの頭皮環境は大丈夫?セルフチェック
頭皮環境の重要性を理解したところで、現在のご自身の頭皮がどのような状態にあるのか気になりませんか。病院に行かなくても、日々の観察で分かるサインは多くあります。
ここでは、自分で簡単にできる頭皮環境のチェック方法を紹介します。
頭皮の色で健康状態を知る
頭皮の色は、健康状態を示すバロメーターです。鏡を使って、特に分け目やつむじ周りの頭皮の色を確認してみましょう。
頭皮の色と健康状態の目安
| 頭皮の色 | 状態 | 考えられる原因や対策 |
|---|---|---|
| 青白い色・透明感のある白 | 健康な状態 | 血行が良く、水分と皮脂のバランスが取れています。現状のケアを継続しましょう。 |
| 黄色・くすんだ色 | 注意が必要(皮脂酸化) | 皮脂の過剰分泌や洗い残しにより皮脂が酸化している可能性があります。丁寧なシャンプーが必要です。 |
| 赤み・ピンク色 | 危険な状態(炎症) | 炎症、かゆみ、紫外線ダメージなどが考えられます。刺激の少ないケアや、皮膚科への相談を検討しましょう。 |
健康な頭皮は、やや青白い色をしています。これは頭皮が透けて毛細血管の色が見えている状態です。
黄色っぽくくすんでいる場合は、皮脂の分泌が過剰であったり、シャンプーのすすぎ残しがあったりして、皮脂が酸化しているサインかもしれません。
赤みがある場合は、何らかの理由で炎症が起きている証拠です。かゆみやヒリヒリ感を伴う場合は特に注意が必要です。
フケの種類と原因
フケも頭皮環境を知るための重要な手がかりです。フケには大きく分けて二つのタイプがあり、それぞれ原因と対策が異なります。
フケの種類と主な原因
| フケの種類 | 特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 乾燥フケ | カサカサと乾燥している 粉のように細かい 肩などに落ちやすい | 頭皮の乾燥 洗浄力の強すぎるシャンプー 空気の乾燥(冬場など) |
| 脂性フケ(湿性フケ) | ベタベタと湿っている 大きく、かたまり状 髪の根元や毛穴に付着 | 皮脂の過剰分泌 シャンプーの洗い残し 脂っこい食事 マラセチア菌の増殖 |
パラパラと肩に落ちるような乾燥したフケは、頭皮の乾燥が主な原因です。洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、洗いすぎ、空気の乾燥などが影響します。
一方、ベタベタして髪の根元にこびりつくような脂性フケは、皮脂の過剰分泌が原因です。脂っこい食事の多い人や、シャンプーのすすぎが不十分な人に見られます。
かゆみや赤みのサイン
頭皮にかゆみや赤みがある場合、それは頭皮が何らかの刺激に対してSOSを発しているサインです。
一時的なかゆみであれば、汗やムレが原因かもしれませんが、継続的にかゆみがある場合は注意が必要です。
乾燥、皮脂の過剰分泌による炎症(脂漏性皮膚炎)、シャンプーや整髪料が合わないことによる接触性皮膚炎(かぶれ)、アトピー性皮膚炎など、様々な原因が考えられます。
特に、かゆみが強くて掻きむしってしまうと、頭皮が傷つき、そこから細菌が侵入してさらに炎症が悪化するという悪循環に陥りがちです。
赤みが広範囲にわたる場合や、かゆみが我慢できない場合は、自己判断せず皮膚科を受診することをお勧めします。
抜け毛の状態を観察する
人は誰でも毎日50本から100本程度の髪が自然に抜けています(自然脱毛)。しかし、その本数が急に増えたり、抜け毛の質が変わったりした場合は、頭皮環境の悪化や脱毛症のサインかもしれません。
シャンプー時や朝起きた時の枕元の抜け毛をチェックしてみましょう。
特に注目したいのは「毛根」の状態です。健康な自然脱毛の場合、毛根は丸く膨らんでおり、白っぽい毛根鞘(もうこんしょう)が付着していることがあります。
しかし、毛根がなかったり、細く尖っていたり、毛根に皮脂の塊がべったりと付着していたりする場合は、頭皮環境の悪化やAGAの影響で、髪が十分に成長しきる前に抜けてしまった可能性があります。
細く短い毛の抜け毛が増えた場合も同様に注意が必要です。
頭皮環境を悪化させる主な原因
良好な頭皮環境を維持するためには、まず何がそれを悪化させるのかを知ることが大切です。原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いです。
間違ったヘアケア
良かれと思って行っている日々のヘアケアが、実は頭皮にダメージを与えているケースは少なくありません。
例えば、洗浄力の強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、必要な皮脂まで奪い去り、頭皮の乾燥を招きます。乾燥した頭皮はバリア機能が低下し、かゆみやフケの原因となります。
逆に、皮脂が多いからといって一日に何度もシャンプーをすると、皮脂の取りすぎを補おうと、かえって皮脂分泌が活発になることもあります。
また、シャンプー時の爪立て洗いは厳禁です。頭皮は非常にデリケートであり、爪を立ててゴシゴシ洗うと細かい傷がつき、そこから炎症が起きる可能性があります。
シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しも、毛穴詰まりや雑菌の繁殖、かゆみの原因となるため注意が必要です。
生活習慣の乱れ
頭皮も体の一部であり、全身の健康状態と密接に関連しています。不規則な生活習慣は、自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮環境に直接的な悪影響を及ぼします。
- 睡眠不足
- 偏った食生活(脂質や糖質の過剰摂取)
- 運動不足
特に睡眠中は、髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」が分泌されるゴールデンタイムです。睡眠不足が続くと、このホルモンの分泌が滞り、髪の健やかな成長が妨げられます。
また、脂っこい食事や甘いものの食べ過ぎは、皮脂の分泌を過剰にし、脂性フケや毛穴詰まりの原因となります。運動不足は全身の血行不良を招き、頭皮に十分な栄養が届きにくくなる原因となります。
ストレスとホルモンバランス
精神的なストレスも頭皮環境の大敵です。過度なストレスを感じると、自律神経のうち交感神経が優位になります。
交感神経は血管を収縮させる働きがあるため、頭皮の毛細血管が収縮し、血行不良を引き起こします。血行が悪くなれば、毛母細胞に届く栄養や酸素が減少し、髪の成長にブレーキがかかります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにも繋がります。
男性ホルモン(特にジヒドロテストステロン:DHT)の感受性が高い人は、ストレスによって男性ホルモンの分泌が促されると、皮脂腺が刺激されて皮脂分泌が過剰になったり、AGAの進行が早まったりする可能性が指摘されています。
紫外線や乾燥などの外的要因
頭皮は、顔の皮膚の約2倍以上の紫外線を浴びていると言われています。帽子や日傘などで対策をしていない場合、頭皮は深刻なダメージを受けています。
紫外線は頭皮を乾燥させ、バリア機能を低下させるだけでなく、活性酸素を発生させて毛母細胞の働きを弱らせる(光老化)原因にもなります。
また、冬場の乾燥した空気や、夏場のエアコンによる室内の乾燥も、頭皮の水分を奪い、乾燥フケやかゆみを引き起こします。
頭皮も顔の肌と同じように、湿度や温度といった外部環境の変化に敏感に反応することを忘れてはいけません。
毎日の習慣から見直す 頭皮環境の整え方「基本の生活習慣」
頭皮環境を整えるためには、高価な育毛剤を使う前に、まず日々の生活習慣を見直すことが最も重要です。体の内側から健康になることが、頭皮環境改善への一番の近道です。
髪の成長を支える食生活
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。特に重要な栄養素を意識して摂取しましょう。
頭皮と髪の健康に役立つ主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミンB群 | 皮脂の分泌を調整し、代謝を助ける | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆、バナナ |
| 亜鉛 | たんぱく質の合成(ケラチンの生成)を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ、アーモンド |
髪の約90%は「ケラチン」というたんぱく質でできています。そのため、まずは良質なたんぱく質をしっかり摂ることが基本です。肉、魚、卵、大豆製品などをバランスよく取り入れましょう。
また、ビタミンB群(特にB2、B6)は、皮脂の分泌をコントロールし、頭皮のターンオーバーを正常に保つ働きがあります。脂性フケで悩む人は特に意識したい栄養素です。
亜鉛は、たんぱく質を髪の毛(ケラチン)に再合成する際に必要不可欠なミネラルです。不足すると髪の成長が妨げられるため、積極的に摂取しましょう。
ただし、これらの栄養素だけを偏って摂るのではなく、様々な食品をバランスよく食べることが大切です。
質の高い睡眠の確保
前述の通り、睡眠中、特に眠り始めの深いノンレム睡眠時に「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。成長ホルモンは、細胞の修復や再生を促し、毛母細胞の分裂を活発にする働きがあります。
単に長く寝るだけでなく、「質の高い睡眠」を確保することが重要です。そのためには、
- 就寝1〜2時間前に入浴して体を温める
- 就寝前のスマートフォンやパソコン操作を控える
- カフェインやアルコールの摂取を夜は避ける
といった工夫が有効です。毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きるという規則正しい睡眠リズムを作ることも、自律神経を整え、頭皮環境の安定に繋がります。
適度な運動と血行促進
頭皮の毛細血管は非常に細く、血行不良の影響を受けやすい場所です。デスクワークが多い人や運動不足の人は、全身の血流が滞りがちになり、頭皮にも十分な栄養が届きにくくなります。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの有酸素運動を週に数回取り入れる習慣をつけましょう。運動は全身の血行を良くするだけでなく、ストレス発散にも効果的です。
運動する時間がなかなか取れないという人は、日常生活の中で意識的に階段を使ったり、一駅分歩いたりするだけでも違います。また、入浴時に湯船にしっかり浸かって体を温めることも、血行促進に役立ちます。
上手なストレス発散法
現代社会でストレスをゼロにすることは困難です。大切なのは、ストレスを溜め込まず、自分に合った方法で上手に発散することです。
趣味に没頭する時間を作る、好きな音楽を聴く、友人と話す、自然の中でリラックスするなど、自分が「心地よい」と感じる時間を持つことが、交感神経の高ぶりを抑え、副交感神経を優位にする(リラックス状態にする)ために役立ちます。
ストレスが溜まると、無意識に頭皮を掻いたり、食生活が乱れたり、睡眠が浅くなったりと、頭皮環境に悪影響を及ぼす行動をとりがちです。
心身のバランスを整えることが、結果として頭皮の健康を守ることに繋がります。
正しいヘアケアで整える 頭皮環境の整え方「外側からのアプローチ」
生活習慣の改善と並行して、日々のヘアケアを見直すことも、頭皮環境を整える上で非常に重要です。間違ったケアを続けていては、せっかくの生活改善の効果も半減してしまいます。
自分に合ったシャンプーの選び方
シャンプーは、頭皮の汚れを落とすためのものですが、自分の頭皮タイプに合っていないものを使うと、トラブルの原因になります。
頭皮タイプ別のおすすめシャンプー洗浄成分
| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨されるシャンプー(洗浄成分) |
|---|---|---|
| 乾燥肌・敏感肌 | フケがカサカサしている かゆみが出やすい シャンプー後につっぱる | アミノ酸系シャンプー (例:ココイルグルタミン酸Na) マイルドな洗浄力で保湿性が高い |
| 脂性肌(オイリー肌) | フケがベタベタしている 日中、髪がベタつく ニオイが気になる | 高級アルコール系シャンプー(適度に) (例:ラウレス硫酸Na) または、アミノ酸系でも洗浄力高めのもの |
| 混合肌 | ベタつくのにカサつく部分もある Tゾーンは脂っぽいなど | アミノ酸系シャンプー または、スカルプケアシャンプー 洗浄力と保湿のバランスが良いもの |
一般的にドラッグストアなどで多く市販されている「高級アルコール系」は、洗浄力が強く泡立ちも良いですが、乾燥肌の人には刺激が強すぎることがあります。
乾燥やフケが気になる人は、洗浄力がマイルドで保湿成分が配合された「アミノ酸系」のシャンプーを試してみると良いでしょう。
逆に、皮脂が多い脂性肌の人がアミノ酸系を使うと、洗浄力が物足りず、かえって毛穴詰まりを起こすこともあります。
自分の頭皮タイプ(フケの種類や日中のベタつき具合)をよく観察して、適切な洗浄力の製品を選ぶことが大切です。
誤解だらけ?正しいシャンプーの手順
毎日行うシャンプーだからこそ、正しい手順をマスターすることが頭皮環境改善の鍵となります。
シャンプー前のブラッシング
乾いた髪の状態で、まずは優しくブラッシングをします。髪の絡まりをほどき、表面のホコリや汚れを浮かせることができます。
これにより、シャンプー時の泡立ちが良くなり、髪への摩擦も減らせます。
ぬるま湯での予洗い(すすぎ)
シャンプー剤をつける前に、38度前後のぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと濡らします。熱すぎるお湯は頭皮を乾燥させる原因になるため避けてください。
この予洗いだけで、髪の汚れの7割程度は落ちると言われています。頭皮までしっかりお湯が届くよう、1〜2分かけて丁寧に行います。
シャンプー剤の泡立てと洗い方
シャンプー剤は手のひらに適量を取り、軽く泡立ててから髪につけます。決して原液を直接頭皮につけてはいけません。
洗う時は、爪を立てず、「指の腹」を使います。頭皮をマッサージするように、優しく揉み込むように洗いましょう。
特に皮脂の多い生え際や頭頂部、襟足は洗い残しがないよう意識します。洗う時間は1〜2分程度で十分です。
徹底的なすすぎ
シャンプーで最も重要なのが「すすぎ」です。シャンプー剤が頭皮や髪に残っていると、かゆみやフケ、毛穴詰まりの原因になります。
洗う時間の2倍以上の時間をかけるつもりで、ぬめり感が完全になくなるまで、頭皮からしっかりとお湯で洗い流してください。
コンディショナー・トリートメントの使い方
コンディショナーやトリートメントは、主に髪の毛を保護し、指通りを良くするためのものです。頭皮につくと毛穴詰まりの原因になるため、毛先を中心に塗布し、頭皮には極力つけないように注意します。
使用後は、これもシャンプー同様、ぬめりがなくなるまでしっかりすすぎます。
タオルドライと乾燥
シャンプー後は、清潔なタオルで頭皮の水分を優しく拭き取ります。ゴシゴシ擦るのではなく、タオルで頭皮を押さえるようにして水分を吸い取ります。
その後、必ずドライヤーで乾かします。濡れたまま放置する「自然乾燥」は、頭皮に雑菌が繁殖しやすくなり、ニオイやかゆみの原因となります。
ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、一箇所に熱が集中しないよう動かしながら、まずは頭皮(根元)から乾かします。
全体が8割方乾いたら、冷風に切り替えて仕上げると、キューティクルが引き締まり、髪にツヤが出ます。
頭皮マッサージの方法と効果
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに有効です。シャンプー中や、育毛剤をつけた後などに行うと良いでしょう。
指の腹を頭皮に密着させ、頭蓋骨から頭皮を動かすようなイメージで、下から上へ(側頭部から頭頂部へ)と円を描くように揉みほぐします。
爪を立てたり、強く擦ったりしないよう注意してください。毎日数分続けることで、頭皮が柔らかくなり、血流が改善されます。
育毛剤や頭皮用ローションの活用
頭皮環境を整えるための補助として、育毛剤や頭皮用ローションを活用するのも一つの方法です。
育毛剤には、血行促進成分(センブリエキスなど)や、抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)、皮脂分泌抑制成分、保湿成分などが含まれています。
自分の頭皮の悩みに合った成分が配合されている製品を選びましょう。
特に乾燥が気になる人は保湿ローションを、フケやかゆみが気になる人は抗炎症成分が入ったものを選ぶと良いでしょう。これらはシャンプー後、髪を乾かした清潔な頭皮に使用します。
使用する際は、頭皮に直接塗布し、指の腹で優しくなじませます。
【悩み別】フケ・かゆみ・抜け毛への具体的な対策
頭皮環境の悪化は、フケ、かゆみ、抜け毛といった具体的な悩みとして現れます。基本的なケアに加え、それぞれの悩みに特化した対策を知っておきましょう。
べたつくフケ・乾燥フケの対策
フケのタイプによって対策は異なります。
「乾燥フケ」の場合は、まず保湿が最優先です。洗浄力のマイルドなアミノ酸系シャンプーに変える、シャンプーの回数を二日に一回に減らしてみる(ただし汚れが気になる場合は毎日洗う)、頭皮用の保湿ローションを使う、といった対策が有効です。
「脂性フケ」の場合は、過剰な皮脂を適切に取り除くことが必要です。
ただし、洗浄力が強すぎると逆に皮脂分泌を促すため、適度な洗浄力のあるシャンプー(アミノ酸系やスカルプケア用)で丁寧に洗い、すすぎを徹底することが重要です。
また、皮脂の分泌を抑えるビタミンB群を食事で積極的に摂ることも心がけましょう。
しつこいかゆみを抑えるには
かゆみの原因が乾燥であれ、皮脂であれ、炎症が起きている可能性が高いです。まずはシャンプーや整髪料が肌に合っているか見直しましょう。
刺激の少ない製品(敏感肌用、無香料、無着色など)に変えてみるのも手です。
それでもかゆみが治まらない場合、脂漏性皮膚炎などを起こしている可能性があります。
この場合、フケの原因菌であるマラセチア菌の増殖を抑える成分(ミコナゾール硝酸塩など)が配合された薬用シャンプーを試す価値があります。
かゆみが強い時は、掻きむしるのを我慢し、冷やしたタオルなどで一時的に冷やすと楽になることがあります。症状が長引く、あるいは悪化する場合は、早めに皮膚科医に相談してください。
フケ・かゆみ対策に用いられる有効成分の例
| 悩み | 有効成分の例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| フケ・かゆみ全般 | グリチルリチン酸ジカリウム | 抗炎症作用。頭皮の炎症を抑える。 |
| 脂性フケ・かゆみ | ミコナゾール硝酸塩 ピロクトンオラミン | 抗真菌(カビ)作用。原因菌の増殖を抑える。 |
| 乾燥フケ・かゆみ | セラミド、ヒアルロン酸 | 保湿作用。頭皮のバリア機能をサポートする。 |
抜け毛が気になる時の集中ケア
抜け毛が増えてきたと感じたら、まずは頭皮環境を悪化させている原因(生活習慣、ヘアケア)がないか総点検しましょう。その上で、頭皮の血行促進を意識したケアを取り入れます。
頭皮マッサージを習慣化することに加え、血行促進成分が含まれた育毛剤の使用を開始するのも良いタイミングです。育毛剤は、毛根に栄養を届けやすくする環境を整えるサポートをします。
ただし、抜け毛が細く短い、生え際や頭頂部が特に薄くなってきた、という場合は男性型脱毛症(AGA)の可能性が高いです。AGAは進行性のため、頭皮環境のケアだけでは進行を止めることは困難です。
この場合は、セルフケアと並行して、AGA専門のクリニックに相談することを強く推奨します。
頭皮環境を整える上でよくある誤解
頭皮ケアに関しては、多くの俗説や誤解が存在します。間違った情報に振り回されず、正しい知識を持つことが大切です。
シャンプーは朝と夜どちらが良い?
シャンプーは「夜」行うのが基本です。一日の活動で頭皮に付着した汗、皮脂、ホコリ、整髪料などをその日のうちにリセットすることが重要です。
汚れを放置したまま寝てしまうと、雑菌が繁殖しやすく、頭皮環境の悪化に繋がります。
また、髪の成長を促す成長ホルモンは夜間の睡眠中に分泌されます。その時間帯に頭皮を清潔な状態にしておくことが、育毛の観点からも望ましいです。
朝シャンは、寝癖直し程度に軽くお湯ですすぐ(湯シャン)か、どうしても必要な場合のみに留め、洗いすぎによる乾燥を防ぎましょう。
頭皮はしっかりこするべき?
これは大きな誤解です。皮脂や汚れを落としたい一心で、爪を立てたり、ブラシで強くこすったりすると、頭皮の角質層を傷つけてしまいます。
傷ついた頭皮はバリア機能が低下し、乾燥やかゆみ、炎症を引き起こしやすくなります。
シャンプーは「洗髪」ではなく「洗頭(せんとう)」、つまり頭皮を洗うものですが、その洗い方は「優しく揉み洗い」が正解です。指の腹を使って、泡のクッションで頭皮をマッサージするように洗いましょう。
汚れの多くは予洗いと泡で十分に落ちます。
自然乾燥は頭皮に優しい?
ドライヤーの熱が髪に悪いというイメージから、自然乾燥を選ぶ人もいますが、頭皮環境にとっては逆効果です。
髪が濡れた状態が長く続くと、頭皮の湿度が上がり、雑菌(カビや細菌)が非常に繁殖しやすい環境になります。これがフケやかゆみ、嫌なニオイの主な原因です。
また、髪が濡れているとキューティクルが開いた状態のため、摩擦ダメージも受けやすくなります。
シャンプー後は、できるだけ速やかにドライヤーで乾かすことが、頭皮と髪の健康を守るために重要です。
Q&A
頭皮環境を整える方法に関して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 頭皮環境が整うまでどれくらいかかりますか?
-
頭皮環境の改善にかかる期間は、個人の現在の状態や、生活習慣の乱れの程度によって大きく異なります。
一概には言えませんが、まずは実感できる変化(フケやかゆみの減少など)を目指して、最低でも1ヶ月から3ヶ月は正しいヘアケアと生活習慣の改善を継続することが大切です。
髪の毛にはヘアサイクル(成長期・退行期・休止期)があるため、抜け毛の減少や髪質の変化を実感するには、半年以上の長期的な取り組みが必要になる場合もあります。
- 食生活で特に気をつけるべき栄養素は何ですか?
-
髪の主成分である「たんぱく質」、その合成を助ける「亜鉛」、頭皮の新陳代謝や皮脂分泌の調整に関わる「ビタミンB群」は特に重要です。
これらを多く含む、肉、魚、卵、大豆製品、牡蠣、レバー、緑黄色野菜などをバランスよく摂取することを心がけてください。
逆に、脂質の多い揚げ物やジャンクフード、糖質の多いお菓子やジュース類の過剰摂取は、皮脂の分泌を増やし頭皮環境を悪化させる可能性があるため、控えるようにしましょう。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきですか?
-
育毛剤(医薬部外品)は、主に「今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防する」ことを目的としています。
そのため、抜け毛が増えてきた、髪が細くなってきた、頭皮が硬いと感じるなど、何らかの頭皮トラブルや将来への不安を感じ始めた時点が使い時と言えます。
AGAが強く疑われる場合は、育毛剤でのケアと並行して、早期に専門クリニックで相談し、適切な治療(医薬品の使用など)を検討することも重要です。
- 頭皮が日焼けしてしまった場合どうすればよいですか?
-
頭皮が日焼けして赤くなったり、ヒリヒリしたりする場合は、顔の肌と同様に「冷やす」ことと「保湿」が基本です。
まずは冷水や濡れタオル、保冷剤をタオルで包んだものなどで優しく冷やし、炎症を鎮めます。刺激の少ない(アルコールフリーや敏感肌用など)化粧水や頭皮用ローションで、しっかりと保湿を行います。
皮がむけてきた場合、無理に剥がすと頭皮を傷つけるため、自然に剥がれ落ちるのを待ちましょう。日頃から帽子や日傘、頭皮用の日焼け止めスプレーなどで予防することが最も大切です。
Reference
NEWTON‐FENNER, A., et al. Clear scalp, clear mind: Examining the beneficial impact of dandruff reduction on physical, emotional and social wellbeing. International journal of cosmetic science, 2025, 47.3: 466-475.
NARSHANA, M., et al. An overview of dandruff and novel formulations as a treatment strategy. Int J Pharm Sci Res, 2018, 9.2: 417-431.
XIAO, Lei, et al. A Timosaponin B‐II containing scalp care solution for improvement of scalp hydration, dandruff reduction, and hair loss prevention: A comparative study on healthy volunteers before and after application. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.3: 819-824.
BARAK-SHINAR, Deganit; GREEN, Lawrence J. Scalp seborrheic dermatitis and dandruff therapy using a herbal and zinc pyrithione-based therapy of shampoo and scalp lotion. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.1: 26.
TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.
KERR, Kathy, et al. Epidermal changes associated with symptomatic resolution of dandruff: biomarkers of scalp health. International journal of dermatology, 2011, 50.1: 102-113.
SCHWARTZ, James R.; JOHNSON, Eric S.; DAWSON, Thomas L. Shampoos for normal scalp hygiene and dandruff. Cosmetic Dermatology: Products and Procedures, 2022, 165-174.