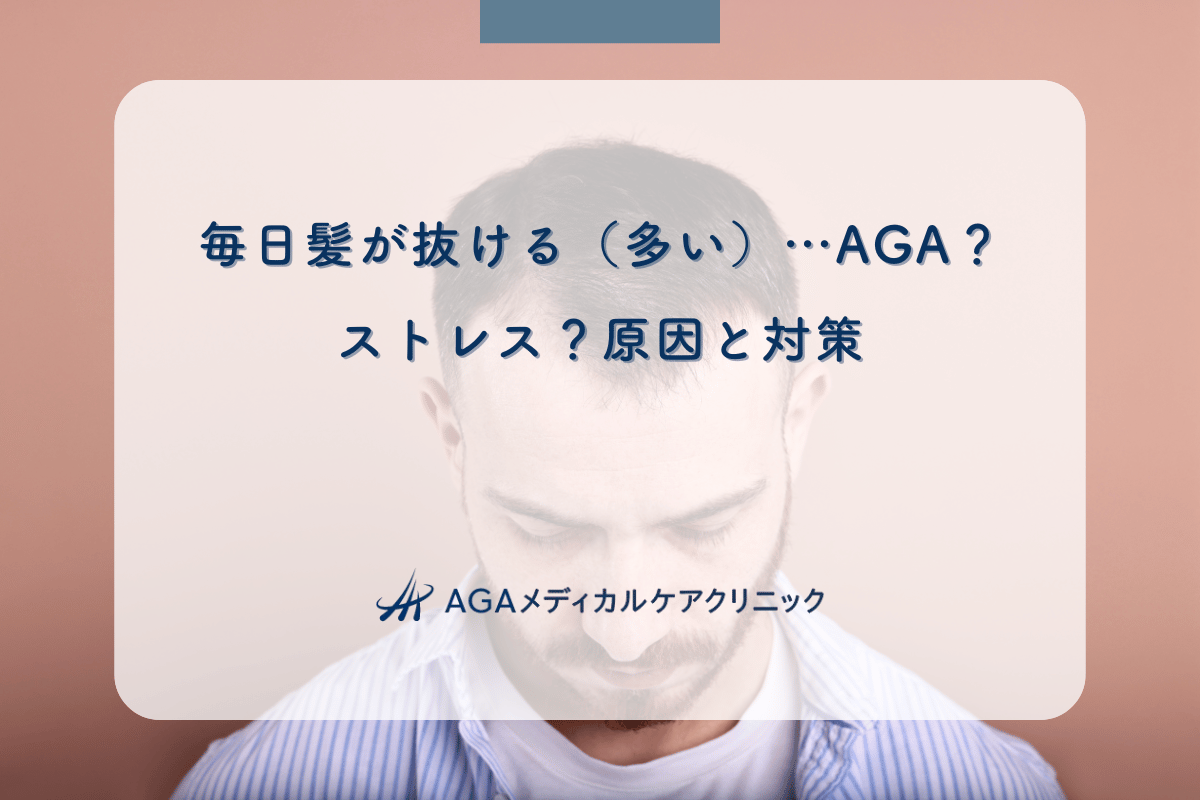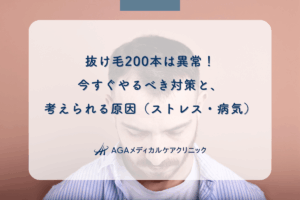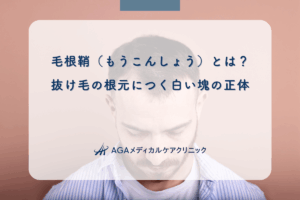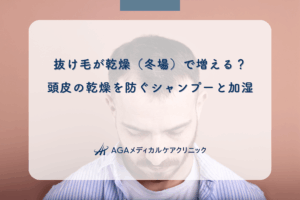お風呂の排水溝や朝起きた時の枕を見て、「毎日髪が抜ける量が多い…」と不安になっていませんか。
髪は毎日抜けるものですが、その量が明らかに多いと感じると「AGA(男性型脱毛症)かもしれない」「ストレスが原因だろうか」と心配になるのは当然のことです。
この記事では、毎日髪が抜けることに悩む男性のために、正常な抜け毛と危険な抜け毛の見分け方から、AGAやストレスといった主な原因、そして今日から始められる対策まで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
毎日どれくらい髪が抜けるのが普通か
毎日髪が抜けること自体は、実は非常に正常な生理現象です。問題は「その量」と「質」にあります。まずは、どれくらいが正常な範囲なのかを知り、ご自身の状況と比べてみましょう。
正常なヘアサイクル(毛周期)とは
私たちの髪の毛一本一本には寿命があり、一定の周期で生え変わっています。これを「ヘアサイクル(毛周期)」と呼びます。
ヘアサイクルは、大きく分けて「成長期」「退行期」「休止期」の3つの期間に分かれます。
「成長期」は髪が太く長く成長する期間で、男性の場合は2年から5年ほど続きます。頭髪全体の約85%から90%がこの状態にあります。
「退行期」は髪の成長が止まり、毛根が縮小していく期間で、約2週間ほどです。全体の約1%がこの状態です。「休止期」は髪の成長が完全に止まり、毛根が浅い位置に移動して抜け落ちるのを待つ期間です。
これが約3ヶ月から4ヶ月続き、全体の約10%から15%を占めます。そして、休止期の毛が抜け落ちると、同じ毛穴からまた新しい髪が(成長期として)生え始めます。
このサイクルを繰り返しているため、毎日髪が抜けるのは自然なことなのです。
1日の平均的な抜け毛本数
健康な頭皮状態の人でも、1日に抜ける髪の毛の本数は平均して約50本から100本程度と言われています。このうちの多くは、シャンプー時やブラッシング時に抜けています。
シャンプーの時に排水溝にたまる髪の毛を見て驚くかもしれませんが、その多くは休止期に入り、自然に抜け落ちるはずだった髪の毛が集まったものです。
したがって、1日に100本程度の抜け毛であれば、過度に心配する必要はありません。
季節による抜け毛の変動
抜け毛の本数は一年中一定というわけではなく、季節によっても変動します。特に「秋」は抜け毛が増えやすい季節として知られています。
これには諸説ありますが、夏の間に浴びた紫外線のダメージが頭皮に蓄積されることや、動物の毛が生え変わる換毛期の名残などが理由として考えられています。
秋口に一時的に抜け毛が増えたと感じても、それが通常の1.5倍から2倍程度(例えば150本から200本)であれば、季節性の要因である可能性が高いです。
ただし、その状態が長く続くようであれば注意が必要です。
抜け毛の本数を数える方法
自分がどれくらい抜けているか正確に知りたい場合、簡単な目安として数える方法があります。
朝起きた時の枕についている抜け毛、日中のブラッシングや手ぐしで抜ける毛、そしてシャンプー時の排水溝にたまった毛を大まかに集計します。
特にシャンプー時は抜け毛が集中するため、排水溝にネットなどを設置して1日分の抜け毛を集めてみると、おおよその本数を把握しやすくなります。
これを数日間続けて平均を見ることで、自分の抜け毛が正常範囲内かどうかを判断する材料になります。
髪が「多い」と感じる危険な抜け毛のサイン
毎日髪が抜ける本数が100本を超えていなくても、「多い」と感じる場合は、抜け毛の「質」に問題が隠れているかもしれません。
本数だけでなく、抜け毛の状態や頭皮のコンディションにも目を向けることが重要です。
抜け毛の質をチェックする
正常なヘアサイクルを終えて自然に抜けた毛(休止期毛)は、毛根部分が丸く膨らんでおり、ある程度の太さと長さがあります。一方で、危険な抜け毛には特徴があります。
抜けた髪の毛をよく観察してみてください。
もし、抜けた毛が「細く短い」「毛根部分が小さい、または尖っている」「毛根に白い皮脂のようなものが付着している」といった特徴が見られる場合、それはヘアサイクルが乱れ、髪が十分に成長する前に抜けてしまった(成長期毛)可能性を示しています。
これらはAGAや頭皮環境の悪化が疑われるサインです。
表:正常な抜け毛と危険な抜け毛の特徴
| チェック項目 | 正常な抜け毛(休止期毛) | 危険な抜け毛(成長期毛など) |
|---|---|---|
| 太さと長さ | 太く、しっかりしている | 細く、短い(うぶ毛のよう) |
| 毛根の形状 | 丸く膨らんでいる(こん棒状) | 小さい、尖っている、または無い |
| 毛根の色 | 白っぽいか透明 | 黒い、または皮脂が付着している |
頭皮の状態を確認する
抜け毛が増えたと感じる時、同時に頭皮にも何らかの症状が出ていないか確認しましょう。健康な頭皮は青白い色をしていますが、不健康な状態になると色が変わります。
「頭皮が赤い」場合は炎症を起こしている可能性があり、「茶色っぽい」場合は血行不良や代謝の低下が考えられます。
また、「フケ(特に脂っぽく湿ったフケ)が多い」「かゆみが常にある」「頭皮が脂っぽい、または逆に乾燥しすぎている」といった症状も、頭皮環境が悪化し、抜け毛を引き起こしているサインです。
頭皮は髪が育つ土壌です。土壌の状態が悪ければ、健康な髪は育ちません。
抜け毛が増える特定の状況
「朝起きた時の枕」「シャンプー時」以外にも、特定の状況で抜け毛が目立つ場合は注意が必要です。
例えば、「日中に手ぐしを通しただけで、何本も髪がついてくる」「デスクワーク中にふと見ると、キーボードや机の上に抜け毛がたくさん落ちている」といった場合、髪の毛が弱っており、少しの刺激で抜けやすくなっている証拠です。
これらのサインを見逃さず、早期に対処することが大切です。
毎日髪が多く抜ける主な原因
毎日髪が抜ける量が多いと感じる背景には、さまざまな原因が考えられます。代表的なものには脱毛症、生活習慣の乱れ、そしてホルモンバランスの変化などがあります。
原因を特定することが、適切な対策への第一歩となります。
脱毛症の種類と特徴
「抜け毛が多い」状態が続く場合、何らかの脱毛症を発症している可能性があります。男性の抜け毛で最も多いのは「AGA(男性型脱毛症)」です。これは特定のパターンで薄毛が進行するのが特徴です。
他にも、ストレスが引き金となると考えられている「円形脱毛症」(コイン状に髪が抜ける)、頭皮の皮脂が過剰になって起こる「脂漏性脱毛症」(フケやかゆみを伴う)、髪を強く引っ張り続けることで起こる「牽引性脱毛症」など、脱毛症には種類があります。
自分の抜け毛のパターンや頭皮の状態がどれに当てはまるかを知ることが重要です。特にAGAは進行性のため、早期の認識が求められます。
生活習慣の乱れ
髪の毛は、私たちが日々摂取する栄養素から作られています。そのため、食生活の乱れは髪の健康に直結します。
脂っこい食事の摂りすぎ、過度なダイエットによる栄養不足、特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助けるビタミン、ミネラル(特に亜鉛)の不足は、髪の成長を妨げ、抜け毛を増やします。
また、睡眠不足は髪の成長を促す「成長ホルモン」の分泌を妨げます。喫煙は血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させ、過度な飲酒は体内でビタミンを消費し、肝臓に負担をかけます。
これらの生活習慣の乱れが複合的に絡み合い、抜け毛を加速させているケースは少なくありません。
ホルモンバランスの変化
男性の抜け毛、特にAGAと深く関係しているのが男性ホルモンです。
男性ホルモンの一種である「テストステロン」が、頭皮に存在する特定の酵素「5αリダクターゼ」と結びつくと、「ジヒドロテストステロン(DHT)」という強力な男性ホルモンに変換されます。
このDHTが、毛根にある受容体と結合すると、髪の成長期を短縮させる信号を出し、髪が太く長く成長する前に抜け落ちるように仕向けます。
これがAGAの主な原因です。このDHTの感受性は遺伝的要因が強いとされていますが、ストレスなどによってホルモンバランス全体が乱れることも、抜け毛に影響を与えます。
原因① AGA(男性型脱毛症)の詳しい解説
毎日髪が抜ける量が多いと感じる男性にとって、最も可能性が高く、また最も心配されるのがAGA(男性型脱毛症)です。
AGAは進行性であり、放置すると薄毛が徐々に広がっていきます。正しい知識を持つことが重要です。
AGAとは何か
AGAは「Androgenetic Alopecia」の略で、日本語では「男性型脱毛症」と呼びます。
成人男性に多く見られ、思春期以降に発症し、生え際(M字部分)や頭頂部(O字部分)、あるいはその両方から髪が薄くなっていくのが特徴です。
前述の通り、男性ホルモン(DHT)がヘアサイクルを乱し、成長期を極端に短くしてしまうことが原因です。
通常のヘアサイクルでは2年から5年ある成長期が、AGAを発症すると数ヶ月から1年程度に短縮されます。
これにより、髪の毛は太く長く成長する機会を失い、細く短い「うぶ毛」のような状態のまま抜け落ちてしまいます。その結果、全体の毛髪量が減少し、地肌が目立つようになるのです。
AGAの進行パターン
AGAによる薄毛の進行パターンには個人差がありますが、いくつかの典型的な型が知られています。
これらは「ハミルトン・ノーウッド分類」という指標で分類されることが多く、薄毛の進行度合いを示す目安となります。
表:主なAGAの進行パターン
| パターンタイプ | 特徴 | 進行の仕方 |
|---|---|---|
| M字型(Ⅰ型、Ⅱ型など) | 額の生え際、特に両サイド(M字)から後退していく。 | こめかみ部分の剃り込みが深くなっていく。 |
| O字型(Ⅲ型 vertexなど) | 頭頂部(つむじ周辺)から円形に薄くなっていく。 | つむじを中心に地肌が透けて見える範囲が広がる。 |
| U字型(混合型) | M字型とO字型が同時に進行し、最終的にU字型に残る。 | 生え際の後退と頭頂部の薄毛が繋がり、側頭部と後頭部の毛が残る。 |
AGAの自己診断チェック
ご自身がAGAの傾向があるかどうか、いくつかの項目でセルフチェックが可能です。当てはまる項目が多いほど、AGAの可能性が考えられます。
リスト:AGAセルフチェック項目
- 家族(特に父方・母方の祖父)に薄毛の人がいる。
- 以前と比べて、髪の毛にハリやコシがなくなった。
- 抜けた毛が細く、短いものが多い。
- 生え際が後退してきた、または額が広くなったと感じる。
- 頭頂部の地肌が透けて見えるようになった。
- シャンプーやスタイリングの際に、髪のボリュームが減ったと感じる。
これらはあくまで目安です。AGAは進行性のため、これらのサインに気づいたら、そのままにせず対策を考えることが重要です。
自己判断で「まだ大丈夫」と考えるのではなく、客観的な事実として受け止めましょう。
遺伝との関係
AGAの発症には、遺伝的要因が強く関与していることが分かっています。
「薄毛は遺伝する」とよく言われますが、具体的には「5αリダクターゼの活性度」と「男性ホルモン受容体(DHTを受け取る部分)の感受性」の2つが遺伝しやすいとされています。
特に、男性ホルモン受容体の感受性は、母親から受け継ぐX染色体上にあるため、母方の家系(母方の祖父や叔父)に薄毛の人がいる場合、AGAを発症する可能性が高まると言われています。
ただし、遺伝的要因があっても必ず発症するわけではなく、また遺伝的要因がなくても発症する可能性はあります。遺伝はあくまで「なりやすさ」の指標の一つと捉えましょう。
原因② ストレスと抜け毛のつながり
「毎日髪が抜ける量が多い」と感じる時、AGAと並んで多くの方が心配するのが「ストレス」です。
仕事、人間関係、将来への不安など、現代社会で生きる男性は多くのストレスにさらされています。ストレスは心だけでなく、確実に身体、そして髪の毛にも影響を及ぼします。
ストレスが頭皮に与える影響
人が強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れます。自律神経には活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」があります。
ストレス状態が続くと交感神経が優位になり続け、血管が収縮します。頭皮には毛細血管が張り巡らされており、髪の成長に必要な栄養や酸素を運んでいます。
血管が収縮すると、この血流が悪化し、毛根にある毛母細胞が栄養不足に陥ります。その結果、髪の成長が妨げられ、抜け毛が増加するのです。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、皮脂の過剰分泌を引き起こすこともあります。過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、頭皮環境を悪化させる一因となります。
精神的ストレスと身体的ストレス
ストレスには、職場のプレッシャーや人間関係の悩みといった「精神的ストレス」と、過労、睡眠不足、不規則な生活といった「身体的ストレス」があります。どちらのストレスも、抜け毛の原因となり得ます。
特に慢性的な睡眠不足は、髪の成長に重要な成長ホルモンの分泌を著しく低下させます。
精神的な悩みが睡眠不足を引き起こし、それが身体的ストレスとなって抜け毛を加速させる、という悪循環に陥ることも少なくありません。
ご自身がどの ようなストレスを抱えているかを認識することが、対策の第一歩です。
ストレスによる脱毛症の種類
ストレスが主な引き金となって起こる脱毛症も存在します。AGAとは異なる特徴を持つため、見分けることが大切です。
表:ストレスが関連する主な脱毛症
| 脱毛症の種類 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 円形脱毛症 | コイン大(10円玉程度)の円形や楕円形に髪が抜ける。 | 自己免疫疾患の一種と考えられ、ストレスが引き金になることが多い。多発することもある。 |
| 休止期脱毛症 | 頭部全体の髪が均一に薄くなる(びまん性)。 | 強いストレスや高熱、出産、過度なダイエットなどにより、多くの髪が一度に休止期に入り、数ヶ月後に一気に抜ける。 |
| 抜毛症(トリコチロマニア) | 自分で無意識のうちに髪の毛を引き抜いてしまう。 | 精神的なストレスや不安が背景にあることが多い。抜け毛の毛根が損傷していることが多い。 |
もし円形に抜けている場合や、短期間で急激に全体の毛量が減った場合は、AGAではなくこれらの脱毛症の可能性も考え、皮膚科などの専門医に相談することを推奨します。
AGAと円形脱毛症が併発することもあります。
その他の抜け毛の原因と生活習慣の見直し
AGAやストレス以外にも、日々の何気ない習慣が「毎日髪が抜ける」原因となっていることがあります。生活習慣全体を見直し、頭皮環境を整えることが抜け毛対策の基本です。
栄養バランスの偏り
髪の毛は「ケラチン」というタンパク質から主に構成されています。そのため、肉、魚、卵、大豆製品などの良質なタンパク質の摂取は非常に重要です。
しかし、タンパク質だけを摂取しても健康な髪は作られません。タンパク質を髪の毛に合成する際には、ビタミンやミネラルが補酵素として働きます。
特に「亜鉛」はケラチンの合成に深く関わり、「ビタミンB群(特にB2, B6)」は皮脂の分泌をコントロールし、頭皮環境を整えます。「ビタミンE」は血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくします。
脂っこい食事やジャンクフード、インスタント食品ばかりの食生活では、これらの栄養素が不足しがちです。
また、過剰な脂質は皮脂の分泌を増やし、頭皮環境を悪化させます。バランスの取れた食事を心がけることが、抜け毛予防につながります。
表:髪の健康に役立つ主な栄養素と食材例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける。ヘアサイクルを正常に保つ。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂分泌を調整する。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、納豆 |
睡眠不足の影響
髪の毛は、毛根にある毛母細胞が分裂・増殖することで成長します。この細胞分裂を最も活発に促すのが「成長ホルモン」です。
成長ホルモンは、私たちが深い眠り(ノンレム睡眠)に入っている時間帯、特に夜10時から深夜2時のゴールデンタイムと呼ばれる時間帯に最も多く分泌されると言われてきました。
(最近では時間帯よりも「入眠後最初の深い眠り」が重要という説が有力です)。
いずれにせよ、睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が不十分になります。
これにより毛母細胞の働きが低下し、髪の成長が妨げられ、抜け毛や細毛の原因となります。毎日最低でも6時間から7時間の質の良い睡眠を確保するよう努めましょう。
誤ったヘアケア
頭皮を清潔に保つことは重要ですが、間違ったヘアケアが逆に頭皮を傷つけ、抜け毛を増やしているケースがあります。
「洗浄力が強すぎるシャンプー」は、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥やフケ、かゆみの原因となります。
逆に「汚れが落としきれていない」場合、皮脂や整髪料が毛穴に詰まり、炎症を引き起こします。
シャンプーは1日1回、自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌など)に合ったアミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のものを選び、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗いましょう。
すすぎ残しは頭皮トラブルの元なので、十分な時間をかけて洗い流すことも大切です。
リスト:見直したい誤ったヘアケア習慣
- 1日に何度もシャンプーをする。
- 爪を立ててゴシゴシ洗っている。
- 熱すぎるお湯ですすいでいる。
- シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しがある。
- 髪を乾かさずに濡れたまま寝る。(雑菌が繁殖しやすい)
病気や薬の副作用
まれなケースですが、特定の病気(甲状腺機能の異常、膠原病など)や、服用している薬の副作用として抜け毛(薬剤性脱毛症)が起こることもあります。
AGAやストレス、生活習慣の乱れに心当たりがなく、急激に抜け毛が増えた場合は、かかりつけの医師や皮膚科医に相談し、全身の健康状態についても確認することが賢明です。
抜け毛が気になり始めた時の対策
毎日髪が抜ける量が多いと感じ、その原因がAGAであれストレスであれ、不安を感じた時点ですぐに対策を始めることが、将来の髪を守るために最も重要です。できることから着手しましょう。
まずはセルフケアでできること
専門的な治療を始める前に、ご自身で見直せる生活習慣は数多くあります。まずは「食事・睡眠・運動」の生活基盤を整えることが基本です。
前述した栄養バランスの取れた食事を心がけ、質の良い睡眠時間を確保しましょう。また、適度な運動(ウォーキングやジョギングなど)は、全身の血行を促進するだけでなく、ストレス解消にも非常に有効です。
ストレスを溜め込まないよう、趣味の時間を持ったり、リラックスできる入浴方法を取り入れたりすることも大切です。そして、正しいヘアケアを実践し、頭皮環境を清潔で健康な状態に保ちましょう。
これらのセルフケアは、抜け毛の進行を緩やかにし、育毛剤などの効果を高める土台となります。
専門家(皮膚科・クリニック)への相談
セルフケアを続けても抜け毛が減らない、あるいはAGAの進行パター(M字やO字)が明確に見られる場合は、自己判断で悩み続けるよりも専門家へ相談することを強く推奨します。
皮膚科やAGA専門のクリニックでは、医師が頭皮の状態や毛根をマイクロスコープなどで詳しく診察し、抜け毛の原因を客観的に診断します。
AGAと診断された場合は、進行を抑制するための内服薬(5αリダクターゼ阻害薬など)や、発毛を促すための外用薬(ミノキシジルなど)の処方といった、医学的根拠に基づいた治療を受けることが可能です。
早期に相談することで、治療の選択肢も広がり、改善の可能性も高まります。
育毛剤や発毛剤の選び方
クリニックでの治療と並行して、または初期段階のセルフケアとして、育毛剤や発毛剤の使用を検討するのも一つの方法です。
ただし、「育毛剤」と「発毛剤」は目的と成分が異なりますので、違いを理解して選ぶ必要があります。
「育毛剤」(医薬部外品)は、主に「今ある髪を健康に育てる」ことを目的としています。
頭皮の血行を促進したり、毛根に栄養を与えたり、頭皮環境を整えたりすることで、抜け毛を予防し、髪にハリやコシを与えます。
「発毛剤」(第一類医薬品)は、主に「新しい髪を生やす」ことを目的としています。
日本で唯一「発毛」効果が認められている成分「ミノキシジル」が配合されており、毛母細胞に直接働きかけてヘアサイクルを正常化し、発毛を促します。
表:育毛剤と発毛剤の主な違い
| 項目 | 育毛剤 | 発毛剤(ミノキシジル配合) |
|---|---|---|
| 分類 | 医薬部外品 | 第一類医薬品 |
| 主な目的 | 抜け毛予防、育毛促進(今ある髪を育てる) | 発毛促進(新しい髪を生やす) |
| 主な有効成分 | 血行促進成分(センブリエキスなど)、抗炎症成分など | ミノキシジル |
| 適している人 | 抜け毛が増え始めた人、髪のハリ・コシが欲しい人 | 薄毛が進行している人、AGAと診断された人 |
ご自身の状態が「抜け毛予防」の段階なのか、「発毛」が必要な段階なのかを見極め、目的に合った製品を選びましょう。
当メディアでは男性用の育毛剤を特集しており、あなたの頭皮タイプや悩みに合わせた製品選びの参考情報を提供しています。
若年性・初期症状に戻る
よくある質問
毎日髪が抜けることに関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
- 抜け毛は一度増えると元に戻らないのか?
-
原因によります。例えば、ストレスや生活習慣の乱れによる一時的な「休止期脱毛症」であれば、原因が取り除かれ、ヘアサイクルが正常に戻れば、再び髪が生え揃う可能性は高いです。
しかし、AGA(男性型脱毛症)の場合は進行性です。何もしなければ抜け毛は減らず、薄毛は徐々に進行していきます。
ただし、AGAも早期に適切な対策(育毛剤の使用や専門的な治療など)を開始することで、その進行を遅らせたり、発毛を促したりすることは可能です。
諦めずに原因を特定し、行動することが重要です。
- シャンプーは毎日しない方が良いのか?
-
基本的には、シャンプーは毎日1回行うことを推奨します。特に脂性肌の人や、日中に汗をかいたり整髪料を使ったりした場合は、その日の汚れや皮脂をしっかりとリセットする必要があります。
汚れを放置すると、雑菌が繁殖し、毛穴が詰まって頭皮環境が悪化し、かえって抜け毛の原因になります。
ただし、乾燥肌の人が洗浄力の強すぎるシャンプーで毎日洗うと、頭皮が乾燥しすぎることもあります。
その場合は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーを選んだり、洗い方をより優しくしたりする工夫が必要です。自分の頭皮状態に合わせて「優しく丁寧に洗う」ことを心がけましょう。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきか?
-
育毛剤は、抜け毛の「予防」や「現状維持」を目的とする側面が強いため、抜け毛の量が気になり始めた「初期段階」から使い始めるのが最も効果的です。
「まだ大丈夫」と思っているうちから頭皮環境を整えるケアを始めることが、将来の薄毛進行を食い止める鍵となります。
髪のハリやコシがなくなってきた、地肌が少し透けて見える気がする、といったサインを感じたら、それは育毛剤を検討し始める良いタイミングです。
薄毛が明確に進行してしまってからでは、育毛剤だけでの改善は難しくなるため、早期のケアが大切です。
- 食生活だけで抜け毛は改善できるか?
-
もし抜け毛の原因が「栄養不足」のみであった場合は、食生活の改善だけで抜け毛が減る可能性はあります。
しかし、多くの場合、抜け毛の原因はAGA、ストレス、血行不良、睡眠不足など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
そのため、食生活の改善は非常に重要な「土台作り」ではありますが、それ「だけ」でAGAの進行を止めたり、ストレスによる脱毛を完全に治したりすることは難しいのが現実です。
バランスの取れた食事は、あくまで抜け毛対策の基本の一つとして捉え、他の対策(生活習慣の改善、育毛剤の使用、専門家への相談)と組み合わせて行うことが、改善への近道です。
Reference
CHENG, Yi, et al. Psychological stress impact neurotrophic factor levels in patients with androgenetic alopecia and correlated with disease progression. World journal of psychiatry, 2024, 14.10: 1437.
AUKERMAN, Erica L.; JAFFERANY, Mohammad. The psychological consequences of androgenetic alopecia: A systematic review. Journal of Cosmetic Dermatology, 2023, 22.1: 89-95.
CASH. The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: a review of the research literature. British Journal of Dermatology, 1999, 141.3: 398-405.
CASH, Thomas F. The psychological effects of androgenetic alopecia in men. Journal of the American Academy of Dermatology, 1992, 26.6: 926-931.
FRITH, Hannah; JANKOWSKI, Glen S. Psychosocial impact of androgenetic alopecia on men: A systematic review and meta-analysis. Psychology, Health & Medicine, 2024, 29.4: 822-842.
MOHAMMED, Sherif. Psychological and Emotional Impacts of Androgenetic Alopecia on Adolescent and Young Adult Males: A Systematic Review. Available at SSRN 5557045, 2025.
CASH, Thomas F.; PRICE, Vera H.; SAVIN, Ronald C. Psychological effects of androgenetic alopecia on women: comparisons with balding men and with female control subjects. Journal of the American Academy of Dermatology, 1993, 29.4: 568-575.
SAWANT, Neena, et al. Androgenetic alopecia: quality-of-life and associated lifestyle patterns. International journal of trichology, 2010, 2.2: 81-85.
GONUL, Muzeyyen, et al. Comparison of quality of life in patients with androgenetic alopecia and alopecia areata. Anais brasileiros de dermatologia, 2018, 93: 651-658.
MONSELISE, Assaf, et al. Examining the relationship between alopecia areata, androgenetic alopecia, and emotional intelligence. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 2013, 17.1: 46-51.