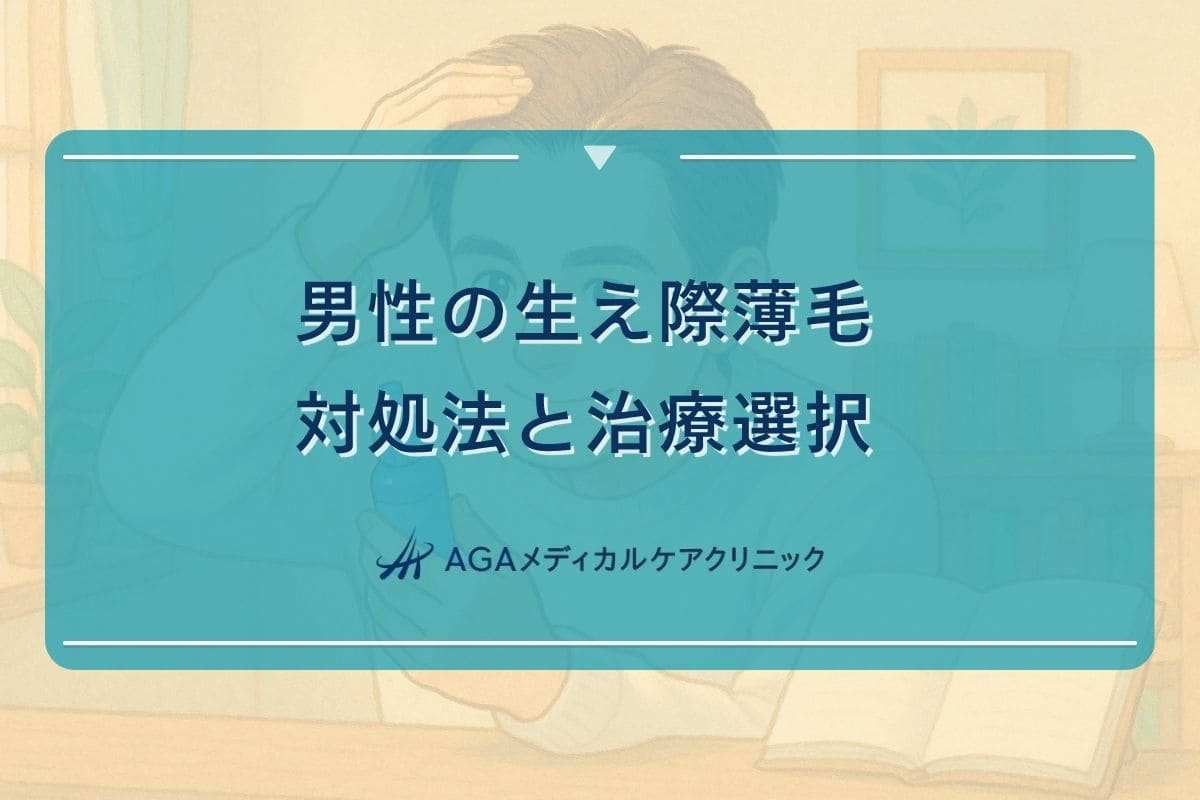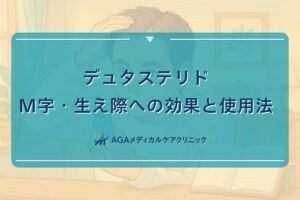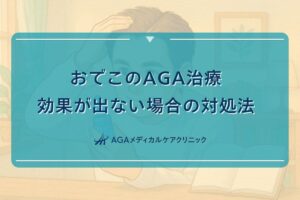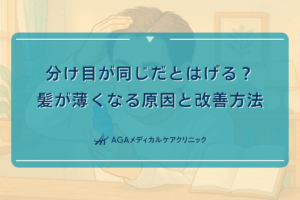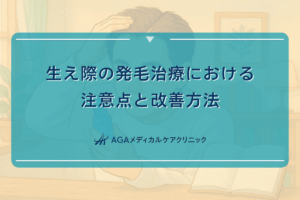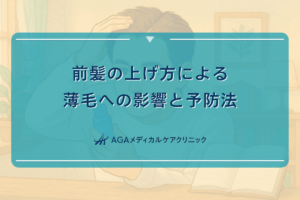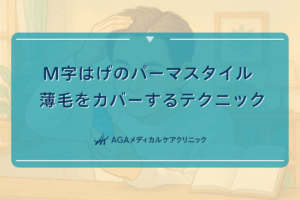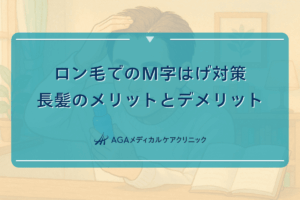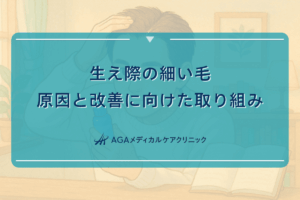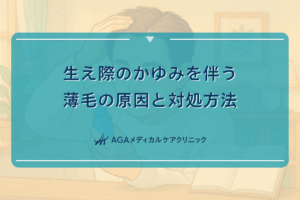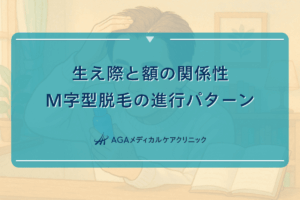「生え際が後退してきた…」「後頭部の髪が薄くなった気がする…」そのような悩みは多くの男性が経験するものです。
特にM字型やU字型に進行する生え際の薄毛は見た目の印象を大きく左右するため、深刻なコンプレックスになりがちです。
しかし、諦める必要はありません。生え際の薄毛はその原因を正しく理解し、適切な対処と治療を行うことで進行を食い止め、改善を目指すことが可能です。
この記事では生え際と後頭部の薄毛の主な原因であるAGAの知識から、具体的な治療選択肢までを専門的な観点から詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
生え際と後頭部 なぜ薄くなるのか
生え際や後頭部の薄毛が目立ち始めるのには、明確な理由があります。その多くは男性特有の脱毛症であるAGA(男性型脱毛症)が関係しています。
まずは、薄毛が起こる基本的な知識を理解しましょう。
AGA(男性型脱毛症)が主な原因
成人男性に見られる薄毛のほとんどはAGAが原因です。AGAは進行性の脱毛症で、一度発症すると自然に治ることはありません。
放置すると髪の毛は徐々に細く短くなり、最終的には生えてこなくなってしまいます。特に生え際と頭頂部(後頭部)の毛髪が影響を受けやすいのが特徴です。
M字・U字・O字 進行パターンの違い

AGAの進行パターンには個人差があり、主に3つのタイプに分けられます。
自分がどのタイプに当てはまるかを知ることは現状を把握する上で重要です。複数のパターンが同時に進行することもあります。
AGAの代表的な進行パターン
| 進行パターン | 特徴 | 薄くなる部位 |
|---|---|---|
| M字型 | 額の左右の生え際が後退していく | 前頭部(こめかみの上あたり) |
| U字型 | 生え際全体が後退していく | 前頭部全体 |
| O字型 | 頭頂部から円形に薄くなっていく | 頭頂部(つむじ周り) |
悪玉男性ホルモンDHTの影響
AGAの直接的な引き金となるのが、DHT(ジヒドロテストステロン)という強力な男性ホルモンです。男性ホルモンのテストステロンが特定の酵素「5αリダクターゼ」と結びつくことでDHTに変換されます。
このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結合すると髪の成長を妨げる信号が出され、ヘアサイクルが乱れて薄毛が進行します。
遺伝とホルモンの関係性
AGAの発症には遺伝が大きく関わっています。具体的には「5αリダクターゼの活性度の高さ」と「男性ホルモン受容体の感受性の高さ」という2つの要素が遺伝しやすいと言われています。
親族に薄毛の方がいる場合、AGAを発症する可能性が高いと考え、早めの対策を心がけることが大切です。
「まだ大丈夫」その油断が生え際後退を加速させる
「少し生え際が後退しただけ」「髪型で隠せるから問題ない」。薄毛の初期段階では、このように考えてしまう方が少なくありません。
しかしその油断こそが、気づいたときには手遅れになりかねない状況を招く最大の敵です。
ここでは多くの方が見過ごしがちな心理的な側面から、早期行動の重要性を考えます。
初期サインを見過ごす心理
薄毛はゆっくりと進行するため、日々のわずかな変化には気づきにくいものです。
また、「自分はまだ大丈夫」という正常性バイアス(自分にとって都合の悪い情報を無視する傾向)が働き、問題を直視することを避けてしまいがちです。
そのような心理が対策を遅らせる大きな原因となります。
見過ごされがちな薄毛の初期サイン
| サイン | 具体的な状態 |
|---|---|
| 髪質の変化 | 髪にハリやコシがなくなり、細く柔らかくなった |
| 抜け毛の増加 | シャンプーや朝起きたときの枕元の抜け毛が目立つ |
| 頭皮の状態 | 頭皮が透けて見えるようになった、地肌が硬い |
鏡で見る自分と他者から見た印象のギャップ
毎日鏡で見ている正面からの姿と、他人から見られる斜めや上からの姿には大きな違いがあります。自分では気づきにくい頭頂部の薄毛や、後退した生え際の進行具合も、他人の視線は正直に捉えています。
「最近、疲れてる?」など間接的な指摘を受けて初めて、事の重大さに気づくケースも少なくありません。
時間の経過がもたらす不可逆的な変化
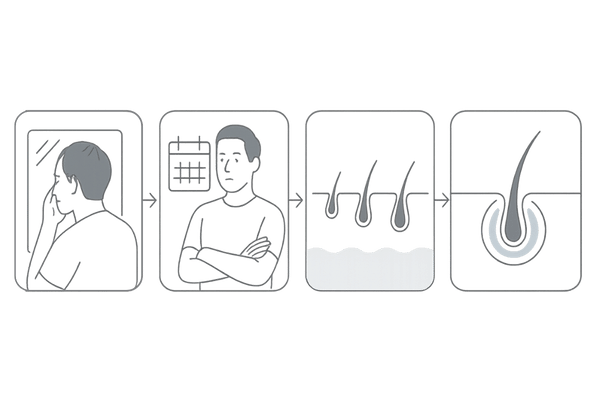
AGAによってヘアサイクルが乱れると毛根は徐々に小さくなり、髪を生み出す力を失っていきます。
この状態が長く続くと毛根は完全に活動を停止し、治療をしても髪が生えてこない状態(線維化)に至ることがあります。
失われた毛根は現在の医学では元に戻すことは困難です。だからこそ、手遅れになる前の行動が何よりも重要になります。
後悔する前に行動を起こす重要性
「あの時もっと早く相談していれば…」。私たちは多くの患者さんからこのような後悔の言葉を耳にしてきました。
薄毛の悩みは一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への最短ルートです。あなたのその小さな一歩が、未来の髪と自信を守るための最も確実な一歩となります。
市販の育毛剤やシャンプーで生え際は復活するのか
薄毛が気になり始めたとき、まず手に取るのが市販の育毛剤やスカルプシャンプーかもしれません。
しかしこれらのセルフケアでAGAの進行を止め、生え際を元に戻すことは可能なのでしょうか。その効果と限界を正しく理解しましょう。
育毛剤と発毛剤の根本的な違い
市販されている製品には「育毛剤」と「発毛剤」があり、その目的は全く異なります。「育毛剤」は今ある髪を健康に保つためのもので、「発毛剤」は新しい髪を生やすことを目的としています。
AGA対策には「発毛剤」が必要ですが、市販されているのはミノキシジル配合のものに限られます。
育毛剤と発毛剤の目的の違い
| 分類 | 主な目的 | 区分 |
|---|---|---|
| 育毛剤 | 頭皮環境を整え、抜け毛を予防する | 医薬部外品 |
| 発毛剤 | 毛母細胞を活性化させ、新たな髪を生やす | 第一類医薬品 |
シャンプーの役割は頭皮環境の改善
スカルプシャンプーや薬用シャンプーは頭皮の余分な皮脂や汚れを洗い流し、清潔な環境を保つことを目的としています。
頭皮環境の改善は健康な髪にとって大切ですが、シャンプー自体に髪を生やす効果やAGAの進行を止める効果はありません。あくまで補助的なケアと位置づけましょう。
市販品にできることの限界
市販品によるセルフケアは、あくまで頭皮環境の維持や、ごく初期の抜け毛予防が限界です。AGAの根本原因であるDHTの生成を抑制する効果は市販品には期待できません。
すでに生え際の後退や頭頂部の薄毛が進行している場合、セルフケアだけで改善するのは非常に困難です。
誤ったセルフケアが招くリスク
効果が不確かな製品に頼り続けることは時間とお金を浪費するだけでなく、貴重な治療の機会を逃すことにつながります。
AGAは進行性であるため、対策が遅れるほど改善のハードルは高くなります。
- 治療機会の損失
- 症状の悪化
- 精神的ストレスの増大
クリニックで行う生え際・後頭部の薄毛治療
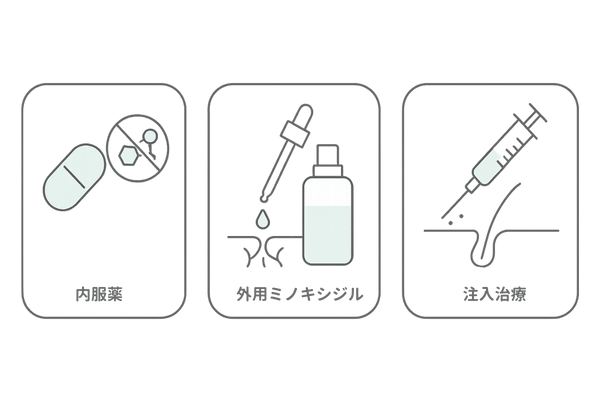
AGAによる生え際や後頭部の薄毛に対して専門のクリニックでは医学的根拠に基づいた効果的な治療を行います。
自己流のケアとは異なり、薄毛の根本原因に直接アプローチすることが可能です。
進行を止める内服薬治療
AGA治療の基本となるのが、内服薬による治療です。AGAの原因であるDHTの生成を抑制する「5αリダクターゼ阻害薬」を服用することで抜け毛を減らし、薄毛の進行を食い止めます。
この治療は現状を維持し、これ以上悪化させないための守りの治療と言えます。
発毛を促す外用薬治療
内服薬と並行して行われることが多いのが、ミノキシジルを配合した外用薬による治療です。ミノキシジルには血管を拡張して頭皮の血流を促進し、毛母細胞を活性化させる働きがあります。
この作用により発毛を促し、髪の毛を太く長く成長させるという攻めの治療です。
主な治療法の比較
| 治療法 | 主な効果 | 役割 |
|---|---|---|
| 内服薬(5αリダクターゼ阻害薬) | AGAの進行抑制、抜け毛の減少 | 守りの治療 |
| 外用薬(ミノキシジル) | 発毛促進、毛髪の成長 | 攻めの治療 |
| 注入治療 | 有効成分を直接頭皮に届ける | 積極的な攻めの治療 |
より積極的な注入治療
内服薬や外用薬だけでは効果が不十分な場合や、より早く効果を実感したい場合には、注入治療という選択肢もあります。
これは発毛を促進する成長因子などの有効成分を注射や特殊な機器を使って頭皮に直接注入する治療法です。
毛母細胞に直接栄養を届けることで、より高い発毛効果を期待できます。
治療法の組み合わせと個別化
AGAの治療ではこれらの治療法を単独で行うのではなく、患者さん一人ひとりの症状の進行度や体質、ライフスタイルに合わせて組み合わせることが重要です。
専門医が診察の上で、最も効果的なオーダーメイドの治療計画を提案します。
治療薬の種類とそれぞれの特徴
クリニックで処方されるAGA治療薬には、主に2種類の内服薬と1種類の外用薬があります。
それぞれの薬がどのように作用し、どのような特徴があるのかを理解することは、安心して治療を受けるために大切です。
5αリダクターゼ阻害薬(フィナステリド)
フィナステリドは世界で広く使われているAGA治療薬です。5αリダクターゼの中でも、主に生え際や頭頂部に存在する「II型」の働きを阻害します。
このことによりDHTの生成を抑制し、AGAの進行を食い止めます。
5αリダクターゼ阻害薬(デュタステリド)
デュタステリドはフィナステリドと同様に5αリダクターゼの働きを阻害する薬ですが、より強力な特徴を持ちます。
「II型」だけでなく、皮脂腺に多く存在する「I型」の5αリダクターゼも阻害するため、より広範囲かつ強力にDHTの生成を抑制する効果が期待できます。
AGA内服治療薬の比較
| 薬剤名 | 阻害する酵素の型 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| フィナステリド | II型 | 世界的に実績が豊富 |
| デュタステリド | I型およびII型 | より強力なDHT抑制効果 |
血行促進薬(ミノキシジル)
ミノキシジルは、もともと高血圧の治療薬として開発された成分ですが、発毛効果があることが分かり、薄毛治療に用いられるようになりました。頭皮に直接塗布することで毛細血管を拡張させ、血流を改善します。毛母細胞に栄養を届け、発毛を促進する作用があります。
各治療薬の作用と注意点
これらの治療薬は医師の処方のもとで正しく使用することが重要です。
個人輸入などで安易に入手すると偽造薬であったり、副作用が出た際に対応できなかったりするリスクがあります。
必ず専門のクリニックで診察を受け、適切な指導のもとで治療を開始してください。
治療効果を高めるための生活習慣の見直し
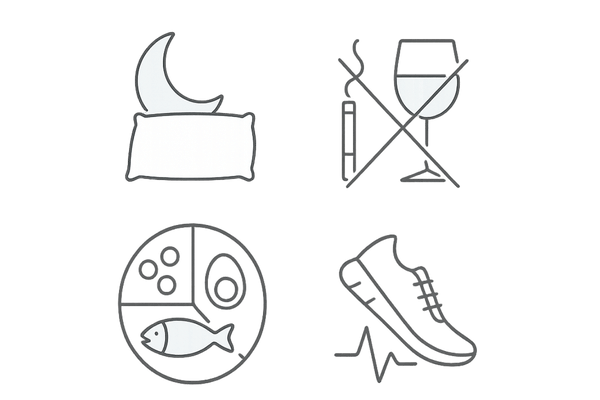
AGA治療の効果を最大限に引き出すには、薬による治療と並行して日々の生活習慣を見直すことが重要です。
食事、運動、睡眠などが頭皮環境やホルモンバランスに与える影響は決して小さくありません。
髪の成長を支える食生活
髪の毛は私たちが食べたものから作られます。
特に髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮の血行を良くするビタミンEなどをバランス良く摂取することが大切です。
- タンパク質
- 亜鉛
- ビタミン類
髪の健康に役立つ栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、ナッツ類 |
| ビタミンE | 血行を促進し、頭皮環境を整える | アボカド、アーモンド、かぼちゃ |
血行促進とストレス管理に役立つ運動
ウォーキングやジョギングなどの適度な有酸素運動は全身の血行を促進し、頭皮にも十分な栄養を届ける助けとなります。
また、運動はストレス解消にも効果的であり、ストレスによるホルモンバランスの乱れや血行不良を防ぐことにもつながります。
睡眠の質がホルモンバランスを左右する
髪の成長や体の修復に重要な成長ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。慢性的な睡眠不足はホルモンバランスを乱し、頭皮環境を悪化させる原因となります。
毎日7時間程度の質の良い睡眠を確保するよう心がけましょう。
喫煙と飲酒が頭皮に与える影響
喫煙は血管を収縮させ、頭皮の血行を著しく悪化させます。
また、過度な飲酒は髪の成長に必要な栄養素の吸収を妨げたり、肝臓でアルコールを分解する際にビタミンやアミノ酸を大量に消費したりするため、薄毛を助長する可能性があります。
治療効果を高めるためにも、禁煙や節酒を検討することが望ましいです。
クリニック選びで失敗しないためのポイント
AGA治療は継続することが重要であり、信頼できるクリニックをパートナーとして選ぶことが成功の鍵となります。
どのような点に注意してクリニックを選べば良いか、具体的なポイントを紹介します。
専門医による正確な診断
まずは、薄毛治療に関する知識と経験が豊富な医師が在籍しているかを確認しましょう。
マイクロスコープなどで頭皮の状態を詳細に診察し、薄毛の原因を正確に診断してくれるクリニックが望ましいです。
カウンセリングで、あなたの質問や不安に丁寧に答えてくれるかも重要な判断材料です。
治療選択肢の豊富さと説明の丁寧さ
内服薬や外用薬だけでなく、注入治療など幅広い治療選択肢を提案できるクリニックを選びましょう。
それぞれの治療法のメリット・デメリット、効果、費用について、患者さんが納得できるまで分かりやすく説明してくれるかどうかも大切なポイントです。
クリニック選びのチェックポイント
| チェック項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 医師の専門性 | AGA治療の実績や経験が豊富か |
| 治療法の多様性 | 複数の治療法から適したものを提案できるか |
| 費用の透明性 | 料金体系が明確で追加費用の説明があるか |
費用体系の明確さ
AGA治療は自由診療のため、費用はクリニックによって異なります。
初診料や再診料、薬代、検査代など治療にかかる総額がどのくらいになるのか、事前に明確に提示してくれるクリニックを選びましょう。
ウェブサイトやカウンセリングで料金体系をしっかりと確認することが重要です。
通院のしやすさと継続的なサポート
治療効果を実感するには、一般的に6ヶ月以上の継続的な通院が必要です。自宅や職場からアクセスしやすく予約が取りやすいなど、無理なく通い続けられるクリニックを選びましょう。
また、治療中の経過を定期的に診察し、親身にサポートしてくれる体制が整っているかも確認しましょう。
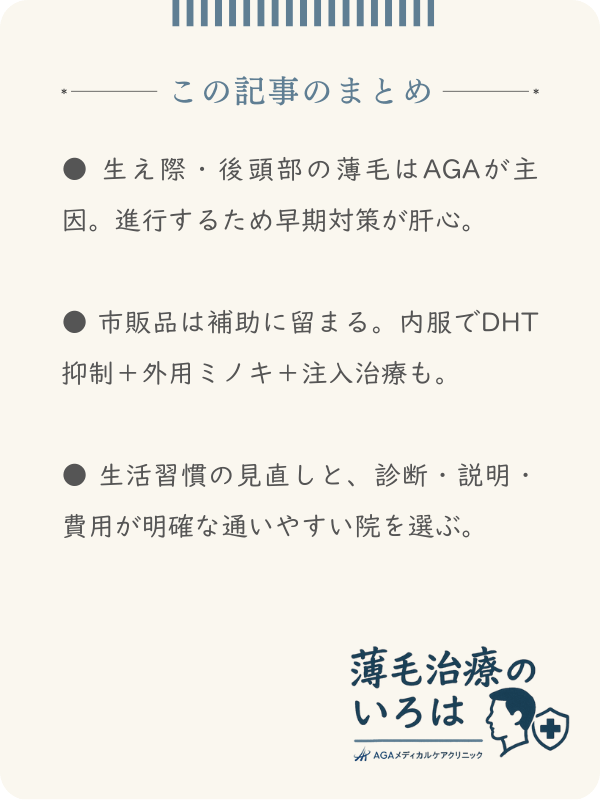
M字ハゲの原因に戻る
生え際の薄毛治療に関するQ&A
最後に、生え際の薄毛治療に関して患者様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
- 治療はどのくらいで効果が出ますか?
-
治療効果には個人差がありますが、多くの場合、治療開始から3ヶ月から6ヶ月ほどで抜け毛の減少や産毛の発生といった初期効果を実感し始めます。
目に見える形で生え際や頭頂部の改善を実感するには、1年以上の継続的な治療が必要になることが一般的です。
- 治療の費用はどのくらいかかりますか?
-
治療内容は自由診療のため、クリニックや治療内容によって費用は異なります。一般的な内服薬と外用薬による治療の場合、月々15,000円から30,000円程度が目安となります。
カウンセリングの際に、ご自身の症状に合った治療法の具体的な費用を確認してください。
- 治療薬の副作用が心配です
-
AGA治療薬には、ごく稀に性機能の低下や肝機能障害などの副作用が報告されていますが、その頻度は非常に低いです。
クリニックでは治療前に医師が副作用のリスクについて丁寧に説明し、必要に応じて血液検査を行うなど、安全に治療を進められるよう配慮します。
万が一体調に変化を感じた場合は、すぐに医師に相談してください。
- 治療をやめると元に戻りますか?
-
AGAは進行性のため、治療を完全にやめてしまうと薬で抑制されていたDHTの影響が再び現れ、薄毛の状態にゆっくりと戻っていきます。
ただし、医師と相談の上で症状が改善した後に薬の量を減らしたり、維持療法に切り替えたりすることは可能です。
自己判断で中断せず、必ず医師に相談してください。
以上
参考文献
OURA, Hajimu, et al. Adenosine increases anagen hair growth and thick hairs in Japanese women with female pattern hair loss: a pilot, double‐blind, randomized, placebo‐controlled trial. The Journal of dermatology, 2008, 35.12: 763-767.
NAGASAWA, Azumi, et al. t-Flavanone improves the male pattern of hair loss by enhancing hair-anchoring strength: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Dermatology and Therapy, 2016, 6.1: 59-68.
TANAKA, Yohei, et al. Androgenetic alopecia treatment in Asian men. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.7: 32.
LULIC, Zrinka, et al. Understanding patient and physician perceptions of male androgenetic alopecia treatments in Asia–Pacific and Latin America. The Journal of Dermatology, 2017, 44.8: 892-902.
YOSHITAKE, Toshihiro, et al. Five‐year efficacy of finasteride in 801 Japanese men with androgenetic alopecia. The Journal of Dermatology, 2015, 42.7: 735-738.
SATO, Akio; TAKEDA, Akira. Evaluation of efficacy and safety of finasteride 1 mg in 3177 Japanese men with androgenetic alopecia. The Journal of dermatology, 2012, 39.1: 27-32.