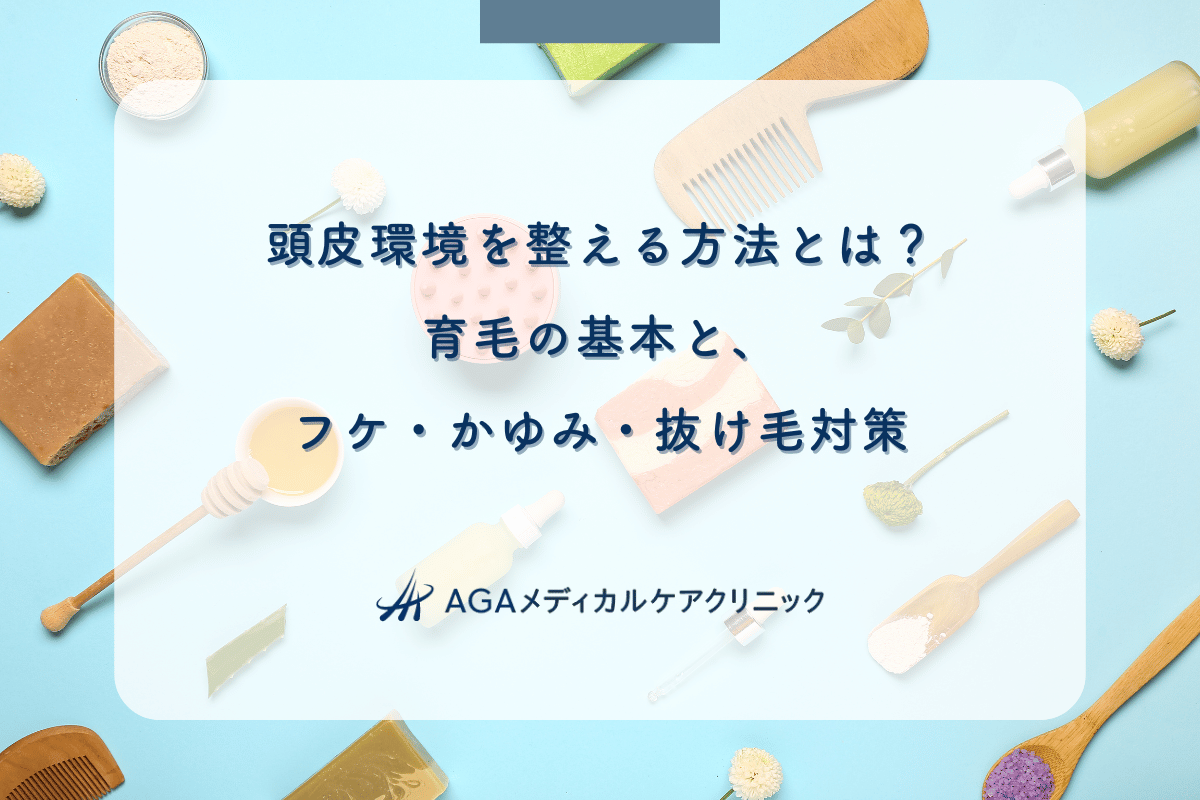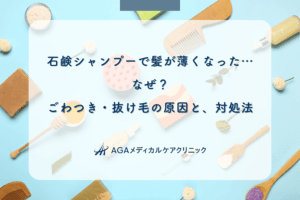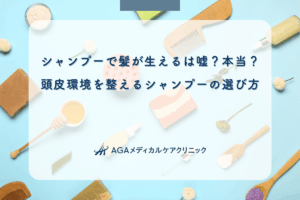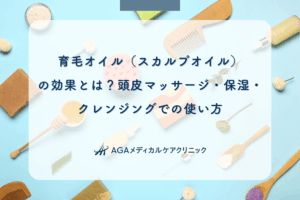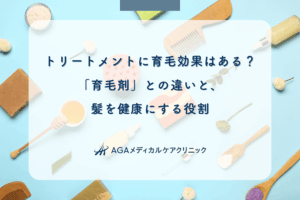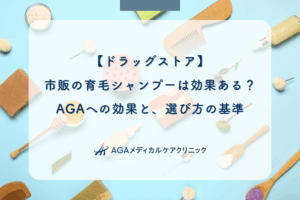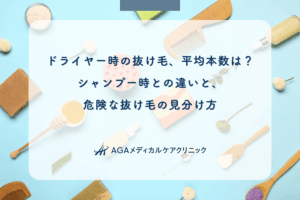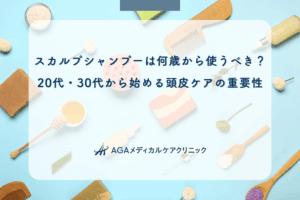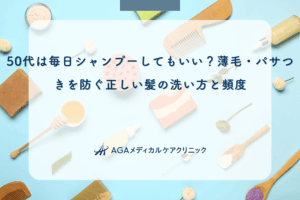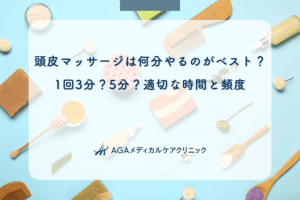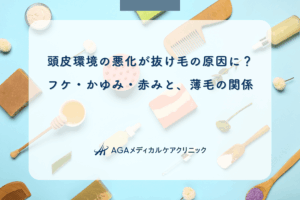フケやかゆみ、抜け毛の増加、頭皮のべたつき。これらの悩みは、多くの場合「頭皮環境の乱れ」が原因で起こります。健やかな髪は、健康な頭皮という土壌から育ちます。
育毛を考える上で、まず頭皮環境を整えることは最も重要な基本です。
この記事では、なぜ頭皮環境が乱れるのか、その原因を掘り下げるとともに、毎日のシャンプー方法から食生活、生活習慣の見直しまで、頭皮環境を整えるための具体的な対策を詳しく解説します。
育毛の第一歩を踏み出し、自信の持てる頭皮を目指しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
頭皮環境の悪化が引き起こすサインとは
頭皮は非常にデリケートな部分であり、体調や外部からの刺激によってその状態は日々変化します。頭皮環境が悪化すると、単に不快なだけでなく、髪の毛の健康にも直接的な影響を与えます。
育毛を考えるなら、まずは頭皮が発している危険信号を見逃さないことが重要です。ここでは、頭皮環境の悪化を示す代表的なサインについて解説します。
フケ・かゆみは頭皮の悲鳴
フケやかゆみは、頭皮環境悪化の最も分かりやすい初期症状の一つです。フケには、乾燥によるカサカサしたものと、皮脂の過剰分泌によるベタベタしたものの2種類があります。
乾燥性のフケは、頭皮の水分不足や洗浄力の強すぎるシャンプーが原因で、頭皮のバリア機能が低下しているサインです。
一方、脂性のフケは、過剰な皮脂をエサにマラセチア菌などの常在菌が異常増殖し、その代謝物が頭皮を刺激して発生します。
どちらのタイプも、頭皮のターンオーバー(生まれ変わり)が乱れている証拠であり、放置すると炎症を引き起こし、かゆみを伴うようになります。
抜け毛・薄毛の進行
頭皮環境の悪化は、抜け毛の増加や薄毛の進行に直結します。例えば、過剰な皮脂や古い角質が毛穴に詰まると、髪の毛の正常な成長を妨げます。
また、毛穴周辺で炎症が起きると、毛根部にある毛母細胞の働きが弱まり、髪が十分に成長する前に抜けてしまう「ヘアサイクルの乱れ」を引き起こします。
さらに、頭皮の血行不良は、髪の成長に必要な栄養素が毛根に届きにくくなる大きな原因です。
頭皮が硬くなったり、色が赤っぽくなったりしている場合は、血行不良や炎症が起きている可能性があり、抜け毛のリスクが高まっている状態と考えましょう。
頭皮環境と抜け毛について詳しく見る
頭皮環境の悪化が抜け毛の原因に?フケ・かゆみ・赤みと、薄毛の関係
べたつきと嫌な臭い
洗髪して間もないのに頭皮がべたついたり、頭から嫌な臭いがしたりするのも、頭皮環境が乱れているサインです。主な原因は皮脂の過剰分泌です。
皮脂は本来、頭皮を乾燥や外部刺激から守るバリアの役割を果たしますが、ホルモンバランスの乱れ、脂質の多い食事、ストレスなどが原因で過剰に分泌されることがあります。
この過剰な皮脂が毛穴に詰まったり、空気中の酸素に触れて酸化したり、雑菌によって分解されたりすることで、特有の脂っぽい臭い(酸化臭)が発生します。
べたつきは毛穴詰まりによる炎症や抜け毛の原因にもなるため、注意が必要です。
頭皮タイプ別チェック
| 頭皮タイプ | 主な特徴 | 起こりやすいトラブル |
|---|---|---|
| 乾燥肌 | 洗髪後につっぱり感があり、カサカサした細かいフケが出やすい。 | かゆみ、乾燥性フケ、バリア機能低下による刺激感。 |
| 脂性肌(オイリー肌) | 日中になると頭皮や髪がべたつく。湿った大きめのフケが出やすい。 | べたつき、臭い、毛穴詰まり、脂漏性皮膚炎、脂性フケ。 |
| 混合肌 | Tゾーンはべたつくが頬は乾燥するなど、場所によって状態が違う。頭皮も同様の傾向がある。 | フケとかゆみ、部分的なべたつきと乾燥の混在。 |
乾燥とつっぱり感
べたつきとは対照的に、頭皮が常に乾燥してつっぱった感じがするのも問題です。これは頭皮の水分保持能力と皮脂の分泌量が低下している状態(乾燥肌)を示します。
エアコンによる空気の乾燥、熱いお湯での洗髪、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用などが原因となります。頭皮が乾燥すると、外部からの刺激を守るバリア機能が著しく低下します。
その結果、わずかな刺激にも敏感に反応してかゆみが出たり、バリア機能を補おうとして逆に皮脂が過剰に分泌されたりすることもあります。
カサカサしたフケは、この乾燥が原因であることが多いです。
なぜ頭皮環境は乱れるのか?主な原因を探る
健やかな頭皮環境は、さまざまな要因のバランスの上に成り立っています。このバランスが崩れると、前述のようなトラブルが発生します。
育毛ケアを正しく行うためには、まず自分の頭皮環境がなぜ乱れてしまったのか、その根本的な原因を知ることが重要です。ここでは、日常生活に潜む主な原因を詳しく見ていきます。
間違ったヘアケア習慣
良かれと思って行っている日々のヘアケアが、実は頭皮にダメージを与えているケースは少なくありません。特にシャンプーの方法は影響が大きいです。
洗浄力が強すぎるシャンプーは、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥やバリア機能の低下を招きます。
逆に、皮脂が多いからと一日に何度もシャンプーをすると、頭皮が皮脂不足を感じ取り、かえって皮脂分泌を活発化させてしまうこともあります。
また、爪を立ててゴシゴシ洗う行為は、頭皮を傷つけ炎症の原因となります。シャンプー剤やコンディショナーのすすぎ残しは、毛穴詰まりやかゆみを引き起こす代表的な原因です。
シャンプー時の一般的な誤り
- 熱すぎるお湯(40度以上)での洗髪
- シャンプー剤を直接頭皮につけて泡立てる
- 指の腹ではなく爪を立てて洗う
- すすぎが不十分で生え際や耳の後ろに泡が残る
- コンディショナーを地肌につける
- 洗髪後、濡れたまま長時間放置する
コンディショナーについて詳しく見る
コンディショナーでハゲるは嘘?本当?頭皮への影響と、薄毛を防ぐ正しい使い方
食生活の乱れと栄養不足
髪は「血余(けつよ)」とも呼ばれるように、体内の栄養状態が最後に反映される場所です。食生活の乱れは、頭皮環境に深刻な影響を与えます。
特に、脂質の多い揚げ物やジャンクフード、糖分の多いお菓子やジュースの過剰摂取は、皮脂の分泌を促進し、頭皮をべたつかせます。
一方で、極端なダイエットなどによる栄養不足は、髪の毛の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足し、髪が細くなったり、頭皮の健康を維持できなくなったりします。
健やかな髪と頭皮を育てるには、バランスの取れた食事が欠かせません。
ストレスと睡眠不足の影響
精神的なストレスや慢性的な睡眠不足も、頭皮環境を悪化させる大きな要因です。強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位になります。
これにより血管が収縮し、頭皮の血行が悪化します。血行不良になると、毛根にある毛母細胞へ十分な酸素や栄養が供給されなくなり、髪の成長が妨げられます。
また、ストレスはホルモンバランスを乱し、皮脂の過剰分泌を引き起こすこともあります。睡眠中は、髪の成長に欠かせない「成長ホルモン」が分泌されるゴールデンタイムです。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低かったりすると、頭皮や髪のダメージが修復されず、環境の悪化につながります。
睡眠不足が頭皮に与える影響
| 影響 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 成長ホルモンの分泌減少 | 髪の毛の成長や頭皮細胞の修復が妨げられる。 |
| 自律神経の乱れ | 血行不良や皮脂の過剰分泌につながる。 |
| 免疫力の低下 | 頭皮のバリア機能が弱まり、炎症や常在菌の増殖を招きやすくなる。 |
加齢やホルモンバランスの変化
年齢を重ねることも、頭皮環境が変化する避けられない要因の一つです。加齢に伴い、体内の水分保持能力が低下するため、頭皮も乾燥しやすくなります。
また、血行も悪くなりがちで、栄養が届きにくくなります。
特に男性の場合、男性ホルモン(テストステロン)が特定の酵素と結びついてジヒドロテストステロン(DHT)に変化することが、AGA(男性型脱毛症)の主な原因となります。
このDHTは、皮脂腺を刺激して皮脂の分泌を過剰にさせたり、ヘアサイクルを短縮させたりするため、頭皮環境の悪化と薄毛を同時に進行させる要因となります。
育毛の第一歩は頭皮環境の改善から
抜け毛や薄毛が気になると、すぐに「髪を生やす」ことばかりに意識が向きがちですが、その前にやるべきことがあります。それが「頭皮環境を整える」ことです。
どんなに高価な育毛剤を使用しても、その土台である頭皮が健康でなければ、十分な効果は期待できません。育毛の成功は、頭皮環境の改善から始まります。
頭皮は髪の毛が育つ土壌
髪の毛を植物に例えるなら、頭皮は畑の「土壌」です。硬く乾燥した土壌や、栄養がなくジメジメとした土壌では、立派な作物が育たないのと同じように、不健康な頭皮からは健やかな髪は育ちません。
フケやかゆみ、炎症がある頭皮は、いわば「荒れた畑」です。育毛とは、まずこの土壌を耕し、柔らかく、栄養豊かな状態に戻すことから始める必要があります。
頭皮環境を整えることは、育毛剤などの「肥料」が効きやすい状態を作るための準備作業とも言えます。
血行促進が鍵
髪の毛は、毛根の底にある「毛乳頭」が毛細血管から栄養素と酸素を受け取り、それを「毛母細胞」に渡すことで成長します。つまり、頭皮の血行こそが、髪の成長の生命線です。
頭皮環境が悪化し、頭皮が硬くなったり、ストレスで血管が収縮したりすると、この栄養供給ルートが細くなります。その結果、髪は十分に成長できず、細く弱々しくなり、やがて抜け落ちてしまいます。
頭皮環境を整える上で、頭皮を柔らかく保ち、血流をスムーズにすることは非常に重要な目的の一つです。
毛穴の詰まりと炎症を防ぐ
頭皮の毛穴は、髪の毛の出口であると同時に、皮脂の出口でもあります。皮脂が過剰に分泌されたり、シャンプーのすすぎ残しがあったり、古い角質が溜まったりすると、毛穴は簡単に詰まってしまいます。
毛穴が詰まると、皮脂が内部に溜まり、それをエサに雑菌が繁殖して炎症(毛嚢炎)を引き起こすことがあります。
この炎症は、かゆみや痛みを伴うだけでなく、毛根そのものにダメージを与え、髪の成長を直接的に妨げる原因となります。
健康な髪を育てるためには、毛穴を常に清潔に保ち、炎症のないクリーンな状態を維持することが求められます。
頭皮環境改善の基本について詳しく見る
「スカルプ」とはどこのこと?髪の土台「頭皮」を健やかに保つスカルプケアの基本
頭皮環境を整える日々のシャンプー術
頭皮環境を整えるために、今日からすぐに実践できる最も効果的な対策が「毎日のシャンプー」の見直しです。シャンプーは単に髪の汚れを落とすためだけのものではありません。
「頭皮の汚れを適切に落とし、健やかな状態に保つ」ことが最大の目的です。正しい知識を身につけ、頭皮をいたわるシャンプー術を習慣にしましょう。
自分に合ったシャンプー剤の選び方
シャンプー選びは頭皮環境改善の第一歩です。自分の頭皮タイプに合わないものを使うと、かえって状態を悪化させます。
例えば、乾燥肌の人が洗浄力の強い「高級アルコール系」のシャンプーを使うと、必要な皮脂まで奪われてさらに乾燥が進みます。
逆に、脂性肌の人が洗浄力のマイルドすぎるシャンプーを使うと、皮脂を落としきれず毛穴詰まりの原因になります。
育毛を考える男性には、頭皮への刺激が少なく、適度な洗浄力と保湿力を持つ「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を主としたシャンプーがおすすめです。
主なシャンプー洗浄成分の種類
| 洗浄成分の種類 | 特徴 | おすすめの頭皮タイプ |
|---|---|---|
| アミノ酸系 | 洗浄力がマイルドで低刺激。保湿性が高い。泡立ちは控えめ。 | 乾燥肌、敏感肌、軽度の脂性肌、育毛ケア中の方。 |
| 高級アルコール系 | 洗浄力が非常に高く、泡立ちが良い。洗い上がりがさっぱりする。 | 脂性肌(皮脂が非常に多い場合)、健康な頭皮。 |
| 石けん系 | 洗浄力は強い。天然由来だがアルカリ性のため、髪がきしみやすい。 | 脂性肌(肌が強く、さっぱり感を重視する方)。 |
正しい髪の洗い方とすすぎの重要性
シャンプー剤を選んだら、次は洗い方です。正しい洗い方をマスターすることで、頭皮への負担を最小限にし、汚れだけを効果的に落とすことができます。
ポイントは「頭皮を洗う」意識を持つことです。髪の毛自体の汚れは、泡が通過するだけで十分に落ちます。
正しい洗髪の手順
1.ブラッシング
シャンプー前に、乾いた状態で髪のもつれを解き、ホコリや大まかな汚れを浮かせます。頭皮への適度な刺激が血行促進にもつながります。
2.予洗い
シャンプー剤をつける前に、38度程度のぬるま湯で頭皮と髪を1分から2分ほどしっかりと濡らします。これだけで、汚れの7割程度は落ちると言われています。
3.泡立て
シャンプー剤は適量を手のひらに取り、少量のお湯を加えながら両手でしっかりと泡立てます。泡立てネットを使うのも良い方法です。
泡立てることで、頭皮全体に均一に洗浄成分を行き渡らせ、摩擦を減らします。
4.頭皮を洗う
泡立てたシャンプーを頭皮の数カ所(側頭部、頭頂部、後頭部など)につけ、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。決して爪を立ててはいけません。
頭皮全体を動かすイメージで、毛穴の汚れを揉み出すように洗いましょう。
5.すすぎ
洗う時間よりも長く、3分以上を目安に時間をかけて丁寧にすすぎます。特に、生え際、耳の後ろ、襟足などはシャンプー剤が残りやすい部分なので、意識してしっかりと洗い流します。
すすぎ残しは、フケやかゆみの最大の原因の一つです。
洗浄後の保湿ケア
シャンプー後の頭皮は、汚れと共に必要な皮脂もある程度失われ、乾燥しやすい状態になっています。顔を洗った後に化粧水をつけるのと同じように、頭皮にも保湿ケアが必要です。
乾燥肌の人はもちろん、脂性肌の人も、頭皮が乾燥するとかえって皮脂が過剰に分泌されることがあるため、保湿は重要です。
頭皮専用のローションや、保湿成分が含まれた育毛剤を使用して、頭皮にうるおいを与え、バリア機能をサポートしましょう。
頭皮の保湿や毛穴のクレンジングを重視するときは、シャンプー前のホホバオイルを使用した頭皮マッサージもおすすめです。
ホホバオイルについて詳しく見る
ホホバオイルは頭皮の乾燥・フケ・かゆみに効く?保湿とマッサージの効果
髪の乾かし方にも注意
洗髪後、髪を濡れたまま放置するのは厳禁です。濡れた頭皮は雑菌が繁殖しやすく、臭いやかゆみの原因となります。また、髪のキューティクルが開いたままになり、ダメージを受けやすくなります。
まずは清潔なタオルで、ゴシゴシこすらずに、頭皮の水分を優しく押さえるように拭き取ります(タオルドライ)。
その後、ドライヤーを使って乾かします。ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、一箇所に熱が集中しないように小刻みに動かしながら、まずは根元(頭皮)から乾かしていきます。
全体が8割方乾いたら、冷風に切り替えて頭皮をクールダウンさせると、毛穴が引き締まり、乾燥しすぎるのを防げます。
内側から整える食生活と栄養素
頭皮環境は、体の内側の状態を映し出す鏡です。毎日のシャンプーで外側からケアすることも大切ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、食生活による内側からのケアです。
健やかな髪と頭皮は、私たちが食べたものから作られています。育毛の基本として、食生活を見直しましょう。
髪の成長に必要な栄養素
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。したがって、良質なタンパク質の摂取は不可欠です。しかし、タンパク質だけを摂取しても、それだけでは髪にはなりません。
摂取したタンパク質をアミノ酸に分解し、ケラチンに再合成する際には、ビタミンやミネラルが補酵素として働きます。
特に「亜鉛」はケラチンの合成に深く関わり、「ビタミンB群」は頭皮の代謝を促進し、皮脂の分泌をコントロールする上で重要な役割を果たします。
頭皮と髪の健康に役立つ栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンを作る材料となる。 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品(豆腐・納豆)、乳製品。 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成(ケラチンの生成)を助ける。細胞分裂を促進する。 | 牡蠣、レバー(豚・牛)、牛肉(赤身)、チーズ、アーモンド。 |
| ビタミンB群 (B2, B6) | 頭皮の皮脂分泌を調整し、代謝(ターンオーバー)を正常に保つ。 | レバー、豚肉、マグロ、カツオ、バナナ、玄米、納豆。 |
| ビタミンA, C, E | 血行を促進し(E)、頭皮の酸化を防ぎ(A,C,E)、コラーゲン生成を助ける(C)。 | 緑黄色野菜(人参、ほうれん草)、果物、ナッツ類、植物油。 |
頭皮の健康をサポートする食品
上記の栄養素をバランスよく摂取することが基本です。特に、タンパク質は毎食取り入れることを意識しましょう。
動物性タンパク質(肉、魚、卵)と植物性タンパク質(大豆製品)を偏りなく食べることが理想です。また、亜鉛は吸収率があまり高くないため、意識的に摂取する必要があります。
ビタミン類は、血行促進や抗酸化作用により、頭皮の老化を防ぎ、健康な状態を維持するのに役立ちます。
特定の食品ばかりを食べるのではなく、多様な食材を組み合わせることが、頭皮環境を整える近道です。
避けるべき食習慣
頭皮環境を悪化させる食習慣も存在します。最も注意すべきは、脂質と糖質の過剰摂取です。
フライドポテトや唐揚げなどの揚げ物、スナック菓子、動物性脂肪(バターやラード)の多い食事は、血液をドロドロにし、皮脂の分泌を過剰にします。
また、甘いお菓子や清涼飲料水に含まれる糖質も、体内で中性脂肪に変わりやすく、皮脂の原料となります。
アルコールの過剰摂取は、体内で分解される際にビタミンB群を大量に消費してしまうため、頭皮の代謝異常を招く可能性があります。
刺激の強い香辛料なども、摂りすぎると頭皮を刺激し、かゆみの原因となることがあるため注意しましょう。
生活習慣の見直しで頭皮を健やかに
シャンプーや食事と同様に、日々の生活リズムそのものが頭皮環境に大きな影響を与えます。
睡眠、ストレス管理、運動といった基本的な生活習慣を整えることは、自律神経やホルモンバランスを安定させ、結果として頭皮環境の改善につながる重要な土台作りです。
質の高い睡眠を確保する
睡眠は、単なる休息ではありません。日中に受けた頭皮や髪のダメージを修復し、髪を成長させるための大切な時間です。特に、入眠後から数時間の深い眠りの間に「成長ホルモン」が最も多く分泌されます。
この成長ホルモンが、毛母細胞の分裂を促し、頭皮のターンオーバーを正常化します。慢性的な睡眠不足や、眠りが浅い状態が続くと、この修復・成長の時間が奪われ、頭皮環境は悪化の一途をたどります。
毎日6時間から7時間の十分な睡眠時間を確保するとともに、就寝前のスマートフォン操作を控える、リラックスできる環境を整えるなど、睡眠の「質」を高める工夫も重要です。
上手なストレス発散法
現代社会においてストレスをゼロにすることは困難ですが、溜め込まないように上手に発散することは可能です。過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、頭皮の血管を収縮させて血行不良を引き起こします。
また、男性ホルモンの分泌に影響を与え、皮脂の過剰分泌や抜け毛を促進させる可能性もあります。自分に合ったストレス発散法を見つけることが大切です。
趣味に没頭する時間を作る、軽い運動で汗を流す、友人と話す、ゆっくりと入浴するなど、心身ともにリラックスできる時間を持つことを意識しましょう。
適度な運動と血行促進
デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、全身の血行が悪くなりがちです。
特に、心臓から遠い頭部は、血行不良の影響を受けやすい場所です。適度な運動は、全身の血流を改善し、頭皮の隅々まで栄養を届けるための最も効果的な方法の一つです。
激しい運動である必要はありません。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの有酸素運動を週に数回、習慣的に行うだけでも、血行促進やストレス発散に大きな効果が期待できます。
日常生活の中でエスカレーターではなく階段を使うなど、こまめに体を動かす意識も大切です。
日常生活でできる簡単な血行促進法
| 方法 | ポイント | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 頭皮マッサージ | シャンプー時や育毛剤塗布時に、指の腹で頭皮全体を優しく動かす。 | 頭皮の血流を直接的に促し、頭皮を柔らかくする。リラックス効果。 |
| 入浴(湯船に浸かる) | 38度から40度のぬるめのお湯に15分程度浸かり、体を芯から温める。 | 全身の血管が拡張し、血行が改善する。リラックスによるストレス緩和。 |
| 軽いストレッチ | 特に首や肩周りの筋肉をほぐす。デスクワークの合間に行う。 | 首のコリを解消し、頭部への血流をスムーズにする。 |
紫外線対策の重要性
顔の数倍もの紫外線を浴びていると言われる頭皮。紫外線対策は見落とされがちですが、頭皮環境を守る上で非常に重要です。
紫外線は頭皮を乾燥させるだけでなく、活性酸素を発生させて頭皮の細胞を酸化させ(光老化)、炎症やバリア機能の低下を引き起こします。
また、毛母細胞に直接ダメージを与え、抜け毛や白髪の原因になるとも考えられています。
特に日差しの強い季節や、屋外での活動時間が長い日は、帽子をかぶる、日傘を使う、頭皮用の日焼け止めスプレーを利用するなどして、頭皮を紫外線から守る意識を持ちましょう。
頭皮環境をサポートする育毛剤の活用
シャンプー、食事、生活習慣の見直しといった「守り」のケアで土台を整えたら、次は「攻め」のケアとして育毛剤の活用を検討しましょう。
育毛剤は、頭皮環境をより良い状態に導き、抜け毛の予防や健やかな髪の成長をサポートするための有効成分を含んでいます。自分の頭皮の悩みに合ったものを選ぶことが重要です。
育毛剤の役割と目的
育毛剤の主な役割は、すでに生えている髪の毛を健康に育て、抜け毛を防ぐことです。
また、頭皮の血行を促進したり、炎症を抑えたり、皮脂のバランスを整えたりすることで、「頭皮環境を改善する」ことが大きな目的です。
毛母細胞の働きを活性化させ、ヘアサイクルを正常に近づけることで、髪が太く、長く成長するのを助けます。
医薬品である「発毛剤」とは異なり、医薬部外品である「育毛剤」は、主に予防や現状維持、頭皮環境の改善を目的としています。
育毛剤の選び方のポイント
育毛剤にはさまざまな種類があり、含まれる有効成分も異なります。自分の頭皮の悩みに合わせて選ぶことが大切です。
例えば、頭皮の血行不良が気になるなら「血行促進成分(センブリエキスなど)」、フケやかゆみが悩みなら「抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)」、頭皮のべたつきが気になるなら「皮脂分泌抑制成分」、乾燥が気になるなら「保湿成分」が配合されているものを選ぶと良いでしょう。
また、アルコール(エタノール)の配合量が多いものは、清涼感がある一方で、敏感肌の人には刺激になることもあるため注意が必要です。
育毛剤の主な有効成分と目的
| 成分カテゴリ | 主な成分例 | 期待される主な働き |
|---|---|---|
| 血行促進成分 | センブリエキス、ビタミンE誘導体、ニコチン酸アミド | 頭皮の毛細血管を拡張し、血流を改善。毛根への栄養供給を促す。 |
| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸ジカリウム(2K)、アラントイン | フケやかゆみの原因となる頭皮の炎症を鎮め、頭皮環境を整える。 |
| 毛母細胞活性化成分 | パントテニルエチルエーテル(ビタミンB5誘導体) | 毛母細胞の働きを活性化させ、髪の成長をサポートする。 |
| 保湿成分 | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、各種植物エキス | 頭皮の乾燥を防ぎ、バリア機能を高める。 |
効果的な使い方とタイミング
育毛剤の効果を最大限に引き出すには、正しい使い方を続けることが重要です。最も効果的なタイミングは、シャンプー後で頭皮が清潔になり、血行が良くなっている時です。
髪を乾かした後(完全に乾かす前、少し湿り気がある程度が理想)、育毛剤のノズルを頭皮に直接つけ、気になる部分を中心に適量を塗布します。
塗布した後は、すぐに流したりせず、指の腹を使って頭皮全体を優しくマッサージし、成分を浸透させます。育毛剤は一度に大量に使っても効果が上がるものではありません。
毎日1回または2回、製品の推奨する使用量を守り、最低でも3ヶ月から6ヶ月は継続して使用することが、変化を感じるための鍵となります。
Q&A
- 頭皮環境が整うまでどれくらいかかりますか?
-
頭皮環境の改善にかかる期間には個人差が大きく影響します。
頭皮のターンオーバー(生まれ変わり)の周期は健康な状態で約28日とされていますが、乱れた環境が正常に戻るまでには時間がかかります。
一般的に、ヘアケアの見直しや生活習慣の改善による変化を実感し始めるまでには、早くても3ヶ月、多くの場合6ヶ月程度の継続的なケアが必要です。
すぐに結果が出ないからと諦めず、地道に正しいケアを続けることが最も重要です。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきですか?
-
育毛剤は、抜け毛や薄毛が目立ってから使うものだと思われがちですが、実際には「頭皮環境の乱れを感じ始めた時点」で使い始めるのが理想的です。
フケやかゆみが続く、頭皮がべたつく、あるいは乾燥するなど、何らかの頭皮トラブルを感じた時が、予防的なケアを開始する良いタイミングです。
育毛剤の主な目的は、今ある髪を健やかに保ち、抜け毛を予防し、頭皮環境を整えることです。問題が深刻化する前の早期ケアが、将来の髪を守ることにつながります。
- フケが止まらない場合、どうすればよいですか?
-
フケが長期間続く場合、まずはシャンプーの方法や使用しているシャンプー剤が自分の頭皮に合っているかを見直すことが基本です。
洗浄力が強すぎて乾燥を招いているか、逆に弱すぎて皮脂や汚れが落としきれていない可能性があります。
アミノ酸系などの低刺激なシャンプーに変えてみる、すすぎを今一度丁寧に行うなどを試みてください。食事で脂っこいものを控えることも有効です。
これらのセルフケアを1ヶ月ほど続けても全く改善しない場合や、かゆみや赤みが非常に強い場合は、脂漏性皮膚炎などの皮膚疾患の可能性もあるため、自己判断を続けず、専門の皮膚科医に相談することを検討してください。
- 頭皮マッサージは本当に効果がありますか?
-
頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、頭皮自体を柔らかく保つ上で効果が期待できます。頭皮が硬くなると血流が悪くなり、毛根に栄養が届きにくくなります。
マッサージによって物理的に血流を促し、毛穴に詰まった皮脂を押し出す助けにもなります。
ただし、強くこすりすぎたり、爪を立てたりすると頭皮を傷つける逆効果になるため、必ず指の腹を使って「頭皮を動かす」イメージで優しく揉みほぐすように行ってください。
リラックス効果も高いため、シャンプー時や育毛剤を塗布した後の習慣に取り入れることをおすすめします。
頭皮環境と保湿の記事
Reference
NEWTON‐FENNER, A., et al. Clear scalp, clear mind: Examining the beneficial impact of dandruff reduction on physical, emotional and social wellbeing. International journal of cosmetic science, 2025, 47.3: 466-475.
XIAO, Lei, et al. A Timosaponin B‐II containing scalp care solution for improvement of scalp hydration, dandruff reduction, and hair loss prevention: A comparative study on healthy volunteers before and after application. Journal of Cosmetic Dermatology, 2021, 20.3: 819-824.
TRÜEB, Ralph M., et al. Scalp condition impacts hair growth and retention via oxidative stress. International journal of trichology, 2018, 10.6: 262-270.
NARSHANA, M., et al. An overview of dandruff and novel formulations as a treatment strategy. Int J Pharm Sci Res, 2018, 9.2: 417-431.
DAVIS, Michael G., et al. Scalp application of antioxidants improves scalp condition and reduces hair shedding in a 24‐week randomized, double‐blind, placebo‐controlled clinical trial. International Journal of Cosmetic Science, 2021, 43: S14-S25.
SCHWARTZ, James R.; JOHNSON, Eric S.; DAWSON, Thomas L. Shampoos for normal scalp hygiene and dandruff. Cosmetic Dermatology: Products and Procedures, 2022, 165-174.
BARAK-SHINAR, Deganit; GREEN, Lawrence J. Scalp seborrheic dermatitis and dandruff therapy using a herbal and zinc pyrithione-based therapy of shampoo and scalp lotion. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2018, 11.1: 26.
SCHWARTZ, James R., et al. Incubatory environment of the scalp impacts pre‐emergent hair to affect post‐emergent hair cuticle integrity. Journal of Cosmetic Dermatology, 2018, 17.1: 105-111.
WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.