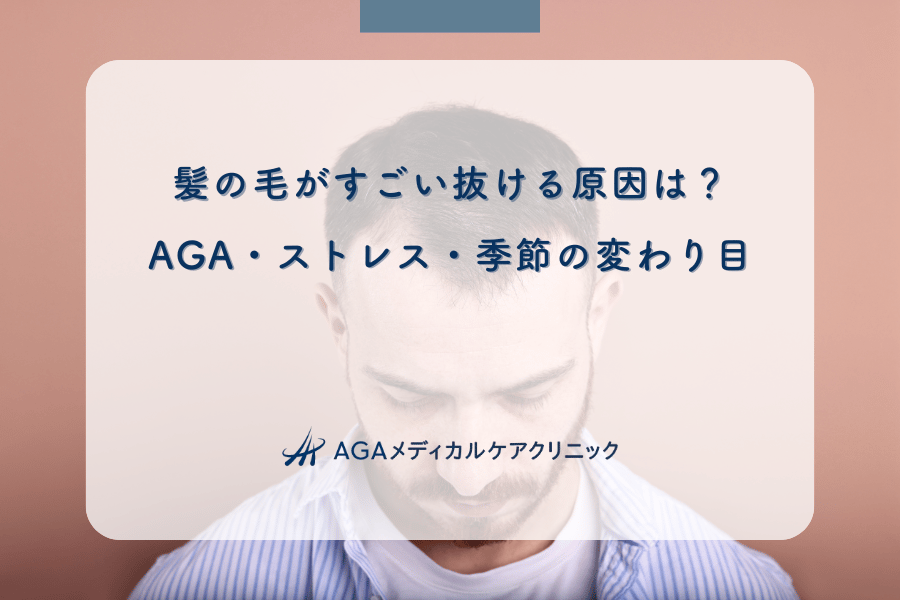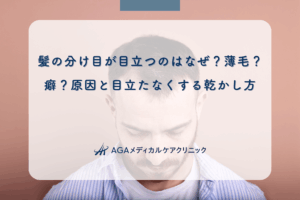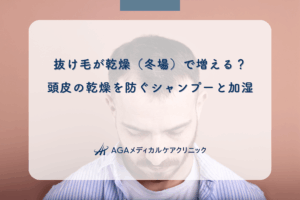お風呂の排水溝や朝起きたときの枕を見て、「最近、髪の毛がすごい抜ける」「すぐ抜けるようになった」と不安を感じていませんか。
一時的なものなら良いのですが、もし抜け毛が続くようなら、何らかのサインかもしれません。
この記事では、髪の毛がすごい抜ける主な原因として考えられるAGA(男性型脱毛症)、ストレス、季節の変わり目について詳しく解説します。
さらに、それ以外の原因や自分でできる対策、専門家への相談の目安まで、あなたの不安に寄り添いながら、親切丁寧に情報を提供します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪の毛が「すごい抜ける」と感じる目安は?
毎日ある程度の髪の毛が抜けるのは自然なことです。しかし、どの程度から「すごい抜ける」と心配すべきなのでしょうか。
まずは、正常な抜け毛と注意が必要な抜け毛の違いについて理解を深めましょう。
1日あたりの正常な抜け毛の本数
健康な成人男性であっても、1日に50本から100本程度の髪の毛は自然に抜け落ちています。
これは、髪の毛の「ヘアサイクル(毛周期)」によるものです。髪の毛は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しており、休止期に入った髪の毛が抜け落ち、新しい髪の毛が生える準備をします。
したがって、1日に100本程度の抜け毛であれば、過度に心配する必要はない場合が多いです。
危険な抜け毛の見分け方
正常な抜け毛と、何らかの原因で引き起こされている「危険な抜け毛」を見分けることは大切です。
排水溝にたまる髪の毛の量が明らかに増えた、枕につく髪の毛が目立つようになった、という主観的な感覚も重要ですが、抜けた毛の状態を観察することもヒントになります。
正常なヘアサイクルを経て抜け落ちた髪の毛は、毛根部分がふっくらと丸みを帯ていることが多いです。
一方、AGAや他の原因で抜けた髪の毛は、毛根が小さかったり、細く弱々しかったり、毛根自体が見られなかったりすることがあります。また、抜けた毛が全体的に細く短い場合も注意が必要です。
正常な抜け毛と注意が必要な抜け毛の特徴
| 特徴 | 正常な抜け毛(休止期) | 注意が必要な抜け毛 |
|---|---|---|
| 1日の本数 | 50本~100本程度 | 150本以上、または急激に増加 |
| 抜けた毛の毛根 | ふっくらと丸みがある | 細い、小さい、形がいびつ、付着物がある |
| 抜けた毛の太さ | 太く、しっかりしている | 細く、短い毛(うぶ毛のような毛)が多い |
抜け毛のセルフチェック方法
自分の抜け毛が正常範囲内かどうかを簡易的にチェックする方法があります。
例えば、朝起きたときの枕元の抜け毛を数えてみたり、シャンプーの際に指に絡みつく髪の毛や排水溝にたまる髪の毛の量を、数日間観察してみたりします。
毎日同じ条件で比較することで、抜け毛が増加傾向にあるかどうかを把握しやすくなります。「以前と比べて明らかに量が増えた」と感じる場合は、何らかの原因が隠れている可能性を考えましょう。
抜け毛が急に増える主な原因 AGA(男性型脱毛症)
男性で「髪の毛がすごい抜ける」と感じる場合、最も一般的に考えられる原因の一つがAGA(男性型脱毛症)です。
これは進行性の脱毛症であり、早期の認識と対策が重要です。
AGAとはどのような脱毛症か
AGA(AndrogeneticAlopecia)は、一般的に「男性型脱毛症」と呼ばれ、成人男性に多く見られる脱毛症です。思春期以降に発症し、徐々に進行するのが特徴です。
髪の毛が細く短くなり、最終的には生え際が後退したり、頭頂部が薄くなったりします。遺伝的な要因や男性ホルモンの影響が深く関わっていると考えられています。
AGAが進行する仕組み
AGAの主な原因物質とされるのが「DHT(ジヒドロテストステロン)」という強力な男性ホルモンです。
体内の男性ホルモン「テストステロン」が、「5αリダクターゼ」という還元酵素と結びつくことでDHTが生成されます。
このDHTが、毛根にある毛乳頭細胞の受容体と結合すると、髪の成長を抑制する信号が出され、ヘアサイクルの「成長期」が短縮されます。
その結果、髪の毛が十分に太く長く成長する前に抜け落ちてしまい、細く短い毛が増えることで薄毛が目立つようになります。
AGAの初期症状と特徴
AGAはゆっくりと進行するため、初期段階では気づきにくいこともあります。以下のような症状が見られたら、AGAの始まりを疑う必要があります。
- 生え際(特にM字部分)が後退してきた
- 頭頂部(つむじ周り)の地肌が透けて見えるようになった
- 髪の毛全体のハリやコシがなくなり、細く柔らかくなった
- 抜け毛に細く短い毛が多く混じるようになった
これらの症状は、AGAの典型的なパターンです。家族(特に父方・母方の祖父や父)に薄毛の人がいる場合、AGAを発症しやすい傾向があるとも言われています。
AGAの主な進行パターン
| パターン | 特徴 | 主な部位 |
|---|---|---|
| M字型 | 額の両サイド(そりこみ部分)から後退していく | 生え際 |
| O字型 | 頭頂部(つむじ)から円形に薄くなっていく | 頭頂部 |
| U字型(混合型) | M字型とO字型が同時に進行し、最終的に側頭部と後頭部のみ毛が残る | 生え際と頭頂部 |
自分でAGAかどうか判断できるか
AGAの進行パターンや初期症状は特徴的ですが、自分で「絶対にAGAだ」と断定することは困難です。抜け毛の原因は一つとは限らず、後述するストレスや生活習慣、他の病気が関わっている可能性もあります。
抜け毛の量や質、頭皮の状態などを総合的に判断する必要があります。もしAGAが疑われる場合は、自己判断で対策を誤る前に、皮膚科やAGA専門のクリニックで専門家の診断を受けることを推奨します。
ストレスによる抜け毛の増加とその背景
現代社会において、ストレスは多くの健康問題と関連していますが、髪の毛も例外ではありません。「髪の毛がすごい抜ける」と感じる時、精神的な負担が原因となっているケースも少なくありません。
ストレスが頭皮環境に与える影響
強いストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れます。自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があり、ストレス状態では交感神経が優位になります。
交感神経が活発になると血管が収縮し、血流が悪化します。頭皮の血流が悪くなると、髪の毛の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。
これにより、髪の成長が妨げられ、抜け毛が増加する可能性があります。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れも引き起こします。
ストレスを感じると副腎皮質から「コルチゾール」というホルモンが分泌されますが、過剰なストレスが続くとホルモンバランス全体が崩れ、頭皮環境やヘアサイクルに悪影響を与えることがあります。
ストレスが髪に与える主な影響
| ストレス要因 | 身体への影響 | 髪への影響 |
|---|---|---|
| 精神的・身体的ストレス | 自律神経の乱れ(交感神経優位) | 頭皮の血管収縮、血行不良 |
| 持続的なストレス | ホルモンバランスの乱れ | ヘアサイクルの乱れ、成長阻害 |
| ストレスによる行動 | 睡眠不足、食欲不振、暴飲暴食 | 栄養不足、頭皮環境の悪化 |
精神的ストレスと身体的ストレス
ストレスには、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みといった「精神的ストレス」だけでなく、過労、睡眠不足、怪我、手術、過度なダイエットといった「身体的ストレス」も含まれます。
身体が強い負担を感じると、生命維持に必要な臓器が優先され、髪の毛のような末端部分への栄養供給は後回しにされがちです。どちらのストレスも、長期化すれば抜け毛の原因となり得ます。
ストレス性脱毛症の種類
ストレスが直接的、あるいは間接的な引き金となって発症する脱毛症もあります。代表的なものに「円形脱毛症」があります。
これは自己免疫疾患の一種と考えられており、ストレスが発症の引き金の一つとなることがあります。突然、円形や楕円形に髪が抜けるのが特徴です。
また、「抜毛症(トリコチロマニア)」といって、無意識のうちに自分で髪の毛を引き抜いてしまう症状もあり、これも精神的なストレスが背景にあることが多いです。
季節の変わり目に抜け毛が増える理由
「秋になると抜け毛が増える」という話をよく聞くように、季節の変わり目は抜け毛が増加しやすい時期です。
これは一時的な現象である場合も多いですが、なぜ特定の季節に抜け毛が増えるのでしょうか。
特に抜け毛が増えやすい季節は
一般的に、抜け毛が最も増えやすいのは「秋」とされています。次いで「春」にも抜け毛の増加を感じる人がいます。
動物の毛が生え変わる「換毛期」のようなものが、人間にもある程度残っているという説もありますが、はっきりとした理由はまだ完全には解明されていません。
しかし、いくつかの環境要因が関わっていると考えられています。
季節変動によるホルモンバランスの影響
日照時間の変化などは、体内のホルモンバランスに微妙な影響を与える可能性があります。
例えば、男性ホルモンであるテストステロンの分泌量は、秋口に一時的に増加するという報告もあり、これがAGAの原因物質であるDHTの増加につながり、抜け毛に影響を与える可能性が指摘されています。
ただし、これはすべての人に当てはまるわけではありません。
夏の紫外線ダメージと秋の抜け毛
秋に抜け毛が増える大きな原因として、夏の間に受けたダメージの蓄積が考えられます。夏場は紫外線が非常に強く、頭皮も日焼けをします。紫外線は頭皮の細胞を傷つけ、乾燥や炎症を引き起こします。
また、毛根にある毛母細胞の働きを弱めることもあります。このダメージが数ヶ月遅れて、ヘアサイクルの乱れとして現れ、秋の抜け毛増加につながると考えられています。
冬の乾燥と頭皮への影響
冬は空気が乾燥し、暖房の使用によって室内も乾燥しがちです。頭皮が乾燥すると、バリア機能が低下し、フケやかゆみ、炎症を引き起こしやすくなります。
頭皮環境が悪化すると、健康な髪の毛が育ちにくくなり、抜け毛の原因となることがあります。春先の抜け毛は、こうした冬場の頭皮トラブルが影響している可能性もあります。
AGAやストレス以外にもある 髪が抜ける原因
抜け毛の原因はAGA、ストレス、季節性だけではありません。日々の生活習慣が大きく影響している場合や、何らかの病気が隠れている場合もあります。
栄養バランスの偏り
髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、タンパク質の摂取が不足すると、健康な髪の毛を作ることができません。
また、タンパク質をケラチンに変えるためには「亜鉛」が、頭皮の血行を良くするためには「ビタミンE」が、頭皮環境を整えるためには「ビタミンB群」が必要です。
極端なダイエットや偏った食生活は、これらの栄養素の不足を招き、抜け毛を増加させる大きな原因となります。
髪の健康に必要な主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の毛の主成分(ケラチン)を作る | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける | 牡蠣、レバー、赤身肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂分泌を調整する | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、納豆 |
睡眠不足と髪の成長
髪の毛は、私たちが寝ている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長が促されます。特に、入眠後の深いノンレム睡眠中に成長ホルモンは多く分泌されます。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が悪かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の毛の成長や頭皮の修復が十分に行われません。
結果として、ヘアサイクルが乱れ、抜け毛が増えることにつながります。
間違ったヘアケア
良かれと思って行っているヘアケアが、逆に頭皮にダメージを与えている可能性もあります。
例えば、洗浄力の強すぎるシャンプーで必要な皮脂まで洗い流してしまったり、逆に洗い残しがあって毛穴が詰まったりすること。
また、爪を立ててゴシゴシと頭皮を洗う行為は、頭皮を傷つけ炎症の原因となります。合わないヘアワックスやスプレーの使いすぎも、頭皮環境を悪化させる一因です。
病気や薬の副作用による脱毛
特定の病気が原因で脱毛が起こることもあります。例えば、甲状腺機能の異常(亢進症や低下症)は、ホルモンバランスの乱れから脱毛を引き起こすことがあります。
また、自己免疫疾患である円形脱毛症は、ストレス以外が原因の場合もあります。さらに、一部の薬(抗がん剤、特定の降圧剤など)の副作用として脱毛が見られることもあります。
AGAとは異なる急激な抜け毛や、全身の毛が抜けるような場合は、内科的な病気も疑う必要があります。
抜け毛が気になるときに自分でできる対策
「髪の毛がすごい抜ける」と感じたとき、専門家に相談する前に、まずは自分で見直せる生活習慣やヘアケアがあります。
これらを改善するだけでも、頭皮環境が整い、抜け毛の予防につながることが期待できます。
食生活の見直しと重要な栄養素
髪の毛の健康は、日々の食事から作られます。特定の食材だけを食べるのではなく、バランスの取れた食事を心がけることが最も重要です。
特に、髪の主成分である「タンパク質」、その合成を助ける「亜鉛」、頭皮環境を整える「ビタミンB群・C・E」を意識して摂取しましょう。
過度な脂質や糖分の摂取は、皮脂の過剰分泌につながり頭皮環境を悪化させる可能性があるため、控えるのが賢明です。
質の高い睡眠をとる工夫
髪の成長を促す成長ホルモンは、睡眠中に分泌されます。単に長く寝るだけでなく、「睡眠の質」を高めることが大切です。
就寝前はスマートフォンやパソコンの画面を見るのを避け、リラックスできる環境を整えましょう。寝室の温度や湿度、寝具などを見直すことも有効です。
毎日なるべく同じ時間に寝て、同じ時間に起きる規則正しい生活リズムを作るよう努めましょう。
正しいシャンプーの方法と頭皮ケア
毎日のシャンプーは、頭皮環境を清潔に保つために重要ですが、洗い方が間違っていると逆効果になります。正しいシャンプーの方法を身につけ、頭皮を健康に保ちましょう。
正しいシャンプーの基本手順
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. ブラッシング | シャンプー前に髪のもつれを解き、大きな汚れを落とす。 |
| 2. 予洗い | ぬるま湯(38度程度)で1~2分かけ、髪と頭皮をしっかり濡らし、汚れを浮かせる。 |
| 3. 泡立て | シャンプー剤を手のひらでよく泡立ててから、髪につける。 |
| 4. 洗う | 指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗う。爪を立てない。 |
| 5. すすぎ | シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて念入りにすすぐ。生え際や耳の後ろも忘れずに。 |
シャンプー後は、タオルドライで優しく水分を拭き取り、ドライヤーで早めに乾かします。濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。
育毛剤の活用と選び方
育毛剤は、今ある髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防し、頭皮環境を整えることを目的とした医薬部外品です。
AGAのように髪を生やす「発毛」を目的とした医薬品(発毛剤)とは異なりますが、頭皮環境の悪化や血行不良による抜け毛が気になる場合には、育毛剤の使用も一つの選択肢となります。
育毛剤を選ぶ際は、自分の頭皮の状態(乾燥肌か、脂性肌か)や、悩みに合った成分(血行促進成分、抗炎症成分、保湿成分など)が含まれているかを確認しましょう。
シャンプー選びのポイント
- 自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌)に合わせる
- 洗浄力が強すぎないアミノ酸系シャンプーを選ぶ
- フケやかゆみがある場合は、抗炎症成分配合のものを選ぶ
専門家への相談を考えるタイミング
セルフケアを続けても抜け毛が減らない場合や、抜け毛の状態が異常だと感じる場合は、自己判断を続けずに専門家に相談することが重要です。早期の対応が、将来の髪を守ることにつながります。
抜け毛以外にこんな症状が出たら注意
単なる抜け毛だけでなく、以下のような症状が伴う場合は、AGAや他の脱毛症、あるいは内科的な病気の可能性も考えられます。早めに専門機関を受診しましょう。
- 頭皮に強いかゆみ、痛み、フケ、湿疹がある
- 抜け毛の量が急激に、かつ大量に増えた(1日200本以上など)
- 円形や楕円形など、特定の箇所だけ集中的に抜ける
- 髪の毛だけでなく、眉毛や体毛なども抜ける
- 体調不良(倦怠感、体重の変化など)を伴う
何科を受診すればよいか
髪の毛や頭皮の悩みは、基本的には「皮膚科」が専門です。皮膚科では、頭皮の状態を診察し、必要に応じて検査を行い、脱毛の原因を診断します。
最近では、AGA治療を専門に行う「AGA専門クリニック」も増えています。AGAが強く疑われる場合(生え際の後退や頭頂部の薄毛など)は、専門クリニックに相談するのも良いでしょう。
内科的な病気が疑われる場合は、皮膚科医から適切な診療科を紹介してもらえることもあります。
受診を検討する目安
| 症状 | 相談先 |
|---|---|
| 抜け毛が急増し、細い毛が増えた | 皮膚科またはAGA専門クリニック |
| 頭皮の赤み、かゆみ、フケがひどい | 皮膚科 |
| 円形に髪が抜けた | 皮膚科 |
クリニックで行う検査や相談内容
クリニックでは、まず問診(いつから抜け毛が増えたか、生活習慣、家族歴など)を行います。その後、医師が視診や触診で頭皮や髪の状態を確認します。
マイクロスコープで頭皮や毛穴の状態を拡大して見ることもあります。
AGAの診断では、進行パターンや毛髪の状態から判断することが多いですが、他の脱毛症との鑑別が必要な場合は血液検査などを行うこともあります。
不安に思っていることや、試してきた対策などを具体的に医師に伝えることが、適切な診断と治療への第一歩です。
季節・ストレス・生活習慣に戻る
髪の毛がすごい抜ける原因に関するよくある質問
- 抜け毛は一度増えたら減らないのでしょうか?
-
原因によります。例えば、季節の変わり目や一時的なストレスによる抜け毛であれば、その原因が解消されたり、頭皮環境が改善したりすることでおさまる場合が多いです。
しかし、AGA(男性型脱毛症)の場合は進行性のため、何もしなければ抜け毛は減らず、薄毛は徐々に進行していく可能性が高いです。原因に応じた適切な対策を行うことが重要です。
- 育毛剤と発毛剤の違いは何ですか?
-
育毛剤は、現在生えている髪の毛を健康に保ち、抜け毛を予防すること(育毛・養毛)を目的とした「医薬部外品」です。主に頭皮環境を整えたり、血行を促進したりします。
一方、発毛剤は、新しい髪の毛を生やすこと(発毛)を目的とした「医薬品」です。
AGAの治療薬などに含まれる成分(ミノキシジルなど)が代表的で、医師の診断や薬剤師の説明が必要なものもあります。
- シャンプーは毎日した方がいいですか?
-
頭皮の皮脂量や生活環境(汗をかく量など)によりますが、基本的には毎日シャンプーをして、その日の汚れや余分な皮脂を落とし、頭皮を清潔に保つことを推奨します。
ただし、乾燥肌や敏感肌の方が洗浄力の強いシャンプーで洗いすぎると、必要な皮脂まで奪ってしまい逆効果になることもあります。
ご自身の頭皮タイプに合ったシャンプーを選び、優しく洗うことが大切です。
- 食事以外で栄養を補う方法はありますか?
-
バランスの取れた食事が基本ですが、忙しい現代人にとって毎日完璧な食事を摂るのは難しいかもしれません。
どうしても食事が偏りがちな場合は、サプリメントで不足しがちな栄養素(特に亜鉛やビタミンB群など)を補うことも一つの方法です。
ただし、サプリメントはあくまで補助的なものです。過剰摂取は体に負担をかけることもあるため、適切な量を守り、基本は食事から摂るよう心がけましょう。
Reference
OWECKA, Barbara, et al. The hormonal background of hair loss in non-scarring alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.
TRÜEB, Ralph M. Is androgenetic alopecia a photoaggravated dermatosis?. Dermatology, 2003, 207.4: 343-348.
SPRINGER, Karyn; BROWN, Matthew; STULBERG, Daniel L. Common hair loss disorders. American family physician, 2003, 68.1: 93-102.
OIWOH, Sebastine Oseghae, et al. Androgenetic alopecia: A review. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 2024, 31.2: 85-92.
LYAKHOVITSKY, Anna, et al. Changing spectrum of hair and scalp disorders over the last decade in a tertiary medical centre. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2023, 37.1: 184-193.
REDLER, Silke; MESSENGER, Andrew G.; BETZ, Regina C. Genetics and other factors in the aetiology of female pattern hair loss. Experimental Dermatology, 2017, 26.6: 510-517.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. The Role of Biochemical Stress in AGA/FPHL. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 249-262.
ZHAO, Jun, et al. Serum 25 hydroxyvitamin D levels in alopecia areata, female pattern hair loss, and male androgenetic alopecia in a Chinese population. Journal of Cosmetic Dermatology, 2020, 19.11: 3115-3121.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. The role of solar radiation in AGA/FPHL. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 263-271.
KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.