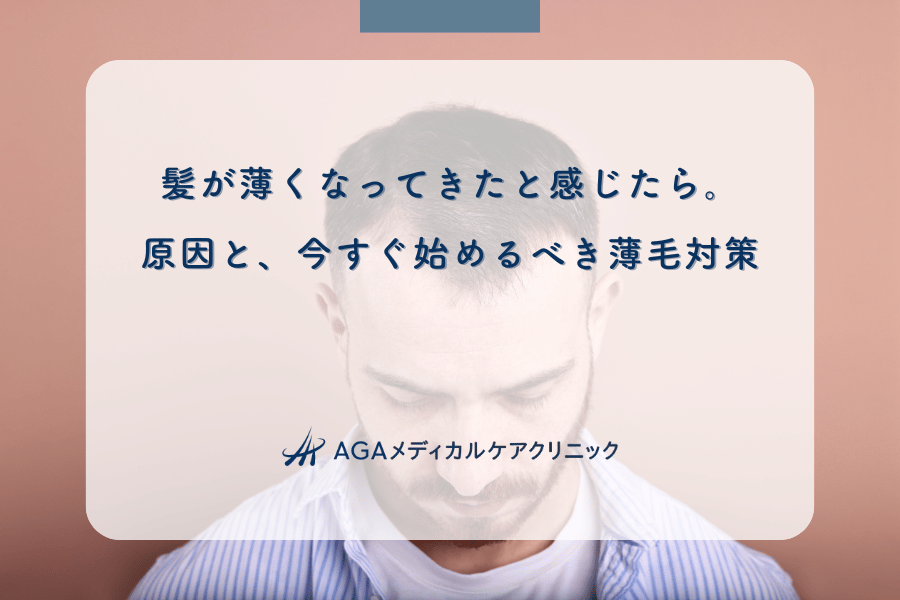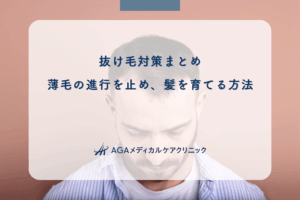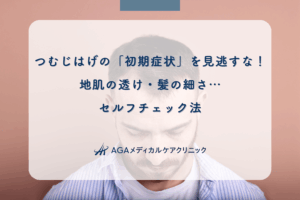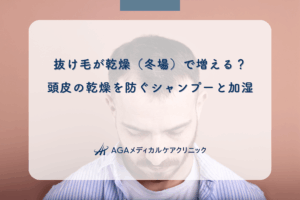「最近、枕元の抜け毛が増えた気がする」「シャンプーの時、指に絡まる髪が多くなった」「鏡を見ると、以前より地肌が目立つようになった」。
ふとした瞬間に「髪が薄くなってきた」と感じ、不安を覚えている方へ。その悩み、決して一人ではありません。髪の変化は、体からの何らかのサインかもしれません。
この記事では、なぜ髪が薄く感じるようになるのか、その主な原因を分かりやすく解説し、今日からすぐに始められる具体的な薄毛対策をご紹介します。
早期の対策が、将来の髪を守る鍵となります。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
「髪が薄くなってきた」と感じるサイン
多くの場合、「髪が薄くなってきた」という感覚は、徐々に進行する変化によってもたらされます。毎日鏡を見ていると気づきにくいものですが、特定のサインに注目することで、早期に髪の変化を察知できます。
ここでは、薄毛の初期段階で見られる主な兆候を確認しましょう。
抜け毛の増加
髪にはヘアサイクル(毛周期)があり、健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜け落ちます。
しかし、シャンプー時や朝起きた時の枕元、部屋の床などで、明らかに以前より多くの抜け毛が目につくようになった場合、注意が必要です。
特に、細く短い毛が多く抜けている場合は、ヘアサイクルが乱れている可能性があります。排水溝にたまる髪の量が急に増えたと感じたら、それは重要なサインの一つです。
髪の毛が細くなった(軟毛化)
薄毛の進行は、本数が減るだけでなく、髪の毛一本一本が細くなる「軟毛化」という現象を伴うことが多くあります。
以前と比べて髪にハリやコシがなくなり、全体的にボリュームダウンしたように感じるのは、この軟毛化が原因かもしれません。
髪を触った時の感触が柔らかく、弱々しくなったと感じる場合、髪が十分に成長しきる前に抜けてしまっている可能性があります。
地肌が透けて見える
髪全体の密度が低下すると、地肌が透けて見えるようになります。特に頭頂部(O字)や生え際(M字)は、薄毛が進行しやすい部位です。
明るい場所で鏡を見たときや、髪が濡れたときに、以前よりも地肌の白さが目立つようになったら要注意です。
他人から「頭頂部、少し薄くなってきた?」と指摘されて初めて気づくケースも少なくありません。
髪のボリュームダウンとスタイリング
髪が細くなったり、本数が減ったりすると、髪全体のボリュームが失われます。その結果、ヘアスタイルが以前のように決まらなくなります。
「セットしてもすぐに髪がペタンとしてしまう」「分け目がくっきりと目立つようになった」「つむじ周りがうまく隠せない」といったスタイリングの悩みは、髪が薄くなってきたサインである可能性が高いです。
なぜ髪は薄くなるのか?主な原因を探る
髪が薄くなる原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。遺伝的な要因から日々の生活習慣まで、様々なものが髪の健康に影響を与えます。
ここでは、男性の薄毛を引き起こす主な原因について詳しく見ていきましょう。
AGA(男性型脱毛症)の影響
男性の薄毛の最も一般的な原因が、AGA(Androgenetic Alopecia)、すなわち「男性型脱毛症」です。これは思春期以降に発症し、徐々に進行する脱毛症です。
主な原因は、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、頭皮に存在する「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力な「ジヒドロテストステロン(DHT)」に変換されることです。
このDHTが毛乳頭細胞にある受容体と結合すると、髪の成長期が短縮され、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまいます。これが軟毛化と抜け毛の増加につながります。
生活習慣の乱れ
髪の健康は、全身の健康状態と密接に関連しています。特に、食生活の乱れ、睡眠不足、運動不足といった生活習慣は、頭皮環境や髪の成長に直接的な影響を及ぼします。
髪は主にタンパク質(ケラチン)からできており、その生成には亜鉛やビタミン類も必要です。栄養バランスの偏った食事は、髪に必要な栄養素の不足を招きます。
また、睡眠中に分泌される成長ホルモンは、髪の成長と修復に重要な役割を果たします。睡眠不足は、この大切な時間を奪うことになります。
ストレスと髪の関係
精神的なストレスも、薄毛の大きな要因となります。過度なストレスを感じると、自律神経が乱れ、交感神経が優位な状態が続きます。これにより血管が収縮し、頭皮への血流が悪化します。
頭皮の血流が悪くなると、髪の毛根にある毛母細胞へ十分な酸素や栄養素が届かなくなり、髪の健やかな成長が妨げられます。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮脂の過剰分泌などを招いて頭皮環境を悪化させることもあります。
頭皮環境の悪化
髪が育つ土壌である頭皮の環境が悪化すると、健康な髪は育ちません。
間違ったシャンプーの方法(洗いすぎ、すすぎ残し)、皮脂やフケの過剰な蓄積、乾燥、紫外線によるダメージなどが、頭皮環境を悪化させる主な原因です。
頭皮に炎症やかゆみがあると、無意識にかきむしってしまい、さらに頭皮を傷つけ、抜け毛を助長するという悪循環に陥ることもあります。
清潔で潤いのある、血行の良い頭皮環境を保つことが、薄毛対策の基本となります。
AGA(男性型脱毛症)とは何か
「髪が薄くなってきた 対策」を考える上で、AGA(男性型脱毛症)についての正しい理解は欠かせません。
これは特定の病気ではなく、遺伝的背景と男性ホルモンの影響によって起こる、進行性の脱毛症です。多くの男性が悩む薄毛の、最大の原因とされています。
AGAの進行パターン
AGAによる薄毛の進行パターンには、一定の傾向が見られます。
これは「ハミルトン・ノーウッド分類」という国際的な基準で分類されることもありますが、一般的には生え際か頭頂部、あるいはその両方から薄くなるケースがほとんどです。
AGAの主な進行パターン
| パターン | 特徴 | 通称 |
|---|---|---|
| 生え際の後退 | 額の生え際が両サイドから、または中央から後退していく。 | M字型 / U字型 |
| 頭頂部の薄毛 | 頭のてっぺん(つむじ周辺)から円形に薄くなっていく。 | O字型 |
| 混合型 | 生え際の後退と頭頂部の薄毛が同時に進行していく。 | M字+O字型 |
どのパターンで進行するかは個人差がありますが、放置すると薄毛の範囲は徐々に拡大していきます。
遺伝とホルモンの関与
AGAの発症には、主に二つの要因が関わっています。「遺伝」と「男性ホルモン」です。
第一に、男性ホルモン(テストステロン)をDHT(ジヒドロテストステロン)に変換する「5αリダクターゼ」という酵素の活性度の高さは、遺伝によって決まると考えられています。
第二に、DHTを受け取る「男性ホルモン受容体(アンドロゲンレセプター)」の感受性の高さも、遺伝(特に母方の家系から受け継がれやすいX染色体上の遺伝子)によって影響されます。
つまり、「DHTが作られやすい体質」と「DHTの影響を受けやすい体質」が遺伝すると、AGAを発症しやすくなると言えます。
AGAは進行性
AGAの最も重要な特徴は、「進行性」であるという点です。一度発症すると、自然に治癒することはなく、対策を講じなければ薄毛はゆっくりと、しかし確実に進行し続けます。
髪の成長期が短縮され、休止期に留まる毛包が増えていくため、全体として髪の量が減少し続けます。
「そのうち治るだろう」「生活習慣を正せば元に戻るだろう」と楽観視していると、対策のタイミングを逃してしまう可能性があります。
自分でできるAGAセルフチェック
自分がAGAかどうかを正確に診断するのは専門のクリニックでなければできませんが、いくつかの兆候からその可能性を推測することは可能です。
以下の項目に当てはまる数が多いほど、AGAの可能性が疑われます。
- 家族(特に父方・母方の祖父や父)に薄毛の人がいる。
- 思春期以降に抜け毛が増え始めた。
- 抜け毛に、細く短い毛が多く含まれている。
- 生え際が後退してきた(M字になってきた)。
- 頭頂部(つむじ周り)の地肌が透けて見えるようになった。
- 髪のハリやコシがなくなり、細くなったと感じる。
これらのサインに気づいたら、それは「髪が薄くなってきた 対策」を本格的に開始すべき合図かもしれません。
今すぐ見直したい生活習慣
AGAが遺伝やホルモンの影響を強く受ける一方で、日々の生活習慣は髪が育つための「土壌」を整える上で非常に重要です。
不健康な生活は、AGAの進行を早めたり、AGA以外の要因による薄毛(生活習慣性の脱毛)を引き起こしたりします。
ここでは、髪の健康のために今すぐ見直すべきポイントを解説します。
栄養バランスの取れた食事
髪の毛は、私たちが食べたものから作られています。特定の食品だけを食べるのではなく、バランスの取れた食事が髪の成長を支えます。
特に、髪の主成分であるタンパク質、その合成を助ける亜鉛、頭皮の健康を保つビタミン類は重要です。
髪の成長に必要な主な栄養素と食材例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、ヘアサイクルを正常に保つ。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、ナッツ類 |
| ビタミン類 | 頭皮の血行促進(E群)、皮脂の調整(B群)、コラーゲン生成(C群)など。 | 緑黄色野菜、果物、玄米、豚肉 |
外食やインスタント食品が多い方は、意識してこれらの栄養素を食事に取り入れる工夫が必要です。
質の高い睡眠の確保
髪の毛は、私たちが眠っている間に最も成長します。睡眠中、特に深いノンレム睡眠の間に「成長ホルモン」が活発に分泌されます。
この成長ホルモンが、毛母細胞の分裂を促し、髪の成長と日中に受けたダメージの修復を行います。
睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の健やかな成長が阻害されます。
毎日6〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保し、就寝前のスマートフォン操作を控えるなど、睡眠の質を高める努力が大切です。
適度な運動の重要性
適度な運動は、全身の血行を促進します。もちろん、頭皮の血流も例外ではありません。頭皮の血流が良くなれば、髪の成長に必要な栄養素と酸素が毛根までしっかりと運ばれます。
デスクワーク中心で運動不足を感じている方は、ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、日常生活の中で無理なく続けられる運動を取り入れましょう。
また、運動はストレス解消にも役立ち、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。
喫煙と飲酒の影響
喫煙と過度な飲酒は、髪の健康にとってマイナス要因となります。これらが髪に与える影響を理解し、生活習慣を見直すことが薄毛対策につながります。
喫煙・飲酒が髪に与える主な影響
| 要因 | 髪への主な悪影響 |
|---|---|
| 喫煙 | ニコチンによる血管収縮で、頭皮の血行が悪化する。ビタミンCなどを破壊し、栄養不足を招く。 |
| 過度な飲酒 | アルコールの分解時に、髪に必要なアミノ酸やビタミンB群が大量に消費される。肝臓に負担がかかり、タンパク質の合成能力が低下する。 |
タバコは「百害あって一利なし」です。禁煙を目指すことが最も望ましい対策です。
飲酒については、適量を守り、休肝日を設けるなど、体に負担をかけない楽しみ方を心がけましょう。
自宅でできる頭皮ケアと薄毛対策
専門的な治療と並行して、あるいはその第一歩として、自宅で毎日行う頭皮ケアは薄毛対策の基本です。
間違ったケアはかえって頭皮環境を悪化させる可能性もあるため、正しい知識を身につけ、実践することが重要です。
ここでは、今日から始められる具体的なセルフケア方法を紹介します。
正しいシャンプーの方法
シャンプーの目的は、髪の汚れではなく、頭皮の余分な皮脂や汚れを落とすことです。洗いすぎは頭皮を乾燥させ、逆に皮脂の過剰分泌を招くこともあります。
正しいシャンプーの手順
- ぬるま湯(38度前後)で髪と頭皮を予洗いする。
- シャンプーを手のひらで泡立て、髪ではなく頭皮につける。
- 指の腹を使い、頭皮をマッサージするように優しく洗う。
- すすぎ残しがないよう、時間をかけてしっかりと洗い流す。
特に生え際や襟足は泡が残りやすいため、意識してすすぎましょう。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つける原因になるため厳禁です。
頭皮マッサージのやり方
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進するのに役立ちます。シャンプー中や、育毛剤を塗布した後に行うのが効果的です。リラックスした状態で、指の腹を使って行います。
まず、両手の指の腹で側頭部(耳の上あたり)をつかみ、円を描くようにゆっくりと揉みほぐします。次に、生え際から頭頂部に向かって、頭皮全体をゆっくりと引き上げるように動かします。
最後に、頭頂部にある「百会(ひゃくえ)」というツボを、心地よい強さで数秒間押します。力を入れすぎず、頭皮を擦るのではなく「動かす」意識で行うのがコツです。
育毛剤の選び方と使い方
「髪が薄くなってきた 対策」として育毛剤の使用を検討する方も多いでしょう。
育毛剤は、主に「今ある髪を健康に育てる」「抜け毛を防ぐ」ことを目的とし、頭皮環境を整える成分が含まれています。
育毛剤の主な有効成分と期待される働き
| 成分カテゴリ | 期待される働き | 代表的な成分例 |
|---|---|---|
| 血行促進成分 | 頭皮の血流を良くし、毛根へ栄養を届ける。 | センブリエキス、ビタミンE誘導体 |
| 抗炎症成分 | 頭皮の炎症やフケ、かゆみを抑え、環境を整える。 | グリチルリチン酸ジカリウム |
| 毛母細胞活性化成分 | 毛母細胞の働きをサポートし、発毛を促す。 | t-フラバノン、アデノシン(一部製品) |
育毛剤は、髪が乾いた状態(洗髪後ならタオルドライでしっかり水分を拭き取った後)で使用します。ノズルを直接頭皮につけ、気になる部分を中心に塗布し、指の腹で優しく揉み込むようにマッサージします。
製品に記載されている用法・用量を守り、毎日継続して使用することが大切です。
市販の対策商品の種類
育毛剤のほかにも、市販されている薄毛対策商品は多様化しています。
例えば、頭皮の皮脂や汚れをしっかり落とすことを目的とした「スカルプシャンプー」や、髪にハリ・コシを与えてボリュームアップして見せる「コンディショナー」などがあります。
これらは直接的に髪を生やすものではありませんが、育毛剤の効果を高めるための土台作りや、見た目の印象を改善するために役立ちます。
自分の頭皮の状態(乾燥肌、脂性肌など)や悩みに合わせて、適切な商品を選びましょう。
育毛剤と発毛剤の違い
薄毛対策を始めようとするとき、多くの人が「育毛剤」と「発毛剤」の違いで悩みます。この二つは目的も成分も、そして法的な分類も異なります。
「髪が薄くなってきた 対策」としてどちらが自分に適しているのかを判断するために、その違いを正確に理解しておくことが重要です。
目的と効果の違い
二つの製品の最大の違いは、その「目的」です。育毛剤は、今生えている髪の毛を健康に育て、抜け毛を予防し、頭皮環境を整えることを目的としています。
一方、発毛剤は、毛母細胞に働きかけて、新しい髪の毛を生やし、細くなった髪を太く育てる(発毛・育毛)ことを目的としています。
育毛剤と発毛剤の比較
| 項目 | 育毛剤 | 発毛剤 |
|---|---|---|
| 分類 | 医薬部外品(または化粧品) | 第1類医薬品 |
| 主な目的 | 育毛、抜け毛予防、頭皮環境の改善 | 発毛、育毛、脱毛(薄毛)の進行予防 |
| 主な作用 | 血行促進、抗炎症、保湿など | 毛母細胞の活性化、ヘアサイクルの改善 |
主な成分の違い
目的が異なるため、含まれている有効成分も異なります。育毛剤(医薬部外品)には、先述したような血行促進成分(センブリエキスなど)や抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)が配合されています。
これらは比較的穏やかに作用します。
一方、日本国内で市販されている発毛剤(第1類医薬品)には、有効成分として「ミノキシジル」が配合されています。
ミノキシジルは、もともと高血圧の治療薬として開発されましたが、その副作用として発毛効果が認められ、現在は発毛成分として広く使用されています。
毛母細胞の働きを直接活性化させ、ヘアサイクルの成長期を延長させる働きがあります。
どちらを選ぶべきか
どちらを選ぶべきかは、その人の薄毛の状態や目的によって異なります。
「最近抜け毛が増えてきた」「髪が細くなった気がする」「将来のために予防を始めたい」という、薄毛の初期段階や予防を目的とする場合は、まず「育毛剤」で頭皮環境を整えることから始めるのがよいでしょう。
一方で、「すでにつむじや生え際の地肌が目立つ」「明らかな薄毛(AGA)が進行している」と感じる場合は、「発毛剤」の使用が適しています。
発毛剤は医薬品であるため、薬剤師からの説明を受けて購入する必要があります。
使用上の注意点
育毛剤は医薬部外品であり、副作用のリスクは低いとされていますが、肌に合わない場合はかゆみや赤みが出ることがあります。
発毛剤(ミノキシジル配合)は第1類医薬品であり、効果が期待できる反面、副作用のリスクもあります。
主な副作用としては、頭皮のかゆみ、かぶれ、発疹のほか、まれに動悸やめまい、むくみなどが報告されています。
使用前には添付文書をよく読み、定められた用法・用量を厳守することが重要です。不安な点があれば、医師や薬剤師に相談しましょう。
薄毛対策でよくある誤解
「髪が薄くなってきた」と悩み始めると、様々な情報に触れる機会が増えます。しかし、中には科学的根拠のない俗説や、間違った情報も少なくありません。
誤った対策は、効果がないばかりか、かえって頭皮環境を悪化させる可能性もあります。ここでは、薄毛対策に関してよく聞かれる誤解を解き明かします。
海藻類を食べれば髪は生える?
「ワカメや昆布などの海藻類は髪に良い」と昔からよく言われます。確かに海藻類にはミネラルや食物繊維が豊富に含まれており、健康維持に役立ちます。
しかし、「海藻類をたくさん食べれば髪がフサフサになる」というのは誤解です。髪の主成分はタンパク質であり、海藻類だけを食べていても髪は作られません。
あくまでも、タンパク質やビタミンなど、他の栄養素とバランス良く摂取することが髪の健康につながります。
頭皮を叩くと髪が増える?
「ブラシなどで頭皮をトントンと叩くと、刺激になって血行が良くなり髪が生える」という俗説があります。
しかし、これは非常に危険な行為です。頭皮を強く叩くと、毛細血管や毛根がダメージを受け、炎症を引き起こす可能性があります。
頭皮が硬くなり、かえって抜け毛を増やす原因にもなりかねません。血行促進が目的なら、指の腹を使った優しいマッサージで十分です。
帽子をかぶると蒸れて薄くなる?
「帽子やヘルメットを長時間かぶっていると、蒸れて薄毛になる」と心配する声も聞かれます。
確かに、長時間かぶり続けることで汗や皮脂がたまり、頭皮が不潔な状態になると、雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮環境には良くありません。
しかし、帽子をかぶること自体が直接的な薄毛の原因になるわけではありません。むしろ、帽子には頭皮を紫外線から守るという重要なメリットがあります。
汗をかいたらこまめに拭き取り、帰宅後はシャンプーで頭皮を清潔に保つことを心がければ、問題ありません。
シャンプーは朝夜2回すべき?
皮脂が多いからといって、1日に何度もシャンプーをするのは逆効果です。シャンプーをしすぎると、頭皮を守るために必要な皮脂まで洗い流してしまいます。
すると、頭皮は乾燥を防ごうとして、かえって皮脂を過剰に分泌するようになります。これにより頭皮環境が悪化する可能性があります。シャンプーは基本的に1日1回、夜に行うのが適切です。
日中の汚れや皮脂をその日のうちにリセットし、清潔な状態で就寝(髪の成長時間)を迎えるのが理想です。
その他の薄毛に関する迷信
- ノンシリコンシャンプーなら髪が生える
- 白髪の人は薄毛にならない
- パーマやカラーリングをすると必ず薄毛になる
これらも明確な根拠はありません。ノンシリコンが頭皮に優しい側面はありますが発毛効果はありませんし、白髪と薄毛の因果関係も証明されていません。
パーマなども、頭皮にダメージを与えないよう適切に行えば、過度に恐れる必要はありません。
Q&A
ここでは、「髪が薄くなってきた 対策」に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 対策を始めたらどれくらいで変化を感じますか?
-
薄毛対策は、始めてすぐに結果が出るものではありません。髪にはヘアサイクル(毛周期)があり、新しい髪が生えてから成長し、目に見える長さになるまでには時間がかかります。
一般的に、生活習慣の見直しや育毛剤の使用を始めてから、抜け毛の減少や髪のハリ・コシの変化を感じ始めるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。
焦らず、根気よく続けることが何よりも重要です。
- 育毛剤はいつ使うのが効果的ですか?
-
育毛剤を使用する最も効果的なタイミングは、夜のシャンプー後です。
シャンプーによって頭皮の汚れや余分な皮脂が洗い流され、清潔な状態になっているため、育毛剤の成分が浸透しやすくなります。
また、就寝中は成長ホルモンの分泌が活発になり、髪が成長するゴールデンタイムです。この時間に合わせて頭皮環境を整えておくことが、育毛剤の効果を高めることにつながります。
塗布後は、しっかりと乾かしてから就寝しましょう。
- 薄毛対策はいつから始めるべきですか?
-
薄毛対策は、「気になった時が始め時」です。AGAは進行性であるため、放置している間に薄毛は着実に進行してしまいます。
毛根が活動を終えてしまう(毛包がミニチュア化しすぎる)と、そこから再び太く長い髪を生やすことは非常に困難になります。
そのため、抜け毛の増加や髪の軟毛化など、少しでも「髪が薄くなってきた」というサインを感じたら、できるだけ早く対策を始めることが、将来の髪を守る上で最も重要です。
- 対策をやめるとどうなりますか?
-
AGAが原因の場合、育毛剤や発毛剤の使用、あるいは生活習慣の改善によって薄毛の進行が抑えられていたとしても、対策をやめると、元の状態に戻ってしまう可能性が高いです。
特にAGAは進行性のため、対策を中断すれば、再びDHTの影響を受けてヘアサイクルが乱れ始め、抜け毛が増加し、薄毛が進行していきます。
薄毛対策は、効果を維持するためには継続することが前提となります。
Reference
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
MANABE, Motomu, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of male‐pattern and female‐pattern hair loss, 2017 version. The Journal of Dermatology, 2018, 45.9: 1031-1043.
BANKA, Nusrat; BUNAGAN, MJ Kristine; SHAPIRO, Jerry. Pattern hair loss in men: diagnosis and medical treatment. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 129-140.
PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.
COLEMAN, Emma. Types and treatment of hair loss in men and women. Plastic and Aesthetic Nursing, 2020, 40.4: 222-235.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
ROSS, Elizabeth K.; SHAPIRO, Jerry. Management of hair loss. Dermatologic clinics, 2005, 23.2: 227-243.
MOUNSEY, Anne L.; REED, Sean W. Diagnosing and treating hair loss. American family physician, 2009, 80.4: 356-362.
LIN, Richard L., et al. Systemic causes of hair loss. Annals of medicine, 2016, 48.6: 393-402.