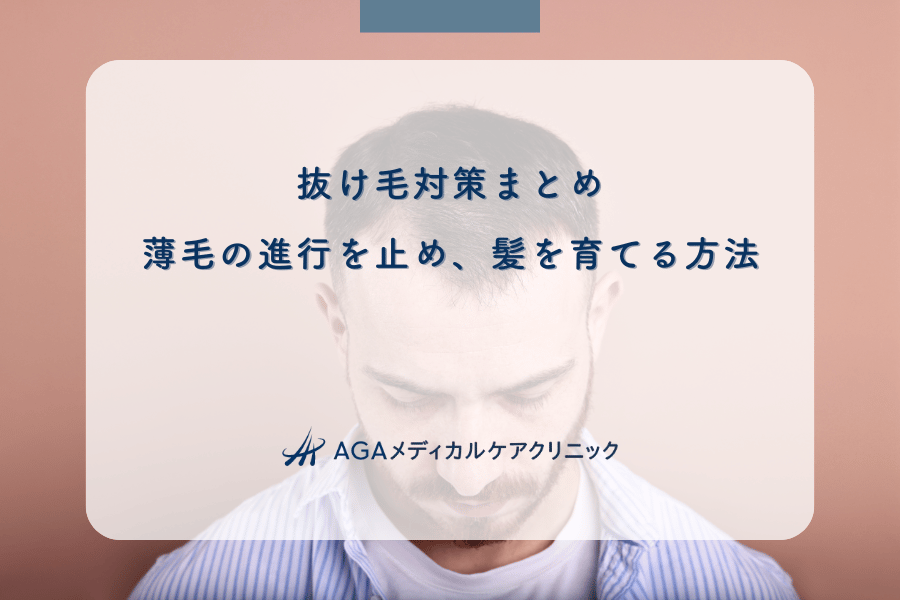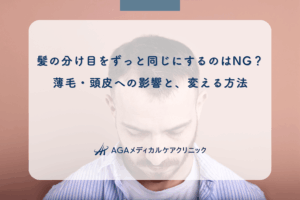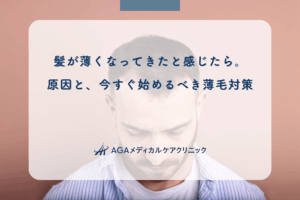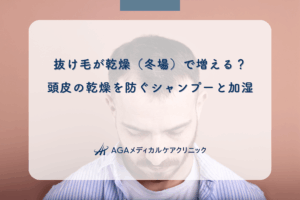抜け毛が気になり始めた方へ。鏡を見るたび、枕に残る髪の毛を見るたびに不安を感じていませんか。抜け毛は多くの男性が直面する悩みですが、早期の対策が進行を食い止める鍵となります。
この記事では、抜け毛が起こる基本的な理由から、日常生活で実践できる頭皮ケア、食生活の見直し、さらには育毛剤の正しい選び方と使い方まで、抜け毛対策を総合的に解説します。
薄毛の進行を止め、健やかな髪を育てるための一歩を、ここから踏み出しましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
抜け毛のサインを見逃さないでください
抜け毛対策の第一歩は、自分自身の状態を正確に把握することから始まります。毎日ある程度の髪の毛が抜けるのは自然な現象ですが、それが薄毛のサインである可能性もあります。
まずは、抜け毛がなぜ起こるのか、そして注意すべき抜け毛の特徴について理解を深めましょう。
抜け毛はなぜ起こるのか
髪の毛には「ヘアサイクル(毛周期)」があり、成長期、退行期、休止期を経て自然に抜け落ち、また新しい髪が生えてきます。
しかし、何らかの要因でこのサイクルが乱れると、抜け毛の量が増えたり、髪が十分に育つ前に抜け落ちたりします。
その主な要因としては、男性ホルモンの影響(AGA)、遺伝的な要因、生活習慣の乱れ(食生活、睡眠不足、ストレス)、不適切なヘアケアによる頭皮環境の悪化などが挙げられます。
多くの場合、これらの要因が複雑に絡み合って抜け毛を引き起こします。
危険な抜け毛と自然な抜け毛の違い
1日に抜ける髪の毛の量は、個人差はありますが、一般的に50本から100本程度であれば自然の範囲内と考えられます。しかし、抜けた髪の毛の状態や量によっては注意が必要です。
特に、細くて短い毛や、毛根部分が弱々しい毛が多く抜ける場合は、ヘアサイクルが短縮しているサインかもしれません。自分の抜け毛がどちらに当てはまるか、一度確認してみましょう。
抜け毛の状態比較
| 特徴 | 自然な抜け毛(休止期毛) | 注意が必要な抜け毛(異常毛) |
|---|---|---|
| 毛根の形 | マッチ棒の先端のように、白っぽく丸く膨らんでいる。 | 毛根が細い、いびつな形、または毛根自体が付着していない。 |
| 髪の太さ | 太く、しっかりとしたハリやコシがある。 | 細く短い毛(うぶ毛のような毛)が多い。 |
| 抜ける量 | 1日100本程度まで。季節の変わり目などで一時的に増えることもある。 | シャンプー時や朝起きた時、明らかに以前より増えたと感じる。 |
薄毛が進行する初期症状
薄毛は、ある日突然始まるわけではありません。多くの場合、ゆっくりと進行し、気づいた時にはかなり目立つ状態になっていることもあります。
以下のような初期症状に気づいたら、早めの対策を検討するタイミングです。
- 髪のボリュームが減った気がする
- セットがうまくいかない
- 髪の毛が細く、柔らかくなった
- 地肌が以前より透けて見えるようになった
- 生え際が少し後退したように感じる
- つむじ周りの地肌が目立つようになった
など、日々の小さな変化に注意を払うことが重要です。
抜け毛対策の基本となる生活習慣の見直し
健やかな髪を育てるためには、土台となる体が健康であることが重要です。高価な育毛剤を使用しても、日々の生活習慣が乱れていては期待する効果は得られにくいでしょう。
食事、睡眠、ストレス管理、運動といった基本的な生活習慣を見直すことが、抜け毛対策の基盤となります。
髪の成長と食生活の関係
髪の毛は、私たちが食べたものから作られます。特に髪の主成分である「ケラチン」というタンパク質を生成するためには、良質なタンパク質の摂取が欠かせません。
また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の血行を促進するビタミンE、頭皮の代謝をサポートするビタミンB群なども、髪の成長に深く関わる栄養素です。
偏った食事を避け、バランスの取れた食事を心がけましょう。
髪の成長を助ける主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質をケラチンに合成する際に必要。 | 牡蠣、レバー、赤身肉、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 頭皮の皮脂バランスを整え、代謝を促進する。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、バナナ |
良質な睡眠が頭皮環境を整える
睡眠不足は、髪の成長にとって大敵です。私たちは睡眠中に「成長ホルモン」を分泌します。
この成長ホルモンは、体の細胞分裂や修復を促す働きがあり、髪の毛の成長や頭皮のダメージ回復にも重要な役割を果たします。
特に、入眠後の深い睡眠時に多く分泌されるため、睡眠時間だけでなく「睡眠の質」を高めることも意識しましょう。
就寝前のスマートフォンの使用を控える、リラックスできる環境を整えるなど、安眠のための工夫を取り入れてください。
ストレス管理の重要性
現代社会においてストレスを完全になくすことは困難ですが、過度なストレスは抜け毛の要因となります。強いストレスを感じると自律神経が乱れ、交感神経が優位な状態が続きます。
これにより血管が収縮し、頭皮への血流が悪化します。血流が悪くなると、髪の毛の成長に必要な酸素や栄養素が毛根まで届きにくくなり、結果として抜け毛や髪の細毛化につながる可能性があります。
自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにすることが大切です。
運動不足が血行に与える影響
デスクワーク中心の生活や運動不足は、全身の血行不良を招きます。当然、頭皮の血流にも影響します。心臓から送られた血液は、体の末端である頭皮には届きにくい傾向があります。
適度な運動、特にウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、心肺機能を高め、全身の血行を促進するのに有効です。日常生活の中で意識的に体を動かす時間を作り、血流を改善しましょう。
頭皮環境を整えるヘアケア術
日々のヘアケアが間違っていると、知らず知らずのうちに頭皮にダメージを与え、抜け毛を助長している可能性があります。
髪を育てる土壌である頭皮を、清潔で健やかな状態に保つための正しいヘアケア方法を学びましょう。
自分に合ったシャンプーの選び方
毎日使うシャンプーは、頭皮環境に大きな影響を与えます。洗浄力が強すぎるシャンプーは、頭皮を守るために必要な皮脂まで洗い流してしまい、乾燥やフケ、かゆみの原因となることがあります。
逆に、洗浄力が弱すぎると皮脂や汚れが残り、毛穴を詰まらせる原因にもなります。
自分の頭皮の状態(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)を理解し、それに合った洗浄成分や保湿成分が配合されたシャンプーを選ぶことが重要です。
頭皮タイプ別シャンプー選びの目安
| 頭皮タイプ | 主な特徴 | 選びたいシャンプーの傾向 |
|---|---|---|
| 乾燥肌 | 洗髪後につっぱり感がある。カサカサしたフケが出る。 | アミノ酸系洗浄成分。保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)配合。 |
| 脂性肌 | 日中に頭皮がベタつく。湿ったフケが出る。 | 高級アルコール系など、適度な洗浄力があるもの。さっぱりした洗い上がり。 |
| 敏感肌 | かゆみや赤み、ヒリヒリ感が出やすい。 | 低刺激性、無添加(香料・着色料など)、薬用(抗炎症成分配合)など。 |
正しい髪の洗い方と乾かし方
シャンプーの目的は、髪の汚れを落とすことよりも「頭皮の汚れを落とす」ことです。
洗い方一つで頭皮の状態は大きく変わります。まず、シャンプーをつける前に、ぬるま湯で頭皮と髪をしっかりと予洗いします。これだけで汚れの多くは落ちます。
シャンプーは手のひらでよく泡立ててから頭皮につけ、爪を立てずに指の腹を使って優しくマッサージするように洗いましょう。
特に生え際や襟足は泡が残りやすいため、すすぎは「洗い」の倍以上の時間をかける意識で、丁寧に行います。
シャンプーの基本手順
- ぬるま湯(38度程度)で頭皮までしっかり予洗いする
- シャンプーを手のひらで十分に泡立てる
- 指の腹を使い、頭皮全体をマッサージするように洗う
- 時間をかけて、すすぎ残しがないよう徹底的にすすぐ
洗髪後は、タオルで髪をこするのではなく、頭皮の水分を優しく拭き取るようにタオルドライします。その後、できるだけ早くドライヤーで乾かしましょう。
濡れたまま放置すると、頭皮で雑菌が繁殖しやすくなり、臭いやかゆみの原因となります。ドライヤーは頭皮から20cm以上離し、一箇所に熱が集中しないように動かしながら乾かすのがコツです。
頭皮マッサージの具体的な方法
頭皮マッサージは、硬くなりがちな頭皮をほぐし、血行を促進するために有効なケアです。血流が改善することで、毛根に栄養が行き渡りやすくなります。
シャンプー中や、育毛剤を塗布した後などに行うと良いでしょう。指の腹を頭皮に密着させ、頭蓋骨から頭皮を動かすようなイメージで、ゆっくりと円を描いたり、掴んで持ち上げたりします。
生え際から頭頂部へ、側頭部から頭頂部へと、頭皮全体をまんべんなくほぐしましょう。心地よいと感じる強さで行うことが大切です。
育毛剤選びで失敗しないために
抜け毛対策として、育毛剤の使用を検討する方は多いでしょう。しかし、市場には多くの製品があり、どれを選べばよいか迷ってしまいます。
ここでは、自分に合った育毛剤を選ぶための基礎知識と、使い始めるタイミングについて解説します。
育毛剤と発毛剤の違いを理解する
まず、混同されがちな「育毛剤」と「発毛剤」の違いを明確に理解することが重要です。この二つは医薬品医療機器等法(薬機法)上の分類が異なり、目的や含まれる成分、入手方法も異なります。
自分の現在の状態が「予防」をしたいのか、「発毛」を期待するのかによって、選ぶべきものが変わります。
育毛剤と発毛剤の比較
| 項目 | 育毛剤 | 発毛剤 |
|---|---|---|
| 分類 | 医薬部外品 | 第1類医薬品 |
| 主な目的 | 頭皮環境を整え、抜け毛を予防し、育毛を促進する(今ある髪を育てる) | 毛母細胞に働きかけ、新たな髪の毛を生やす(発毛を促す) |
| 入手方法 | ドラッグストア、通信販売などで購入可能 | 薬剤師のいる薬局・ドラッグストア、またはクリニックでの処方 |
この記事では、主に「育毛剤(医薬部外品)」の選び方や使い方に焦点を当てて解説を進めます。
注目すべき育毛剤の有効成分
育毛剤(医薬部外品)には、厚生労働省が効果・効能を認めた「有効成分」が配合されています。これらの成分は、その働きによっていくつかのカテゴリーに分類できます。
製品のパッケージや説明書を見て、どのような成分が配合されているかを確認しましょう。
主な育毛有効成分の働き
| 働きの分類 | 主な成分例 | 期待される働き |
|---|---|---|
| 血行促進 | センブリエキス、ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)、ニンジンエキス | 頭皮の毛細血管の血流を良くし、毛根への栄養供給をサポートする。 |
| 抗炎症 | グリチルリチン酸ジカリウム(2K)、アラントイン | 頭皮の炎症やフケ・かゆみを抑え、頭皮環境を健やかに保つ。 |
| 毛母細胞活性 | パントテニルエチルエーテル、t-フラバノン | 髪の毛を作り出す毛母細胞の働きを助け、育毛を促す。 |
自分の頭皮タイプに合わせた選び方
育毛剤は毎日頭皮に直接塗布するものです。そのため、シャンプーと同様に、自分の頭皮タイプに合った使用感のものを選ぶことが継続の鍵となります。
例えば、乾燥肌や敏感肌の方は、アルコール(エタノール)の配合量が少ないものや、保湿成分(セラミド、コラーゲンなど)が豊富な製品を選ぶと良いでしょう。
逆に、脂性肌でベタつきが気になる方は、清涼感のあるさっぱりとした使用感の製品が向いているかもしれません。テクスチャー(液体、ジェル、スプレーなど)も好みで選びましょう。
育mol剤を使い始めるタイミング
抜け毛や薄毛の対策は、できるだけ早期に始めることが望ましいとされます。髪の毛を作り出す毛根が完全に活動を停止してしまうと、育毛剤でのケアは難しくなります。
「最近、抜け毛が増えた気がする」「髪にハリやコシがなくなってきた」「地肌が少し目立つようになった」など、初期のサインを感じ取った時点が、育毛剤によるケアを始める良いタイミングです。
予防的な観点から使い始めることも、将来の頭皮環境を考えると有効な選択です。
育毛剤の効果的な使い方
せっかく選んだ育毛剤も、使い方が間違っていては期待する効果を発揮できません。育毛剤の成分を頭皮にしっかりと届け、その働きを最大限に引き出すための正しい使用方法をマスターしましょう。
効果を高める塗布のタイミング
育毛剤を使用する最も良いタイミングは、洗髪後の清潔な頭皮です。シャンプーで頭皮の皮脂や汚れを落とした後は、育毛剤の成分が浸透しやすい状態になっています。
洗髪後、まずはタオルで髪と頭皮の水分を優しく拭き取ります(タオルドライ)。その後、ドライヤーで髪を乾かす前に育毛剤を塗布し、頭皮になじませてから再度ドライヤーで髪全体を乾かすと効率的です。
製品によっては朝晩2回の使用を推奨しているものも多いため、説明書を確認しましょう。
育毛剤使用のポイント
- 夜の洗髪後、頭皮が清潔で温まっている時に使用する
- 朝も使用する場合は、頭皮の汚れを軽く拭き取るか、軽く湯洗いしてから使用する
- 整髪料(ワックスなど)は、育毛剤が乾いた後につける
正しい塗布量と塗布方法
「たくさんつければ効果が上がる」というものではありません。むしろ、過剰な塗布は頭皮トラブルの原因にもなりかねません。製品ごとに定められた1回の使用目安量を必ず守ってください。
塗布する際は、ボトルのノズルを頭皮に直接軽く当て、気になる部分(生え際、頭頂部など)を中心に、頭皮全体に行き渡るように塗布します。
髪の毛ではなく、頭皮に直接つけることを意識しましょう。塗布後はすぐに流したりせず、指の腹を使って頭皮に優しく揉み込み、成分を浸透させます。
継続使用の必要性
育毛剤は、使い始めてすぐに抜け毛が減ったり、髪が生えたりするものではありません。髪の毛にはヘアサイクルがあり、抜け毛の予防や育毛の効果を実感するまでには、時間がかかります。
一般的に、最低でも3ヶ月から6ヶ月は毎日継続して使用することが必要です。すぐに変化が見られないからといって使用を中断してしまうと、それまでのケアが無駄になってしまう可能性もあります。
抜け毛対策は、根気強く続けることが何よりも重要です。
抜け毛対策でよくある誤解
抜け毛や薄毛に関しては、科学的根拠のない俗説や誤った情報も多く出回っています。間違った思い込みで不適切なケアを続けると、かえって頭皮環境を悪化させることにもなりかねません。
ここで、抜け毛対策に関するよくある誤解を解き、正しい知識を身につけましょう。
「頭皮が脂っぽいから」は本当か
「頭皮が脂っぽい(皮脂が多い)から抜け毛が増える」と心配する声をよく聞きます。
確かに、過剰に分泌された皮脂を放置すると、酸化して頭皮に刺激を与えたり、毛穴を塞いで炎症を引き起こしたりする(脂漏性皮膚炎)可能性があります。
しかし、皮脂が多いこと自体が抜け毛の直接的な原因ではありません。皮脂は本来、頭皮を乾燥や外部の刺激から守るバリア機能を持っています。
必要なのは、皮脂を取りすぎず、残しすぎず、適切なシャンプーで頭皮を清潔に保つことです。
「白髪染めやパーマ」は薄毛に直結する?
白髪染めやパーマに使用する薬剤は、化学的な刺激が強く、頭皮に付着すると炎症やかぶれを引き起こすことがあります。頭皮環境が悪化すれば、一時的に抜け毛が増えることも考えられます。
しかし、これらの施術がAGA(男性型脱毛症)の直接的な引き金になるわけではありません。
施術の頻度を空ける、頭皮に薬剤をつけないように美容師に依頼する、施術後はしっかり保湿ケアを行うなど、頭皮への負担を最小限に抑える工夫が大切です。
「帽子をかぶる」と抜け毛は増える?
「帽子やヘルメットを長時間かぶっていると蒸れてハゲる」というのもよくある誤解です。帽子をかぶること自体が抜け毛の原因になることはありません。
むしろ、夏場の強い紫外線は頭皮にダメージを与え、抜け毛の原因にもなるため、帽子は有効な紫外線対策となります。ただし、問題は「蒸れ」です。
汗をかいたまま放置すると、雑菌が繁殖しやすくなり頭皮環境が悪化します。
通気性の良い素材を選ぶ、こまめに汗を拭く、帰宅後は早めにシャンプーするなど、頭皮を清潔に保つことを心がければ問題ありません。
その他のよくある誤解
| 誤解 | 事実 | 補足 |
|---|---|---|
| 海藻類(ワカメなど)を食べると髪が増える | 髪の健康維持に必要なミネラルを含むが、特定の食品だけで発毛はしない。 | あくまでもバランスの良い食事の一部として重要。 |
| 頭皮をブラシで強く叩くと血行が良くなる | 強い刺激は頭皮を傷つけ、炎症や抜け毛を悪化させる可能性がある。 | 優しく揉みほぐす頭皮マッサージの方が安全で有効。 |
| シャンプーは朝より夜が良い | どちらでも良いが、夜のシャンプーの方が1日の汚れを落とせるため合理的。 | 自分のライフスタイルに合わせて清潔を保つことが重要。 |
専門家への相談も選択肢に入れる
セルフケアは抜け毛対策の基本ですが、すべての抜け毛がセルフケアだけで改善するわけではありません。特に、抜け毛の原因がAGA(男性型脱毛症)である場合、対策が追いつかないこともあります。
自分の状態を客観的に把握し、時には専門家の助けを借りることも賢明な判断です。
セルフケアの限界を知る
これまで述べてきた生活習慣の改善、正しいヘアケア、育毛剤(医薬部外品)の使用を数ヶ月間(例えば6ヶ月以上)続けても、抜け毛が減る兆候が見られない、あるいは明らかに薄毛が進行していると感じる場合、セルフケアの範囲を超えている可能性があります。
育毛剤はあくまで「予防」や「育毛」が目的であり、「発毛」を促すものではありません。進行を止める力が、抜け毛の勢いに負けている状態かもしれません。
AGA(男性型脱毛症)の可能性
成人男性の薄毛の多くは、AGA(男性型脱毛症)が原因であると言われています。
AGAは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、特定の酵素(5αリダクターゼ)と結びついてジヒドロテストステロン(DHT)に変化し、このDHTが毛根の受容体と結合することでヘアサイクルを乱し、髪が太く長く成長する前に抜け落ちてしまう現象です。
これは遺伝的な要因も関わっており、進行性であるため、放置すると薄毛は徐々に進んでいきます。生え際の後退や頭頂部の薄毛が目立つ場合は、AGAの可能性を疑う必要があります。
クリニックで受けられる相談内容
皮膚科や薄毛治療を専門とするクリニックでは、医師による専門的な診察を受けることができます。
まずは問診や視診、マイクロスコープによる頭皮状態のチェックなどを行い、抜け毛の原因がAGAなのか、他の皮膚疾患(脂漏性皮膚炎や円形脱毛症など)なのかを診断します。
AGAと診断された場合、セルフケアの指導に加え、医学的根拠に基づいた治療(内服薬や外用薬(発毛剤)の処方など)の提案を受けることができます。
自分の抜け毛の原因を正確に知ることが、最も効果的な対策への近道となります。
季節・ストレス・生活習慣に戻る
Q&A
最後に、抜け毛対策に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
- 育毛剤はどれくらいで効果が出ますか?
-
育毛剤は医薬部外品であり、その目的は主に頭皮環境を整え、抜け毛を予防し、今ある髪を健やかに育てることです。
髪の毛の成長サイクル(ヘアサイクル)を考慮すると、効果を実感するまでには個人差がありますが、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の継続使用が必要です。
すぐに効果が出ないからといって諦めず、根気よく続けることが大切です。
- 抜け毛対策をやめると元に戻りますか?
-
生活習慣の乱れや不適切なヘアケアが原因だった場合、対策をやめれば再び抜け毛が増える可能性があります。
また、AGA(男性型脱毛症)の場合、その進行を抑えるための対策(治療を含む)を中断すると、再び薄毛が進行し始めることが一般的です。
健やかな頭皮環境を維持するためには、良い習慣を継続することが重要です。
- 複数の育毛剤を併用してもよいですか?
-
基本的には推奨しません。複数の製品を同時に使用すると、成分同士が予期せぬ反応を起こしたり、頭皮への刺激が強すぎたりする可能性があります。
また、どの製品が自分に合っているのか判断しにくくなります。一つの製品をまずは数ヶ月間使用し、その効果を見極めるようにしてください。
- 食生活だけで抜け毛は改善しますか?
-
食生活の改善は、抜け毛対策の非常に重要な基盤です。髪の成長に必要な栄養素が不足すれば、抜け毛が増えたり、髪が細くなったりする原因になります。
しかし、抜け毛の原因がAGAや他の要因である場合、食生活の改善だけでは進行を止めることは難しいかもしれません。
食生活を見直しつつ、他の対策(ヘアケア、育毛剤の使用、専門家への相談など)も併せて行うことをお勧めします。
Reference
NULL, C.; FELDMAN, Martin. Comprehensive lifestyle intervention improves hair and skin status and mental and physical functioning. Townsend Lett, 2008, 86-94.
HU, Sophia, et al. Holistic dermatology: An evidence-based review of modifiable lifestyle factor associations with dermatologic disorders. Journal of the American Academy of Dermatology, 2022, 86.4: 868-877.
ALOTIBY, Amna A. Integrating Psychological Support and Topical Therapy for the Effective Management of Stress-Induced Alopecia Areata: A Case Report. Cureus, 2025, 17.1.
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
DRAKE, Lara, et al. Evaluation of the safety and effectiveness of nutritional supplements for treating hair loss: a systematic review. JAMA dermatology, 2023, 159.1: 79-86.
ROSS, Elizabeth K.; SHAPIRO, Jerry. Management of hair loss. Dermatologic clinics, 2005, 23.2: 227-243.
YADAV, Mahipat S.; KUSHWAHA, Neeti; MAURYA, Neelesh K. The Influence of Diet, Lifestyle, and Environmental Factors on Premature Hair Greying: An Evidence-Based Approach. Archives of Clinical and Experimental Pathology, 2025, 4.1.
CEDIRIAN, Stephano, et al. The exposome impact on hair health: non-pharmacological management. Part II⋆. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2025.
JADKAUSKAITE, Laura, et al. Oxidative stress management in the hair follicle: Could targeting NRF2 counter age‐related hair disorders and beyond?. Bioessays, 2017, 39.8: 1700029.