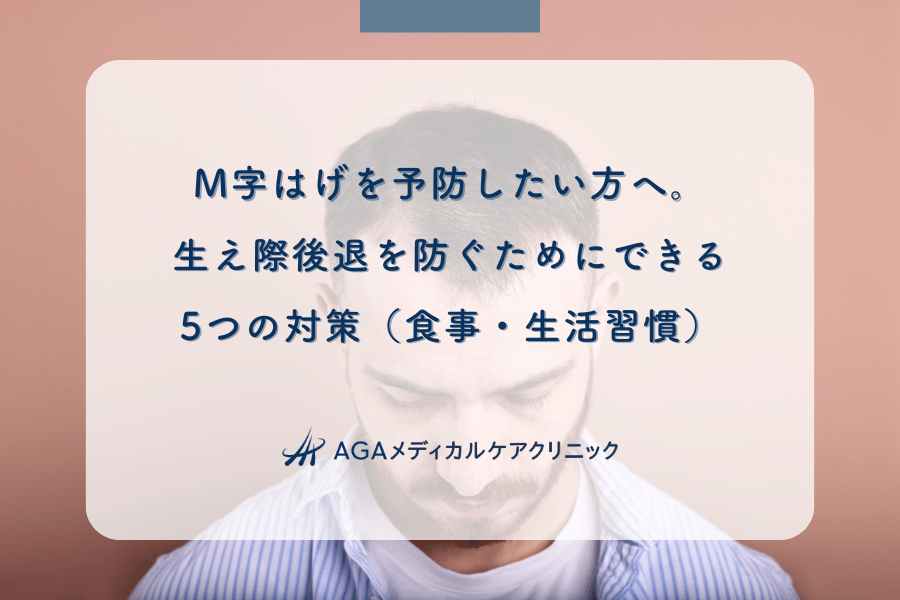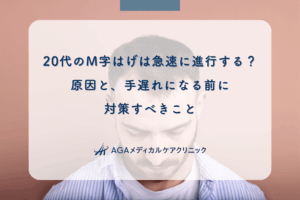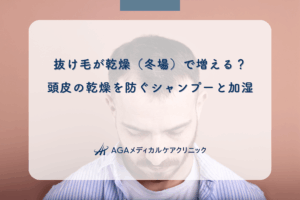「最近、生え際が後退してきた気がする」「おでこが広くなったかもしれない」と鏡を見るたびに不安を感じていませんか。
特にこめかみの上あたりから薄くなる「M字はげ」は、多くの方が早い段階で気になり始める悩みの一つです。M字はげの予防や対策は、手遅れになる前に始めることが重要です。
この記事では、M字はげの予防と対策に関心がある方へ向けて、今日から始められる食事や生活習慣の改善点について、5つの具体的な対策を詳しく解説します。
大切な髪を守るために、できることから取り組んでいきましょう。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
M字はげとは? 生え際が後退する主な原因
M字はげの対策や予防を考える前に、まずはその特徴と原因を正しく理解することが大切です。なぜ生え際が後退してしまうのか、その背景を知ることで、適切なアプローチが見えてきます。
M字はげの特徴とセルフチェック
M字はげとは、その名の通り、額の生え際がアルファベットの「M」の字のように、左右の剃り込み部分から後退していく状態を指します。
正面から見たときに、中央部分は残り、両サイドが深く切れ込んで見えるのが特徴です。
初期段階では自分では気づきにくいこともありますが、以前の写真と見比べたり、髪を濡らしてオールバックにしてみたりすると、生え際の変化が分かりやすくなります。
「M字はげ 対策」を検索している方の中には、すでにこの変化に気づき始めている方も多いかもしれません。
AGA(男性型脱毛症)との関係性
M字はげの進行は、多くの場合AGA(男性型脱毛症)と深く関係しています。AGAは成人男性に見られる進行性の脱毛症で、思春期以降に発症し、徐々に薄毛が進行します。
生え際(特にM字部分)や頭頂部から薄くなるのが典型的なパターンです。
M字部分の後退は、AGAの初期症状として現れることが非常に多いため、M字はげの予防は、AGAの早期対策と言い換えることもできます。
遺伝的要因の影響
AGAの発症には、遺伝的な要因が関与していることが知られています。具体的には、「男性ホルモン(テストステロン)の感受性」や「5αリダクターゼという酵素の活性度」が遺伝しやすいとされています。
ご家族に薄毛の方がいる場合、ご自身もAGAを発症しやすい体質を受け継いでいる可能性があります。
ただし、遺伝的要因があるからといって必ずM字はげが進行するわけではなく、あくまで「なりやすさ」の問題です。適切な予防策を講じることで、その進行を遅らせることは十分に可能です。
ホルモンバランスの乱れ(DHT)
AGAによるM字はげの直接的な引き金となるのが、DHT(ジヒドロテストステロン)という強力な男性ホルモンです。
DHTは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、頭皮(特にM字部分や頭頂部)に多く存在する「5αリダクターゼ」という酵素によって変換されることで生成されます。
このDHTが、髪の毛の成長期を短縮させ、髪が太く長く成長する前に抜け落ちるように指令を出してしまいます。このサイクルが繰り返されることで、髪は細く短くなり、M字部分の地肌が目立つようになるのです。
「M字はげ 予防」において、このDHTの働きをいかに抑えるか、またDHTの影響を受けにくい頭皮環境を維持するかが鍵となります。
M字はげ予防の基本 食事で見直すべきポイント
髪の毛は、私たちが日々摂取する栄養素から作られています。M字はげの予防と対策を考える上で、食生活の見直しは最も基本的かつ重要な取り組みの一つです。
身体の内側から頭皮環境を整え、健康な髪の育成をサポートしましょう。
髪の成長に必要な栄養素
健康な髪を育てるためには、特定の栄養素だけを摂取するのではなく、バランスの取れた食事が重要です。特に以下の3つの栄養素は、髪の健康維持に深く関わっています。
髪の主成分「タンパク質」
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。タンパク質が不足すると、髪が細くなったり、ツヤが失われたり、成長が妨げられたりする原因となります。
M字はげの予防を目指すなら、良質なタンパク質の摂取は欠かせません。肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品などから、毎食バランスよく取り入れることを心がけましょう。
頭皮環境を整える「ビタミン類」
ビタミン類は、タンパク質の代謝を助けたり、頭皮の血行を促進したり、皮脂の分泌をコントロールしたりと、頭皮環境を健やかに保つために多彩な働きをします。
特にビタミンB群(B2, B6)は皮脂のバランスを整え、ビタミンEは血流を改善して頭皮に栄養を届けるサポートをします。緑黄色野菜、果物、ナッツ類などを積極的に摂取することが大切です。
毛母細胞の働きを助ける「亜鉛」
亜鉛は、タンパク質(ケラチン)の合成をサポートする重要なミネラルです。毛母細胞の分裂を促し、髪の成長を助ける役割も担っています。亜鉛が不足すると、髪の成長が滞り、脱毛の原因にもなり得ます。
亜鉛は体内で作ることができず、汗などで失われやすいため、食事から意識的に摂取する必要があります。牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズなどに多く含まれます。
避けるべき食生活とM字はげのリスク
M字はげの対策として栄養バランスを考える一方で、避けるべき食生活もあります。高脂肪・高カロリーな食事は、皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。
皮脂が毛穴に詰まると、髪の健やかな成長を妨げることにつながります。また、過度な飲酒や糖分の多い食事も、ビタミンB群を大量に消費してしまうため、髪に必要な栄養が不足しがちになります。
インスタント食品やファストフードに偏った食事は避け、バランスの取れた食生活を意識することが重要です。
予防に役立つ食材の具体例
M字はげの予防と対策のために、具体的にどのような食材を選べばよいのでしょうか。先に挙げた栄養素を効率よく摂取できる食材の例を見てみましょう。
M字はげ予防のための栄養素と食材
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材の例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る | 鶏むね肉、鮭、卵、豆腐、納豆 |
| ビタミンB群 | 皮脂の調整、タンパク質の代謝補助 | レバー、マグロ、バナナ、ほうれん草 |
| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | アーモンド、アボカド、かぼちゃ |
| 亜鉛 | ケラチンの合成サポート | 牡蠣、牛肉(赤身)、チーズ、いわし |
生活習慣の改善で取り組むM字はげ対策
食事と並んで、M字はげの予防に大きな影響を与えるのが日々の生活習慣です。睡眠、ストレス、喫煙、飲酒など、見直すべきポイントは多岐にわたります。
健康な髪は、健康な生活習慣から育まれます。
睡眠の質と髪の成長
髪の毛は、私たちが寝ている間に分泌される「成長ホルモン」によって成長が促されます。特に、入眠後最初の深い眠り(ノンレム睡眠)の間に成長ホルモンは最も多く分泌されます。
睡眠時間が不足したり、眠りが浅かったりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の成長に悪影響を及ぼします。
M字はげの対策として、毎日6〜7時間程度の十分な睡眠時間を確保し、就寝前のスマートフォン操作を控えるなどして「睡眠の質」を高める工夫が重要です。
ストレスが頭皮に与える影響
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱します。自律神経のうち交感神経が優位になると、血管が収縮し、頭皮の血流が悪化します。
血流が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素や酸素が毛根まで十分に行き渡らなくなります。これがM字はげの進行を助長する一因となり得ます。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながるため、M字はげの予防を考える上ではストレス管理が欠かせません。
ストレスコーピングの方法
ストレスをゼロにすることは難しいですが、上手に付き合っていく方法はあります。自分に合ったストレス発散法(コーピング)を見つけることが大切です。
例えば、趣味に没頭する時間を作る、軽い運動(ウォーキングやジョギング)で汗を流す、ゆっくりと入浴する、信頼できる友人と話すなど、心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。
M字はげのことを考えすぎて、それが新たなストレスにならないよう、上手に気分転換を図ることが予防につながります。
喫煙と飲酒の習慣を見直す
喫煙と過度な飲酒は、M字はげの対策において見直すべき代表的な生活習慣です。これらが髪に与える影響は少なくありません。
喫煙・飲酒が髪に及ぼす主な影響
| 習慣 | 主な影響 | 髪への具体的なダメージ |
|---|---|---|
| 喫煙 | 血管収縮・ビタミン消費 | ニコチンが血管を収縮させ、頭皮の血流を悪化させます。また、髪の健康に必要なビタミンCなどを大量に破壊します。 |
| 過度な飲酒 | 栄養素の消費・肝機能低下 | アルコールの分解過程で、髪の栄養となるビタミンB群や亜鉛が大量に消費されます。肝機能が低下するとタンパク質の合成能力も落ちます。 |
M字はげの予防を本気で考えるのであれば、禁煙や節酒(または禁酒)は非常に効果的な対策となります。
頭皮環境を整える 正しいヘアケア方法
M字はげの予防には、外側からのケア、すなわち頭皮環境を清潔で健やかに保つヘアケアも重要です。
毎日のシャンプーやマッサージが、知らず知らずのうちに頭皮にダメージを与えている可能性もあります。正しい方法を学びましょう。
シャンプー選びの基準
シャンプーの主な目的は、頭皮の汚れや余分な皮脂を洗い流すことです。
しかし、洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、必要な皮脂まで取り除いてしまい、頭皮の乾燥やかゆみを引き起こすことがあります。
逆に、乾燥した頭皮を守ろうとして皮脂が過剰に分泌されることもあります。
M字はげの対策としては、頭皮への刺激が少ない「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を使用したシャンプーを選ぶことをお勧めします。
自分の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌)に合ったものを見つけることが大切です。
間違ったシャンプー方法と正しい洗い方
ゴシゴシと強くこすったり、爪を立てて洗ったりする行為は、頭皮を傷つける原因となります。また、シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しは、毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こす可能性があります。
正しい洗い方は、まずお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、汚れの大半を落とします。次に、シャンプーを手のひらでよく泡立て、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗います。
特にM字部分は皮脂が溜まりやすいため、丁寧に洗いましょう。最後は、すすぎ残しがないよう、時間をかけてしっかりと洗い流します。
頭皮タイプ別シャンプーの選び方
| 頭皮タイプ | 特徴 | 推奨されるシャンプー成分 |
|---|---|---|
| 脂性肌(オイリー) | 皮脂が多く、ベタつきやすい | アミノ酸系、ベタイン系(適度な洗浄力) |
| 乾燥肌(ドライ) | カサつき、フケが出やすい | アミノ酸系(保湿成分配合) |
| 敏感肌 | 刺激を感じやすい、赤みが出やすい | アミノ酸系、ベタイン系(低刺激、無添加) |
頭皮マッサージのやり方と注意点
頭皮マッサージは、硬くなった頭皮をほぐし、血行を促進する効果が期待できます。M字はげが気になる生え際や、血流が滞りやすい頭頂部を中心に、指の腹で優しく揉みほぐします。
シャンプー中や、入浴後で血行が良くなっている時に行うのが効果的です。ただし、力を入れすぎたり、爪を立てたりすると逆効果です。
頭皮が動くのを感じる程度の力加減で、リラックスしながら行うことが「M字はげ 予防」につながります。
紫外線の頭皮へのダメージと対策
見落としがちなのが、紫外線の影響です。紫外線は肌だけでなく、頭皮にもダメージを与えます。頭皮が日焼けすると、乾燥や炎症を引き起こし、毛母細胞の働きを弱めてしまいます。
M字部分は特に紫外線を浴びやすいため、注意が必要です。日差しの強い日には、帽子をかぶる、日傘を使う、頭皮用の日焼け止めスプレーを利用するなど、紫外線対策を心がけましょう。
運動習慣がM字はげ予防につながる理由
意外に思われるかもしれませんが、適度な運動習慣もM字はげの予防と対策に役立ちます。デスクワークが多く、運動不足を感じている方は、ぜひ生活に取り入れてみてください。
血行促進と頭皮への栄養供給
運動をすると全身の血流が良くなります。もちろん、頭皮への血流も例外ではありません。
頭皮の毛細血管まで血液がしっかりと巡ることで、食事から摂取した栄養素や酸素が毛根の毛母細胞に効率よく届けられます。
M字はげの対策として食事改善に取り組んでも、栄養を運ぶ「血流」が滞っていては効果が半減してしまいます。運動は、この「運搬」をスムーズにするために重要です。
運動によるストレス発散効果
運動は、代表的なストレス発散方法の一つです。体を動かして汗を流すことは、心身のリフレッシュにつながり、ストレスホルモンの分泌を抑える効果が期待できます。
前述の通り、ストレスは頭皮の血流悪化やホルモンバランスの乱れを引き起こすため、運動によってストレスを軽減することは、間接的にM字はげの予防につながります。
おすすめの運動の種類と頻度
M字はげの予防を目的とする場合、激しい運動よりも、継続しやすい有酸素運動が推奨されます。無理なく続けられることが何よりも大切です。
M字はげ予防に推奨される運動
| 運動の種類 | 推奨される頻度・時間 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| ウォーキング | 毎日 20〜30分程度 | 手軽に始められ、全身の血行を促進する |
| ジョギング | 週 2〜3回 30分程度 | 効率的な血行促進とストレス発散 |
| サイクリング | 週末 1時間程度 | 楽しみながら長時間続けやすい |
これらの運動を日常生活に取り入れ、運動不足を解消することが、健やかな頭皮環境の維持に役立ちます。
M字はげ対策における育毛剤の役割
食事、生活習慣、ヘアケア、運動。これら5つの対策のベースを整えた上で、M字はげの予防をさらに後押しするのが育毛剤です。
育毛剤は、M字はげの対策においてどのような役割を担うのでしょうか。
育毛剤と発毛剤の違い
まず、「育毛剤」と「発毛剤」の違いを明確に理解しておくことが重要です。これらは目的と成分が異なります。
育毛剤と発毛剤の比較
| 種類 | 主な目的 | 分類(日本において) |
|---|---|---|
| 育毛剤 | 今ある髪の成長促進、抜け毛予防、頭皮環境改善 | 医薬部外品 |
| 発毛剤 | 新しい髪を生やす、毛母細胞の活性化 | 第1類医薬品(ミノキシジル配合など) |
M字はげの「予防」や、初期段階の「対策」として頭皮環境を整えたい場合には、まず育毛剤の使用を検討するのが一般的です。
育毛剤がサポートする頭皮環境
育毛剤には、頭皮の血行を促進する成分、毛母細胞の働きをサポートする成分、頭皮の炎症やフケ・かゆみを抑える成分、保湿成分などが含まれています。
M字はげが気になる部分は、頭皮が硬くなったり、乾燥したりしがちです。育毛剤を使用することで、頭皮にうるおいを与え、柔軟に保ち、髪が育ちやすい環境へと整えるサポートをします。
M字はげ予防のための育毛剤の選び方
M字はげの予防や対策として育毛剤を選ぶ際は、ご自身の頭皮の状態に合ったものを選ぶことが大切です。
例えば、乾燥が気になるなら保湿成分が豊富なもの、皮脂が多めなら皮脂バランスを整える成分が入ったものを選びます。
また、M字はげの原因であるAGA(DHT)にアプローチする成分(例:キャピキシル、リデンシル、ノコギリヤシエキスなど)に着目して選ぶ方法もあります。
毎日使うものなので、香りやテクスチャー(使用感)が好みに合うかどうかも、継続のしやすさに関わる重要なポイントです。
生活習慣改善と併用する重要性
最も大切なことは、育毛剤だけに頼らないことです。育毛剤はあくまで「サポート」役です。
不規則な生活や栄養バランスの悪い食事を続けながら育毛剤を使っても、その効果を十分に感じることは難しいでしょう。
この記事で解説してきた食事、睡眠、運動、ヘアケアといった基本的な「M字はげ 対策」の土台があってこそ、育毛剤はその役割を発揮します。
生活習慣全体の改善と併用することで、M字はげの予防効果を高めることが期待できます。
M字はげの進行を感じたら考えるべきこと
ここまでは、M字はげの「予防」と「対策」として、ご自身でできるセルフケアを中心に解説してきました。
しかし、これらの努力を続けても、生え際の後退が止まらない、あるいは明らかに進行していると感じる場合、次のステップを考えることも重要です。
セルフケアの限界
食事の改善や生活習慣の見直し、育毛剤の使用は、あくまで頭皮環境を整え、抜け毛を「予防」するための対策です。
M字はげの原因がAGAであり、すでにそれが進行し始めている場合、セルフケアだけで進行を完全に食い止めたり、元の状態に戻したりすることには限界があります。
特に、M字部分の毛包が活動を終えてしまうと、セルフケアでの回復は非常に難しくなります。
専門クリニックへの相談という選択肢
セルフケアで改善が見られない場合や、M字はげの進行が速いと感じる場合は、皮膚科やAGA専門のクリニックに相談することを推奨します。
専門医による診断を受けることで、ご自身の薄毛の原因が本当にAGAなのか、他の要因(円形脱毛症や脂漏性皮膚炎など)が隠れていないかを知ることができます。
専門機関では、セルフケアでは行えない医学的根拠に基づいた治療(内服薬や外用薬の処方など)の提案を受けることが可能です。
早期対策の重要性
M字はげ、特にAGAによるものは進行性です。放置しておくと、薄毛の範囲は徐々に広がっていきます。対策を始めるのが早ければ早いほど、進行を食い止め、良好な状態を維持できる可能性が高まります。
「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、異変を感じた時点で「M字はげ 予防」や「M字はげ 対策」のアクションを起こすことが、将来の髪を守る上で最も重要です。
抱え込まない心構え
M字はげの悩みは非常にデリケートであり、一人で抱え込みがちです。しかし、悩むこと自体がストレスとなり、さらに頭皮環境を悪化させる悪循環に陥ることもあります。
大切なのは、客観的に自分の状態を把握し、適切な対策を淡々と実行することです。セルフケアでできることを実践しつつ、必要な場合は専門家の助けを借りる。
そのように前向きに捉える心構えが、M字はげの対策を続けていく上で大切です。
Q&A
M字はげの予防や対策に関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- M字はげはどのくらいの期間で進行しますか?
-
M字はげ(AGA)の進行速度には個人差が非常に大きいです。遺伝的要因、生活習慣、ストレスの度合いなど、様々な要因が影響します。
数ヶ月で急激に進行するように感じる方もいれば、数年かけてゆっくりと後退していく方もいます。進行が始まったと感じたら、速度に関わらず早めに対策を始めることが重要です。
- 食事を変えたらすぐに効果は出ますか?
-
食事改善によるM字はげ予防の効果は、すぐには現れません。
髪の毛には「ヘアサイクル」があり、新しい健康な髪が成長し、その変化を実感できるようになるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。
効果が出ないからとすぐに諦めず、バランスの取れた食事を「継続する」ことが何よりも大切です。
- 頭皮マッサージはやりすぎても良いですか?
-
頭皮マッサージは、やりすぎや力の入れすぎに注意が必要です。1回のマッサージは5分程度を目安にし、1日に何度も行う必要はありません。
力を入れすぎると、かえって頭皮を傷つけたり、毛細血管を圧迫して血流を妨げたりする可能性があります。指の腹で「優しく、気持ち良い」と感じる程度の力加減で行ってください。
- 育毛剤はいつから使い始めるべきですか?
-
育毛剤を使い始めるタイミングに明確な決まりはありませんが、「M字はげの予防」を意識し始めた時点、つまり「少し生え際が気になってきたな」と感じた初期段階から使い始めることをお勧めします。
頭皮環境を健やかに保つことは、抜け毛が本格化する前からの継続的な取り組みが効果的です。食事や生活習慣の改善と並行して、日々のヘアケアの一環として取り入れると良いでしょう。
Reference
GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.
RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutrition Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.
RAJENDRASINGH, J. R. Role of non-androgenic factors in hair loss and hair regrowth. J Cosmo Trichol, 2017, 3.2: 118.
RUSHTON, D. H., et al. Causes of hair loss and the developments in hair rejuvenation. International journal of cosmetic science, 2002, 24.1: 17-23.
PAN, Xuexue, et al. Technological Advances in Anti-hair Loss and Hair Regrowth Cosmeceuticals: Mechanistic Breakthroughs and Industrial Prospects Driven by Multidisciplinary Collaborative Innovation. Aesthetic Plastic Surgery, 2025, 1-50.
PENG, Lin, et al. Unhealthy diet and lifestyle factors linked to female androgenetic alopecia: a community-based study from Jidong study, China. BMC Public Health, 2025, 25.1: 606.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
KĘPIŃSKA, Klementyna; JAŁOWSKA, Magdalena; BOWSZYC-DMOCHOWSKA, Monika. Frontal Fibrosing Alopecia–a review and a practical guide for clinicians. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2022, 29.2: 169-184.
FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.