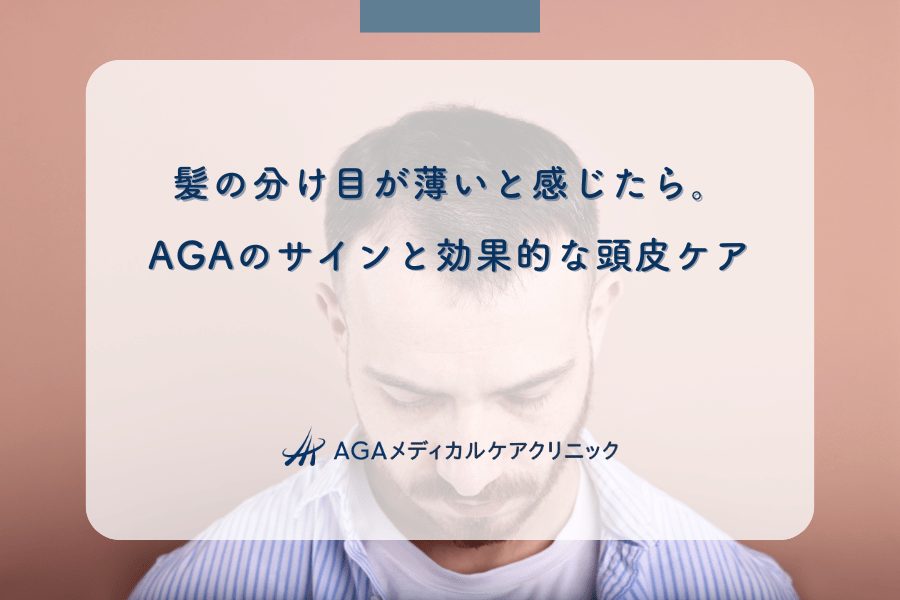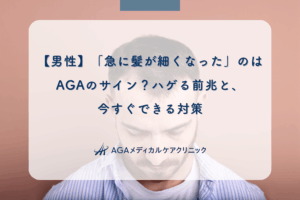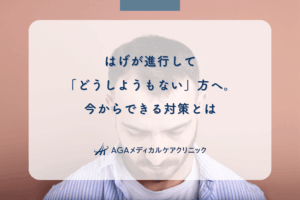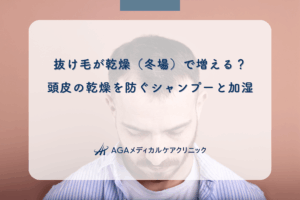「あれ、なんだか髪の分け目が目立つようになった…?」鏡を見てふと感じる不安。それは単なる気のせいでしょうか、それともAGA(男性型脱毛症)の初期サインかもしれません。
分け目が薄く見える原因は様々ですが、放置してしまうと薄毛が進行する可能性もあります。
この記事では、髪の分け目が薄くなる原因、特にAGAとの関連性、そして今日から始められる効果的な頭皮ケアについて、専門的な知見に基づきながら分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
なぜ髪の分け目は薄く見えるのか?その主な原因
髪の分け目が目立つようになると、多くの方が「髪が減ったのではないか」と心配します。その原因は一つではなく、複数の要因が関わっていることが多いです。
まずは、分け目が薄く見える主な理由について理解を深めましょう。
頭皮環境の悪化と血行不良
頭皮は髪の毛が育つ土壌です。この土壌の状態が悪化すると、健康な髪は育ちません。例えば、過剰な皮脂分泌やフケ、乾燥は頭皮の毛穴を塞いだり、炎症を引き起こしたりします。
これにより、髪の毛が細くなったり、抜けやすくなったりすることがあります。
また、ストレスや生活習慣の乱れから頭皮の血行が悪くなると、髪の毛根にある「毛母細胞」に必要な栄養素や酸素が十分に行き届かなくなります。
その結果、髪の成長が妨げられ、分け目周辺のボリュームダウンにつながるのです。
紫外線や外的ダメージの蓄積
頭皮は体の中で最も高い位置にあり、紫外線を直接浴びやすい場所です。特に分け目は、頭皮が露出しやすいため、紫外線のダメージを集中して受けがちです。
紫外線は頭皮を乾燥させ、日焼けによる炎症を引き起こすだけでなく、髪の毛そのもの(キューティクル)にもダメージを与えます。
さらに、パーマやカラーリングの薬剤、ヘアスプレーの使い過ぎ、洗浄力の強すぎるシャンプーなども、頭皮や髪に負担をかけ、分け目の薄毛を進行させる要因となり得ます。
分け目が目立つ主な原因と特徴
| 原因 | 特徴 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 頭皮環境の悪化 | フケ、かゆみ、赤み、過剰な皮脂。 | 正しいシャンプー、頭皮の保湿。 |
| 血行不良 | 頭皮が硬い、くすんでいる。 | 頭皮マッサージ、適度な運動、入浴。 |
| 紫外線ダメージ | 分け目が日焼けしやすい、頭皮が乾燥。 | 帽子や日傘の使用、頭皮用日焼け止め。 |
AGA(男性型脱毛症)の初期症状
男性の薄毛の最も一般的な原因であるAGA(男性型脱毛症)も、分け目の薄毛として現れることがあります。
AGAは、男性ホルモン(テストステロン)が特定の酵素(5αリダクターゼ)と結びつき、脱毛を促進するジヒドロテストステロン(DHT)に変化することで進行します。
このDHTが毛乳頭細胞の受容体に作用し、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)を短縮させます。
通常よりも早く髪が抜けてしまい、新しく生えてくる髪も細く弱々しくなるため、全体的に髪の密度が低下し、分け目が目立つようになるのです。
AGAは生え際の後退と同時に、頭頂部(つむじ)から薄くなるパターンが多く、分け目もその影響を受ける部分と言えます。
生活習慣の乱れによる影響
私たちの体は、日々の生活習慣によって大きく左右されます。
髪の毛も例外ではありません。偏った食生活による栄養不足、特に髪の主成分であるタンパク質や、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類が不足すると、健康な髪は作られません。
また、睡眠不足は髪の成長に重要な「成長ホルモン」の分泌を妨げます。過度なストレスは自律神経のバランスを崩し、血行不良やホルモンバランスの乱れを引き起こし、薄毛を助長します。
これらの生活習慣の乱れが、頭皮環境の悪化やAGAの進行を早める一因となることもあります。
「髪の分け目が薄い」はAGAのサイン?見極めのポイント
分け目が薄いと感じたとき、最も気になるのが「これはAGAなのか?」という点でしょう。AGAは進行性の脱毛症であり、早期の対策が重要です。
ここでは、AGAの可能性を見極めるためのポイントを解説します。
AGA(男性型脱毛症)とは何か
前述の通り、AGA(Androgenetic Alopecia)は、男性ホルモンと遺伝的要因が深く関わる脱毛症です。主な特徴は、思春期以降に発症し、徐々に進行することです。
男性ホルモンの一種であるDHT(ジヒドロテストステロン)が、髪の毛の成長期を極端に短くしてしまいます。
これにより、髪が十分に太く長く成長する前に抜け落ち、細く短い「うぶ毛」のような髪が増えていきます。この結果、地肌が透けて見えるようになり、薄毛が目立つのです。
分け目以外の薄毛(生え際・頭頂部)の確認
AGAには特徴的な進行パターンがあります。分け目だけが薄くなるというよりは、他の部位と同時に薄毛が進行することが多いです。特に注意すべきは以下の2点です。
AGAの主な進行パターン
| パターン | 特徴 |
|---|---|
| M字型(生え際) | 額の左右の生え際(そりこみ部分)が後退していく。 |
| O字型(頭頂部) | 頭頂部(つむじ周辺)から円形に薄くなっていく。 |
| U字型(混合型) | 生え際と頭頂部の両方から薄毛が進行し、最終的につながる。 |
分け目が薄いと感じると同時に、生え際が以前より後退した、あるいは頭頂部の地肌が目立つようになったと感じる場合、AGAの可能性は高まります。
鏡で正面と頭頂部を注意深くチェックしてみてください。
髪の毛の「質」の変化(細く、弱々しくなっていないか)
AGAのもう一つの重要なサインは、髪の毛の「質」の変化、すなわち「軟毛化(なんもうか)」です。AGAによってヘアサイクルが短縮すると、髪の毛は太く硬い「硬毛」に成長する十分な時間を与えられません。
その結果、新しく生えてくる髪が、細く、柔らかく、色の薄い「うぶ毛」のような状態になります。
分け目周辺や頭頂部を触ってみて、他の部分(側頭部や後頭部)の髪と比べて、明らかに細く、コシがなくなっている場合、AGAが進行している可能性があります。
抜け毛をチェックした際に、短く細い毛が多い場合も注意が必要です。
家族歴(遺伝)との関連性
AGAの発症には遺伝的要因が強く関わっています。具体的には、「男性ホルモンの影響の受けやすさ(DHTへの感受性)」と「5αリダクターゼの活性度」が遺伝します。
特に、母方の祖父や父方の祖父、父親に薄毛の症状が見られる場合、自身もAGAを発症する可能性は統計的に高いとされています。
もちろん、遺伝的要因があっても必ず発症するわけではなく、また家族に薄毛の方がいなくても発症するケースもありますが、一つの判断材料として家族歴を確認することは有益です。
勘違いしやすい?AGA以外の薄毛・脱毛症
分け目が薄い=すべてAGA、というわけではありません。AGA以外にも薄毛を引き起こす原因は存在します。対策を誤らないためにも、他の脱毛症との違いを知っておくことは大切です。
円形脱毛症との違い
円形脱毛症は、自己免疫疾患の一種と考えられており、突然、円形や楕円形に髪が抜け落ちるのが特徴です。
AGAが徐々に薄くなるのに対し、円形脱毛症は境界がはっきりしており、短期間でごそっと抜けることが多いです。分け目が薄く見えるというよりは、「コイン大のハゲができた」という表現が当てはまります。
原因は完全には解明されていませんが、ストレスやアレルギーなどが引き金となることがあります。
脂漏性脱毛症(頭皮の皮脂トラブル)
脂漏性脱毛症は、皮脂の過剰分泌によって引き起こされます。過剰な皮脂が毛穴を塞ぎ、酸化することで頭皮に炎症(脂漏性皮膚炎)が起こります。
頭皮が赤くなり、ベタベタしたフケやかゆみを伴うのが特徴です。この炎症が毛根にダメージを与え、抜け毛が増加します。
AGAとは異なり、ホルモンバランスだけでなく、食生活の乱れ(脂っこい食事)や不規則な生活、ストレス、使用しているシャンプーが合わないことなどが原因となります。
牽引性脱毛症(髪型による負担)
牽引性脱毛症は、髪を強く引っ張る髪型を長期間続けることで発症します。例えば、オールバックやポニーテール、きつく結ぶような髪型です。
常に特定の分け目を続けていると、その部分の毛根に継続的に物理的な負担がかかり、血行が悪化し、髪が抜けやすくなります。
AGAとは異なり、原因が物理的なものであるため、髪型を変えたり、分け目を定期的に変えたりすることで改善が期待できます。
AGAと他の主な脱毛症の比較
| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| AGA(男性型脱毛症) | 男性ホルモン(DHT)、遺伝 | 生え際・頭頂部から徐々に薄毛が進行、軟毛化。 |
| 円形脱毛症 | 自己免疫疾患(ストレス等) | 円形・楕円形に突然抜け落ちる、境界明瞭。 |
| 脂漏性脱毛症 | 皮脂の過剰分泌、炎症 | ベタつくフケ、強いかゆみ、頭皮の赤み。 |
| 牽引性脱毛症 | 物理的な牽引(髪型) | 特定の分け目や生え際が薄くなる。 |
ストレスや栄養不足による一時的な脱毛
過度な精神的ストレスや、極端なダイエットなどによる急激な栄養不足は、「休止期脱毛」を引き起こすことがあります。
髪の毛は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返していますが、強いストレスや栄養不足が起こると、多くの髪が一斉に「休止期」に入ってしまい、その数ヶ月後に大量に抜け毛が発生します。
これは特定の部位だけではなく、頭部全体で起こることが多いですが、結果として分け目が目立つように感じることもあります。原因が取り除かれれば回復することが多い、一時的な脱毛です。
髪の分け目の薄さを放置するリスク
「まだ大丈夫だろう」「そのうち治るだろう」と、分け目の薄さを放置してしまうと、取り返しのつかない事態につながる可能性があります。
特に、その原因がAGAであった場合のリスクは大きいです。
薄毛の進行と範囲の拡大
AGAは進行性の脱毛症です。つまり、何もしなければ、薄毛はゆっくりと、しかし確実に進行し続けます。
最初は気にならなかった分け目の薄さが、やがて頭頂部全体に広がり、生え際も後退していく可能性があります。
AGAの進行速度には個人差がありますが、一度失われた毛根の機能は、元に戻すのが非常に困難です。
早期であれば対策の選択肢も多いですが、進行してしまうと、育毛剤や生活習慣の改善だけでは満足のいく結果が得られにくくなります。
頭皮ダメージの深刻化
分け目が薄くなるということは、地肌を保護する髪の毛が少なくなるということです。これにより、頭皮が紫外線や乾燥、外部からの刺激に直接さらされる時間が増えます。
ダメージを受けた頭皮はさらに硬くなり、血行が悪化します。この頭皮環境の悪化が、残っている髪の成長をさらに妨げるという悪循環に陥ります。
薄毛が進行するほど、頭皮のダメージも深刻化しやすいのです。
見た目の印象と精神的ストレス
髪の毛は、その人の印象を大きく左右する要素の一つです。分け目が目立つようになると、実年齢よりも老けて見られたり、清潔感がないと誤解されたりすることを心配する方も少なくありません。
こうした外見の変化は、「人目が気になる」「自信が持てない」といったコンプレックスにつながり、大きな精神的ストレスとなります。
そして皮肉なことに、このストレス自体が血行不良を引き起こし、薄毛をさらに悪化させる要因にもなり得るのです。
対策が遅れるほど回復が困難に
AGAの対策は、「いかに現状を維持し、残っている毛根の活力を保つか」が鍵となります。
AGAによってヘアサイクルが短縮し、毛根が「うぶ毛」しか作れなくなる状態が長く続くと、最終的には毛根自体が活動を停止(線維化)してしまいます。
活動を停止した毛根から、再び太く健康な髪を生やすことは、現在の医療やケアでは非常に困難です。対策を始めるのが早ければ早いほど、毛根の活力を維持しやすく、回復の可能性も高まります。
放置することは、その回復の可能性を自ら狭めていることと同じなのです。
自宅でできる!効果的な頭皮ケアの基本
分け目の薄さが気になり始めたら、まずは自宅でできる頭皮ケアの見直しから始めましょう。
頭皮環境を整えることは、AGA対策であっても、それ以外の原因であっても、健康な髪を育てるための基本です。
正しいシャンプーの方法と選び方
シャンプーは、単に髪の汚れを落とすためだけのものではありません。頭皮の余分な皮脂や汚れを適切に除去し、頭皮環境を清潔に保つことが最大の目的です。
しかし、洗い方や選び方を間違えると、逆効果になります。
シャンプーの正しい手順
- 予洗い:シャンプーをつける前に、ぬるま湯(38度程度)で頭皮と髪を1〜2分間しっかりすすぎます。これだけで汚れの7割程度は落ちると言われています。
- 泡立て:シャンプーを手のひらに取り、少量のお湯を加えながらよく泡立てます。原液を直接頭皮につけると、刺激が強すぎたり、すすぎ残しの原因になったりします。
- 洗う:泡立てたシャンプーで、髪ではなく「頭皮」を洗います。指の腹を使い、頭皮を優しくマッサージするように動かします。爪を立ててゴシゴシ洗うのは、頭皮を傷つけるので厳禁です。
- すすぎ:最も重要な工程です。シャンプー剤が頭皮に残らないよう、洗う時の倍以上の時間をかけて、ぬるま湯で徹底的にすすぎます。生え際、耳の後ろ、襟足は特に残りやすいので注意しましょう。
シャンプー剤は、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系」や「ベタイン系」の洗浄成分を使用したものがおすすめです。特に頭皮の乾燥や刺激が気になる方は、アルコールフリーや無添加のものを選ぶと良いでしょう。
逆に、皮脂が多いと感じる方でも、洗浄力の強すぎる高級アルコール系(ラウリル硫酸〜など)のシャンプーを毎日使うと、必要な皮脂まで奪い、頭皮の乾燥や過剰な皮脂分泌を招くことがあります。
頭皮マッサージの重要性と実践
頭皮の血行は、髪の成長に直結します。頭皮が硬くなっていると感じる場合、血行が悪くなっているサインかもしれません。
頭皮マッサージは、物理的に頭皮を動かすことで血流を促進し、毛根に栄養を届きやすくする効果が期待できます。リラックス効果もあるため、ストレスの緩和にも役立ちます。
シャンプー中や、お風呂上がりの血行が良い時に行うのが効果的です。指の腹を使い、頭皮全体を優しく掴むように動かします。
「下から上へ」を意識し、側頭部、後頭部、前頭部、そして頭頂部へと、ゆっくり圧をかけながらマッサージします。爪を立てたり、強くこすったりしないよう注意しましょう。
保湿と栄養補給(育毛剤・頭皮用美容液)
顔のスキンケアと同様に、頭皮にも保湿が必要です。シャンプー後の頭皮は乾燥しやすいため、頭皮専用のローションや美容液(スカルプエッセンス)で保湿を心がけましょう。
特に乾燥が気になる方は、ヒアルロン酸やセラミドなどの保湿成分が配合されたものが適しています。
また、分け目の薄さが気になる場合は、頭皮環境を整える成分や、血行促進、毛母細胞の活性化をサポートする成分が含まれた「育毛剤」の使用を検討するのも良いでしょう。
育毛剤は、あくまで「今ある髪を健康に育てる」「抜け毛を予防する」ことを目的とした医薬部外品です。頭皮を清潔にした後に使用し、マッサージと併用するとより効果的です。
紫外線対策(帽子・日傘・スプレー)
分け目の薄い部分が紫外線を浴び続けると、頭皮は深刻なダメージを受け、光老化(シミやシワの原因)や乾燥、炎症を引き起こします。これが薄毛をさらに進行させる原因となります。
外出時には、帽子や日傘を使用することを習慣づけましょう。特に夏場や長時間の屋外活動では必須です。最近では、髪や頭皮にも使えるスプレータイプの日焼け止めも市販されています。
これらを活用し、分け目を紫外線から守る意識を持つことが大切です。
育毛剤の選び方と正しい使い方
頭皮ケアの一環として育毛剤を取り入れることは、分け目の薄毛対策として有効な手段の一つです。しかし、多種多様な製品があるため、どれを選べばよいか迷う方も多いでしょう。
ここでは、育毛剤の選び方と効果的な使い方を解説します。
自分の頭皮タイプ(乾燥肌・脂性肌)を知る
育毛剤もスキンケア用品と同じで、自分の頭皮タイプに合ったものを選ぶことが重要です。
頭皮が乾燥しがちな方(乾燥肌)が、皮脂抑制効果の強いさっぱりタイプの育毛剤を使うと、さらに乾燥が進んでしまう可能性があります。
この場合は、保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミドなど)が豊富に含まれた、しっとりタイプのものが適しています。
逆に、頭皮がベタつきやすい方(脂性肌)は、皮脂の過剰分泌を抑える成分(ビタミンC誘導体、ピリドキシン塩酸塩など)や、抗炎症成分(グリチルリチン酸2Kなど)が含まれ、さっぱりとした使用感のものを選ぶと良いでしょう。
育毛剤に含まれる主な有効成分
日本の育毛剤(医薬部外品)には、厚生労働省が効果・効能を認めた「有効成分」が配合されています。自分の悩みに合った成分が含まれているかを確認しましょう。
育毛剤の主な有効成分と期待される働き
| 成分カテゴリー | 主な成分例 | 期待される働き |
|---|---|---|
| 血行促進 | センブリエキス、酢酸トコフェロール(ビタミンE誘導体)、ニコチン酸アミド | 頭皮の血流を改善し、毛根への栄養供給をサポートする。 |
| 毛母細胞の活性化 | t-フラバノン、アデノシン(一部製品)、パントテニルエチルエーテル | 髪の毛を作る毛母細胞の働きを活発にし、発毛を促す。 |
| 抗炎症・殺菌 | グリチルリチン酸ジカリウム、ピロクトンオラミン | フケやかゆみ、炎症を抑え、頭皮環境を整える。 |
| 皮脂分泌抑制 | ビタミンC誘導体、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) | 過剰な皮脂の分泌をコントロールする。 |
※なお、AGAの進行を抑制する「ミノキシジル」(発毛剤・第1類医薬品)や「フィナステリド」(内服薬・医療用医薬品)は、これらの育毛剤(医薬部外品)とは区別されます。
効果を実感するための継続期間と塗布量
育毛剤は、使用してすぐに髪が生えたり、太くなったりするものではありません。髪の毛は1ヶ月に約1cmしか伸びず、ヘアサイクル全体で見ると数年単位の時間がかかります。
育毛剤の効果は、このヘアサイクルを正常化し、頭皮環境をじっくりと改善していくことで現れます。そのため、最低でも6ヶ月間は、毎日継続して使用することが大切です。
また、使用する際は、製品に記載されている「用法・用量」を必ず守ってください。
「早く効果を出したい」と一度に大量につけても、効果が上がるわけではなく、かえって頭皮トラブルの原因になることもあります。
適量を、気になる分け目だけでなく、頭皮全体に行き渡るように塗布することが重要です。
使用時の注意点と副作用の可能性
育毛剤は医薬部外品であり、医薬品に比べると副作用のリスクは低いですが、体質や頭皮の状態によっては、アレルギー反応(かゆみ、赤み、発疹など)が起こる可能性があります。
特にアルコール(エタノール)が多く含まれている製品は、敏感肌の方には刺激となることがあります。
使用前には必ずパッチテスト(腕の内側などに少量塗布し、24時間様子を見ること)を行うことを推奨します。使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、水かぬるま湯で洗い流してください。
症状が改善しない場合は、皮膚科専門医に相談しましょう。
頭皮環境を整える生活習慣の改善
どれだけ高価な育毛剤を使用しても、体の中からのケア、すなわち生活習慣が乱れていては、その効果は半減してしまいます。健康な髪は、健康な体から作られます。
分け目の薄毛対策は、日々の生活を見直すことから始まります。
髪の成長に必要な栄養素と食事バランス
髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。したがって、良質なタンパク質の摂取は、髪の健康に必要です。肉、魚、卵、大豆製品などをバランスよく食事に取り入れましょう。
また、タンパク質がケラチンに再合成される際には、「亜鉛」が必要です。亜鉛は牡蠣、レバー、牛肉(赤身)などに多く含まれます。
さらに、頭皮の血行を良くし、皮脂の分泌をコントロールする「ビタミンB群」(レバー、マグロ、納豆など)や、抗酸化作用があり血行を促進する「ビタミンE」(ナッツ類、アボカドなど)、コラーゲンの生成を助ける「ビタミンC」(野菜、果物)も重要です。
髪の健康をサポートする主な栄養素
- タンパク質(髪の主成分)
- 亜鉛(タンパク質の合成を助ける)
- ビタミンB群(代謝・血行促進)
- ビタミンE(血行促進・抗酸化)
- ビタミンC(抗酸化・コラーゲン生成)
これらの栄養素を特定の食品で偏って摂るのではなく、様々な食材を組み合わせた「バランスの良い食事」を一日三食、規則正しく摂ることが、健康な頭皮と髪を育てる基盤となります。
質の高い睡眠の確保
髪の毛の成長や頭皮の新陳代謝は、私たちが寝ている間に行われます。特に、入眠後(特にノンレム睡眠時)に分泌される「成長ホルモン」は、毛母細胞の分裂を促し、髪の成長に深く関わっています。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、成長ホルモンの分泌が減少し、髪の成長が妨げられ、頭皮の修復も十分に行われません。
質の高い睡眠を確保するためには、毎日決まった時間に寝起きする、寝る前のスマートフォンやPCの使用を控える、適度な運動を心がける、リラックスできる環境を整える(寝室の温度・湿度、照明など)ことが大切です。
睡眠と髪の成長
| 要素 | 髪への影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 成長ホルモン | 毛母細胞の分裂を促進し、髪の成長を促す。 | 入眠後3時間(特に深いノンレム睡眠時)に多く分泌される。 |
| 睡眠不足 | ホルモン分泌低下、自律神経の乱れ、血行不良。 | 6〜8時間の十分な睡眠時間を確保する。 |
| 睡眠の質 | 浅い眠りでは成長ホルモンが十分に分泌されない。 | 就寝前のリラックス、寝室環境の整備。 |
ストレス管理と適度な運動
現代社会においてストレスをゼロにすることは困難ですが、過度なストレスは自律神経のバランスを崩します。自律神経のうち「交感神経」が優位になると、血管が収縮し、頭皮の血行が悪化します。
これが毛根への栄養供給を妨げ、抜け毛や薄毛の原因となります。 自分なりのストレス解消法を見つけることが重要です。
趣味に没頭する時間を作る、ゆっくり入浴する、友人と話すなど、心身ともにリラックスできる時間を持つようにしましょう。
また、適度な運動は、ストレス解消に非常に効果的です。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、全身の血行を促進し、頭皮への血流改善にもつながります。
運動を習慣化することで、自律神経が整いやすくなり、睡眠の質の向上も期待できます。
喫煙・過度な飲酒の見直し
喫煙は、分け目の薄毛対策において大きな妨げとなります。タバコに含まれるニコチンは、血管を強力に収縮させる作用があります。これにより頭皮の毛細血管が収縮し、深刻な血行不良を引き起こします。
また、タバコは体内で大量の活性酸素を発生させ、ビタミンCを破壊するため、頭皮や毛根の老化を早めます。 過度な飲酒も避けるべきです。
アルコールが肝臓で分解される際には、ビタミンやアミノ酸が大量に消費されます。これらは髪の毛の生成に必要な栄養素でもあるため、結果として髪への栄養が不足しがちになります。
また、アルコールの過剰摂取は、AGAの原因物質であるDHTを増加させる可能性も指摘されています。適度な飲酒(節度ある適度な量)を心がけ、休肝日を設けることが賢明です。
喫煙・過度な飲酒が髪に与える影響
| 項目 | 髪(頭皮)への主な影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 喫煙(ニコチン) | 深刻な血行不良、栄養不足、老化促進。 | 血管の強力な収縮作用、ビタミンCの破壊。 |
| 過度な飲酒 | 栄養不足(アミノ酸・ビタミン)、AGA助長懸念。 | アルコール分解時に栄養素を大量消費、DHT増加の可能性。 |
髪の分け目が薄いと感じたら(よくある質問)
最後に、髪の分け目が薄いと感じた方から多く寄せられる質問にお答えします。
- 分け目を変えれば薄毛は改善しますか?
-
いつも同じ分け目にしていると、その部分が紫外線のダメージを受けやすくなったり、牽引性脱毛症の原因になったりすることがあります。
定期的に分け目を変えることは、これらのリスクを分散させ、頭皮の負担を軽減する上で有効です。
しかし、もし薄毛の原因がAGAや頭皮環境の悪化、栄養不足などにある場合、分け目を変えるだけで薄毛が根本的に改善することはありません。
あくまで頭皮ケアの一環として捉え、他の対策と並行して行うことが大切です。
- 育毛剤はいつから効果が出ますか?
-
育毛剤は、髪の成長サイクル(ヘアサイクル)に働きかけ、頭皮環境を整えることで、抜け毛を防ぎ、健康な髪の成長をサポートするものです。
ヘアサイクルは数年単位の長い周期であり、目に見える変化を実感するまでには時間がかかります。
個人差はありますが、一般的に最低でも6ヶ月間は、毎日継続して使用することが推奨されます。即効性を期待するものではなく、地道なケアを続けることが重要です。
- 食事だけで髪は太くなりますか?
-
健康な髪を育てるためには、バランスの取れた食事が非常に重要です。髪の主成分であるタンパク質や、亜鉛、ビタミンB群などの栄養素が不足すれば、髪は細く弱々しくなります。
その意味で、食事内容を改善することで、髪質が改善し、ハリやコシが出て太くなる可能性は十分にあります。
ただし、もし薄毛の原因がAGAである場合、食事改善だけでAGAの進行を止めることは困難です。
食事はあくまで健康な髪の「材料」を供給するものであり、AGA対策(血行促進やホルモンへのアプローチ)と並行して行う必要があります。
- 専門のクリニックに行くべき目安は?
-
以下のいずれかに当てはまる場合は、セルフケアだけでなく、皮膚科やAGA専門のクリニックに相談することを推奨します。
- 分け目だけでなく、生え際の後退や頭頂部の薄毛も明らかに進行している。
- 抜け毛が急激に増え、短く細い毛が多い。
- 頭皮に強いかゆみ、赤み、痛み、大量のフケなど、明らかな異常がある。
- セルフケア(育毛剤や生活習慣改善)を6ヶ月以上続けても、薄毛の進行が止まらないか、悪化している。
- 薄毛の原因がAGAなのか他の脱毛症なのか、自分では判断できず不安が強い。
専門医の診断を受けることで、薄毛の正確な原因を知ることができ、自分に合った適切な対策(医薬品の処方を含む)についてアドバイスを受けることができます。
Reference
OLSEN, Elise A., et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2005, 52.2: 301-311.
YORK, Katherine, et al. A review of the treatment of male pattern hair loss. Expert opinion on pharmacotherapy, 2020, 21.5: 603-612.
YORK, Katherine, et al. Treatment review for male pattern hair-loss. Expert Opin Pharmacother, 2020, 21.5: 603-612.
REDMOND, Leah C., et al. Male pattern hair loss: Can developmental origins explain the pattern?. Experimental Dermatology, 2023, 32.7: 1174-1181.
HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.
BLUME‐PEYTAVI, Ulrike, et al. S1 guideline for diagnostic evaluation in androgenetic alopecia in men, women and adolescents. British Journal of Dermatology, 2011, 164.1: 5-15.
BHAT, Yasmeen Jabeen, et al. Female pattern hair loss—an update. Indian dermatology online journal, 2020, 11.4: 493-501.
SPRINGER, Karyn; BROWN, Matthew; STULBERG, Daniel L. Common hair loss disorders. American family physician, 2003, 68.1: 93-102.