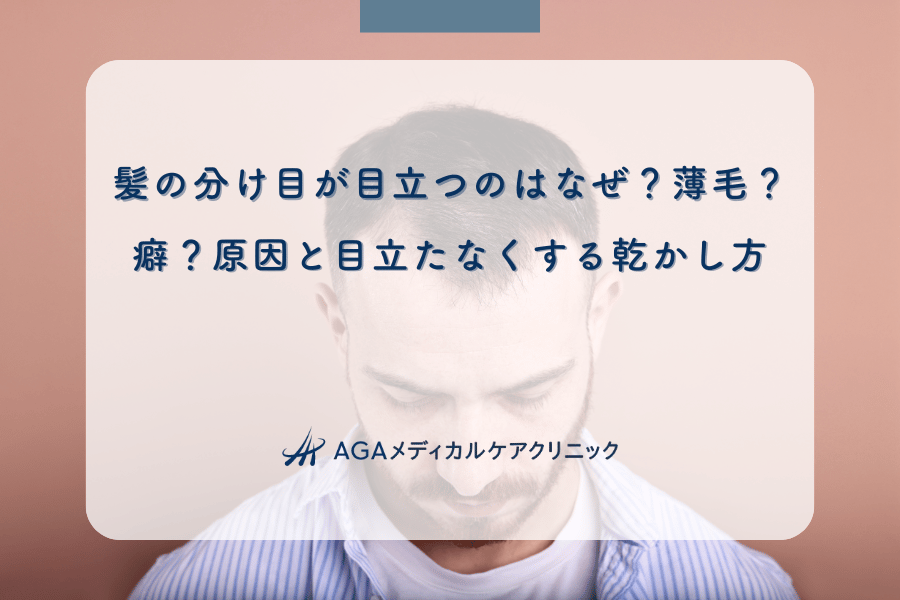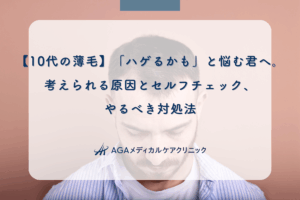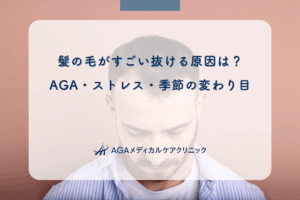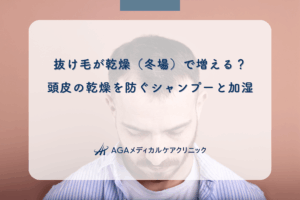ふと鏡を見たとき、髪の分け目が以前よりくっきりと目立つようになったと感じることはありませんか。
「もしかして薄毛が始まったのでは?」と不安になったり、「単なる髪の癖だろう」と思おうとしたり、多くの方が悩む問題です。
特に男性の場合、分け目の目立ちは生え際や頭頂部と並んで、見た目の印象を大きく左右します。
分け目が目立つ原因は一つではなく、生まれつきの癖、長年同じ分け目を続けたことによる頭皮への負担、あるいは薄毛の初期サインである可能性も否定できません。
この記事では、髪の分け目が目立つ原因を多角的に探り、薄毛との関連性、そして今日から実践できる目立たなくする乾かし方や頭皮ケアの方法を詳しく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪の分け目が目立つのは「癖」か「薄毛」か
髪の分け目が目立つと感じたとき、多くの人がまず「癖」なのか「薄毛」なのかという二択で悩みます。どちらの可能性もあるため、一概にどちらが原因とは言えません。
しかし、それぞれの特徴を知ることで、ご自身の状態に近いものを判断する手助けになります。まずは分け目が目立つ背景にある基本的な要因を見ていきましょう。
分け目が目立つ主な要因
分け目が目立つ要因は、大きく分けて三つ考えられます。一つ目は、長期間同じ場所で髪を分け続けることによる「癖」です。髪の毛は一定方向に流れ続けると、その形を記憶しやすくなります。
二つ目は、髪の毛そのものが細くなったり、密度が低下したりする「薄毛」の進行です。これにより地肌が透けて見えやすくなります。三つ目は、頭皮環境の悪化です。
頭皮が乾燥したり、逆に皮脂が過剰になったりすると、髪の健康が損なわれ、分け目が目立ちやすくなることがあります。
分け目が目立つ要因の比較
| 要因 | 特徴 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 髪の癖 | 同じ場所で分かれやすい。髪を濡らすとリセットされることが多い。 | 分け目を変える、乾かし方を工夫する。 |
| 薄毛の進行 | 分け目部分の地肌が広範囲に見える。髪が細く弱々しい。 | 専門家への相談、育毛剤の使用、生活習慣の見直し。 |
| 頭皮環境の悪化 | 頭皮に赤み、フケ、かゆみなどがある。 | シャンプーの見直し、頭皮ケア。 |
いつも同じ分け目による頭皮への負担
毎日同じ場所で髪を分けていると、その部分の頭皮は常に外部からの刺激にさらされることになります。特に注意したいのが紫外線です。
分け目部分は頭皮が直接日光を浴びやすいため、紫外線のダメージが蓄積しやすい場所です。紫外線は頭皮を乾燥させ、炎症を引き起こすだけでなく、毛母細胞の働きを弱める可能性も指摘されています。
長期間同じ分け目を続けることは、その特定の部分の頭皮を集中的にいじめることになり、結果としてその部分の髪が弱り、分け目が目立ちやすくなる悪循環を生む可能性があります。
髪の生え癖とつむじの位置
生まれつきの髪の生え方やつむじの位置も、分け目の目立ちやすさに関係します。つむじは髪の毛が渦を巻くように生えている部分であり、その流れが髪全体の方向性を決定づけることが多いです。
つむじが二つある方や、特定方向に強い毛流がある方は、どうしても髪が分かれやすい部分が決まってしまい、分け目が目立ちやすくなることがあります。
これは髪の癖であり、薄毛とは直接関係ない場合も多いですが、目立つこと自体が悩みとなるケースです。この場合、薄毛対策とは異なるアプローチ、つまりスタイリングや乾かし方の工夫が中心となります。
分け目が目立つ原因を深掘り
分け目が目立つ理由は、単純な癖や薄毛の始まりだけではありません。日々の生活の中で無意識に行っていることや、体内の変化が影響している可能性もあります。
ここでは、さらに深く分け目が目立つ原因を探っていきます。
頭皮環境の悪化(乾燥・皮脂過剰)
頭皮は髪の毛が生える土壌です。この土壌の状態が悪ければ、健康な髪は育ちません。
頭皮が乾燥すると、フケが発生しやすくなるだけでなく、外部からの刺激に弱くなり、かゆみや炎症を引き起こすことがあります。
逆に、皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が詰まりやすくなり、脂漏性皮膚炎などのトラブルを招くこともあります。
皮脂が毛穴に詰まると、髪の毛の正常な成長が妨げられ、髪が細くなったり、抜けやすくなったりして、結果的に分け目が目立って見えるようになります。
洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、洗いすぎ、逆に洗わなすぎなどが原因となることが多いです。
加齢による髪の変化
年齢を重ねるとともに、髪の毛にも変化が現れます。髪の毛一本一本が細くなる「菲薄化(ひはくか)」や、髪の毛のハリやコシが失われることは、加齢による自然な変化の一つです。
髪の毛が細くなると、同じ本数でも全体のボリュームが減少し、地肌が透けて見えやすくなります。
また、髪にハリやコシがなくなると、根元が立ち上がりにくくなり、分け目がぺたんと寝てしまい、より目立つようになります。
これは男性ホルモンの影響によるAGAとは異なる、加齢性の変化ですが、分け目の目立ちに寄与する大きな要因です。
牽引(けんいん)性脱毛症の可能性
牽引性脱毛症とは、髪の毛が長時間強く引っ張られることによって引き起こされる脱毛症です。
いつも同じ場所できつく髪を結んだり、特定のヘアスタイルを長期間続けたりすることで、毛根に継続的な負担がかかり、その部分の髪が抜けやすくなります。
男性の場合、長髪の方がポニーテールやお団子ヘアを日常的に行っている場合に注意が必要です。
この場合、分け目そのものというより、髪を引っ張っている生え際や分け目のラインに沿って薄くなる傾向があります。
原因がはっきりしているため、髪型を変えたり、髪を結ぶ強さを緩めたりすることで改善が期待できます。
生活習慣の乱れが及ぼす影響
髪の毛の健康は、体全体の健康状態と密接に関連しています。栄養バランスの偏った食事、睡眠不足、過度なストレス、喫煙や過度な飲酒などは、すべて髪の健康に悪影響を及ぼします。
髪の毛は主にタンパク質でできていますが、その成長にはビタミンやミネラルも必要です。これらの栄養素が不足すると、健康な髪が作られにくくなります。
また、睡眠不足やストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こします。
血行が悪くなると、髪の成長に必要な栄養素が毛根まで届きにくくなり、髪が弱々しくなり、分け目が目立つ原因となります。
分け目と薄毛(AGA)の危険なサイン
分け目が目立つことが、単なる癖や一時的な頭皮トラブルではなく、AGA(男性型脱毛症)のサインである可能性も考慮する必要があります。
AGAは進行性の脱毛症であり、早期の対策が重要です。分け目の状態と合わせて、他のサインがないか確認しましょう。
分け目ハゲと呼ばれる状態
「分け目ハゲ」とは、分け目部分の地肌が目立ち、そこから薄毛が進行しているように見える状態を指す俗称です。
長年同じ分け目を続けることで、その部分の頭皮がダメージを受けたり、癖が強くついたりして目立つ場合もありますが、AGAが頭頂部から進行する「O字型」の初期段階として、分け目が広がって見えるケースもあります。
分け目の幅が以前より明らかに広がった、分け目部分の髪の毛が細く、コシがなくなったと感じる場合は注意が必要です。
AGA(男性型脱毛症)の初期症状との違い
AGAは、主に男性ホルモンの影響で、思春期以降に発症する進行性の脱毛症です。AGAの典型的な症状は、「生え際の後退(M字型)」と「頭頂部の薄毛(O字型)」です。
もし分け目が目立つと同時に、生え際が後退してきた、または頭頂部(つむじ周り)の地肌が透けて見えるようになってきた場合、AGAの可能性が高まります。
単に分け目が目立つだけでなく、これらのAGAの特徴的な症状が併発していないかを確認することが重要です。
AGAの初期症状チェック
| チェック項目 | 状態 | AGAの可能性 |
|---|---|---|
| 生え際 | 以前より後退した、M字部分が深くなった。 | 高い |
| 頭頂部 | つむじ周りの地肌が透けて見えるようになった。 | 高い |
| 髪の質 | 抜け毛が細く短い。髪全体のハリやコシがなくなった。 | 高い |
| 分け目 | 分け目を変えても、全体のボリュームが少なく地肌が見える。 | 中〜高い |
頭皮の色や硬さのチェック
健康な頭皮は、青白く、適度な弾力があります。しかし、血行が悪くなっていたり、炎症を起こしていたりすると、頭皮の状態に変化が現れます。
頭皮が赤い場合は炎症を、茶色っぽい場合は血行不良や代謝の低下を示している可能性があります。また、頭皮を指で動かしたときに、硬く突っ張った感じがする場合も血行不良が疑われます。
血行不良は髪の成長に必要な栄養素が届きにくくなるため、薄毛の進行と関連が深いです。分け目部分だけでなく、頭皮全体の健康状態を確認してみましょう。
抜け毛の質や量の変化
健康な人でも一日におおよそ50本から100本程度の髪の毛は自然に抜けます。しかし、抜け毛の量が急に増えた場合や、抜けた毛の質に変化が見られる場合は注意が必要です。
AGAが進行すると、髪の毛が十分に成長する前に抜けてしまう「ヘアサイクルの乱れ」が生じます。そのため、太く長い毛髪ではなく、細く短い、弱々しい抜け毛が増える傾向があります。
シャンプー時や朝起きた時の枕元の抜け毛をチェックし、細く短い毛が増えていないか確認することも、薄毛のサインを見極める上で役立ちます。
分け目を目立たなくする毎日のシャンプー習慣
分け目を目立たせる原因の一つである頭皮環境の悪化は、毎日のシャンプー習慣を見直すことで改善が期待できます。間違ったケアは、かえって頭皮にダメージを与えているかもしれません。
正しい知識で、健やかな頭皮環境を目指しましょう。
頭皮ケアを意識したシャンプーの選び方
シャンプーの主な目的は、頭皮の汚れや余分な皮脂を落とすことです。しかし、洗浄力が強すぎると、頭皮に必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥やバリア機能の低下を招きます。
逆に洗浄力が弱すぎると、皮脂や汚れが残り、毛穴詰まりの原因となります。ご自身の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合った洗浄成分(アミノ酸系、石鹸系など)を選ぶことが重要です。
また、フケやかゆみが気になる場合は、有効成分が配合された薬用シャンプー(スカルプシャンプー)を選ぶのも良いでしょう。
頭皮タイプ別シャンプー選びのポイント
| 頭皮タイプ | 特徴 | おすすめの洗浄成分 |
|---|---|---|
| 乾燥肌・敏感肌 | フケ(カサカサ)が出やすい、かゆみを感じやすい。 | アミノ酸系(ココイルグルタミン酸など) |
| 脂性肌(オイリー肌) | 頭皮がベタつきやすい、フケ(ベタベタ)が出やすい。 | 石鹸系、高級アルコール系(適度な洗浄力のもの) |
| 普通肌 | 目立ったトラブルがない。 | アミノ酸系、またはバランスの取れたもの |
汚れを落とす正しい洗い方の手順
効果的なシャンプーは、洗い方にあります。まず、シャンプーをつける前に、お湯だけで頭皮と髪をしっかりと予洗い(湯シャン)します。これだけで汚れの多くは落ちます。
次に、シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。洗う際は、爪を立てずに指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく揉み洗いします。
特に皮脂の多い頭頂部や生え際は丁寧に洗いましょう。髪の毛自体は、泡が通過するだけで汚れは落ちるため、ゴシゴシと擦り合わせる必要はありません。
すすぎ残しが頭皮に与えるダメージ
シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しは、頭皮トラブルの大きな原因となります。
洗浄成分が頭皮に残ると、それが刺激となってかゆみや炎症を引き起こしたり、毛穴に詰まって雑菌の繁殖を招いたりします。
洗う時間よりもすすぐ時間を長く取ることを意識し、シャワーのお湯でしっかりと洗い流しましょう。
特に、耳の後ろや襟足、生え際などはすすぎ残しが多い部分なので、意識して丁寧にすすぐことが大切です。
洗髪後の頭皮保湿の重要性
洗顔後に化粧水で肌を保湿するように、洗髪後の頭皮も保湿ケアが重要です。シャンプー後の頭皮は、汚れと共に皮脂も洗い流され、乾燥しやすい状態になっています。
頭皮が乾燥すると、バリア機能が低下したり、逆に皮脂が過剰に分泌されたりすることがあります。
頭皮専用のローションや育毛剤などを使用し、うるおいを補給することで、頭皮環境を健やかに保ち、フケやかゆみを防ぐ助けになります。
特に乾燥が気になる方や、育毛剤を使用している方は、保湿の観点からもケアを続けると良いでしょう。
【実践】分け目をぼかす髪の乾かし方
分け目を目立たなくするためには、髪の乾かし方が非常に重要です。髪は濡れている状態から乾く瞬間に形が決まります。
この習性を利用し、根元を立ち上げることで、分け目をふんわりとぼかすことができます。今日から試せる具体的な方法を紹介します。
タオルドライで水分をしっかり取る
ドライヤーの時間を短縮し、髪への熱ダメージを減らすために、まずはタオルドライで髪の水分をしっかり取り除きます。このとき、ゴシゴシと強くこすると髪や頭皮を傷める原因になるため注意が必要です。
タオルで頭皮を優しくマッサージするように水分を吸い取り、髪の毛はタオルで挟み込むようにしてポンポンと叩いて水分を取ります。
特に根元部分の水分をしっかり取っておくことが、後のドライヤー作業を効率的にするポイントです。
ドライヤーは根元から乾かす
ドライヤーをかける際、多くの人が毛先から乾かしがちですが、分け目を目立たなくするためには「根元」から乾かすことが鉄則です。
髪の根元が濡れたままだと、髪の重みで寝てしまい、ぺたんとした印象になって分け目がくっきりついてしまいます。
まずは頭皮全体、特に分け目をつけたくない部分の根元に温風を当てて、しっかりと乾かします。
根元を立ち上げるテクニック
分け目をぼかす最大のポイントは、根元を立ち上げることです。いつも分けている分け目とは逆方向からドライヤーの風を当てたり、髪の毛をかき上げるように指でジグザグと動かしながら乾かしたりします。
例えば、いつも左側で分けているなら、髪全体を右側に流しながら根元を乾かし、次に右側で分けているなら左側に流しながら乾かします。
こうすることで、特定の分け目がつくのを防ぎ、根元がふんわりと立ち上がります。
ある程度乾いたら、今度は上から(頭頂部から)前に向かって髪を下ろすように風を当てると、全体のボリュームが出やすくなります。
乾かし方の比較
| ポイント | NGな乾かし方 | OKな乾かし方(分け目をぼかす) |
|---|---|---|
| 乾かす順番 | 毛先から乾かす。 | 頭皮、根元から乾かす。 |
| 風の当て方 | いつも同じ方向から当てる。 | 分け目と逆方向から当てる。髪をかき混ぜるように乾かす。 |
| 仕上がり | 分け目がくっきりつき、根元が寝てしまう。 | 根元が立ち上がり、分け目がふんわりとぼける。 |
冷風でスタイルをキープする
髪の毛は、温風で温められると形が変えやすくなり、冷風で冷やされるとその形で固定される性質があります。
全体が8割から9割程度乾き、根元が立ち上がったら、最後にドライヤーの冷風モードに切り替えます。立ち上げた根元や全体のスタイルに冷風を当てることで、ふんわりとした状態をキープしやすくなります。
このひと手間が、スタイルの持続性に大きな差を生みます。
乾かし方以外の対策 分け目を変える習慣作り
髪の乾かし方を工夫するのと同時に、日常生活で分け目を変える習慣を取り入れることも、分け目を目立たなくするために有効です。
同じ場所ばかりに負担がかかるのを防ぎ、髪の癖をリセットしましょう。
定期的に分け目を変えるメリット
定期的に分け目を変えることには、複数のメリットがあります。第一に、特定の分け目が固定化するのを防ぎます。これにより、根元が立ち上がりやすくなり、全体のボリューム感を出しやすくなります。
第二に、同じ場所の頭皮が常に紫外線や外部刺激にさらされるのを防ぎ、頭皮ダメージを分散させることができます。これにより、分け目部分の頭皮環境を健やかに保つ助けになります。
分け目を変える主な利点
- 根元のボリュームアップ
- 特定箇所の頭皮ダメージ(紫外線など)の分散
- 髪の「癖」のリセット
分け目を変える頻度とタイミング
分け目を変える頻度に厳密な決まりはありませんが、例えば1ヶ月に一度や、数週間に一度など、ご自身でルールを決めて試してみるのが良いでしょう。
あまり頻繁に変えすぎても新しい癖がつきにくいですが、長期間同じままにするのは避けるべきです。タイミングとしては、美容室で髪を切った時や、シャンプー後のスタイリング時などが変えやすいでしょう。
最初は違和感があるかもしれませんが、乾かし方を工夫することで徐々に馴染んできます。
癖がついた分け目をリセットする方法
長年同じ分け目を続けていると、強い癖がついてしまい、なかなか変えられないことがあります。この癖をリセットするには、髪が濡れている状態で行うのが最も効果的です。
シャンプー後、タオルドライした髪を、新しい分け目をつけたい方向とは「逆」の方向にまず乾かします。
根元が乾いてきたら、本来つけたい分け目にコーム(櫛)などで軽く線を入れ、その部分にドライヤーの温風を当て、最後に冷風で固定します。
これを数日間繰り返すことで、徐々に新しい分け目に馴染んできます。
就寝中の摩擦対策
睡眠中、枕と頭皮や髪がこすれることで摩擦が生じ、髪が傷んだり、特定の分け目がつきやすくなったりすることがあります。
特に髪が半乾きのまま寝てしまうと、摩擦が大きくなるだけでなく、雑菌が繁殖しやすくなり頭皮環境にも悪影響です。就寝前には髪をしっかり乾かすことが基本です。
また、枕カバーの素材をシルクやサテンなどの摩擦が少ないものに変えることも、髪や頭皮への負担を減らす一つの方法です。
健やかな髪を育むためのインナーケア
分け目を目立たなくするための乾かし方や頭皮ケア(外的アプローチ)と同時に、体の内側から髪の健康をサポートするインナーケアも非常に重要です。
バランスの取れた食事、良質な睡眠、ストレス管理が健やかな髪を育む基盤となります。
髪の成長に必要な栄養素
髪の毛は主に「ケラチン」というタンパク質で構成されています。そのため、良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)の摂取は必須です。
また、タンパク質が髪の毛に合成されるのを助ける「亜鉛」(牡蠣、レバー、ナッツ類など)や、頭皮の血行を促進し、栄養素を運ぶ働きをサポートする「ビタミンE」(アーモンド、アボカドなど)、頭皮環境を整える「ビタミンB群」(豚肉、マグロ、バナナなど)も重要です。
これらの栄養素をバランスよく摂取することを心がけましょう。
髪の健康をサポートする主な栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促す。皮脂のバランスを整える。 | 豚肉、レバー、マグロ、カツオ、バナナ |
質の高い睡眠をとる工夫
髪の毛の成長は、成長ホルモンが活発に分泌される睡眠中に行われます。特に、入眠後最初の深いノンレム睡眠(ゴールデンタイムとも呼ばれる)が重要です。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられ、髪の健やかな成長が阻害されます。
毎日決まった時間に寝起きする、就寝前のスマートフォン操作を控える、リラックスできる環境を整えるなど、質の高い睡眠を確保するための工夫をしましょう。
ストレスとの上手な付き合い方
過度なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行不良を引き起こします。血行が悪くなると、毛根に十分な栄養が届かず、髪の成長に悪影響を与えます。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、皮脂の過剰分泌などを引き起こすこともあります。現代社会でストレスをゼロにすることは難しいですが、自分なりの解消法を見つけることが大切です。
ストレス管理のヒント
- 軽い運動(ウォーキング、ストレッチ)
- 趣味に没頭する時間を作る
- ゆっくりと入浴する
- 親しい人と話す
血行を促進する適度な運動
適度な運動は、全身の血行を促進するために非常に有効です。血行が良くなれば、頭皮の末端にある毛細血管まで血液が巡り、髪の成長に必要な栄養素と酸素が毛根に届きやすくなります。
ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、ストレス解消にも役立つため特におすすめです。
デスクワークが多い方は、合間にストレッチをするだけでも、血流の改善に役立ちます。運動を習慣化し、血流の良い状態を保ちましょう。
よくある質問
ここでは、髪の分け目が目立つことに関して多くの方が抱く疑問にお答えします。
- 髪の分け目を毎日変えるのは良いことですか?
-
毎日必ず変えなければならない、ということはありません。
しかし、長期間(数年単位で)全く同じ分け目を続けることは、その部分の頭皮への負担(特に紫外線ダメージ)が集中するため、避けた方が賢明です。
数週間から数ヶ月に一度程度、意識的に分け目を変えたり、スタイリングで分け目をぼかしたりする日を作ることをおすすめします。
無理のない範囲で、頭皮への負担を分散させる意識を持つことが大切です。
- 分け目が目立つのに育毛剤は使った方が良いですか?
-
分け目が目立つ原因が、頭皮環境の悪化(乾燥や血行不良)や、髪のハリ・コシの低下にある場合、頭皮環境を整えたり、毛髪に栄養を与えたりする育毛剤(医薬部外品)の使用は一つの選択肢です。
ただし、分け目の目立ちがAGA(男性型脱毛症)の進行によるものである可能性が疑われる場合は、育毛剤では進行を止める効果は期待できません。
AGAが疑われる(生え際後退や頭頂部の薄毛も伴う)場合は、専門のクリニックに相談することを推奨します。
- ドライヤーを使わずに自然乾燥させるのはだめですか?
-
自然乾燥はおすすめできません。髪が濡れたままの状態が続くと、頭皮で雑菌が繁殖しやすくなり、かゆみやフケ、臭いの原因となります。
これは頭皮環境の悪化につながり、分け目が目立つ遠因にもなり得ます。また、髪は濡れているときが最もダメージを受けやすい状態です。
自然乾燥ではキューティクルが開いたままになり、髪の水分やタンパク質が流出しやすくなります。シャンプー後は、できるだけ速やかにドライヤーで頭皮から乾かすことが、頭皮と髪の健康のために重要です。
根元を立ち上げるように乾かせば、分け目をぼかす効果も期待できます。
- 帽子をかぶると分け目が目立ちやすくなりますか?
-
帽子をかぶること自体が、直接的に分け目を目立たせる原因にはなりにくいです。むしろ、紫外線から頭皮を守るという点では非常に有効です。
ただし、長時間帽子をかぶり続けることで頭皮が蒸れると、雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮環境が悪化する可能性があります。
また、サイズの合わないきつい帽子をかぶり続けると、頭皮が圧迫されて血行不良になることも考えられます。
帽子をかぶる際は、適度に脱いで通気性を良くしたり、帰宅後は早めにシャンプーで清潔にしたりするなど、蒸れ対策を心がけましょう。
Reference
ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.
OLSEN, Elise A. The midline part: an important physical clue to the clinical diagnosis of androgenetic alopecia in women. Journal of the American Academy of Dermatology, 1999, 40.1: 106-109.
VAN NESTE, Dominique. Female patients complaining about hair loss: documentation of defective scalp hair dynamics with contrast‐enhanced phototrichogram. Skin Research and Technology, 2006, 12.2: 83-88.
WHITING, David A. Possible mechanisms of miniaturization during androgenetic alopecia or pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2001, 45.3: S81-S86.
ORFANOS, C. E. Androgenetic alopecia: clinical aspects and treatment. In: Hair and hair diseases. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990. p. 485-527.
PRICE, Vera H. Androgenetic alopecia in women. In: Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. Elsevier, 2003. p. 24-27.
CASH. The psychosocial consequences of androgenetic alopecia: a review of the research literature. British Journal of Dermatology, 1999, 141.3: 398-405.
SOGA, Shigeyoshi, et al. MR imaging of hair and scalp for the evaluation of androgenetic alopecia. Magnetic Resonance in Medical Sciences, 2021, 20.2: 160-165.
VISHU, Michelle. Trichoscopic Analysis of Female Pattern Hair Loss and Correlation of Findings with Disease Severity: A Cross-Sectional Study. 2019. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).
LEROY, Thérèse; VAN NESTE, Dominique. Contrast enhanced phototrichogram pinpoints scalp hair changes in androgen sensitive areas of male androgenetic alopecia. Skin Research and Technology, 2002, 8.2: 106-111.