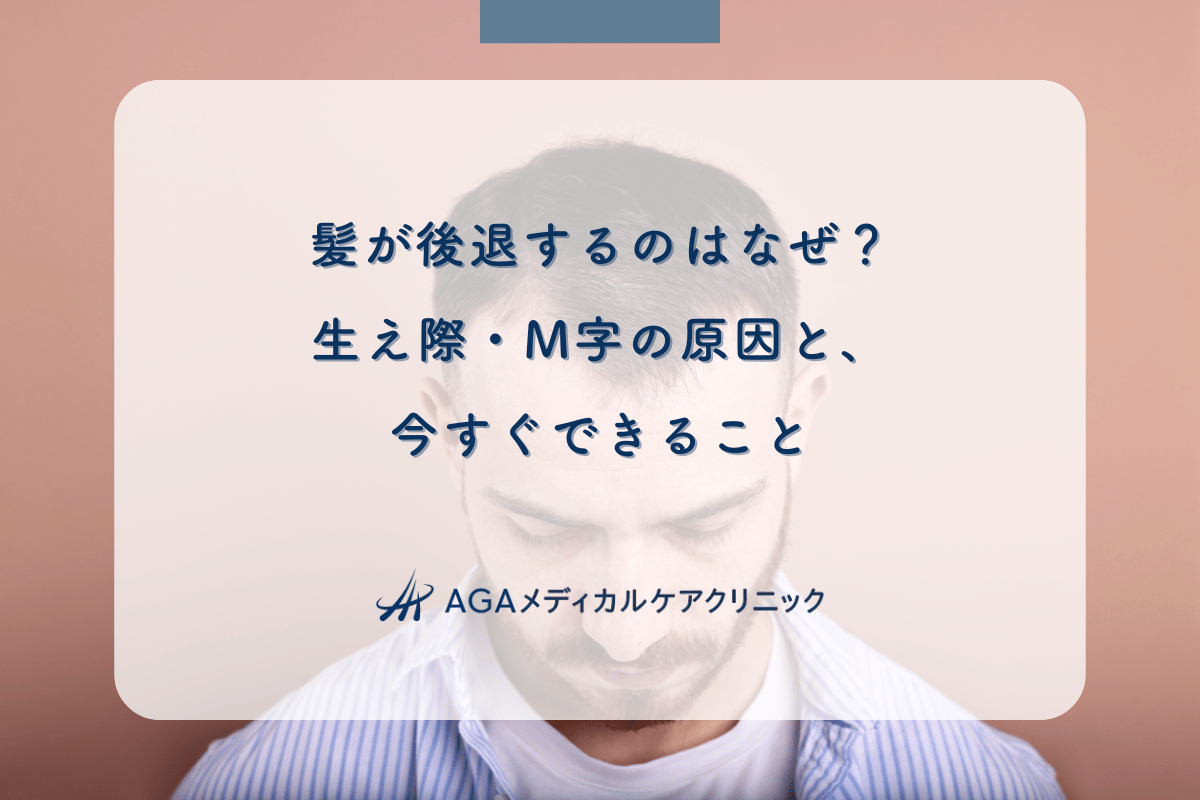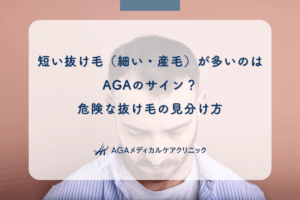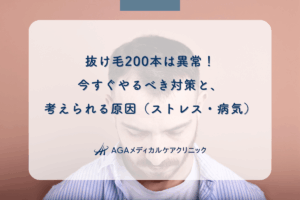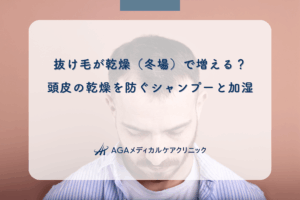鏡を見るたび、ふと指で触れたとき、以前とは違う生え際の位置に気づいて不安になっていませんか。特にM字部分の後退は、多くの方が気にする悩みの一つです。
「もしかして、このまま進んでしまうのでは…」と感じるその心配、とてもよく分かります。髪が後退するには、AGA(男性型脱毛症)や生活習慣、頭皮環境など、さまざまな原因が関係しています。
しかし、原因を知り、適切な対策を早期に始めることで、進行を緩やかにしたり、頭皮環境を整えたりすることは可能です。
この記事では、髪が後退する理由を丁寧に解き明かし、今日からご自身でできる具体的なケア方法を分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

AGAメディカルケアクリニック 統括院長
前田 祐助
【経歴】
慶應義塾大学医学部医学研究科卒業
慶應義塾大学病院 初期臨床研修課程終了
大手AGAクリニック(院長)を経て、2018年に薄毛・AGA治療の「AGAメディカルケアクリニック」新宿院を開設
2020年に横浜院、2023年に東京八重洲院を開設
資格・所属学会・症例数
【資格】
- 医師免許
- ⽇本医師会認定産業医
- 医学博士
【所属学会】
- 日本内科学会
- 日本美容皮膚科学会
- 日本臨床毛髪学会
【症例数】
3万人以上※
※2018年5月~2022年12月AGAメディカルケアクリニック全店舗の延べ患者数
髪の後退が始まるサインとは
髪の後退は、ある日突然起こるわけではありません。多くの場合、日常の中で少しずつ変化が現れます。初期の小さなサインを見逃さず、早期に気づくことが対策の第一歩として重要です。
ご自身の状態と照らし合わせながら確認してみてください。
以前と違う生え際の形
最も分かりやすいサインの一つが、生え際の形の変化です。
以前はまっすぐだった、あるいは緩やかなカーブだった生え際が、徐々にM字型になってきたり、全体的に後退して額が広くなったように感じたりする場合、注意が必要です。
毎日鏡を見ていると変化に気づきにくいこともありますが、数ヶ月前や一年前の写真と比較すると、その違いが明確になることがあります。
髪の毛が細く弱々しくなった
髪が後退する部分、特に生え際や頭頂部では、太く健康な髪の毛が少なくなり、代わりに細くて短い、いわゆる「うぶ毛」のような弱々しい毛が目立つようになります。
これは、ヘアサイクル(毛周期)が乱れ、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまうために起こります。
髪全体のボリュームが減った、ハリやコシがなくなったと感じる場合も、このサインに該当する可能性があります。
地肌が目立つようになった
髪の毛一本一本が細くなることや、髪の毛の総数が減少することにより、以前よりも地肌が透けて見えるようになります。特に、髪が濡れているときや、特定の照明の下で顕著に感じることが多いでしょう。
生え際だけでなく、つむじ周りや頭頂部も合わせて確認することが大切です。地肌の目立ち具合は、髪の後退の進行度を測る一つの目安になります。
抜け毛の質や量の変化
シャンプーのときや朝起きたときの枕元で、抜け毛の量が増えたと感じることもサインの一つです。ただし、健康な人でも一日あたり50本から100本程度の髪は自然に抜けます。
注目すべきは「量」だけでなく「質」の変化です。抜けた毛の中に、細く短い毛や、毛根がはっきりしないような弱々しい毛が増えていないかを確認しましょう。
太く長い毛が抜けるのは自然な生え変わりである可能性が高いですが、成長しきる前の毛が抜けている場合は、ヘアサイクルに問題が生じている兆候かもしれません。
なぜ髪は後退するのか?主な原因を探る
髪が後退する背景には、一つだけでなく複数の原因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
最も大きな要因とされるAGA(男性型脱毛症)から、日々の生活習慣まで、髪の後退を引き起こす主な原因について詳しく見ていきましょう。
AGA(男性型脱毛症)の影響
成人男性の髪の後退や薄毛の悩みの多くは、AGA(AndrogeneticAlopecia)、すなわち「男性型脱毛症」が原因であると考えられています。これは進行性の脱毛症であり、早めの対策が重要です。
AGAとは何か
AGAは、男性ホルモンや遺伝的要因が関与して発症する脱毛症です。主な特徴として、思春期以降に始まり、生え際や頭頂部の髪が徐々に薄くなっていく点が挙げられます。
男性ホルモンの一種であるテストステロンが、特定の酵素(5αリダクターゼ)の働きによってDHT(ジヒドロテストステロン)という強力な男性ホルモンに変換されます。
このDHTが、毛根にある受容体と結合することで、髪の成長を妨げる信号を出し、ヘアサイクルを短縮させてしまいます。
ヘアサイクルとの関係
髪の毛には「成長期(髪が太く長く成長する期間)」「退行期(成長が止まる期間)」「休止期(髪が抜け落ちる期間)」という一連のヘアサイクルがあります。健康な髪の場合、成長期は通常2年から6年続きます。
しかし、AGAを発症すると、この成長期が数ヶ月から1年程度にまで著しく短縮されます。
その結果、髪は太く長く成長する前に抜け落ちてしまい、細く短い毛ばかりが目立つようになり、地肌が透けて見える、いわゆる「薄毛」の状態が進行します。
生活習慣の乱れと髪の関係
AGA以外にも、日々の生活習慣が髪の健康に大きな影響を与えます。不規則な生活は、髪の成長に必要な環境を損なう原因となります。
栄養バランスの偏り
髪の毛は、私たちが摂取する栄養素から作られています。主成分であるケラチン(タンパク質)をはじめ、その合成を助ける亜鉛、ビタミン類などが髪の成長には必要です。
ファストフードやインスタント食品に偏った食事、極端なダイエットなどは、これらの栄養素の不足を招きます。髪に十分な栄養が届かなければ、健康な髪は育ちにくくなります。
睡眠不足の影響
髪の成長や頭皮の修復は、主に睡眠中に行われます。特に、入眠後まもなく訪れる深い眠りの時間帯に成長ホルモンが多く分泌されます。
睡眠時間が不足したり、睡眠の質が低下したりすると、成長ホルモンの分泌が妨げられます。
これにより、髪の成長が遅れたり、日中に受けた頭皮のダメージが十分に修復されなくなったりして、髪の後退につながる可能性があります。
ストレスが頭皮に与える影響
過度な精神的ストレスは、自律神経のバランスを崩します。自律神経は血管の収縮や拡張をコントロールしており、バランスが乱れると血管が収縮しやすくなります。
特に頭皮の毛細血管は細いため、血行不良に陥りやすいのです。血行が悪くなると、毛根にある毛母細胞へ酸素や栄養素が届きにくくなり、髪の成長が阻害されます。
また、ストレスはホルモンバランスの乱れを引き起こすこともあり、間接的に髪の健康に悪影響を及ぼします。
頭皮環境の悪化
髪が育つ土壌である頭皮の環境が悪いと、どれだけ栄養を摂っても健康な髪は生えてきません。頭皮トラブルも髪の後退を加速させる要因です。
間違ったヘアケア
頭皮を清潔に保つことは重要ですが、洗浄力の強すぎるシャンプーを使ったり、一日に何度もシャンプーをしたりすると、頭皮を守るために必要な皮脂まで奪ってしまいます。
皮脂が不足すると頭皮は乾燥し、フケやかゆみの原因となります。逆に、乾燥を防ごうと皮脂が過剰に分泌され、毛穴を詰まらせることもあります。
また、シャンプーのすすぎ残しは、頭皮に刺激を与え、炎症を引き起こす原因にもなります。
頭皮の血行不良
前述のストレスや睡眠不足に加え、運動不足や長時間のデスクワークによる肩こり・首こりなども、頭部への血流を悪化させます。
頭皮が血行不良になると、髪の成長に必要な栄養が届かない「栄養不足」の状態になります。血行が悪く、硬くなった頭皮では、健康な髪は育ちにくいのです。
生え際・M字が特に目立つ理由
髪の後退が始まる際、多くの方が生え際、特に「M字」部分から進行することに気づきます。
なぜ頭頂部や側頭部など他の部位に比べて、生え際が目立ちやすいのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。
AGAの影響を受けやすい部位
生え際(前頭部)と頭頂部は、AGAの原因となるDHT(ジヒドロテストステロン)の影響を最も受けやすい部位であると考えられています。
これは、DHTと結合する受容体(アンドロゲンレセプター)が、この2つの部位に多く存在するためです。DHTが受容体と結合すると、髪の成長期が短縮され、髪が細く短くなります。
一方、側頭部や後頭部の髪は、この受容体が少ないため、AGAの影響を受けにくく、薄くなりにくい傾向があります。
顔周りの血流の特徴
頭皮の中でも、生え際、特にM字部分は、他の部位に比べて毛細血管が少なく、血行不良に陥りやすいという特徴があります。
頭頂部や後頭部に比べて筋肉の動きも少ないため、血液を送り出すポンプ機能が働きにくいのです。血流が滞ると、毛根への栄養供給が不十分になり、髪が育ちにくくなります。
皮脂分泌と毛穴の詰まり
額から生え際にかけては、顔の中でも皮脂腺が多く存在する「Tゾーン」の延長線上にあります。そのため、皮脂の分泌が活発になりがちです。
分泌された皮脂が、古い角質やホコリなどと混ざり合って毛穴に詰まると、頭皮の炎症を引き起こしたり、髪の健やかな成長を妨げたりする原因になります。
適切な洗髪ができていない場合、この傾向はさらに強まります。
外部からの刺激を受けやすい部位
生え際は、顔と同様に紫外線や外気、ホコリなどの外部刺激に常にさらされている部位です。紫外線は頭皮を乾燥させ、毛母細胞にダメージを与える可能性があります。
また、洗顔料のすすぎ残しや、整髪料の付着なども、生え際の皮膚にとっては刺激となり得ます。
こうした日々の小さなダメージの蓄積が、頭皮環境を悪化させ、髪の後退を助長する一因になることがあります。
髪の後退を放置するリスク
生え際の変化に気づきながらも、「まだ大丈夫だろう」「そのうち治るかもしれない」と対策を先延ばしにすると、いくつかのリスクが生じる可能性があります。
髪の後退は、早期の認識と行動が非常に重要です。
進行性の脱毛症(AGA)
髪の後退の主な原因がAGAである場合、それは進行性の特徴を持っています。つまり、放置しておくと、髪の後退や薄毛はゆっくりとですが着実に進行していく可能性が高いのです。
AGAは自然に治癒することは期待しにくいため、何らかの対策を講じない限り、ヘアサイクルは短いまま固定され、細く短い髪の毛の割合が増え続けます。
気づいたときには、対策がより困難な状態になっていることも少なくありません。
見た目の印象への影響
髪型は、その人の印象を大きく左右する要素の一つです。生え際が後退し、額が広くなると、実年齢よりも年上に見られたり、疲れているような印象を与えてしまったりすることがあります。
本人の意図とは関係なく、周囲からの見え方が変わってしまうことは、日常生活において小さくない影響を及ぼす可能性があります。
心理的な負担の増加
髪の状態を過度に気にするあまり、自信を失ってしまうこともあります。
他人の視線が生え際に集まっているように感じたり、鏡を見るのが憂鬱になったり、好きな髪型に挑戦できなくなったりするなど、精神的なストレスが増大することが懸念されます。
こうした心理的な負担が、さらにストレス性の血行不良を招くといった悪循環に陥る可能性も否定できません。
対策が遅れるほど回復が困難に
AGAの進行によってヘアサイクルが短縮され続けると、毛根は次第にその活動を休止していきます。
髪を生み出す「毛母細胞」の働きが完全に止まってしまうと、その毛穴から再び太く健康な髪を生やすことは非常に困難になります。
対策を始めるのが早ければ早いほど、まだ活動している毛根を守り、ヘアサイクルを正常に近づける可能性が残されています。
放置する期間が長引くほど、取りうる選択肢が限られてしまうリスクがあるのです。
今すぐ始めたいセルフケア対策
髪の後退に気づいた今、専門的な治療を検討する前に、ご自身の生活の中で見直せる点が数多くあります。
健康な髪を育む土台となる体と頭皮の環境を整えるために、今日から始められるセルフケア対策を紹介します。
食生活の見直し
私たちの体、そして髪は、日々の食事から作られています。バランスの取れた食事は、健康な髪を育てるための基本です。
髪に必要な栄養素
髪の主成分はケラチンというタンパク質です。まずは良質なタンパク質をしっかり摂ることが大切です。
また、タンパク質を髪の毛に合成する際には亜鉛が、頭皮の健康を保つためにはビタミン類が必要です。
髪の成長をサポートする栄養素と主な食材
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食材例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)の材料となる | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |
| 亜鉛 | タンパク質(ケラチン)の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ、アーモンド |
| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促し、皮脂の分泌を調整する | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、カツオ、納豆 |
| ビタミンE | 血行を促進し、頭皮に栄養を届けやすくする | ナッツ類、アボカド、かぼちゃ、植物油 |
避けるべき食習慣
高脂質・高糖質な食事は、皮脂の過剰分泌を招き、頭皮環境を悪化させる可能性があります。また、過度な塩分は血圧を上げ、血流に影響を与えることもあります。
ファストフードやスナック菓子、甘い飲み物の摂りすぎには注意し、バランスの良い食事を心がけましょう。
質の高い睡眠を確保する
髪の成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。特に、就寝から約3時間は、最も深いノンレム睡眠が現れやすく、成長ホルモンが活発に分泌されるゴールデンタイムと言われています。
単に長く寝るだけでなく、ぐっすりと深い眠りを得ることが重要です。就寝前のスマートフォン操作やカフェイン摂取、飲酒は睡眠の質を下げるため、控えるようにしましょう。
リラックスできる環境を整え、毎日決まった時間に就寝・起床する習慣をつけることが理想です。
ストレスとの上手な付き合い方
現代社会でストレスをゼロにすることは困難です。しかし、ストレスは自律神経を乱し、頭皮の血行不良を引き起こします。
大切なのは、ストレスを溜め込まず、上手に発散する方法を見つけることです。
自分に合ったリラックス法
趣味に没頭する時間を作る、適度な運動で汗を流す、湯船にゆっくり浸かる、友人と話すなど、ご自身が心からリラックスできると感じる方法を日常生活に取り入れましょう。
短時間でも意識的に休息を取ることが、心と体の緊張をほぐし、結果として頭皮環境にも良い影響を与えます。
正しいシャンプー方法の実践
毎日のシャンプーは、頭皮環境を左右する重要なケアです。間違った方法を続けていると、かえって頭皮にダメージを与えてしまうことがあります。
頭皮を清潔に保つ洗い方
目的は「髪」を洗うことではなく、「頭皮」の汚れや余分な皮脂を落とすことです。洗い残しやすすぎ残しがないよう、丁寧に行いましょう。
正しいシャンプーの手順とポイント
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. ブラッシング | 乾いた髪の状態で、毛先から優しくブラッシングし、ホコリを落とし髪のもつれを解く。 |
| 2. 予洗い | シャンプー前にぬるま湯(38度程度)で1〜2分、頭皮と髪をしっかり濡らし、表面の汚れを流す。 |
| 3. 泡立て | シャンプーを手のひらに取り、少量のお湯を加えて軽く泡立ててから、髪全体(特に頭皮)になじませる。 |
| 4. 洗う | 爪を立てず、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗う。生え際や襟足も忘れずに。 |
| 5. すすぎ | 最も重要。シャンプー剤が残らないよう、時間をかけて(洗いの倍程度)ぬるま湯で徹底的にすすぐ。 |
| 6. 乾燥 | タオルで優しく水分を拭き取り(ゴシゴシ擦らない)、ドライヤーで頭皮から中心に乾かす。 |
シャンプー選びの注意点
洗浄力が強すぎるシャンプー(高級アルコール系など)は、頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥を招くことがあります。
頭皮が乾燥しやすい方や、かゆみ・フケが気になる方は、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーなどを選ぶのも一つの方法です。ご自身の頭皮の状態に合ったものを選びましょう。
頭皮環境を整える生活習慣
セルフケアと並行して、頭皮環境そのものを健やかに保つための生活習慣も非常に重要です。日々の小さな積み重ねが、髪の土台を強くします。
適度な運動のすすめ
運動不足は、全身の血行不良の大きな原因となります。特にデスクワークが多い方は、体が凝り固まりやすく、頭部への血流も滞りがちです。
定期的な運動は、心肺機能を高め、全身の血流を促進します。
運動が血行に与える好影響
ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、全身の血流を改善するのに効果的です。血流が良くなることで、毛根にある毛母細胞へ酸素や栄養素が運ばれやすくなります。
また、適度な運動はストレス発散にもつながり、自律神経のバランスを整える上でも役立ちます。週に2〜3回、30分程度からでも良いので、無理のない範囲で体を動かす習慣を取り入れましょう。
禁煙と節酒の重要性
喫煙や過度な飲酒は、髪の健康にとって多くのデメリットをもたらします。これらを見直すことは、頭皮環境の改善に直結します。
喫煙・過度な飲酒が髪に及ぼす主な悪影響
| 要因 | 髪への主な悪影響 |
|---|---|
| 喫煙(ニコチン) | 血管を強力に収縮させ、頭皮の血行を著しく悪化させる。 |
| 喫煙(活性酸素) | 体内で大量の活性酸素を発生させ、細胞の老化を早め、毛母細胞の働きを弱める。 |
| 過度な飲酒 | アルコールの分解過程で、髪の成長に必要なビタミンや亜鉛が大量に消費される。 |
| 過度な飲酒(睡眠) | 睡眠の質を低下させ、成長ホルモンの分泌を妨げる。 |
髪の健康を考えるならば、禁煙することが最も望ましいです。飲酒については、適量を守り、休肝日を設けるなど、体に負担をかけない楽しみ方を心がけることが重要です。
頭皮マッサージの試み
硬くなった頭皮をほぐし、直接的に血行を促進する方法として、頭皮マッサージがあります。リラックス効果も期待でき、シャンプー時や就寝前など、リラックスした状態で行うのがおすすめです。
頭皮マッサージの簡単な手順
力を入れすぎず、「痛気持ちいい」と感じる程度の圧で行うことがポイントです。爪を立てず、指の腹を使いましょう。
自宅でできる簡単頭皮マッサージ
| 部位 | 方法 |
|---|---|
| 側頭部(耳の上) | 両手の指の腹を当て、円を描くようにゆっくりと回しながら頭皮を引き上げる。 |
| 前頭部(生え際) | 指の腹を生え際に当て、頭頂部に向かってジグザグに動かしながらマッサージする。 |
| 頭頂部 | 両手で頭を包むように指の腹を当て、頭皮全体をゆっくりと動かすイメージで圧をかける。 |
| 後頭部(襟足) | 両手の親指を襟足のくぼみに当て、他の指で頭を支えながら、親指で心地よい圧を加える。 |
毎日続けることが大切ですが、やりすぎや力の入れすぎは逆効果になることもあるため、1回あたり数分程度を目安に、優しく行いましょう。
育毛剤の活用を考える
生活習慣の改善や正しいヘアケアと並行して、髪の後退が気になる部分に直接アプローチする方法として、育毛剤の使用があります。
育毛剤は、頭皮環境を整え、今ある髪を健やかに育てることを目的とした製品です。
育毛剤の役割とは
育毛剤の主な役割は、「脱毛を予防」し、「毛を育てる(育毛)」ことです。頭皮の血行を促進したり、毛母細胞の働きをサポートしたり、頭皮の炎症を抑えたりする成分が含まれています。
今生えている髪の毛を太く長く成長させ、抜けにくい健康な状態に導くためのサポートをします。
育毛・発毛・脱毛予防の違い
「育毛剤」と「発毛剤」は、目的や分類が異なります。それぞれの違いを理解し、ご自身の目的に合ったものを選ぶ必要があります。
育毛剤と発毛剤の主な違い
| 項目 | 育毛剤 | 発毛剤 |
|---|---|---|
| 分類 | 医薬部外品 | 第1類医薬品 |
| 主な目的 | 今ある髪を育てる・脱毛を予防する・頭皮環境を整える | 新しい髪を生やす(発毛)・髪を成長させる |
| 主な対象 | 薄毛・抜け毛が気になり始めた方・頭皮環境を改善したい方 | 薄毛が進行している方・AGA(男性型脱毛症)の方 |
| 主な成分例 | センブリエキス、グリチルリチン酸ジカリウムなど | ミノキシジルなど(※発毛効果が認められた成分) |
自分に合った育毛剤の選び方
育毛剤には多くの種類があり、含まれる成分や使用感が異なります。ご自身の頭皮の状態や悩みに合わせて選ぶことが大切です。
配合成分に注目する
ご自身の悩みに合った有効成分が配合されているかを確認しましょう。
例えば、頭皮の血行が気になるなら「血行促進成分(センブリエキスなど)」、フケやかゆみが気になるなら「抗炎症成分(グリチルリチン酸ジカリウムなど)」、頭皮の乾燥が気になるなら「保湿成分」が配合されているものが適しています。
複数の悩みにアプローチできる製品も多くあります。
使い続けられる価格と使用感
育毛剤は、短期間で劇的な変化をもたらすものではありません。ヘアサイクルを考慮すると、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度は継続して使用することが推奨されます。
そのため、経済的に負担なく続けられる価格帯であることが重要です。
また、液だれのしにくさ、スプレーの使いやすさ、香り、べたつきのなさなど、ご自身がストレスなく毎日使い続けられる使用感であるかも、選ぶ上で大切なポイントです。
育毛剤の効果的な使い方
せっかく育毛剤を使用するのであれば、その効果を最大限に引き出す使い方を実践しましょう。正しい使用方法が、頭皮への浸透を助けます。
使用するタイミング
最もおすすめのタイミングは、シャンプー後の清潔な頭皮に使用することです。頭皮の汚れや皮脂が落ちているため、育毛剤の成分が角質層まで浸透しやすくなります。
シャンプー後、ドライヤーで髪を乾かし、頭皮が完全に乾いた、あるいは半乾きの状態で使用しましょう。濡れすぎていると成分が薄まってしまいます。
正しい塗布量と方法
製品に記載されている規定の使用量を守ることが重要です。「多くつければ早く効く」わけではなく、多すぎると頭皮トラブルの原因になることもあります。
気になる生え際やM字部分だけでなく、頭皮全体にいきわたるように塗布します。塗布後は、すぐに流したりせず、指の腹で優しく頭皮になじませるようにマッサージすると、血行促進にもつながり効果的です。
よくある質問
- 髪の後退はいつから始まりますか?
-
髪の後退が始まる時期には個人差が非常に大きいです。AGA(男性型脱毛症)の場合、早い方では10代後半から20代前半でその兆候が現れ始めます。
一般的には30代から40代にかけて、生え際や頭頂部の変化を自覚する方が多い傾向にあります。遺伝的な要因や生活習慣によって、その発症時期や進行速度は異なります。
- 遺伝はどの程度関係しますか?
-
髪の後退、特にAGAの発症には、遺伝的要因が強く関係していると考えられています。AGAの原因となる男性ホルモンの影響の受けやすさ(受容体の感受性)は、遺伝によって受け継がれやすい性質の一つです。
ご家族、特に母方の家系に薄毛の方がいる場合、ご自身もAGAを発症しやすい体質である可能性はありますが、必ずしも遺伝するとは限りません。
遺伝的要因があっても、生活習慣の改善や早期のケアによって、進行を緩やかにすることは期待できます。
- 育毛剤はどれくらいで効果が出ますか?
-
育毛剤は、医薬部外品であり、その主な目的は頭皮環境を整え、抜け毛を予防し、今ある髪を健やかに育てることです。
髪の毛にはヘアサイクルがあるため、使用してすぐに目に見える変化(発毛など)が現れるわけではありません。
多くの場合、頭皮環境の改善や抜け毛の減少、髪のハリ・コシの変化を感じ始めるまでに、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の継続使用が必要とされています。
焦らず、日々のケアとして根気よく続けることが重要です。
- 髪の後退が止まらない場合はどうすれば良いですか?
-
セルフケアや育毛剤の使用を続けても、髪の後退が明らかに進行していると感じる場合、またはAGA(男性型脱毛症)の可能性が高いと思われる場合は、ご自身でのケアだけでは限界があるかもしれません。
その際は、皮膚科や薄毛治療を専門とするクリニックに相談することを推奨します。
専門の医師が頭皮の状態や髪の状態を診断し、医学的根拠に基づいた治療法(内服薬や外用薬の処方など)を提案してくれます。
早期に専門家の診断を受けることが、進行を食い止め、より良い結果につながる可能性があります。
Reference
KIM, Han Jo, et al. An analysis of shapes and location of anterior hairline in Asian men. Archives of Dermatological Research, 2023, 315.5: 1233-1239.
HAMED, Ahmed Mohammed, et al. Relation between Androgenic Alopecia with Metabolic Syndrome. The Egyptian Journal of Hospital Medicine (January 2024), 2024, 94: 1207-1211.
SPRINGER, Karyn; BROWN, Matthew; STULBERG, Daniel L. Common hair loss disorders. American family physician, 2003, 68.1: 93-102.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. Female pattern hair loss. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 181-203.
MARKS, Dustin H.; SENNA, Maryanne M. Androgenetic alopecia in gender minority patients. Dermatologic clinics, 2020, 38.2: 239-247.
CHIN, Evelyn Y. Androgenetic alopecia (male pattern hair loss) in the United States: What treatments should primary care providers recommend?. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 2013, 25.8: 395-401.
KIM, J. N., et al. Morphological and morphometric study of the androgenetic alopecic scalp using two‐and three‐dimensional analysis comparing regional differences. British Journal of Dermatology, 2014, 170.6: 1313-1318.
DHURAT, Rachita; AGRAWAL, Sandip. Hair Loss and Hair Disorders. In: Essentials for Aesthetic Dermatology in Ethnic Skin. CRC Press, 2023. p. 50-58.
ŚLIWA, Karol, et al. The diagnosis and treatment of androgenetic alopecia: a review of the most current management. In: Forum Dermatologicum. 2023. p. 99-111.
ANASTASSAKIS, Konstantinos. Hairline Design and Grafting. In: Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 3 Hair Restoration Surgery, Alternative Treatments, and Hair Care. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 345-369.